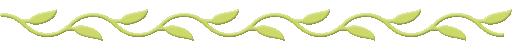
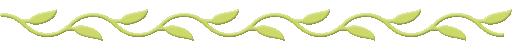
2バイト文字の国のジレンマ
ある商用Webサイトを取材したとき、そこのWebmasterが外字のハンドリングに困っていました。そこのサイトは、ユーザーの会員登録が非常に大きなウエイトを占めていて(どこもそうかもしれませんが)、その内容も名前や住所以上の詳細な属性情報を記入してもらうため、外字の登場する確率がすごく高いのです。WindowsのIMEには、一部JISの規格を越えたメーカー外字(IBM外字など)が入っているので、ユーザーは外字だとは知らずに使うのですが、サーバがWindowsではないと認識できなくなります。
彼らは独自の文字変換プログラムをサーバ部分に加えようとしているのですが、どうもうまくいかないとのこと。そのWebmasterは日本語でサイトを開いているかぎり、ユーザーの利用するすべての文字を受け入れるのは当然だと考えており、何とかこの問題に対処したいと奮闘しています。
別の機会に、商用Webサイトを委託により運営しているソフトハウスに、“御社では外字の扱いはどうされていますか?”と聞いてみました。すると“外字はすべてはねている”という答えが返ってきました。そこも中心は外資系ソフトウェアを利用しているのですが、ソフトウェアでハンドリングする責任がもてないものを受け入れるわけにはいかない、というのがその理由でした。かたや外字積極容認派、かたや外字拒絶派。サイトによって考え方がすごく違うんだな、と非常に印象的でした。
問題は、外字を自分の名前や住所、社名などに持つ人が、それを入力できないことをどう思っているのか。ある人は“おおげさかもしれないけれど、略字ではアイデンティティーが侵される気がする”といいました。ある人は“本来の字にこだわっていると入力が面倒だから、コンピュータ上は略字やひらがなを使っている”といいました。“別にアイディンティティー・クライシスはない”そうです。こちらも考え方に両極あるようです。
サイトを開設するということは、こうした日本語の問題と向き合うことでもあります。今回はどちらのユーザーに照準を合わせるのか。何か明確な指針があればいいのですが、コンピュータ上の文字の扱いは、それだけで本が一冊できあがるくらい、非常に複雑な様相を呈しています。しかし、かといって答えがでるまで待っているわけにはいきません。非常に難しい問題ですが、サイト開発者は“われわれはこれで行く!”という着地点を、それぞれに自分たちの見識で見出していかねばならないようです。
(この文章は日経ソフトウエアメールニュースに掲載したものを再録しました)
![]()