弘文堂.、1991年、7,900円。
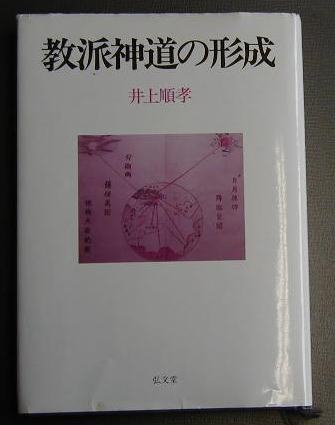 【目次】
【目次】第1章.神道教派体制の成立過程
第2章.研究視点の変遷―戦前と戦後
第3章.教派神道研究の新たな視角
第4章.佐野経彦と神理教の形成
第5章.新田邦光と神道修成派の形成
第6章.芳村正秉と神習教の形成
第7章.平山省斎と神道大成教の形成
第8章.教派神道の特性
『教派神道の形成』
弘文堂.、1991年、7,900円。
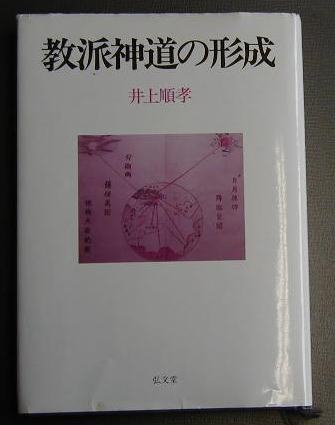 【目次】
【目次】
第1章.神道教派体制の成立過程
第2章.研究視点の変遷―戦前と戦後
第3章.教派神道研究の新たな視角
第4章.佐野経彦と神理教の形成
第5章.新田邦光と神道修成派の形成
第6章.芳村正秉と神習教の形成
第7章.平山省斎と神道大成教の形成
第8章.教派神道の特性
【まえがきから】
教派神道研究は、戦後は停滞気味である。その理由の一つとして、教派神道各派が社会的な影響をもったのは、大部分明治期がピークであるという事実を指摘できる。とくに本書で中心的に取り上げた教派の今日の状況からすれば、教派神道研究が、近代の宗教運動研究の中では、周辺的な場所に追いやられているのも無理はない。けれども、近代日本において、神道的な伝統に基づく宗教運動がどのように出現し、それがどのような意味をもったかを考えるときに、教派神道の意義を抜きにしては論議は進めることはできない。
戦後は、多くの神道系新宗教が教勢を拡大しているが、教派神道が課題として担っていたものの一部は、これら新しい運動にも継承されている。その課題とは、記紀に代表される神道古典をどのように解釈するか、民族的アイデンティティという問題をどのように扱うか、また、外来の宗教、とくにキリスト教に対し、どのようなスタンスをとるか、などである。一般的には、新宗教は病気治しなど、現世利益的なものを直接的媒介として信者を獲得し、それによって教団を存続させていると考えられている。そうした理解の仕方がまったく的外れというのではない。だが注意深くその教えを検討していくなら、そこに大きな体系的教えへの関心が横たわっているのを感知できる。病気治しに代表される除災招福的な関心事は、人々が宗教に至る大きな入り口であるには違いないが、中にはいったすべての人が、そうした関心にのみ終始するわけではないのである。教団の使命とか、信者の生き方とか、あるいはぐっと大きく人類存在の意味といった、世界観、人生観に関わる事柄に、強い関心を持つ人々が出てくる。そうした探究心や求道心に応えられないようでは、運動の生命もそう長いものではなかろう。
新宗教の中でも、ことに神道系新宗教が、教義を体系化しようとすれば、そこに、民族の位置付け、宗教的シンクレチズムの処理、神観念の整備といった問題が大なり小なり含まれざるを得ない。教派神道が展開した議論の末裔が見出されるのである。これらは幕末以来の宗教文化の新しい局面においては、逃れることのできない教学的課題として突き付けられてきたと言える。それゆえ、その取り組みの先駆的形態が教派神道であったという理解の仕方が可能になるのである。
教派神道はまた、神道的伝統が初めて本格的な教団化を達成したときの産物として捉えられる。それまで神社神道や民間信仰、民俗宗教の中で呼吸をしてきた神道の諸要素が、教団宗教へと新たな展開を遂げたときに出現した一つが教派神道であると考えられるのである。教派神道における教団宗教化の過程には、いくつかの興味深い現象が観察される。それらは、ある面では今日なお新たに出現する新宗教が示すものと共通しているし、また他の面では、当時の時代状況抜きにしては存在し得ないような局面も見いだされる。しかし、その多くは、神道という長い宗教伝統が近代社会の中に適応しようとするときのジレンマというものに近いことに興味が惹かれる。
近代日本の宗教運動は実に変化に富む。それはその間の日本の社会変化の激しさを物語っている。しかし、日本社会がこの間に無原則に変化したのではないように、近代の宗教システムも、あてもなく試行錯誤を繰り返したのではない。少なくとも、そこに執拗に守ろうとした部分と、きわめて容易に変化した部分という違い位は読みとれる筈である。また、幕末維新期に凝縮されて噴出した固有文化をめぐる問題が、今日はまったく消失してしまったとも思えない。近世までにかなり根強い伝統的宗教文化が形成されているからには、それが変容する可能性が高まった場面では、何らかの対処法が宗教システム内部で模索されると考えるべきであろう。ファンダメンタリズムに向かうか、意図的な融合(本書で提起した用語に従えば、ネオ・シンクレチズム)を志向するか、あるいは単なる防衛行動に出るか。むろん道は一通りではない。
教派神道を一つの新しい宗教システムとして捉えるという本書の前提は、近代日本が宗教文化におけるシステム変換を迫られ続けてきたという認識に基づいている。好んで用いられる「宗教ブーム」などという視点からのアプローチでは、そうした変換の本質的な部分と表面的な部分を見分けることはできない。われわれに突きつけられてきた、世界理解の枠組の変容という課題が、宗教現象の次元では具体的にどのような姿としてあらわれてきたかを、正面から問う必要がある。この厄介な問をいくらかでも整理するためのステップとしての意味を、この研究には与えている。
【刊行物へ戻る】