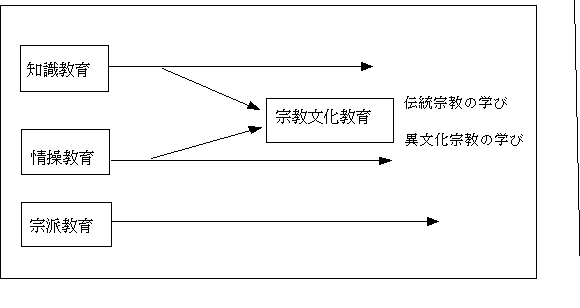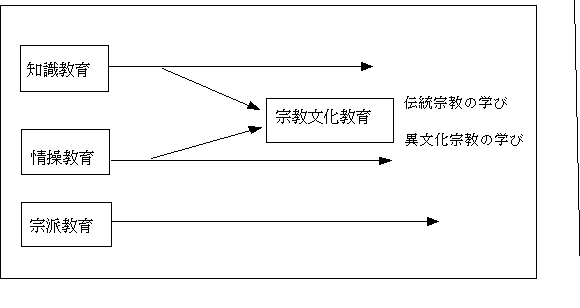
公立学校における宗教教育の課題
1. 公立学校における宗教問題を議論する視点
1990年代半ばより、日韓の宗教教育の比較研究が開始されて、これまでに数度の韓国における現地調査をはじめ、釜山の東西大学校における国際シンポジウム(2001年)、「宗教と社会」学会のワークショップ(2002年)、その他数多くの研究会が重ねられてきた。この調査が本格化した頃、日本においては、教育基本法の見直しの一環として、第9条の宗教教育の改正議論も起こった。
宗教教育をとくに日韓の現代社会における問題を踏まえて議論すると、宗教文化教育というものが現実的な方策として浮かび上がってきた。この点については前回の報告書(1)においてもある程度指摘されていたことである。本論では、これらの成果に基づいて考察を加え、日本社会の情報環境、宗教状況、その他の条件を考えると、少なくとも公立の学校において宗教を扱う場合には、宗教文化教育がもっとも実現性が高く、また社会的な抵抗も少ないと考えられるということについて、その背景を説明しながら、さらに詳しく述べたい。
個人的には、宗教教育の問題に取り組んでから、約13年ほどになる。1990年に、國學院大學の日本文化研究所で、宗教教育のプロジェクトを専任プロジェクトとして立ち上げた。学外の研究者の協力を得て、調査・研究チームを組織した。当初、先行の研究が比較的少なかったので、各種の基礎データを集めることから出発した。すなわち、今の日本の学校教育において、宗教がいったいどう扱われているのか、学校で行われる授業はどういうものであるのか、あるいは生徒たちが宗教というものをどういうふうに見ているのか、感じているのかといったことについて、郵送法、面接法、その他の方法によって資料を収集した。
ちょうどこの研究の中間的な成果(2)を作成している頃、1995年にオウム真理教の事件が起こった。この事件を契機に宗教教育の問題も、広く行われるようになった。各種のシンポジウムその他が開催され、あらためてこの問題が従来等閑視されてきたということが、浮き彫りにされた。戦後日本で長い間、宗教教育についての議論が避けられたきたのは、戦前の状況にさかのぼるいくつかの社会的な理由があるわけだが、結果的に、学校の教育の現場で宗教というものが、一種タブーに近いような扱いをされてきたというのは事実である。
しかしながら、オウム真理教事件以後、過去の経緯にとらわれたり引きずられるような形で、教育の現場における宗教問題を論じていてもいいのかというような意見もあちこちで生じた。つまり、オウム真理教事件は、宗教教育に関する議論を新たな展開へと導く引き金になったのである。こうした議論のなかには、現状を確実に踏まえていないものが少なくなく、いわば精神論的な宗教教育論すら見受けられるようになった。グローバル化時代の宗教教育を考える時には、社会全体が以前とはどのように変わってきたのかという点を的確に把握しておくことは大前提となる。現実を直視しない理念先行の宗教教育論では、実現が困難であることは明白である。
教育基本法の第9条は「宗教教育」とされており、次の二項からなる。
①宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。
②国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他の宗教的活動をしてはならない。
この条文が現代社会において適切かどうかを議論する場合には、条文だけを抽象的に議論しても意味がない。これに対応する現実の状況というものを的確に把握しておく必要がある。とくに宗教界の一部には、教育において宗教についてもっと教えることが大切であるということを強調するあまり、現実の学校における生徒の情報環境がどのようなものであるかについての認識が乏しいのもみられる。むろん、こうした宗教界からの発言と研究者としての立場からの議論とは、一応次元が異なるものではある。だが、教育基本法をどうするかというような場合には、両者の見解が参考とされることになると考えられるから、宗教界がどのような認識をもって、このテーマについて議論しているかにも注意を払わざるを得ない。
とくに公立の学校における宗教教育の議論においては、憲法20条との関係から、宗教的理念を優先させたような宗教教育論は前面に出すわけにはいかないのである。しかしそうした基本的なことも踏まえられていないことがしばしばである。つまり宗教系の学校における宗教教育と公立学校における宗教教育との区別が十分なされないまま、宗教教育の必要性を主張するという宗教関係者は数多く見られる。あとで述べるように、こうした態度は、宗教を自覚的に信仰していない人々にとっては、むしろ警戒を呼び起こすものであり、宗教教育問題に関する適切な議論を阻害する可能性すらある。この点は意外に見過ごされがちな点である。
公立学校における宗教教育を本格的に議論するとなれば、それ相応の理論的な準備が必要であることは言うまでもない。公立学校に通う生徒たちの親の大半は特定の信仰を持たない。そういう現実を踏まえた上で議論するという当然の手続きが、宗教界から発せられる主張にはしばしば欠けている。
いわゆる「宗派教育」、すなわち特定の宗教・宗派の理念に基づいてなされる教育は、日本では宗教系の学校では自由に行えるようになっている。もし、宗教的な教育を適切に行うことが、次世代の若者を育てる上で貢献できるということを実証的に示そうとするならば、まず宗教系の学校における宗教教育において、一定の成果を示すということが求められる。そのことによって、宗教系の学校における宗教教育は、たとえば人格を陶冶し、道徳心や倫理感をはぐくむ上で有効であるという議論につながる。理論あるいは理念にしたがった議論だけでなく、実際に検証できるようなものを提起しなければ、実質的な意味が薄い。つまり、宗教教育を充実させれば、宗教情操教育もほとんどなされることのない公立学校とは何か違った生徒たちが育つのである、という実例を示すことが必要になる。こうした実践的な面を伴わない宗教教育の議論をいくら重ねても、公立学校側がこの問題に真剣に取り組むということはありえないのは明らかである。
2. 宗教教育議論をめぐる3つのベクトル
1990年代半ば以降、宗教教育の議論が急速に高まった主たる理由は、オウム真理教事件であることを冒頭に述べたが、それ以外にも理由が求められる。一つは、日常的に若い世代における倫理とか道徳というのが、一時期に比べれば明らかに弱まっているという印象があり、この点への反省が高まったことである。実際に若者の間における倫理観、道徳観が乏しくなっていると言えるかどうかは、簡単な議論ではないが、少なくともマナーや道徳心・公共心と呼ばれるようなもの、広い意味での社会性というものが、いくぶん乏しくなってきているのは、日常的に観察されることである。こうしたことに対し、「恥を知らない」、「モラルが低い」などと直接な批判が投げかけられることがあるが、それ以前に、倫理・道徳に関する社会的な統制力がすべての世代に対して弱まっているという認識が必要になる。そして、若い世代はそれに対し特有の反応を示しているというふうに捉えられる。そうなると、モラルの低下と称されるような現象も、むしろ社会的な原因がある。そのような社会的仕組み全体についての考察が必要である。
しかし、ともすれば、もっぱら結果としての若い世代の意識や行為のありようが問題とされるのが現状である。電車の中での振る舞いとか、学校にいれば教室での振る舞いとか、かつての倫理や道徳で叫ばれていたようなことはどこへ行ってしまったのだろうというような形での批判が噴出することになる。このような事態への対処として、宗教教育問題が議論されるということになった。この立場からの議論はオウム以前から続いていた。
これに対し、オウム事件以後、これとは少し異なる立場からの議論が出てきた。それが、小渕・森首相時代に出てきた教育改革国民会議での議論であり、教育基本法改正を絡めるものであった。一定の理念を提示しながらの議論であったとは考えられるが、基本的にはどうしても上からの「若い者をこうしなければいけない」というような、かつての宗教情操あるいは道徳教育の議論のスタンスと似たようなスタンスがあちこちに散見される。確かに教育改革国民会議の議論には21世紀を見据えてということが示されており、その中には異文化教育も必要だといった視点も含まれてはいるが、同時に、例えば教育勅語も肯定的に見ようとするような議論も、その中にいつのまにか出てくる余地のあるようなものになっていった。
このように1990年代以降の宗教教育の議論の背景にはいくつかの要因が想定される。これについて以下のように三点にまとめて整理しておきたい。
第一は、オウム真理教事件を契機に一挙に強まった主張で、カルト対策という色彩の強い宗教教育論である。怪しい宗教団体に勧誘されることのないように、正しい宗教と間違った宗教を見分けるために、宗教についての「正しい」基礎的な教育が必要であるという主張である。これは簡単に言ってしまうと、特にカルト宗教に対する免疫的な効果を宗教教育によって養おうという発想法である。こういう立場を明確に表明しているジャーナリストもいる。(3)
しかしながら、対カルト教育的なことを公立学校における宗教教育に求めるのは、現実としてはかなり困難である。まずもって、教えられる教員がほとんどいないという事実がある。どのような形であれ、宗教のよしあしについて言及するには、一定の知識と見識とが必要になる。現状のままの状態で、公立学校においてこのようなことを教員に求めるのは、きわめて現実離れしている。
第二は、倫理・道徳が失われているのではないかという認識に基づいて、モラルを向上させる、道徳性を養う動きと連動している主張である。これは従来の「宗教情操教育」の主張ともっとも深い関わりをもっている。このタイプの議論においては、しばしば戦前への価値観に一部回帰しようとする志向も観察される。「教育勅語というのはなかなかよかったではないか」というような主張も見出されたりする。また、現在の社会の規範の乱れのもっとも大きな問題は、やはり家族が崩壊しているところにあるということで、家族のつながりを重視するといったような点を宗教教育に関連させようという動きを含んでいる。
第三は、教育改革国民会議における議論の中にもあったように、価値観の多様化に備えようという主張である。現代社会はきわめて多様な価値観が混在しているので、一つの価値観で日本社会がまとまるということはあり得なくなっている。そしてこれは世界的な傾向である。ところが、問題は多様な価値観を認めると口では言うけれども、実際の場では、これを実行するのは大変に難しいということである。理念的に宗教協力とか、異なった価値観を寛容に受け入れるといったことが掲げられていても、現実に起こっていることの大半は、むしろ多様な価値観のぶつかり合いである。
特に「9・11」のショックは、教育の現場でも非常に大きい。「9・11」以降、明らかに日本人の学生、一般の人もイスラームに以前より強い関心を寄せ始めた。異文化というものが、何か遠い文化ではなくて、自分たちの身に直接関わってくるのだということを、「9・11」による一種のショックを伴いながら受け止めたと考えられる。
グローバル化時代は、人の往来が非常に激しくなる。小学校・中学校のレベルから、級友の中に外国人がいる、あるいは外国で生活した日本人が帰国して授業を受けるといった例は、かつてに比べればずっと増えている。そういう中で、異文化とか国や民族ごとの価値観の違いといったようなものを、比較的若い頃から身近に接することになる。世界中にいろいろな人がいる、いろいろな言葉があるという知識だけなら、従前から教えられていたことである。ただ、知識としてだけ知っているのと、日々顔を突き合わせるなかに、異文化を現実問題として感じのとでは大きく異なる。その人とどうやってコミュニケーションを取るかという問題が日常的に突き付けられたりするわけである。学校教育の場にもそういうグローバル化の影響が、じわじわと及んできている。
抽象的な意味で多様な価値観があるというのではなくて、現実的に異なる考えの人がいる。そういう人と向かい合わなくてはいけないのだということが、今までになくリアリティーを帯びてきているし、若い世代は実際に体験する割合が増えている。ホームステイとかいろいろなことを、今の生徒たちは高校の頃から気軽に行う例が増えている。
3. 理念と現実
そういう変化を考えると、むしろ教える側、宗教教育を議論する側の方々が、一世代前の時代状況を前提としているということに気づかされる。この点は宗教教育の具体的展望を議論するときの大きなネックとなりかねない。そのように、多様な価値観への対応という中で、宗教教育を考えていかなければいけないということである。ほかにもいくつかあるのであるが、以下、宗教教育の理念の問題、現実の状況、そしてそこから導かれることの大きく三つを述べていく。
まず、宗教教育を取り巻く現実的環境を確認したい。宗教教育を考える場合、先に述べたように公立の学校と私立、特に宗教系の学校とでは、条件が全く異なる。このことをいささかでも混同すると、議論はまったく迷走する。「宗教立の学校でやっているような教育を公立学校でやるべきだ」という議論が皆無ではないことが、この問題に関する認識の不十分さを示している。
憲法20条においては、信教の自由、国の宗教活動の禁止が、次のように定められている。
①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
また、先に示した教育基本法9条でも、特定の宗教を保護し布教の手助けになるようなことは公立の学校ではできないことになっている。このような大前提というものが、実際の議論において、ときどき無視されるというのは、信じがたいかもしれないが、そう稀ではないのである。
日本における宗教系の学校の宗教教育は、国際比較をすれば分かることであるが、きわめて緩やかな条件のもとに置かれている。そうした条件のもとにあるにもかかわらず、実際は熱心な宗教教育というのは、今日ではさほど多くは観察されない。ほとんどの場合、宗教系の学校は週1時間しか宗教の時間を設けていないのが実情である。例外的に3時間くらい設けている学校もある。そうした熱心な宗教教育を行っている典型的な例は、キリスト教系のセブンスデー・アドベンチスト教団によって設立された学校の場合である。独自性の強い教派で、コーヒーも飲まない、お酒も飲まないといった食べ物に関する戒律を持っている。この教団立の学校は「三育学園」と言う名称であるので、すぐ分かるが、宗教教育はかなり熱心に実施している。
具体的に示すと、週に3時間程度、場合によっては5時間もの宗教の授業(「聖書」といった科目名)があり、専用のテキストや教材、ビデオ類も作成されている。学校の宗教教育以外にも、寮でまた夕方に聖書を読み、賛美歌を歌ったりする。ここはもともと信者の子弟が来るわけであるから、そういうシステムでも成り立っていると考えられる。このように積極的な宗教教育のカリキュラムを設置しても、憲法違反でもなければ、教育基本法に抵触するわけでもない。こうした事例によっても、日本の宗教系学校の宗教教育は非常に自由ということが示される。しかし、実際はほとんどの宗教系学校で、これほど積極的な宗教教育は行われていない。なぜか。それはあまり積極的に宗教教育を行うと、生徒が来ない、親から文句が来ると考えているからである。経営上マイナスになるので、宗教の授業は週1回程度になっている。
もちろん宗教科の教師のなかには、こうした事態に対して批判的、もしくは残念がる人もいたりするが、私立学校では経営が優先される。さらにまた、その週に一時間の宗教の授業においても、生徒は半分寝ているではないか、そんな授業は必要ない、といった類の批判が寄せられることがある。多くの宗教系の学校であっても、それが現実であるということは認識されるべきである。
宗教系の学校はそういう現実であっても、ともかく宗派教育が自由である。しかし、公立の学校では宗派教育はいささかも行えないのであるから、もし公立学校で今よりも突っ込んだ、あるいは意義のある宗教教育をするにはどうしたらいいか、ということを主張しようとするならば、この条件の差を踏まえた上での論理構成が必須である。
公立学校では今までそういうことはほとんど念頭においていなかった。宗教教育を行える宗教系の学校を見ても、きっちりとした成果を上げていると思えるのはごく一部である。撤退しようとさえしているような学校もある。こうした宗教教育における厳しい現実からからスタートしないことには議論は始まらないということである。
4. 公立学校で宗教教育は可能か
以上の点をさらに詳しく述べてみたい。特に公立学校において、教育理念の中に宗教教育的な要素を含めようとする場合に、それを「宗教」とは言いにくいので、知育・体育・徳育の中の徳育に関わることを、もう少し推進しようではないかということで、繰り返し言われているのが「道徳教育」である。けれども、道徳教育は道徳教育として、また別のカテゴリーとして位置づけた方が適切と考えられる。むろん、宗教教育と道徳教育をどうリンクさせるかということは、とても大きな問題であるが、あまり簡単に両者を混同させない方がいいのではないか。それを簡単にリンクさせると、すぐ厄介な問題が起こる。今の教育の現場においては、道徳教育にさえいろいろな抵抗があるわけである。
実際問題として、宗教教育をめぐる議論で過去からつながりを持ってきたのは、「宗教情操の涵養」ということである。宗教情操の涵養は戦前、戦後も議論があり、繰り返され、絶えず問題になっている。これが現代においても解決しがたい問題をもたらしている理由は大きく二つある。
一つは戦前の問題の引きずり、もう一つは理論的な問題である。戦前の引きずりというのは、宗教情操の涵養ということが戦前からあり、とくに1930年代以降は、国体思想とか、「神社は宗教に非ず」という立場から、実際は宗教的なものでありながら、皇国史観に基づいたような神道的な思想が国民すべてが受け入れるべきものとして、学校教育で教えられるようになっていった経緯がある。そのことを否定的にとらえる見方があり、そういう形でふたたび宗教情操が説かれるのはきわめて問題である、という反応が起こるわけである。
もう一つは、少し込み入った議論である。果たして宗派教育と切り離した宗教情操教育は可能か、という疑問である。この点は繰り返し議論されている。特定の宗教と関わりなく教えられる宗教情操があるという立場と、宗教情操は個別の宗教に即してしか教えられないという立場がずっと対立している。特定の宗教と関わりを持たない宗教情操という場合に、しばしば例として出されるのは、例えば「いのちの尊厳」とか「自然に対する畏敬の念」ということである。これは確かに特定の宗教に関わりのない情操に見えるわけであるけれども、しかし例えば自然への畏敬といっても、果たしてそれは日本の土着の宗教的な感性と切り離されて、一般的な宗教的な情操と言えるかという厄介な問題がある。
自然の恵みというような表現であると、日本だけで考えるなら、これは大抵の人はそう思っていると言えるかもしれないけれども、しかし沙漠で生まれた宗教とか、いったん違う宗教の価値観から見ると、それはまさしく日本的な宗教的感性ではないかとみなされる可能性もある。特定の宗教と切り離された宗教情操というものは、基本的にはないだろうという立場が、より説得的である。日本でやる教育だから、日本的な感性を前提にすればいいという考えもあるだろうが、ここにグローバル化時代の複雑さが絡んでくると、そう単純な議論でもなくなる。
一般的な宗教情操というものは考えにくいという点は、比喩を用いた方が分かりやすいであろう。例えば一般的な音楽はあるか、というとなかなか思い描けない。音は物理現象であるからある程度は文化と切り離せる面もある。しかし、音楽となれば完全に文化的に作り出されたものであるから、西洋音楽や邦楽、中国の音楽、また民謡と、具体的に何かを素材にして語るしかない。多くの音楽について学ぶことによってしか、音楽についての感性とか知識とかを得ることができない。いろいろな音楽について学ぶことが、「音楽を学ぶこと」ではあるが、音楽一般についてとはいかない。ドレミファソラシドの八音階も一つのタイプの音階にすぎないし、違う音階もある。そういうことで言うならば、やはり宗教情操も個別の宗教に則して得られるものであると考えられる。
この点について、個々の宗教に即した宗教情操はあるが、宗情操一般がないというのは、個々の「木」はあっても「木」一般はないという議論ではないか、という形での反論がみられるようである。これは概念と実体の混同であり、記号論のイロハを学べば、その誤りにすぐ気づかれるであろう。また、何が「木」とみなされるかも、まさに文化的に決められることである。これも比較文化研究のイロハである。しかし、現実にはこうした基礎的なことを踏まえない議論を行う研究者が存在しているのである。
また、一般的宗教情操という例として、すぐ「いのちの尊厳」を持ち出して議論するというのは、むしろ宗教という問題にあまり真剣に取り組んでいない可能性があるのである。なぜなら「いのち」ということで言うならば、現在は臓器移植とかクローン人間などといった、さまざまな新しい問題が「いのち」に関連して生じている。宗教に関わりなく「いのちの尊厳」を説いて、宗教的情操を涵養するとは、いったい具体的には、どのようなことになるのか。例えば一人の堕胎した赤ん坊のES細胞を使って、ほかの人の治療に充てるということがすでに行われている現代世界において、「いのちの尊厳」はどう説明されるのか。こうした類の話は、現代には数多くある。生命倫理というテーマのもとに激しい議論が交わされている。そこでは宗教ごとに立場が異なることがはっきりしている。そうした現実を前にして、「宗教の尊厳」にまつわる一般的な宗教情操を教えるとはどういうことになるか。真摯に取り組もうとするほど、抽象的に「いのちは大切ですね」という言葉以上には進めないことになってくる。
これ以上深く「いのちの尊厳」の問題に踏みこんで教えようとするなら、やはりある特定の宗教的な立場というものに拠らなければ、説得的な説明は難しい。仏教は仏教なりの、キリスト教はキリスト教なりの、あるいはまた宗派ごとのこの問題への対処法が示されることになろう。「いのち」の具体的なとらえ方が宗教ごとに異なるというのは、比較宗教学的な知識が少しでもあれば、むしろ常識に属する。
そうした一定の信念の基盤なしに、宗教的情操について教えようとしても、生徒たちへの影響はほとんど期待できない。「いのちは大切ですね」という言い方なら、別に宗教の教師でなくても、校長の朝の朝礼でも言えることである。そういうことを宗教情操教育と銘打って議論する必要があるとは考えにくい。
国学院大学の宗教教育プロジェクトでは、多くの宗教系の学校を訪問し、宗教の授業を実際に見学し、生徒との面談を行った。その結果からすると、表面的な宗教情操教育であれば、生徒に受け入れられないケースが多いのが観察された。中学生・高校生あたりの年代というのは、敏感な感性をもつ時期であるから、例えば「いのち」の問題を語るときには、十分な準備が必要となってくる。そうしたことを考えても、「宗教情操の涵養」などというテーマは、教師にとって簡単なことではないのである。
5. 韓国における宗教教育の現状
現実問題として、公立学校にいささかでも宗教教育を導入することは可能なのかということを考える上で、韓国における議論は参考になる点が多い。この点に、簡単ながら触れておきたい。宗教教育プロジェクトでは、10回ほど韓国で学校調査を行ったり研究会合を開いたりしてきたが、韓国が抱える問題は、日本よりやや複雑な構図になっている。
韓国の宗教教育は一連の平準化の政策による影響を大きく受けている。1969年に中学校の無試験制度が始まり、1974年には平準化の政策によって学群制が導入された。1980年には大学入試での内申成績を反映させるといった一連の教育政策は、宗教系の学校における〈宗教〉科目に大きな影響を与えるようになった。無試験制度による抽籤入学制度の結果、本人の意思とは関係なく、特定の宗立学校に配定される多数の生徒が出てきた。この抽籤制度は、公立と私立の学校、そして私立のなかの宗教立の学校が混在するなかで行われるから、自分や家族の意志とは関わりなく宗教立の学校に行かなければならないという状況が生じうるのである。キリスト教徒である生徒が仏教系の学校に行かされるとか、その逆のケースといったものがある。この点は日本の状況とは基本的に異なっている。
韓国では、宗教系の学校では、通常「宗教」の授業を週1回行えるようなシステムになっている。一応選択科目としての「宗教」という授業になっているが。事実上、すべての生徒が「宗教」を選んでいる。このようなシステムであるので、宗教系の学校における宗派教育に対しても、一種の箍(たが)がはめられている。例えば他宗教・宗派についても言及するとか、現代社会における宗教の役割について触れるとか、特定の宗教を批判するような内容にはしてはいけないといった形においてである。
しかし実際はシラバスとおりにやらない例も多いようである。比較的幅広く宗教を扱った教科書を用いていても、実際の授業では、キリスト系だったらもっぱら聖書のことを話すといった形態である。日本と比較して、こういう違いはあるが、そういう学校であっても、週1回の授業がせいぜいである。それも生徒が3年生になったらやめるという所が多い。つまり、中等教育で宗教についての授業をもっと実質的に行うにはどうしたらいいかという点に関しては、実は日本と同じような問題を抱えているのである。日本も韓国も、公立学校の教師は、宗教系学校と違い宗教に対して非常に距離を置いている。端的に言うと、宗教についての基礎知識がほとんどない。宗教教育に対しては消極的である。
6. 親や生徒のニーズ
次に、親のニーズという点も無視できないことである。日本は「宗教を信じている」という人が2~3割という結果を示す国である。子どもをミッション系の学校に入れる親の大半は宗教的理由にはよらない。進学率とか躾に対する信頼度といった別の要因によって選ぶのが実情である。したがって、宗教系の学校に子どもを入学させて、もし子どもがその学校が関連する宗教を真剣に信じはじめたら、むしろとまどったり、止めたりする親が多いと考えられる。大半の親は、強い宗教教育が行わないことを前提して、宗教系の中学や高校に子どもを送っているのが現状である。
たとえばミッション系の学校のうち、ラ・サール高校、栄光学園などはカトリック系の学校であるが、進学率がきわめて高いということで選択されるのが一般的である。実際、キリスト教系学校のなかには、いわゆる有名進学校が数多くある。ミッション系の学校において、このような実情であるわけで、公立学校における宗教教育を推進して欲しいと積極的に考えている親がどれほどいるか疑問である。
生徒たちの宗教に対する意識はどうであろうか。中学、高校の生徒の宗教に関する意識調査はなかなか難しいけれども、彼らが大学生になった段階で、「中学・高校のとき、宗教系の学校に通ったことをどう思っているか?」といった形で、宗教に対して中等教育レベルでどのような意識をもっていたことを質問するのは容易であり、実際そのような調査を1992年には行った。
「授業が宗教についての理解や関心を深めるのに役立ったと思いますか」という問いに対して、少なくとも中学か高校のどちらかが宗教系であった者208名について分析した結果をみると、次のようであった。(4)これをみると、3分の2以上が宗教についての理解が関心を深めるのに役立ったと答えているので、結果的には、宗教系の学校に通ったことをある程度肯定的にとらえていると考えられる。しかし、これはあくまで宗教系の学校をみずから選んだ生徒たちの回答であり、非宗教系ではまた異なった意識をもっていると考えられる。
大変役に立った 24%
少し役に立った 44%
どちらとも言えない 17%
あまり役に立たなかった 8%
まったく役に立たなかった 5%
分からない 1%
また、この調査は1992年であり、オウム真理教による地下鉄サリン事件以前である。学生たちの宗教に関するイメージは1995年以後、顕著に悪化していることがこれまでの調査で明らかであり、宗教について学ぶ意欲は変化している可能性がある。
また、宗教に関する意識に関しては、大学生に対するアンケート調査の結果、宗教への警戒感が非常に強いことが分かる。そしてその警戒感は、やはりオウム事件によって急速に高まったのである。宗教に対するマイナスのイメージの高まりは、宗教界にとっては「1995年ショック(オウムショック)」といってもいいであろう。こうした状況のなか、公立学校で宗教に関することを教えようとする場合、最初から非常に厄介な条件のなかにある。(5)
7. 宗教系学校と非宗教系学校の違い
むろん、こうした悪条件を考慮しつつも、宗教についてのなんらかの教育をやることは、一定の意味をもつと言えるだろう。1992年、及び1995年~2001年まで毎年行った学生に対するアンケート調査の結果を見ると、宗教というものを比較的距離を置いて見ようとする傾向はオウム事件以降、一貫してあるわけであるが、宗教系の学校と非宗教系の学校を比較すると、多少ではあるが違いが観察される。この違いがどうなっているかは、宗教教育の効果を考える上では参考となる。
おおよその特徴を指摘すると、宗教系の学校に通うと、生徒は宗教に対する親しみが増加するのは確かである。いわゆる宗教アレルギーというものも若干であるがなくなる。例えば「宗教家の話を聞きたいと思うか」という質問に関しても、非宗教系学校の生徒よりは数%から10数%高い。また、過半数の学生が宗教に対してマイナスのイメージをもっているが、その程度が宗教系の生徒ではいくぶん和らぐ。
しかし他方では、あまり違いが見られないものもある。キリスト教系の学校でキリスト教を、仏教系の学校で仏教について教えることで、その宗教については一般的に理解も進み、何となく親しみもわいてくるというのはみてとれる。しかし、それ以外の宗教についての認識の度合いはどうかというと、非宗教系の学校に比べて、必ずしも高いとは言いがたい。きわめてわずかな違いしかない。このことから、各学校でやっている宗派教育というのは、やはり自分たちの宗教についての宗教理解には心を砕いているけれども、宗教全般についての理解を進めているかどうかについては疑問がある、と言わざるをえない。
宗教系学校のうちの三分の二程度はキリスト教系であるが、授業では聖書の話とかは詳しくするけれども、現代宗教については教師自身もよく知らないというような実例に数多く出会った。例えばある生徒が具体的に新宗教の名前を挙げて「どういう宗教ですか」と聞きに行ったとき、宗教科の教師が「それは新宗教だから知らない方がいい」という反応をしたという面談結果もある。その意味で、宗教に対する親しみがわくと言っても、ある程度限定された対象に対する親しみであって、宗教的情操とか宗教全般に対してとなると、あまりはっきりした影響は見て取れないと考えた方がよさそうである。
のみならず、逆効果ということも無視してはならない。とくに「教師の言行不一致」がもたらす逆効果は大きい。宗教教育はほかの科目に比べ、教える側の資質が非常に大きな比重を占める。他の科目であると、嫌いな先生であるが数学のことが詳しいからちゃんと聞くとか、英語の会話が流暢だから授業には身を入れるというパターンもありうるだろう。それは教えられる内容を技術として受け止め、教師の資質はまた別の問題と受け止められやすい科目だからである。
しかし、宗教関連の授業であると、教師が宗教について話し、「いのちの大切さ」や「平和を愛している」とか言いながら、その教師が酔っ払って喧嘩して相手を殴ったり、シスターが「神の愛」と言いながら、生徒に対して意地悪い仕打ちをするとなると、これはまったくの逆効果になってしまう。ますます宗教嫌いになって卒業していくという生徒も実際に面談調査の中で見出された。教師の裏と表を見てしまって「宗教家が嫌になった」と、われわれの面談調査の際に、はっきり表明した高校生もいた。宗教教育は「諸刃の剣」であり、やり方しだいで逆効果となる可能性の高いものである。
このような宗教系の学校における現状を踏まえるなら、公立の学校において、宗教情操教育を行うことの困難さは容易に予測できることである。この点を考慮しない宗教情操教育の議論は意外に多い。宗教関係者のなかには、「僧侶ももっと宗教教育の場に立つべきだ」と言う主張が見られたりする。仮に公立学校で、さまざまな宗教者を順番に招いて話を聞くというようなカリキュラムが、どの程度効果的であろうか。「今日はこのお坊さんに話をしてもらいます」という形で、僧侶を招いて、果たして宗教情操教育を実質的に行える僧侶がどれほどいるのかという疑問がある。繰り返すが、逆効果になる可能性も低くはないのである。
8. 現実的な課題とは何か
宗教教育はこのように非常に多くの課題を抱えているので、手をつけないほうがいいという結論に傾きやすい。しかし、これは宗派教育とか宗教の情操教育という観点から宗教教育を考えた結果であって、視点を変えるなら、より現実的な方策が選択肢として浮かび上がってくる。宗教情操教育は、基本的に家庭とか各宗教が主として担うべきことがらであって、政教分離が原則なっているような社会において行われる宗教についての教育は、おのずと別の観点のものが模索されるべきである。
そうした観点から、今教室である程度の対処が可能、あるいは期待されることがらは何かということについて、4点ほど列挙する。
一つには、伝統的宗教文化の学びである。宗教というものはどの国でも伝統文化と大きな関わりをもっている。その伝統的な部分をどう扱うべきかを学ぶ必要性が高くなっている。なぜ今ことさらにこういうことが問題になるといえば、社会における情報伝達のメカニズムの変容が生じたからである。従来ならば、伝統的なものは、地域社会とか家とか、そういう場でかなりの部分が伝えられてきた。「このお祭りはこういう意義と意味をもっている」とか、「あなたはこの年になったらこういうことを知るべきだ」ということも含めて、家族や地域共同体によって情報が伝達され、伝統が継承されてきた。しかしながら、現代社会においては、家庭自体が、親子で帰る時間がばらばらといった理由で、そもそもコミュニケーションが成り立たないような所が多くなっている。地域社会もとくに都市部であれば、つながりはきわめて希薄である。このような状況であるとするなら、かつて家庭や地域共同体が伝達機能を担っているものの一部を、教育の場がある程度肩代わりすることも求められるようになる。伝統的な宗教文化の学びということを、教育も多少分担しなくてはならない時代状況となっているということである。
二番目に、国内外の新しい宗教についてどのような態度をとるかを学ぶということ。伝統的な宗教というものは、宗教というより半分は社会習俗とか文化として社会に定着している。日本人は古くからこうしてきた、儒教の国ではこんなふうにしてきたとか、キリスト教徒は大体こういうような文化的なスタイルを持っているのだというような、伝統的な宗教についての話については探せばいろいろな情報がある。しかし、新しい宗教は情報が不足しているし、その活動や教えの内容は実にさまざまで、個々人での判断はきわめて困難である。
社会に対して積極的に貢献しようというような意識の団体もあれば、いわゆる「カルト」と呼ばれることもあるような団体のように、社会的なトラブルを多発する団体もある。があるように、何のためにあるのか、犯罪組織とどう違うのかというような疑問が起こるようなものもある。こうしたものに対してどう考えていったらいいのか。実はこれは個々の教員や学校による努力では困難な課題であるので、より大きな単位で対応を考えていくしかない。
三番目としては、グローバル化時代の特性への対応である。グローバル化は、価値観のせめぎあいを生じさせる。異なった文化のなかに生きている人が、情報の世界だけで存在しているときは、われわれと異なる価値観の人が世界に数多くいるという認識だけでも済んだかもしれない。しかし現在はそうした異なった価値観の人々が教室で机を並べるという事態も増えている。多様な価値観に対処することが、実践的な課題として生徒たちにも突きつけられるようになっている。この点についての教育は、家庭とか地域社会ではなかなか十分行えない。あるいは企業のような組織でも対処は容易ではない。学校教育で、異なる価値観の共存とはどういうことを意味するかということを教える必要が出てきている。そして、異なる価値観の代表的なものが、それぞれの宗教的価値観であることはいうまでもない。
最後の四番目、これはあまり指摘されないことであるが、それはマスメディアの発する情報への対処方法を教えるという問題である。メディア・リテラシーの一種と考えていい。宗教にはマイナスイメージが強まっているが、その原因はオウムなどいくつか社会的トラブルを起こした団体があることが大きく関係していることは間違いない。しかし、それとともにそうしたものがどう報道されているかということも、同じくらい重要な要因である。どのようなスタンスで報道するかによって、見る側の判断が大きく変わるというのは宗教だけに限ったことではないが、とくに宗教問題に関しては大きな影響がある。報道されるべきことが報道されなかったり、しなくてもいい面に殊更焦点が当てられたりということである。
オウム事件報道もそうであって、本当に突き詰めていくべき面の報道は、それほど多くなかったと言える。多くは教祖や教団幹部の一種スキャンダル報道的な面に焦点が当てられた。マスメディアは本来そうした性格であるという考えもあるが、であるとするなら、そのような性格であるということを学ぶということも必要になってくる。
教育の現場でも、マスメディアから発信される映像の影響力は大きい。これを敷衍していくなら、マスメディアから発せられる情報とは別種のさまざまな映像ソフトを、学校教育においても用意しなければならない。そしてメディア・リテラシーを教えながら、知識を得ていくという環境を構築するのが望ましいであろう。
9. 宗教文化教育の提唱
こうした条件を踏まえると、やはり公立の学校で行いうる現実的な教育は「宗教文化教育」ということになる。宗教情操教育というのは、きわめて解決しにくい問題をはらんでいることを指摘したが、この厄介な議論の構造を整理していくのは容易ではない。そこで、より積極的な視点をもち、公立学校でも受け入れられやすいタイプの教育内容は何か、実現可能性のあるものは何かというということから取り組むべきであろう。
「宗教文化教育」は、教育学で言われている「宗教学習(study of religion)」ときわめて近いものである。(6)宗教学習は、多民族国家であるアメリカにおいて、いろいろな宗教についての学ぶ姿勢を養うという趣旨のようであるが、日本や韓国では宗教文化教育という形で似たような目的が追求される。
狭い意味の宗教教育である「宗派教育」は宗教系の学校のみで行えるので、従来「知識教育」「情操教育」として区分されてきたものが、宗教文化教育においてはどういう位置付けになるかを最後に述べたい。
まず知識教育との関係であるが、宗教についての知識教育は、実はかなり宗教的な素養、感性というものがないと難しい。いわゆる受験的な知識、つまり「何年にルターが宗教改革を行ったのか」とか、「親鸞が書いた本は何か」といったものは、狭い意味での知識教育とでも言える。そうしたものは受験用の知識とでも言うべきものであるから、世界史、日本史、地理といったような各科目で学びうるのである。しかし、その中でもう少し宗教の内容について配慮した知識教育というものがありうる。これを宗教文化教育のなかにふくめていく。
他方、情操教育の中で文化的なものを理解しようとして育まれるものについては、より知識教育に近い部分である。一般的な情操教育というのではなくて、異なった文化の宗教を通して得られる情操というふうに理解すれば、情操教育の一部が宗教文化教育に含まれる。「いのちを慈しむ」「畏敬の念を抱く」ということを本当に実感を伴ったものとして体験させたいというのであれば、それは宗教系の学校に期待すべきであろう。その一歩手前のところで、他者への理解の姿勢を学ぶといったような態度がありうる。毎日祈りを日課としている人たちの存在、食べ物に厳しいタブーを課している人たちの存在、こういう人たちと実際に向かい合った場合、どうしたらよいのだろうか。そういうことを考えさせるのは、公立の学校でも必要であると考えられる。
つまり、国外の宗教文化・異文化教育的な内容と、伝統的な自分たちの文化について、いくらか掘り下げて学ぶということである。こうした教育内容であるならば、現在の公立学校においても、それほど拒否感はないだろうと予測される。(図参照)
ただ、ここで述べられたような宗教文化教育の実現は、個々の教師の努力や学校ごとの努力では、かなり困難である。国あるいは都道府県単位くらいでの取り組みが求められる。「宗教文化」の学びが21世紀の日本の若い人にとっては大事なことだと考えるならば、何らかのセンター的なものを造る必要がある。共同利用機関的なものを設置し、できる限りの資料を集めたり、ソフトを開発したり、一種の体験学習ができたり、生徒だけではなくて、むしろ教師が学べるようなシステムが求められる。その宗教について生徒に教える時にはどうしたらいいのだろうかということを知りたい教師が、学んだり研修できたりするような設備である。
公立学校の教師たちにとっても、「なるほど、これは自分たちにの教育にとっても有益である。必要性が感じられる。こういうことを生徒に教えれば視野が広まるかもしれない」というようなシステムが構築されなければならない。このような具体的なプランなしには、現在の公立学校における宗教教育をめぐる議論は、ほとんど進捗しないであろうと断言できる。(7)
注
1. 井上順孝『宗教教育の日韓比較』國學院大學、2002年。
2. 国学院大学日本文化研究所編『宗教教育資料集』すずき出版、1993年、及び同編『宗教と教育』弘文堂、1997年。
3. 菅原伸郎『『宗教をどう教えるか』(朝日新聞社、1999年)における議論を参照。
4. 田口めぐみ「中等教育における宗教教育の意義」(『宗教と教育』(前掲書)所収)に示されたデータを引用。
5. この点についての細かなデータは、拙論「現代学生が示す宗教への意識と態度―1992年~2001年のアンケート調査の分析」(『国学院大学日本文化研究所紀要』92、2003年)を参照のこと。
6. 江原武一編『世界の公教育と宗教』東信堂、2003年。
7. この点については、拙論「宗教文化教育の提唱」(『教育』53-11、国土社、2003年、所収)を参照のこと。