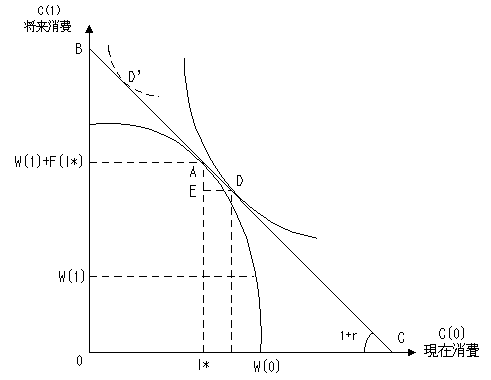
資金循環分析とは,通貨・資金の流れを実証的に観察して、金融全体の仕組みと動きをとらえ、金融と経済の関係を明らかにすることを目的とする金融分析手法の一つである。
資金循環分析の主要な論点は次の通りである。
(1)経済の実体面と金融の関係−投資・貯蓄・経常収支バランスと資金循環バランス
(2)広義金融市場の分析
(3)経済・金融面の国内面と対外面の関係
(4)経済の流動性と金融資産負債残高の蓄積
(5)金融面の作用の支出面への波及−金融政策の効果波及の問題
(6)世界の資金循環の分析へのアプローチ
国民経済全体を仮に人体に例えるならば、通貨および資金はあたかも血液のように企業相互間・企業と家計・企業から政府・政府から企業、また家計から政府へと循環している。その間に様々な商品・サービスの生産と消費、所得の形成と消費が行われている。(通貨の産業的流通面)
また、通貨は、企業が生産活動に必要な資金を調達したり、家計が所得の一部を銀行預金や有価証券の購入に充てたりするなどの金融的流通も同時に行っている。
このような経済全体の循環の中では、ケインズが「雇用・利子および貨幣の一般理論」いわゆる「一般理論」で述べているところの『貯蓄=投資』の関係が成立している。
従って経済全体としては貯蓄と投資は恒常的に等しいが、部門別には必ずしもそうではない。ならば全体の均衡を保つためには黒字(貯蓄超過)部門から赤字(投資超過)部門に資金の流入があるはずである。このような資金の循環を分析する具体的アプローチとして資金循環分析では、「資金循環勘定」を用いる。
この「資金循環勘定」は、「部門」と「取引項目」により組み立てられる。部門とは、無数の経済主体によって個々に行われた通貨の受け払いや資金の貸借取引をマクロ的に集計し、経済主体のうち同質なものをグループ化したものである。
「取引項目」とは、資金取引がどのような形態で行われたかを項目別に分類しておくもので、これにより資金の金融的流通の実態が明らかになる。「資金循環勘定」は前記のように「部門」と「取引項目」に分けて記録されるが、具体的にはフロー表の「金融取引表」とストック表の「金融資産負債残高表」から成る。
「金融取引表」は日本経済を5部門に分け、うち金融部門を3内訳に分けさらに海外部門を設けてこれらの一定期間の資金の金融的流通の集計値を記録したものである。
「金融資産負債残高表」は資金の金融的流通の背後にある金融負債の蓄積状態を記録したものである。
以上のように、資金循環分析とは、資金の金融的流通の態様と作用を特に通貨の産業的流通との関係において分析し、金融システムの経済に及ぼす影響を検討することを目的としている。
部門別貯蓄・投資バランスの変遷
部門別貯蓄・投資バランスの変化については、テキストP47図2−11及び配布資料1にある「部門別資金過不足」の資料を検討することで、実体経済面の変化が部門別貯蓄・投資バランスの変化にどのように影響したのか理解することができる。
高度成長期・70年代のインフレ低成長期・80年代及び90年代前半の期間を検討の対象とする。
個人部門は、この間、多少の変動はあるが、一貫して資金余剰(貯蓄超過)であり、資金の貸し手である。
逆に大きな動きがあったのは、企業部門・公共部門である。60年代の高度成長期から70年代後半の低成長期への移行にともなって、資金不足部門の交代である。すなわち、資金の借り手のトップが企業部門から公共部門へと入れ替わった。
理由:公共部門=均衡財政→国債発行へ→景気拡大税収増加のため資金不足低下
企業部門=設備投資→景気停滞設備投資鎮静化→半導体革命景気拡大傾向
海外部門については、2度の石油ショック時には、資金余剰(我が国経常収支赤字)となったが、全体的には資金不足(我が国経常収支黒字)となり80年代前半よりさらに上昇し、公共部門の資金不足をはるかに上回っている。
その後、資金の借り手のトップは、80年代後半の円高、内需主導型経済への転換、半導体革命、金融緩和にともなった景気拡大局面で再び企業部門へと資金不足・資金の借り手トップの座が移ることとなった。
資金取引の意義を二期間のモデルで図解せよ。
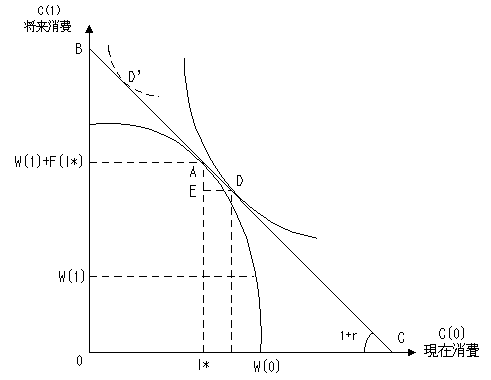
C(0):現在消費
C(1):将来消費
W(0):今期の所得
W(1):来期の所得
I* :経済主体にとって最適な投資水準
W(1)+F(I*):将来所得
BC :現在財1単位と将来財(1+r)単位の交換が可能であるとし、この線上で現在消費・将来消費を任意の点で選択できる。(消費可能領域)
r :実質利子率 資金取引市場が存在するとして、rの利子率で資金取引を可能とする。
AE :今期の借り入れに対応する将来の返済額
DE :経済主体が今期借り入れる資金量
点D :資金を借り入れることにより得られる、より満足度の高い消費点
点A :自給自足の場合の消費可能領域と資金取引が可能である場合の消費可能領域との接点(投資点)
点D’ :点Dに消費点を持つ無差別曲線の経済主体よりも、将来消費を重視する経済主体は資金を貸し付け、線分AB上の点D’を消費点に持つ無差別曲線を描く。
資金取引が発生する理由は、個々の経済主体において必要とする財・サービスの取得や支出に時間的差異があるからである。
資金取引が不可能であれば、他の経済主体から資金を得ることができないため、自給自足の低い経済成長しか実現できない。資金取引が可能となることによって個々の経済主体の支出決定の選択機会及び自由度が高められ、その結果として経済全体の投資額が増加し投資の効率的な配分が行われ、投資が不可能な場合よりも高い経済成長が期待できる。
参考文献
金融論 堀内昭義 東京大学出版会
入門マクロ経済学 中谷 巌 日本評論社
入門価格理論 倉澤資成 日本評論社
新版わが国の金融制度 日本銀行金融研究所
日本の金融システム 蝋山昌一 東洋経済
金融読本 呉 文二 東洋経済
島村高嘉
日本経済の資金循環 石田定夫 東洋経済新報社
