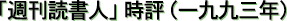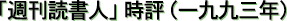|
|
|
| 詩のエネルギーの貯水池
|
| 宇野邦一、瀬沼孝彰らの詩集
|
言葉で、五感から得たもの、たとえば映像を再構成してゆくとき、再帰的なものに無意識が投射される。感情的なものから論理的なものまで、どんな材料でも詩は可能だ。そして材料は“傾向”として通過されるのにとどまる。思考から思考へと繋げるときの心的エネルギーの状態、それが静かなものか、動きのあるものか、そのエネルギーの密度がどのくらい読者のもつ言葉を入口にして読者の心的エネルギーに覚醒を与えるかが、その詩の濃度なのだ。
宇野邦一『日付のない断片から』(書肆山田)の思考は素直な連続性を感じさせる。典型的に起承転結をもって、そのエネルギーの段差を暗示してもいいし、最初から爆発させちゃってもいいし、韜晦しながら最後であっと思わせる段差を暗示させてもいいと思う。それは固有の興味の中心を対象にした物事に発せられる言葉であるはずだろうと思うのだが、宇野の素直に流れる思考のなかで、詩の方法はうまく機能していないと思う。一箇所ぐらい、論理的な言葉よりイメージ・トリップの優位になる場所が必要だと思う。おそらく宇野は意味から逸脱する言葉に慣れていないのだと思う。《皇帝たちの臭う口に/きみの背中を贈るとき/どこをさがしても/煙のみえない性器時代/語れない明日の臓物/瀕死のファウル・ボール》
瀬沼孝彰『ナイト・ハイキング』(ミッドナイト・プレス)には、都市の裏側のうらぶれた風景や人物がたくさんでてくる。つげ義春みたいにラジカルさで衝撃を与えるような、映像あるいは物語を差し出せたら“へたうま”の詩も本物になるのではないだろうか。
山本博道『死をゆく旅』(花神社)は前作に続いて、父の死が主題。この国の生の単位は家に向かって収縮して、バッチリ切れたところで書けないのが死の主題だが、前作よりよほどよくできていると思った。井上瑞貴らの「蟻塔」三十一号、大西時夫らの「白」二号はこの先期待させるものを感じる。
(一九九三年一月十一日号)
|
|
|
| 淡々とした発掘の作業
|
| 遠丸立『埋もれた詩人の肖像』
|
遠丸立の『埋もれた詩人の肖像』(武蔵野書房)の淡々とした語り口には、ぼくにカミソリのような批評的創見を突き付け、反応を促すというようなところはなかった。それには二つの意味がある。まず、多くが一九七〇年代に書かれたこれらの批評を通読して、現在、ずいぶん遠くまできたんだな、という感慨である。それから副題の“同時代詩史の落丁をひろう”というような緩やかな批評意識の淡泊さ、である。たとえば林芙美子の詩について書かれた冒頭の“詩の発掘”と、二番目の“同時代詩”を特に興味深く読んだのだが、むしろその手つきはのどかに感じられ、引用された永山則夫、長岡弘芳、卜部昭二、平田好喜、水こし町子、立中潤など詩史に忘れられようとしている詩人の引用と紹介を、のんびりとした読み方で味わった。遠くまできたんだなという感じは、ここにある問題性が直接にはぼくと関わらないという印象からきている。詩的表現全体が七〇年代から八〇年代を通りぬけることによって、決定的な変容を遂げてしまったのではないだろうか。にもかかわらず、この本には優れた美点がある。それは“埋もれた詩人”を日に晒す地味な作業を遠丸なりに続けようとする意思である。
『銀河鉄道の夜』のジョバンニとカンパネルラをユリディスとオルフェになぞらえたりする、文章の情念の深さと面白さのある天沢退二郎『宮沢賢治の彼方に』がちくま学芸文庫になった。こういう本が文庫化されるのは読者にとって、その手軽さに大きな意味がある。賢治論なら谷川徹三『宮沢賢治の世界』、平尾隆弘『宮沢賢治』、最近のものでは吉本隆明『宮沢賢治』など文庫でも読みたい。
「文学」冬季号の真木悠介(=見田宗介)の〈類の仕掛ける罠〉は『宮沢賢治』(一九八四年)の延長に新しい視点を提出しているようには思えなかった。詩集『浦へ』(福井桂子、れんが書房新社)の植物名への思い入れが面白い。さらに深みを見たい欲望に駆られる。
(一九九三年二月十五日号)
|
|
|
| さまざまな異化作用
|
| ――吉田裕『歴史の「中心」をめぐって』
|
吉田裕『歴史の「中心」をめぐって』(非売品)は一九八九年から九一年までの、詩を書いている築山登美夫への手紙を中心に編まれている。八九年の春から一年間フランスにいて、ルーマニアのことなどが日本への情報とは違ったかたちで受けとめられたことなど、もちろん文学をやっている者が状況とどんなふうにかかわっていくか、という根底的な問題ももどかしく感じながらも書かれている。この本のもうひとつの中心はジュネットのセミネールで直接講義を受けた体験と、ジュネットの思想の解析である。ジュネットはタイトル、献辞、序言、あとがき、インタヴュー、自己解説、回想などの周辺のテキストをパラ・テキストという概念にまとめ、テキスト論を展開する。手紙の形式からいっても量的にも、ジュネットの考え方をめぐった随想というかたちであり、著者の関心はバタイユに移っていくところで手紙は終わっている。ちょうど同時に読んでいた講談社文芸文庫の磯田光一『萩原朔太郎』の評伝的にオーソドックスな綿密な事実確認とパラ・テキストの解析の延長上に、鮮明な批評精神がみなぎっているのに感動していた。テキストの時間空間軸、パラ・テキストや事実関係の時空軸、歴史の時空軸、批評家の時空軸、揺るぎなく自在で骨のある批評である。
吉田の本を読んでいてもうひとつ感じたのは、西洋やその他の国の思想の異化ということが身近に自然になってきたということである。わが家にも昨年アメリカ人の少年が二カ月ほど、ごく自然に生活していった。ヘヴィメタルバンド・メガデスのマーティ・フリードマンのアルバム『憧憬』の〈Realm Of The Senses〉という曲の演歌のメロディラインの異化作用。日本の時間的な隔たりによる異化ならば寺山修司作高取英演出『盲人書簡』。
谷かずえの詩集『ノー・グラース』(北國新聞社)の昆虫や植物たちの小世界の緊密でのびやかな構成も今月記しておきたい。
(一九九三年三月十五日号)
|
|
|
| 夢とエロスが堕ちる手前で
|
| 吉沢巴『式典』
|
夢をそのまま記述すれば、書き手のイメージの喚起力が試される。しかし、詩は言葉を記しながらなにものかを確認する作業であることをやめない。だから夢を記述する詩も作る場所において“嘘”も“ほんとう”も、常に試されているという緊張感をはらんでいる。もちろん山師や変態でもいいのだ。だいいちに、言葉が詩に凝縮するところに“嘘”がなければいいことになる。虚でも実でも徹底すれば詩になるわけだ。
ところで、作品として提出されたときそれは全面的にあますところなく言葉の出自は読者によって見抜かれると思ってまちがいない。そこにテキスト至上主義も出てくる素地もあるし、いっぽうでテキスト成立の事実関係において厳密に釘をさしておけば、奇態な神秘主義におちいってもいいという批評的戦略もなされる原因もある。いずれにしても優れた書き手の夢の記述は、迂回しているように見えて逆に直接的に言葉の質を露わにするのだ。
吉沢巴『式典』(思潮社)は夢の非論理性や空間混乱性をバネにして、成立させているような詩群を収めている。粕谷栄市や粒来哲蔵の散文詩の系列のように見えて違うのは、クライマックスの部分が低い物語性の水準に抑えられているところだと思う。徹底的なイメージの沸騰の頂点に、混乱してそれでいて鮮烈な場面を提出することにこれらの詩は賭けられていない。意識的にそうなっているのではないが、はやくいえばそこまで欲望が深くないのである。《春の野辺には/静かな駅が似合う/瓜二つ兄弟の駅が/たんぽぽ道の両側にあって/黒い折紙の汽車が仲良く停まっている/(中略)/あの春の野辺で赤いスカートをまくり/放尿したい/と、思ったとき/見知らぬ乗客が/灼けた火掻き棒を私につき立てた》(〈車輛〉部分)沈黙の動きから言葉にわたる嘘を椰揄すること。このイメージの抑えられた動きは通俗的に堕ちる手前で耐えている。
(一九九三年四月十二日号)
|
|
|
| 典拠となる孤独
|
| 北村太郎『すてきな人生』
|
フジテレビ系の朝の子供(?)番組『ウゴウゴ・ルーガ』の導入映像は、サラリーマンが路地の居酒屋で飲んでいるところをコンピュータ・グラフィックスで作ったものである。カウンターのなかには金属の怪物がいる。引戸が開くとスーツを着た男が赤ん坊のあやし道具を鳴らし、眼鏡のガラスがギラッと光る。新しい感覚のこの番組の初めのこの映像にどんな意味があるのだろうか? 実はほとんど意味はない(笑)。
北村太郎の遺稿詩文集『すてきな人生』(思潮社)には十五篇の詩と新聞などに書いたエッセイが収められている。発表順からいえば最後の詩〈八月の林〉に次のような部分がある。
《うらみごとを、いわせぬ速さで/風は来たり、風は去り/(略)/ヘビやチョウのたぐいが、林の/神経のように、かろうじて/働いているようだけれど、見えない//麦藁帽子を、ひざに置き/下の、池のほとりのベンチに坐る男を/林ぜんたいが、気づいていて/知らぬふりのまま、遠ざけており/男は、うなだれて動こうとしない/(略)/ひどい暑さが、水面を緊張させて/虫いっぴきの飛び出しをも、けっして/許そうとはせず、男の/眠りを、眠りの手でゆっくりかきまわし/ずれているひざの帽子を、落とさせない》静かな作品だが、ばらまかれる否定の辞にいくらか強迫観念の響きがある。ほとんどの生活者は決められた生活範囲の枠組みから、飛び出そうとはしない。変化はだれだって怖いのだ。飛び出そうと思えばいつでも飛び出せる、とは思っている。その反面、いちいち調整が面倒臭いなというイライラはあるだろう。「どうも、どうも」なんて言いながら内心「面倒臭いな」と思っているわけだ。〈マツリのあと〉という文章にマツリで騒いでいる人の風景は楽しさ三分、怖さ七分で薄気味悪いというところがある。「荒地」の詩人たちの時代的刻印のある本物の孤独は典拠となる。
(一九九三年五月十七日号)
|
|
|
| 基礎的な筆力
|
| 橋本碧『路地』
|
橋本碧『路地』(千路留)は詩集というより掌篇小説集といったほうがいいかもしれない。ぼくはこの本に基礎的な筆力を感じた。作者は〈あとがき〉で《なぜ、これほど路地が好きなのか、解らない》と書いている。この空間設定のなかで繰り出すイメージには、切れがいいが重いところがあってちょうど主題と釣り合っている。《――骨は白いでしょうか。/――さあ、晒された骨は白いでしょうけど。/――生きている骨は生白いのかしら。》(〈骨と石〉部分)それらは重い塊のような形で据わっているが、その裏に十分な筆力がある。
詩についての詩を書くのは、それ自体が自家撞着といえる。詩とは何か、という詩の主題は、入れ子にならないからだ。詩自体が詩を追究する以外に手立てはない。こういうことを谷川俊太郎が考えていないはずはないとは思うのだが、『世間知ラズ』(思潮社)では、詩についての感慨を含む詩が多数収録されている。上記のことを踏まえていれば、詩についての詩は、そこがいわば空虚になるところでそれを意識的にばらまいた、ということになるかもしれない。そういう試みという見方をすれば、ひねくれていて面白いといえる。しかし、作者は大まじめだ。《紙飛行機が宙に浮いていた数十秒の間ぼくの心を満たしたもの/それをぼくは詩と呼ぶ》(〈紙飛行機〉部分)《一篇の詩を書いてしまうと世界はそこで終わる/それはいまガタンと閉まった戸の音が/もう二度と繰り返されないのと同じぐらいどうでもいいことだが》(〈一篇〉冒頭》大まじめなところに対応すれば、「ああ、そうですか。でもそんな一般論はなりたたないよ」と茶々をいれたくなるが、これ自体詩として書かれているのだ。いわば、ダブルバインドだ。野村喜和夫『特性のない陽のもとに』(思潮社)の自己陶酔の気分には、どこか質朴なところがあり、これが救いだし、まだ遣れる感じがする。
(一九九三年六月十四日号)
|
|
|
| 琺瑯びきの浴槽と喩法の解析
|
| 瀬尾育生と北川透<
|
関係性というものは、“実現”されなければ露わにはならない。しかし言葉ではすべて語られたことが実現への留保になりうる。つまり関係性を仮構したことによって、関係が実現することにはならない。いっぽうで言葉が“知”のなかで淫し、関係性の瀬戸際まで創作することは可能である。これはけっこう冷たい事態といえるかもしれない。しかし遠隔操作のように自分が理想とする関係性を弾にして撃ちこむことはできる。たとえば僕だったら自分のもつ極限の自由の概念をそこらじゅうに撃ちこみたい。単なる言葉だけの操作だが、そのへんの意思だけは直接でありたいと思う。
現代詩文庫版『瀬尾育生詩集』(思潮社)に未刊詩集として収められている“〈DEEP PURPLE〉”を読んで、琺瑯びきの浴槽をイメージした。これは瀬尾の作品の関係性や感じられるライフスタイルの比喩だ。なぜかしら蛇口から言葉がはいり、排水口から言葉が出ていくのを外側から見ている映像が湧いてきた。もちろん浴槽で水は溜まり温熱による対流や裸の人体などから作用を受ける。木でもタイルでもなく琺瑯びき。
《その夏は、過去のどの夏より冷たかった、と思う。/ゆきなさい。帰ってきなさい。そこにとどまりなさい。/だれも通らない夜更けの路地の、麺麭(パン)屋にすわりつづける細い店番になって。》(〈月蝕〉末尾)
最後まで喩が織物のようになって起伏を作っていく。近頃これほど安心して読める詩篇は稀だったが、そこに表われる関係性は遠くにたたずんでいる琺瑯びきの浴槽だった。
北川透『詩的レトリック入門』(思潮社)は現代詩の喩法分析の書である。《詩的メタファーとは、既成の意味の関係では表現できないものを、未知のイメージとして表現するレトリックである》という考えが繰り返し述べられている。詩的意味、詩的境界の互いの侵犯を基とする展望。示唆的な本だ。
(一九九三年七月十二日号)
|
|
|
| 素材としての夢の映像
|
| 寺門仁『木に育つ魚』
|
夢は、端的にいえば精神の経済に関係している。拡張すれば、共同的なものに概括できる類型に分けられなくもない。これが物語の類型に関係しているとすれば、詩の喩に関係しているのは固有に行なわれる時間空間の置換、またそのモザイク状の在り方である。
夢が精神の経済の調整の役目に関係しているとすれば、その映像や細部も“必要”であるから自然に作られる、ということができる。機能からいえば再構成によるプラスの調整である。だから夢の記述を読むとき、読者は不安から安心への方向を嗅ぎとっている。楽観的なハッピーエンドで終わる作りものの物語を読むときより、悪夢の記述のほうが逆に不安を消されるということは当然ある。
寺門仁『木に育つ魚』(思潮社)はこの意味でとても自然な書記である。
《咲き初める白梅の 剪定をと/太枝を切ったが/落ちてくれない/ハンマーで下部を叩くと 根元から/ころりと倒れた/幹の仄暗い洞から/紙魚のごとき銀白色を光らせ/鮭ほどの太った魚が 横ざまに/ぴょろっと吐き出された》(〈木に育つ魚〉前半)
《妻にカメラを持ってすぐ撮りに来るよう/母屋へ駈けた》(同作品末尾)
操作が粉飾になるということからいえば不明確さをまったく逃れようとするのが夢の記述だ。だから粗雑さがでないのが不満にもなる。そしてここにあるような不可能を可能にしてしまう転換に対するショックの度合が物語の基礎だ。コミュニケーションの映像作りから白昼夢、白昼夢から瞑想の訓練、そして睡眠時の映像まで、さまざまな階梯がある。それらを切れ目なく統合して構成できるのが詩だ。もちろんここに優勢意識や劣等意識、ルサンチマンなどの悪も含まれるし、それを読んで反応するのが楽しみになるのだと思う。
田中宏輔『Pastiche』(花神社)にはナイーブさが自然に作ってしまった皮膜がまどろっこしいところがあるが、愛すべき一冊だ。
(一九九三年八月九日号)
|
|
|
| 新しい都市の音声
|
| 辻仁成『希望回復作戦』
|
言葉が都市のなかで自由に発せられて、それが表現の重要な新しい側面を見せてくれるという場合、どうしても現在の都市への哲学が自然に表われてくる。膨大な人たちが行なっている詩作――詩、歌、句の方向の一つの大きなポイントとして都市がある。詩作者たちの雲のような混沌とした塊から、その声が届くようにする装置は規模の大小があっても、いくつか存在する。いちばん遠くまで届く声は何か。それは明らかに現在の都市の元型のイメージを持ち、また現在までの都市の固定的概念を破砕できている表現だろう。これは読者の数には関係しないし、当然生まれてくる集団のスノビズムやジャーナリズムも突き抜けてしまうものだから、結局は大きな流れを作っていくわけである。
辻仁成『希望回復作戦』(集英社)からは何よりも新しい都市の音声が聴こえる。
《よく(マシーンになるって言ってたよな)/どうやって死ぬのかとおれは考える/どうやって生まれたのかは/考えない/(マシーンになれれば別なんだ)/だってそれはもう/過ぎてしまったことだから》(〈だからどうということもないけれど〉冒頭)
この作品の“いらつき”の裏側には都市への哲学が胚胎している。この詩集を読んでぼくは吉本ばななの近作短編集『とかげ』(新潮社)を思い出した。とくに〈大川端奇譚〉は乱交経験がたくさんある女性の心が恋人に受け入れられるときの陰影が一瞬に描写されている、という脱システムの物語だ。
岩成達也『フレベヴリイのいる街』(思潮社)、加島祥造・新川和江『潮の庭から』(花神社)、池井昌樹『水源行』(思潮社)の三冊の主題も、都市の内部、都市から近郊都市、上京してきた田舎への追懐の変容といくつかのベクトルをもっているが、逡巡もなく入り込めることからいえばこの三冊はあまりにもすっきりしている。持ち味を楽しむかたちでこれらを読んだ。
(一九九三年九月二十日号)
|
|
|
| シナプスの葉脈
|
| 建畠晢と高柳誠の詩集
|
人との関係においてのこだわり、断裂は詩の映像の繋がり方に投射される。機能的関係も感情的関係も、いくら砦のように作品を構築していっても投射されている。構築的な作品を読むときにも、読者はこちら側で再構築しながらもその裏側に作者の人との関係を読んでいるといっていい。たとえば宮沢賢治の〈永訣の朝〉の聖性に、この作者の人間関係の在り方ならきつい隘路だが永遠についていくことができるなと思う、それが感動である。しかし聖性はめったに現われてこないし、複雑な経験を経てイノセンスを保つのはパラノイアックともいえる持続の困難が控えている。
詩集が個人史を時系列で横割りにしたような記念碑とみると、その時点の化石のように鮮明であったり曖昧であったりする作者のシナプスの葉脈が見えてくる。建畠晢『そのハミングをしも』(思潮社)、高柳誠『塔』(書肆山田)は共に散文詩で、とくに『塔』は構築的である。はっきりとした映像を追い求めるという意味では一般的な散文詩の構築の手法だといえる。だからミステリアスな空間に誘おうとする意思はすっきりとしている。『ハミングをしも』はもっと複雑な何かをいおうとしている。《 まあ嘘だと思う人は多いだろうが、カボチャには胆石があっ/た。手術は成功したから安心だが、どうしてカボチャに胆石が/できたかというと、謎である。人生には説明のつかないことが多いが、カボチャの一生も同じようなものだということだ。》(〈カボチャの胆石〉冒頭)
喩の飛躍とシニシズムを織り交ぜた口調で構築的であろうとするのを避けているのだが、結局構築的になっている。シニシズムというのは二種類あって、単純な直接性を経た徹底的シニシズムと、実際に作者のシニックな性格がわかるものがある。この詩集の場合後者だろう。これは逆に世俗的なのだ。平出隆の散文集『左手日記例言』(白水社)も似たような意味で淡泊だと思われた。
(一九九三年十月十一日号)
|
|
|
| 硬化と融解のリズム
|
| 平田俊子と伊藤比呂美の詩集
|
日常のなかで観念的なものが硬化したり、融解したりする過程がそのまま生活のリズムになっている。おおっぴらに自分の家庭のことを話すことは、帰りの居酒屋などでなければ顰蹙をかう恐れがあるのだが、微細な日常の心の移ろいを描ききる私小説という形式は、そういう恥じらいを捨てることによって”普通の人“普通の人”を成立させている。詩ではどうかというと、そのものが硬化、融解の過程という側面があるから難しい。平田俊子の『(お)もろい夫婦』(思潮社)の一部の作品を雑誌掲載時に読んだとき、夫婦別居という日常の物語化の過程が中途半端に見えたことがあった。今度詩集にまとまった連作を読んで、一定の抑制がうまくフィクションとして成り立って完結しているな、と思った。
ブロック著『マーフィーの法則』(アスキー)がよく売れているのは、《絶好のチャンスは最悪のタイミングでやってくる》というようなユーモアが、硬化した観念を一時的にでも融解する効果があるからだと思う(再読のときはつまらないかもしれないが)。平田は一発勝負のギャグでうまくこの連作をまとめた。何回か笑うことのできた詩集は珍しい。伊藤比呂美『わたしはあんじゅひめ子である』(思潮社)は平田の詩集より身体を観念に近付けている。これは力量というより、エロスへのかかわり方の差異だ。
吉田裕著訳『聖女たち――バタイユの遺稿から』(書肆山田)はバタイユの三つのテキストを訳し、〈淫蕩と言語と〉というバタイユ論を収めた本である。バタイユのエロチシズムの考察や、それを追究する散文詩、小説の世界はほとんど途方もない場所までいっている。観念的に行く着くところまでいっているといってもいい。吉田の論考はそれを考えるときの適切ないとぐちを与えている。またバタイユのような作品はきわめてヨーロッパ的で、日本人には一つの身体からはとてもこういう観念的求心はできにくいと再確認し得たと思った。
(一九九三年十一月十二日号)
|
|
|
| 幽かなものを追求する姿勢
|
| 吉田加南子と鈴村和成の詩集ほか
|
新しい好奇心への通路が作品に見えないと、まとまりは感じられても、通過していってしまう。力動的でないと詩集はおもしろくない。自然にできた一定の水位で言葉を記す、しかしその水位には疑いがある、もしくは次の興味の対象へとはやくも視線をすべらせている、という詩集がおもしろい。現在、幽玄のようなものをまともに追求するのは可能だろうか。仮の結晶みたいな形として疑いながら、幽玄がにじみ出るように追求するしかない。あるいはそちらへは絶対行かないという意思が詩を成立させる。「カッコいい」というのも、読者が決めることで「ほら、カッコいいだろう」と書いてもダサく感じられる。このあたりが時々刻々と自分の言葉を客観化する必要がある所以だ。
吉田加南子『定本 闇』(思潮社)は、《吐きだしたいの//じぶんを》のようにまっすぐにかそけきものを追っているように感じる。吉原幸子の詩はその真摯さが、僕の印象では異様な領域にまで達していて、いわば幼形成熟になっていて腑に落ちるところがあるのだが、吉田にはそこまでの求心性はなく漂っている。しかし爽やかだ。栗原洋一『草庭』(思潮社)はもっと造形的な意思を感じるが、やはりか幽かなものに迫ろうとしている。しかし、現代詩の造形の範型にまとまるところに粘りがないと思う。鈴村和成『ケルビンの誘惑者』(思潮社)も、ある意味では微細な構造体を追っている。作者の批評や翻訳を読むと、淡々としたところがちょうど鈴村と等身大で生き生きしているのがわかる。この詩集のイメージを支えているのはとても庶民的な素直な部分なのだ。
加藤健次『やなぎ腰のおとこ芸者』(思潮社)、近藤洋太『水縄譚』(思潮社)の二つの詩集の言葉は力業をやろうとしている。イメージのキレという観点からはそれほど印象に残らないが、とにかく押さえ込んでいる。その力瘤の当否はこれから決まるだろう。
(一九九三年十二月十日号)
|
|
|
一九九三年回顧
容赦のない独創性が現われる時
|
| 現代詩の様々な試み
|
僕は高校に入ったころから、近代詩、現代詩を読み始めたのであるが、それまでに読んできた翻訳小説などの西欧世界のイメージがプリズムの役目を果たして、日本語でのイメージを一定の幅に拡大したように思える。しかし、光の密度はその拡大に比例して高くなったとはいえない。なぜこんなことを思い出すのかというと、限りなく一回性の世界を言語体験し、こちらの世界に戻ってくることの構造を考える必要があるからだ。この体験に似た一回性は徐々に速度を増して数多くなり、ついにはほとんど日常のなかで振動になったともいえる。また異質の世界を一回日本語で覆うという作業のため中空に置いた感じになり、頻繁な情報アクセスのため、中空が肥大していっている。表現の当為に対する判断もこの構造の雛型の無意識に触れることから始まっているように思う。
吉本隆明『世界認識の臨界へ』(深夜叢書社)の〈成熟と死と生き延びるもの〉というインタビューで吉本は《意識はぼくらでも統御できるんですが、統御できない無意識が若い世代は荒れてないんですよ。》と言っている。体験の強度というところから無意識を世代的に見ると、劇的な転換はなく、細かな波動が認識されるのかもしれない。その荒れていない無意識が客観化され、まっとうに生成されるものの兆しが現在現われ始めたのではないだろうか。前の言い方でいえば、肥大する中空や頻繁なアクセスを通じて、また実際の交通によって得られたイメージによって持続的な分析の出発の兆しが見え始めたといってもよい。言語の一般性からは《映像言語であれ文学の言語であれ、それが表出されたとき、つぎにどのような言葉がくるかという予定性は、身体行為では、ひとたび表現した映像言語や文学言語に対して、否定の意識を働かさないとどうしてもつぎの言語が表現できません。いつでも否定意識を媒介にしないと、差異性が表現されていかない。》(前掲書〈現代における言葉のアポリア〉)というような認識がある。書字や音声という身体行為としての言語表現と媒体のさまざまな高度化のなかに、生成、壊滅、再生が繰り返されていく。中空に設定したものが希釈され、やがて移ろっていく。それが客観化されて設定するものの素地が見えだすとき、世界が見えてくるのではないだろうか。容赦のない独創性が現われるのはその時だ。
徹底性と無垢なるものの保持はその持続にしか成されない。現代詩の厚いさまざまな試みのなかに、兆しである信号をいくつか受け取ったと思う。『瀬尾育生詩集』(現代詩文庫、思潮社)は意思の中に対峙すべき関係性の成分をみることができる。建畠晢『そのハミングをしも』(思潮社)や鈴村和成『ケルビンの誘惑者』(思潮社)は現在の中空の濃度を見せてくれる。僕は、作者たちが回帰的になったときには必ず決着をつけるべき成分が含まれていると思う。いっぽうで辻仁成『希望回復作戦』(集英社)などの生活のにおいをさせながら高度な都市の音声を放っている詩集には限りなく愛着を覚える。また北村太郎『すてきな人生』(思潮社)の“荒れた無意識”の底の清澄さには、少なからず詩を書くことの勇気を与えられるといってよい。
批評では北川透『詩的レトリック入門』(思潮社)が、“恐るべき啓蒙の書”には届いてはいないが、再読すべき優れた喩法分析の書だと思われた。(一九九三年十二月二十四日号)
|
|
|
|
Copyright (C) 1993 Shimizu Rinzo, etc. |
|
|
「週刊読書人」時評(一九九二年)
|
|
■Shimirin's HomePage■Urokocity■SiteMap■ |