PC処世術 - パソコンの周辺機器
周辺機器 - 年賀状に見るプリンタの進化
2004年も師走を迎え、我が国においては年賀状作成という一大行事のシーズンを迎えている。パソコンと年賀状というのは相性が良いらしく、年賀状作成というのはパソコンの利用方法として一大ジャンルを形成しているようだ。年末のパソコン売り場を覗いて見ると、「筆何某」と称するソフトの新バージョンが新発売されているほどである。
年賀状は,基本的にハガキに宛先や絵や文面を印刷して成るものであり、当然その作成作業の最終章は印刷だ。そして送られてくる年賀状を眺める度に感じるのが、プリンタの進歩だ。
ここでは、パソコン用周辺機器の重鎮の一つであるプリンタについて考えてみたい。
約20年ほど前(つまり1980年代)、年賀状の裏面(宛名でない文面側)をパソコンやワープロで印刷したような年賀状などというのを見かけることはまずなかった。それもその筈、当時はまともに鑑賞に堪える印刷を行えるプリンタなどなかった。その当時の年賀状作りの主役はプリント・ゴッコであである。絵をカラー刷りできる装置として絶大なる威力を誇り、プリントゴッコによる年賀状作成は「国民行事」とまで言われた時代だ。
この時代のプリンタといえば、“チキチキ”と甲高い音をたてヘッドを熱くしながら,インクを染み込ませた布のリボンをヘッドで叩き付けて妙に薄い字を印刷するドットインパクト・プリンタか、薄いフィルム状のインクリボン上のインクをヘッドの熱で溶融しながら転写する熱転写プリンタが主流だった。後者はワープロ専用機にも多く搭載されていたものだ。レーザープリンタ(ページプリンタ)というのもあったが、庶民には遠い存在であった。
そして、この頃のプリンタの主要命題は「文字を印刷すること」であり、そもそも印刷とは言わずに印字と言った。プリンタに送出されるコードも基本的に文字列そのものであり,倍角文字などはエスケープシーケンスで制御したものだ。勿論、カラー印字できるものなどは稀であり、出来たとしても写真など印刷できるシロモノではなかったりした。もっとも、この当時はパソコンで写真などを取り扱うこと自体難しかったので、これで事足りた。
このようなプリンタ古典時代から、プリンタの技術開発における三大命題は基本的に「印字(印刷)品質」「スピード」「ランニングコスト」であり、これを五大命題にまで拡張すると「印刷の耐久性」「静粛性」が加わるだろうか。これらの命題は,現在もその流れが引き継がれている。これらは場合によっては互いに相反することもあり、時として何かに特化していびつなプリンタを登場させたりもした。
「印字品質」については、1980年代の後半には“48ドットプリンタ”(現代風には360DPI)のプリンタが登場し、だいぶ改善されている。特に、モノクロ文字列印字において熱転写プリンタは極めて品質が高い印字が可能であり、それはトナーの飛び散りのあるレーザープリンタや現代のインクジェットプリンタのモノクロモードよりも品質が高かったかもしれない。
筆者も長らくその 48ドット・熱転写プリンタを使用していた時期があったのだが、その泣き所はスピードとランニングコストだった。当時のプリンタは,そのスピードを表すのに、cps (Character Per Second)とか分/枚とかいう単位を用いていたことからも分かるように、非常に遅かった。少々長いレポートなど印刷しようものなら、印刷に1時間程度要することも珍しくはないことだったのだ。この問題は、熱転写プリンタに頼るところが大きかったワープロ専用機でも顕在化していたらしく、三行革命などという三行を一度に印字するプリンタを搭載したワープロも出現した。言うまでもないことだが、これはリボンを3倍無駄にするプリンタでもあったので、あっけなく廃れることになる。
パソコン用熱転写プリンタのインクリボンは(物にもよるが)一巻き買うとカセット入りで大体3千円,リボン単体で約2千円であり、しかもすぐになくなった。リボン式のプリンタでは印字する文字が例え罫線であったり句読点であったり空白であったりしても送られて無駄になったりした。プリンタという装置としては、そうした空白でリボンが無駄に送られないようにすることは不可能ではなかったとは思うが、それはきっと印字スピードとトレードオフだったのだろう。
1980年代〜1990年代初頭にかけてのプリンタはこんな有様であったので、年賀状の表(宛名の面)こそワープロもしくはパソコンで打たれたものは見かけたのだが、裏面に関しては依然としてプリントゴッコの時代が続いたわけだ。
それが1990年代の末頃になると俄然プリントゴッコによる年賀状は減ってゆく。この原因として、勿論パソコン自体の進歩も見逃せないところだが、プリンタの世界ではインクジェット方式全盛期が出現していたのである。
インクジェット方式自体は 1980年代末頃から民生用に存在しており、今もなおプリンタ業界の雄である E社がピエゾ方式で出していたのだが、モノクロ専用である上に高価(20万円くらいだったろうか)だった。1990年代初頭〜中頃にかけては、もう一方の雄であるC社がバブルジェット方式を庶民向け価格で繰り出してくる。当初は旧態然たるモノクロ専用大型プリンタだったが、A4ファイルサイズのプリンタや、手頃な価格のカラープリンタを売り出し、インクジェット方式は一気に主役に踊り出た。このころのインクジェットは印字品質もイマイチでくしゃみをすると判読不能になったが、それでも印字速度と経済性は魅力だったものだ。
この時代は、丁度32bit 試行フェーズから革命を待つ時期でもあり、多くのパソコン関連機器と共に旧式プリンタも同時に淘汰されていった。プリンタドライバの対応状況であったり、あるいは使用感が淘汰を推進したのである。実際、筆者もそれまで使用していた熱転写プリンタが Windowsにおいてリボンの無駄遣いと遅さに磨きがかかるのを目の当たりにして,この時期にインクジェットプリンタへの移行を果たしている。
パソコンの時代のフェーズの移り変わりは、プリンタという周辺機器にも少なからず影響を与えていたようだ。
さて、このようにしてインクジェットへと明け渡された小市民向けプリンタの主役の座であり、それは2004年現在にも引き継がれている。現在は写真画質に加えてインクの耐久性やスキャナとの一体化などで付加価値を高めようとしている時代に突入している(その過程ではインクヘッドの代わりにスキャンユニットを付ける過渡期製品も登場したわけだが)。やってくる年賀状も、表裏共にパソコンで印刷というのもかなりの割合に上る時代だ。
筆者はアナログ感覚多彩なプリントゴッコが好きだったのだが、近年では以前と比べてインクやランプの入手も容易でなくなっているようだ。こうした消耗品は入手しにくくなると、本体まで兵糧攻めでお蔵入りを果たすことになる。
これは、プリンタとて同じことだ。プリントゴッコ同様に,プリンタ市場もまた消耗品ビジネスの戦場となっている昨今だけに、インクの入手し易さはプリンタ選択のポイントとして重要だ。もちろんそれはインク売り場を見渡せば一目瞭然かもしれないのだが、あんまりな面積を占めているのも考えものだ。広大なインク売り場面積が示すのは,勿論旧機種までの対応度合いや製品バリエーションの多さなのかもしれないが、機種毎に悉くカートリッジを変えてきた歴史とメーカーの姿勢が刻まれたものでもある。
筆者としては、年の瀬のインク切れに近所の店を捜し歩いた挙句,大型パソコン店に辿り着く旅はあんまりしたくないところだ。そうしたシチュエーションは、自分が使用しているプリンタが最新ではなくなったときに出くわすことが多かったりする。勿論、最高級・ド級プリンタよりも、沢山売れる(た)プリンタのカートリッジの方が入手性は良いように思う。(7.Dec, 2004)
周辺機器 - “テレビ”とパソコン用のモニタ-CRT編
パソコンにとって必須の周辺機器として、ディスプレイ装置がある。様々な情報を視覚として表示させるモニタは、パソコンから人間への情報出力装置の主役を担い続けている。
パソコン用モニタのスペック上のキーポイントは、画面のサイズに加えて解像度、そして奥行きの小ささである。画面のサイズは、俗に対角線の長さで“○○インチ”と称せられるもので、一般に大きい方が偉いことになっている。また、良く知られているように,コンピュータが作り出す画面は「画素(ピクセル)」の集合体で構成されているので、縦と横で何画素表示できるかを以って解像度が表わされる。解像度が高い,すなわちより大きい数値の画面を表示させられる方が偉いことになっている。そして、画面が大きい方が良いし、同じ性能なら奥行きなど小さい方がいいに決まっている。このことは、薄型大画面テレビなどと同様である。
 パソコン用モニタの代表格は,ブラウン管CRT(Cathod Ray Tube)である。かつて 8bitの時代のモニタは、性能的にテレビと大差なかった。実際に MSXなどはそうであったように,パソコン用モニタはテレビでこと足りた。それは、当時のパソコンの表示能力はテレビとほぼ同じであったためだ。
パソコン用モニタの代表格は,ブラウン管CRT(Cathod Ray Tube)である。かつて 8bitの時代のモニタは、性能的にテレビと大差なかった。実際に MSXなどはそうであったように,パソコン用モニタはテレビでこと足りた。それは、当時のパソコンの表示能力はテレビとほぼ同じであったためだ。
16bit時代を迎えると,パソコンの表示能力の方がテレビよりずっと優るようになる。この頃のCRTは14〜15インチが主流であり、テレビモニタと非常に似た形状をしていたが,それは高解像度な専用モニタだったわけだ。
基本的に、モニタの能力はピクセルクロックで測り知ることが出来る。あまり馴染みのない言葉かもしれないが、ピクセルクロックというのは“各画素を更新する周波数”だ。モニタと言うのは、基本的に画面の左上から右へと1画素ずつ描画していく。この描画の周波数がピクセルクロックだ。
例えば、640×480のVGA画面は約30万画素であり、これを70Hzのリフレッシュレートで表示させると,30万×70(画素/秒)でおよそ 22MHz となる。実際には,画素以外にも帰線信号などが含まれるので、信号はこれより更に高い周波数(60Hzのリフレッシュレートで約25MHz)である。そしてこの周波数で R,G,B のそれぞれ8bit 程度(つまり計24bit)の情報をCRTへと伝送しなければならないわけで,デジタルに換算すればおよそ 500Mbpsに相当する。16bit 時代のコンピュータは、CPUのクロックすら 10〜20MHz程度であったので、如何にCRTが高速なデバイスであったかが分かる。当時のデバイスではとてもデジタルで伝送することなど不可能であった(大昔にデジタルI/Fのモニタというのもあったが、性能的には厳しかった)。16bit時代の後半には「ハイレゾ」という 1120×750画素というのもあった(右上図)が、上記のようなピクセルクロックで考えて見ると、それ用のディスプレイが大変高価だった理由が良く分かる。
そしてSVGA, XGA, あるいはそれ以上の解像度を高いリフレッシュレートで表示できるモニタが多数登場したのは 32bit時代の本格到来の頃からのことだ。価格も著しく低下し、32bit時代の革命〜躍進フェーズにかけて全盛期を迎える。ピクセルクロックは100MHzを超え、ケーブルの良し悪しも画質に影響を与えるレベルとなり,低級機から高級機まで幅広くラインナップされた。画面のサイズも15インチから17インチ,あるいは19インチやそれ以上といったものが相応な価格で売られていた。
しかしながら、2004年現在の状況を見渡して見ると、CRTは衰退の一途を辿っている。まともな品質のモニタを購入するのも、あるいは難しいかもしれない。かつてCRTディスプレイを製造・販売していたメーカーの多くも既に撤退しているようだ。
CRTディスプレイは、確かに幅広い解像度(の信号)に柔軟に対応でき、しかもマスクというアナログ的なローパスフィルタによって,どんな解像度の画面も滑らかに表示し、しかも高速な応答性を有しているのでパソコンにはぴったりだった。
筆者は個人的にはCRTの画面が好みで,昨年先代のCRTが故障した際に廃盤になりかけていたCRTを調達した。だが,価格こそ10年前と比較すると格段に下がっていたが、品質も低下気味だったように思う(それなりのものを購入したつもりだったのだが)。もはやパソコン用モニタとしてのCRTはその役目を終えているのかもしれない。
このようなCRT凋落の原因は、やはり何と言っても奥行きの長さだろう。横幅30cm強程度のモニタの奥行きが 50cmにも達する(17インチモニタの場合)というのは、机の上に置くことを考えるとかなり厳しい。
最近はパソコンをテレビと融合させることが流行のようだが、リビングに置くことを考えるとやはり大画面が欲しくなる。そうなるとCRT奥行きは,一般的な家庭には容認し難いものになってしまうだろう。筆者はかつて(15年くらい前か?)、NHKの展示場に鎮座していたアナログハイビジョン用テレビの試作機を見たことがあったが、30インチ程度のサイズで奥行きは1メートルを超えていた。CRTはその原理からして、薄型化と高精細化を両立させていくのが難しいのだろう。
こうした問題を背景として、液晶を始めとする薄型モニタやテレビの勢いが増しているのは、当然と思える。そして、旧来のピクセルクロック 14.31818MHz の地上波テレビに代わって,HD-TV の波が押し寄せてきている現在、テレビ受像機もパソコン用モニタも岐路に立たされているようだ。[次回,薄型編に続く…] (23.Dec, 2004)
周辺機器 - “テレビ”とパソコン用のモニタ-薄型編
「モニタ」の分野で21世紀になって俄かに活気づいているのは薄型モニタとか薄型テレビだ。その方式は,液晶やプラズマといった既に市場を賑わせているものから、小型系の有機EL(Electro-Luminescense)やプロジェクタ系のDLP(Digital Light Processing)や,未だ見ぬSED (Surface-conduction Electron-emitter Display)など百家争鳴の状態である。
また、モニタのハードの方式だけでなく,表示させる信号に視点を移すと、現在日本の家庭用地上波アナログテレビの信号である NTSC の寿命は既に宣告されている状態にあり(2011年7月にアナログ放送終了の予定)、新しいテレビへと買い替える機運が高まっている。その中にあって、パソコンによる高い解像度の画面をテレビモニタに映し出すことも珍しくはなくなり、その境目は徐々に薄れつつあるように思う。
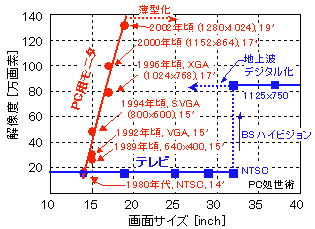 だが、そのテレビとパソコン用モニタの進化の過程をそれぞれ回想して見ると、随分違った経過があったように思う。右図はその進化の過程をグラフで表したものだ。横軸に画面サイズ、縦軸に解像度をとり、各年代の代表的なテレビやパソコン用モニタのスペックをプロットしてある。グラフでは時間軸の情報が欠落しているが、PC用モニタについては参考情報としてそれが主流であったと思われる年代を付記してある。
だが、そのテレビとパソコン用モニタの進化の過程をそれぞれ回想して見ると、随分違った経過があったように思う。右図はその進化の過程をグラフで表したものだ。横軸に画面サイズ、縦軸に解像度をとり、各年代の代表的なテレビやパソコン用モニタのスペックをプロットしてある。グラフでは時間軸の情報が欠落しているが、PC用モニタについては参考情報としてそれが主流であったと思われる年代を付記してある。
まず青色で示したテレビだが、図を見てお分かりの通り長らく解像度はさっぱり向上しないまま画面のサイズだけが大きくなったりワイド化したりした。その過程ではアナログハイビジョンの登場などもあったが一般には全く馴染まないものであり、実質的にはBSハイビジョン放送が開始された2000年頃から32インチ以上の大画面テレビでようやく高解像度化した。薄型テレビの台頭も,この頃からである。
赤色で示したパソコンの方はというとテレビとは対照的で、サイズはあまり大きくならないまま解像度が著しく向上してきた。VGA(640×480)の時代には14〜15インチ程度であったのに対し、SXGA(1280×1024)が標準的となった現在も、モニタのサイズは17〜19インチ程度に留まっているのである。
このことは、パソコンとテレビとでは使用するシチュエーションに違いがあるためだとも考えられる。テレビはリビングなどに置いて“遠くから眺める”ものであるのに対して、パソコン用モニタは“近くで凝視する”類のものであるからかもしれない。
あるいは、この傾向は現在衰退しつつあるCRTの奥行き問題とも関係していたかも知れない。パソコン用モニタは高解像度が要求される上に、ユーザーと比較的近距離に置かれることが多い。そしてCRTでは高解像度になるほど奥行きが大きくなり、画面はユーザーに近づいてしまうというわけだ。視野角で考えれば、接近したディスプレイは大きく見えるものだ。このために、大画面モニタはさほど必要とされてこなかったのかもしれない。
テレビやモニタの薄型化を迎えつつある現在はどうだろうか。テレビの方はアナログ放送打ち切りの圧力により,より小型のものが高解像度化しつつある。その一方で、パソコン用モニタの方は薄型化に伴って設置位置が後退する影響なのか、比較的大きいサイズのディスプレイの台頭が目立つようになってきている。この辺りが、テレビとパソコンの融合という図式となって体現されているのだろう。
さて、我々一消費者にとって興味の対象は、どんな薄型モニタなりテレビなりを入手したら良いのかという問題だろう。特に大画面薄型モニタは一般には高価なのであり、できればハズレを掴みたくないところだ。これについて、筆者の乏しい体験に基づく漠然とした感覚なのだが、最後の決め手は機械的寿命と消費電力に懸かっているように思う。
 筆者と薄型系モニタとの最初の出会いは左の絵にあるラップトップPC(PC-9801LX5C)用のSTN液晶だった。当時これより以前に,ラップトップPC用モニタとしてはモノクロ液晶や妙にオレンジ色のプラズマモニタというのがあったのだが、カラー液晶はこれが初であったと思う。当時定価で約75万円もしたこのPCだったが、2年と経たないうちに温度が上がると縦縞だらけになる悲しい画面を見せていたのが印象的だった。歴史の浅いこの類のモニタの機械的寿命というのは、それほど長くはないこともある。勿論、このマシンから10数年が経過して歴史と市場テストを積み重ねた現在では、液晶はTFTになり,充分な耐久性を有している。
筆者と薄型系モニタとの最初の出会いは左の絵にあるラップトップPC(PC-9801LX5C)用のSTN液晶だった。当時これより以前に,ラップトップPC用モニタとしてはモノクロ液晶や妙にオレンジ色のプラズマモニタというのがあったのだが、カラー液晶はこれが初であったと思う。当時定価で約75万円もしたこのPCだったが、2年と経たないうちに温度が上がると縦縞だらけになる悲しい画面を見せていたのが印象的だった。歴史の浅いこの類のモニタの機械的寿命というのは、それほど長くはないこともある。勿論、このマシンから10数年が経過して歴史と市場テストを積み重ねた現在では、液晶はTFTになり,充分な耐久性を有している。
モニタの寿命体験は、つい最近,50型プラズマテレビでもあった。これは2001年製だったのだが、通算7000時間の使用で画面上部が緑色になって故障した。モニタ内に使用時間がメモリされていることから分かるように、メーカーも寿命に対してナーバスになっているようだ。この時は新品に交換していただけたのだが、それからやはり1万時間未満で同じ症状は起こった。2回目の時には新品交換はしてもらえず、修理と相成ったのだが、帰ってきたものには冷却ファンが増設されていた。やはり数百Wに達する消費電力(による発熱)と寿命との間には深い関係があるようだ。プラズマモニタをお持ちの方は、背面の冷却を励行されたい。
未だ歴史の浅い薄型モニタは、宣伝文句に“寿命”という言葉が入ることから分かるように、メーカー自身が気にせざるを得ないレベルにあることを認識する必要があるのかもしれない。(もっとも、パソコン用モニタなら2004年現在は液晶以外選択肢がないのが実情だ。「もうすぐ出る」という新方式の見極めには未だ数年を要するだろう。)
なお、蛇足かもしれないが、巷で“液晶TV”と称して売られている小型液晶の中には解像度がNTSCに退化しているものも結構高値で売られていたりするようだ。より高解像度なTVチューナー内蔵のパソコン用モニタの方が安いという不思議なことも散見される。きっと、低解像度でテレビにすることで何らかのメリットがあるのだと信じたいが,TV以外に使い途がない上にもうじき論理的寿命を迎える高価な装置に,筆者は手をだす気にならない。(26. Dec, 2004)
デジタル・スチル・カメラ - 画素数の変遷を振り返る
デジカメ、ことデジタルカメラが市民権を得て久しい。筆者がおよそ10年ほど前にデジタル・スチル・カメラを購入した当時,世間では未だその認知度は低く,シャッターを他人に頼むと、「これはどうやって撮影するのですか?」と聞かれたり,液晶に撮影されたばかりの写真が写ることに随分と感心されたり、あるいは少し知っている人からは「これがデジカメってやつですか」などと聞かれたものだった(ハンディカムは既に市民権を得ていた時代なのだが)。このように、デジカメは結構なハイテク商品であったわけだ。
筆者が購入した黎明期のそれは,それなりに高価(7万円超だった)なシロモノであった。それだけに、デジカメを様々な場所に持って行き、“その場で仕上がりを確認しつつ,失敗したら消せる”という銀塩カメラには無い機動性を発揮してもらったものだ。
だが今になってみると,その機動性は可としても、その価格を考えてしまうとデジカメはコストパフォーマンスが大変悪いシロモノだったように思う。2005年現在のデジカメと比較したら勿論その差は大変なものだが、当時の銀塩コンパクトカメラと比較しても,「電池が持たない,撮れる枚数が少ない,動作が遅い,大きく重い,色バランス・露出時間は良くはずす…」などの欠点を持っていた。
当時はフラッシュメモリも未だ高価でデジカメ内蔵の2MBほどのメモリではどうにもならず、筆者も僅か12MBほどのメモリに2万円以上のお金をはたいて購入したりしたものだ。また、当時は1000mAh 程の容量の単三充電式電池なんかを使って、それを何セットも持ち歩いたり、液晶モニタは原則使わないなどの使用上の工夫が要ったものである。
このように、色々と厳しい部分が多かった当時のデジカメだが、中でも厳しかったのが画質の問題である。7万円超のそのデジカメの画素数は、僅かに 30万画素ほどであり、VGAサイズの画像を取るのが関の山というシロモノだった。
理解していない人も結構多いのだが、基本的にカラー・デジカメの解像度は額面解像度の 1/3である。3板式でない限り,“カラー素子”とは言っても,規則正しく並んだ画素は上下左右にR・G・Bとフィルタが交互に並んでおり、つまりそれぞれの色で全画素の1/3ずつを受け持っているという勘定だ。通常、デジカメは額面画素数の解像度の画像を出力する様にはなっているが、それは三分の一ずつの画像から画像処理によって補完・合成された画像を眺めているだけに過ぎない。保存された画像を1:1(フル)のサイズで見ると妙にボヤけていて、サイズを縮小して行くにつれてシャープに見えるというのは誰しも体験するところだろう。
したがって、当時のデジカメはVGA(640x480=約30万画素)とは言っても、実のところは10万画素相当の解像度しか持っておらず、大体 320x240(つまり1/4)程度にまで縮小して初めてシャープな像が得られるというシロモノだったのだ。画質が厳しいと感じたのもムリはない。いくら10年前とはいえ、画面はVGAよりは大きく 800x600や 1024x768 が主流であったわけで、画面にデジカメ画像を表示させることだけを考えても厳しい画質だった。ホームページ用のミニ写真専用と揶揄されたりもした。
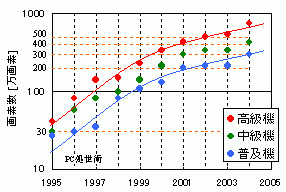 さて、このようにデジカメは画質面では大変厳しいところから始まったことから、その進化の中心は画素数であった。右図はその変遷を示すグラフである。当初30万画素程度で始まったデジカメも、100万画素を超えるのに僅か2年程度しか要しない進化のスピードであった。
さて、このようにデジカメは画質面では大変厳しいところから始まったことから、その進化の中心は画素数であった。右図はその変遷を示すグラフである。当初30万画素程度で始まったデジカメも、100万画素を超えるのに僅か2年程度しか要しない進化のスピードであった。
そしてそのメガピクセルカメラも、あっという間にローエンドになり下がり、ハイエンドの画素数は増加の一途を辿って行ったわけだ。グラフを横方向に読むと,1996年頃はハイエンド機とローエンド機の差はおよそ1年強であったから、“ハイエンド”と称して登場した画素数のデジカメも,僅か1年ちょっとでローエンドに成り下がっていたのである。
そこから現代に目を向けてみると、画素数の進化は2001年頃から鈍化し、ローエンドとハイエンドの差は4年程度にまで広がっている。つまり、現代のハイエンド機は,少なくとも4年程度はローエンド機に画素数で抜かれることはないということだ。ミドルレンジ機に追いつかれるのにも、2年程度は要する公算だ。
要するに2005年現在のデジカメは,画素数に関して言えばもはやサチュレートしつつあり、高級機,低級機はそれぞれに異なる味付けがなされ,自ずと役割も異なると認識すべきものなのだろう。
ところで、サチュレートが始まった2001年頃の画素数に注目してみよう。大体、中級機で300万画素といったところだ。つまり、1/3すると 100万画素程度の画素数であり、画面に画像として表示させると丁度いい按配の画素数だとも言える(XGAで80万画素、SXGAで130万画素)。したがって、「画面で眺めて満足するか、印刷しても十分な解像度が得られるか」が高級機との差だとも考えられる。その辺りを一つの目安にしてみるのも良いかもしれない。
もっとも、デジカメの性能は画素数ばかりではない。近頃では、携帯電話にすらメガピクセル超級のカメラが搭載されることが当たり前になっている。しかしながら、その使い勝手や画質に関しては,必ずしも画素数の数字が示すほどではない場合もかなり多い。…次回はその辺りにもスポットライトを当ててみたいと思う。(7. Jul, 2005)
デジタルカメラ - 画質を決めるもの-その1
前回書いた通り、デジカメの“画素数”に関しては長足の進歩を遂げ、2005年現在に至っては写真機として実用に十分なところまでやってきている。それどころか、今日びの携帯電話に内蔵されているデジカメすら、メガピクセル超は当たり前で、200万,300万画素に達しているのだ。もはやエクストラ・コストを支払わなくたって、まともなデジタル写真を撮ることができる時代に突入しているのである。
そんな時代にあっても、なお“デジカメ”はデジタル機器の一大勢力として電器量販店の店頭に並んでおり、それなりに人気を博しているようだ。やっぱり“ケータイの付属品”ではないデジカメにはそれなりに期待するところがある、と言うわけだろう。
もちろん、サイズや機動性(操作性),デザインなどもデジカメ選択の重要な要素であることに間違いない。今日びのデジカメを選ぶに当たっては、それだけを考えて購入したとしても、そうそう大ハズレということにはならないだろう。だがその一方で、やっぱり気になってしまうのが“写り”の問題だ。やはり、ケータイのオマケではないプラスアルファとして、どうせなら“画質”のいいものが欲しいというのが人情というものだ。
画質の問題は、最終的には写してみないと分からないのだが,ここでは、デジカメが本質的に持っている性質を考察しながら、何に留意しながらデジカメを選んだら良いか,について考えて見たい。
デジカメの画質を考えるにあたって、まず「画質とは何なのか」について簡単に考えてみたい。筆者の素人的分類によると、画質は大きく分けて,「精細さ」と「明るさ」に大別できるように思う。
画質における「精細さ」の追求は、撮るべき絵をいかにシャープに取れるかということである。記録素子の細かさはもちろん、ピントやブレといった要素によって,写真の精細さは決まると思われる。
また、画質における「明るさ」の追求は、単に明るい/暗いということだけではなくて、被写体が持っているの明るさに関する情報を記録する段階で、いかに“人間の感覚に近づけるか”ということだ。
人間の視覚は,輝度に対してもまた対数的であるので、視覚が捉える輝度情報というのは極めてレンジが広い。“撮影”という作業は、このレンジが広い情報を本来それよりも遥かに狭い情報しか発信できない紙や画面に置き変えるというわけだ(例えば、太陽の写真を撮ったとしても、紙は太陽のように輝きはしないし、モニタだって同様である)。
このように、明るさに関する情報は「写真を撮る」という作業の中で最も落とされてしまう情報だとも言える。(「明るさ」に関する情報は、明るさの絶対値はもちろん,明るさの諧調の細かさと広さ,そして色のバランスといった要素も含んでいる)。
このように考えてみると、画質を決める多くの要素の中で、“画素数”というスペックはその一部分でしかないということが分かる。直接関係しそうな“精細さ”に対してだってそれを決める一要素でしかなく、ピントが甘くても,ブレても精細な写真は撮れない。
次に、画質を決める重要な要素である“明るさ”について考えると、これに関する情報が欠落した場合には,例えば黒・白ツブレが生じるような諧調の乏しさや、絶対的な暗さからくる低S/N比(ノイズ)、などが起こる。つまり、“明るさ”には画質に関係しそうな要素が多いことが想像できる。
更に、精細さに関連する“ピントやブレ”にしても、基本的には“明るさ”と深く関係している。基本的に明るさの調整を電子シャッターに頼っているデジカメでは,暗ければ露光時間が長くなりがちでブレ易いし、合焦判定に対しても十分な情報を与えにくい(ピントを外し易い)。
かつてブレークした「レンズ付きフィルム」の背景に,高感度フィルムの普及があったことを忘れてはいけない。デジカメの場合、もちろん合焦装置や補正機構に依るところもあるだろうが、輝度情報の欠落は撮れる写真の精細さにも影響大であることに間違いない。
このように、画質に対して“明るさ”というのは“画素数”と並んで(またはそれ以上に)重要なファクターなのである。然るに、デジカメのカタログなどを眺めてみると、なんとしたことか「明るさ」に関する仕様は分かりにくい。画素数が画質を決める数字として盛んに宣伝されているのとは好対称だ。
単純に言って「明るさ」は素子のサイズとレンズのF値と素子の感度で大体決まってしまうと思うのだが、デジカメのパンフを見ても,仕様表を見ても,なかなかそのデジカメの“明るさ”のポテンシャルを見出しにくい状況にある。
そして店頭に並んでいるデジカメを眺めてみると、画素数は多くて画質に配慮していそうな高価な機種が必ずしもそのポテンシャルが高いとは限らないので、消費者にとってはますます選定が難しい。次回は、このあたりの詳細にもう少し迫ってみようと思う。(16. Jul,2005)
デジタルカメラ - 画質を決めるもの-その2
さて前回,“画質を決めるファクター”について、それは「画素数のほかに“明るさ”がある」と書いた。そして“明るさ”に対するキー・ファクターである“レンズのF値”と“素子のサイズ”と“素子の感度”で構成される「デジカメの明るさ」は、おおよそ次のような式で表わせると考えられる。
デジカメの明るさ= 素子の感度(係数) × 1画素の面積 /(F値)^2
素子の感度というのは、デジカメの内部で用いられている光電変換素子(主にCCD)が有している感度であり、光子からの変換効率とS/N比,および素子の開口率で大体決まる。(インターライン型の)CCD素子というのは,電子シャッタ時に瞬時に全ての画像(電荷)を移動完了する必要があるために,感光する画素の隣には不感のCCD画素が設けられており、素子のかなりの部分は実は感光しない。
これらの問題を解決するために、素子メーカー各社は画素数争いの他にレンズアレイによる感光素子への集光やノイズの低減, ダイナミックレンジ拡大などにシノギを削ってきたわけだ。このため,年々素子の「感度」は向上してきた。もっとも、素子の感度をデジカメのカタログから読み取ることはできず、また素子のメーカーによって多少の差はあるのだが、世に出ているデジカメを見る限り,大体製造年代が近いなら大差はないようだ。
[ 余談だが、一般に“感度”として銀塩時代からISO感度が用いられ,デジカメに対しても使用されてきた(参考)が、数字の上がり方(100, 200, 400, …)を見れば分かる通り、等比数列的である。これは人間の視覚の特性に鑑みたものと思われるが,逆にいうと感度には大差がないと人間の目には分からないとも考えられる。]
そして次にレンズのF値だが、これは受光径と拡大率の比と考えてよい。この場合の拡大率は長さスケールであるので、画素が受ける光の量はF値の2乗で効くのである(絞りの区切りは通常 1.4, 2.0, 2.8, 4, 5.6... となっているが、これは1段絞ると受光量が半分になるという区切り。ルート2のn乗で増えていくのはそのためだ。)。
もっとも、レンズのF値というのは必要な画角と許容される各収差の範囲が決まってしまうと、各社デジカメも大体一定のところに収まるようだ。
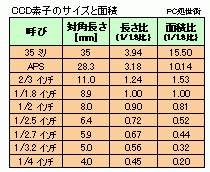 さて、各社・各クラスのデジカメで差がつき易いのが、1画素の面積である。デジカメの中での序列を決めている最大の要素は,1画素の面積と画素数の積である素子のサイズではないかと思う。このことは,デジカメのカタログデータからも読み取ることができ、高級機ほど大きい素子が使われる傾向がある。
さて、各社・各クラスのデジカメで差がつき易いのが、1画素の面積である。デジカメの中での序列を決めている最大の要素は,1画素の面積と画素数の積である素子のサイズではないかと思う。このことは,デジカメのカタログデータからも読み取ることができ、高級機ほど大きい素子が使われる傾向がある。
カタログにはご存知の通り、“1/○インチ素子”などと書いてある。この値は分数で表示されている上に,この世界の1インチは何故かおよそ16ミリ(25.4mmではない)なので素子の実際のサイズというのは直感的に分かりにくいものになっている。右の表はそれをまとめて,面積比でまとめたものである。例えば、デジカメで少し高級(なコンパクト)機に用いられる 1/1.8型素子と、一般的なコンパクトデジカメに用いられる 1/2.5型とでは、素子の面積は倍も違うのである。
更に踏み込んで、画素数と1画素あたりの面積の関係を概算してみたのが左図だ。デジカメ黎明期の“26平方ミクロン”から考えると、随分と微細化してきた様子が良く分かる(と同時に、それに耐えうるだけ開口率・SN比が向上してきた、ということ)。
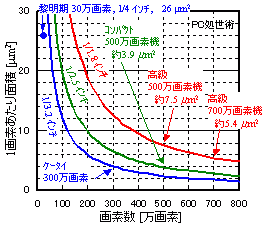 さて2005年現在,いわゆるデジカメ(一眼レフ除く,コンパクトジャンル)の「フラッグシップ機」に用いられているのは 1/1.8インチ程度の 600〜800万画素といったところだろうか。相当に微細化されたCCD素子ではあるが、それでも 700万画素で各画素は 5.4平方ミクロン程度の面積を持っていることが分かる。
さて2005年現在,いわゆるデジカメ(一眼レフ除く,コンパクトジャンル)の「フラッグシップ機」に用いられているのは 1/1.8インチ程度の 600〜800万画素といったところだろうか。相当に微細化されたCCD素子ではあるが、それでも 700万画素で各画素は 5.4平方ミクロン程度の面積を持っていることが分かる。
これに対して、廉価コンパクト系のデジカメに用いられている 1/2.5型のものでは500万画素で 4平方ミクロン弱の面積しかないことになり、高級系700万画素に対しておよそ半絞り分くらい明るさが不足する勘定である。また“500万画素がフラッグシップだった頃”と比較してみると、1画素の面積は約半分になっており、1絞り分くらいの差があることになる。デジカメの高画素化も進んで、「廉価機がかつての高級機に追いついた」と勝手に感じていたが、この観点からすると必ずしもその通りではなかったようだ。
更にケータイに用いられている 1/3.2インチを見てみよう。近頃は 300万画素などというものも用いられるようだが、その画素のサイズはやはり廉価デジカメ500万画素級と同程度なのであり、かつての300万画素デジカメと同じというわけにはいかない(。
このようにしてみると、デジカメのランクの差は単純に画素数の違いなのではなく、素子のサイズの差であるように思われる。そしてその差は“明るさ”に起因するが故に、単純な微細化プロセスの進展だけでは追い付けない場合もあるということだ。
以上を踏まえて「デジカメの選択」を考えると、自ずとどのような点をチェックすべきかが見えてきそうだ。どうも世間を見渡してみると、立派なレンズ(ズーム倍率命)やゴツイ筐体と高価なプライスタグを下げるデジカメであっても筆者の素人的分類によると高級機に属さず、良い写真を撮るのに技能が要りそうなデジカメもあるようだ。
あるいは低額機であっても、画素数と画素サイズのバランスが良く,多様なシーンで失敗しにくそうなデジカメというのもありそうだ。
因みに、このような“明るさ”問題に対しては、明暗コントラストのある画像の暗い部分を使って,大雑把に「暗いところを写した時の画質がどうなるか」を見ることができる。これは、デジカメが画面の大多数を占める明るい部分に露光を合わせると、必然的に暗い部分は露光アンダーになるためだ。
例えばメーカー提供のサンプル画像にガンマ補正γ=3をかけた画像を用いて比較してみると良いかもしれない。風景画など、“黒ツブレ”が発生している(ように見える)画像の暗部のゲインが大きくとられてノイジーになっている様子が分かるはずだ。各社素子サイズの異なるデジカメを比較してみると、この辺りに差が見えるかもしれない。(メーカー提供サンプルはそのままでは参考にならないので)
あるいは店頭に並んだデジカメで黒い部分(例えば黒い靴とか)を撮ってみるというのも妙案だ。デジカメの液晶パネルはγ補正が効いていて暗い部分も明るく見えるし,拡大してみるとアラも良く見える。
もっとも、ここまで書いておいて何なのだが、デジカメの購入基準は画質ばかりでもない。重量や携帯性、デザイン、シャッターのタイムラグや起動時間などの操作性、など,多様な要件がある。大蔵大臣の意向が画質と正反対を向いていることもあるだろう。上記は、「それでもやはりちょっとでも写りが良い方が…」と考える方に向けたものであることをお断りしておく。(19. Jul,2005)
* 何故デジカメ記事を突然連続して書き始めたのかといえば、それは筆者のデジカメが更新時期を迎えたため…である。
PC処世術トップページへ

当サイトにある記事の著作権は M.Abe に属します。
なお、当サイトの記事の転載はご遠慮ください。
 パソコン用モニタの代表格は,ブラウン管CRT(Cathod Ray Tube)である。かつて 8bitの時代のモニタは、性能的にテレビと大差なかった。実際に MSXなどはそうであったように,パソコン用モニタはテレビでこと足りた。それは、当時のパソコンの表示能力はテレビとほぼ同じであったためだ。
パソコン用モニタの代表格は,ブラウン管CRT(Cathod Ray Tube)である。かつて 8bitの時代のモニタは、性能的にテレビと大差なかった。実際に MSXなどはそうであったように,パソコン用モニタはテレビでこと足りた。それは、当時のパソコンの表示能力はテレビとほぼ同じであったためだ。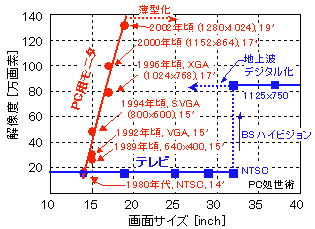 だが、そのテレビとパソコン用モニタの進化の過程をそれぞれ回想して見ると、随分違った経過があったように思う。右図はその進化の過程をグラフで表したものだ。横軸に画面サイズ、縦軸に解像度をとり、各年代の代表的なテレビやパソコン用モニタのスペックをプロットしてある。グラフでは時間軸の情報が欠落しているが、PC用モニタについては参考情報としてそれが主流であったと思われる年代を付記してある。
だが、そのテレビとパソコン用モニタの進化の過程をそれぞれ回想して見ると、随分違った経過があったように思う。右図はその進化の過程をグラフで表したものだ。横軸に画面サイズ、縦軸に解像度をとり、各年代の代表的なテレビやパソコン用モニタのスペックをプロットしてある。グラフでは時間軸の情報が欠落しているが、PC用モニタについては参考情報としてそれが主流であったと思われる年代を付記してある。 筆者と薄型系モニタとの最初の出会いは左の絵にあるラップトップPC(PC-9801LX5C)用のSTN液晶だった。当時これより以前に,ラップトップPC用モニタとしてはモノクロ液晶や妙にオレンジ色のプラズマモニタというのがあったのだが、カラー液晶はこれが初であったと思う。当時定価で約75万円もしたこのPCだったが、2年と経たないうちに温度が上がると縦縞だらけになる悲しい画面を見せていたのが印象的だった。歴史の浅いこの類のモニタの機械的寿命というのは、それほど長くはないこともある。勿論、このマシンから10数年が経過して歴史と市場テストを積み重ねた現在では、液晶はTFTになり,充分な耐久性を有している。
筆者と薄型系モニタとの最初の出会いは左の絵にあるラップトップPC(PC-9801LX5C)用のSTN液晶だった。当時これより以前に,ラップトップPC用モニタとしてはモノクロ液晶や妙にオレンジ色のプラズマモニタというのがあったのだが、カラー液晶はこれが初であったと思う。当時定価で約75万円もしたこのPCだったが、2年と経たないうちに温度が上がると縦縞だらけになる悲しい画面を見せていたのが印象的だった。歴史の浅いこの類のモニタの機械的寿命というのは、それほど長くはないこともある。勿論、このマシンから10数年が経過して歴史と市場テストを積み重ねた現在では、液晶はTFTになり,充分な耐久性を有している。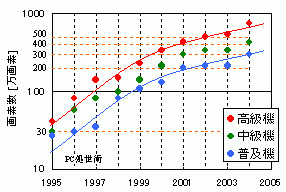 さて、このようにデジカメは画質面では大変厳しいところから始まったことから、その進化の中心は画素数であった。右図はその変遷を示すグラフである。当初30万画素程度で始まったデジカメも、100万画素を超えるのに僅か2年程度しか要しない進化のスピードであった。
さて、このようにデジカメは画質面では大変厳しいところから始まったことから、その進化の中心は画素数であった。右図はその変遷を示すグラフである。当初30万画素程度で始まったデジカメも、100万画素を超えるのに僅か2年程度しか要しない進化のスピードであった。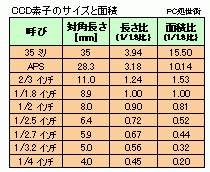 さて、各社・各クラスのデジカメで差がつき易いのが、1画素の面積である。デジカメの中での序列を決めている最大の要素は,1画素の面積と画素数の積である素子のサイズではないかと思う。このことは,デジカメのカタログデータからも読み取ることができ、高級機ほど大きい素子が使われる傾向がある。
さて、各社・各クラスのデジカメで差がつき易いのが、1画素の面積である。デジカメの中での序列を決めている最大の要素は,1画素の面積と画素数の積である素子のサイズではないかと思う。このことは,デジカメのカタログデータからも読み取ることができ、高級機ほど大きい素子が使われる傾向がある。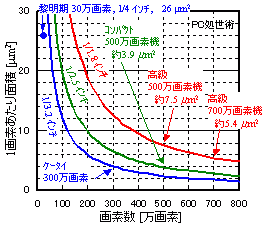 さて2005年現在,いわゆるデジカメ(一眼レフ除く,コンパクトジャンル)の「フラッグシップ機」に用いられているのは 1/1.8インチ程度の 600〜800万画素といったところだろうか。相当に微細化されたCCD素子ではあるが、それでも 700万画素で各画素は 5.4平方ミクロン程度の面積を持っていることが分かる。
さて2005年現在,いわゆるデジカメ(一眼レフ除く,コンパクトジャンル)の「フラッグシップ機」に用いられているのは 1/1.8インチ程度の 600〜800万画素といったところだろうか。相当に微細化されたCCD素子ではあるが、それでも 700万画素で各画素は 5.4平方ミクロン程度の面積を持っていることが分かる。