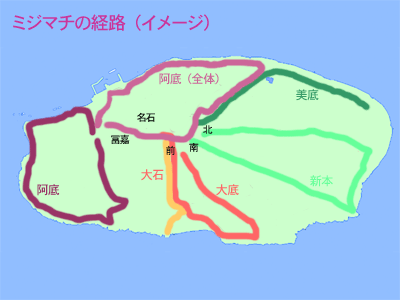|
|
|
波照間島の神行事・中篇ー作物願い、雨乞いー
|
中篇では、前篇での機能別分類に従って、それぞれの行事の概要のうち、作物願いと雨乞いをみていくことにする。なお、記述の内容はアウエハント(1985)の1960年代半ばの記録をベースに、宮良(1972)の70年代初頭の調査、畠山(1982)の80年代初頭の調査、仲底(1998)、中鉢(2002)の90年代半ばの調査結果、仲本(2004)の20世紀前半の覚え書きなどを反映させてまとめている。 【農暦の正月】 シン(シチ、シィシィン) 「節祭」の意。旧暦9月頃の戊戌または己亥の日からから4日間行われるシンから、神行事=農耕儀礼のサイクルが始まる。期間中となる「己亥(つちのとい)」は十干十二支の60日のサイクルの最後、その翌日の「庚子(かのえね)」はサイクルの最初となっており、理念上、大晦日と元旦に相当していたと思われる(中鉢2002)。つまり、シンは農暦の正月であるといえる。 1日目の深夜、島の最東端のK家(北部落)当主が東から西に順々に5つのウツィヌワー(集落の御嶽)と各部落の主要なトゥニムトゥ(宗家)を訪れる「島トゥーシ」を行い、島を「閉じる」。K家はかつてシムスケーの周囲に存在した島最東端の集落シムス村のトゥニムトゥであった。なお、神行事サイクルの終盤、プーリンの前夜に再び「島トゥーシ」が行われ、島は「開かれる」。 この期間中は、人々は農作業を休み、家屋を掃除し、身辺を清めた。3日目は別名「ユーニゲー」とも呼ばれ、冨嘉、前+名石、南+北の3組に分かれ船漕ぎの儀式が行われる。これは、海の彼方よりユー(祝福)を呼び寄せる意味を持つ。現在は港内で簡略化して行われているようである。琉球王府支配時代は、これ以降すべての労力を農耕に集中し禁欲的にならなければいけなかったという。 【作物願い】 ツクリニゲー 「作り願い」の意。旧暦10月〜12月にかけて、アラタービ、ナータービ、ブータービと、計3回行われる。ブータビはアラタービの60日後となる。「タービ」は「崇べ(たかべ)」の意であり、沖縄の他の島には「○月タカビ」といった名称の神事がある。 粟の種蒔き(アラタビ)、発芽(ナータービ)、生長・遅まき粟の種蒔き(ブータービ)と、粟の成長過程に沿っているが、一方稲のサイクルも複合している。そのため、稲作の中心地であった冨嘉のナータビは他の4集落に比べ時期が遅くなっている。また、現在は祈祷の文言にサトウキビの成育についても触れられているという。 各ウツィヌワーの司とパナヌファは、トゥニムトゥ家での祈願の後ピテヌワーを参拝し、神をウツィヌワーに招聘する。ウツィヌワーでは供物を捧げ、五穀豊穣の祈願を行う。各家庭でもブナリにより祈願が行われていた。 なお、アラタービではその年新たにパナヌファになった者の就任式もあわせて行われる。 ブザシマシ 旧暦4月頃行われる早蒔きの粟の初穂祭。「大崎祭」の意と推定され、「大崎」は高那崎を指している可能性が指摘されている。南集落のトゥニムトゥM家、前集落のトゥニムトゥU家のみが行う神事であるが、島全体の神行事日程に組み込まれていることから重要な神事であることがわかる。トゥニムトゥの主人(=男)が儀礼用の畑から粟の初穂を収穫し、粥をつくる(現在は米の握り飯)。これをウツィヌワーの司(=女)がニンニクと共にピテヌワーに持っていき、神前に捧げた後食す。 ほか南集落のMi家にも無名称だが同様の初穂儀礼が伝えられているという。Mi家主人が高那崎で香、神酒、粥を海に捧げ、東の創世神話に関わる場所の神々へ呼びかけを行う。東の粟の起源神話(高那崎で蟹が持ってきた粟穂が東の粟作の始まりとなった)の関係が推測されている。 なお、ブザシマシとスクマンマシの間は、粟を島の東半分から西半分に持ち込むことが禁止されており、一方スクマンマシからプーリンの間は米を西半分から東半分に持ち込むことが禁止されていた。ここに島の東西二分とそれに応じた粟/稲の二分がみてとれる。 スクマンマシ(シィクマン) ブザシマシの30日後に行われる、島全体の粟の初穂祭であり「小豊年祭」とも呼ばれる。各ウツィヌワーでは初穂を神に捧げ、この後の豊かな収穫を得られるように願う。この時期まだ稲は熟していない。この後プーリンまでの期間に、各家庭で同様なスクマンマシの神事が行われていた。なお、麦はこれ以前の旧3月初めに、各家庭にて初穂の奉納が行われていた(特に儀礼の名前はなし)。 一方、冨嘉のトゥニムトゥF家では、この日、粟の初穂からつくった神酒や握り飯をプルマ崎(ニシ浜東端)のプトゥングパナ石に捧げていた。 プーリン
スクマンマシの30日後に行われる「豊年祭」であり、「首尾」の儀礼である。「大折(ほうれ=大祭)」が語源と推測されている(中鉢,2002)。本来は粟の収穫祭で、その後に行われるアミジュワーが米の収穫祭であったものが、後に米、粟共にプーリンにまとめられ、アミジュワーが雨乞い中心になったのではないかとの推測がある。暦にもよるが大体新暦5月となることが多く、沖縄全体で最も早い時期に行われる豊年祭である。(八重山の他地域は新暦7月、沖縄本島は新暦8〜9月) 当日午前、冨嘉では、トゥニムトゥの3つの家をアスクワーの司、女パナヌファが訪れ儀礼を行う。そののち、一同はマトゥルワー(真徳利御嶽)に向かい、フタムリゲー(阿底御嶽の神井戸)の水、花米、線香、神酒、酒、粥を捧げ、神を招いて阿底御嶽に戻ってくる。一方、一部はニシ浜沿いの聖地の井戸ミシクゲーに向かい、フタムリゲーの水を捧げ戻ってくる。阿底御嶽では神を迎え、供物を捧げて感謝の祈願を行う。 前集落ではトゥニムトゥの家に大石御嶽、大底御嶽、ケーシムリ御嶽の司と女パナヌファが訪れ儀礼(大石御嶽の司は名石部落トゥニムトゥで既に儀礼)を行う。ほかのトゥニムトゥでも簡単な儀礼の後、アバティワー(阿幸俣御嶽)へ向かい、大底御嶽の神井戸の水を捧げる。途中大底御嶽、ケーシムリ御嶽や、ボーザヤマ、キナヤマといった拝所でも水を捧げる。 南集落でも同様に、司とパナヌファがトゥニムトゥを回った後、シサバルワー(白郎原御嶽)に向かう。 このようにして3つのピテヌワーから集落のウツィヌワーに神が招待される。 一方、島北東のシムスケーでは、さきのK家の主導により儀礼が行われる。冨嘉以外の4集落の代表(男性)が参加し、供物を供えて祈願を行い、そののちにK家にて歓待の宴となる。この儀礼は粟の儀礼の色彩が濃く、捧げられる神酒もかつては粟からつくったものであった。アミジュワー午後に冨嘉主導で行われるミシクゲーでの儀礼と対をなしていると推測されている。
昼過ぎからは、西から東への「カンシン」の神旅が行われる。「カンシン」はアスクワーのパナヌファ9名で構成される。カンシンの一人が鳴らす草笛を合図に一行は出発し、線香と花米、クバの葉の扇を持って、他の4つの御嶽を順番に訪れていく。この神旅は、西側(=ブナリ(姉妹))の祝福を東側(=ビギリ(兄弟))に齎す意味があるとされる。カンシンは各御嶽を訪れ、マソーミに座している各御嶽の司に花米を捧げる。各御嶽では司やパナヌファが出迎え、酒(かつては粟製であった)を授け祝宴を開く。ここでは、島の西側(冨嘉)が東側に米をもたらし、東側(他の4集落)が西側に粟をもたらすという構図が現れる。
2日目は「アサヨイ(朝祝い)」と呼ばれ、御嶽以外の村内の拝所での儀礼などが行われる。また、各トゥニムトゥ家ではクパナと呼ばれる行事が行われる。夕方にはムシャーマ公園で公民館主催の巻き踊りが行われる。 翌日、翌々日と続くアミジュワについては雨乞いの項で記すことにする。 【雨乞い】 アミニゲーアサニゲー
「雨願い 朝願い」の意。3回行われるが、前2回(旧11月)は田植え前に対応し、後1回(旧3月)は芋の植え付けに対応していると思われる。それぞれ3日間続けて行われる。当日は早朝、司とパナヌファがウツィヌワーで雨乞いと作物生育の祈願を行う。その後、パナヌファの中から選ばれた2名の「ミジヌファ」が神井戸の水を持ち、各ウガンパカの範囲内の様々な聖地や定められた地点に注いで回る「ミジマチ」が行われる。このような巡礼は波照間独特のものと思われる。
アミニゲースーニゲー 「雨願い 総願い」の意。小雨の年など必要と判断されたときに、2回目、3回目のアミニゲーアサニゲーの後に連続して2日間行われる。2日とも午前中は「アサニゲー」よりも更に多くの箇所をまわる「ミジマチ」が行われる。それが終了すると、今度は「オーシャピトゥ」(公民館の役員)が、西(阿底御嶽)から東(美底御嶽)へと阿底の神井戸の水を持ち御嶽や神井戸の巡礼を行う。午後になると、阿底御嶽の「ミジヌファ」が阿底の神井戸の水をいれた瓢箪を持ち、各御嶽のウガンパカを横断して東へ向かう「ミジマチ」に出る。各集落の御嶽にて水を捧げた後にシムシケーに向かい、水を捧げる。空になった瓢箪に今度はシムシケーの水をいれ、島北岸の神道を西進して阿底御嶽に戻り、神井戸と御嶽のマソーミにその水を捧げる。 更に夜になると、東から西への男性の巡行が行われる。各御嶽の代表者はそれぞれの神井戸の水を持ち合流しながら冨嘉に向かう。そして阿底御嶽に水を捧げた後、阿底の神井戸の水を持ち帰り、各御嶽にその水を捧げる。この後、御嶽の拝殿で司やヤマニンジュが夜を明かす「ユーマチ」が行われた。 なお、かつては「アミニゲースーニゲー」の2日目の夜、この男性の巡行の代りに仮面神「フサマラー」が出現していた。フサマラーは各御嶽の側の森から2頭ずつ出現し、東の美底御嶽から順に合流しながら西進し、阿底御嶽に計10頭のフサマラーが集まる。ここで雨乞いの神歌が歌われる。この後各御嶽のフサマラーは阿底御嶽の神井戸からの水を持ち帰り、各御嶽で雨乞いの神歌が歌われた後消える。「フサマラー」は「草から生まれる」の意と推測される。八重山には南方系と推定される仮面神が点在しており、西表島古見、小浜、新城、石垣島宮良では豊年祭に仮面神「アカマタ/クロマタ」が出現するが、古見では白マター、赤マターを「フサマラー」、また新城島下地でも子神を「フサマロ」とも呼ぶ場合があり、関連が考えられる。現在ではフサマラーはムシャーマの仮装行列に登場している。 クムリ クムリは文字通り「籠り」行事であり、旧12月辛酉の日より60日おきに2月、4月の3回、いずれも辛酉に行われる。司とバシヌシカ(年長のパナヌファ)2名が御嶽に籠り、供物を供え、火と香を絶やさず燃やし続ける。順に「3日クムリ」「5日クムリ」「7日クムリ」と呼ばれ、かつては実際にそれぞれの日数籠ったが、80年代には1〜2晩に、最近は1日に短縮されたという。男子禁制の神事。 2日目には神井戸で「アマグイヌパン」と呼ばれる雨乞いの神歌が歌われる。神歌では、雨を司る神の生誕と成長を描写した詞や、水田のあった場所や降雨時に水路となる場所の地名を読み込んだ詞が歌われる。各御嶽で読み込まれている地名を繋いでいくと、東から西への水脈が浮かび上がる。また琉球王府への上納品であった麻や綿の生育も祈願される。こののち各ウガンパカで「ミジマチ(水祭り)」が行われる。また、その後にアミニゲースーニゲーと同様の、冨嘉の「ミジヌファ」による西から東への「ミジマチ」も行われる。 ミジトゥリ 昭和初期まで年3回(旧暦11月末、12月末、3月)行われていた、西表島に水を取りに行く神事。第1回、第3回は冨嘉集落から西表島南風見村の「ボーラケー」、北集落から仲間の井戸、古見の井戸に旧家の男が小船で水を取りに行き、また井戸の底の「水の子」と呼ばれる黒い小石が共に運ばれ、御嶽の庭に埋められた。 西表島の雲が雨水をもたらすと考えられていたことや、波照間の住民が西表にルーツを持つと考えられていたことに由来する神事であると推測されている。また、第2回目は、石垣島バンナ岳麓の「ナルンカーラ」から水を取ってくる。これは石垣島の山々に湧き立った雲が雨水をもたらすと考えられていたためと思われる。第2回目はケーシムリ御嶽と深い関係があるとされる。 アミジュワー アミジュワーは内容的にはプーリンの繰り返しに近いが、雨乞い関係の祈願に対する「首尾」儀礼であり、次の農耕期の雨の祈願・豊作祈願でもある。かつてはプーリンの20日後に行われ、神行事サイクルの終わりに位置したが、現在はプーリンと連続して行われる。また2日目には仮装行列や綱引きが行われていたが、18世紀後半に島の東西の間で起こった争いを機に、綱引きは廃止され仮装行列はムシャーマに移されたという。この時点まではプーリンと連続して行われており、その後20日後となり、更に近年連続開催に戻ったという説もある(仲本)。
午前中はプーリンと同様、トゥニムトゥ、ピテヌワー、ウツィヌワーでの儀礼があり、午後もプーリンと同様にカンシンの巡行が行われるが、儀礼での祈願は来期の豊作を祈願する言葉や、雨乞いの言葉に差し替えられている。プーリンと同様、美底御嶽から阿底御嶽への帰路についてはアマグイヌパン(雨乞いの神歌)が歌われながら、御嶽や聖地、井戸など様々な場所に立ち寄っていく。阿底御嶽に辿り着くと、プーリンと同様神踊りが踊られる。
アミニゲー スーニゲーが行われた年の場合は、この晩に御嶽での夜籠りがある。2日目は「アサニゲー」「ユーニゲー」となり、宴や巻き踊りが行われる。
後編では天候願い、疫病払い・虫払い、事務的神事のグループについてとりあげる。
参考文献:
Cornelis Ouwehand 1985 "HATERUMA :socio-religious aspects of a South-Ryukyuan island culture" E.J. Brill |
|
|
|
| HONDA,So 1998-2005 | 御感想はこちらへ |