PC処世術 - 消費電力の壁
消費電力の壁 - 序章
CPUの消費電力が顕在化して久しい。かつて、パソコンCPU の消費電力など数W程度かそれ以下であり、CPUは冷却ファンはおろかヒートシンクすらも必要としなかった時代もあった。それが i486の頃であったか、ヒートシンクが登場し、クロックダブラなどが搭載された頃から冷却ファンが必要とされるようになったのである。
その当時からCPUの消費電力と発熱の問題はやかましく言われるようになっていったように思う。その当時から、一部では「発熱のために100MHz程度がクロック周波数の限界」などという熱によるCPUパワー限界説が囁かれていた。 Pentiumが発表された当時も、今から思えば高々数Wという消費電力であったが「大変な熱を発するCPUだ」という具合に世間では扱われた。また PentiumII が登場したときには消費電力が 30Wを超え、筆者も「ちょっとした半田ごて級の発熱だ・・・」と空恐ろしく思ったものである。
それがどうであろう、今やデスクトップパソコン用CPUの消費電力は100W級にも達しつつあるのである。ちょっとした半田ごてどころか、電気工事用の半田ごて級の電力をCPUは消費し、発熱しているのである。しかもプロセス技術の進歩によってCPUのダイ自体は大きくなっていないので、発熱密度(面積あたり発熱量)は著しく大きくなってきたわけである。これまで筆者は、消費電力が大きくなりつづける新CPUを見るにつけ、かつての高速ロジックIC 74Sシリーズの‘S’が、ショットキ・ダイオードのS,スピードのS,そして「焦熱のS」と呼ばれながら消えていったことを連想し、行く末を案じていた。しかし、筆者の心配をよそにCPUは大消費電力化への道をひた走ってきた。
それを支えてきた影には冷却装置の進歩(巨大化)があったわけだ。現在はその冷却装置も騒音を発してその存在を顕示したり、発光してみたり、あるいはPCケースの外側でオブジェとして置かれるなど、PCのパーツとしての地位を築いているようだ。単純に冷却能力のことだけを考えるのならば、工夫やそこに掛けるコスト次第で、まだ更に大きい発熱に対応することは不可能ではない。したがって、更なる大消費電力・高発熱路線をCPUが歩むという可能性は、無いわけではなかった。
では、CPUの発熱は今後も成長(?)を続けていくのだろうか? 2004年の100W級時代に至って、その答えの一つをIntel自身が曝したようだ。それは周知のとおり、 Prescotより先の NetBurst系CPUをキャンセルし、低消費電力系のCPUに軸足を置くと発表したことである。巷の噂どおり、消費電力と発熱の問題が Intel の計画を変更させたのだろう。
大消費電力系CPUを先導するIntelが、“ロードマップ”と称する先読みキャッシュをミスヒットさせてパイプラインを空けるという大ペナルティを負ってまで戦略を変更したという事実は重い、と筆者は見ている。 Prescott で最も消費電力の大きいものは、TDP (=Thermal Design Power)で 115Wであったが、この値が商品としてのデスクトップパソコンに使用できるCPUの消費電力の限界を指しているように思えるのである。
100WのCPUを1日5時間使用すると、1年あたりの電力料金は(1kWhあたり20円として) \3650 程にもなる。つまり、CPUをその命数一杯まで使ったとすると、電力料金はCPU単体の1年当たり価格に匹敵するほどにまでなっているのだ。これでは、CPUの消費電力に限界があるのは当然とも言える。
このことは、直ちにCPUの進化の歩みが止ることを意味しているとは筆者は思わない。しかし、どれをとっても右肩上がりの線を示すPCの主要パーツにおいて,その限界が見えたという事実は、CPUの進化にもやがてサチュレートする時期が訪れることを暗示しているように思うのだ。
その時期は、一体いつ頃になるのだろうか?それは残念ながら筆者にとっては未知である。しかし 64bit時代が少なくとも30年続く ことを考えると、64bit時代の中でその時期を迎えることになるのではないかというのが筆者の読みである。
CPUの進化のサチュレートに伴って、技術が低消費電力へ向けられて騒音や熱風の枷から開放される時代が到来することを切望する筆者としては、それが何時やってくるのかは非常に興味のあるところである。次回以降で、消費電力の変遷について定量的考察を進めていきたいと思う。(19. Jun, 2004)
PC処世術トップページへ
消費電力の壁 - その変遷
消費電力について,115W程度のところに限界がありそうなことを前回書いた。今回は、どのような経過を辿ってそのような大消費電力CPU時代に突入してきたかを振り返ってみたい。図1がIntel CPU の消費電力の変遷を示すグラフである。MMX Pentium 166MHz からの変遷を縦軸をTDPにとって表示してある。TDP は熱設計のための値ではあるが、機械的仕事をしないCPUにとっては実質的な消費電力とニアリ・イコールと考えてよかろう。なお、ピークの消費電力はこれよりも大きい。(図1のデータはこちらのサイトのデータに手を加えて整理したものである。また、消費電力については各社各CPUをクロック周波数で整理したサイトもある。
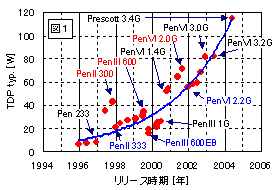 グラフを見るまでもなくご存知のこととは思うが、消費電力は長期的に見て右肩上がりであった。しかしながらグラフを良く見ると、必ずしも消費電力の増加は単調増加ではなかった。例えば、Klamath コアの PentiumII 300MHzの消費電力は 40W を超えていたわけだが、 Deschutesコアの PentiumII 333MHz ではクロック周波数が増加しているにも関わらず、20W 強の消費電力に落ち着いている。また、Willamette コア 2.0GHz では 70Wを超えるに至っていたのだが、Northwood コアの 2.2GHzでは 55W にまで抑えられている。
グラフを見るまでもなくご存知のこととは思うが、消費電力は長期的に見て右肩上がりであった。しかしながらグラフを良く見ると、必ずしも消費電力の増加は単調増加ではなかった。例えば、Klamath コアの PentiumII 300MHzの消費電力は 40W を超えていたわけだが、 Deschutesコアの PentiumII 333MHz ではクロック周波数が増加しているにも関わらず、20W 強の消費電力に落ち着いている。また、Willamette コア 2.0GHz では 70Wを超えるに至っていたのだが、Northwood コアの 2.2GHzでは 55W にまで抑えられている。
一般に、クロック周波数が上がることに伴って消費電力も増加するものであるのだが、プロセスルールの微細化によって動作電圧が下げられ、消費電力は低下するものである。
例えば、Klamathコアの PentimuII から Deschutesコアへ移行した際(1998年頃)には、プロセスが 0.35μmから 0.25μm へと進歩している。また、PentiumIIIでは 0.25μmの Katmai コアから0.18μmの Coppermine コアへ移行した際(1999年後半頃)にも消費電力は低下している。Pentium4 においては、Willamette から Northwood コアで 0.18μmから 0.13μm へと進歩(2002年頃)し、やはり消費電力は低下している。縦軸リニアでプロットしてある図1のグラフからも分かるように、PentiumIII 300MHz とPentium4 2.2GHz で 12Wしか違わないのも、プロセス技術の恩恵に依るところが大きいのだ。
とかくCPUが高速化すると消費電力が上がるような感覚はあり、確かに長い目で見ればそれは事実である。しかしながら、プロセス技術の進歩に伴って消費電力は大きく上下するのも、また事実である。その変遷の過程では、クロック周波数の向上,或いはCPUアーキテクチャの世代交代に伴って消費電力が急上昇した後にプロセスの微細化によって急減することを繰り返してきた様子が垣間見られる。
消費者の観点からすると、電力料金はもちろんのこと,PCの安定性、静音性を考えると、できれば低消費電力のCPUを選択したいところである。今年,2004年の夏は例年にない猛暑となっているところだが、出来ることなら余計な発熱体を部屋には持ち込みたくないところだし、PCの安定性を鑑みても冷却能力に余裕をみたいところであり、あまりな大消費電力CPUというのはチョイスしにくい。
こうした観点で見ると、消費電力が上がりきったところにあるCPUはお買い得とは言い難いように思う。したがって、前世代と同じプロセスで作られた新型最強CPUや、次のプロセスへの以降が始まる直前の最高クロックCPUなどは消費電力の観点からは厳しい選択となることを認識しておく必要があるだろう。これらの速いCPUに苦労しながら熱対策を施して安定性を確保したとしても、次世代プロセスのCPUが当たり前になる頃になって,「何故に遅いCPUの熱対策に苦労しなければならないのか」を考えさせられることになるかもしれない。或いは喉元過ぎれば暑さ忘れたパーツ屋は、そうした古くて熱いCPU用の冷却パーツの販売も忘れてしまうかもしれない。
なお、図1は中古パソコン選定の際にも参考にすると良い。もはや過去のことは十分データを集めることが出来るのだから、古くて熱いCPUを搭載したパソコンなどは出来るだけ選定しない方がよかろう。暑い日に,謎のフリーズ現象のために好んで脳天を熱くする必要はないのだ。
さて,気になるところは 2004年現在 Intel からリリースされている Prescott コアのペンティアム4である。どうも巷の噂によると、リーク電流の所為だかトランジスタ数が多い所為だか、プロセスを微細化したのに消費電力が下がらない問題に突き当たっているらしい。確かに図1を見てもこのCPUの消費電力は突出している。
Intel は未だこの路線で 4GHz程度までCPUのクロック周波数を上げていく予定であるようだが、その裏では消費電力がそろそろ限界であることを認めてもいる。消費電力限界が現在の Prescott の115W級にあるとすると、CPUの進歩は電力を下げる以外に道がないことになる。モバイル向けCPUの路線が、低電力CPUの本命であるとも言われている。次回以降で、このあたりのCPUの消費電力動向や、Intel以外のCPUベンダの動向も併せて考察してゆきたいと思う。(26.Jul, 2004)
PC処世術トップページへ
モバイルCPUの消費電力に将来を見る
これまでに、CPUの能力の向上と共にCPUが消費する電力も増大してきた経緯を紹介した。元々数W程度の消費電力であったCPUも、今や100W級になっている。果たしてこの事態は、高速な演算性能のためには仕方の無いことなのだろうか。
CPUの性能は確かに向上して、デスクトップPCの演算能力は向上し、重たいOSも動かせるようになった。その一方で、モバイルPCは性能の進化から取り残されただろうか?
周知の通り、その答えは偽である。ノートPCはバッテリ使用での連続使用時間や、小さい筐体での放熱を考えると、消費電力の増大に対しては自ずと限界がある。しかしながら、2004年現在のモバイル・ノートPCを見回してみると、デスクトップと同じOSが動作し、必要にして十分なパフォーマンスが得られるようになっている。つまり、モバイルCPUの性能もデスクトップ向けに追従するように向上してきたのだ。
1998年頃から2004年現在迄の間に、デスクトップ向けCPUの消費電力はおよそ3〜5倍になった。では、モバイルPCの連続使用時間はそれに見合うほど著しく短くなったのだろうか?そんなことはないように思う。
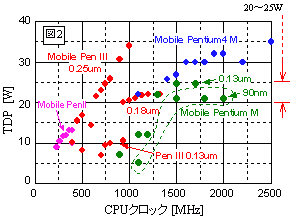 そこで、Intel のモバイルCPUの消費電力の分布を調べてみたのが図2である。横軸にはクロック周波数をとって TDP をプロットしてみた。(元データはこちら, Intel。消費電力と TDPは異なるものだが、TDPは平均的な消費電力を代表する値と考えてプロットした。)
そこで、Intel のモバイルCPUの消費電力の分布を調べてみたのが図2である。横軸にはクロック周波数をとって TDP をプロットしてみた。(元データはこちら, Intel。消費電力と TDPは異なるものだが、TDPは平均的な消費電力を代表する値と考えてプロットした。)
まず、モバイル PentiumII(グラフ上ピンク)の時代には "mini cartridge" などという変な形態ではあったが、CPUの消費電力は10W以下であった。そしてクロックの上昇に伴って、消費電力がほぼリニアに増大している様子が分かる。このCPUは10Wを超えた後、その最期に 0.25μmから0.18μmにプロセスが進歩して再び10Wを切るCPUがリリースされている。
そして モバイル PentiumIIIでは PentiumII の消費電力増大の流れを受け継ぐように20W程度まで消費電力が上がる。そしてその後プロセスが 0.18μmになるのと同時に、"Speed Step"なる機能が追加されて、TDPは頭打ちになるがやはり20W近辺をめがけて成長している。
Mobile Pentium4 Mの世代では 20W近辺で始まって、30W超にまで消費電力が増大しているが、評判は芳しくなかったように思う。水冷ノートPCなどまで登場し、モバイルPCのバッテリ駆動時間は軒並み縮んでしまったように記憶している。なお、この頃には Mobile Pentium4 という"M"の付かないCPUもリリースされているが、こちらは60W級と、モバイルとは呼べないシロモノ(つまりタダのPen4)であるので図2からは除外してある。
そして現在の Pentium Mプロセッサに至って再び20〜25W近辺でのせめぎ合いの中でモバイルCPUは進化を続けているようだ。そして昨今では Pentium4 M からこの Pentium M へのシフトが進んだことで、バッテリ駆動時間は飛躍的に伸びているようだ。この事実からすると、Intelによる「CPUの平均消費電力はTDPよりずっと低く、CPUがノートPCの消費電力のほんの一部しか決定付けていない。バッテリ駆動時間の問題はCPUの所為ばかりではない」という内容の2000年のIDFのキーノートスピーチにおける主張はデマゴギーであった疑いが濃厚だ(丁度 モバイルPentium4 Mがリリースされる直前だろうか)。
こうして見てみると、モバイル用途のCPUでは、消費電力20〜25WをMAXとした壁が存在しているようだ。これは熱的設計もさることながら、やはりバッテリ使用が重要なモバイル用途において,CPUに許される消費電力の限界がこの辺りにあることを示しているのだろう。
そして興味深いのは、例え消費電力に壁があったとしても演算能力の向上は可能だという事実が図2には示されていることである。どうやら能力向上のために消費電力増加が必要だ、というのは錯覚だったということだ(錯覚していたのは筆者だけだろうか?)。したがって、モバイルCPUで見てみると,消費電力に対する演算能力は、プロセス技術の進歩の恩恵を浴して上がり続けていると見てよい。更に,デスクトップ向けCPUでは Prescott において 90nmプロセスでのリーク電流が問題で消費電力が上がってしまったとされているが、Pentium M ではプロセスが 0.13μmから90nm へ進歩することでやはり消費電力は低下しており、1.1GHzのものに至っては 5Wとかなり頑張っているようだ。
さて、デスクトップ向けCPUにもそろそろ消費電力の限界が見えつつあるようである。その限界は勿論、発熱や電力供給などの技術的問題によるところもある。しかし、最近ではモバイル向けCPUをデスクトップPCに用いるという動きが流行しつつあることが示すように、静音性に代表される商品性や電力料金という経済性といった問題が「パーソナル・コンピュータ」の壁として立ちはだかりそうだ。その壁は、おそらく当面は100W級程度のところになるのだろう。このような消費電力の壁は、CPUの4.27db/year という成長速度を鈍化させる可能性はあるが,現在のモバイルCPUの追従度合いを見ると,成長を止めてしまうほどではないように思われる。
そして、殆どの消費者にとってCPU能力の進歩が不要になったとき,CPUの演算能力の成長が止まり、消費電力は低下する方向に向かうことになるだろう。そして、それの目指すところが現在のデスクトップに対して著しく少ない 20W級に向かうとしても、CPUの能力を維持しながら消費電力を低下させることは可能と思われるのである。
その時期は何時来るのか?少なくとも、64bit革命の後に続く長い期間は、消費電力低下のフェーズになるように思う。もっとも、そうしたフェーズを待つまでもなく,図2を見た筆者は、現在使用しているPentium4マシンを前にして己の浅慮を自戒しつつ,騒音に耐えながら暫く使用していく所存である。(16.Sep, 2004)
PC処世術トップページへ
CPU 消費電力大戦の様相 - Desktop編
さて、これまでCPUの消費電力について,インテルのCPUの消費電力についてその変遷を考えてきた。そうすると、当然気になるのは互換CPUの消費電力の変遷である。そこで、Pentium の世代から現代に至るまで常に Intel の CPU と渡り合って来たAMDのCPUについても消費電力(前稿同様に, TDPを評価指標とした)を調べて見たのが図3である。(横軸にはクロック周波数をとっているが、AMD のAthlonXP以降についてはモデルナンバでプロットしてある。)
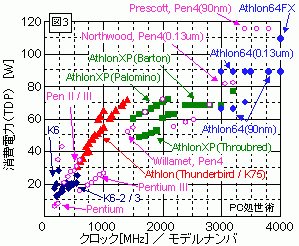 まず、その歴史を追って見ることにしよう。初代〜MMX Pentiumの世代に対抗していた AMD の CPU は K6 である(参考対抗の歴史)。この時代は Pentium が 10W以下のレベルであったのに対して、K6 は 15〜20W超と大喰らいなCPUであったことが分かる。この頃のCPUも,やはり消費電力や冷却のことが喧しく言われていたが、Pentium と K6 の差がそれほどの大問題とならなかったのは、やはりこの時代におけるCPUの消費電力問題は未だ致命的ではなかったためだろう。
まず、その歴史を追って見ることにしよう。初代〜MMX Pentiumの世代に対抗していた AMD の CPU は K6 である(参考対抗の歴史)。この時代は Pentium が 10W以下のレベルであったのに対して、K6 は 15〜20W超と大喰らいなCPUであったことが分かる。この頃のCPUも,やはり消費電力や冷却のことが喧しく言われていたが、Pentium と K6 の差がそれほどの大問題とならなかったのは、やはりこの時代におけるCPUの消費電力問題は未だ致命的ではなかったためだろう。
さらにその次の世代では “PentiumII 対 K6-2/3”という構図での戦いがあった。PentiumII は一時期カートリッジタイプになって冷却が難しかったこともあり、その消費電力は問題視されたのだが、図3を見る限り,K6-2/3 軍勢がやや優勢だが大差は無かったようだ。
Intel と AMD のCPUで消費電力に大差がついたのは“Athlon 対 PentiumII/III”の頃だ。この時代には 1GHz 先駆け競争が演じられ,AMD はこれに勝利したのだが、GHzを達成した時の消費電力は PentiumIIIの倍近くになっていたのである。したがって当時の Athlonは、PentiumIIIと同程度の冷却では到底その放熱は追いつかず、CPUコアが焼けてしまうという事故なども発生したようだ(特にクロックアップ時に多かった)。この時代の Athlon はコアが「サンダーバード」であったことから、この事故で死んだCPUを俗に「焼き鳥」などと呼んだものだ。この時代に関しては、明らかに AMD のCPUは Intel のそれと比較して大喰らいであった。
消費電力について混戦模様となるのは “Pentium4 対 AthlonXP”以降だ。Intel の NetBurst アーキテクチャCPU(Pentium4)の消費電力は、それ迄の PentiumIII と比較して著しく高く、パロミノ・コア(0.18μm)で消費電力を下げてきた AthlonXP の消費電力と拮抗する。この時代においても、AMD のCPUについては前述の「焼き鳥」事故のトラウマ体験が語り継がれていたのだが、実質的には Pentium4 と Athlon は大体同程度の消費電力という理解が正しい。また、この世代の Athlon からは過熱防止の焼き鳥対策機能がついている。
この頃のCPU消費電力のレンジは60〜80W程度であり、2005年現在もこの辺りの消費電力レンジがデスクトップ向けCPUの主戦場であるように思われる。
このレンジの戦いは 0.13μmプロセスの 「Intel Northwoodコアのペンティアム 対 AMD Bartonコアのアスロン」に引き継がれることになる。2005年現在は、この戦いの様相はそのまま“Celeron 対 Sempron”というバリュー・デスクトップ向けCPUのレンジにシフトしている。(なので、2005年現在のバリューデスクトップCPUの消費電力は、60〜70W前後と心得ておけば良い)
このように拮抗していた Intel vs AMD の消費電力(抑制)大戦であったが、2004年から2005年現在にかけて動きはあったようだ。一方の Intel は 90nmプロセス化で「リーク電流云々」と言い訳しながら消費電力が100W超の領域に踏み込んだのに対して、AMD は 90W近かった Athlon64 の消費電力を 90nmプロセス(Winchester)で 70W弱という現在の主戦場レベルにまで抑えることに成功しているようだ。この状況に対して Intel が泡食って NetBurst路線(クロック周波数至上路線)を諦めたのは、去る2004年の出来事だ。
さて、こうして眺めて見ると、ハイエンドの100W超級CPUは置いておくとして、筆者の観測では 2005年現在のCPU消費電力の主戦場は60〜80Wである。今後,CPUのマルチコア化が進むにつれて,やはり消費電力は重要なキーワードになってくるようだが、ハイエンドで壁となるであろう100W強の消費電力を保ちながら戦いを続けるにはボリュームゾーンのCPUの消費電力は70W前後である必要があるように思う。(これは、かつて焼き鳥事故を起こした Athlon と大体同じレベルの消費電力だ。)
この観点から、2005年にお目見えするであろうデュアルコアのCPUの消費電力がどのレンジに収まるかは注目である。筆者の観測によれば既に100W超級という消費電力は、経済的にも,「パーソナルコンピュータ」の商品性と言う見地からも“壁”であることには間違いなさそうに思われる(Intel のNetBurst蹉跌問題も、その答えの一つだろう)。したがって、プロセッサのラインナップを考えた場合に、Intel と AMDのどちらが主戦場となる70W前後の消費電力レンジにデュアルコア・CPUを入れてこられるか、注目したいところである。
そして、さらに先のマルチコアまでを考えると,現在モバイルや静音PC向けと位置付けられている数W級の低消費電力CPUの動向が如何に重要かが見えてくる。当サイトでも、どこかのタイミングで各社の低消費電力CPUの様相について考えてみたいと思う。(11.Jan, 2005)
PC処世術トップページへ
当サイトにある記事の著作権は M.Abe に属します。
なお、当サイトの記事の転載はご遠慮ください。
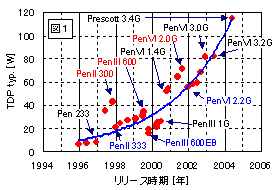 グラフを見るまでもなくご存知のこととは思うが、消費電力は長期的に見て右肩上がりであった。しかしながらグラフを良く見ると、必ずしも消費電力の増加は単調増加ではなかった。例えば、Klamath コアの PentiumII 300MHzの消費電力は 40W を超えていたわけだが、 Deschutesコアの PentiumII 333MHz ではクロック周波数が増加しているにも関わらず、20W 強の消費電力に落ち着いている。また、Willamette コア 2.0GHz では 70Wを超えるに至っていたのだが、Northwood コアの 2.2GHzでは 55W にまで抑えられている。
グラフを見るまでもなくご存知のこととは思うが、消費電力は長期的に見て右肩上がりであった。しかしながらグラフを良く見ると、必ずしも消費電力の増加は単調増加ではなかった。例えば、Klamath コアの PentiumII 300MHzの消費電力は 40W を超えていたわけだが、 Deschutesコアの PentiumII 333MHz ではクロック周波数が増加しているにも関わらず、20W 強の消費電力に落ち着いている。また、Willamette コア 2.0GHz では 70Wを超えるに至っていたのだが、Northwood コアの 2.2GHzでは 55W にまで抑えられている。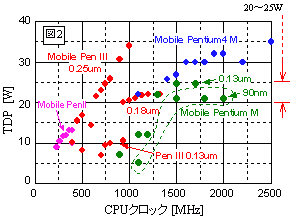 そこで、Intel のモバイルCPUの消費電力の分布を調べてみたのが図2である。横軸にはクロック周波数をとって TDP をプロットしてみた。(元データは
そこで、Intel のモバイルCPUの消費電力の分布を調べてみたのが図2である。横軸にはクロック周波数をとって TDP をプロットしてみた。(元データは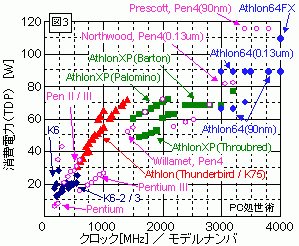 まず、その歴史を追って見ることにしよう。初代〜MMX Pentiumの世代に対抗していた AMD の CPU は K6 である(参考
まず、その歴史を追って見ることにしよう。初代〜MMX Pentiumの世代に対抗していた AMD の CPU は K6 である(参考