PC処世術 - CPU編
CPUの進化を考える
付録: CPUの賞味期限と命数(寿命)
PCの性能を語る上でCPUのパワーは花形である。筆者がPCというものに触れはじめた当初(1980年代後半)はNEC のV30, 10MHz またはIntel286,10MHz というスペックが全盛の時代であった。これと比較すると、現在のPCは GHz級のCPUの搭載は常識であるし、同一クロック数でも処理スピードは当時のCPUよりはるかに速くなっている。
一般にムーアの法則で知られるように、PC関連の機器は時間に対して指数関数的にその能力が向上してゆく。そこでCPUの処理能力の対数をとって、どのようなスピードで能力が向上してきたか、検証してみた。
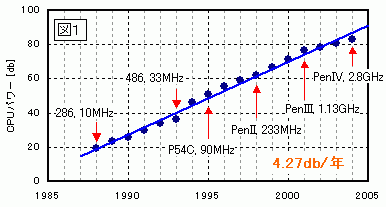 CPUは進化に伴って同一クロックでも処理能力は異なる。そこでCPUの種類に応じて係数を算定し、この係数とクロック周波数との積を以ってCPUパワーとした。この係数は筆者の経験に基づく値を用いている。参考までに値を書くと、V30を0.5, 386DXは1.0, 486DXは2.0, Pentiumは4.0, PentiumIIIで6.0, Pentium4で5.0という具合で、色々異論はあるとは思うが実勢から大きく逸脱してはいないだろう。こうして算出したCPUパワーのlog(対数)をとり、20を掛けてグラフにしたのが図1である(つまり、縦軸はdb[デシベル]表示である)。CPUには、各年代において標準的かややハイスペックであったものを各年代の代表とした。
CPUは進化に伴って同一クロックでも処理能力は異なる。そこでCPUの種類に応じて係数を算定し、この係数とクロック周波数との積を以ってCPUパワーとした。この係数は筆者の経験に基づく値を用いている。参考までに値を書くと、V30を0.5, 386DXは1.0, 486DXは2.0, Pentiumは4.0, PentiumIIIで6.0, Pentium4で5.0という具合で、色々異論はあるとは思うが実勢から大きく逸脱してはいないだろう。こうして算出したCPUパワーのlog(対数)をとり、20を掛けてグラフにしたのが図1である(つまり、縦軸はdb[デシベル]表示である)。CPUには、各年代において標準的かややハイスペックであったものを各年代の代表とした。
PC-98シリーズ時代まで含んだ十数年・数世代にわたるCPUを当てはめているにもかかわらず、グラフは見事に直線的で、ムーアの法則が実勢をよく言い当てたものであることがよく分かる。CPUの能力ゲインは4.27db/yearであり、これがCPU進化のスピードであり、また陳腐化のスピードでもある。このスピードは1年経つとCPUの能力は約1.6倍, 2年で2.7倍, 3年で4.4倍になることを意味している。
図1から得られた 4.27db/year という値を用いると、CPUの賞味期限を算出することが出来る。ここで賞味期限とは、あるCPUがローエンドCPUに成り下がってしまうまでの時間である。算出方法は簡単な算数で、ある時点でのローエンドのCPUパワーをデシベルに換算(logをとって20倍)し、そして賞味期限を知りたいCPUのパワーのデシベル換算値との差を計算する。そして4.27db/year で割ればよい。
例えば、現時点(2004.1時点)でのハイエンドCPUは3.2GHzであり、ローエンドを1.7GHzとするとその能力の比は1.9倍、デシベル換算で5.5dbであり、4.27db/yearで割ると約1.3年ほどの賞味期限しかない。ハイエンドの3.2GHz CPUも、1.3年後には、現時点の1.7GHz CPU と同様の扱いを受ける、と読むことが出来る。
このような観点で、1998年から2004年までのCPUの賞味期限とCPUの価格との関係を整理してみたのが図2である。データは各年第一四半期頃のIntelのCPUのものを使用しているが、筆者がウォッチしてきた価格のプロットであり、必ずしも厳密ではない点は容赦いただきたい。また、グラフが突然折れ曲がっていて必ずしも連続的でないのは、セレロンなどの廉価CPUの台頭や新CPU出現による異種のCPUが混在しているためである。
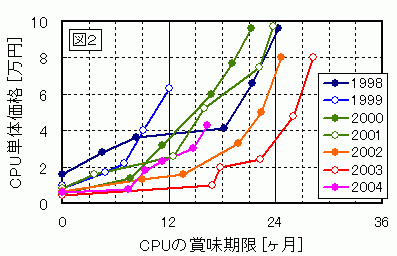 図2を見ると、年によって販売されているCPUの賞味期限は12ヶ月〜28ヶ月と、倍以上開きがあることがわかる。そして、同じ価格であっても年によって賞味期限は異なる。
図2を見ると、年によって販売されているCPUの賞味期限は12ヶ月〜28ヶ月と、倍以上開きがあることがわかる。そして、同じ価格であっても年によって賞味期限は異なる。
このため、「CPUはどのような時が買い頃か?」という問いに対して筆者は、「より長い賞味期限のCPUを販売している時」と回答することにしている。図2で言えば、2002, 2003年がそれに該当する。逆に、1999年や2004年のように、販売されているCPUの賞味期限が短いような場合には要注意と思っている。このような局面で大枚をはたいても、短期間で更新を迫られる可能性が高い。
続いて、「現時点ではどのCPUを選択すればオトクか?」という問いもよく耳にする。Intelの傾向線である図2を見ると、大体2〜3万円のプライスタグをつけたCPUより上のグレードでは、CPUの賞味期限の伸びに対して価格上昇のほうが大きいように見える。したがって、3万円を超えるようなCPUには手を出さないほうが無難である。特に4万円以上の領域は完全にプレミア価格が転嫁されていると見るべきで、よほどの必要に迫られていない限り、選択しても賞味期限はさほど伸びないことを覚悟する必要があるだろう。
では、賞味期限切れのCPUはどうか。現在販売されているローエンドのCPUよりさらに遅いCPUであってもきちんと実用に供しており、賞味期限切れのCPUを食したからといって食あたりを起こすわけではない。
そこでCPUの命数(寿命)、すなわち本当に使用が困難になるまでの時間を計ってみたい。算出方法自体は、CPUの賞味期限と同様である。基準となるCPUを「現在使用上自分で堪え難いと思うCPU」に置けばよい。 筆者の場合、現在堪え難いと感じるCPU速度はCeleron 400MHzくらいであろうか。そして現在使用中のPCはPentium4 2.4GHzである。その能力差は17.3db 程であり、命数にして3.8年である。すなわち、約4年後にはCPU周りのアップデートを考えることになるということだ。そして現在のハイエンド3.2GHzのCPUの命数は4.3年で、筆者の2.4GHzに対して半年ほど長生きできる計算である。
過去の例にあてはめてみると、筆者は1995年に Pentium 133MHzを導入している。そして、この頃最低限必要と考えていたCPUパワーは486 66MHz程度であっただろうか。命数を改めて計算してみると、2.9年ほどのCPUであった。果たして筆者は1998年には不足を感じ、CPUの換装を実施していたのだった。もっと溯ってみよう。筆者がPC-9801互換の386機(20MHz)を導入したのは1990年で、この当時の最低ラインはV30 10MHzであった。そこから計算すると、CPUの命数はやはり2.9年であった。果たして筆者はCPUの換装を3年後の1993年に実行することになっていた。
この考え方を巷で売られている激安PCにも適用してみると、激安PCに搭載されているCPUの命数は意外と長いことが分かる。筆者の試算では、約2.5〜3年である。こうしてみると、CPUに関しては「その時売られているCPUであればどれを選んでも大差なく、3〜4年もすればいずれ交換か買い替えを迫られる」のである。ハイエンドと言われるCPUに目が眩みそうになったら、そのCPUの命数を数えてみると目が覚めるかもしれない。
このような試算はハイエンドCPUを否定するものではないが、CPU選択の際には是非CPUの賞味期限や命数を計算されることをお薦めしたい。勿論、こうして計算される値は単純にグラフに定規で線を引いただけの値なので厳密ではない点はご容赦いただきたい(この計算結果を利用した結果について筆者は保証できない)。
なおここまで記してきたことは、CPUの処理能力がムーアの法則に沿って成長しつづけることを前提としている。また、この傾きが技術の進歩によるものなのか、ユーザーの欲求によるものなのか、ハード/ソフトベンダの思惑によるものなのかは分からない。いずれこのような成長は止ってしまうかもしれないし、傾きが大きく変わる可能性もある。しかしながら、湾岸戦争やイラク戦争,日経平均株価の8000円割れといった社会情勢はこの成長に対して大きな影響を与えてはこなかったようである。
ただ、CPUの賞味期限や命数を数えて解ることは、ムーアの指数法則はハイエンドCPU導入の根拠とはならない、ということである。平たく言うと、「パソコンは進化が速いから、とにかく最速のものを揃えておかないとスグに遅れちゃうよ」という類のアドバイスは必ずしも正しくないということである。忘れてはいけない。最速CPUといえども等しく時間の流れには抗えず、やはり時が来れば遅れてしまうのだ。
また、CPUの命数の計算方法から明らかなように、何を基準となる最低CPUと置くかによって寿命は延びたり縮んだりする。したがって、いかに同一の体感速度をより遅いCPUで実現するかを探求することも、PCを延命させることを考える上で重要であることを付記しておきたい。
さてここではCPUについて話題にしたが、せっかく大枚はたいて購入したPCが時代遅れになったり、「そろそろ買い替え」感を醸すようになるのは、なにもCPUのせいばかりではない。PCを構成する要素は多々あり、実はそれぞれバラバラの速度で進歩している。PCとの共存共栄のためには、これらについても今後考察してゆく必要があるだろう。今後の考察課題としたい。(31.Jan, 2004)
PC処世術トップページへ
CPUのコストパフォーマンス
前稿を書いて日が浅いが、Intelから Prescott コアのCPUが発表され価格も明らかとなった。CPUの価格は値下げされ、雑誌やインターネットなどの評価記事にありがちな「この価格ならコストパフォーマンス的にもリーズナブル」的な文章が脳裏に浮かんだ。そしてネット上では早速棒グラフ対決記事が躍り始めている。
ここでCPUの賞味期限や命数を計ってみるのは勿論のこと、CPUのコストパフォーマンスを定量評価してみたい。雑誌をはじめとするメディアに書かれる「コストパフォーマンス」という言葉は一見それらしいが、その結論とするところは「リーズナブル」だとか、「パワーユーザーになら薦められる」といった主観的な感想が主だったりする。結局のところ、経験(霊験)のありそうな記者の言うことを信じるしかないのだろうか?
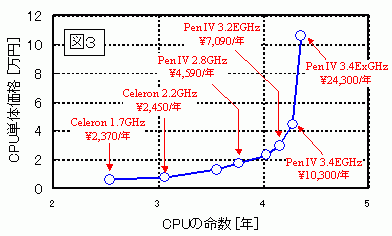 そこで、価格と命数の関係を整理してみたのが図3である。我慢の限界基準はCeleron 400MHzとして命数を計っている(係数は、筆者の見積もり値。正しいかどうかは保証しない。)。なお価格は、Pentium4については新たに発表されたIntelの価格を元に1ドル105円で計算してあり、Celeronについては実勢価格で示してある。
そこで、価格と命数の関係を整理してみたのが図3である。我慢の限界基準はCeleron 400MHzとして命数を計っている(係数は、筆者の見積もり値。正しいかどうかは保証しない。)。なお価格は、Pentium4については新たに発表されたIntelの価格を元に1ドル105円で計算してあり、Celeronについては実勢価格で示してある。
赤字で記してあるのはコストパフォーマンス値である。これはCPUの価格を命数で割った値であり、1年間あたりどれだけのコストをCPUにつぎ込むことになるか、という意味を持つ値である。
Celeron勢は \3,000/年以下と、非常にコストパフォーマンスに優れている一方で,Pentium4勢はやや分が悪い。価格の高いCPUになるにつれて必ずコストパフォーマンスは悪くなっており、長期間使用するということを目的としたCPU選びでは、高価なCPUは価格分ほど長持ちしないことを示している。したがって、この命数(寿命年数)あたりの価格差は純粋に速さの分と割り切る必要があるだろう。
但し、筆者が個人的に過去のCPUのコストパフォーマンス変遷を調べてみたところ、時期によってはコスト/パフォーマンス比の最小値が存在することが分かっている。このようなCPUはローエンド近辺のCPUに見られるので、場合によってはこれより安い最安系CPUで、実はコストの割に陳腐化の速いCPUを売りつけられる可能性がある点に注意したい。
どのラインまでのコスト/パフォーマンス比を許容するかは評価者の主観が入るところではあるが、CPUの命数を用いたコストパフォーマンス評価方法の特長は「いつの時代も年数という基準でCPUのコストパフォーマンスを知ることが出来る」点にある。CPUの価格が改定になったり新CPUが出たといった局面では、コストパフォーマンスを割り出してみれば、なにも霊験あらたかな経験者の談を仰いだり、ごく短期的なCPUメーカの事情や刹那的な棒グラフによる比較記事の内容を知る必要もないかもしれない。
また、このグラフはCPU価格の下落曲線もしくは陳腐化曲線としてみることもできる。一年経つと命数が一年削られると考えると、そのCPU(または同等の性能をもったCPU)が1年後にどのような価格で販売されるかを、ある程度予測できるのである。ExtremeEditionのようなもともとプレミアム性の高いCPUの場合は1年後という短期予測は立てにくいが、3.4EGHzのような普及クラスに落ちてきそうなCPUの予測は比較的当たるのではなかろうか。現在 4.4万円ほどのプライスタグをつけられた 3.4GHz CPUだが、1年後には1.2〜1.5万円といった価格で同様の性能のCPUが手に入る、とグラフから読むこともできる。
このような見方をしてみると今回のような新CPU発表&価格改定というのは、これまでに体験してきたそれと本質的に大きく変わるものではない気がしてくる。これまでいつも新CPU発表時には棒グラフと遭遇してデジャブーを見る思いがしていたが、実はジャメビューを見させられていたのかもしれない。
なお、どの程度の命数のCPUを導入するのが良いかは、自分のPCの更新計画や、PCを延命するスキル、及び予算を大蔵省に請求できるサイクルなどを勘案して決めると良いだろう。(3.Feb, 2004)
PC処世術トップページへ
CPUの“bitの境界”を考える
最近、64bit CPUとか64bit時代とか、CPU や OS アーキテクチャのビット幅の変革期であるとの記述をみかけるようになってきた(まだ、「エンタープライズ分野では必要」という記述が多いが)。このような記事や風評は、そういえば16→32bit の時期にも見られたような気がする。ここでは、当時を回想しながら来るべき64bit時代に対し、どのように備えたらよいかを考えてみたい。
そこでCPUのデータ幅を縦軸にとり、年代ごとに整理してみたのが図4である。データはIntelのCPUとし、1974年にリリースされた8bit CPU i8080から2001年リリースの64bit Itanium までをプロットしてみた(青)。
こうしてみると、時間に対してCPUのデータ幅の進化はリニアであることがわかる。そしてデータ幅は2のn乗になっているので、時代が進むにつれて各データ幅の時代は長くなっている。例えば 8bit i8080のリリースから16bitのi8086/i8088のリリースまでの間隔は僅か4年であるが、16bit→32bitは7年、32bit→64bitは15年を要している。こうしてみると、次の64→128bitには実に30年を要し、64bit時代は2030年過ぎまで続くかつてない長期政権となる見通しである。
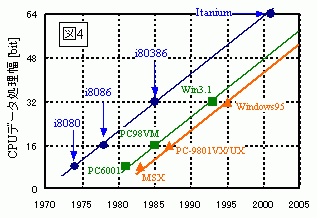 しかし、“xx bit時代”というのは、CPUのリリースと同時には始まらない。過去の例では、それより前のCPUの時代が黄金期を迎え、更にハードウェアがソフトウェアに対してややリッチになる時代を経て次の時代へと遷移している。そしてこの期間は、概して次の時代のCPUは「素人には必要のないハード」という扱いを受けていたように思う。
しかし、“xx bit時代”というのは、CPUのリリースと同時には始まらない。過去の例では、それより前のCPUの時代が黄金期を迎え、更にハードウェアがソフトウェアに対してややリッチになる時代を経て次の時代へと遷移している。そしてこの期間は、概して次の時代のCPUは「素人には必要のないハード」という扱いを受けていたように思う。
図4中の緑の線は、“xx bit時代の幕開け”を告げたイベントのプロットである。8bit 時代はもはやあまり記憶にないが、(日本では)PC-8001やPC-6001, FM-8, MZなどがその時代を告げたものだったと思う。16bit時代はPC-9801の時代であったが、その時代の幕開けを告げた機種は長らく互換の基準となったV30搭載のPC-9801VMの発売ではなかっただろうか。
そして過去の16bit CPU時代に別れを告げ、現在の32bit時代の入り口となったのは Windows386の血を継いだ Win3.1 であった。
これらの“xx bit時代の幕開け”事件は図4を見て分かるとおり、CPUのリリースから一定のディレイがある。筆者の図から読み取ると、そのディレイは7〜8年である。したがって、この法則が当てはまるとすると、64bit時代の幕開けを告げるイベントは2008〜9年にあると予測できるのである。
しかし過去を回想してみると、“xx bit時代の幕開け”でやってきたアーキテクチャは、かならずしもそのまま黄金期へと引き継がれたわけではない。Win3.1時代は比較的短く、あっという間にWin95に取って代わられたことは記憶に新しい。
そこで、“真のxx bit時代”を築いたイベントを橙色でプロットしてみた。8bit時代の黄金期は、MSXであろう。共通規格とあって各社からPCが発売され、ソフトも充実した。16bit時代は 286, 10MHzという仕様のPC-9801VX/UXが発売され、互換機も登場した1987年頃からが黄金期であったのではないかと思う。そして真の32bit時代の到来はWindows95の登場だろう。
これらの黄金期を迎えたイベントもグラフ上では一直線に並んでおり、CPUリリースからのディレイは 9〜10年である。すなわち、xx bit CPU のリリースから9〜10年をかけてxx bit時代は黄金期を迎えるのである。
こうしてみると、64bit CPUが黄金期を迎えその性能を遺憾なく発揮するようになるのは2010〜11年頃から先であると予測できる。
64bit時代は長い期間続く(予定である)。したがってCPUおよびOSベンダにとって、64bit時代の入り口にある現在は、30年という長期間の覇権を掛けた競争の真っ只中にいることになる。
たしかに雑誌記事などには64bitに因んだ記事が踊り始めているし、2004年のIDFでは Intel の次期64bitアーキテクチャについて語られるとかである。
(IntelのCPUでは)64bit 元年が2001年であったから、2004年現在は64bit幕開けまでのカウントダウンが始まった段階といったところだろうか。未だ世評は「パソコンレベルでは必要なく、エンタープライズ云々」という意見が多いものの、きたるべき64bit 時代に向けた煽動のための布石を打っている段階にも見える。いわゆる64bitに対応する「キラー・アプリ」が不在なところが世の中のメディアを消極的にさせているだけかもしれず、キラー・アプリに成り得る存在が見つかったら、そっちへ向かって一直線になるのかもしれない。
では、パソコン小市民たる我々はこの難局にどう立ち向かったらよいのだろうか?答えは簡単、64bit時代の幕が開けるまで静観するに限る。64bit時代に対応できそうなCPUがリリースされても、すぐに手を出すべきではない。
なぜならば、前稿でも書いた通り、販売されるCPUの命数はせいぜい4から5年だからである。ここ1年くらいでリリースされる64bit CPUは、丁度64bit 時代の幕が開けるころに限界を感じることになり、そして真の64bit 時代を迎える頃にはとっくに命数が尽きていることだろう。32bit で言うところの 386や486DXなどに相当する。これらは確かに32bit CPUであり Windows95を動かすことは出来たが、真面目に使う気にはさせなかった。
したがって、先を急いで64bit CPUに手を染めても、まだしばらく続く32bit CPUと同じ使い方をして、いよいよというときにあらゆる延命措置を施した上でその最期を看取ることになりそうだ。勿論、最新OSをいち早く動かしてみたいという趣味的欲求を満たすことはできるだろうし、筆者はそういう趣味を否定はしない。しかしながら、パソコンを半趣味・半実用に供している筆者としては、まだしばらく続く32bit時代を、ややリッチ目な32bitハードで満喫しておこうと思う。
それにしても、64bit 時代のキラー・アプリは何になるのだろうか?また、30年にわたる64bit時代にも今と同じ進歩の道を辿るのか?それともこれまでとは異なる方向を模索するのだろうか?これらについても、いずれ過去の出来事を回想しながら想像を巡らしてみたい。(18.Feb, 2004)
PC処世術トップページへ
互換CPUの戦略 - Cylix編
CPUの選択において、互換CPUの存在は大きな興味の一つといえるだろう。互換x86系のCPUでは古くはIntel完全互換の和製8086などもあったし、日本電気製の8086拡張CPUである V30, V50, V33などもあった。その後もパソコンCPUの代表として君臨しつづけたIntel x86 CPU の互換CPUは数多く生まれてきた。そして、32bit時代の到来に伴うパソコンの増産に伴って、互換CPUの登場も花盛りとなったことも、既に過去の出来事である。互換CPUの戦略とそのIntelに対する位置付けがどのようなものであったのか、過去を振り返ってみたい。ここではまず、互換CPUの老舗の一つ、サイリックス(現在はVIAに買収されている)について振り返ってみよう。
サイリックス社 は筆者の知る限り, 元々はコプロ屋であった。当時、i486DXの登場までは浮動小数点演算プロセッサ(コプロセッサ)はCPUに内蔵されてはおらず、浮動小数点演算を高速で行うためには x87シリーズというコプロセッサが必要であった。Cylix はこの x87互換コプロセッサのベンダであったわけだ。
それが32bit試行フェーズの中盤において、Cx486DLC/SLCという386DX/SXピン互換の CPU をリリースした。この CPUは 僅か1KBコード・キャッシュによって 386DX/SX よりも高い性能を得られるようにした CPU であり、386の乗せ替え用CPUとしてヒットした。また、キャッシュコントロールソフトの不具合などにより問題もあったようだが、16bit の 286 を32bit化するという荒技CPU下駄なども出回ったりして、既に命数が尽きた筈のパソコンを甦らせた向きもあったようだ。
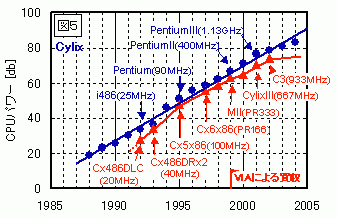 この Cx486DLC/SLC から始まる Cylix のx86互換CPUの歩みを、図1の Intel の歩みに重ねてみたのが図5である。なお、初稿で書いた通り、IntelのCPUについてはミドルレンジ(またはややハイエンド)なCPUがプロットされているのに対して、Cylix のものは各年初頭〜前半において市場に出回っていたもので最高のものをプロットしているので注意されたい。
この Cx486DLC/SLC から始まる Cylix のx86互換CPUの歩みを、図1の Intel の歩みに重ねてみたのが図5である。なお、初稿で書いた通り、IntelのCPUについてはミドルレンジ(またはややハイエンド)なCPUがプロットされているのに対して、Cylix のものは各年初頭〜前半において市場に出回っていたもので最高のものをプロットしているので注意されたい。
さて、Cx486DLC/SLCが登場した頃, 既にインテルは 486SX/DX をリリースしていた。図5から読み取ると,このときのi486 と Cx486の能力差は、およそ2年であり、Cx486は市場に出回ったときには既に賞味期限ギリギリのCPUであった。そしてその翌年頃であったと思うが、Cx486DRx2/SRx2という倍クロックバージョンによって Intel との差を詰めるのだが、それでもIntel のミドルレンジCPUに対して 1〜1.5年ほどの遅れを持ったCPUであった。Cx486DRx2の類は“486”を銘打ってはいたが、プラットフォームが386であったことに加えて、その性能から言っても賞味期限ギリギリで386の乗せ替え用であたことがわかる。丁度この頃筆者も命数尽きつつあった 386 を抱えていたが、Cx486DRx2 に乗せ替え、命脈を保つことができたのである。
この後、時代はいよいよ32bit試行フェーズの末期へと差し掛かる頃、主戦場はSocket3に移っていた。この頃には Intel も乗せ替えCPU市場に乗り込んでオーバードライブプロセッサなどを売るために Socket3 は 抜き挿し易いZIFソケットになっていたのだが、
かえって互換CPUベンダを呼び込むカタチを形成していた。Cylix も486の完全互換プロセッサなどを売っていた時代である。
そして革命フェーズへの移行が起こった 1995年頃には Socket3 でIntel の486以上の能力を発揮する Cx5x86を投入している。この頃のIntel はSocket3 から 4/5 へと逃げており、雑誌記事などでは「CPUのクロックは100MHzが限界だからPCは今が買い時。ハイエンドには低クロックでもパフォーマンスの高いペンティアム。」という煽り記事も散見された時期でもある。そしてこの時期のCylixはパフォーマンス的にIntelのミドルレンジに肉薄して、その遅れは半年〜1年程度にまで詰めることに成功している。Cx5x86は能力的には, 当時のローコストPC向けには十分であったのだが、無情なことに革命フェーズは1995終盤にやってきた。革命フェーズがCPUパワーを要求したこともそうだが、新プラットフォーム(Socket5/7)であるかどうかが土俵際であったために時代の主役となれなかったのだろう。
1995年の Windows95 発売の時期にはCx5x86で苦戦していたCylixなのだが、手を拱いていた訳ではない。6x86の投入をちらつかせていたのである。当初の発表では Pentium 100/120/133 リリースの頃に投入される予定の CPUであり、Intel のハイエンドCPUに追いつく予定であった。
この頃筆者は革命フェーズに際して完全に命数の尽きた386改機の買い替え時期を迎えていた。そして実は、 6x86 の登場を心待ちにしていて人柱となってでも購入する気でいたのだが、無念にもこの時 6x86 は現れなかったのである。
しかしその 6x86 は1996年後半に登場することになる。そして32bit躍進フェーズに繰り広げられた Socket7およびSuper7を主戦場とした互換CPU大戦は、は Socket8 そして Slot1, Socket370 に逃げる Intel を横目に見ながら百家争鳴の体を見せていた。AMDのK6, RISEのmp6, IDTの WinChip などはこの時代の産であるし、Cylixの 6x86は IBMからも販売されたりもした。
そして図5を見ると分かるように、Cylix の 6x86おおび MII の路線は、1998年頃迄 Intel のミドルレンジ CPU に対して1年以内の遅れでよく付いていった。この時代の最新プラットフォームはSlot1からSocket370であったが、躍進フェーズを迎えるにあたり大方のI/Fや拡張バスの類は固まりつつあったので、必ずしも切り捨てられる理由にはならず、1年遅れと言えども競争力があったのである。この頃の最速MII などは、3万円以上のプライスタグをつけることもあった。
このように、互換CPUにも花の時代があったわけだが、残念なことにCylix のCPUがIntelのミドルレンジCPUを追い越すことはなく、常に後を追っていたようである。筆者も、賞味期限ギリギリであった高クロックでないMIIを激安で有り難く入手し、寿命を迎えつつあった Pentium 133MHz の延命を図ったりもした。
互換CPUの比較というと“性能差xx%”ということが気になりがちではあるが、その差を図5の横軸(すなわち年数)で読んでみると、常に旧プラットフォームで戦わなければならなかった互換CPUベンダの苦しさが見えてくる。Cx6x86など、当初の予定通りもう少し早く投入できていれば、Intelにとっては強敵になりえたであろう。このような後追い戦略のために、 Intel との間には相当の経済的体力差が生じてしまったようだ。Cylix はなかなか頑張ったCPUベンダであったと思うのだが、やはり製造プロセスがモノを言う業界にあって、ファブレスという業態には無理があったのかもしれない。
さて、その後 VIA に買収されてしまった Cylix ではあるが、2004年現在の32bit 終焉フェーズにおいてその位置付けはどうなっているだろうか? ご存知の通り、Socket370系のC3 および 静音・低消費電力の Eden などで名を馳せ、支持を得ている。これらのCPUは、図5において完全に Intel に引き離されてしまったようにも見える。しかしながら、C3/Eden を搭載したPCも、十分な実用性を持っている。これらのPCが支持される背景には、騒音問題や廃熱問題, そして消費電力問題があることに疑いはないが、筆者はそれだけではないと思っている。
C3やEden が生き延びている背景には、時代が終焉フェーズを迎えていることもある。実は Cylix は MII の時代に Media GXという、現在の Eden のような路線のプラットフォームとCPUをリリースしていた。しかしながらその時代は躍進フェーズであり、賞味期限切れのMedia GX は残念ながら生き残ることが出来なかったのである。それと比べて終焉フェーズでは、多くの I/F やバス規格が定まっており, メモリも飽食期を迎えてPCにとっては比較的平穏な時期である。C3 や Eden を使用したPCは、ハイエンドな機能を期待しないならば、32bit時代が完全に潰えるまでその使命を全うできるだろう。終焉フェーズには静かでエコなPCを選択するというのもオツなものかもしれない。 (22. May, 2004)
PC処世術トップページへ
互換CPUの戦略 - AMD編
互換CPUと言えば、もう一方の雄 AMD抜きには語れまい。筆者の記憶によれば、198x年代にはAMD はIntel と良好な関係にあり、ライセンスされた x86 CPUを生産していたベンダであった。この点でAMD社は、Intelの互換コプロを独自に作っていた Cylixとは少々異なる成り立ちである。AMD製の8086や286などを知らずに“Intel x86相当品”として使用していた方も少なくないのではなかろうか。
1990年代に入るとその関係にも亀裂が入る。特許や商標に絡んで訴訟などを起こされていたように思う。その頃 AMD は Am386DXLという CPU を製造していたように思うが、日本製のPCではお目にかかることは無かったようである。周波数は25MHz程度と、Intel謹製386が20MHz程度だった時代より若干高めのものがあったように思うが、Intel は既にi486に逃げていた。この頃の AMD は Cylix と同様に、1年以上遅れたCPUをリリースする後追いの形をとっていたわけである。
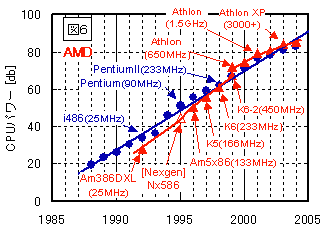 時代は移って 1995年, 32bitの試行フェーズが終了する頃からのAMDのCPUの変遷をプロットしてみたのが図6である。その頃の互換CPUでは Cylix が名を馳せていたが、AMDは Intelに対抗するCPUをリリースすることが出来ていなかった。Socket 3では Am5x86などを出して一部メーカー製PCなどにも採用されたようだが、486乗せ替え用という色合いが濃かった。そして革命フェーズをAMDは、Socket5/7コンパチだが廉価CPUという色合いの濃いK5でしのぐという、完全に後追いの格好であった。
時代は移って 1995年, 32bitの試行フェーズが終了する頃からのAMDのCPUの変遷をプロットしてみたのが図6である。その頃の互換CPUでは Cylix が名を馳せていたが、AMDは Intelに対抗するCPUをリリースすることが出来ていなかった。Socket 3では Am5x86などを出して一部メーカー製PCなどにも採用されたようだが、486乗せ替え用という色合いが濃かった。そして革命フェーズをAMDは、Socket5/7コンパチだが廉価CPUという色合いの濃いK5でしのぐという、完全に後追いの格好であった。
この頃、他に互換CPU といえば Nexgen社の Nx586という CPUがあったが、「専用チップセット, 専用マザー, VLバス」という構成は,アーキテクチャ的には面白かったが性能的には後追いの形であって、世の中にはあまり浸透しなかったようである。しかしながら、この Nexgen という会社は完全にIntelとは異なるアーキテクチャで、Intelの特許や著作権とは無縁にして,しかも独自プラットフォームという孤高の路線で x86互換CPUを完成させていたのである。この Nexgen は Nx686という Pentium に勝る CPU を設計していた途上で AMDに買収されることになる。丁度1995年, Win95の日本語版がリリースされた頃の話である。
32bit革命フェーズの始まりを継げた Win95 のリリースから1年半ほどは、K5(〜PR166)でしのいできたAMD であったが、起死回生のCPUは Nx686 の Socket7版たる K6として 1997年中盤に登場する(図6では1998年にプロットされている)。それまで1年近い差をつけられて後追いしていた AMDであったが、このK6の登場を以って Intel のミドルレンジ CPUにほぼ追いついた。
AMD はその後も、K6-2, K6-III と繰り出し、Slot1に逃げる Intel を Super7 で追いまわして、Intel のミドルレンジCPUに良くついていった。ミドルレンジCPUとハイエンドCPUの差は 価格の差こそあれ、性能の差は対数グラフでは殆ど見えない程度であるので、K6 シリーズの登場は AMD にとっては転換点であり、Intel にとっては脅威の始まりだったといえる。
K6シリーズはメーカー製PCにも採用されるところとなり、かなりの数が売れたようだが AMD の決算は必ずしも安定して良好とはいえなかったように記憶している。パソコン用CPU の価格支配権はハイエンドCPUベンダに与えられるものである。残念ながら、市場に受け入れられた K6 シリーズだけでは Intel の支配するパソコンCPUの牙城に空けた穴は大きいとは言えなかったようだ。
AMD にとってK6シリーズは一つの転換点であったわけだが、更にその後K7として開発が進められて 1998年頃発表されたAthlonの登場は、長きにわたるx86互換CPUの歴史における大転換点と位置付けてよかろう。図6から分かるように、Athlon は Intel のミドルレンジCPUを完全に凌駕する性能を手に入れている。
これまでの互換CPUの歴史では、 Intel プラットフォームの後追い形式でリリースされてきたのに対し、AMD は(かつての Nexgen の気風が生きているのか)独自プラットフォームという路線を取ることによって、Intel 得意の新プラットフォームへ逃げるという戦略を封じると共に、時間軸上での遅れを無くしてしまったわけである。かくして AMD は Intel ミドルレンジCPU勢を追い越し、価格支配権争いの本丸であるハイエンドCPUの土俵に上がったわけである。
AthlonによるAMDの攻勢は、 Slot1 vs SlotA、Socket 370/423/478 vs Socket A、とIntelのプラットフォーム変更に惑わされずに続き、その過程では1GHz先駆け競争なども演じられた。そしてその攻勢は2004年現在もなお続いているとともに、AMDは バリューCPU向けに Duron を繰り出し、Intel 同様に高価格〜低価格帯までをラインナップして高収益半導体メーカーに脱皮するに至っている。
更に現在至って AMD は、 x86の64bit拡張を備えた SledgeHammer/ClawHammer , すなわち Opteron/Athlon 64(FX) をラインナップし、Intel のハイエンドCPUをリードしている感すらある。かつて WINTEL とまで言われた Microsoft と Intel の蜜月関係にも、64bit拡張において亀裂を入れるに至ったとも聞き及んでいる。 AMD は、Intel プラットフォームの後追い戦略から脱却することによって新天地を切り拓き、高い競争力を身につけたわけである
さて、大衆の注目の眼差しは Athlon勢 vs Pentium4勢の行方に熱く注がれているようである。ライバルメーカのミドルレンジCPUに対する半年以上の遅れは命取りになることもある。それを Intel が身をもって体験することになるのか、AMD が再び体験するのかについては、筆者としても興味深く見守っている。
残念ながら、筆者はCPUの能力を正確に測るスキルを持ち合わせてはいない。しかし、インターネット各地で見受けられる棒グラフ対決記事を眺めると、現状ではドングリの背比べであるようだ。ベンチマークの結果によっては10%程度勝ったり負けたりであり、対数グラフに載せてしまうとその程度の差はないに等しい(因みに、図6は AthlonのモデルナンバーとPentium4のクロック数が同程度としてプロットしてある)。
このレースにいずれが勝っているにしても、現在は32bit終焉フェーズ(または64bit試行フェーズ前半)である。CPUの能力がパソコンにとって必ずしもクリティカルな要素でない現在においては、レースは大きく動かないだろう。大きく動くのは、64bit試行フェーズ後半, 32bit終焉フェーズがいよいよ潰える頃だと筆者は観測している。この頃にライバル社を凌駕する性能のCPUをリリースできるかどうかが勝負の勘所となりそうだ。
64bit試行フェーズの終盤では雑誌などで64bit煽り記事が花盛りになるだろう。そして革命フェーズ直前で「64bitの能力を引き出すためには対応のドライバやソフトが出揃うまで・・・云々」という言い訳を聞くことになりそうなことも想像に難くない。
しかしAMD は 64bit 拡張という点において現時点では Intel の Pentium4勢をリードしており、競争を白熱させている。現在64bitを謳うCPUは、真の64bit時代を迎える頃には使いものにならない可能性が高いとは思うが、どうせまともに使えない 64bit 試行フェーズのPCに大枚はたくことになるくらいなら、試行フェーズで64bit の雰囲気だけ味わう目的で AMD の CPUを選択しておいて革命フェーズを虎視眈々と待つというのはありかもしれない。(27. May, 2004)
PC処世術トップページへ
賞味期限対決 AMD vs Intel 2004夏の陣
Socket 939 の新AMD Athlon 64が市場に出回り、パソコンCPU市場におけるIntelに対して AMD は攻勢に出ているようだ。まだどちらも決定打を持っているとはいえない状況にあり、即座にCPUシェアで AMD が Intel を逆転することはない状況にあるのだが、パソコン向けハイエンドCPUでAMD がアドバンテージを奪っているように見える現状は実に興味深い。
前稿では、これまでAMDがIntelの後を追いながら、Athlonに至ってIntelミドルレンジCPUを凌駕してきた経緯について書いた。ここでは、現在の両者がどの程度の差を持っているのかを、賞味期限とコストパフォーマンスという観点で比較・評論してみたい。
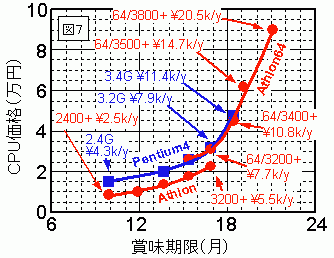 まず、図7は横軸にCPUの賞味期限(Celeron1.7GHzをローエンド基準とした)をとり、縦軸に単体価格をプロットしてみた。これは図2と同様の整理の手法である。そして、各点にはCPUの命数(Celeron400MHzを下限基準)から求めたコストパフォーマンス値(1年あたりコスト)を併記してある。なお、対象としたCPUは Intel のPentium4と AMD のAthlon/Athlon64 である。
まず、図7は横軸にCPUの賞味期限(Celeron1.7GHzをローエンド基準とした)をとり、縦軸に単体価格をプロットしてみた。これは図2と同様の整理の手法である。そして、各点にはCPUの命数(Celeron400MHzを下限基準)から求めたコストパフォーマンス値(1年あたりコスト)を併記してある。なお、対象としたCPUは Intel のPentium4と AMD のAthlon/Athlon64 である。
グラフにしてはっきり分かるのは、AMD は Athlon64をPentium4 の対抗馬として当てているということだ。 Athlon(SocketA)はそれより下のバリューPC向けという位置付けらしい。
現在 Intel がパソコン向けにリリースしているCPUとして最も長い賞味期限を持っているのは3.4GHz の Pentium4 で、およそ18ヶ月(1.5年)である。これに対して AMD の最長賞味期限CPUは Athlon64/3800+ で、およそ21ヶ月の賞味期限を持っている。ハイエンド同士を比較してもその差はおよそ3ヶ月であり、今回のAMDの攻勢は 決定的なアドバンテージを奪ったとは言えないのだ。
決定的なアドバンテージと言えるために、「ミドルレンジCPUがライバルのハイエンドに対して半年」程度の差が必要である、と筆者は観測している。もし Intel がそれほどまでの差をつけられると、完全にIntel は AMD の後追いベンダに堕ちることになり、かつての互換CPUメーカのような立場に立たされることになる。
ただ、それほどまでの差でなくとも Intel にとっては厳しい一撃がある。それは、AMDのミドルレンジ〜バリュー向けCPUが Intel のハイエンドと並びつつあることだ。この構図は、Intel の Celeron vs AMD の K6の構図と非常によく似ているが、立場が逆転している。Intel は現在の Pentium4 3.xGHz をセレロン化して価格競争する必要に迫られているようにも見える。2004年夏、価格支配権は AMD に移りつつあるようである。
Intel CPU は高価格故のブランド力があるかのような意見も世間にはあるが、残念ながらCPU業界にブランドの神通力はない。過去のIntel CPU(例えば486) もブランドモノなのかもしれないが、それは現在においてCPUとして決して高い価値を持ち得ない。価格支配権はハイエンドCPUベンダに与えられるのだ。
実は、お気づきの方も居られるかもしれないが,本ページの図1を見ると2003年頃からCPUの進化が鈍化しており、4.27db/yearの直線を下回っていることが分かる。その結果、図2のように2004年には販売されているCPUの賞味期限が短めになっている。この先、直線に乗る点をプロットしていくのがAMDになるのかどうか、非常に興味深いところである。
さて、では筆者のようなパソコン小市民はどちらを選択したらよいのだろうか?2004年6月現在の状態では、ハイエンドでは賞味期限が長く,ローエンドではコストの低いAMDに軍配を上げざるを得ない。Athlon64 も、64bitの雰囲気を見られるというオマケが付いている。
Intel は最近、プロセッサナンバーとかで難局を乗り切ろうとしているようだが、筆者はこの戦略に際してまたデジャブー体験をした気持ちになった。かつて互換CPUベンダがクロックで勝てないために P-Rating などを持ち出していたし、現在の AMD のモデルナンバもそうなのだが,旗色の悪いときに出現する数字のような感触がある。Intel はデュアル・コアCPUとAMD互換64bit戦略を進めるようだが、将来出現させるCPUがどうなるか分かっている筈のIntelからこのような(パフォーマンスとも関係ない)数字が出てくると、なんとなく行く末が案じられてしまったりする。
なお、筆者は現在 Pentium4 ユーザーであるのだが、あと3年と数ヶ月で寿命を迎える予定である。現在リリースされた Socket939 CPUの賞味期限は長くて 21ヶ月, 命数は4.4年ほどであり、おそらく筆者が CPU周りに限界を感じた頃に、Athlon64/3800+クラスのCPUとマザー一式を半ばジャンクとして有り難く入手させていただくことになるのかもしれない。その頃は,64bit時代は幕を開けて革命を待つ時期である…。(7. Jun, 2004)
追伸:前稿で書き忘れたが、最終的に筆者の以前の主力PCにはジャンクとして入手した K6-IIIが乗っていた。
PC処世術トップページへ
・ 下記のコンテンツは,ファイルサイズ過多のため「プロセッサナンバ編」へ分割・移動いたしました。
CPUのプロセッサ・ナンバの意図を探る(30. Oct, 2004)
モデルナンバとクロック周波数 - AMD編(18.Jan, 2005)
Sempron と GeodeNX のモデルナンバ(6.Feb, 2005)
[オマケ] Socket754 の Sempronシリーズ(27.Feb, 2005)
PC処世術トップページへ
当サイトにある記事の著作権は M.Abe に属します。
なお、当サイトの記事の転載はご遠慮ください。
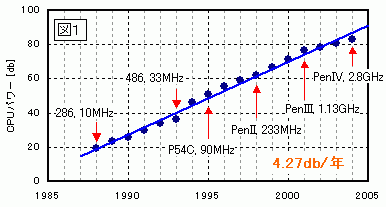 CPUは進化に伴って同一クロックでも処理能力は異なる。そこでCPUの種類に応じて係数を算定し、この係数とクロック周波数との積を以ってCPUパワーとした。この係数は筆者の経験に基づく値を用いている。参考までに値を書くと、V30を0.5, 386DXは1.0, 486DXは2.0, Pentiumは4.0, PentiumIIIで6.0, Pentium4で5.0という具合で、色々異論はあるとは思うが実勢から大きく逸脱してはいないだろう。こうして算出したCPUパワーのlog(対数)をとり、20を掛けてグラフにしたのが図1である(つまり、縦軸はdb[デシベル]表示である)。CPUには、各年代において標準的かややハイスペックであったものを各年代の代表とした。
CPUは進化に伴って同一クロックでも処理能力は異なる。そこでCPUの種類に応じて係数を算定し、この係数とクロック周波数との積を以ってCPUパワーとした。この係数は筆者の経験に基づく値を用いている。参考までに値を書くと、V30を0.5, 386DXは1.0, 486DXは2.0, Pentiumは4.0, PentiumIIIで6.0, Pentium4で5.0という具合で、色々異論はあるとは思うが実勢から大きく逸脱してはいないだろう。こうして算出したCPUパワーのlog(対数)をとり、20を掛けてグラフにしたのが図1である(つまり、縦軸はdb[デシベル]表示である)。CPUには、各年代において標準的かややハイスペックであったものを各年代の代表とした。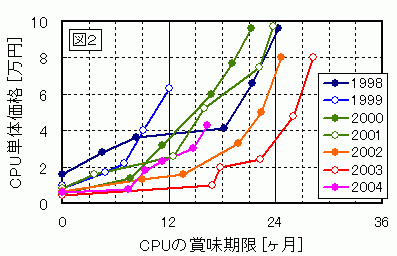 図2を見ると、年によって販売されているCPUの賞味期限は12ヶ月〜28ヶ月と、倍以上開きがあることがわかる。そして、同じ価格であっても年によって賞味期限は異なる。
図2を見ると、年によって販売されているCPUの賞味期限は12ヶ月〜28ヶ月と、倍以上開きがあることがわかる。そして、同じ価格であっても年によって賞味期限は異なる。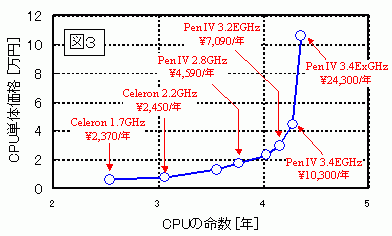 そこで、価格と命数の関係を整理してみたのが図3である。我慢の限界基準はCeleron 400MHzとして命数を計っている(係数は、筆者の見積もり値。正しいかどうかは保証しない。)。なお価格は、Pentium4については新たに発表されたIntelの価格を元に1ドル105円で計算してあり、Celeronについては実勢価格で示してある。
そこで、価格と命数の関係を整理してみたのが図3である。我慢の限界基準はCeleron 400MHzとして命数を計っている(係数は、筆者の見積もり値。正しいかどうかは保証しない。)。なお価格は、Pentium4については新たに発表されたIntelの価格を元に1ドル105円で計算してあり、Celeronについては実勢価格で示してある。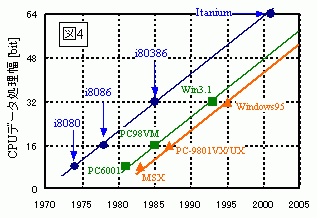 しかし、“xx bit時代”というのは、CPUのリリースと同時には始まらない。過去の例では、それより前のCPUの時代が黄金期を迎え、更にハードウェアがソフトウェアに対してややリッチになる時代を経て次の時代へと遷移している。そしてこの期間は、概して次の時代のCPUは「素人には必要のないハード」という扱いを受けていたように思う。
しかし、“xx bit時代”というのは、CPUのリリースと同時には始まらない。過去の例では、それより前のCPUの時代が黄金期を迎え、更にハードウェアがソフトウェアに対してややリッチになる時代を経て次の時代へと遷移している。そしてこの期間は、概して次の時代のCPUは「素人には必要のないハード」という扱いを受けていたように思う。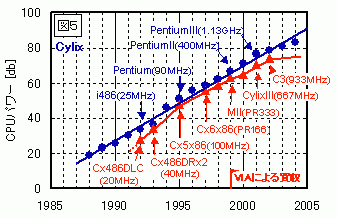 この Cx486DLC/SLC から始まる Cylix のx86互換CPUの歩みを、図1の Intel の歩みに重ねてみたのが図5である。なお、初稿で書いた通り、IntelのCPUについてはミドルレンジ(またはややハイエンド)なCPUがプロットされているのに対して、Cylix のものは各年初頭〜前半において市場に出回っていたもので最高のものをプロットしているので注意されたい。
この Cx486DLC/SLC から始まる Cylix のx86互換CPUの歩みを、図1の Intel の歩みに重ねてみたのが図5である。なお、初稿で書いた通り、IntelのCPUについてはミドルレンジ(またはややハイエンド)なCPUがプロットされているのに対して、Cylix のものは各年初頭〜前半において市場に出回っていたもので最高のものをプロットしているので注意されたい。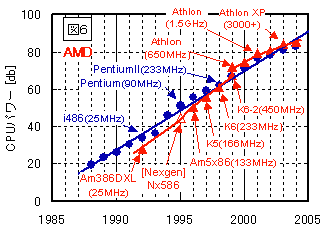 時代は移って 1995年,
時代は移って 1995年, 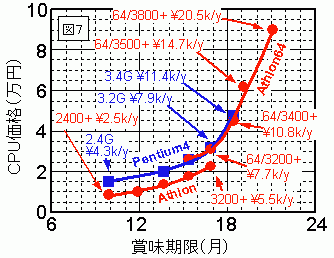 まず、図7は横軸にCPUの賞味期限(Celeron1.7GHzをローエンド基準とした)をとり、縦軸に単体価格をプロットしてみた。これは図2と同様の整理の手法である。そして、各点にはCPUの命数(Celeron400MHzを下限基準)から求めたコストパフォーマンス値(1年あたりコスト)を併記してある。なお、対象としたCPUは Intel のPentium4と AMD のAthlon/Athlon64 である。
まず、図7は横軸にCPUの賞味期限(Celeron1.7GHzをローエンド基準とした)をとり、縦軸に単体価格をプロットしてみた。これは図2と同様の整理の手法である。そして、各点にはCPUの命数(Celeron400MHzを下限基準)から求めたコストパフォーマンス値(1年あたりコスト)を併記してある。なお、対象としたCPUは Intel のPentium4と AMD のAthlon/Athlon64 である。