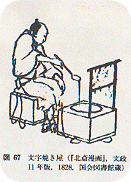 でね、その皮に餡子をつめたのが「銀つば」それが江戸に移って「金つば」
となったり、その皮を簡単な文字や動物形に焼いて楽しむ「文字焼」
というものにもなった。北斎が描いてんですよ、文字焼き屋。ふむふむ。
その文字焼が明治になって、駄菓子さんの店先で子供たちが自由に
焼いて食べるという(この話しは皆さんもご存知かと(笑))、こちら
は「もんじゃ」のルーツ。
でね、その皮に餡子をつめたのが「銀つば」それが江戸に移って「金つば」
となったり、その皮を簡単な文字や動物形に焼いて楽しむ「文字焼」
というものにもなった。北斎が描いてんですよ、文字焼き屋。ふむふむ。
その文字焼が明治になって、駄菓子さんの店先で子供たちが自由に
焼いて食べるという(この話しは皆さんもご存知かと(笑))、こちら
は「もんじゃ」のルーツ。あの手の調理法の元祖は「麩の焼き」という 食べ物だそーです。聞いたことありますか?。 小麦粉を溶いたものを最中の皮のように薄く焼き、それに味噌をぬった もので、創始はあの千利休!(笑)。茶菓子だったり、仏事用 だったりの流れを経て、この食べ物は、江戸時代の色々な文献にも残って、 結構食べられていたようです。
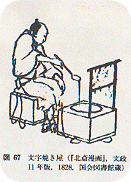 でね、その皮に餡子をつめたのが「銀つば」それが江戸に移って「金つば」
となったり、その皮を簡単な文字や動物形に焼いて楽しむ「文字焼」
というものにもなった。北斎が描いてんですよ、文字焼き屋。ふむふむ。
その文字焼が明治になって、駄菓子さんの店先で子供たちが自由に
焼いて食べるという(この話しは皆さんもご存知かと(笑))、こちら
は「もんじゃ」のルーツ。
でね、その皮に餡子をつめたのが「銀つば」それが江戸に移って「金つば」
となったり、その皮を簡単な文字や動物形に焼いて楽しむ「文字焼」
というものにもなった。北斎が描いてんですよ、文字焼き屋。ふむふむ。
その文字焼が明治になって、駄菓子さんの店先で子供たちが自由に
焼いて食べるという(この話しは皆さんもご存知かと(笑))、こちら
は「もんじゃ」のルーツ。
そこからお好み焼きに発展する大事件、それは関東大震災でした。 みんな食べ物に困ったわけですよ、で、簡単な補食として、もんじゃ の材料配合をもっとリッチにし、「どんどん焼き」「お好み焼き」と 変形していく…。なんと事始めは花柳界のお座敷でであったらしい(笑)。 つまり、お好み焼きよりもんじゃが古いんですよー。ちとびっくり。
でもね、関西では、もんじゃではなく、一銭洋食がルーツで関西が
初めだっていうよね、どっちが元なんだろか。
一銭洋食ともんじゃの関係、ご存知の方いらっしゃいますか〜?
とあるHPによると、一銭洋食のルーツがもんじゃと書いてありましたが。
そもそも、関東では一銭洋食なんて知ってる人、あまりいないかも。
興味ないですか?
(付録:『一銭洋食実食記』へ)
(関連HP:伝説のもんじゃ王国「月島」のHPへ<GO!>・
なぞの「一銭洋食」のHPへ<GO!>)
| TOP | MEMU | MAP | TICKET |