|
|
|
さとうきびと黒糖
―波照間と沖縄の製糖業のすがた―
 波照間の風景でもっとも印象深いのは、島一面に広がるサトウキビ畑でしょう。太陽の日差しをはね返すように背の高さを競い合うキビが道沿いに続き、春には刈入れで島中が忙しげな雰囲気になります。製糖工場の煙突からは甘い香りが漂い、蒸気のボ〜ッという音が鳴り響きます。この時期には島の売店や石垣の空港などに波照間産の黒糖が並びます。 波照間の風景でもっとも印象深いのは、島一面に広がるサトウキビ畑でしょう。太陽の日差しをはね返すように背の高さを競い合うキビが道沿いに続き、春には刈入れで島中が忙しげな雰囲気になります。製糖工場の煙突からは甘い香りが漂い、蒸気のボ〜ッという音が鳴り響きます。この時期には島の売店や石垣の空港などに波照間産の黒糖が並びます。
サトウキビ サトウキビの正式名称は甘蔗(「かんしゃ」、俗には「かんしょ」)。トウモロコシに似たイネ科の多年性植物で、高温多湿を好み、年間平均気温が20度以上の土地でよく育ちます。ニューギニアが原産でインドを経て世界に広まったと推測されています。世界最大の生産国はブラジルで、その他熱帯、亜熱帯地域で栽培されています。 日本には奈良時代、鑑真が大陸からその製法を伝えたと言われ、17世紀から四国や紀伊半島など温暖な地域で栽培が始まりました。しかし開国によるイギリス資本の流入でそのほとんどは駆逐され、現在では沖縄・鹿児島で栽培されています。なお、砂糖の主要な原料としては他に冷涼な地域で育つ「てん菜」があり、これは北海道で栽培されています。 八重山の製糖の歴史 沖縄で本格的な製糖が始まったのは1629年、儀間真常が福州から持ち帰った品種からといわれています。ひろく八重山まで伝播し、1646年には琉球王朝の専売品となり財源を潤しました。しかし、供給過剰による価格低下の恐れや、キビ作が広がるあまり食糧作物の自給がピンチとなったことから1697年、「甘蔗作付制限・禁止令」が出されます。これにより八重山・宮古では神事用を除き栽培が禁止されました。禁止令は廃藩置県後も続き、1881年ようやく撤廃されました。その後は殖産興業の一環として奨励され、第一次大戦の頃には一大産業となりました。その後世界恐慌や沖縄戦で低迷するものの1950年代から復興、50年代末から60年代初めにかけ各地に製糖工場が建設され、現在基幹作物となっています。(八重山では農業粗生産額の30%を占め、1位) 波照間の製糖 波照間では1914年、石垣からの移植により甘蔗栽培が始まりました。小さな精糖小屋で牛を動力に細々と続けられ、数回の中断期間がありました。戦後50年代半ばになると、戦前からの砂糖組(サッターグミ)を引き継ぐ美里製糖組合(南・北)に加え、前原(前)、名石、冨嘉と全集落に製糖組合ができ、それぞれでエンジンと圧搾機による製糖工場が運営されました。いずれも一日15〜30t程度の小規模工場でした。
「分蜜糖」と「含蜜糖」 さとうきびから作られる砂糖は「甘蔗糖」と呼ばれ、「分蜜糖」と「含蜜糖」の2種類があります。「分蜜糖」は製糖の最後の段階で「(廃)糖蜜」を分離したもので黄色〜茶褐色をしており、白糖やグラニュー糖など「精製糖」の「原料糖(粗糖)」として使われます。一方「含蜜糖」はその名の通り糖蜜を分離させません。これはいわゆる「黒糖」です。沖縄の製糖業は大規模化に伴ない「分蜜糖」の製造が主流となっています。「含蜜糖」は規模の小さい離島で生産されており、沖縄で作られる甘蔗糖製造量の6,7%程度に過ぎません。波照間では「含蜜糖」つまり黒糖が作られています。
きびの植付け さとうきびの植付けには「夏植え」「春植え」「株出し」の3種類があります。夏植え、春植えは「挿し木植え」という方法で、キビの枝を挿すことで栽培します。夏植えは1年半、春植えは1年かけて育て、いずれも春先に収穫します。株出しは収穫の後の株から発芽させ育てる方法です。ただし、地力の低下を避けるため、3年ほど続けた後は他の農作物(紅イモなど)を植える等して休ませたのち、夏に挿し木植えします。夏植え、春植え、株出しの比率は波照間ではおよそ6:1:3となっています。 収穫 きびは気温が低下することで、成長が緩やかになり茎中の糖分が増加します。収穫は12月、製糖工場の操業開始にあわせて始まり、操業の終わる翌4月まで続きます。刈り取った後放置しておくと糖分が変化して品質を低下させるので、製糖工場の操業状態に合わせ収穫後なるべく早く製糖できる様計画的に収穫します。波照間を含め大部分の地域で人力による刈入れが行われています。「倒し鍬」で根元から刈り倒し、「脱葉鎌」で梢頭部(糖度の低い頂上の部分)を切りとり、更に葉や根など茎以外の全て取り除き、茎を束ねて搬出します。 機械導入は経営規模が小さく、また収穫時期に雨が多いことから困難です。機械収穫だと、梢頭部をきちんと取り除けず精糖の品質が下がるという技術的な側面での難点もあります。なお石垣島では「ハーベスタ」という機械が導入されています。波照間でも一部の畑では導入されているようです。
製糖工場に搬入されたさとうきびは、品質検査と重量測定が行われます。品質の良し悪しは、さとうきびを搾った汁 (搾汁液) の中からとれる砂糖の割合や製造のし易さで決まります。具体的な調査項目は(1)ブリックス、(2)糖度、(3)還元糖分(砂糖が分解された成分。少ない方が良い)(4)繊維分(13%程度。低い方が良い)です。 「ブリックス」と「糖度」 「ブリックス」は搾汁液の中に溶けていて、 乾燥させると固まる物質(可溶性固形分)の割合を指し、糖類の他に灰分やカルシウム等の栄養成分も含まれています。さとうきびのブリックスは20%程度です(ちなみにミカンは10%程度)。きびのブリックスの80〜90%が砂糖分で、この砂糖分の割合が「糖度」です。
さとうきびは品質検査の後細かく砕かれ、圧搾機で絞りとられて「圧搾汁」と「バガス」に分離されます。「バガス」(bagasse)とはさとうきびの絞りかすを指し、さとうきびの重量の25%位になります。製糖工場のボイラーの燃料として使われ、製糖工場で必要な電力を十分賄えるそうです。
波照間製糖工場の社員は事務系9人、技術系15人。毎年12月に県内のトップを切って操業が開始され、翌4月まで約100日間操業、その間は、100人(大部分が島民)が交代で24時間体制で働いています。出荷された黒糖はそのまま食べられたり、菓子の色付け用として加工して利用されます。(榮太楼飴などにも納入されているそうです。)島内の共同売店でもかけら状のものと粉末状のものが袋詰めで売られています。
きび栽培を営む農家10〜15戸ほどで組となっていて、島全体で17組が組織、持ちまわりで組長が選ばれます。製糖工場から操業計画にあわせて組長に指示が出て、組員のキビ畑を糖度が一定以上に達した所から収穫していきます。収穫作業は基本的に組全員であたり、この際、労働時間に応じて賃金が割り当てられます。労賃は組長のつけた記録をもとに10日ごとに清算され、工場から各自に支払われます。
整理すると、キビ畑を所有している一家では キビ代−(他の組員に対する刈入れ労賃+諸経費)+(家族個々に支払われる、他の組員の畑での刈入れ労賃) がキビ栽培における収入となります。 この刈入れ賃金は男女、年齢差等によって段階をつけられた時給制になっていて、5分単位で細かく清算されます。これにより、私用により作業を少し抜け出すといった自由がきくようになっています。また、病気や老人の1人暮しといった家庭の事情に応じて作業量を調整したり、休暇中の中高生などが部分参加するといったケースにも不公平なく対応できます。近年では労働力不足により、他の組への応援というケースも発生していますが、この際は基準の賃金に上乗せされた賃金となります。 きび栽培の場合全労働の約半分が人力の収穫作業となるため、労働人員の確保が重要なのですが、このシステムによって島内の労働力を最大限に活用することが出来ます。経営規模の大きい農家や労働力の少なくなった農家(現在農家1戸あたり人数は2.68人)は人員不足を気にせずに済みますし、経営規模の小さい農家は刈入れ賃金によって収入を増加することができます。 他の地域ではいわゆる「援農隊」のように他府県からの刈入れ応援を受け入れているところもありますが、波照間でそのような話が聞かれないのはこのシステムによるものなのでしょう。1973年には「朝日農業賞」を受賞しています。
沖縄の農業を支える基幹作物として栽培されてきたサトウキビも、近年では厳しい状況に立たされています。政府は砂糖の自給率維持(現在3割)と価格安定のため、「砂糖の価格安定等に関する法律(糖安法)」や「甘味資源特別措置法」によって保護し、国産品に対しては価格支持、輸入品に対しては関税をかけて価格を調整してきました。
きび価格 さとうきび代として農家に支払われる金額は「甘味資源特別措置法」に基づいて政府により毎年決められます。沖縄「復帰」以降、価格は品質にかかわらず一律であり、また上昇してきましたが、84年以降は据置き、89年以降は引下げられる年も出てきました。また、94年以降はきびの糖度によって価格差をつける「品質取引」が導入されました。現在の農家手取り価格は、標準的な品質の場合1トンあたり20430円となっています。 砂糖の価格 砂糖の原料として使われる「分蜜糖」は「砂糖の価格安定等に関する法律(糖安法)」により政府の決めた価格で農畜産業振興事業団によって製糖工場から買い上げられます。
一方波照間で生産されている「含蜜糖」、すなわち黒糖は糖安法の対象外で自由競争下にあります。「沖縄振興開発特別措置法」により製造コストと販売価格の差額が「価格差補給金」として補償されています。含蜜糖工場が離島に集中(波照間の他、伊平屋島、粟国島、多良間島、小浜島、西表島、与那国島の七工場)しているため、離島経済の振興の意味合いで出されており、毎年11億円が国・県から支払われます。ただし、今のところ2001年までの時限立法となっています。こちらの内外の価格差は2.5倍、もし関税がゼロになると4倍と、厳しい状況です。
70年代に入った頃からキビ栽培は高齢化・過疎化により労働力が不足し始めました。これに対し八重山では復帰前後、台湾や韓国から刈入れ労働者を迎えるという試みもなされましたが定着せずに終わりました。
その結果製糖工場では原料となるきびの不足により経営が厳しくなっています。沖縄本島では製糖会社の統廃合が進み現在では2社体制ですが、なお経営は悪化、赤字を抱えている状況です。 労働力不足への対策としては、株出しの増加により植付の労働力を減らすという方法がとられています。しかし地力の低下などの問題もあり、根本的な解決策ではありません。そして何よりもきび栽培にかかる労働力の半分は収穫作業が占めています。機械化は70年代より試みられ、石垣島や沖縄本島で導入されています。しかし、コストと品質の面で困難を伴うためなかなか普及していません。沖縄本島では法人化による大規模化・機械化の試みが始まりました。省力化・低コスト化は現在のキビ産業の最大の課題となっています。
波照間の黒糖は沖縄一の品質だといわれており、他の含蜜糖工場が軒並み在庫を抱え苦境にある中で、1999年には逆に品不足状態となっています。1997年度の実績で見ると単位当りの収穫量は県平均の1.26倍、一戸あたり収穫面積は1.7倍ときび栽培の方も比較的よい状況にはあるようです。
来間泰男 1982『波照間島の農業とユイの意義』沖縄国際大学南島文化研究所編「波照間島調査報告書」所収
山根嶽雄 1963 「甘蔗糖製造法」 光琳書院
沖縄タイムス関連各記事
|
|
|
|
| HONDA,So 1998-2000 | 御感想はこちらへ |

 含蜜糖の製糖過程
含蜜糖の製糖過程
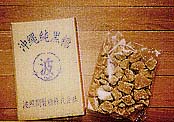 波照間の黒糖は高品質で知られています。これを支えているのが、「ユイ(ユイマール)」の現代版ともいうべき、他の地域にはない独特の刈入れ組織です。「ユイ」とは労働交換のシステムで、地域・血縁共同体の中でお金ではなく労働力を貸し借りするものです。かつては沖縄にかぎらず日本中に存在しましたが、経済社会の発展した今ではその相互扶助の精神はともかくとして実際のシステムとしてはほとんど残っていません。
波照間の黒糖は高品質で知られています。これを支えているのが、「ユイ(ユイマール)」の現代版ともいうべき、他の地域にはない独特の刈入れ組織です。「ユイ」とは労働交換のシステムで、地域・血縁共同体の中でお金ではなく労働力を貸し借りするものです。かつては沖縄にかぎらず日本中に存在しましたが、経済社会の発展した今ではその相互扶助の精神はともかくとして実際のシステムとしてはほとんど残っていません。

 波照間の場合
波照間の場合