PC処世術 - 求める機能とパソコンの選定
パソコンの進化と機能の進化
パソコンの進化に伴って、「できるようになったこと」あるいは「常識になったこと」は沢山ある。例えば音楽をパソコンに記録しておいて聞くとか、あるいは動画を再生するなどといったことは、パソコンおよびその周辺機器の進化を抜きにしては有り得なかった事である。
パソコンにやらせたいことは数多くあり、現在でもその全てが実現された訳ではない。また、実現が可能であってもそれがコスト的に見合わない場合もあるし、「辛うじて不可能ではなくなった」という程度のレベルにPCを増強するために大変な投資を迫られることもある。こんな場合の投資は往々にして焦げ付き易い。 このように、パソコンに与える役目によってパソコンライフが幸せになるかどうかの岐路を通過することがある。ここでは、パソコンの進化と共に「どんな事が」可能になってきたかをおさらいし、パソコンにどんな役割を与えることが幸せなパソコンライフにとって重要かを考察するための,基礎事項をまず説明しておきたい。
筆者の思うところによると、パソコンの機能は,パソコンの性能の向上とリンクして「不可」「可能」「実用」「常識」「空気」の5つの状態に分けられる。
「不可」とは、パソコンでできるようになって欲しい機能でありながら、パソコンの処理能力不足やソフトウェアの未整備などによって全く不可能な状態である。ある機能が「不可」の状態にあるときには、その機能はある種のSF的な捉え方もされたりする。この「不可」の状態にある機能を、次のレベルである「可能」の状態に遷移させるには、ハードウェア/ソフトウェアの進化が必要であり、相当のテクノロジーが要求される。そのキーテクノロジの開発は大いにビジネスチャンスに成り得るところでもある。Microsoftが現在の勢力を得ている源流も, かつて8bit時代に不可→可能の遷移をシコシコ実行して練磨したところにあるのだろう。
「可能」とは、パソコンの処理能力の向上などによって、かつては不可能とされた機能が可能になった状態であり、「不可能ではない」というレベルである。この状態の機能に対しては,物欲煽動が始まるものの特殊ハードウェアが必要であったりして投資額も嵩みがちである。そしてこの状態にある機能は、その使いこなしに対してはそれなりのスキルが要求されるが、世間には使いこなしに対して情報が不足している。このため、ある機能についてユーザーは相当の知識とスキルとを手に入れることができたり、あるいはビジネスチャンスを掴めることもある。ただし、あくまでも消費者としての立場でこの「可能」状態の機能を使おうとした場合には、その投資は焦げ付くことになる。筆者のようなズブの素人は手を出さないほうが良いのかもしれない。
「実用」状態は、「可能」レベルの状態より更にPCの能力が向上し、まともに使えるようになった状態である。実用レベルに達すると、巷でもその使用方法に関する情報として「xx完全マスター」のようなムックの類が溢れ、パソコンもxx対応等と言っていよいよ宣伝が盛んになる。一部はソフトウェアのみでこの機能が実現できるようにはなるものの、専用ハードウェアが必要なことも多く、投資額はそれなりに嵩む。この実用状態にある機能を使いたいがためにパソコンを購入する、といった場面も散見される。投資額に見合った成果が得られるかどうかは微妙であるが、この状態の機能を使わないパソコンの存在意義があるのかどうかも微妙である。なお、入門本の類が溢れることからも分かるように、取扱いにはそれなりのスキルが要求される。
「常識」レベルの機能とは、PCの能力ががその機能を実現することに対して相当の余裕を持ち、既にその機能がパソコンに備わっていることが常識的となる状態の機能である。機能がこの状態に達すると、パソコンでこの機能を使えないという状態のほうが特殊となる。この状態では、外付けの専用ハードウェアなどは要求されることが稀になり、必要なハードウェアがパソコンに内蔵されたり、あるいはソフトウェアで実行可能になる。勿論、この機能が要求するコストは低くなり、あるいはタダで手に入ったりする。巷には相変わらず入門本の類が溢れるが、近くの人に聞く方が早かったりする。この状態になった機能は、コストも大してかからず、情報も多く、またソフトウェアの安定度も高くなっているので、パソコンをこの機能のために使うのであれば生産性が非常に高い。但し、同じ機能を実現できる専用機が出現したりするので、パソコンを利用するのが最も良いかどうかは微妙である。なお、「実用」状態から「常識」状態に遷移するためには、パソコンの能力の他に需要の大きさも必要であることが多い(特にハードウェアを要求する場合)。
「空気」とは一体どのような状態だろうか。それは、既に当たり前すぎて意識することがなくなった機能である。極端な例では、パソコンにモニタやキーボードで入出力ができるとか、時計が内蔵されているとか、そういうことである。このレベルになると、この機能がないとパソコンとして成立しないというレベルであり、ユーザーはもはやその存在や機能を意識する必要がない。このレベルに達すると、その機能が要求するコストは著しく低くなる。しかし時計のためにパソコンを購入するなどと言うのがナンセンスなように、この機能のためにパソコンを導入することは全くコストに見合わない。
さて、ここではパソコンで可能になる機能の状態について述べたが、いささか抽象的だったかもしれない。次回は、具体例を追いながらパソコンに負わせるべき役割について考えてみたい。(6. Apr, 2004)
機能の進化 8bit〜16bit時代編
まずパソコン黎明期である8bit時代については、筆者にとっても記憶朧げなる時代であり、歴史上の事実として書籍などから学んだことをベースに話を進める。この時代においては、文字を入出力する(つまりキーボードとモニタ)といったパソコンのプリミティブな機能も当初(パソコンと言うよりマイコン時代だが)は不可状態にあったわけだが、「パソコン」というジャンルの登場による8bit時代の革命フェーズの到来以来、急速に実用レベルに達した。(注:各時代のフェーズについてはこちら参照)
この頃のパソコンのミッションは、主にプログラムを順番どおり処理することであったと思う。したがって、ソフトウェアに求められていたことはプログラミング環境を提供するという機能であった。マイクロソフトが成長のきっかけを掴んだのも、この機能を可能から実用レベルに押し上げたことに端を発する。8bit機はプログラミングに触れるとかパソコンとはどんなものかを理解するという目的に対しては、投資に対して十分な見返りのあるマシンだったのではないだろうか。
この時代のパソコンにビジネス・アプリケーションを運用させるのは、不可能ではなかったが難しかった。つまり可能レベルであった。日本においては日本語表示やカナ漢字変換が要求されるため、8ビット機はビジネスマシンとしては成功したとはあまり言えない。ビジネスアプリがどうしても必要だった人やソフトウェア開発者にとっては実りあるところだったかも知れないが、一般消費者にとっては実用的とは言えなかったと思う。その一方で簡単なゲームは実用レベルに達していたので、8bit機はゲームマシンとして花を開いたようだ。
16ビットの時代はどうだろうか。まず 16bit試行フェーズから革命フェーズ(286機が登場し、PC-9801の16色表示が常識になった頃)にかけて、ビジネスアプリが実用レベルに達した。そして革命フェーズを過ぎて躍進フェーズにさしかかるところで、PCがビジネスアプリを動作させる機械であることは常識となった。16bit機をビジネス・アプリ使用という役割を与えて購入したならば、パソコンはその能力を遺憾なく発揮し、その投資は間違いなかったと納得できたことだろう。因みに、マウスというポインティングデバイスによる入出力が登場し常識化したのも16ビット時代のことだ。
ラップトップPCやノートPCというジャンルも登場し、PCを持ち運ぶという使用スタイルも一般化した。しかしモバイルPCの真価を発揮するはずのプレゼンテーションという機能については「可能」と「実用」の程度の状態でしかなく、パソコンを使ってプレゼンテーションをするためにはそれなりの投資と労力が必要だったはずだ。
16bit時代も終焉フェーズを迎え32bit時代の試行フェーズとラップする頃、世間では頻りとマルチメディアということが叫ばれていた。マルチメディアパソコンを標榜する機種なども登場し、けっこう高価なものであったと思う。これらは画像や音楽や通信を扱うものだと喧伝されたが、残念ながら16bitマシンや試行フェーズ32bitマシンには荷が重かったようだ。
通信については、速度も1200bpsや2400bpsに達し、テキストベースの通信については実用レベルには達していた。所謂パソコン通信というものだ。画像についてはバイナリファイルとしてダウンロードするしかなく、マルチメディアというには貧弱なものであり、常識というレベルには達していなかった。したがって、パソコン通信が文字のやり取りだけの世界であることを理解してパソコンに投資したならば期待通りの性能を発揮したであろうが、マルチメディア的世界を想像したならば、それは失望の種になったことだろう。
音楽については MIDI などが実用レベルに達し、FM音源による演奏は常識レベルには達していたが、音楽を録音・再生するということに関しては辛うじて「可能」なレベルであった。パソコンをMTR(マルチ・トラック・レコーダ)代わりにするという利用法も登場したが、専用ハードが必要だったり当時としては破格の大容量HDDが必要だったりして、大変な投資と労力が要求された。マルチメディアという言葉に乗せられて、音楽の録音再生目的でこの時代のPCを購入したならば、その直後の32bit革命フェーズで高性能・低価格のPCが続々登場し、大枚はたいたPCは不良債権として焦げ付いたか、あるいは骨董PCとして塩漬けになったことだろう。
画像はどうだろうか。16bit革命フェーズ以降、アニメチックな画像(当時はこれをCGと呼んだ)の読み書きは実用段階に達した。アニメーションも可能もしくは実用レベルだった。しかしフルカラー画像の記録・再生はどうだろうか。VGAサイズの画像でもメモリに展開すると900KBに達するのであり、当時のメモリ搭載量や16bitの壁からするとやはり相当荷が重く、せいぜい「可能」レベルであったと言ってよい。フレームメモリなどという専用ハードウェアもあったが高価であった。動画の記録となるとほぼ絶望的で、極めて高価なハードウェアを用意すれば不可能ではなかったが、庶民にとっては不可レベルだったと思う。
また、2004年現在コンピュータ・グラフィクスと呼ばれている3D CGも、16bit時代当時にもパソコンのカタログ写真を飾っていたが我々パソコン小市民には極めて難しいものだった。当時は浮動小数点演算もコプロのエミュレーションに依らねばならず、一枚画像を表示するのも数時間ということもままあった(当時のコプロはそれなりに高価だった)。
この時代にマルチメディアを目的としてPCを購入していたならば、消費者の立場からすれば高価な出来損ないを購入する結果と相成ったわけである。もちろん、期待する機能が当時のパソコンで十分可能な範囲であれば満足はできたわけだが、それはメーカーが標榜する機能とはいささか違ったものだったような気がする。
このように、PCの購入時にどんな役割を期待するかによってパソコンの評価は大きく変わる。したがって、自分の欲する機能が現在のパソコンにとってどのレベルにあるかを購入時に良く見極めることが、幸せなパソコンライフを送るために重要なことのようである。
さて、今回は8〜16bitという過去の事例を取り上げたが、次回は現在の32ビットから64ビット入り口について、期待される機能がどのような状態にあるかを述べてみたい (9.Apr, 2004)
機能の進化 32bit時代〜編
2004年現在、32bit時代終焉フェーズから64bit時代試行フェーズへと差し掛かったところである。まず、既に終焉フェーズを32bit時代を振り返って、どのような機能がどのフェーズで、いかなる状態を迎えてきたかを振り返ってみたい。
筆者の見解ではあるが、32bit時代はマルチメディアの時代であったように思う。まず16bit時代はせいぜい可能レベルであった音楽の録音再生が、32bit試行フェーズにおいてその機能を有する音源ボードが一般化し、HDD容量増大と相俟って、実用レベルに達した。フルカラー画像の表示と保存が実用レベルに達しつつあったのも32bit試行フェーズだ。(一般向け)デジカメの登場もこのフェーズである。また、通信に関しても、GUIライクなパソコン通信が見受けられ、通信もマルチメディアの一翼を担うものとして、その姿にも変化が現れた。
このように、32bit時代はマルチメディアの時代であったと言って良いと思われる。16bitアーキテクチャが持つ64KBの壁を超えたことで、マルチメディアは現実のものとして受け入れられるようになった。ただ、注意しなければならないのは、これらの機能が実用レベルに達したのは32ビット試行フェーズ終盤で登場したWindows 3.x以降、すなわち32bit時代の幕開け以降の話だということだ。32bit時代の幕開け以前の試行フェーズ習作PCは、結局16bitパソコンとして利用されたことを忘れない方が良いかもしれない。
32bit時代において重要な転換ポイントは、再三指摘してきたように革命フェーズの到来であった。まずマウスおよびそれに類するポインティングデバイスが空気化した。そして、革命フェーズを通過した32bitPCにおいては、高解像度・多色表示が常識的になり、フルカラー画像の保存・再生は全く苦がなくなって常識レベルに達した。デジカメのブレイクもこの頃である。
音楽の録音・再生についても実用レベルから常識レベルへと脱皮しつつあり、躍進フェーズにおいて完全に常識化した。CD-ROMからの音楽の吸出しやHDDへの保存も全く苦ではなくなり、MP3などもこの頃ブレイクした。
そして何と言っても 32bit 革命フェーズにおいてインターネットが一般化し、マルチメディアの一翼を担う通信が常識化した。WWW は通信技術だけでなく画像の編集・表示が楽にこなせるようになったことに伴って常識化できた技術である。このように、32bit 時代はマルチメディアが本格的に開花し、実用そして常識化していった時代であったと言ってよいだろう。
さて、ではマルチメディア最後(?)の砦、動画はどうだろうか。16bit終焉フェーズや32bit試行フェーズにおいては、その記録はおろか再生も困難なものであった。低解像度であったり、コマ飛びを覚悟で導入しなければならなず、また動画を記録しておくメディア容量も不足しがちな「可能」状態の機能であったと考えられる。動画については、32bitの革命フェーズを過ぎた頃からコマ飛びせずに再生できるハードウェアが登場したり、あるいはソフトウェアでも再生がぼつぼつ可能になり、実用レベルに達した。
そして躍進フェーズを迎えると、PCの能力の伸びに伴って速度・容量共に動画の再生という機能に対しては十分となったと考えられる。躍進〜終焉フェーズにかけては、メディアとしてDVDが一般化したことと相俟って、動画再生は常識レベルに達したのである。但しDVDの再生が常識レベルになるのに伴って、DVDプレーヤーという専用機も低価格化が進み、果たして動画再生を目的としてPCを導入することがコストに見合ったかどうかは疑問である。勿論、PCは汎用機なのであり、DVD再生専用機として使うのではないのであるが、それだったら旧式激安PCでも良かったのではないかという疑問は拭えない。音楽にせよ動画にせよ、「再生機として使う」というのはPCに与える役割として中途半端なのかもしれない。記録、そして編集ができることがPC特有の能力であるのかもしれない。
では、動画の記録・編集はどうだろうか。32bit試行フェーズにおいては、辛うじて可能というレベルであったと思う。革命フェーズを迎えても、記録できる画像の解像度が低かったり、著しく高価な専用ハードウェアが必要であったりと、実用レベルに達したとは言えず可能レベルに留まった。
躍進フェーズにおいてはPCの性能向上も勿論あったが、
PC自体は32ビット時代の安定期に向かった時代でもあったので、完成PCベンダなどはパソコンの機能に目新しさを加える必要に迫られ、動画記録が宣伝されたりもした。しかしながら、これはパソコンの能力が十分に向上したと言うよりは、ベンダの都合により専用ハードの低価格化が肝になっていた感が否めない。したがって、32bit躍進フェーズは機能面でみると、動画記録の可能→実用レベルへのシフトフェーズであったと考えられる。
では2004年現在、32bit終焉フェーズはどうだろうか。筆者の見立てでは、やはり動画記録と編集ははPCにとって未だ重荷であると思う。未だに動画のエンコードをソフトウェアのみで行うことは余裕とは言えず、また録画中に別作業をストレスなくこなすことにも無理がある。つまり実用レベルから常識レベルへの脱皮が果たせていないと言うことである。現時点で動画の記録・編集を主目的としてPCを導入すると、投資額はそれなりに嵩むがべらぼうではない。そして、そこそこ使えるが、それなりにスキルが要求される状態となる。したがって、宣伝どおりにラクラク録画・編集という状態を想像して動画をPCの役割として設定すると、失望の種になる可能性があることは認識しておく必要がありそうだ。
動画の記録・編集という機能が常識レベルに昇華するには、どうやら64bit時代を待たねばならないようだ。なお、現在既に64bit試行フェーズが始まりつつあるが、未だ64bit時代の幕は開けておらず、32bit機と状況は変わらない。未だ進歩の余地が多分に残る動画の記録・編集という機能に関しては、64bit試行フェーズを以ってしても常識レベルに達するかはどうか怪しい。
さてここで、64bit時代の幕が開け(2008年頃か)て、革命フェーズを向かえる2010年頃、世間の情勢がどうなる予定であったかを見渡してみよう。そういえば、ここ日本では地上波アナログ放送が打ち切りになる予定だったりもする。これは2004年現在からすると4〜6年後の話であり、CPUやHDDの寿命を考えるとPCの更新サイクル1回分くらい先の話ではある。しかしながら、動画に関してはその製作も配信も再生する機械も多くの利権が複雑に絡む問題であるだけに、64ビット革命フェーズの到来時期と、その機能の目玉になるであろう動画配信に関する革命の到来時期の一致は不気味である。2006年には64bit試行OSのリリースが予定されているらしく、動画記録の類は主たる新機能として喧伝されることが予想される。しかしながら、64bit革命フェーズの直前(試行フェーズ)に行ったアナログ投資は水泡に帰す可能性も秘めており、十分に注意したいところだ。
追記: 筆者の観測によると、機能に関しては可能から実用、そして常識化するまでの時間に定数はないようだ。機能に要求される能力と現状PCの能力とを天秤に掛けて、PCに期待する役割を考えることが失敗しないパソコン選びに繋がるようだ。 (14. Apr, 2004)
パソコンに求める機能 - もう一つの観点
これまで、パソコンに求められ,そして実現してきた機能の変遷について、データの質の変遷とそれに対するPCの能力向上という観点で書いてきた。
筆者は、前稿までに紹介した機能を遠目に眺めてみると、パソコンに求める機能を別の観点で整理できることに気付く。パソコンに求められる機能は,その機能のレベルはともかくとして、大別するとどうも次の3つに分けられるのではないだろうか。それは、1.再生・表示, 2.記録・保存, 3.編集・作成の3つである。
再生とか表示というのは、例えば文書ビューワであったり、音楽再生であったり動画再生であったりするもので、受動的な機能である。Webブラウジングなどもこの範疇にあると思われるし、あるいはゲームなども他人が作ったものを再生して遊ぶという意味で、ここに分類されるかもしれない。
これらの機能は、パソコンに求められる機能としては最も負荷が軽い類であろうと思われる。この再生や表示だけならば、新たに発生するデータもなく容量の不足も置きにくいし、データの質や量に応じた処理能力(転送能力)さえ持っていればそれで済む。
そして、再生・表示だけならば、ユーザーにとっての負荷も軽く、使いこなしが容易であり、パソコンの機能として宣伝し易い。それだけに、本当にパソコンで行うことが適当かどうかは微妙である。大抵の場合、同じ機能を有する専用機が登場するし、そちらのほうが操作が簡単で便利で快適で安かったりするものである。
記録・保存というのは、画像や動画をネットで収集してきたり、デジカメで写真を撮って保存したり、といったことである。どうも人間には、収集してきたり見てきたものを記録したり保存したいという記録欲があるようで、デジタルになる前から記録・保存の類は行われてきた。これがデジタル化するにあたり、パソコンがその機能を提供する装置になったように思う。
こうした機能は、パソコンに対して記憶容量(つまりHDD容量)の増大を促す。しかも、これまでアナログであったものをデジタル化していく過程で、データの質が向上が起こるため,これがもたらすデータ量増大の勢いはHDD容量の変遷に見て取ることが出来る。 そして、やはり記録・保存だけならばユーザーの負荷も大きくはなく、作業は単純であるので、やはり専用機が出現する。2004年現在ではHDDレコーダーだったり、iPodのようなポータブルHDDだったり、あるいはデジカメに対して直にプリントできるプリンタなどが,記録・保存機能を担う専用機ということになる。だがデータの整理や再利用という観点でパソコンが持つアドバンテージも確かにあり、自分の“記録欲”を満たす装置としてPCを位置付けても損ではなかろう。
さて、編集・作成とは、自ら何らかのデータを作成したり編集するということである。例えば、音楽や動画の編集もそうであろうし、ホームページや文書の作成もこれに含まれる。更には技術計算を行って計算結果を得ることや、プログラミングすること自体もここい含まれると考えてよかろう。
編集・作成という機能は、前述の再生や保存という機能のスーパーセットでなければ成り立たないという性質上、パソコンに対する負荷は(同じ種のデータを扱うのであれば)最も重い。また、編集や作成する人間にも、パソコンを操るスキルだけでなく、作成・編集するものに対してそれなりの知識や技術を要求することが多いため,ユーザーにとっても負荷が高い。
この作業を行うためには、キーボードやマウスなどの入力機器を積極的に使用することが必要であるため、民生用の専用機は登場しにくい。したがって、この編集・作成という機能こそパソコンのアイデンティティを示せる機能だ、とも言える。この機能を使わないのであれば,パソコンを使うことに意味があるのかが問われることになるかもしれない。しかしながら、前述のようにユーザーに対する要求もそれなりであるため,需要自体が大きいかどうかも微妙である。
実際のPCの利用形態を考えると、再生,記録,作成の機能のそれぞれ全てを使っていることだろうと思う。しかしながら、自分が扱うデータの全てに対して,「作成」までを行っているかというと、必ずしもそうでもないかもしれない。
例えば筆者の場合、(個人として)作成までを行うものといえばテキストベースの文書か、ワークシート、簡単な図、年賀状程度かもしれない。記録するまでを行うものといえば、音楽や絵および写真、たまに動画といったところである。これに対して再生に関しては何でも再生・表示させる、といった具合である。勿論、使い方は人それぞれであろうが、最もPCのパワーを喰っているのはPCでなくても可能な“再生”機能に使われている傾向があるように思う。次いで“記録”であり、“作成”は最後だ。
PCは現在のところ、汎用的な使い方が可能な楽しい装置ではある。ただ、“PCの家電化”が喧しい昨今、上記のように性能が求められている“再生”や“記録”が専用機で実現できるとなると、先行きが案じられる。PCがPCたる所以は“編集や作成”が可能な道具(or 趣味の玩具)であるところにあるのかもしれず、今後時間の経過と共にどのような道を辿ることになるのか、、楽しみでもある。(23. Jun, 2004)
OSの進化がもたらしたもの - 前編
Windows95 のリリース以来、「OS」とか「基本ソフト」という言葉も一般に知られるようになってから、既に結構な時間が過ぎた。マイクロソフト社がPC界を牛耳っているということも、広く知られている。その過程では新OSのリリースの度に、そのOSがもたらす新機能について宣伝される一方で、「OSが重過ぎる」といった批判も幾度となく見たり聞いたりしてきた。
PCの世界において我々小市民は、CPUやHDD,メモリといったハードウェアの進歩だけでなく、ソフトウェアの進歩を抜きにして、新機能の恩恵を享受することが出来ない。中でも特に、新しいハードウェアのサポートやPCの使い方に対して大きな影響力を持っているのが、OSである。いかなるハードウェアや機能も、ソフトさえ用意すれば使用可能にはなるのだが、OSが標準機能としてサポートするかどうかがその機能なりハードウェアなりが流行するかどうかを左右する。
逆に、標準となっている機能を享受するためには「重い」とされるOSであっても甘んじて使用せざるを得ない状況にあるとも言える。ここでは、2004年現在,強大なシェアを誇っているMS社のOSの流れを、MS-DOSのあたりから振り返り、結局のところどの機能がOSのバージョンアップで得られた機能であったか、について筆者の独断で論じてみたい。
MS-DOS は 1980年代に登場し、IBM-PC のOSとして採用されたところから,8bitマイコンのOSとして使用されていたCP/M に代わって世界に浸透していったDOS(Disk Operating System)である。
“DOS”が提供した機能は、そのOSの名が示す通り、「ディスクにファイル読み書きが出来ること」であった。バージョンアップで提供された機能も明確だった。例えばDOS のVer2.x ではディレクトリ(フォルダ)式のファイル管理がサポートされた。198x年代のDOS本やパソコン雑誌をめくると、必ずといって良いほどディレクトリのツリー構造の解説などが見られたりしたものだ。そして Ver.3.xでサポートされたのもハードディスクであったりと、やはりディスクの読み書きに関する強化が行われていた。
DOSは基本的に、ディスクやファイルに関すること以外は実質的に殆ど管理していなかった。メモリなどはたった16バイト程のMCB(Memory Control Block)で物理メモリ上の何処が空いているかが分かるようになっていただけであったし、表示にしてもキーボード入力にしても標準入出力以外は全く野放図であった。DOS上で動作するアプリは思い思いの絵をVRAM上に直接描いていたわけだ。勿論、GUI的な操作を提供するアプリケーションもあったし、大容量メモリを扱うドライバなども存在したが、それらの機能はDOSが提供していたわけではない。
32bitCPUが市場に浸透しつつあった頃、時代は16bit終焉フェーズを迎えてハードはソフトに対してややリッチな状態にあり、さしあたってPCやOSを更新する必要には迫られていなかった。DOSはバージョンアップする口実を、大容量メモリ利用やマルチタスキングに求めるようになり、Ver.4以降のDOSでEMSやXMSといった大容量メモリへのアクセスがサポートされたり、Ver.5以降でタスクスイッチャやGUI風シェルなどが導入されたりした。
DOSはこの頃から重厚長大路線を歩み始めたようだ。「重い」「不安定」「メモリ不足でアプリ起動できない」といった批判が噴出し始めたのも、この頃である。しかしながら、筆者の周囲だけかもしれないが,このタスクスイッチャの類やDOS付属のGUI風シェルを率先して使っていたユーザーはあまり多くなかったように思う。
因みに、当時の筆者が DOS をバージョンアップさせた理由は,タスクスイッチャでもGUI風シェルでもなく、FAT(File Allocation Table)がそれ以前の12bit から 16bit に拡張されて大容量HDDをサポートできるようになったという、やはりディスク・ファイル絡みの DOSの基本機能だった。
[訂正 10.Oct,2004] 古い文献を読みなおして気付いたのだが,DOSは Ver3.xで16bit FAT に対応していた。筆者が Ver.5以降にバージョンアップした理由はこれではなかったようだ。今となってはその理由を思い出せないのだが、少なくとも雑誌で宣伝されたGUI風シェルはその理由でなかったことは確かだ(HIMEM.SYS あたりが理由だったろうか…?)。
筆者の独断だが、「OSが重い」という構図は32bit試行フェーズのDOSの頃から起こり、そしてその重厚長大路線が雑誌に代表される宣伝媒体で新時代の機能として紹介されていたように思う。だが、多くのパソコン小市民はそうした機能を「重い」と断じた上で、基本機能の向上のためにやむなくバージョンアップしてきたように思う。果たしてそれは、Windows時代でも繰り返されているのだろうか…?(続く, 9.Oct, 2004)
OSの進化がもたらしたもの - 後編
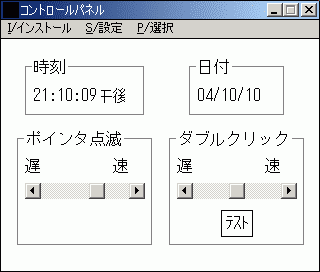 Windows自体は 1980年代半ばの産であるが、消費者向けの Windows は 1980年代末、32bit試行フェーズが始まった頃の MS-Windows 2.1辺りからであったろうか。国内では未だ PC-9800シリーズが磐石のシェアを誇って,DOS上で走るアプリが全盛を極めていた時代でもある。筆者が初めてWindowsに触れることが出来たのは、雑誌の付録に5インチフロッピーで付いてきた MS-Windows 2.11体験版(1990年)であった。
Windows自体は 1980年代半ばの産であるが、消費者向けの Windows は 1980年代末、32bit試行フェーズが始まった頃の MS-Windows 2.1辺りからであったろうか。国内では未だ PC-9800シリーズが磐石のシェアを誇って,DOS上で走るアプリが全盛を極めていた時代でもある。筆者が初めてWindowsに触れることが出来たのは、雑誌の付録に5インチフロッピーで付いてきた MS-Windows 2.11体験版(1990年)であった。
現在も筆者のHDDの中にバックアップとして生存しているこの体験版を見てみると、32個,1.05MBほどのファイルで構成されていた。勿論これは単なる体験版なのだが、ファイルを見てみると “notepad.exe”(20KB)などがあり、現代のWindowsでも実行可能であった(「以前のバージョン用アプリだ」という警告が出た)。つまり、体験版と雖も WinAPI を解するソフトウェア(OS)を僅か1MBほどの中に収めることができたわけである。
当時のWindowsのウリは勿論そのGUIにもあったわけだが、こちらは我々小市民にとっての羨望の的であった Machintosh(高価だった) などと比較すると頗る貧相だった。しかし単一機種がPC界を牛耳っていた日本にあっては、ハードの違いをOSが吸収し、どんなハードでも同一アプリが動かせることがメリットだと宣伝された。右の図は当時のコントロールパネルであり、そのメリットを象徴している。当時は機種毎、アプリ毎に異なるドライバなどを組み込まなければマウスの使用すら叶わなかったのだが、そういった差異をWindowsが吸収し、OSの機能でマウスのクリック速度などを調整できる、というわけだ。
もちろん、当時の筆者にもそのメリットは理解できたが、体験版MS-Windowsで使う notepad は激しく遅く、実際に使用できる画面の狭さには驚いた。当時は 80文字×25行表示が一般的だったが、それに飽き足らない人は無理矢理30行化するなど、(モニタを壊しながらでも)広い画面に渇望していた時代だったのである。MS-Windows 2.xが流行らなかったのは仕方ないことだった。
Windowsのブレーク開始は、MS-Windows3.1からだったように記憶している。なお、3.0というWindows/386の血を引いたバージョンもあり、日本ではNECとEPSONの双方からリリースされたが、残念ながら多くの人にとって動かすべきアプリは殆どなかった。Aldus PageMakerや、Lotus Freelance などはあったが、到底狭い画面では使い物にならなかった。
Windows3.1 が日本でリリースされた頃には、丁度DOS/V機が上陸しつつあるとともに、グラフィックアクセラレータの類が浸透していた。PCハードの能力としては SVGA 以上の表示が可能になるその一方で、「思い思いの絵をVRAMに描いていたDOS」ではこれを利用できるアプリは一部に限られていたのである(もちろん、サポートされるビデオカードも限られた)。このため、もてあまし気味だった解像度の受け皿として,あるいは広い画面を獲得するために Win3.1は流行した。Windowsが提供した GDI(Graphic Display Interface)は、当時のパソコンの非互換部分の本丸を攻め落とし、ハードの進歩と相俟って受け入れられ、漸く32bit時代の幕開けを告げたのである。
Win3.1 は当時のPCにとっては十二分に重たいOSであり、アプリの整備も不十分であったために批判も少なくなかったが、PCにもたらした機能は「窓」の名称に違うことなく,広い画面獲得への突破口になったことは間違いない。
さて、その次にやってきたのは Chicago ことWindows95であり、これが32bit革命をもたらしたと言って良い。Win95自体は 16bitコードを含む不完全な32bitOSではあったが、Win32 API のコードを走らせることが出来た(Win3.1にも、WIN32S があったし、これより少し前のWinNTは32bitOSであったが、一般には浸透しなかった)。16bitの64KBセグメント・メモリモデルの呪縛から解き放たれることによってWindowsアプリの安定性も増して、数多くのWindowsアプリケーションが世に出て行くことになる。
そして Win95 はインターネットへの接続を標準機能として搭載していた。Win3.1 においてもインターネットへの接続は可能であったが、標準ではなかった。WFW のなかった日本においては、Win95 が提供したインターネット接続の標準機能は、このOSを導入する理由に充分成り得た。勿論、当時は「重い」「デカイ」「不安定」という批判は相次いだし、確かにOSのサイズも当時のHDDの結構な割合を占めるものになっていた。しかしながら、筆者の感覚からその重さと引き換えに得られたものを考えると,致し方ないものだったように思う。
Win95 で成功を収めたMS社は、後継OSとして Windows98 や WindowsMe をリリースしていくことになる。パソコン雑誌をはじめとするメディアでは、アクティブ・デスクトップによる「デスクトップとインターネットのシームレスな…云々」などが盛んに宣伝され、これはブラウザ戦争におけるJava勢力の駆逐というMS社にとっての利益をもたらしたが、ユーザーにとっては悪名高いまま終わったようだ。
結局のところOSと巨大ブラウザの合併で重くなった Win98/Me だが、ユーザーにとっての利益は USB の標準サポートだけであったように思う。USBポートのないPCを利用していた筆者には縁のないバージョンアップだった(自分のものでないPCでは多くのWin98/Meマシンに触れたが)。また、多くのユーザーにとってはUSBのために渋々重いOSを受け入れたか、よく分からないが最新にしたか、PCを買ったときからこれだったというのが実情のように思う。この頃時代は 32bit躍進フェーズを迎えていたが、ハードの性能向上分はOS・ブラウザ統合による重さで相殺された感がある。
さて、現在主流のOSである Windows XPだが、その源流は Windows NTである。筆者のPCは前述のように Win98とは無縁であったが、WinNT 4.0 はかなり長いこと使用していた。WinNT はWin95と比較すると確かに重たいOSではあったが、それと引き換えに真面目な動作(つまり安定性)を手に入れることが出来た。
Windows の重要な基本機能の一つはメモリ管理とプロセス管理であり、この点において Win9x系には問題が多く、重たいアプリを使用したり一晩以上要する計算を流すことのある筆者にとってはクリティカルな問題だった。巷で有名なシステムリソースの不足問題は長らく引きずってきた 16bit/64KBの壁によるものだが、この呪縛から開放されることは,OSが重くなることと天秤に掛けても確かにメリットがあったのである。
そして USBはじめとする抜き差し可能デバイスがサポートされた Windows 2000において、32bit時代の一般向けOSとしてはほぼ完成した。この Win2k のリリースの頃から 32bit終焉フェーズは始まり、OSの重さがさほど気にならない時代が到来した。更に、殆どの新デバイス類は出尽くし感があり、ユーザーにとってOSを更新しなければならないという需要の材料も出尽くしつつある。
Windows XP のウリはハイパースレッディングへの対応とユーザー切り替え機能,あとはどうでもいい Luna インターフェイスくらいだろうか。32bit 終焉フェーズの産である WinXP は従来のOS達ほどの「重い」批判を受けてはいないようだが、どうしても乗り換えなければならない理由があったか、と言う点については疑問が残る(別に、乗り換えたらいけないという意味ではない)。
こうして見てみると、OSの進歩とともに少々の基本機能向上のためにユーザーとハードは重たい荷物を背負ってきたように思われる(勿論、避けては通れない進歩もあった)。これから 64bit 時代到来に際して、やっぱり「お荷物」の部分も背負っていかなければならないのだろうか?そしてそれはハードという物量やユーザーのサイフが解決してくれるものだろうか。真の64bit 時代を迎えるまでには未だ時間があり,ひと悶着も想像されるが、これまでのお荷物路線に対抗する新興勢力にも期待したいところである。(11.Oct, 2004)
x64 Windowsで振り返る 32bit の節目-前編
2005年の春を迎えて,既に様々なところで“Windows XP の 64ビット(AMD64/EM64T = x64) 対応バージョンたる “x64 Edition”がリリースされた”とのニュースが駆け巡っている。雑誌やウェブ上のパソコン関係のメディアも,昨年の冷めた反応に比べると随分と64ビットに対して急に熱が入って(入れられて)いるようだ。この x64 Edition は、コンシューマー向けの Windows としては最初の64ビット版ということになるだろうか。そして随分前から噂されているとおり、2006年末(かそれ以降)には次期Windowsたる“Longhorn”がリリースされ、そこには 64bit版 WinAPI たる“WinFX”が実装されるとも言われている。
当サイトでは、これまでに「CPUのビットの境界」について,過去に起きた事象を回顧しながら、これから何が起こるかを考えている。64bit時代の試行フェーズが後半戦に入ろうとしているこの節目に、いま一度,過去 32bitへのシフトがどのように進んだかを振り返ってみたい。
まず、そもそもCPUの“ビット”というのは何を指しているのだろうか(当サイト読者の皆様には解説不要とは思うが)。これには色々と定義があるようだが、基本はレジスタ長だろうと思う。(ここではそれをCPUのビット幅と呼ぶことにしよう。)すなわち、CPUの内部で演算する場合に,“一度で示せる数の範囲”がCPUのビット幅の意味だということになろうか。
そして重要なことは,基本的には指し示すべきメモリの番地もレジスタが指すということだ。つまり、CPUの「ビット幅」が大きくなれば“一度に指し示せるメモリアドレスの範囲”も大きくなる。一般に言われる「リニアにアクセスできるメモリ」とはそういうことだ。これは16bitでは 64KBであり,32bit ではその2乗で 4GB, 64bit では実に 16EB(エクサバイト)にも達する。したがって、CPUのビット幅の拡張は、広大なメモリ空間を求めてのものだったとも言える。
かつての 16bit 時代,64キロバイトというメモリの壁はいかにも小さく、あの手この手で扱えるメモリ空間の拡大が図られていた。そもそも8086の場合、CPU自体が16bitのレジスタ2つを組み合わせて何故か20bitを指し示すという厄介なセグメント方式によって 1MBのメモリ空間にアクセスする機構を備えていた。しかしながら、やはり16bitの壁は64KBだったのであり、メモリ空間拡張の戦いは容易ではなかったのである(最近の例では、Windows9x/ME におけるシステムリソース不足などは、この 64KBの呪縛がもたらした)。
1980年代当時のパソコンにとって、1MBのメモリ空間というのは必要にして十分であり、この空間にメインメモリの640KBとBIOS ROM やビデオメモリを割り振ることができた。その一方で、より広大なメモリを利用する欲求があったのは事実であり、それはバンク式メモリとして実装され、ディスクキャッシュやラムディスクとして利用された。これらは,1MBの空間の中に割り振られるのだが、I/Oポートからの指示で中身がすげ変わり、結果として1MBよりも広い空間にアクセスできるという、単純な仕掛けによるものだった。
ちなみに、その198x年代には、8086 の進化版である 286 や,32bit版である 386が登場している。286 は24bitのアドレス空間をセグメントの拡張でアクセスする方式を提供したし、386は現在のCPUにまで引き継がれている IA-32 アーキテクチャであって、32bitの空間をフラットにアクセスできるモードを提供した。
このように、人々が16bit時代を謳歌していた頃(198x〜1990年代初頭)に、既に32bitハードウェアおよび大メモリ空間へのハード的な下準備は進行していたのだが、実際にそれを利用できるようになるまでには相当の時間を要することになる。こちらでも書いたように、386プロセッサのリリースから 32bit 時代の“幕開け”と後世筆者が評する Win3.1 までの間には 7年を要しているのである。前述のように、16bitの壁は本当にすぐに突き当たるような壁であり、32bitメモリ空間へのフラットなアクセスは渇望されていたにもかかわらず、である。その間の時間は、OSを代表とするソフトウェアにとっては準備期間だったわけだ。
2005年現在は、64ビット時代に向けての準備期間の真っ只中と思われる。32ビットから64ビット時代へ向けてのメモリ空間への渇望度合いは、おそらく16ビット時代におけるそれ程ではないだろう。その一方で、メモリ空間拡張のための障壁というのも当時のそれ程に厳しくない。したがって、やっぱりそれなりの準備期間を経て遷移が行われる、というのが筆者の読みだ。次回は、その準備期間に何が行われ,何が登場して何が廃れたかをおさらいしてみたい。(2. May, 2005)
x64 Windowsで振り返る 32bit の節目-後編
さて、前稿で書いた通り,16ビットから32ビットへのハードウェアの移行は、ソフトウェアに先行して進行していた。そのため、386プロセッサの多くは長らく 16bit CPU として使用された。だが筆者の記憶によると、世間では「32ビットパワー」が盛んに取り沙汰されており、準備期間にあったソフトウェアの方でも何かと「32ビットならでは」が強調されたりしていた。その一方で、従来ソフトウェア資産の継承も重要命題の一つであり、それとの葛藤の中で32ビットへの移行は進むことになる。
当時まず最初に取り沙汰されたのは、やはり「アクセス可能なメモリ領域の拡大」だった。当時の16/20ビットの壁は確かに狭く、大空間メモリへのアクセスは確かに渇望されていた。そこで登場していたのが EMS/XMS に代表される拡張メモリ方式であり、これによって 1MBを超えるメモリにアクセスできると言うフレコミで、かなり流行していた。ちょうど日本で“DOS/V”(PC/AT用日本語表示対応DOS)が出る前後の頃の話である。
EMSなどは 16bitでも専用ボードを使用することで利用可能な拡張メモリの方式だったのだが、これに呼応する形の“32bit売り文句”は、「32bitならEMS/XMSをソフトウェアで実現できます」というものだった。これは仮想86モードと呼ばれる 386 のプロテクトモードの一種を利用したものであり、確かに “386ならでは”であった。しかしながら機能的には 286 + EMSメモリ と変わらず、むしろソフトウェアで実行する分だけオーバーヘッドになる場合すらあった。
要するに、“仮想86モードで拡張メモリへアクセス”というウリ文句は、当時から(利用していた者として)疑問であったが、今から考えても 32bitを売る際の言い訳色が強かった疑いが濃厚である。なお、このような拡張メモリの機構によって動作していた Windows 2.1 は全く実用的ではなかったために流行らず、従前からのDOS上で動かした EMS/XMS が流行するにとどまった。
なお、16bit時代のパソコンOSであったDOS上で 32bit プロテクトモードの全てを利用できるようにするために、“DOSエクステンダ”というものも存在した。これは確かにDOS上で 32bitのメモリ空間にフラットなアクセスを可能にするものではあったが、利用すべきアプリは多くは無かった。(特殊用途でどうしても広いメモリ空間へのフラットなアクセスが必要なシーン,例えば UNIXからの移植アプリ利用などに使われた)。
本来,仮想86モードと言うのは386の広大なアドレス空間の中に20bit(1MB)のメモリ空間を割り当てて仮想的に 8086を複数個作り、マルチタスクを実現するための機構だったのであり、仮想86を一個だけ作って EMSメモリとして拡張メモリにアクセスさせるためのものではなかった。
この本来の使い方を提供したのが、Windows/386 である。このOSでは、仮想86モードのDOS窓を複数動作させることができ,これは当時としては全く画期的なことだったと言って良い。だが残念なことに,当時のCPUは複数のアプリを動作させる程には速くなかった。例えば、Windows/386 の当時日本で最新のマシン(PC9801の場合)は,80386/16MHz か 20MHz 程度だったのだが、二つ以上のアプリを動かせば当然能力も半減する上にOSのオーバーヘッドも相当あったために,DOS窓上で動くアプリの速度は初代98程度だったのである。
そして、残念なことに Windows/386 はメモリアクセスに関しては EMS頼みだった。つまり、アプリケーション内では依然として 16bitの壁が厳然と存在していたのであり、64KBを超えるメモリアクセスのためには相当なオーバーヘッド(アドレスの再計算)が必要であった。このためアプリケーションの実行速度は遅い上によくハングして不安定なOSだったと記憶している。
この流れは Windows 3.0/3.1 まで引きずることになる。Windowsの起爆剤になったとされる Win3.0/3.1 は確かに当時の 32bitCPUの使い途を示したOSではあったのだが、その実質は「擬似マルチタスク+ 16bitメモリ管理」だったのであり、実は32bit時代は訪れておらず,消費者から見れば 386 や 486 は前述のマルチタスク機能があったことと従来CPUよりは速いから使われたというだけのことである。
結局のところヒットしたと言われる Win 3.1 を支えたのは、3.0で不満噴出の大量バグ FIX と,コードのチューニングによる若干の高速化,及び世間のPCのパワーアップであり、32bit云々ではなかったというのが筆者の理解である。
そういう意味で、真の意味での 32bit OSとしては(Winにおいては) Windows NT の登場を待たねばならない。WinNT は、32bit APIセットである Win32 を実装した純然たる 32bit OSだったのだが,ドライバ類が充分出揃うまで相当な待ち時間を要することになる。WinNT は 真の32bit環境を得ることの代償として過去の遺産に目をつぶることになった形である。勿論、WinNTは早くから一部のユーザーの支持を集めていたのではあるが、個人ユース向けとして開花したのは 21世紀の WinXP からとなる(Win2kから、かもしれないが)。
結局、その間に革命的に 32bit 化を推し進めたのは、Win 3.1 + Win32 + 新型GUI(見た目) の Windows95 であった。こちらは“揃ったドライバ&DLL類は32bitで、そうでなければ16bitで”という悪食さ加減が効を奏した形で、世間の 32bit化を推進することになったわけである。
さて、そこで現在世間を賑わせているx64エディションは、後世になってどのように語り継がれるのだろうか。筆者の感覚からすると,少なくとも64bit時代の革命とは言えず、また幕開けかどうかも怪しいように思う。(もちろん、現段階で必要としている人がいることには間違いないが。)
32bit から 64bit への移行は 16bit からのそれとは異なり、「障害は少ない」とも言われており、それは事実だろう。だが、訴求点もまた少ないのもまた事実である。それ故,今は未だ、いにしえのDOSエクステンダーや Win/386 を眺めているような気がしないでもない。そして、当サイトの随所で警告している通り、64bit への移行が本格的に始まるまでの間には「ドライバが出揃うことが望まれる…云々」といった言い訳を聞きながらOS自体や利用形態も変化しつつ、結局数年が過ぎ去るような気がしている。
そして本格的な 64bitへの移行が始まるのは、ハードの能力・ソフト地盤の双方が揃ったタイミングとなるように感じている。(8. May, 2005)
PC処世術トップページへ
当サイトにある記事の著作権は M.Abe に属します。
なお、当サイトの記事の転載はご遠慮ください。
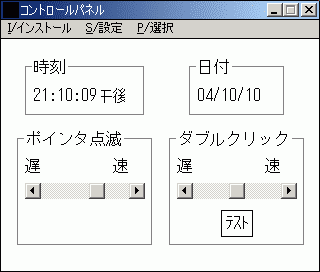 Windows自体は 1980年代半ばの産であるが、消費者向けの Windows は 1980年代末、32bit試行フェーズが始まった頃の MS-Windows 2.1辺りからであったろうか。国内では未だ PC-9800シリーズが磐石のシェアを誇って,DOS上で走るアプリが全盛を極めていた時代でもある。筆者が初めてWindowsに触れることが出来たのは、雑誌の付録に5インチフロッピーで付いてきた MS-Windows 2.11体験版(1990年)であった。
Windows自体は 1980年代半ばの産であるが、消費者向けの Windows は 1980年代末、32bit試行フェーズが始まった頃の MS-Windows 2.1辺りからであったろうか。国内では未だ PC-9800シリーズが磐石のシェアを誇って,DOS上で走るアプリが全盛を極めていた時代でもある。筆者が初めてWindowsに触れることが出来たのは、雑誌の付録に5インチフロッピーで付いてきた MS-Windows 2.11体験版(1990年)であった。