
|
11月の日誌 扉(目次) 深川全仕事 大量点計画 江戸川時代 メ ー ル |
|
平成二十年十二月二十五日(木) 85.6 kg 特別な夜 BGM : Beyond Cool / Lucky Peterson |
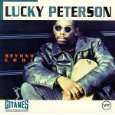
|
昨夜は私の両親と愚妻の両親(つまりセガレの4人の祖父母)を家に招いて会食。セガレは、プーマのGKグローブ、小学館の魚図鑑、なんかよく知らないが水滴をコロコロ転がして遊ぶゲーム、図書カードなどをもらって上機嫌であった。本来パーティ料理は私の任務というのがわが家のしきたりだが今回は仕事が忙しく、大半は愚妻に任せてパスタだけこしらえる。ほうれん草のクリームソースにエビとベーコンを加えた色鮮やかな緑のスパゲティは、私のもっとも得意な料理かもしれない。
(1)大量のほうれん草を茹で、フードプロセッサーでドロドロにする。
(2)それに生クリームをどばどば入れてかき混ぜる。
(3)オリーブ油とニンニクでベーコンを炒める。いや、オリーブ油でニンニクとベーコンを炒める。いや、それでもちょっとニュアンス違うが常識で考えろ。
(4)それにエビを加えて炒める。
(5)そこにほうれん草クリームを投入して煮詰める。
(6)塩・胡椒および大量のパルメザンチーズ(粉末)で味を調える。
(7)茹でたパスタをからめて完成。ああ簡単だ。ああカロリー高い。
というわけで、われながら旨かったっす。あ、書き忘れていたが、ベーコンは適当なサイズに刻んでおいたほうがいいぞ。カタマリのままだとかなり食べづらいと思う。常識で考えろ。あと、エビは量も質もケチらないように。
ひと晩で大変な距離を移動するサンタクロースが目にも留まらぬスピードでセガレの寝室に侵入し(だからサンタは誰も見たことがない)、プレゼントを枕元に置いていたであろう時間帯に、私と愚妻は茶の間でWOWOWの映画を見ていた。『ONCE ダブリンの街角で』。予備知識ゼロで、番組表のタイトルだけに呼ばれて見たのだが、これが大当たりであった。街頭で歌うアマチュアのシンガーソングライターの男(逃げた女がロンドンにいる)とピアノの弾けるチェコ人の女(母国に不仲な夫がいる)がダブリンの暗い空の下で出会い、歌を作り、それをスタジオで録音し、恋には落ちきらずに別れていくという、ただそれだけのお話。ただそれだけなんだろうなぁと、見る者も最初から予測がつく。だが、その歌が、どれもこれもすっげえいい。アカデミー賞で表彰されるぐらい良い音楽を作る奴が、結構いい歳になるまで父親の掃除機修理業を手伝いながら(それ単独で商売になっていることにも驚くが)デビューすることもなく街角で歌っていたという点にやや不自然さは残るものの、まあ、映画とはそういうもんである。私にとっては人生のベスト10に入るであろう名画。故障した掃除機をコロコロと引きずりながら街を歩く女の姿が素敵に見えるという点だけでも、映画の奇跡を感じる。そしてそれは、どんなにカネをかけても作れない奇跡。
|
平成二十年十二月二十四日(水) 85.6 kg 若気の至り BGM : Spirituals & Gospel / Mavis Staples & Lucky Peterson |
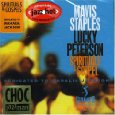
|
月曜の晩にミヤモト君と吉祥寺で飲んだ。くどいようだが小中学校で一緒だった同級生である。面白かったなあ。私が覚えていないことを彼はよく覚えていた。私が彼にさだまさしの『夢供養』を借りたことは前に書いたが、どうやら私は彼に小澤征爾指揮の『春の祭典』を無理やり貸したらしく、彼はそれを聴いて「なんじゃこりゃ」と思ったらしい。さだまさし対ストラヴィンスキーだもんなあ。迷惑をかけたものだ。
あと、彼が生徒会長、私が副会長だった中2の後期に、彼が生徒会と担当教師の板挟みになって苦しんだということも私は知らなかった。聞けば、そのとき生徒会執行部では「校則改正」が一大ミッションとなっていたらしい。それ自体を覚えていないのだから、なんでそんなことになったのかも私にはわからない。当時は薄甘サヨク少年だったから、私が言い出した可能性もあるけども。
で、その中で「所持品の規制緩和」を目指した私たちは、「文庫本はOKにしよう」と考えた。学校に持ってっちゃいけなかったんですね、文庫本。ところがミヤモト会長がその執行部案を担当のオオヌマ先生に打診したところ、敵は「文庫本はダメだが新書ならいい」と返答したそうだ。文庫は教育上よろしくない本もあるが(まあ桃園文庫とかもあるからね)新書なら(当時は堅苦しい本ばかりだったから)問題なかろうということである。その「新書」にカッパの本的なものが含まれていたのかどうか定かではないが、基本的には岩波新書や中公新書を想定してのことだろう。
ミヤモト会長は、その教師見解を執行部に持ち帰った。すると、急進改革派の私とタカギ君が「そんなのおかしいだろ!」「誰が新書なんか学校で読むんだよ!」などと激怒したというのである。タカギ君などは、何を血迷ったのか、黒板に「Die ! Die ! Die ! Die ! Die !」とチョークが折れんばかりの勢いで書き殴って大暴れしたらしい。オオヌマ先生は英語の教師だったのだ。ミヤモト会長、頭を抱えるの図。
結局は新書だけがOKになり、われわれ急進改革派は敗北を喫した。そういえば私は任期終了間際に全校集会で朝礼台に立ち、「靴下に線が入ってちゃいけないなんて校則はバカバカしいと思いませんか!」などと間抜けな演説をぶった記憶がある(とても恥ずかしい)が、あれは校則改正闘争敗北の悔しさを紛らすための最後っ屁だったのかもしれない。微笑ましきは10代前半の情熱であるよ。そんな私が30年後の今、ヒーヒー言いながら新書ばっかり書いているという、この現実この事実。30年前よりも圧倒的に平易な中身になっている(小5のセガレでさえ笑いながら読んでいる)新書だが、今の中学校では持ち込めるのだろうか。ケータイをどうするかで手一杯で、本のことなんか問題にもならんとは思うけど。当時ケータイがあったら、われわれ急進改革派がどんな主張をしたのか考えると怖い。無い時代でヨカッタ。
|
平成二十年十二月二十二日(月) 85.4 kg キラキラ BGM : Lucky Peterson / Lucky Peterson |
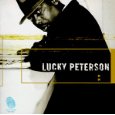
|
土曜日は杉並公会堂でピアノの発表会。セガレの演目は、去年(ピアノソナタ15番第1楽章)に引き続きモーツァルトナンバー。「キラキラ星による12の変奏曲」である。私は家での練習をフルサイズで聴いたことがなかったが、愚妻によれば「1ヶ月前のほうが上手かった」とのことなので、やや心配していた。しかし、去年は「右手が一瞬フリーになった隙に鼻の頭の汗をシャツの袖でゴシゴシ拭く」という荒技を見せたセガレは、相変わらず本番に強い。いくつかミスはあったものの、テキトーに誤魔化しながら最後まで
|
平成二十年十二月二十日(土) 85.4 kg そんなに腹が減るのか BGM : Live: Hope at the Hideout / Mavis Staples |
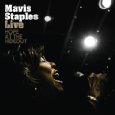
|
どんなニュースよりも理解に苦しむのは、大阪府門真市教育委員会の職員6人が市立小学校の給食調理員から給食の米飯を無料で譲り受け昼食として食べていたという一件である。同じ施設内ならともかく、わざわざ小学校まで出向いて頂戴してくる(しかも大人が6人いて誰もそれを止めなかった)というのが、まずわからないよ。ものすごく面倒臭いだろそれは。かけた手間に見合う利益を得ているとはとても思えない。「自分の弁当だけでは量が足りなかった」って、刑務所の受刑囚じゃないんだからさ。ごはんぐらい家からいっぱい持ってこいよ!と言いたくなるのがフツーだと思うのだが、もしかしてそれは「パンがないならケーキをお食べになればよろしいじゃありませんかオホホホホ!」的な世間知らずのタワゴトなのだろうか。いまどきの庶民は、同じ庶民であるところの私なんかの想像をはるかに上回るくらい貧窮しているのか。教育委員会の職員って、米が満足に買えないレベルの安月給なの? それとも人間は、「タダで手に入る」とわかると、それが何であれ欲しくて欲しくて居ても立ってもいられなくなるということなのか。6人でもりもりとメシを食いながら「こんなもんにカネ払うてる連中はアホでんな」とかヘラヘラ笑って勝ち誇ってたのかもなー。でも、それはごはんなんだぞ。何の変哲もない白いごはんなんだぞ。謎だ。やたらと謎めいている。
|
平成二十年十二月十九日(金) 85.4 kg イケイケでヤレヤレ2 BGM : Have a Little Faith / Mavis Staples |

|
マンチェスター・ユナイテッドとガンバ大阪の試合を後半途中から見た。すでに2-0だったので「もう終わっとるがな」と思ってシラケていたら、そこから6点も入ったのでゲラゲラ笑う。私が観戦した範囲では3-3のドロー。みんなでお遊戯しているようにしか見えないイケイケでヤレヤレな一戦(忘年会かよ)だったが、遠藤のPKにはヘンに固唾を呑ませてもらったのだし、威勢のいい狂気も感じさせるなかなかの娯楽大作であった。この試合の真の勝者は日本のお笑い文化、という理解でいいのだろうか。久しぶりに、赤ら顔で憮然とするファーガソンのツラを拝めただけでも満足。
ところで「イケイケでヤレヤレ」は「マケレレでヤヤ・トゥーレ」と少し似ている。とくに意味はない。でも先日のクラシコを見たら、残念ながらヤヤ・トゥーレはトゥーレ・ヤヤとなっていた。残念ってこともないが、「ほぼトゥーレ」とか「かなりトゥーレ」とかはもう言えない。なんでそんなことが言いたいのかは謎。
|
平成二十年十二月十八日(木) 85.0 kg イケイケでヤレヤレ BGM : I'm Ready / Lucky Peterson |
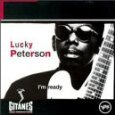
|
この商売をしていると、たまに目の覚めるような仕事の依頼というのがあるのだが、きのう神保町方面から飛び込んできた話も、遅々として進まない原稿を前にグダグダしていた私をシャキ〜ンとさせるものだった。借金じゃないぞ。シャキ〜ンだぞ。なにしろ、ソッコーで来年2月に出してババッと売りたいから何とか頼む!的な緊急企画である。ににに2月だぁ? 来年の春頃までかな〜りスケジュールが詰まっており、なんとな〜くウンザ〜リしていたのだが、編集者がこうして威勢のいい狂気(これだよ今の日本に足りないのは)をほとばしらせて割り込んで来ると、逆にアドレナリンが噴き出して元気になり、「わかりやした。あっしでよろしけりゃ、ひと肌脱ぎやすぜ旦那」みたいな任侠系の使命感が頭をもたげたりするから不思議である。いわゆるひとつのカンフル剤ってやつだわな。別のアングルから光を当てると「ヤケクソ」にも見えたりするわけだが、ともあれゴースト仕事のわりには好きに書かせてもらえそうな雰囲気だったこともあり、あんまり後先考えずに引き受けた。やれやれ引き受けちゃったよなあ。あんがい、相手の心意気次第で木に登ってしまうタイプ。なので、誰でも割り込めるってわけじゃないからね。念のため。
|
平成二十年十二月十七日(水) 85.0 kg 思い出の芋蔓 BGM : Creole Moon / Dr. John |

|
ミヤモト君からメールをもらった。きのう書いた中学時代の同級生である。さっそく検索でここを見つけ、いきなり『キャプテン翼勝利学』を買って通勤電車で読んでくれたとのこと。ありがたい。重版したばかりなので手に入りやすい状況だったのは幸いである。「2002年W杯以前に現在の日本サッカーの問題点を的確に言い当てていることに深く感銘」などと、行間を必要以上に深〜〜〜〜〜〜く読んだとしか思えぬ過分な感想に思わず苦笑……いや恐縮してしまいました。ただし表紙カバー裏の写真は「如何なものか」とのことで、それは私もそう思う。あの写真の私と今の私とでは、体重が10キロ以上ちがいます。ヒゲ以外は昔の面影があるそうだが。
そういえばあの本のプロフィールに、小学生時代に市のサッカー大会で優勝したことを書いたはずだが、私がセンターバックだったそのチームでフォワードとして活躍していたのがミヤモト君だ。頼もしい点取り屋がいたので、私はセンターラインより向こうに行く必要がなかった。関係ないが急に思い出したので書いておくと、中学校の生徒会ではミヤモト君が会長で私が副会長。2人ともさだまさし好きで、リリースされたばかりの『夢供養』を真っ先に買って私に貸してくれたのもミヤモト君である。1979年の話だよ。「パンプキンパイとシナモンティー」が入っているアルバムだが(いまウィキで調べたら日本レコード大賞でベスト・アルバム賞を受賞したらしい)、そんなもん聴いてる2トップって、どんな生徒会だったんだそれは。あと、以前この日誌で、大学の入試を終えるやいなや帰宅途中に友人と喫茶店に入って半年間やめていた煙草を吸った話を書いたことがあったと思うが、その友人もミヤモト君だった(彼が吸っていたかどうかは忘れた)。いろんなこと思い出しちゃった師走である。飲みてー。
|
平成二十年十二月十六日(火) 85.0 kg 忘年会の犬 BGM : Black Midnight Sun / Lucky Peterson |
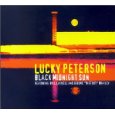
|
土曜日の夜に、突然、中学時代の同級生からケータイに電話が入った。地元の小金井に10人ぐらい集まって飲んでるからおまえも来いという。ものすごく懐かしかったので行きたかったが、そのとき私は赤坂で飲んでいた。遠いよ。小金井と赤坂はとても遠い。なので、申し訳ないが行けなかった。っていうか、もっと早く教えておいてほしいよ。その場で思い出してくれただけでもありがたいけどさ。とりあえず私の筆名を教えて「検索すればいろいろわかる」と伝えたが、これを見てくれただろうか。左にメールアドレスがあるので、次の機会にはひとつよろしく。
赤坂で飲んでいたのは、友人のバンドが主催する忘年ライブ&セッションパーティに顔を出したからだった。何もできないのでセッションには参加せずただ飲んだり食ったり騒いだりしていたが、会場で驚異的なレベルのホコロビ人間を発見したのは大変な収穫。さっそく、きのう締切だったSAPIO新年号用のコラムで使わせてもらった。なので、ここには書かない。犬も歩けば棒に当たる。ネタ拾いはいつだってギリギリだ。こうして手当たり次第にネタにしていくうちに文筆業者は友達を減らすのかもしれないとも思うが、いやはや何とも、まさか世の中にあんな人間がいるとはなぁ。などと書いておけば、少しは雑誌売り上げに貢献できるだろうか、どうだろうか。
|
平成二十年十二月十二日(金) 85.2 kg 恩を仇で返すJR東日本 BGM : City That Care Forgot / Dr. John and the Lower 911 |

|
JR東日本が来年4月から首都圏の226駅を全面禁煙にするという。たばこ増税は見送られるようだが、こうなると、むしろ減税すべきだろ。たばこには4種類(消費税を含めれば5種類)もの税金がかけられており、1箱300円なら約189円は税金(税率約63%!)だが、そのうち約16円は「たばこ特別税」というもので、これは旧国鉄の借金を返すために創設された税金である。その後ろめたさがあるから、いわゆる私鉄各社が全面禁煙にして以降もJRだけは灰皿を撤去できなかったのだろう。そんなJRをいじらしいと思うからこそ、お人好しのわれわれ喫煙者はたばこ特別税を受け入れてきてやった。しかし、ここまでJRが対喫煙者サービスを低下(というか撤廃)させたからには、もうそんなものを負担する筋合いはない。最初からありはしないが、ますますない。たばこ特別税は廃止して、来年4月から16円値下げしなさい。旧国鉄の借金は、「たばこを吸ってから電車に乗り込む喫煙者の呼気には有害物質が含まれ、分煙対策では解決にならない」とかぬかしてた嫌煙団体が、募金活動でもして払いやがれ。それがイヤだと言うなら、JRに限って吸わせろよ。なんか文句あんのかよ。これは健康問題なんかじゃない。義理と人情の問題である。つまり、人をバカにするのもいい加減にしろってことだ。しまいにゃ集団訴訟とかしちゃうぞコンチクショー。そろそろ「モンスター・スモーカー」が最後の悪あがきを始めてもいい頃合いである。
|
平成二十年十二月十一日(木) 84.8 kg 読む子と書く父 BGM : Elephants...Teeth Sinking Into Heart / Rachael Yamagata |
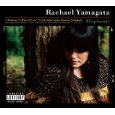
|
10月上旬に脱稿した某社新書が出来上がって自宅に届いたのだが、何を思ったのかセガレがそれをニタニタしながら読み始めた。書名をここに書けないのが残念だが、サラリーマン向けのコミュニケーション術みたいなものである。「おもしろいねコレ」って、ヘンなガキだなあ。ゲラゲラ笑った個所を見たら、著者が言ってもいないのに私がノリで書いた戯れ言の部分だったので、お父さん嬉しかったけど。今朝は登校前に、茶の間でラヴェルのピアノ曲集なんか聴きながらそれを読んでいた。11歳にして、早くも悠々自適な感じ。
ノーベル賞の南部さんはどうしたって「日本人だよなあ」と思ってしまうのが(良くも悪しくも)我々の自然な感覚だろうとは思うのだが、父親が日系三世で母親がイタリア人のレイチェル・ヤマガタまで「日系だ!」などと親近感を抱いている人がいると、それはちょっとどうなのかと思うのであるよ。一方で「もっと西洋風の名前じゃないとイメージに合わないよなあ」などと感じてしまう私もそれはちょっとどうなのかという話だけど、ともあれ曲も歌もアレンジもすばらしい2枚組アルバム(というか2つの異なるアルバムのセット)。とくに「Elephants」と題された1枚目のほうは、ストリングスがうっとりするほど美しい。
ところで、ふと思ったのだが、南部さんの名前を漢字表記にすることに関してメディアでは何か議論のようなものはあったのだろうか。別にどうでもいいのか。しかし「レイチェル山形(か山縣か山県か何なのかは不明)」とは表記しないわけで、どこらへんからカタカナになるんだか、考えてみるとよくわからない。本人が書ければ漢字でOKなのか? あ、それとも出生届が漢字なら漢字でいいのかな。じゃあオノ・ヨーコはどうなんだ。いやアレは芸名か。うーむ。というか、私は今そんなことで悩んでいる暇はないんだった。書籍の仕事って、どうしていつも始めた途端に追い詰められているのか不思議でならないのだが、それについて考えている暇もお父さんにはありません。
|
平成二十年十二月十日(水) 85.0 kg 間違えた BGM : Struttin' / The Meters |
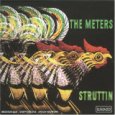
|
広島女児殺害事件の控訴審判決、きのうの私の理解は間違いで、裁判員制度をにらんで始まった公判前整理手続きが裁判の「迅速化」ではなく「拙速化」をもたらすことに警告を発するものだったようだ。いや早とちり早とちり。要は、バカにもわかるように情報を整理したワイドショー的説明じゃイカンよ、ということであろう。公判前整理手続きを経て行われる裁判員裁判というのは、いわばプロが編集したハイライト映像だけを見せて、素人に試合の評価(殊勲選手は誰で敗戦は誰のせいか、とか)をさせようというようなもんである。したがって、マヌケなプロの予断(負けたのは選手の精神力が韓国より劣っていたせいに決まっている、とか)が入り込む余地はいくらでもあるのだし、実は勝敗を大きく左右した重要なシーン(打ち込まれた投手を監督がベンチ裏でブン殴ってた、とか)が抜け落ちていることもあるわけだ。結局、プロのレベルを上げなきゃ裁判の質なんか向上しないんだと思う。
|
平成二十年十二月九日(火) 85.2 kg ニュース雑感 BGM : Little Honey / Lucinda Williams |
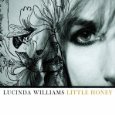
|
■広島の女児殺害事件(05年)で、無期懲役の一審判決を高裁が破棄して地裁に差し戻し。これもまた裁判員制度スタートを前に「被害者1人でも死刑でOK」のレールを敷いている、という理解でいいんでしょうか。(追記:よくありませんでした)
■千葉の女児死亡事件(殺人罪が適用できるかどうかは微妙だと思っている)で、テレビ各局は逮捕前に録り溜めた容疑者映像をじゃぶじゃぶと垂れ流し。容疑者の禍々しさよりも、どういうわけか猫撫で声の女性記者ばかり送り込んでいたテレビ局の邪悪さのほうがビシビシ伝わってくるよね、という感想でいいんでしょうか。
■ニュースサイトで中高生が辞書に載せたい言葉を知ったとたんに「もう忙しくて姫タヒりそう〜」などと書いてみたくなる44歳一児の父は、ナウなヤングにはダサすぎてチョベリバ、という評価でいいんでしょうか。その評価自体がダサダサですか。でも「タヒる」は結構いいと思うな。おれ今日はもうタヒタヒ〜、とか。
|
平成二十年十二月八日(月) 84.8 kg You can smoke ! BGM : Yes We Can / Lee Dorsey |
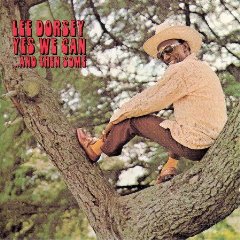
|
アラン・トゥーサンの名曲「Yes We Can」は、このリー・ドーシーが創唱者であるらしい。これがオバマさんの元ネタだったのかどうかは知らない。ともあれ彼にもできないことはあったようで、産経新聞のこの記事によれば、選挙期間中の禁煙には失敗したとのこと。別に無理しなくていいんだよ、次期大統領。ここはひとつ、マイノリティの権利を大事にして、ホワイトハウスの禁煙ルールもチェンジしようじゃないか。
|
平成二十年十二月六日(土) 84.4 kg 歌いたい、そして打ちたい BGM : Let It Flow / Dave Mason |
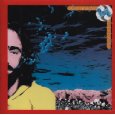
|
書き忘れていたが、火曜日にWOWOWで桑田佳祐の「ひとり紅白」を途中から見た。ちょうど「五番街のマリーへ」を歌っているところで、それ以降、「心の旅」「あの日に帰りたい」「さよならをするために」「シルエットロマンス」「ルビーの指輪」「時代」と続きやがるんだから、たまりませんぜ旦那。うへへ。しかしこのセットリストによると、その前に「学生街の喫茶店」を歌っていたらしい。しまった。再放送はないのか。そういえば、さだまさしの曲がなかったようだが嫌いなのだろうか。嫌いかもしれない。でも桑田版「無縁坂」とか聴いてみたかった。それはともかく、譜割を自分流に動かすことがほとんどなく、日本語の発音も桑田っぽさ抑えめで、楽曲とその創唱者への敬意を感じる歌いっぷり。よか企画でしたでごわす。これでキャンディーズが入ってさえいれば完璧だったけどね。画竜点睛を欠くとはこのことだ。「哀愁のシンフォニー」抜きで昭和のヒット・ポップスを語ることは、たとえ世間が許しても私が許さない。たとえ私が許さなくても、世間が許せばとくに大きな問題はない。小さな問題もなさそうだ。ちなみにセガレは、どういうわけか「長崎は今日も雨だった」が耳について離れなくなった様子。だからって風呂場で歌うのはやめなさい。ところで、「空に太陽があるかぎり」と「情熱の嵐」は、まるで兄弟のようによく似ている。
右上のジャケットは古葉監督ではなくデイヴ・メイソンだが、これの3曲目「ミスティック・トラベラー」も、何かに似ているような気がしてしょうがない。何だ。
昨夜は、小学館「週刊ポスト」「SAPIO」などが主催する「謝恩の会」なる立食パーティにお招きいただき、内幸町の日本プレスセンタービルへ。SAPIO編集部の面々以外に知り合いはいないため、あまり人と話すこともなく、黙々と飲み食い。料理がとても美味しく、こんなところにビュッフェ大好きのセガレを連れてきたらコーフンして大騒ぎだろうな、などと思った。
10万円分の商品券やブルーレイ・レコーダーなどが当たるビンゴ大会は、4ヶ所でリーチがかかった状態で終了。ちくしょう。手に汗を握らせてもらったぜ。厳密に言うと「あと一つでアガリ」の状態は「リーチ」じゃなくて「テンパイ」だと思うが、人はそれを「リーチ」と呼ぶ。それにしても、「リーチ」という言葉は、麻雀を知らない人でもふつうに使うのが不思議だ。「リーチ」が通じるからといって、その人に「イーシャンテン」が通じると思ったら大間違いだぞ。まあ、通じさせる必要もあんまりないとは思うが。ちなみに私の仕事は、イーシャンテンの状態がわりかし長い。テンパったら、意外に早く上がるんだけどね。
久しぶりに麻雀やりたくなってきた。
ところで最近この日誌をご覧になった飯田編集長が、私の顔を見るなり「オル・ダラといえばですねえ……」で始まる話をし出したのでびっくりした。そういう人だったのかー。知らなかったー。「そういう人」がどういう人を指すのかは必ずしも明確ではないが、「わりと珍しい人」であることは間違いない。ともあれ、お元気そう(というかきわめて意気軒昂)だったので安心した。SAPIO編集部のみの2次会にもお邪魔して、23時すぎまで銀座。風邪をひいているのを忘れて、うっかり飲み過ぎた。まだ咳と鼻水が止まらない。
|
平成二十年十二月三日(水) 85.4 kg 私の1冊 BGM : Tango Palace / Dr. John |
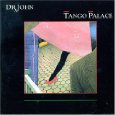
|
風邪はまだグズグズとつきまとっている。咳、鼻水、頭ボンヤリ。最後のは風邪のせいかどうか怪しいが、まあそんな感じでグターッとしつつ、しかし締切は待ってくれないので、きのうは「SAPIO」のコラム書き。もう6回目だ。こんなことをここに書いてはいけないのかもしれないが、いまだに自分のイメージと書いたもののあいだに微妙なズレがあって、わりかし悩んでいる。まあ、結局は書いたものが自分なんだろうから、それはそれでしょうがない。
無理やり仕上げて送稿したら編集部から電話があり、別件の依頼。新年号で常連執筆者の「私の1冊」的な特集を組むので、何か選んで短い書評を書けとのことであった。まずい。まずいっすよ。おれ、本、あんまり読んでないんだよ。なにゆえ世間には「物を書く人間は本に詳しい」という暗黙の了解があるのであろうか。CDじゃダメなんですか? と訊きたかったが、ダメに決まっているので訊けなかった。しかも「今年発売された本で」というのだから困る。しくじったよ。このところ、吉村昭ばっか読んでたんだよ。あー。「零式戦闘機」とかじゃダメかなあ。ダメだよなあ。いま読む意味はそれなりにあると思うんだけどなあ。
それにしても「零式戦闘機」でのっけから驚かされたのは、名古屋の工場で完成した機体を、各務原の飛行場まで牛車で運搬していたということだ。平安時代の話じゃないぞ。昭和の話なんだぞ。道がまともに舗装されておらず、トラックだと揺れて破損するので、世界最優秀の戦闘機を牛に引かせていたのである。ものすごく速いのに、ものすごく遅かったのだ。そのうち牛の体力(!)も弱まり、機体の増産に搬送が追いつかないことに業を煮やした三菱本社副社長岩崎彦弥太の台詞が泣ける。
「馬ではだめなのか」
勝てないよなあ。アメリカがトラックでバンバン運んでるときに、「牛より馬だろ」とか言ってたんだもんなあ。しかし、ここで搬送時間を短縮する方法を提案した岩崎家牧場の管理者がカッコいい。事情を知るやいなや「ペルシュロンを使えば必ず能率が上がる」と断言したのだ。それまで、馬は「暴走する恐れがある」という理由で使われなかったのだが、ペルシュロン系の馬は落ち着きがあり、体力も忍耐力もすぐれているというのだった。これを導入した結果、それまで24時間かかっていたものが12時間まで短縮されたそうな。元祖「プロジェクトX」である。感動した。
|
平成二十年十二月一日(月) 85.4 kg 師走は毎年やって来る BGM : Live at Montreux, 1995 / Dr. John |
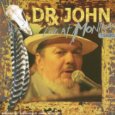
|
■セガレにうつされた風邪でゲホゲホと咳き込みながら、金曜日の夕刻に女性著者のメンタル・トレーニング本を脱稿。自ら出した禁止令に従って徹夜はせず。
■しかし風邪悪化で、週末はほぼ寝たきり。いくらでも眠れた。「徹夜してもしなくても同じじゃん」とはセガレの弁。このところ、ときどき正しいことを言いやがるので頭に来る。
■ともあれ私の場合、大事なのはメンタルよりもフィジカルなのだった。
■休む間もなく、次は弁護士本。たしか一月にも、別の弁護士の本を書いていたような気がする。弁護士で明け、弁護士で暮れる平成二十年。
■というか、ちゃんと年を越さずに書き終えないと、来年も弁護士で明けてしまう。「しまう」ってこともないが。
■おかげでけっこう裁判に詳しくなったので、いっちょ法廷で腕を振るって裁判員制度導入を政府に後悔させてやろう(内側から腐らせる方法はいろいろあるだろう)と意気込んでいたのだが、とりあえず1年目はハズレたらしい。つまんねえの。
■Amazon.co.jpで見るかぎり、売れ行きはものすごく下位だし、カスタマーレビューも見当たらないのだが、ドクター・ジョンの「Live at Montreux, 1995」はそうとうな名演だと思う。モントルーの魔力か何かが作用しているのではないかと思えるような熱情と集中。私はたまたま中古店で(安かったので)気紛れに買ってみたからいいようなものの、こういう名品にちゃあんと目配りしておいてくれないと困るじゃないか、アマゾン村のレビュアーさんたちよ。