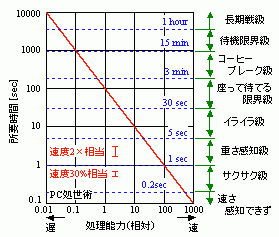PC処世術 - パソコンの寿命/陳腐化/老朽化
パソコンは老朽化するのか?
形あるものには寿命があるのは世の常というものだ。ことさら、人間が製造するものの寿命というのはそんなに長くはないことが多い。冷蔵庫,テレビや洗濯機といった家電や自動車,家具などの“耐久”消費財と呼ばれるものの寿命も永遠ではない。もちろんパソコンとて例外ではなく,購入当初は“最新・最速”マシンであってもやがて寿命を向かえることになる。
「寿命」と一口に言っても,その迎え方には様々な形態がある。真っ先に思い浮かぶ形態は、故障だろう。スイッチを入れても動かなくなったり、動作がおかしくなったりということだ。このような迎え方の寿命は“機械的寿命”とでも呼ぶべきもので、家電や自動車などと同様にパソコンにも起こり得ることだ。
パソコンの場合、このような機械的寿命は世間で思われているよりは長いことが多い。パソコンを構成するパーツの中で最も機械的寿命が短いのは、ハードディスクや DVD, CD-ROM に代表される光学ドライブなど、可動部を有するデバイス類だろうか。次いで電解コンデンサなどケミカル製品が用いられている部位(例えば電源装置)の機械的寿命も短いかもしれない。
これに対して、CPUやメモリなどの半導体デバイスの類はずっと長い寿命を有しているように思われる。筆者の経験では、無理な動作をさせて壊した場合を除けば半導体が死亡した例というのを殆ど知らない。
つまり「パソコン」というひと括りで見た場合、パソコンの機械的寿命はHDDの機械的寿命でほぼ決まり、普通の使い方なら大体4,5年というところになるのだろう。(勿論、機械的寿命の長さというのは使用状況によっても異なるし、製品のばらつきもある。また、当たりハズレの“運”の要素もある。4,5年というのは相場値と考えていただきたい。)
 だが、筆者の周りを見渡してみると、パソコンの買い替えサイクルは大体2,3年程度なのだという。この買い替えサイクルは,前述の機械的寿命よりも短い。必ずしも、古くなったパソコンは故障したために買い替えを向かえるということではないようだ。
だが、筆者の周りを見渡してみると、パソコンの買い替えサイクルは大体2,3年程度なのだという。この買い替えサイクルは,前述の機械的寿命よりも短い。必ずしも、古くなったパソコンは故障したために買い替えを向かえるということではないようだ。
これは、家電や自動車でも同じことだ。決して「故障したから買い換える」という場合ばかりではない。「新しい機能」「より高い性能」を求めて買い替えるというパターンだ。中古市場で未だ充分に稼動するPCが二束三文で流通しているところをみれば、このことが事実であることを確認できる。
例えば右の図は 1980年代終盤の16bit PCであり、既に発売から20年以上が経過したものだが、この年代のPCは未だ中古品として稼動するものを入手することができる。しかしながらこの年代のPCはたとえ稼動できたとしても、現代のパソコンに求められる機能を提供することはできず、充分に寿命を全うしたものと言って良いだろう。
つまり、古いパソコンは最新のものに対して相対的に能力が劣るために新機能を使えないなどの、“陳腐化”を感じて寿命を迎えるというパターンが多いのである。このように陳腐化によって迎える寿命は,“論理的寿命”とでも言うことができ,機械的寿命とは分けて考える必要があるだろう。
さて、機械的/論理的のいずれにしても、パソコンはやがて寿命を向かえる運命にある。その過程で、“老朽化”というのは果たしてあるのだろうか?。勘違いされ易いところではあるが、基本的にパソコンは故障がない限り、「買った時に出来たことが時間の経過とともに性能劣化して出来なくなる」ということは“ない”。パソコンがハード的に老朽化するとすれば、キーボードやマウス、そして本体が汚くなるとか、空冷ファンが異音を出すとかその程度かもしれない。むしろ、パソコンの老朽化は陳腐化に伴って歩み寄る論理的寿命が醸すものであるように、筆者は思う。
当サイト,「PC処世術」では、パソコンを構成する様々なパーツについてその変遷の歩みから陳腐化のスピードを考察している。その考察によれば、パソコンの機械的寿命を律しているHDDは論理的寿命も短く、これを適切なサイクルで交換していけばパソコン自体は相当長持ちする。そういう意味でパソコンは、家電や自動車と大差ない寿命を有しているとも考えられる。ただ、家電や自動車と大きく異なるのは,パソコンは時間の経過とともに時代の変革(こちらやこちら)を迎えることだ。筆者のようなパソコン小市民としては、目先の目新しさに目を眩まされることなく、時代の変革に合わせてパソコンの更新を図っていきたいと思うところだ。そのために,PCのベンダによる頻繁なモデルチェンジと宣伝される内容が、時代の変革を伴うものであるかどうかを見極める目を持ちたいと、筆者は願うのである。(6.Nov, 2004)
パソコンのソフトウェア的劣化
さて、前稿では、「パソコンはハードウェア的には性能劣化せず、陳腐化による論理的寿命が老朽感を醸す」と書いた。では、陳腐化とは何だろうか?それは果たして体感できるものなのだろうか。
そして、よく「最近パソコンの調子が悪くなってきた」とか「重くなってきた」という声も聞く。このような現象は実際にあり、そして既に様々なところで言われていることだが、ソフトウェアに起因することが殆どである。ここでは、“陳腐化”をどのようなシチュエーションで体感し、そしてそこにソフトウェアがどのように関わっているのかについて書いてみたい。
陳腐化を体感できる主要なパターンの一つは、周囲の最新パソコンに触れることだろう。より新しいパソコンに触れれば、自分のパソコンよりも高速でレスポンスも良く、ディスクの空き領域も広大で、確かに自分のPCが劣っていることを確認できる。自分のPCの世代と触れた最新PCの世代とのギャップが大きいほど、その差は歴然たるものであるはずで、場合によってはこれだけで自分のPCの陳腐化を体感することができるだろう。あるいは、最新の機能(例えばビデオの録画再生など)を有するかどうか、といったところで陳腐化を感じることになるかもしれない。これは純粋にハードウェアの陳腐化を感じるパターンだ。
陳腐化を感じるもうひとつのパターンは、最新のソフトウェアに触れることだ。ソフトウェアの使い勝手は日々進歩しているし、“見た目”も日々流行が変わる。こうした最新のソフトウェアを使ってみたいと思ったら、それは陳腐化を体感するシチュエーションとなる可能性が高い。これは、単に新しいソフトをいれるという場合だけでなく、各種機器に付属してくるオマケソフトの類をインストールする場合も同様である。
まず、購入・インストールする前にソフトの推奨動作環境を読んで陳腐化を感じる場合もある。更にインストールして実行すると、その重さに閉口することもあるだろう。あるいは、必ずしもソフトの謳い文句通りにならないこともある。
このようにして新しいソフトに触れることにより、“PCの陳腐化”を体験することができるのだが、陳腐化が起こるのは上記のように意図して新ソフトにチャレンジした場合ばかりではない。意図せずとも、ソフトウェア的劣化に見舞われることはあるのだ。
勿論、巷で言われているように、蓄積したデータの増加に伴うHDDの逼迫や自然発生的なフラグメンテーションも劣化原因の一つであろうが、それよりも大きな影響を与えるものがある。それはソフトウェア・OSのアップデートだ。
ソフトのアップデートというのは、換言すればバグフィックスであることが多い。したがって、基本的にアップデートそれ自体は歓迎すべきものなのだが、実行ファイル類はディスク上に不連続に配置されてフラグメンテーションを誘発する。更にはレジストリに余計なゴミを残しながらシステムを鈍重にさせる効果がある。
更に加えると、“アップデート”が純粋にバグフィックスであれば問題はないのだが、勝手に余計な先進の機能の追加と抱き合わせであることも往々にしてある。もちろん先進の機能は,システムを鈍重にさせる効果が非常に高い。
このため、PCの購入から時間を経て幾度かのアップデートを経験すると、どうしてもPCは鈍重になるし、場合によっては調子が悪くなる。当然、筆者はこれに対するレジスタンスとして,不要のバージョンアップは行わず、「レジストリ軽量化」や「デフラグ」の励行を行うわけだが、残念なことに追加機能と抱き合わせでやってくるアップデートに対しては無力である。
特に最近はセキュリティ関連のバグフィックスが多いから、ユーザーはアップデートせざるを得ない場面も少なくない。ましてやOSのアップデートなら,高い頻度で呼び出される実行ファイルもフラグメンテーションに埋没し、レジストリの肥大化から逃れることは難しい。
これは、例えOSの再インストールを行っても,同時にOSやソフトのアップデートを施すことが殆どであることを考えれば、なおさらである。パソコンは決してハードウェア自体は性能的に劣化することはないのだが、ソフトウェア周りに、「パソコン陳腐化」(“する”場合も“させる”場合も)のキーが存在するようだ。そして、残念なことに我々パソコン小市民はこのようにソフトウェアによって劣化させられ、陳腐化してゆくPCの劣化に付き合ってゆかねばならない。(5.Mar, 2005)
パソコンの処理能力と人間の“時間感覚”
パソコンが“劣化した”と感じる要因は上述した通りだが、劣化を実感として感じるのは「遅い」とか「重い」と感じた場合であることが多い。では、「重い」というのは一体どういうことなのだろうか。もちろん、パソコンが物理的に質量を増すわけはなく、「重い」というのは操作感覚のことだ。操作に対してレスポンスが遅いとか、待ち時間が長い時に「重い」と感じるのである。つまり、パソコンが「重い」かどうかというのは人間の時間感覚に依存するということだ。
さて、ではパソコン小市民として気になるのは、「最速マシンにすれば“サクサク”の操作感は得られるのか」とか、「どのくらい速いマシンに乗り換えたら“重さ”を解消できるのか」といったところだろう。そこで、ここでは人間の“時間感覚”とパソコンの処理能力の間にある関係について考察してみたい。
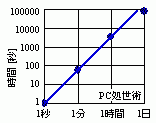 まず、人間の時間感覚というのは対数的であることを認識する必要がある。左の図は、横軸に人間が決めた「時間の単位」(つまり“秒”、“分”、“時間”)を取り、縦軸に「物理的な時間(秒)」をとったグラフで、縦軸は対数である。厳密な方法とは言えないが、グラフを見ると大体直線に近いことが分かる。
まず、人間の時間感覚というのは対数的であることを認識する必要がある。左の図は、横軸に人間が決めた「時間の単位」(つまり“秒”、“分”、“時間”)を取り、縦軸に「物理的な時間(秒)」をとったグラフで、縦軸は対数である。厳密な方法とは言えないが、グラフを見ると大体直線に近いことが分かる。
つまり人間の時間感覚は多分にロガリスミックなのである。例えば1秒2秒を気にしている時の“1秒”は十分に長く感じるが、“1時間2時間”を気にしている時の“1秒”が問題になることはない。誰も,待ち合わせ時間に1秒遅れたからと言って大問題にする者も、そうは居るまい。
さて、そうなると気になってくるのがコンピュータの処理能力と所要時間の関係、そして人間にとっての操作感との関係だ。「処理能力」と一口に言っても、それはCPUの処理スピードだけではなく、メモリの速度、描画速度、ストレージの速度やネットワーク速度などであったりするわけだが、ここではそういったものをひっくるめて「処理能力」と呼ぶことにする。そうすると、ある“処理”なり“演算”なりに対して掛かる所要時間は処理能力に反比例する。
この関係を縦横両対数のグラフにとったのが右の図である。「あるパソコンの処理能力を“1”としたときに“100秒”かかる作業に対して,処理能力が変化した場合の所要時間」がプロットされている。処理能力が10倍になれば10秒で済み、100倍になれば1秒で済むという当たり前の関係である。
さて、そこに筆者の主観ではあるが「人間の感覚」を分類して併記してみた。時間の長い方から説明すると,以下のような具合である。(当然、個人差はあると思う)
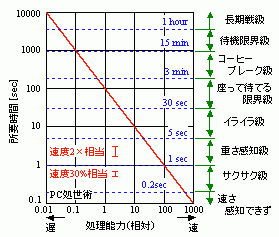
長期戦級(1時間以上): もはや長時間に亘って計算機に任せっきりにするレベル。計算機の前に座るのは、処理の最初と最後だけ(または全く計算機の前に座らない)で、PCでは就寝前などから開始する類の演算。
待機限界級(15分〜1時間): 処理時間中は計算機の前にはいないか別の作業を開始するが、処理が終わるまで計算機を気にしながら待機できる限界レベル。
コーヒーブレーク級(3〜15分): 処理時間中にコーヒーブレークを取ると、ちょうど処理が終了するレベル。このレベルの所要時間では、別の作業を始めたくなる。
座って待てる限界級(30秒〜3分): 処理時間中に計算機の前で座って待っていられる限界レベル。別の作業を開始するにはやや短く、「非常に重たい」と感じられる。
イライラ級(5〜30秒): 処理時間中に計算機の前で座って待たねばならなず、イライラが募るレベル。別の作業を開始するには時間が短すぎ、重たさにイライラする。
重さ感知級(1〜5秒): 処理時間が“長い”ことが人間に感知できるレベル。リアルタイムとは全く言えず、操作にひっかかりや重さをハッキリと感じる。気が短ければイライラする。
サクサク級(0.2〜1秒): 処理時間がまずまず短く、リアルタイムに近い操作感が得られるレベル。敏感な人には操作のひっかかりが気になるかもしれないが、大問題にはならない。
速さ感知できず(〜0.2秒): もやは人間にとってはほぼリアルタイムが実現できているレベル。この領域でパソコンが速くなっても普通は感知できないか、あるいは感知しても意味が無いことも多い。
このようにしてみると、所要時間が5,6分の1にならないと,時間感覚のレベルは変わらないということが分かる。逆に、レベルの違う操作感を得るには、計算機の処理能力比は5,6倍は必要だということである。
しかるに、現在市販されているパソコンの能力に目を向けてみると、ハイエンドとローエンドでせいぜい2倍程度の処理能力比だろうか。そして、普通に「速いグレード」と「遅いグレード」の比較をしても、せいぜい30%程度の処理能力ゲインといったところだろう(図中に赤いバーで示してある)。
要するに、「ある時点で市販されているパソコンのグレードの差は、操作感のレベルを変えるほどではない」ということだ。勿論、その微妙な差がクリティカルな場面もあるのだろうが、筆者には「パソコンのグレードの差よりも,世代の差の方がはるかに大きい」ように思われる。当サイトの各所で考察しているとおり、時間を経ることによるPCの進化は、大きな性能差を生むのである(19. Mar, 2005)。
パソコン性能のボトルネックの本質
当サイトでは何度も繰り返し書いている通り、パソコンの性能は常に向上しつづけてきた。その性能向上は、CPU,メモリ,HDD,通信のそれぞれで起こった。CPUのクロック周波数もかつては数メガHz であったものが今では数ギガHz に達し、データの転送速度もCPU近傍では GB/s という単位を聞くに至った。十数年前と比較すると、千倍を超える速度向上が図られてきた部分もあり、それは間違いないことだ。
にもかかわらず、「果たしてそんなに速くなったのか?」と疑問に思う瞬間が無いでもない。そしてそれらは、パソコンの処理速度にボトルネックがあるためだ、との声も聞く。だがこれまでも幾度となく“ボトルネック解消”を図ってきたという記事に出くわした。本当にボトルネックは解消されているのだろうか。
こうした疑問は、例えばパソコンの起動時間などで端的に感じるところだ。昔から、大体パソコンの起動時間というのは数十秒から1、2分というところだったろうか。これが千倍速くなって数十〜数百ミリ秒で済むようになったという事実は無い。その理由は、起動すべきOSも処理能力向上と共に大きくなったからにほかならないわけだ。
もっと原始的なところでは、起動時のメモリチェックに要する時間も昔から大体数秒であり、これもそういえばあんまり変わっていない。十数年前のメモリと言えばその転送速度は数十MB/s であって、今からすると相当遅かったのだが,容量もまた想像を絶する少なさだった(1MB以下)。
人間が“速い/遅い”を感じるのは,前回の考察でも書いた通り、それは時間が基準であると思われる。例えば 300GBの HDD の内容をコピーするのに、S-ATAの理論速度 150MB/s で転送できたとしよう。それは十分高速な筈なのだが、それでも転送終了には 30分以上を要し、人間にとっての待ち時間は結構なものになる(無論、実際には理論速度などムリなので、もっと時間は掛かる)。
このように、人間にとっての体感速度を決めるのは「転送速度」や「処理速度」のような“機器の速度スペック”だけではなく、“容量(もしくは処理対象とする情報量)とのバランス”だということを認識しておく必要があるように思う。
このことは、リムーバブル媒体の趨勢について考察したものとアナロジーは同じであり、常に「容量÷転送速度=時定数」の関係を持っていることを意識しておきたいところだ。この時定数は,“扱えるデータのサイズと、処理速度との比の目安”といったところである。時定数が数時間もしくは数日に及ぶようなデバイスは人間が扱うには大きすぎ(または遅すぎ)であり,数ミリ秒のようなデバイスは効果を発揮する情報量の範囲が限られる可能性があることを示唆する値である。
例えば、1GBの容量で 6.4GB/s (額面速度)のメモリを考えれば時定数は“1÷6.4=0.16秒”であるのに対して、300GBで150MB/s(こちらも額面)のHDDなら時定数は30分という具合だ。要するに、“全てメモリに乗ってしまうようなデータを扱う分には人間にとって不自由なくパソコンで扱えるが、HDDへの激しいアクセスを要求されるような大データを扱うのはそれなりに忍耐が要る可能性がある”ことを数字は示していると考えられる。
ここで重要なことは、容量が大きなデバイスほど遅いというPC関連機器が持つ傾向だ。もちろん、同じデバイス(例えばHDD)が進化していけば,速度も容量も向上してゆくことには間違いないのだが、ある時点におけるパソコン構成パーツの速度の序列からすると、レジスタ(&キャッシュ)>主記憶(メモリ)>補助記憶(HDD)なのであり、容量の序列とは相反するのが常なのである(更に、情報の揮発性とも相反する)。
そうすると、大容量データを扱うデバイスの時定数は著しく大きくなってしまう。そして扱うデータのサイズは常に大容量デバイスに引きずられる。このことが,大昔のPCと現代のPCとで起動時間に差を与えなかった原因とも言えるだろう。したがって、パソコンにとってのボトルネックは常に大容量側のデバイスにある、というわけだ。
そして筆者の観測によると、こうしたボトルネックはこれまでパソコンの世代が変わることによって解消されてきたように思う。つまり、CPUのクロックに代表される個々のパーツの細かい性能がボトルネックを解消してきたというよりは、HDDの記録密度(プラッタ当たり容量)と各種インターフェイスの規格,メモリアクセスの規格と方式といった“全取っ替え”を要求するような事象によって解消して来たという感が強い。逆にいうと、そういう部分の差がパソコンの世代を指しているのかもしれない。
(29. Aug, 2005)
PC処世術トップページへ
当サイトにある記事の著作権は M.Abe に属します。
なお、当サイトの記事の転載はご遠慮ください。
 だが、筆者の周りを見渡してみると、パソコンの買い替えサイクルは大体2,3年程度なのだという。この買い替えサイクルは,前述の機械的寿命よりも短い。必ずしも、古くなったパソコンは故障したために買い替えを向かえるということではないようだ。
だが、筆者の周りを見渡してみると、パソコンの買い替えサイクルは大体2,3年程度なのだという。この買い替えサイクルは,前述の機械的寿命よりも短い。必ずしも、古くなったパソコンは故障したために買い替えを向かえるということではないようだ。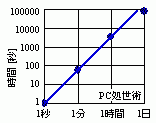 まず、人間の時間感覚というのは対数的であることを認識する必要がある。左の図は、横軸に人間が決めた「時間の単位」(つまり“秒”、“分”、“時間”)を取り、縦軸に「物理的な時間(秒)」をとったグラフで、縦軸は対数である。厳密な方法とは言えないが、グラフを見ると大体直線に近いことが分かる。
まず、人間の時間感覚というのは対数的であることを認識する必要がある。左の図は、横軸に人間が決めた「時間の単位」(つまり“秒”、“分”、“時間”)を取り、縦軸に「物理的な時間(秒)」をとったグラフで、縦軸は対数である。厳密な方法とは言えないが、グラフを見ると大体直線に近いことが分かる。