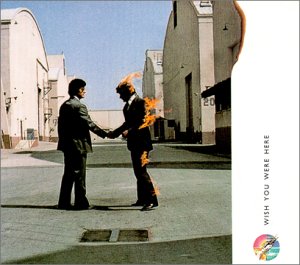2004.02.18.Wed. 10 : 40 a.m.
BGM : JIMI HENDRIX "ARE YOU EXPERIENCED ?"
 脱稿から一夜明けて起床すると、セガレがテレビ東京の『いい旅』という番組(再放送)を見ていた。「もうじき小学生」という意識が強いのか、そろそろ『おかあさんといっしょ』を卒業しようとしているようだ。にしても、朝っぱらから温泉かいな。画面の中では、デビ夫人と杉田かほるが新潟の温泉につかっていた。う〜ん、フォクシー・レディ〜。どちらかというと、脱稿の翌朝に見たいシーンではない。じゃあ、いつならデビ夫人の入浴シーンを見たいのかと訊かれると、返答に窮するけれど。しかし、去年箱根で露天風呂の気持ちよさをエクスペリエンスしたセガレは、画面を食い入るように見つめながら「行きてー」と呟いていた。仕事が一段落した途端に、このプレッシャーだ。はいはい。しばらく、どこにも連れてってなかったからね。温泉かー。行きてーなー。ところでジミヘンも、どちらかというと脱稿明けの朝9時半から聴きたい音楽ではなかったかもしれない。でも、かっこいい。ゆうべ仕事を終えた後に、スカパー!でグーリットの現役時代のゴール集のようなものを見たのだが、ジミヘンとグーリットはプレイのテイストがどこか似ているような気がする。それがどこなのかは、これから考える。
脱稿から一夜明けて起床すると、セガレがテレビ東京の『いい旅』という番組(再放送)を見ていた。「もうじき小学生」という意識が強いのか、そろそろ『おかあさんといっしょ』を卒業しようとしているようだ。にしても、朝っぱらから温泉かいな。画面の中では、デビ夫人と杉田かほるが新潟の温泉につかっていた。う〜ん、フォクシー・レディ〜。どちらかというと、脱稿の翌朝に見たいシーンではない。じゃあ、いつならデビ夫人の入浴シーンを見たいのかと訊かれると、返答に窮するけれど。しかし、去年箱根で露天風呂の気持ちよさをエクスペリエンスしたセガレは、画面を食い入るように見つめながら「行きてー」と呟いていた。仕事が一段落した途端に、このプレッシャーだ。はいはい。しばらく、どこにも連れてってなかったからね。温泉かー。行きてーなー。ところでジミヘンも、どちらかというと脱稿明けの朝9時半から聴きたい音楽ではなかったかもしれない。でも、かっこいい。ゆうべ仕事を終えた後に、スカパー!でグーリットの現役時代のゴール集のようなものを見たのだが、ジミヘンとグーリットはプレイのテイストがどこか似ているような気がする。それがどこなのかは、これから考える。
逃避力がゼロのせいか、もう書くことが思いつかない。夕刻からのレッスンに備えて、ギターの練習をしておこう。レッスンに臨むときは、自分なりに課題や疑問点を整理しておくことが大事だ。……などと書いていたら、PHPから次の仕事の資料が宅配されるのだから世の中うまくできている。はいはい。口述開始までに、課題や疑問点を整理しておけってことですね。もっとも、最大の課題は内容云々ではなく、私自身のスピードなんですが。うー。また逃避力がムクムクと。しかし次の仕事は久しぶりにスポーツ関係なので、ちょっと楽しみ。
2004.02.17.Tue. 24 : 20 a.m.
BGM : JIM HALL "CONCIERTO"
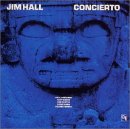 ふいー。更新が滞っていたのは、FAカップでチェルシーがスペイン人のガキに沈められたショックで寝込んでいたからではなく、脱稿目指して原稿を書いて書いて書きまくっていたからである。やっと終わった。「遅くとも1月中には」などと自己申告していた原稿が2週間以上も遅れたのは、2月に書く予定だった仕事が著者の都合で先送りになって目の前に広大なスペースが開けてしまったことが最大の原因であるが、しかしそれにしてもこの遅筆ぶりはおそらくもう治らないような気がしてきましたよ編集者のみなさん。困らせて申し訳ないが、私も困っているので勘弁してくれ。もうね、昔みたいなペースでは書けないんです。書けないんです書けないんです。まあ、それでも雑誌の原稿はほぼ〆切守ってるんですけどもね。単行本のゴーストが大詰めを迎えていたこの週末にも、「わしズム」の〆切は完璧に守った。たぶん次の「裏わしズム」には、シギーさんが「深川は〆切を守ったからえらい」と書いてくれるだろう。でも、単行本はダメだ。ぜんぜん、えらくない。だから、えらくないことを承知の上で発注してほしい。ものすごく弱気になっている。それにしてもジム・ホールのアランフェス協奏曲はいいなぁ。たまにはジャズでもと思って久しぶりに聴いたらハマってしまい、この2日間で30回ぐらい聴いている。この構成、このテンポで、同じ曲をロックの音で演れないだろうかなどという妄想が広がる今日この頃。明日は、久しぶりの虎の穴レッスンである。
ふいー。更新が滞っていたのは、FAカップでチェルシーがスペイン人のガキに沈められたショックで寝込んでいたからではなく、脱稿目指して原稿を書いて書いて書きまくっていたからである。やっと終わった。「遅くとも1月中には」などと自己申告していた原稿が2週間以上も遅れたのは、2月に書く予定だった仕事が著者の都合で先送りになって目の前に広大なスペースが開けてしまったことが最大の原因であるが、しかしそれにしてもこの遅筆ぶりはおそらくもう治らないような気がしてきましたよ編集者のみなさん。困らせて申し訳ないが、私も困っているので勘弁してくれ。もうね、昔みたいなペースでは書けないんです。書けないんです書けないんです。まあ、それでも雑誌の原稿はほぼ〆切守ってるんですけどもね。単行本のゴーストが大詰めを迎えていたこの週末にも、「わしズム」の〆切は完璧に守った。たぶん次の「裏わしズム」には、シギーさんが「深川は〆切を守ったからえらい」と書いてくれるだろう。でも、単行本はダメだ。ぜんぜん、えらくない。だから、えらくないことを承知の上で発注してほしい。ものすごく弱気になっている。それにしてもジム・ホールのアランフェス協奏曲はいいなぁ。たまにはジャズでもと思って久しぶりに聴いたらハマってしまい、この2日間で30回ぐらい聴いている。この構成、このテンポで、同じ曲をロックの音で演れないだろうかなどという妄想が広がる今日この頃。明日は、久しぶりの虎の穴レッスンである。
2004.02.15.Sun. 15 : 45 p.m.
BGM : JIMMY PAGE "OUTRIDER"
セガレの所属する水色チーム(いい色だ)は、まず黄色チームと対戦。なかなか手強い相手で、とくに強引な突破力を誇る1番とゴール前での嗅覚に優れた2番はかなり危険な選手だった。しかし水色チームにも、炎のストライカー・小次郎くん(仮名)と、物静かなテクニシャン・岬くん(仮名)がいる。いちおう、セガレもいる。なので、拮抗した好勝負だった。
小次郎くんは朝が弱いのかいつもの力強さがなく、そのため黄色チームに押し込まれる場面も多々あったが、岬くんの冷静な守備とボールキープ力のお陰もあって何とかしのぎ、そうこうしているうちにカウンターから水色チームが先制。直後にセガレがGKになったので、かなりのプレッシャーを感じた。誰がって私がだ。うー。しっかり守らなければ。当然、すぐにゴール裏へ走ってコーチング開始。するといきなり黄色チームのカウンターだ。わわ。センターライン付近でボールを奪った1番が独走してくる。あわわわ。どうしようどうしよう。おいおい完全にセガレと一対一じゃないか。抜かれたら同点になっちゃうじゃないか。R太郎、はやく前へ出ろ。前だ前だシュートさせるなボールに食らいつけええええええ。
見事なクリアだった。1番がペナルティエリアに侵入したところで、勇気を持って体を寄せたセガレがボールを蹴り出し、すんでのところで事なきを得たのだった。しかし黄色チームの攻勢は続く。しばらくしてセガレはフィールドに戻ったものの、終盤の水色チームは雨アラレとシュートを浴びて七転八倒。どうして失点しなかったのかよくわからないが、早稲田のゴール前ディフェンス(ラグビーの話ね)のような集中力を見せて1-0の辛勝である。いやー、荒ぶった荒ぶった。
これで銀メダル以上が確定するのだから楽なものだが、だからこそ2位では我慢できない。優勝あるのみ。どうして公式戦になると結果にこだわっちゃうのかなぁ。しょうがないなぁ父さん。決勝の相手は黒チームである。1回戦は緑チームとスコアレスドローに終わり、抽選で勝ち上がってきたチームだ。決勝の前に行われた3決では黄色チームが緑チームに3-0ぐらいで圧勝していたので、そんな緑チームと引き分けた黒チームは、理論上(黒=緑<黄色<水色)、明らかに水色チームより弱い。ふふふ、もらったな。
でも黒チームは強かった。豊富な運動量とすばやい出足で序盤から圧倒的にボールを支配し、カサにかかって攻め込んでくる。水色チームは防戦一方。しかし黒チームは決定力だけが決定的に不足していたので助かった。6歳児のカテゴリーともなるとかなりサッカーらしくなってくるもので、そう簡単にシュートチャンスは与えてもらえない。どちらもゴールを割れないまま、試合は終盤へ。水色チームも何度か反撃を試みたものの、相手の守備が実に厚い。結局、試合はスコアレスドローに終わったのだった。水色チームが(親も子も)火の玉になって攻め込んでいた終了直前、タッチライン際で観戦していた私の足元にボールが転がってきたときは、思わず全身の力を込めてシュートしてしまいそうだった。すでに前へ踏み込まれた左足の膝はかすかに曲げられ、右足は後方に引かれていた。コースも完全に見えていた。よく我慢できたものだ。
で、延長戦もPK戦も行われず、勝敗は抽選に委ねられたのである。勝ち点でいえば水色4・黒2、得失点差でいえば水色+1・黒0、総得点でいえば水色1・黒0なんだから、水色の優勝でいいじゃーん。トーナメントだから関係ないとは言え、大会のパンフレットにも(意味がよくわからないのだが)「勝敗が同じ場合は得失点差で勝敗を決めます。それでも同じ場合は監督による抽選」と書いてあるのだ。どうもリーグ戦と勘違いして書いてるような気がして仕方ないのだが、とにかく「得失点差」という概念がこの大会に存在するのは間違いない。しかしフィールドでは、両チームの監督(先生)がクジを引き始めた。で、あろうことか黒チームの監督が1回戦に続いて「勝ち」を引き当てやがったのである。一つの勝利も(そして一つのゴールも)上げられなかったチームが優勝して金メダルをもらったのである。ものすごく納得がいかない。小次郎君も泣いていた。ほんとうに悔しそうだったので抱きしめてあげたかったが、それは小次郎君のお父さんとお母さんの仕事なのでやめておいた。もちろんセガレも不納得な顔をしていたので、「いちばん運がよかったのは黒チームだが、いちばん強かったのはおまえたちだ」と言ってやった。銀メダルおめでとう。
ラツィオ戦の中継が録画を含めて一切ない今節のセリエだが、エンポリを3-0で一蹴したらしい。なんかやけに強いな最近。パルマに3-0、ミランに4-0(コッパ)、エンポリに3-0で、私の計算がたしかならば3試合で10ゴールじゃないか! 10ゴールのうち7ゴールも見られないなんてひどいじゃないか! しかも、またコウトが決めたようだ。どうなってんだコウト。EUROに向けてコンディション上がってきたのか。彼の場合、コンディションがどうとかという問題ではないと思うが、なんかノリノリな感じ。さらに昨日はスタムもゴールを決めたんだとか。見てえなあチクショー。
2004.02.14.Sat. 16 : 20 p.m.
BGM : THE ROLLING STONES "LET IT BLEED"
IN THROUGH THE OUT DOOR
聖バレンタインデー特別編
「お客さん、しばらくだったね」
もうここには来ないつもりだったんだけど……
家に居てもチョコとか届かないし……
ちょっと昔話もしたくなったもんでね。
「昔話?」
もう5年ぐらい前の話だけど……
カズも危ないところだったよな。
それともあれは……
トルシエが勝手に燃えてたのかな。
そういう男かもしれないよな。
「いわゆる一つの燃える男っていうの?」
「話はそれだけかよ」
2004.02.13.Fri. 18 : 00 p.m.
BGM : THE ROLLING STONES "EXILE ON MAIN ST."
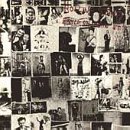 ちょっと説明が足りなかったような気がするので、べつに頼まれもしないのに補足しておくと、ES細胞を使った医療というのは、まず「再生医療」という大枠の中に位置づけられるべきものなんだな。ここんとこを最初に把握しておかないと、
ちょっと説明が足りなかったような気がするので、べつに頼まれもしないのに補足しておくと、ES細胞を使った医療というのは、まず「再生医療」という大枠の中に位置づけられるべきものなんだな。ここんとこを最初に把握しておかないと、細胞(や細胞の機能)を失うことで起きる病気はたくさんあって、きのう書いたパーキンソン病や糖尿病(食い過ぎや運動不足でなるやつじゃなくて「インシュリン依存型=1型糖尿病」のほうね)は、その代表例。失ったものを取り戻せば治るわけだから、これらの病気を細胞移植で治療しようというアイデアは、生物学業界でES細胞の研究が始まる前から医学業界にあった。いや、「前から」かどうかはよくわかんないけど、とにかく再生医療としての細胞移植は「はじめにES細胞ありき」ではなかったわけね。たとえば、これは昨日も書いたけど、中絶胎児の脳細胞をパーキンソン病患者の脳に移植するというのも、その試みの一つだわな。患者が失ったドーパミン産生細胞(パーキンソン病ってのはドーパミンが出なくなっちゃう病気なんです)を、中絶胎児のドーパミン産生細胞で補おうって寸法よ。これはそれなりに効果が期待できたんだけど、移植用の細胞が入手しにくいのがネックなのは、ほかの臓器移植と同じ。「インフルエンザの特効薬が不足してま〜す」どころの騒ぎじゃない。ぜんぜん、足りない。中絶胎児からの移植だって、一人の患者に一人分じゃないからね。数字は忘れちゃったけど、患者一人治すのに中絶胎児が何体も必要になるんだよ。耳をふさぎたい気持ちはわかるけど、そういうことなんだよ細胞移植って。そんなこんなで医学業界が「どうしたもんかのう、困ったのう」と言ってたときに、生物学業界のほうでは「なんや細胞ようけ要るんやったら、試験管の中で増やせそうでっせ」っちゅう話になっとったわけやね。そこで初めてES細胞やらクローニングやらが再生医療と結びついてくる。
するとだな、いささか話は飛躍するのだが、その先には必ず「医療って何だ」という問題が待っているわけですよ。だって考えてもみなさい。オールマイティのES細胞を自由自在に分化させることで、失われた細胞を何から何まで取り戻せるとなったら、当然「老化」がそのターゲットになるでしょうが。人体はおよそ60兆個の細胞で出来ているわけで、老化ってのはその細胞が老いることだからね。老化は自然現象で病気じゃないとはいえ、何らかの苦痛を伴うのが常だから、失った「若さ」を取り戻せるなら取り戻したいってのが人情だ。でも、それが医療の役割なのかと考えると、と〜っても微妙。もっと言っちゃえば、老化の先には「死」ってやつがあるわけで、こりゃ「命を失う」ってことであるんである。さて、それではここで問題です。死の際に「人体から失われたもの」は、再生医療の対象となるんでしょうかどうなんでしょうか……このあたりは「いや〜ん、クローン人間って怖〜い」ってところで思考停止(せざるを得ないのかもしれんけど)しているような新聞報道からはなかなか見えてこないので、やっぱりみんな『痛快!人体再生学』を読んで勉強しよう。この本に書いてあることは、これからの人間社会を考える上で欠かせない教養の一つだと私は思う。
そもそも人の「死」とは「人体」から命が失われる現象なんでしょうか。生命はどこに宿っているんでしょうか。どこかに宿っているものなんでしょうか。
2004.02.12.Thu. 22 : 10 p.m.
BGM : 細野晴臣 "TROPICAL DANDY"
 そうかー。韓国では作ってたのかー。
そうかー。韓国では作ってたのかー。というのは何の話かというと、写真と本文は例によってぜんぜん関係ないのであって、「ヒトクローン胚からES細胞作成に成功 韓国の研究者ら」(朝日)「クローン技術で万能細胞…韓国で世界初の成功」(読売)というニュースの話である。どういうわけか私はこの話にちょっと詳しいので、自分の知識を整理する意味も含めて書いてみると(間違ってたらゴメン)、そもそもES細胞(Embryonic Stem Cell=胚性幹細胞)というのはですね、これから様々な器官に分化していく胚盤胞(受精卵が胎児のカタチになる少し前の段階だと思えばよかろう)から取り出してシャーレの中で培養した万能幹細胞(厳密には「万能」ではなく「多能性幹細胞」)のことなんだな。幹細胞(stem cell)ってのは、「枝」に対する「幹」みたいなもんだと思えばいいんだな。幹細胞から、いろんな機能を持った細胞が派生していく(これを細胞の「分化」という)わけなんだな。たとえば神経幹細胞は神経細胞にしか分化しないけど、ES細胞はあらゆる細胞に分化できるんだな。最近は神経幹細胞などの体性幹細胞にも多能性がありそうだという話になっているけど、とりあえずそれはまた別の話なんだな。
そういうわけで、試験管の中で生きているES細胞の「枝分かれ」を人の手でコントロールして、たとえばドーパミン産生細胞に分化誘導できればパーキンソン病が治療できる(TVに復帰したマイケル・J・フォックスも病人以外の役ができるようになるだろう)し、インシュリン産生細胞に分化させられれば糖尿病を治せる(つまり細胞の欠損に起因するあらゆる病気を治せる可能性を持っている。もしかしたら五体不満足なボディから手足がニョキニョキ生えてくるかもしれない……とまで言うと極端すぎるが可能性はゼロではない)という話だ。これまでは、たとえば中絶胎児の脳細胞をパーキンソン病患者の脳に移植する、なーんていう実験治療も北欧あたりを中心に行われていた(成功例も結構あった)そうだが、ES細胞があれば試験管の中で必要な細胞を作れるようになるんですね。すごいすごい。
もっとも、「万能」「多能」というのはあくまでもポテンシャルの話であって、たとえ無限に増やせるES細胞株の樹立に成功しても、それを試験管の中で特定の機能を持った細胞に目論見どおり分化させるのがまた厄介なのだが(むしろ今はそちらの研究のほうで熾烈な競争が起きている)、ともあれ、まずはES細胞の「タネ」にする胚盤胞をどこから持ってくるかというのが、研究上の大きなモンダイの一つなのである。細胞は試験管の中で増やすことはできてもゼロから作ることは(今のところ)できないので、最初は生き物から取ってくるしかないわけやね。どうやって調達しようと、「もともとは生き物」という点では、中絶胎児から頂戴してくるのと変わらない。
で、ヒトES細胞を作る以上は、そのドナーは「ヒト」ということになる。ES細胞の研究がマウスで行われていたときはいくらでも調達できたけれど、ヒトから頂戴するのはいろいろあってアレだ。なにしろ受精卵だから、子宮に置いておけばそれはヒトになるんである。というか、見方によってはすでにヒトかもしれない。私の記憶がたしかならば、少なくともバチカンはそれをヒトだと言っている。受精卵がヒトじゃないっておっしゃるなら一体どっからヒトになるんですかバカにもわかるように説明してください、っちゅうような話だよ。こういうコトはいろいろ大変なんだよ真面目に考え始めると。
しかしそれはともかくとして、日本でもあれは去年だったか一昨年だったか、人工授精医療の現場で余った受精卵(無事出産に成功したら予備として作っておいたやつが不要になるわけで、そういうモノ−バチカンに言わせりゃ「ヒト」−が山ほど「余って」いるということ自体がドキドキするような話なのだが)を、「持ち主」である夫婦の了解を得た上でES細胞の「タネ」にすることが認められた。カネもかかるから永遠に保存しとくわけにもいかんし、いずれ廃棄しちゃうなら研究に役立ててもまあよかろう、ということだわな。「本人」の了解を得るのは無理だから、それはまあ仕方がない。安楽死や尊厳死もそうだが、生命の「両端」に関わる医療は本人のインフォームド・コンセントを取るのが難儀なのである。植物人間になってしまってから「死なせてもいい?」とは訊けないし、受精前に「試験管で混ぜ混ぜしてもいいかしら?」とも訊けないのだった。そりゃまあ、試験管を使わない「混ぜ混ぜ」だって、(相手の了解は得たほうがいいと思うが)「本人」の了解は得られないわけですけどもね。人生すべて事後承諾だ。子供は親を選べない。許せR太郎。
さて、ここからが問題なのであって、余り物の人工受精卵から作ったヒトES細胞株は読売の記事にもあるとおり日本でもすでに京大で樹立されているのだが、これは患者にとって見知らぬ他人の細胞なので、仮に必要な細胞への分化に成功して患部に移植したとしても、拒絶反応によって治療効果が得られないことがある。そこで浮上するのが、クローン技術なんだな。誰かの卵子から細胞核を抜き取って、そこに患者本人の体細胞(皮膚だろうが骨だろうが細胞には一人分のDNAが全部揃ってるから理論的にはどの部位でもよろしい)から取った細胞核を埋め込んでやれば(これが「ヒトクローン胚」ですね)、そこから作ったES細胞は100パーセント自分のDNAを持っているのだった。これを「マイES細胞」と呼んだりして(今回の韓国のケースでは体細胞の提供者が女性のようだから「ハーES細胞」か)、その世界では、拒絶反応が絶対に起こらない究極のES細胞だと目されておったわけだよ。輸血(これも一種の細胞移植なわけだが)になぞらえて言えば、他人の血液をもらうのではなく、あらかじめ自分の血液を培養してボトルキープしておく、というような話だ。分化誘導さえ自由自在にできるようになれば、角膜だろうが皮膚だろうがあらゆる細胞移植に対応できるってわけ。うーん、安心安心。
しかし、だ。この「自分の細胞核を埋め込んだ受精卵」をマイES細胞のタネにせず、そのまま子宮に戻してやるとどうなるかというと、これはもう言うまでもない。いろいろなことがうまく運んで出産までこぎつければ(そこにも何かと乗り越えがたい障壁があるのだがそれはともかく)、自分のクローンになりやがるんだぜベイビー。このあいだお亡くなりになった羊のドリーちゃんも、そうやって生まれた。ここに倫理的な問題ってやつが出てくるのでありまして、だったら希望する細胞に分化させるのが容易ではないES細胞なんてかったるいじゃーん、自分のクローン作って冷凍保存でもしときゃ、細胞どころか臓器丸ごと拒絶反応なしに移植できるじゃーん、って話にもなっていくわけですな。自分の全身バックアップだ。ハードディスクがクラッシュしても、MOにコピーがあるからオッケーさ。いやはや、便利便利。いや、おそろしやおそろしや。そんなこともあって、クローン人間の一歩手前の段階とも言える「マイES細胞」の研究には、日本をはじめとしてゴーサインが出ていない国が多いわけだが、しかし韓国ではオッケーだったらしい。これ、うまくすりゃ莫大な経済効果を生じさせる研究ですからね。「いいから、やっとけやっとけ」という国があるのも無理はないだろうと思われるのだった。解禁しとけば、禁止されてる国から「優秀な頭脳」ってやつも入ってくるだろうしな。
 というわけで、私だってサッカーやロックにばかりウツツを抜かしているわけではなく新聞も読んでるんだということを示す意味もあって、珍しくニュース解説の真似事をしてみました。しかしあんまり自信がないので、興味のある人には右に掲げた西川伸一『痛快!人体再生学』(集英社インターナショナル・本体2200円)を御一読されることをオススメするわけだが、まあ、こういうモンダイはほんとうに難しい。とっくに「クラスに一人は試験管ベビー」みたいな状態になっている(いや2クラスに一人ぐらいの割合だったかな。とにかく、それぐらいは生まれているらしい)ことを考えれば、ここで躊躇するのも「何をいまさら」な話だ。
というわけで、私だってサッカーやロックにばかりウツツを抜かしているわけではなく新聞も読んでるんだということを示す意味もあって、珍しくニュース解説の真似事をしてみました。しかしあんまり自信がないので、興味のある人には右に掲げた西川伸一『痛快!人体再生学』(集英社インターナショナル・本体2200円)を御一読されることをオススメするわけだが、まあ、こういうモンダイはほんとうに難しい。とっくに「クラスに一人は試験管ベビー」みたいな状態になっている(いや2クラスに一人ぐらいの割合だったかな。とにかく、それぐらいは生まれているらしい)ことを考えれば、ここで躊躇するのも「何をいまさら」な話だ。
そう言えば何日か前には、「男女産み分けに着床前診断」という報道もあったが、これだって、子供は親を選べないのに親が子供を選ぶのはアンフェアだと思わなくもないものの、やりたい患者(「患者」なのかそれは)とやりたい医師がいれば、そりゃあ、やるだろう。「病気の治療・予防に限定すべきだ」って言ったって、「あたし、男の子ばっかり8人も生まれちゃって、もうノイローゼになりそうなんですぅ。だから予防して〜ン」なんて言われたら困っちゃうしね。何が病気で何が健康か、きっぱり線を引くのは難しい。ついでに言えば「病気の治療」と「病気の解決」の境目も微妙なところで、たとえば人工授精だの代理母だのといった手段が不妊の「治療」と言えるのかどうか、私にはよくわかりません。治ってないし。とはいえ、たとえば義手や義足や入れ歯だって「治って」はいないが失われた機能を取り戻すための立派な医療なのであって、治療だけが医療ということはないんである。ふう。書いてて疲れてきました。
こういったアレやコレやが将来どんな事態を招くかは、たぶん、誰にもわからない。神様に訊いても、「ンなもん、俺の知ったことかよ」とヘソを曲げるだろうしなぁ。しかし、たとえば輸血にしたって「わからないけど、やってみよう」と死にかけた王様に若い男から搾り取った血を飲ませた(むろん王様も若い男も死んだ)ところから始まっていたりするわけで、医学の進歩というのはそういうものだ。本当なら「試験管ベビーのその後」とか(さらには「試験管ベビーを親とする試験管ベビーのその後」とか「試験管ベビーを親とする非試験管ベビーのその後」とか「試験管ベビーと非試験管ベビーを親とする試験管ベビーのその後」とか「試験管ベビーと非試験管ベビーを親とする非試験管ベビーのその後」とか)を追跡調査して疫学的に統計でも取らないといけないような気がするが、そりゃまた人権だ何だって話になるし、試験管ベビーにとってネガティブな結果になるとは限らないわけで、万が一「東大合格者の75パーセントが試験管ベビーでしたっ」とか「試験管ベビーのほうが平均寿命が5年も長いですっ」なんて結果になったら、それはそれでえらいこっちゃである。フツーに妊娠できる女(やフツーに妊娠させられる男)が「負け犬」なんて話にもなりかねん。わーお。ちょっと刺激が強すぎましたか。でも、そんなことだって、あり得ないとも言い切れないよな。
「混ぜ混ぜ」って、かなり秀逸な婉曲表現だと思わない?
2004.02.12.Thu. 10 : 50 a.m.
BGM : THE ROLLING STONES "BEGGARS BANQUET"
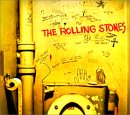 なにしろストーンズはキャリアが長くてアルバムも山ほど出ているので、どれがいつ頃の作品なのかもよくわからず、さすがにデビュー作から順に聴けとは誰も言わないだろうし言われても断るが、とりあえずこれまで聴いたアルバム(『BLACK AND BLUE』『DIRTY WORK』『SOME GIRLS』『STICKY FINGERS』『IT'S ONLY ROCK'N ROLL』)には一つもハズレがない。もしかして、滅多に三振もしないがホームランも少ないアベレージ・ヒッターなんだろうか。ロック界の篠塚なのか。おまえら不良のくせにそんな偏差値秀才みたいな態度でいいのか!と思わないでもないが、だから長くやってられるのかもしれない。ともあれ、今さらながら大した人たちである。「大した人」と書いて「オトナ」と読むのかどうかは知らない。
なにしろストーンズはキャリアが長くてアルバムも山ほど出ているので、どれがいつ頃の作品なのかもよくわからず、さすがにデビュー作から順に聴けとは誰も言わないだろうし言われても断るが、とりあえずこれまで聴いたアルバム(『BLACK AND BLUE』『DIRTY WORK』『SOME GIRLS』『STICKY FINGERS』『IT'S ONLY ROCK'N ROLL』)には一つもハズレがない。もしかして、滅多に三振もしないがホームランも少ないアベレージ・ヒッターなんだろうか。ロック界の篠塚なのか。おまえら不良のくせにそんな偏差値秀才みたいな態度でいいのか!と思わないでもないが、だから長くやってられるのかもしれない。ともあれ、今さらながら大した人たちである。「大した人」と書いて「オトナ」と読むのかどうかは知らない。
この『BEGGARS BANQUET』も、よくわからないまま中古店で目にしたジャケットが気に入って買った(私の持っているものは写真ほど黄色くない)のだが、右中間を深く破る三塁打ぐらいのアタリだったので嬉しかった。調べてみたら世間的にも「大名盤」であるらしく、なんだよ早く言ってくれよって話だが。
で、『悪魔を憐れむ歌』だ。なるほど1曲目の『Sympathy For The Devil』の邦題がソレなのかぁと思ったのは、同じ邦題の映画をテレビで観たことがあったからである。デンゼル・ワシントン主演の「シリアスなえんがちょ」みたいなオハナシのやつね。邦題がストーンズの曲と同じだと言いながら、劇中で重要な役割を果たす歌はストーンズの別の曲(Time Is On My Side)だったりするので、じゃあ『悪魔を憐れむ歌』ってどんな歌なんだろうとずっと気になっていたのだった。こういう歌か。かっこいい歌だ。でも、どうやらこの曲も映画のエンディングで流れていたらしい。WOWOWで観たから最後までやったと思うんだけど、ぜんぜん記憶がないや。もう一度、映画を観たくなった。どうでもいいようなオハナシなのに、妙に印象に残る不思議な映画だったし。
中学時代の同級生のうち唯一いまでも交流のある男から、メールで結婚式の招待状が届いた。へえ。驚かせるなぁ。あいつの辞書に結婚という言葉があるとは思っていなかった。これぐらいの年齢になると、もう同年代の友人はあらかた結婚して(あるいは結婚し終わって)おり、次に結婚式に出席するのは甥や姪が大人になってからだろうと思っていたので、なんだか新鮮だ。めでたいのう。
2004.02.10.Tue. 21 : 40 p.m.
BGM : LED ZEPPELIN "渋い飛行船"
だからというわけでは全然ないのだが、きょう吉祥寺で昼飯を食ったついでにまたフラフラと中古レコード&CD屋に立ち寄ったら、復刻版の紙ジャケットシリーズが各1000円で4タイトル(1と2と3とプレゼンス)並んでおり、財布にその店のサービス券が1500円分あったこともあって、つい全部買ってしまったのだった。嗚呼。何をしてるんだ私。音はどれも持っているのに。早くもメンタリティがマニアのそれに近づいているような気がして怖い。ちなみに同じ棚にはブートも何枚か並んでいて、眺めていたら冷や汗が出てきた。ああ、俺ってば興味津々だ。欲しがってる。手を伸ばして曲目をチェックしている。欲しがってる欲しがってる、こいつ欲しがってるぞオイ。その世界に足を踏み入れるとどういうことになるかというのは、アルコ弾きで有名なバッヂのギタリスト氏から先日お話をうかがったばかりなのに。とりあえず今日のところは堪えたが、どうなることやらである。
しかし、あれだ。Kay'n師匠をはじめ復刻版紙ジャケットをあまり快く思っていない人が少なくないので、これは小さい声でコソコソと言うのだが、私、あんがい好きかもしれない。紙ジャケ。なんかこう、精巧にできたミニカーみたいで可愛いじゃないか。「3」なんて、こんなに小さいのにちゃんとクルクル回るんだぜ。机の上にちょいと置いとくにしても、プラスチックより風情があるし。って、そういう心理につけ込まれていると言えばつけ込まれているわけだが、中古で1000円なら、まあねぇ。10枚組は仕事場用、紙ジャケは家庭用という考え方もあるしな。うんうん。誰に向かって何を言い訳しているのかよくわからないが、それにしても「IN THROUGHT THE OUT DOOR」は復刻版も6種類出てるんだろうなぁ、きっと。……なんかゾクゾクしてきた。
えーと、忙しいので手短に済ませますが、ちゃんとサッカーも見てます。ラツィオもチェルシーも勝って嬉しいです。パルマって、すげえ弱いんでやんの。あれじゃ生中継してもらえんわなぁ。と、人のせいにしてみました。
2004.02.09.Mon. 16 : 55 p.m.
BGM : LED ZEPPELIN "EDOGAWA'S BOX"
とはいえディスク1枚で収まるはずもないので、タボン君に借りて最初に聴いたやつにならって、4枚組ボックスセットの製作(箱はいずれ工作好きなセガレに作ってもらおう)に踏み切ることにしたのである。まだCD-Rに焼かずにiTuneに演奏させてMacで聴いている段階なので、内容や曲順は変更される可能性があるが、おおよその構成はこんな感じ。
ほとんど中学生レベルのテーマ設定であり、緩急もへったくれもない「これでもかこれでもか」の構成になっているわけだが、それでも飽きたり胸焼けしたりしないところがレッド・ツェッペリンの偉大なところである。しかも、似たテイストの曲を並べるとそれぞれが足を引っ張り合って埋没するかと思いきや、かえって1曲ごとの輪郭が際立つケースもあるということがわかった。とくに「DISC 2」は、オリジナル・アルバムではあまり目立たずサラリと聴き流してしまう曲が多いのだが(そんなことないですか)、こうして立て続けに聴いてみると、「アレもコレもこんなに美しかったのかぁ!」と感動を新たにするから不思議だ。改めて、このバンドの底知れない力量を感じざるを得ない。底なんか無いのかもしれない。ちなみに各ディスクの1曲目は、いずれも「
Edogawards' LZ sellection【BOX SET】【NOT FOR SALE】
Led Zeppelin

ディスク枚数:4
価格:売らないっつうの。
発送可能時期;送らないっつうの。
Disc 1:かっこいい飛行船
01. ROCK AND ROLL 3:40
02. CUSTARD PIE 4:13
03. FOR YOUR LIFE 6:24
04. GOOD TIMES BAD TIMES 2:46
05. BLACK DOG 4:57
06. WHOLE LOTTA LOVE 5:34
07. HEART BREAKER 4:14
08. MISTY MOUNTAIN HOP 4:38
09. HOUSES OF THE HOLY 4:02
10. TRAMPLED UNDER FOOT 5:36
11. WEARING AND TEARING 5:31
12. CAROUSELAMBRA 10:34
13. THE SONG REMAINS THE SAME 5:30
14. ACHILLES' LAST STAND 10:25
Disc 2:美しい飛行船
01. STAIRWAY TO HEAVEN 8:03
02. THE RAIN SONG 7:39
03. BABE I'M GONNA LEAVE YOU 6:41
04. OVER THE HILLS AND FAR AWAY 4:50
05. THAT'S THE WAY 5:37
06. THANK YOU 4:49
07. NIGHT FLIGHT 3:37
08. RAMBLE ON 4:24
09. TANGERINE 3:10
10. GOING TO CALIFORNIA 3:31
11. HEY HEY WHAT CAN I DO 3:56
12. YOUR TIMES IS GONNA COME 4:34
13. I'M GONNA CRAWL 5:30
Disc 3:渋い飛行船
01. WHEN THE LEVEE BREAKS 7:07
02. SINCE I'VE BEEN LOVING YOU 7:23
03. I CAN'T QUIT YOU BABY 4:42
04. THE ROVER 5:37
05. YOU SHOOK ME 6:28
06. DAZED AND CONFUSED 6:26
07. IN MY TIME OF DYING 11:06
08. NOBODY'S FAULT BUT MINE 6:16
09. NO QUARTER 7:00
10. SICK AGAIN 4:43
11. TEA FOR ONE 9:26
Disc 4:謎の飛行船
01. FOUR STICKS 4:45
02. ROYAL ORLEANS 2:59
03. THE CRUNGE 3:17
04. CELEBRATION DAY 3:29
05. BRING IT ON HOME 4:19
06. KASHMIR 8:28
07. BOOGIE WITH STU 3:53
08. MOBY DICK 4:21
09. FRIENDS 3:54
10. GALLOWS POLE 4:56
11. BRON-Y-AUR STOMP 4:16
12. FOOL IN THE RAIN 6:13
13. IMMIGRANT SONG 2:25
14. LIVING LOVING MAID 2:39(BONUS TRACK)
 」から持ってきてみたんじゃがの。様式美の一端じゃと思ってもろうたらよろし。しかし楽しいなぁ、こういう作業って。
」から持ってきてみたんじゃがの。様式美の一端じゃと思ってもろうたらよろし。しかし楽しいなぁ、こういう作業って。