2004.03.02.Tue. 21: 35 p.m.
BGM : PFM "ULISSE"
そんでもって今日も午後からシギーと「わしズム」の対談取材。待ち合わせ場所の自由が丘に早く着いたので、駅前の書店に入って次回新書の会の課題図書を買おうとレジに並んでいたら、前の女性がゆうべ打ち上げをしたその本を『号泣する準備はできていた』と一緒に買っていたのでドキドキした。その荒い文章を直木賞受賞作と併読されたのでは、いたたまれないじゃないか。その場で奪い取って赤入れしたかったぐらいだ。それにしても、私もけっこう長くこの商売をやっているが、ゴーストした本のお買い上げ現場に遭遇したというのは記憶がない。どうして買うのか問い質したくてたまらなかった。だって、『号泣する準備はできていた』と併読されるような本では絶対にないんだよ。その本のタイトルを書けないのが悔しいが、あえて言うなら、浜崎あゆみと鳥羽一郎のCDを一緒に買うのと同じぐらい異様かも。人の購買動機って、ほんとうに謎だ。
そんなこんなで外出する用事が多い今日この頃。明日も午前中から打ち合わせ、午後から口述取材、夕刻からギターのレッスンという感じなので、日誌の更新はたぶんありません。じゃあ明後日は更新するかというと、サッカーズの〆切なので確約はできません。確約なんか一度もしたことないけど。
2004.03.01.Mon. 15: 05 p.m.
BGM : PAULINA RUBIO "BORDER GIRL"
そんなわけで、CKをいっぱい貰える程度には攻め込んだのだが、やっぱマルディーニって上手いよなぁと溜め息が出る場面の連続で、ネスタのいない(そして終盤にはパンカロのいた)ミラン守備陣を混乱させるまでには至らず0-1の負け。トップスピードでボールに飛び込んだアンブロジーニのダイビングヘッドは、敵ながら惚れ惚れするぐらいカッコよかった。ウルトラマンみたいだ。セガレに見せたら、喜んで真似しようとするかもしれない。……あ、でも、終わるやいなやビデオ消しちゃったんだった。
残念だったのは(いや最初から最後まで残念なことしかない試合だったのだが)、途中出場のパンカロが右サイドに入ってしまったことだ。オッドと同時にフィールドインしたので、トイメンに入って「パンカロとオッドはどちらがよりパンカロ的か」という、およそどうでもいい問題に決着をつけてほしかったのだが。クロスを上げようと右足を振るオッド。顔を背けながら左足を出すパンカロ。さてボールの行方はいかに……。見たいなぁ、そういう場面。世界最弱の矛と世界最弱の盾はどっちが弱いかって話ですが。想像しただけでワクワクする。
 たまには目の保養にと思って載せているだけで、写真と本文はまったく関係がないので誤解しないでほしいのだが、金曜の夜に出版業界志望の女子大生(1年生)と話をしていて強く感じたのは、いかに自分が結果オーライの人生を送ってきたかということである。相手はこれから自己錬磨に励んで道を切り開こうとしているわけで、したがって当然、私がどのように大学以降の日々を過ごしたかという話になるのであるが、これがもう、話していて情けなくなるぐらいナーンモ考えてない人生だったのだよなぁ。学生時代? 麻雀してました。勉強? 卒業に必要なこと以外はしませんでした。就職の準備? 何をすればいいのか今でも知りません。就職活動? 始めようとしたときは、多くの友人がすでに内定をもらってました。欠員補充のために急遽新卒を募集したSD社から内定をもらったのは、卒業を目前に控えた3月のことでした。一体全体、どうするつもりだったんだろう私は。3年後に辞表を出したときも、次の仕事の目処なんかナーンモ立ってなかったしなぁ。振り返ると怖くなるので、あんまり昔のことは思い出させないでほしいです。とはいえ、先のことを考えても怖くなるのでアレなんだけど。
たまには目の保養にと思って載せているだけで、写真と本文はまったく関係がないので誤解しないでほしいのだが、金曜の夜に出版業界志望の女子大生(1年生)と話をしていて強く感じたのは、いかに自分が結果オーライの人生を送ってきたかということである。相手はこれから自己錬磨に励んで道を切り開こうとしているわけで、したがって当然、私がどのように大学以降の日々を過ごしたかという話になるのであるが、これがもう、話していて情けなくなるぐらいナーンモ考えてない人生だったのだよなぁ。学生時代? 麻雀してました。勉強? 卒業に必要なこと以外はしませんでした。就職の準備? 何をすればいいのか今でも知りません。就職活動? 始めようとしたときは、多くの友人がすでに内定をもらってました。欠員補充のために急遽新卒を募集したSD社から内定をもらったのは、卒業を目前に控えた3月のことでした。一体全体、どうするつもりだったんだろう私は。3年後に辞表を出したときも、次の仕事の目処なんかナーンモ立ってなかったしなぁ。振り返ると怖くなるので、あんまり昔のことは思い出させないでほしいです。とはいえ、先のことを考えても怖くなるのでアレなんだけど。
ともあれ人は自分の経験に基づいて喋るしかないので、まあ出版界への入り方なんかいろいろあるし、いったん入っちゃえば何とかなるもんだよアッハッハーなどという無責任な話をしてしまった。ものすごくマズかったんじゃないかと深く反省している。そうやって何の戦略もなしに結果オーライの生き方をしている人間のほうがきっと少ないし、その「結果」にしたって私自身が「オーライ」だと思い込まないとやってられんというだけのものであって、もっと努力していればもっとマシな結果になっていたに違いないわけなので、やっぱり勉強はしたほうがいいのである。それに、たしかに私は大学での4年間を遊び呆けていたけれど、べつに「学生時代しかやれないことをやるんだもんねヤッホッホ」とスーパーフリーに遊んでいたわけではない。常に「こんなことしてる場合なのか俺は」という後ろめたさを抱えながら朝まで麻雀を打っていた。と思う。思いたい。要するに遊びというのは現実逃避なのであって、なんだよおまえ、だったら今と同じじゃねえかという話にもなるわけだが、やっぱりこの「忸怩たる思い」みたいなものは大切なんじゃないかなぁと思ったりして、それは大人の「世の中そんなに甘くねえんだぞだから勉強しろ」というプレッシャーから生じるのであるから、もうじき四十になる人間としては、そろそろちゃんと若者の前に立ちはだかる「壁」として機能してあげなければいけなかったのではないか私は。
しかし、彼女を含めた大学生にとって出版界は「狭き門」のように感じられるらしく、東大や早稲田や慶応でちゃんと勉強したエリートだけが入れる世界だという強い思い込みがあるようなので、それはそうでもないんだぜ子猫ちゃん、という話ができたのはよかったんだろうと思っている。学生さんにとって「出版界」というのは講談社やら小学館やら集英社やら新潮社やら文藝春秋やらを指す言葉なのであろうし、だとすればまあ彼らが抱きがちな先入観もそんなに間違っていないかもしれないが、泥にまみれる覚悟さえあれば「出版の仕事」は間口が広いからね。大出版社で仕事してる編集者がみんな自己実現を果たして幸福そうにしてるかというと、私の目にはそんなふうにも見えないし。
もちろん、業界人の中には「結局、大出版社に入った奴が勝ち組なのさ」という者もいるだろうし、それはそれで一つの見解としてアリだろう。人間の幸福感や勝利感はさまざまですから。しかし、有名大学出のエリートさんの中にだって使えない奴は掃いて捨てるほどいるのであって、「こいつ使えねえ」と思われながら無駄に高い給料を貰うことが「勝ち」なんだったら、べつに出版界じゃなくても自己愛を満たす道はあるだろっていう話である。というような話をしたら、「どういう人が使えないんですか?」と訊かれたので、「こういう奴」という実例(具体的には何年か前にここで書いたピン子ちゃんのケース)を教えたら、「え〜! そんな人が本当にいるんですか?」とビックリしてくれたので少し安心した。それにビックリできるようなら、とりあえず可能性はある。ものすごく低いハードルだが、そのハードルを越えないまま出版界で仕事をしている人間は大勢いる。つまるところ、まず心掛けるべきは良い編集者になることではなく、まっとうな職業人になろうとすることなんじゃないでしょうか。というわけで、結果的にまた仕事の愚痴をこぼした私だった。
2004.02.27.Fri. 16: 25 p.m.
BGM : RENAISSANCE "PROLOGUE"
 めずらしく外で人と会っている昨日今日である。昨日はまず午後3時に半蔵門でTOKYO-FM出版のOさんと6年ぶりぐらいで面談。以前は現場で一緒に取材などしていたOさんは今では部長になっており、6年の歳月を感じた。まだ先行き不透明な企画の相談で、仕事をすることになるかどうかも未定だが、しばらくブランクがあってもこうして私のことを思い出して相談を持ちかけてもらえるのはありがたい。6年ぶりに会った相手に仕事の愚痴ばかりこぼしてしまい、反省した。
めずらしく外で人と会っている昨日今日である。昨日はまず午後3時に半蔵門でTOKYO-FM出版のOさんと6年ぶりぐらいで面談。以前は現場で一緒に取材などしていたOさんは今では部長になっており、6年の歳月を感じた。まだ先行き不透明な企画の相談で、仕事をすることになるかどうかも未定だが、しばらくブランクがあってもこうして私のことを思い出して相談を持ちかけてもらえるのはありがたい。6年ぶりに会った相手に仕事の愚痴ばかりこぼしてしまい、反省した。その後、渋谷を2時間も一人でウロウロするという孤独な暇潰しを経て、7時に三軒茶屋で月例新書の会。今回から課題図書をみんなで読んでくるという形式になり、その課題図書は仲正昌樹『「不自由」論−−「何でも自己決定」の限界』(ちくま新書)である。今日は時間がないので本の内容や読書会の模様などに触れている余裕がないのだが、不自由について語り合うために集まった人々の前で仕事の愚痴ばかりこぼしてしまい、反省した。
今日は午前中に愚妻と銀座へ行き、昼はサッカーズ編集長&担当すずき君と会食。編集長のイタリア土産 for セガレは、イタリア語版のポケモンカードであった。あるんだねぇ。おそらく、セガレはこれでローマ字の読み方を覚えるに違いない。どうもありがとうございました。旨いフカヒレソバを食いつつ、仕事の愚痴ばかりこぼしてしまい、反省した。
んで、今日はこれから吉祥寺で出版業界志望の女子大生(!)と会うことになっている。私の兄の同級生が高校で国語の先生をやっており、その教え子がその女子大生なのであって、べつに怪しい関係ではない。私に会って何がどうなるものでもないと思うが、とりあえず話を聞きたいというので話をすることになった。仕事の愚痴ばかりこぼして相手の夢や希望を粉砕しないよう、気をつけようと思う。ぜんぜん関係ないがルネッサンスはあまり面白くない。
2004.02.26.Thu. 11 : 05 a.m.
BGM : JIMMY PAGE & ROBERT PLANT "WALKING INTO CLARKSDALE"
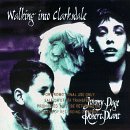 にわかファンの私は、ペイジとプラントの双頭ユニットが存在することも少し前まで知らなかったわけだが、そういうものがあると聞いたときは、正直なところ意外な気がした。その意外感には2つの側面があるのであって、1つはもちろん「別れたメンバーとヨリを戻す」ことに対する違和感なのであるが、それ以前に、この2人がツェッペリン解散以後もミュージシャンであり続けていたことに対して、どういうわけか私はヘンな感じを受けてしまったのである。ふつうに考えれば当たり前のことで、むしろバンド解散と同時に引退するミュージシャンのほうが少ないだろう(キャンディーズだって普通の女の子には戻れなかったし)と思うのだが、どうも私の場合、10枚組ボックスセットを買った時点で「こいつらのスタジオ録音はこの10枚(9タイトル)しかないのだ」という覚悟というか悲愴感というかそんなような気持ちを強く抱いてしまっていたせいか、その後のソロ活動のことが想像できなかったようなところがあるのだった。
にわかファンの私は、ペイジとプラントの双頭ユニットが存在することも少し前まで知らなかったわけだが、そういうものがあると聞いたときは、正直なところ意外な気がした。その意外感には2つの側面があるのであって、1つはもちろん「別れたメンバーとヨリを戻す」ことに対する違和感なのであるが、それ以前に、この2人がツェッペリン解散以後もミュージシャンであり続けていたことに対して、どういうわけか私はヘンな感じを受けてしまったのである。ふつうに考えれば当たり前のことで、むしろバンド解散と同時に引退するミュージシャンのほうが少ないだろう(キャンディーズだって普通の女の子には戻れなかったし)と思うのだが、どうも私の場合、10枚組ボックスセットを買った時点で「こいつらのスタジオ録音はこの10枚(9タイトル)しかないのだ」という覚悟というか悲愴感というかそんなような気持ちを強く抱いてしまっていたせいか、その後のソロ活動のことが想像できなかったようなところがあるのだった。さて、そんな違和感を抱きながらもペイジのソロアルバム『OUTRIDER』やザ・ファームのアルバムは聴いてみたわけだが、まあ、どれもピンと来なかったなぁ。で、それを踏まえてのペイジ&プラントなのである。うーむ。そうかー。これはどうなんだろう。……と、またぞろミスター・アウトドアを登場させたくなるような気分。もどかしいなぁ。ペイジのソロやザ・ファームよりは当然ツェッペリンっぽいように聞こえるものの、だからこそボーナムの不在感が際立ってしまうのはやむを得ないところで、何だ何だこの寝惚けたドラムの音は!といった思いが先に立ってしまい、ニュートラルな聴き方ができないですね、なかなか。というか、ニュートラルな聴き方なんかできるわけがないのであって、別れたメンバーとヨリを戻した以上、作り手側だってそれを覚悟していないはずがない。だったら、もうちょっとマシなドラマー連れてこられなかったんでしょうか。いい曲が揃っているだけに、残念だ。
チャンピオンズリーグも再開しているが、まずは週末のビッグゲームを消化すべく、ゆうべはミラン×インテル(セリエ第22節)をビデオ観戦。うっかりラツィオ戦を最初のほうだけ主音声で観てしまい、その実況を通じてミランが勝ったことは知っていた(スコアは知らなかった)ので、前半はすごく意外だった。スタンコビッチのCKがそのままゴールインしてインテルが先制。それだけでもビックリしていたのに、さらにザネッティだか誰だかのゴールで0-2である。ひょっとして「ミラン勝利」は私の聞き間違いだったかと思ったのだが、しかしインテルは本当にそこから逆転負けを食らっていた。後半10分前後のあいだにトマソンとカカの連続ゴールで同点。トマソンって、あまり登場しないが登場すると必ずゴールを決めているような気がする。意外にえらい人だ。そして85分、セードルフの息を呑むような美しいミドルシュートがゴールに突き刺さって3-2。「2-0は怖い」と思わせる試合を久しぶりに観た。「さすがインテル」と思わせる試合も久しぶりに観た。おもしろかった。
それにしてもパンカロだ。後半途中、カフーに替わって右サイドに。ミラノダービーでカフーの替わりに投入されるなんて、彼にとっては人生最大の勲章かも。しかし、どうも左サイドとは勝手が違うのか、自分では「ここに立ってりゃパスは来ない」と思い込んでいるときにパスが来たりなんかして、オロオロする場面が散見された。ガットゥーゾはまだパンカロのことをよく理解していないのかもしれない。あー、ダメダメ、そこでパス出しちゃ。ほーら、クロスがDFに引っかかるだろ? そんなもんなんだよ。ちょっと前にゴールなんか決めちゃったらしいから信用してんのかもしれんけど、それが今シーズン最後のバカヅキだったんだからね。
2004.02.25.Wed. 15 : 40 p.m.
BGM : PFM "www.pfmpfm.it(il Best)"
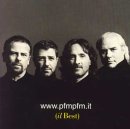 作品の完成度が高いので、スタジオに引きこもるタイプのような印象もあるPFMだが、ライブ盤も素晴らしいのが素晴らしい。スタジオ盤にはない陽気さや激しさがあって、じつに楽しいのである。これに収められた名曲『E' FESTA』など聴くと、彼らがたしかに「ロックバンド」であるということが実感できるのだった。ちなみに、いちばん左の人はディ・ビアッジョではありません。
作品の完成度が高いので、スタジオに引きこもるタイプのような印象もあるPFMだが、ライブ盤も素晴らしいのが素晴らしい。スタジオ盤にはない陽気さや激しさがあって、じつに楽しいのである。これに収められた名曲『E' FESTA』など聴くと、彼らがたしかに「ロックバンド」であるということが実感できるのだった。ちなみに、いちばん左の人はディ・ビアッジョではありません。
昨日から今日にかけて、やたらあちこちから電話がかかってくる。花の命も短いが仕事からの解放感も長続きはしないもので、また何やら日程が風雲急を告げてきたのである。まず、「わしズム」編集部から対談を収録したMDとポータブルMDプレーヤーがバイク便で届けられた。テープ起こしならぬMD起こしからやれということだ。このMDプレーヤーはいったい誰の物なんだろう。もしかして私にくれるんだろうか。それにしても、MDに対談を録音する時代なのであるなぁ。わりと迷惑です。ちょっと起こしてみたが、音質はきわめて良いのでその点では仕事がしやすいものの、途中で止めると次に再生するときのレスポンスが遅くて調子が狂う。「聞く」と「キーを叩く」のタイミングをテープのときとは変えなければならず、そのリズムを身につけるまで時間がかかりそうだ。それより何より、ちょっと操作の順番を間違えるといちばんアタマまで戻ってしまうのがアタマに来るぞ。あと、音質が良すぎるのも考えものだ。メシ食いながら対談してるのだが、咀嚼音やフォークと皿の触れ合う音まで忠実に再現しやがるので、旨そうでかなわん。俺にも食わせろ。
さらに、「もっと肉付けしたい」という著者の意向で先送りになっていた講談社のゴースト仕事は、結局その著者が肉付け作業を断念したとかで、当初の内容のまま進めることに。だったら先週から取りかかれたのになぁ。ライターのスケジュールなんか考えようともしない著者には、ほんとうに困らされる。こっちは、あんたの仕事だけやってるわけじゃないんだよ。あんたの仕事だけで食えるぐらいお金くれるんなら話は別だけどさ。まあ、ライターAが忙しけりゃライターBがやるだろうぐらいの感覚なんでしょうけどもね。ともあれ、できれば5月に刊行したい(それも著者の会社の都合だそうで、ほんとに自分勝手ですね)とのことなので、ライターAとしてはそれを3月中に片づけて、PHPのゴースト仕事(スポーツ関係)は4月にやることにした。5月にはシギーに頼まれたゴースト仕事をやる予定になっている。うー。だから、もうそんなペースでは書けないんだって言ってるのにぃ。ものすごく憂鬱だ。
 Yさんからお借りしたビデオ『レッド・ツェッペリン 狂熱のライブ』を一家三人で途中まで鑑賞。いきなり凄惨な銃撃シーンから始まったので、こりゃセガレに見せるのはいかがなものかと思ったが、そんなことはともかく、かっこええなぁジミー・ペイジ。ロバート・プラントの胸や腹はそんなに見たくないから、もっとペイジを映してほしい。ちょっと挙動不審な感じがしなくもないが(とくにテルミンの演奏中とか)、私も早くあんなふうにヨロヨロ歩きながらギターを弾けるようになりたいものである。セガレはペイジのダブルネックギターが印象的だった様子。このところ足し算を少し覚えたもので、得意げな顔で「弦が12本もあるんだね」と言っていたが、残念でした。あれは上が12弦ギターだから、計18本あるのだ。小学校に上がったら、算数のテストでは引っかけ問題に気をつけなくちゃダメだよ。ところでジミー・ペイジって、顔のテイストがときどきアイマールに似ている。
Yさんからお借りしたビデオ『レッド・ツェッペリン 狂熱のライブ』を一家三人で途中まで鑑賞。いきなり凄惨な銃撃シーンから始まったので、こりゃセガレに見せるのはいかがなものかと思ったが、そんなことはともかく、かっこええなぁジミー・ペイジ。ロバート・プラントの胸や腹はそんなに見たくないから、もっとペイジを映してほしい。ちょっと挙動不審な感じがしなくもないが(とくにテルミンの演奏中とか)、私も早くあんなふうにヨロヨロ歩きながらギターを弾けるようになりたいものである。セガレはペイジのダブルネックギターが印象的だった様子。このところ足し算を少し覚えたもので、得意げな顔で「弦が12本もあるんだね」と言っていたが、残念でした。あれは上が12弦ギターだから、計18本あるのだ。小学校に上がったら、算数のテストでは引っかけ問題に気をつけなくちゃダメだよ。ところでジミー・ペイジって、顔のテイストがときどきアイマールに似ている。
2004.02.24.Tue. 12 : 15 p.m.
BGM : CAMEL "CAMEL(1st album)"
 世の中には「聴いてると楽しいけど演奏してみると意外につまらない曲」というのがあって、たとえば吹奏楽のオリジナル曲にはそういうものが多い。私が吹奏楽で吹いていたユーフォニアムという楽器の役回り(担当する仕事は多彩だけど簡単なフレーズが多いんです)のせいかもしれないが、何度か練習するとすぐに吹き飽きてしまうことが多いのである。なんちゅうか、こう、表面ばっかり取り繕っていて奥行きがないっていうんでしょうかね。逆に、「聴いてるとつまんないけど演奏してみると意外に楽しい曲」というのもあって、たとえばトロンボーン吹きとしての私にとってはネイティブサン(!)の「GO FOR IT」という曲がそうだったりするのだが、そんな読者のうち5人ぐらいしか知らない曲のことはともかくとして、もしかしたらキャメルって前者(聴いていると楽しいけど演奏してみると意外につまらない)なのかもしれないと思い始めているのだった。わりと大づかみなフレーズが多くて、そんなに難しいことはやっていないように聞こえるのだが、それをリズムやテンポの変化等によってドラマチックに聴かせる術に長けているバンドなのかもしれない。
世の中には「聴いてると楽しいけど演奏してみると意外につまらない曲」というのがあって、たとえば吹奏楽のオリジナル曲にはそういうものが多い。私が吹奏楽で吹いていたユーフォニアムという楽器の役回り(担当する仕事は多彩だけど簡単なフレーズが多いんです)のせいかもしれないが、何度か練習するとすぐに吹き飽きてしまうことが多いのである。なんちゅうか、こう、表面ばっかり取り繕っていて奥行きがないっていうんでしょうかね。逆に、「聴いてるとつまんないけど演奏してみると意外に楽しい曲」というのもあって、たとえばトロンボーン吹きとしての私にとってはネイティブサン(!)の「GO FOR IT」という曲がそうだったりするのだが、そんな読者のうち5人ぐらいしか知らない曲のことはともかくとして、もしかしたらキャメルって前者(聴いていると楽しいけど演奏してみると意外につまらない)なのかもしれないと思い始めているのだった。わりと大づかみなフレーズが多くて、そんなに難しいことはやっていないように聞こえるのだが、それをリズムやテンポの変化等によってドラマチックに聴かせる術に長けているバンドなのかもしれない。しかし、だからといって吹奏楽のオリジナル曲のような底の浅さを感じるわけではなく、勿論いわゆるムードミュージックのようなものでもない。ムードミュージックって何だかよくわからないが、おそらくそれは「匿名性の高い音楽(誰が演奏していようがどうでもいい音楽)」という側面を持っているのだろうと私には思われるのであり、しかしキャメルの音楽はそういうものではない。どこを切ってもラクダの顔が描いてある。だから決して耳に心地よいだけの音楽ではないのであって、たぶんコピーした場合は「つまらない」ではなく「本物みたいに響かない」ことに苛立つのではないか。キャメルの曲はキャメルが演奏しないとキャメルっぽくならないというか、まあ、どんなバンドだってきっとそうなのだが、キャメルの場合はアマチュアがコピーすると目も当てられないほどのダサダサ感が生じるような気がする。何が言いたいのかよくわからくなってきたが、そんなキャメルが私は好きだ。
ゆうべは、キエーボ×ラツィオ(セリエ第22節)を23時からの録画中継で観戦。以下、試合を観ながら愚妻と交わした会話の断章。
◇キエーボのコッサートとかいうFWの顔は出来損ないのデルベッキオみたいだ。
◇しかしデルベッキオ自体が出来損なっていると言えなくもない。
◇セーザルは髪型が可愛らしくなった。
◇ミハイロの頭はカツラが後ろにズレたみたいでヘン。
◇ペロッタのオデコ狭すぎ。
◇あ、ミハイロってばキャプテンじゃん。
◇明日の保護者会、なに着て行こうかな。
だからさ。そんなことばっかり気になるような試合をしてほしくないわけです。4試合で12ゴールはどこへ行ったんじゃ。どこかどう絶好調なんじゃ。まともに興奮したのは、後半にスタムがドドドドドドッと攻め上がってきたときだけだった。深夜に声を揃えて「行けスタム!」と叫んでいる夫婦もどうかと思うけどね。完璧にハモってしまいました。クラウディオ・ロペスがPK決めてりゃ……セーザルのゴールがオフサイド(誤審)で取り消されなけりゃ……とも思うが、もっとも悔やまれるのがコウトの不出場ってどういうことだおまえら! あんな奴がポイントゲッターでいいのか! というわけで、スコアレスドローだ。パンカロクロスさえ上げられないオッドをグーで殴りたくなった。フィオーレもどこで何やってんだかわからんしなぁ。花の命は短いのう。
2004.02.23.Mon. 18 : 05 p.m.
BGM : PFM "L'ISOLA DI NIENTE"
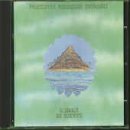 プレミアシップマガジンYさんよりレッド・ツェッペリン『狂熱のライブ』のビデオ&サッカーズ編集長よりPFMのCD(右の写真を含めて4枚)を借りるべく、京橋のフロムワンへ。諸氏がサッカー雑誌の編集者であることを忘れそうになる勢いである。しかも自分がモノを借りておきながら昼食をご馳走になって帰ってくるのだから図々しい。「Dobro」というレストランへ連れて行っていただき、生まれて初めてクロアチア料理を食べた。店員によれば、店名の「Dobro」はクロアチア語(というのかどうか知らないが要は向こうの言葉で)「good」という意味だそうだ。なんでも、W杯でクロアチア代表を受け入れた新潟の関係者が開いた店で、店員によればオーナーは「クロアチア・マニア」なのだという。クロアチア・マニア。そろそろ発売されたはずのサッカーズ4月号にもちょっと書いたが、やはり日本人の多様性は世界一かもしれない。
プレミアシップマガジンYさんよりレッド・ツェッペリン『狂熱のライブ』のビデオ&サッカーズ編集長よりPFMのCD(右の写真を含めて4枚)を借りるべく、京橋のフロムワンへ。諸氏がサッカー雑誌の編集者であることを忘れそうになる勢いである。しかも自分がモノを借りておきながら昼食をご馳走になって帰ってくるのだから図々しい。「Dobro」というレストランへ連れて行っていただき、生まれて初めてクロアチア料理を食べた。店員によれば、店名の「Dobro」はクロアチア語(というのかどうか知らないが要は向こうの言葉で)「good」という意味だそうだ。なんでも、W杯でクロアチア代表を受け入れた新潟の関係者が開いた店で、店員によればオーナーは「クロアチア・マニア」なのだという。クロアチア・マニア。そろそろ発売されたはずのサッカーズ4月号にもちょっと書いたが、やはり日本人の多様性は世界一かもしれない。落ち着いた店内は、男ふたりで入るのがやや申し訳ない感じの雰囲気。テーブルクロスは赤と白の市松模様ではなかった。やはり国旗や代表ユニの上でメシを食ったりはしないということだろうか。Yさんはビーフシチュー、私はロールキャベツを注文。それぞれクロアチアの言葉で何というのかは忘れた。クロアチアのロールキャベツは、Kay'n師匠のロールキャベツとはコンセプトの異なるサワー系のロールキャベツで、なかなかイケる。パンにつけて食するクルミとチーズのペーストも美味。さてクロアチア料理の本質はなんぞやと思い、まず「スロベニア料理というのもあるのか」と店員に問うたところ、「あるでしょうけど、同じですよ」とのこと。ついでに言うと、ハンガリー料理とも大差ないようだ。要は料理名がクロアチアの言葉であればそれはクロアチア料理であるらしい。たしかに、デザートのプリンやクレープにもクロアチア語の名前がついていたが、それはプリンとクレープであった。なるほど。でも、旨けりゃ何だっていいや。Yさんと別れたあと、銀座のアップルストアを冷やかし、山野楽器でキャメルのCDを2枚買って帰る。
話が前後するが、仕事が一段落したので、久々に週末らしい週末を過ごした。土曜日は、どうしてもチェルシー×アーセナル(プレミア)を観たいというアーセナルファンのKay'n師匠を自宅に招待。料理も上手い師匠に手料理をふるまうのは気が引けたが、私の場合ギターよりは料理のほうが今のところ上手いので、そうひどいダメ出しはされないだろうと思い、タコのバジリコソース、カルド・ガジェゴ(スペアリブとジャガイモとカブの煮込み)、エビやらアサリやらキノコやらの入ったトマトクリームのリングイネを食べさせた。食べながら懸命に褒め言葉を探す師匠の姿がやや痛々しかったが、まあ、あんなもんだ私の料理なんてものは。食後にはギターの腕前をちょいと披露してもらい、セガレにギター本来のかっこよさを思い知らせてやった。どうだギターはかっこいいだろう。と私が威張るこたぁないのだが、「父さんとは大違いだね」とのことで、その違いがわかればよろしい。父親が何を目指して努力しているか、これで理解できたことだろう。そこまでは、たいへん良い土曜日だった。
いや、正確にいえば、キックオフの28秒後までは、たいへん良い土曜日だったのである。ジェレミがファーサイドに上げたクロスをグジョンセンが決めて、チェルシーが電光石火の先制。しかし試合は、1週間前のFAカップを40分ほど前倒ししただけの展開であった。先週は後半に逆転されたが、今週は前半のうちにひっくり返されました。むう。また1-2の負け。強いなぁアーセナル。まあ、負けた試合のことをうだうだ言ってもしょうがない。来週は後半40分ぐらいに先制すれば逆転されないだろうから、そうしてください。……え? 来週はアーセナルと試合しないの?
きのうの日曜日は、春一番の吹きすさぶなか、神代植物園近くの公園へ。久しぶりにセガレとボールを蹴って楽しかった。ふだんは上手な子と一緒にやっているので目立たないが、セガレは明らかにボールの扱い方がサッカーらしくなっている。昔はボールをプレイスすると自分が後退して助走をつけていたが、今は少しドリブルしてボールを前に出してから蹴ったりしていて、なるほど知らないうちにそういう感覚を身につけているのだなぁとちょっと感心した。キックも以前とは比較にならないぐらい力強い。子供の成長具合というのは、他人と比較するのではなく、本人の過去と比較して見なければいけませんね。そう心掛けているつもりだったが、なかなかそうもいかないものだと反省した。
運動したあとは、蕎麦など食いつつ深大寺界隈を散歩。近所に水木しげるが住んでいるとかで、「鬼太郎茶屋」なる店ができていた。目玉オヤジのキャンディやら「ふりかけばばあ」というふりかけやらが売っていて、わりと可笑しい。いろいろなキャラクターグッズを見ながら、結局ポケモンの原形もコレなんだろうなと思ったりした。鬼太郎の頭に目玉オヤジが乗っているように、サトシの肩にはピカチュウが乗っているのである。攻撃指令のベクトルは逆だけど。10枚入りの妖怪カードをセガレに買い与えて帰宅。風は強かったが、仕事から解放されるやいなや春めいてきたのは気分がいい。
2004.02.20.Fri. 14 : 45 p.m.
BGM : PINK FLOYD "ANIMALS"
 幼稚園の学芸会を鑑賞。幼稚園だから「学芸会」じゃなくて「園芸会」か。しかし、だからといって園児たちが舞台の上でガーデニングや盆栽いじりをするわけでは勿論なく、植物よりもむしろ熊や馬や兎や犬や羊などのアニマルズ(豚さんはいなかったな)を演じる園児が圧倒的に多いわけだが、そうは言っても刑務所や戦場や老人ホームの慰問じゃないんだから「演芸会」と呼ぶのもいかがなものかという話なのかどうかは知らないが、正式には「発表の会」という。はいはい、最初からそう書けっちゅう話です。発表の会。
幼稚園の学芸会を鑑賞。幼稚園だから「学芸会」じゃなくて「園芸会」か。しかし、だからといって園児たちが舞台の上でガーデニングや盆栽いじりをするわけでは勿論なく、植物よりもむしろ熊や馬や兎や犬や羊などのアニマルズ(豚さんはいなかったな)を演じる園児が圧倒的に多いわけだが、そうは言っても刑務所や戦場や老人ホームの慰問じゃないんだから「演芸会」と呼ぶのもいかがなものかという話なのかどうかは知らないが、正式には「発表の会」という。はいはい、最初からそう書けっちゅう話です。発表の会。さて、子供の演劇における動物の擬人化とピンク・フロイドの『アニマルズ』の関係というのも研究に値する興味深いテーマではあるが、それはまた後日ということにしておいて、セガレのクラスの出し物は『アルタバン物語』というお芝居だった。イエス誕生の物語に登場する東方の三博士は有名だが、実は「四人目の博士」がいたことを知っている者は少ないだろう。……え? 有名なの? 私は知らなかったぞ。ともあれ、その四人目の博士がアルタバンである。
アルタバンは三人の仲間と一緒にイエスに会いに行く予定だったのだが、待ち合わせ場所に向かう途中で瀕死の病人を助けていたために遅刻してしまい、先に出発した三人を後から追うことになった。ところが、過酷な砂漠の旅を終えてベツレヘムに着いてみると、すでにイエス一家も三人の博士たちも街から立ち去ったという。神の子誕生を快く思わないヘロデ王が、兵隊を使って街中の赤ん坊という赤ん坊を皆殺しにしていると聞いて、逃げたのだ。さあ、どうするアルタバン。果たして四人目の博士はイエスに会うことができるのか。無事、贈り物のサファイア、ルビー、真珠を救い主に届けることができるのだろうか……という、とても面白そうな一大スペクタクル冒険活劇である。
んで、そのお芝居でセガレが何の役を与えられたかというと、アルタバンだった。『アルタバン物語』のアルタバン役といえば、『ハチ公物語』のハチ公、『次郎物語』の次郎、『南極物語』の南極と同じ役回りである。つまり主役。押しも押されもせぬド主役。おまえが来なきゃ芝居が始まらねーんだよ、そういうのはアルタバン物語っていわねーんだよの世界である。うー。親が緊張してもしょうがないのだが、緊張した。セガレ自身はさほどプレッシャーを感じていない様子で、家で台詞を練習することもなく数日前から「もう全部覚えた」と余裕を見せていたのだが、今朝はふだん一膳しか食べない朝ごはんを三杯もおかわりしていた。私に似て、ストレスを食べることで解消するタイプのようだ。べつにいいけど、本番の朝に食い過ぎて「おなか痛い」って言うなよな。こっちが焦るから。
主役だから当然といえば当然なのだが、舞台では冒頭のシーンから出ずっぱり。ものすごく硬い表情で、ときどき客席の母親と父親のほうをチラチラ見やがる。えーい、見るな見るなこっちを見るな。どんな顔していいかわかんないじゃないか。しかし意外に本番に強いセガレは、台詞を忘れてアタマンナカマッシロデースになることもなく、(やや台詞回しが早口ではあったものの)無難に自分の役をこなしていた。実のところアルタバン役は二人いて、「それから33年が経ちました」(そんなに長いあいだアルタバンはイエスを追い続けたのだ。待ち合わせに遅れると人生を棒に振ることもある、というのがこの物語の教訓である)というナレーションの後は別の子と交替したのだが、どうせならラストシーンまで演じ切らせてやりたかったなぁ。その結末が知りたい人は、このページをお読みください。わりと感動的。
2004.02.19.Thu. 13 : 05 p.m.
BGM : AEROSMITH "DRAW THE LINE"
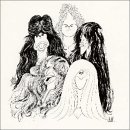 エアロスミスを聴いていると、どういうわけか、むかし竹中直人がやっていた「笑いながら怒っている人」という芸を思い出すことがしばしばある。ロックと呼ばれる音楽には総じて怒気(や怒気めいたもの)が含まれているように思うのだが、エアロスミスの怒気には何か独特なものがあるのかもしれない。映像どころか写真も見たことがないので音を聴いた印象だけで言うのだが、スティーブン・タイラーのボーカルも、ジョー・ペリーのギターも、どこか半笑いで怒っているというか、おもしろがって怒っているというか、陽気な怒気というか、コントロールされた怒気というか、「アッタマ来たで〜」と吠えるタイラーにペリーがギターで「なんで怒ってんねーん」とツッコミを入れているというか、なんかそんな感じ。だからといってそれが良くないと言いたいわけでは全然なく、そこにプロフェッショナルな芸人魂を感じたりするのだった。こういう言い方をすると、ファンに怒られるのだろうか。いや私だってファンなのだが。この『DRAW THE LINE』というアルバムも、全編に横溢するテンションの高さが、(タイトルが示すように)ドラッグによってもたらされたものだとは、私にはどうしても思えない。たとえば「アルバム全体にぶっ飛んだことによるつき抜けたアシッド感を感じることができる」などといったレビューを見ると、あんたソレ、LINEをDRAWした経験があって言ってるわけ?などと茶化したくなったりなんかするわけです私の場合。いや、経験に基づいておっしゃってるなら謝りますが。すまん。
エアロスミスを聴いていると、どういうわけか、むかし竹中直人がやっていた「笑いながら怒っている人」という芸を思い出すことがしばしばある。ロックと呼ばれる音楽には総じて怒気(や怒気めいたもの)が含まれているように思うのだが、エアロスミスの怒気には何か独特なものがあるのかもしれない。映像どころか写真も見たことがないので音を聴いた印象だけで言うのだが、スティーブン・タイラーのボーカルも、ジョー・ペリーのギターも、どこか半笑いで怒っているというか、おもしろがって怒っているというか、陽気な怒気というか、コントロールされた怒気というか、「アッタマ来たで〜」と吠えるタイラーにペリーがギターで「なんで怒ってんねーん」とツッコミを入れているというか、なんかそんな感じ。だからといってそれが良くないと言いたいわけでは全然なく、そこにプロフェッショナルな芸人魂を感じたりするのだった。こういう言い方をすると、ファンに怒られるのだろうか。いや私だってファンなのだが。この『DRAW THE LINE』というアルバムも、全編に横溢するテンションの高さが、(タイトルが示すように)ドラッグによってもたらされたものだとは、私にはどうしても思えない。たとえば「アルバム全体にぶっ飛んだことによるつき抜けたアシッド感を感じることができる」などといったレビューを見ると、あんたソレ、LINEをDRAWした経験があって言ってるわけ?などと茶化したくなったりなんかするわけです私の場合。いや、経験に基づいておっしゃってるなら謝りますが。すまん。
きのうはKay'n師匠のスタジオでギターのレッスン。前回はクルマで行ったので、ギターを持って電車に乗るのは今回が初めてだった。自分が持っていると他人が持っているのが目につくもので、たとえば昔セガレをベビーカーに乗せて歩いているときは「世間にはこんなに赤ん坊がいたのか」と感じたものだが、きのうは世間におけるギター人口の多さを改めて思い知りました。何度か乗り換えたのだが、どの駅でも必ずギター(ベースかもしれないが)を持った人を見かけるのである。そんなにギタリストが世の中に必要だとは思えないものの、大半のギタリストはべつに世の中のために弾くわけじゃないのであって(私自身はどうせなら世のため人のためにギターを弾けるようになりたいと願っているが)、まあ、楽器を持ち歩く人が多いのはたぶん良いことだ。いちいち近寄って「ねえねえ、左手、どんな感じて握ってる?」と尋ねたい衝動に駆られたりしたが、どう考えても気味悪がられるに決まっているのでやめておいた。
で、その左手は相変わらずダメだ。一人でいろいろ研究してはいたのだが、正しいフォームを理解したとしても、やはり、まずはフィジカル面の問題を克服しなければそれを実践できないということがわかった。なにしろ肘から先の関節やら筋肉やらがカタすぎるのである。中年ビギナー特有のハンディキャップですわ。新鮮な左手細胞をES細胞から分化させて移植したいぐらいの気分である。左手細胞という細胞はありません。しかし、右手のピッキングはまあまあいい感じになっているようなのでヨカッタ。歩みは遅くとも、練習すればしただけ進歩することを信じてやるしかない。
今回は、師匠が初めて「曲」の譜面を用意してくれていた。まだ早いような気がしなくもないが、そろそろ音楽っぽいこともやらんと煮詰まるだろうというご配慮である。私自身はそうでもなく、単調な反復練習にもそのつど何らかの変化が感じられて面白いのだが、家で練習しているとセガレに「またそれ〜?」などと言われるので、いろいろバリエーションがあるのはありがたい。基礎訓練の大事さをセガレに教える意味では単調かつ退屈なフレーズのくり返しも悪くないのだが、まあ、聴かされるほうは少しメロディでもないと発狂しそうになるだろうからね。
で、曲はレッド・ツェッペリンの『LIVING LOVING MAID』だ。うほほー。和音は省いた単音の譜面なのでペイジのプレイをコピーするわけではないが、最初に練習するツェッペリンの曲がこれというのは、なかなか嬉しい。例の江戸川ボックスでは4枚目の最後にボーナストラックとして入っている曲で、かっこよくも美しくも渋くも謎でもないという意味ではもっともZEPらしくないナンバーとも言えるような気がするのだが、しかしその「らしくない曲」がああいうポピュラリティというかキャッチーな存在感みたいなものを持っているところが、あのバンドの偉大さを物語っているようにも思うわけで、私としてはかなり思い入れのある曲なのである。
そんなゴタクはともかくとして、聴いている分には実に単純で簡単そうなフレーズなのであるが、いざ弾こうとすると、そこではギターによる表現に必要な技術がいくつも要求されるのでありまして、それを知ること自体が私には面白くてしょうがない。このあたりが入門者の醍醐味なのである。すべての技術を無意識にこなしている上級者には、この面白さがわかるまい。もし「プロの入門者」というものがこの世にあるのなら、私はそれになりたいぐらいだ。
レッスン終了後は、師匠の用意してくれたおでんをつつきつつ、日本×オマーン(W杯アジア1次予選)をライブ観戦。師匠はギターもうまいが料理もうまいのであって、お手製のロールキャベツなんざ、そりゃあもう絶品でございました。それにしても、彼と一緒にサッカーを観るのは初めてだったが、レッスン時のダメ出しも厳しいが選手へのダメ出しも厳しい人だ。生かされていないスペースを見つけるたびに、いちいち腰を浮かせて「ココだよココ」と画面を指差す人を私は初めて見た。それは立派なことだと思うし、指摘することはいちいちごもっともなのだが、でもね師匠、それやられると見えないんですテレビが。あれは何というキカイなのか知らないが、きのうBS−1の中継でハーフタイムに早野さんが矢印やら丸やらを書いていたアレがお茶の間でも使えればいいのに。
試合のほうは、ご承知のとおり後半ロスタイムにスパークした久保のミラクルによって1-0。いやあ、さすがさすが。久保っていう男はね、いつか必ずやる奴だと思ってたよ。うんうん。しかしオマーン人にとっては、「サイタマの悲劇」だわな。いまごろオマーンのメディアでは、「アラーがまだW杯に出るのは早いと言っている」とか何とかいう話になっているに違いない。もっとも、よその国のことはどうだっていいのであって、こっちのネクタイ嫌いな神様のほうはどうなんだ。この強運を信じていいのか。