2004.03.11.Thu. 11 : 50 a.m.
BGM : ピチカート・ファイヴ "BOSSA NOVA 2001"
なので、掃除をした。私は掃除が苦手だが、大掃除はあんがい好きだ。滅多にやらないが、やり始めると止まらなくなる。ふだんからコツコツやればいいのにそれを怠り、いざとなったら一気にやるあたり、仕事の進め方と何ら変わらない。つまりはそういう性格だということだろう。そんなわけで、除菌もできて2度ぶきなしのかんたんマイペット(新緑の香り)を買ってきて、いろんなところを拭きまくった。マイペットってすばらしい。汚れが落ちていく有り様と言ったら、通販番組のウソくさい実演を見ているのかと思うぐらいだ。感心してないで、たかがマイペットで感動するぐらい汚れていたことを反省しろっていう話です。しかし来客の到着までに掃除を完遂することはできず、いまだ部屋の中は「掃除してコレかいな」という状態。今日も掃除に逃避してしまいそうで怖い。
で、誰が訪ねてきたかというと、タボン社長だった。私がCDをなかなか返そうとしないのに業を煮やして、取り立てに来たのである。借金じゃないから取り立てって言わないか。もちろん私はわざと人聞きの悪い言い方をしているのであって、本当は何やら府中のほうでギターを弾く用事があったらしく、そのついでに立ち寄って当面必要なCDをピックアップしていったのだった。本やCDやビデオを長く借りっぱなしにしてしまうのは私たちの悪いクセだ。もちろん私はわざと複数形にして話を一般論にすり替えようとしているのであって、本当は私が悪い。そういえばヤマ(嫁)ちゃんからナンシー関の単行本をたくさん借りていることや、ハポエル君からサッカーのビデオをたくさん借りていることも今思い出した。まるで借り物王みたいだ。申し訳ない。近いうちに、耳をそろえて返却いたします。
タボン社長は私のギターをいじり、私はタボン社長が持ってきたアコースティック・ギターをいじらせてもらった。いっしょに「LIVING LOVING MAID」も弾いた。弾いたって言っても、私の演奏なんかまだ小学生の鼓笛隊をはるかに下回る(というか「演奏」とは呼べない)レベルなのだが、それでも楽しいよな、合奏って。タボン社長に言わせると、私のギターは「ものすごくダイレクトに音が出てくる感じで、ベースのしっかりしたいいギターだと思う」とのこと。ふうん。ダイレクトに音が出ないギターってどういうギターなのか私にはわからないが、楽器を褒められると自分が作ったわけでもないのに嬉しいですね。CDを借りた御礼(および返さないお詫び)として自家製矢野真紀セレクションをプレゼントしたら、タボン社長は少し迷惑そうだった。
 ところでCDの返却が遅れているのは、まだ聴いていないものがいくつかあったからだ。とくに7枚も借りてしまったピチカート・ファイヴは、それを聴く前にレッド・ツェッペリンの4枚組ボックスセットでロックに目覚めてしまったために、なかなか手が回らなかった。そもそもピチカート・ファイヴを借りるのが主眼で、ZEPはついでに借りたにすぎなかったのに、申し訳ないことだ。なので、きのうから慌てて聴きまくっている。いいよね、ピチカート・ファイヴ。私がピチカート・ファイヴを聴いていて感じるのは、「開き直った者の強さ」だ。「世の中にはスウィートやキャッチーがいっぱいあるよね」って、ふつうはそういうことを言われると不愉快になるものだが、ここまで開き直られるとグウの音も出ないというか、ハイいっぱいありますと素直に頷いてしまうのだった。
ところでCDの返却が遅れているのは、まだ聴いていないものがいくつかあったからだ。とくに7枚も借りてしまったピチカート・ファイヴは、それを聴く前にレッド・ツェッペリンの4枚組ボックスセットでロックに目覚めてしまったために、なかなか手が回らなかった。そもそもピチカート・ファイヴを借りるのが主眼で、ZEPはついでに借りたにすぎなかったのに、申し訳ないことだ。なので、きのうから慌てて聴きまくっている。いいよね、ピチカート・ファイヴ。私がピチカート・ファイヴを聴いていて感じるのは、「開き直った者の強さ」だ。「世の中にはスウィートやキャッチーがいっぱいあるよね」って、ふつうはそういうことを言われると不愉快になるものだが、ここまで開き直られるとグウの音も出ないというか、ハイいっぱいありますと素直に頷いてしまうのだった。
あと、どういうわけか私はピチカート・ファイヴを聴いていると、スペクトラムを思い出す。スペクトラムにも、どこか「開き直り」を感じるのである。それが何なのかはこれから考える(考えないかもしれない)が、もしかしたら私がUKの『U.K.』に感じた「余裕」や「プログレを対象化する視点」も、ある種の「開き直り」の産物なのかなぁとも思ったりするものの、そんなことをとやかく言っているとGreenroomにおける師匠の話がなかなか先に進まなくなってしまいそうなので、瞠目して待つことにしようっと。とりあえず、UKが「何に適応したのか」は大変よくわかりました。どもども。
ゆうべは、マンチェスターU×ポルト(CL)を観戦。結末を知ってから見たので(知らなかったら見ないわけですが)、愉快で愉快でたまらなかった。ヤマちゃん夫妻には悪いけどね。スコールズの先制ゴールに大ハシャギするファーガソンの表情を、あんなに心穏やかに眺められるのだから、先に結果を知ってから観るのも悪くない。だははは、おっさん、最後に何が起きるかも知らんで笑ってるよ、いやはや気の毒になぁ。などと言いつつ、指までさしてしまいました。そういう態度って人として最低のような気もするが、一生のうちにそう何度もあることではないので許してもらいたい。そんなわけで後半ロスタイム、ポルトのFKをGKハワードが前にハタキ落とし、これを何者かが押し込んでagg.2-3でユナイテッド敗退。試合後のサー・アレックスは、ロッカールームでこんどは誰の顔にスパイクを命中させたんだろうか。
2004.03.10.Wed. 13 : 20 p.m.
BGM : 矢野真紀 "はるか−遙歌"
子「買うの?」
父「買うに決まっている」
子「好きだねぇ」
父「ああ、好きだ」
子「レッド・ツェッペリンと矢野真紀、どっちがいいの?」
父「…………」
 と、またしても朝っぱらから難しい質問を受けて絶句しつつ、まっしぐらに吉祥寺の新星堂へ向かい、脇目もふらずにJ−POPの「や」の棚へ近づくやいなや、ニュー・アルバム『はるか−遙歌』をゲットして一目散に帰ってきたのである。もちろんレジにも寄ってカネは払ったから心配するな。で、聴いた。一抹の不安を呼び起こさずにおかないアルバム・タイトルであるが、これはすばらしい! いいぞ矢野真紀! その調子だ矢野真紀! 矢野真紀の歌い手としての芸域の広さと世界観の深さを堪能できるアルバムといえよう。亀田プロデューサー時代の大傑作『そばのかす』に次ぐ出来映えかもしれない。
と、またしても朝っぱらから難しい質問を受けて絶句しつつ、まっしぐらに吉祥寺の新星堂へ向かい、脇目もふらずにJ−POPの「や」の棚へ近づくやいなや、ニュー・アルバム『はるか−遙歌』をゲットして一目散に帰ってきたのである。もちろんレジにも寄ってカネは払ったから心配するな。で、聴いた。一抹の不安を呼び起こさずにおかないアルバム・タイトルであるが、これはすばらしい! いいぞ矢野真紀! その調子だ矢野真紀! 矢野真紀の歌い手としての芸域の広さと世界観の深さを堪能できるアルバムといえよう。亀田プロデューサー時代の大傑作『そばのかす』に次ぐ出来映えかもしれない。
この成功は、寺岡呼人と矢野真紀本人と共にプロデューサーとして名を連ねている藤井謙二の手腕によるものではないかと私は想像する。どういう人だかぜんぜん知らないけど。前作『この世界に生きて』は寺岡の単独プロデュースで、藤井は「Co-Producer」だったのだが、今回は三人並記の共同プロデュース。詞や曲も、前作は『いつか僕が還る場所』だけ藤井の曲だったが(これがそのアルバムの白眉ともいえる名曲なのだが)、今回は寺岡四曲に対して藤井は三曲に詞や曲を提供している。そして、私の聴くかぎり、藤井の詞や曲のほうが圧倒的に矢野真紀の良さを引き出しているのだった。藤井は大半の曲で演奏もしているのだが、ギタリストとしてもなかなか魅力的だ。
あー。寺岡の『エレジー』と『夜曲』と『蜜』がなければ、もっと聴き応えのある傑作になっただろうに、惜しいよなぁ。『夜曲』はシングル曲だから削るわけにもいかないわけだが、4ビートの『蜜』は曲も詞も悪い冗談としか思えない「なんちゃってジャズ」だし、『エレジー』という曲も、明らかにラブ・サイケデリコを真似ているのだが真似しきれていないというか、ああいうのをカッコよく作ることの難しさがわかっていないというか(私もわかっていないが)、要するにこの人は音楽をナメてるんじゃないだろうかと言いたくなるのである。あれ、前にもそう言ったっけ? 寺岡の曲の中では唯一悪くない『薄暮の街』にしても、陳腐な歌詞世界に矢野真紀の歌唱が何とか陰影をつけているから救われているような気がするし。文句ばっかり。
しかし、矢野真紀自身の作詞・作曲によるナンバーはいずれも彼女らしい複雑かつ濃厚な味わいにあふれているのであり、とりわけ二曲目の『地上の光』は、なんでこれをシングルにしないかと思うぐらいキャッチーな名曲だ。『背中』という曲で沼澤尚がドラムを叩いているのも、なんだか嬉しい。あと、ジャケットは今までで一番いいですね。ライブで矢野真紀がこんな顔に見えたことは一度もないけど。ともあれセガレの質問には、やはりあえて「矢野真紀」と答えたい。理由は……私は日本語が好きだから、ということにしておこう。
2004.03.09.Tue. 11 : 30 a.m.
BGM : DEFUNKT "IN AMERICA"
というわけで、のっけから崩壊寸前のラックに、いままで数カ所に分散していたCDたちを恐る恐る収納。とりあえず木ダボはその重量に耐えてくれた。私の腕力もまんざらではないのである。練習すればハンマーパンチも打てるようになるかもしれない。並べてみたら、CDは思ったより多かった。せいぜい300枚ぐらいだろうと思っていたのだが、500枚ぐらいありそう。CDを初めて買ったのは1987年の夏だから(就職して最初のボーナスでCDコンポを買ったのだ)、年間30枚ぐらい買ってるわけですね。今後はハイペースで増えることが予想され、だから余裕をもって850枚ぐらい入るラックを買ったのだが、もっと大きいやつにしたほうがよかっただろうか。
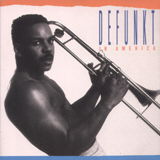 あらためて整理していると、当然、いつどうして買ったのかまるで記憶のないCDがたくさん出てくる。いま聴いているデファンクトもそんな一枚だ。デファンクト? よくわからないが異様なジャケットである。トロンボーンって、そんなポーズで構えてサマになる楽器じゃないと思うんですけどね。こういうキャラクターの人は、ふつう、トロンボーンを選ばないと思うし。わりとシュールだ。ロバート・メイプルソープに撮らせたら、どんな写真になるだろうか。
あらためて整理していると、当然、いつどうして買ったのかまるで記憶のないCDがたくさん出てくる。いま聴いているデファンクトもそんな一枚だ。デファンクト? よくわからないが異様なジャケットである。トロンボーンって、そんなポーズで構えてサマになる楽器じゃないと思うんですけどね。こういうキャラクターの人は、ふつう、トロンボーンを選ばないと思うし。わりとシュールだ。ロバート・メイプルソープに撮らせたら、どんな写真になるだろうか。
しかしジャケ写からリンクを張ったページの記述によれば、彼はアート・アンサンブル・オブ・シカゴのレスター・ボウイの弟のジョー・ボウイという人であるらしく、たぶんお兄さんの影響で金管楽器に興味を持ったのだろうと思われ、だとすれば私と同じなのでわりと共感できるのだった。無論そんなことはいま初めて知ったので、それが購買動機だったわけがないのであるが、音を聴いてたちどころに思い出したのだよ猿渡君。学生時代、私の演奏を聴いたイントロ(高田馬場のジャズ喫茶)のマスターに「デファンクトみたいな音だね」と言われて、そりゃどんな音なんだと思い、デファンクトのLPを買ったことがあるのだった。たしかそれには『熱・核・発・汗』という凄まじい邦題がつけられていた。手元にないのだが、あのLPは一体どこに行ってしまったのだろうか。ひょっとして私から借りてないか猿渡君。
ともあれ、このCDもそんなことがあったから買ったのであろう。このアルバムでのジョー・ボウイはトロンボーンよりもボーカリストとしてのプレイのほうが目立つのだが、かっこいいなデファンクト。何がってギターが。トロンボーンを聴くために買ったCDでそういう意欲が湧くというのもおかしな話だが、こういうギターも弾けるようになりたいぞ。
ゆうべは、ローマ×インテル(セリエ第24節)をビデオ観戦。前半にローマのゴールが二度も取り消されたにもかかわらず、終わってみれば4-1でローマの圧勝である。4点目が決まるやいなや八塚さんが呟いた「インテルはズタズタにされました……」という一言がとても印象的で笑った。ズタズタ。もっとも端的に視聴者の共感を獲得できる表現であろう。それ以上、インテルについて何を語ればいいというのか。ローマのほうは、悔しいけれど威圧感たっぷりの攻撃力。熱・核・発・汗な感じと言ってもいい。魚雷のような動き出しでトッティのラストパスを引き出し、落ち着き払って決めてみせたカッサーノのゴールもすばらしいものだった。
でも、ゴールパフォーマンスがすばらしくない。脱ぐな。おまえが脱ぐなって言ってんだよ。見たくないんだよ。モザイクかけてほしいよ。観戦中、トッティの顔が大人っぽくなり、本来のカンジ悪さが薄れてきたという話を愚妻としていたのだが、しかしそれはトッティが変わったわけではなく、こちらがカッサーノと比較してしまうため相対的にカンジ良く見えるだけで、つまりは錯覚のようなものだと私は思う。カンジの悪さでトッティを超えたカッサーノは、ある意味、偉大だ。
2004.03.08.Mon. 12 : 15 p.m.
BGM : KING CRIMSON "LARKS' TONGUES IN ASPIC"
しょうがないので、ミラン×サンプドリア(セリエ第24節)をライブ観戦したのだが、こりゃあ観てよかった。なにしろパンカロが絶好調だったのだ。もしかしたら生涯ベストパフォーマンスなのではないかと思えるぐらいの出来。あんなにアグレッシブなパンカロは初めて見た。とくに、誰かがセードルフの足元に出したパスを後方から矢のような猛ダッシュでインターセプト(味方だけど)して中に返すやいなや前線に駆け上がったプレイには、度肝を抜かれたぜ。パンカロが風の化身のように見えた。空前絶後の錯覚だ。セードルフも度肝を抜かれたのか、しばらく何が起きたかわからない様子で茫然と立ちつくしてました。そのインターセプトにどんな意味があったのかわからないが、一体どうしちゃったんだパンカロ。とにかく、まあ、エンジンを新品と交換したかのような走りっぷりで、攻め上がる攻め上がる。クロスも上げる上げる。それも左足をどっかから借りてきたような精度で、ピッポの勝ち越しゴールをアシスト。「パンカロのピンポイント・クロス」って「石毛の無四球完投」と同じくらいあり得ない話なので、あまりの驚愕に体が震えた。発狂したピッポに押し倒されるパンカロ。いいモノ見ちゃったよなぁ。恐れ入りました。
だが、私は見逃さなかったのである。前半の早い時間帯、なぜかCBのマルディーニが長駆左サイドを攻め上がり、攻撃が不発に終わると、背中にウンザリ感を漲らせながら自分のポジションに戻っていったのを。そのときパンカロが何をしていたかというと、後ろのほうでボンヤリと守っていた。いや、サボっていた。あれは「こういうタイミングで上がるんだよオメーは」というマルディーニからのメッセージだったに違いない。これでパンカロは、自分のサボり癖がキャプテンにバレていることに気づいたんだと思う。結局、えらいのはマルディーニなのだった。3-1でミランの勝ち。
というわけで、コラムやら対談原稿やら雑誌の仕事は片づいたもののホッとしている暇はなく、今日から講談社のゴースト仕事に着手するのである。どうしても今月中に上げてほしいということなので、あえて自らにプレッシャーをかけることにした。31日から二泊三日で日光の温泉宿を予約してしまったのである。ものすごく無謀だ。30日までに脱稿しなかったら、家族に何を言われるかわからない。編集者からの催促に倍する重圧。まさに背水の陣である。いや温泉だから背湯の陣か。なんかドキドキしてきた。スリリングな三月。
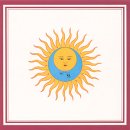 週末は仕事をしながらシギーに借りたプログレシリーズを聴き直していたのだが(だから原稿がはかどらなかったかもしれないが)、音楽というのは不思議なもので、最初は退屈だと思っていたものが急に魅力的に感じられるようになることがあるんである。まあ、どんな芸術だってそうかもしれないが、音楽はとりわけそのギャップが大きいような気がするのであり、その音楽の中でもとりわけプログレは聴き手の体調や精神状態や体験の蓄積具合によって印象が大きく左右されるように思われるのだった。情報量の多い音楽だからだろうか。このキング・クリムゾン『太陽と戦慄』も、最初は「こういうのがプログレの名盤なのかぁ面倒臭いなぁプログレって」などと乱暴な印象を抱いていたものの、改めて聴いてみると何だかよくわからないまま人をその音空間に巻き込んでしまう恐ろしいほどの吸引力を持っているのであって、これを名盤と呼ばずに何を名盤と呼ぶんだよこのボケ!などと結局また乱暴なことを言い出したりするわけだが、あり得ないような時間と空間を創出するプレイヤーこそが偉大であるという点は音楽もサッカーも同じなんだな、きっと。
週末は仕事をしながらシギーに借りたプログレシリーズを聴き直していたのだが(だから原稿がはかどらなかったかもしれないが)、音楽というのは不思議なもので、最初は退屈だと思っていたものが急に魅力的に感じられるようになることがあるんである。まあ、どんな芸術だってそうかもしれないが、音楽はとりわけそのギャップが大きいような気がするのであり、その音楽の中でもとりわけプログレは聴き手の体調や精神状態や体験の蓄積具合によって印象が大きく左右されるように思われるのだった。情報量の多い音楽だからだろうか。このキング・クリムゾン『太陽と戦慄』も、最初は「こういうのがプログレの名盤なのかぁ面倒臭いなぁプログレって」などと乱暴な印象を抱いていたものの、改めて聴いてみると何だかよくわからないまま人をその音空間に巻き込んでしまう恐ろしいほどの吸引力を持っているのであって、これを名盤と呼ばずに何を名盤と呼ぶんだよこのボケ!などと結局また乱暴なことを言い出したりするわけだが、あり得ないような時間と空間を創出するプレイヤーこそが偉大であるという点は音楽もサッカーも同じなんだな、きっと。
で、このキング・クリムゾンとファーストアルバムにおけるUKは二人のメンバー(ジョン・ウェットンとビル・ブラフォード)が共通しているのであり、こっちからあっちまでには五年の歳月が流れているわけなのだが、やっぱり「歯の食いしばり方」が違うというか、前者のほうが後者よりも激しくもがいているように聞こえるのだった。いや、だからってUKが「これぐらい楽勝だもんねー」とヘラヘラ笑いながらプレイしているはずはないんですけどね。それはもうKay'n師匠がGreenroomで書いているとおりで、たとえばどんなにくだらないバカコラムだって、書き手のほうはオノレの技術と集中力と脳味噌と人格を総動員して歯を食いしばりながら書いているのである。私がそうなので、みんなもそうだと思いたいわけですが。そうでもないのかなぁ。「8分の力で、ゆったりと力まず」に書いてる人もいるのかなぁ。あの人なんか、そうかもしれないよなぁ。
あの人って誰だかよくわからないが、とにかくそんなわけで、先日UKが「余裕でプログレしている」などと書いたことをちょっぴり反省しているのだが、しかし私が感じた「余裕」というのは、「プレイにおける余裕」ではなかったような気もするのでありまして、じゃあ何かというと「プログレすることにおける余裕」などと言うとまたワケがわからなくなるのだが、なんかこう、キング・クリムゾンは自らが「プログレになる」ことを目指して身悶えしているように感じられるのに対して、UKはプログレを対象化して練り上げようとしているというか、プログレを観察するメタレベルの視線があるというか、そんなような感じかしらね。
などと考えていたら、師匠がおそらくは半笑いで使っているであろう「ブリティッシュ・プログレの最終進化型」という地上波民放風の言葉がやけに興味深く思われてきた。「進歩」と「進化」の違い、なんてことを考えてみたくなるのである。進歩的なロックが進化するとは一体どういったことなのか。それはこれから考える(考えないかもしれない)が、私の理解では「進化」とは「適応」のことで、そうだとすればUKが「プログレの最終進化型」というのは何となく腑に落ちる気もする。でも、何に適応したのかはよくわからない。わからないが、進化による適応は「安定」という概念も伴っているらしく、ならばそれがUKの「余裕」の正体なのだろうか、どうなのだろうか。
2004.03.06.Sat. 14 : 20 p.m.
BGM : UK "NIGHT AFTER NIGHT"
 さっきGBで「憂国」の話をしたあとでふと思ったのだが、もしかして「UK」というユニット名(およびアルバムタイトル)には「英国ロックのアメリカ化」を憂える思いが込められていたりしたのだろうか。だったら『憂国の四士』って凄い邦題だよなぁ。レッスン時に師匠からイギリスのロックとアメリカのブルースの関係などについてレクチャーを受けたこともあって、そんなことを考えた。レッド・ツェッペリンがそうであるようにイギリスにはブルースの影響を受けたロック・ミュージシャンが大勢いるわけだが、どうやらプログレには「アンチ・ブルース」という側面があるらしい。それでもブルースから自由になるのは困難なことのようなのだが、もしプログレがある意味で「反米ロック」なのだとしたら(もっとも「ブルース=アメリカ」と決めつけてはいけないのでしょうが)、アメリカにプログレが少ない(少ないんだよね?)のも頷ける話だったりするのだがどうなんだろう。そして、ブルースのように人間の感情と直結した魅力的な音楽の浸透力から逃れるには、それに対抗できる強いロジックを持った(ある意味で排他的な?)「様式」が必要だったのではあるまいか。軍服姿のあの人の演説風景を思い浮かべつつ、「憂国」の具現化には様式美が欠かせないのかもしれない、なんて思ってみたりして。うーむ。ちょっと私には荷が重すぎる話になってきちゃったので、仕事に逃避します。
さっきGBで「憂国」の話をしたあとでふと思ったのだが、もしかして「UK」というユニット名(およびアルバムタイトル)には「英国ロックのアメリカ化」を憂える思いが込められていたりしたのだろうか。だったら『憂国の四士』って凄い邦題だよなぁ。レッスン時に師匠からイギリスのロックとアメリカのブルースの関係などについてレクチャーを受けたこともあって、そんなことを考えた。レッド・ツェッペリンがそうであるようにイギリスにはブルースの影響を受けたロック・ミュージシャンが大勢いるわけだが、どうやらプログレには「アンチ・ブルース」という側面があるらしい。それでもブルースから自由になるのは困難なことのようなのだが、もしプログレがある意味で「反米ロック」なのだとしたら(もっとも「ブルース=アメリカ」と決めつけてはいけないのでしょうが)、アメリカにプログレが少ない(少ないんだよね?)のも頷ける話だったりするのだがどうなんだろう。そして、ブルースのように人間の感情と直結した魅力的な音楽の浸透力から逃れるには、それに対抗できる強いロジックを持った(ある意味で排他的な?)「様式」が必要だったのではあるまいか。軍服姿のあの人の演説風景を思い浮かべつつ、「憂国」の具現化には様式美が欠かせないのかもしれない、なんて思ってみたりして。うーむ。ちょっと私には荷が重すぎる話になってきちゃったので、仕事に逃避します。
2004.03.05.Fri. 13 : 50 p.m.
BGM : UK "U.K."
GBでもちょっと書いたが、一昨日のレッスンでは師匠がブルース・スケールってやつを教えてくれた。いよいよ「ギターのお稽古」に「ロックのお稽古」が加わってきたような感じ。レッスンの進度と技術の進度にギャップがあるような気がしなくもないが、新たな課題が与えられると、まだこなしきれていない課題に取り組む意欲も高まるというものだ。こういうものは、たぶん、少し無理めの負荷をかけたほうが進歩が早いのであろう。だとすれば、やはり「ゆとり教育」なるものは人間をダメにするシステムなのかもしれない。
それにしても驚いたのは、師匠がレッスン前にベーグルを食わせてくれたことだ。いまどきベーグル自体は珍しくないが、自宅のキッチンでベーグルを焼いている独身男性というのはかなり珍しいと思う。いくら「食いたいものは自分で作る」がモットーだからって、ベーグル焼くかふつう。小腹が空いていたのでコンビニでメロンパンを買っていった私とは、人間の出来方が根本的に違う。このあたりが、同級生の師匠になれる人間と同級生の弟子になれる人間の違いなのである。チョリソー入りの自家製ベーグルはとても美味しかった。
レッスン終了後は、最近師匠が東急ハンズで買ったばかりの「レジスタ」というボードゲームにトライ。とはいえ、スーパーで買い物をするゲームではない。「レジスタ」とは「司令塔」を意味するイタリア語で、11個のコマを使ってゴールを目指す「フットボールのチェス」のようなものである。ルールはシンプルとは言えず、慣れるまで時間がかかる(私もまだ慣れていない)が、これはなかなか面白い。うまい具合にコマは赤チームと青チームに色分けされているので、FAカップ&プレミア連敗の仇を討つべく、Kay'nアーセナルに挑んだ江戸川チェルシーであった。だが、あれは前半20分頃だったか(プレイヤーの攻守が一往復するたびに時計が進むのだ)、アンリとベルカンプの巧みな連携プレイにしてやられて失点。師匠が、「ゴ〜〜〜〜ル!」と言いながらアンリにボードの上でゴールパフォーマンスをやらせていたのでアタマに来た。前半を終わって1-0。時間もなかったので今回は「とりあえず半チャン」ということにしたが、私も買って研究し、次回の雪辱を期したいと思う。オセロでセガレに負けることもあるぐらいボードゲームが苦手なので、まるで自信はないが。
 UKの『U.K.』は、師匠が中学だか高校だかのときにさんざん聴きまくったアルバムであるらしい。なので、借りてみた。ものすごくプログレらしいプログレというのが第一印象である。じゃあ「プレグレらしさ」って何だよ答えてみろよと言われると困るのだし、「らしさ」を身につけた音楽がプログレッシブなのかどうかという問題もあるのかもしれないが、まあ、そんなことを聴き手に考えさせるのがプログレのプログレたる所以であるようにも思われるのであった。ともあれ、78年に発表されたこのアルバムが、プログレッシブ・ロックと総称される音楽の一つの到達点であるのは間違いないのであろうし、おそらくUKのメンバーもそのことに自覚的だったに違いない。いや、実際はどうなのか私にわかるはずもないが、音を聴いていると、そういう覚悟のようなものが私には伝わってくる。たとえば、そうだなぁ、「7拍子の決定版を俺たちがやってやろうじゃないか」とか、そんなような感じ。
UKの『U.K.』は、師匠が中学だか高校だかのときにさんざん聴きまくったアルバムであるらしい。なので、借りてみた。ものすごくプログレらしいプログレというのが第一印象である。じゃあ「プレグレらしさ」って何だよ答えてみろよと言われると困るのだし、「らしさ」を身につけた音楽がプログレッシブなのかどうかという問題もあるのかもしれないが、まあ、そんなことを聴き手に考えさせるのがプログレのプログレたる所以であるようにも思われるのであった。ともあれ、78年に発表されたこのアルバムが、プログレッシブ・ロックと総称される音楽の一つの到達点であるのは間違いないのであろうし、おそらくUKのメンバーもそのことに自覚的だったに違いない。いや、実際はどうなのか私にわかるはずもないが、音を聴いていると、そういう覚悟のようなものが私には伝わってくる。たとえば、そうだなぁ、「7拍子の決定版を俺たちがやってやろうじゃないか」とか、そんなような感じ。
ただ、もしかするとプログレには、「プログレのプログレスを突き詰めていくとプログレ的でなくなる」という側面があるのではないか。「プログレらしいプログレ」でありながら、ここにはそれ以前の古いプログレにあった何かが失われているようにも聞こえるのである。何だろう。洗練されすぎてるんだろうか。プログレ的な音楽が始まったときと比べれば楽器や録音技術なども相当に進歩しているはずで、そのテクノロジーのプログレスが、過去のプログレをプログレたらしめていた「プログレスする意志」みたいなものを覆い隠しているのかもしれない。書いていてよくわからなくなっているが、たとえば初期のキング・クリムゾンやイエスが必死でプログレしていたように感じられるのに対し、UKは余裕でプログレしているように思えるのだった。
で、余裕でプログレできるようになると、プログレのモチベーションは下がるのではないか。だから彼らはアルバム一枚で離散してしまったのではないか。そんなふうに思うのは、最近、90年代後半に復活したPFMが録音した2枚のアルバム(『ULISSE』と『:serendipity』)を聴いたからで、私はどちらも気に入って何度もくり返し聴いているのだが、これはもう、ぜんぜんプログレっぽくない。バイオリンのマウロ・パガーニが入っていないせいもあるのだろうが、昔のPFMとはまるで違う音楽。もちろん、だからといって単なるポップスや単なるロックになっているはずもなく、評論家の中には「プログレの規範」と呼ぶ人もいるぐらいプログレだったPFMだからこそのテイストに満ちているのであるが、しかし10年の活動停止期間がなければおそらくこういう音楽は作れなかったわけで、きっと活動停止前はひどく煮詰まってたんだろうなぁと想像させるのである。そうやってプログレが煮詰まる寸前に作られたのが、たぶんUKの『U.K.』だったんでしょうね。したがって、味はものすごく濃い。しかしだからこそ、次はどうしたって雑炊でシメたくなるのだった。
2004.03.04.Thu. 12 : 35 p.m.
BGM : PFM ": serendipity"
そんなのは誰だっていいが、行き先の決まっていた昨日までの日々は楽だったよなぁ。待ち合わせの場所と時間のことを考えてるだけでよかったもんなぁ。一体全体、私は(そして私の原稿は)今日どこへ行けばいいのか。そんなことは自分で決めろと言われるだろうが、しかし自己決定には限界があるんである。新書の会で読んだ仲正昌樹『「不自由」論』(ちくま新書)にそう書いてあった。どうして限界があるのかは、もう忘れました。たぶん「ポスト・モダンだから」だな。とはいえポスト・モダンがよくわからないのだから話にならないが、まあ、ポスト・モダンだろうがロケット団だろうが自己なんてそんなに立派なもんじゃないし、他者との関係性によっていかようにも変容するわけだから、それはそういうもんだよ。うんうん。つまり原稿書きと面談では、その他者の有り様がぜんぜん違うんだな。今日の私はその切り替えがうまくいかなくて、他者不在のエアポケットに入ってしまったんだな。そうだそうだ。茫然自失じゃなくて茫然他失だ。他者がいないんじゃ、そりゃあ何も書けないよ。無理もない無理もない。と言いながらずいぶん書いているが、つまり私は日々こうして日誌をダラダラと書きながら内なる他者(たとえば猿渡君)を引き寄せているのかもしれない。……あ、突然思い出したぞ。猿渡は中学時代の校長先生の名前だ。