2004.04.15.Thu. 17 : 20 p.m.
BGM : STEVE VAI "FIRE GARDEN"
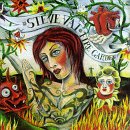 前に「ヤバイ」と書いたフランク・ザッパの『たどり着くのが遅すぎて溺れる魔女を救えなかった船』というアルバムで「Impossible Guiter Parts」とクレジットされているのが、スティーヴ・ヴァイというギタリストである。なので、後になって「ヤヴァイ」と表記すべきだったかと反省したりもしたわけだが、いま聴いている『FIRE GARDEN』はそのスティーヴ・ヴァイの大作だ。聴いていると、ギターという楽器が秘めているポテンシャルの大きさを感じて空恐ろしくなる。なんて壮大な世界に足を突っ込んでしまったんだろうか私は。
前に「ヤバイ」と書いたフランク・ザッパの『たどり着くのが遅すぎて溺れる魔女を救えなかった船』というアルバムで「Impossible Guiter Parts」とクレジットされているのが、スティーヴ・ヴァイというギタリストである。なので、後になって「ヤヴァイ」と表記すべきだったかと反省したりもしたわけだが、いま聴いている『FIRE GARDEN』はそのスティーヴ・ヴァイの大作だ。聴いていると、ギターという楽器が秘めているポテンシャルの大きさを感じて空恐ろしくなる。なんて壮大な世界に足を突っ込んでしまったんだろうか私は。
さて、このアルバムの白眉といえば一般的には『ファイアー・ガーデン組曲』ということになっているようであり、私もこれは凄い芸術作品だと思うのだが、しかし最も衝撃的だったのは2曲目の『クライング・マシーン』である。この曲だけアマゾンで試聴した人は、ことによると「これって松岡直也?」と思うかもしれない。つまり、メロディ(とくにAメロ=アマゾンで聴ける部分の後半)が歌謡曲なのだ。私は近頃、ひょっとして日本のフュージョンというのはジャズとロックではなく「ジャズと歌謡曲の融合」だったのではないかと思い始めているのだが、それはともかくとして、この『クライング・マシーン』という曲には、昭和の歌謡曲を聴いて育った人間が速攻でカラオケ屋に駆け込みたくなるぐらいのインパクトがあるのだった。そりゃあもう、思わず「なーみーだに濡ーれたー、わーたーしの頬をー」といった類の陳腐な歌詞をつけて歌いたくなるほど歌謡曲。「泣きのギター」どころか、これはほとんど号泣レベルと言っていい。
いったい何なのだこれは。……最初に聴いた瞬間、のけぞりながらそう思った。これがスティーヴ・ヴァイの中でもきわめて異色な作品であることは、彼のリーダー作を初めて聴いた私にだってわかる。とてもじゃないが、インポッシブルなギターを弾く人が好む種類の音楽だとは思えない。しかしスティーヴ・ヴァイはノリノリで歌いまくるのだった。どうしたんだスティーブ・ヴァイ。そんなことでいいのかスティーブ・ヴァイ。私の知っているスティーヴ・ヴァイはそんな人じゃないはずじゃないか。そんな訝しい思いを抱きつつ、私も昭和は好きなのでノリノリで聴いていたわけだが、なんとも複雑な心境ではあった。
だが曲の途中、彼はこれが一種のパロディであることを匂わせる。私にはそう聴こえた。スティーヴ・ヴァイは突如としてパーカッションにコミカルなリズムを叩かせ、「涙に濡れた私の頬を」にあたる部分を、ヨボヨボのジジイが杖をついて歩いているような調子でヘロヘロと弾き始めるのである。あとでライナーを読んだら、フランク・ザッパは日頃から「音楽はユーモアを忘れてはいけない」と口にしていたらしく、ヴァイはその言葉をこの曲で実践したのかもしれない。ともあれ私は、そのズッコケたフレーズを聴いて、これは「なんちゃって歌謡曲」だったのだと得心したのだった。
でも。その短い中間部が終わると、スティーヴ・ヴァイは再び号泣を始めるのである。どこまで本気なのか、こうなるとよくわからない。「そうは言っても、こういうのもたまにはイイよね」と言っているようにも聴こえるが、それは私がこのメロディにグッと来てしまう自分を肯定したいからだろうか。どうでもいいっちゃどうでもいい話だが、なんとも聴き方が難しい曲だ。私にも経験があるが、文章でも、シャレで書いたことを本気で受け止められるのは結構ツラい。無論、それも含めて引き受けるのが作り手の責任ですけども。
そんなこんなで、いずれにしろ私は『クライング・マシーン』という曲が気に入ったのであり、ちょっとギターで弾いてみたらやっぱりキモチ良かったのだが、いま私がコピーすべき曲は『クライング・マシーン』ではなく『モビー・ディック』である。GBの師匠の書き込みによれば、これをコピーするには弾く前に「或ること」をしなければいけないらしい。どうやらナゾナゾの類ではないようなので、トンチを利かせることなく真剣に考えているのだが、全然わからない。だって、すでに運指は把握したつもりでいたのだ。あとはフレーズを滑らかに弾く練習をするだけだと思っていた。しかし、弾く前に必要な「或ること」に気づいていない以上、私がいま弾いているのは『モビー・ディック』ではないのである。いわば『なんちゃってモビー・ディック』だ。私は『なんちゃってモビー・ディック』なんか弾きたくない。くっそー。何としても、明日のレッスンまでに気づいてやる。
2004.04.14.Wed. 14 : 00 p.m.
BGM : THE KINKS "THE KINKS"
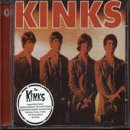 CCRの『雨を見たかい』もそうだったが、古いアルバムを聴くと「コレこの人たちだったのか」ということが往々にしてあるのであり、物知らずな私はヴァン・ヘイレンの『You Really Got Me』が元々キンクスの曲だということも、このデビューアルバムを聴いて初めて知ったのだった。温故知新ってやつだわな。何が「知新」なのかよくわからんが。さらにキンクスのセカンドアルバム『Kinda Kinks』も聴いたら、『Dancing In The Streets』も入っていた。私はどうしてこの曲を知っているんだろう。キンクスの演奏では聴いたことがないが、曲はどこかで聴いた記憶がある。っていうか、どっかのバンドで演奏したんだっけ? ブラス入りのカバー・バージョンとか存在する? うーむ。記憶が混濁している。
CCRの『雨を見たかい』もそうだったが、古いアルバムを聴くと「コレこの人たちだったのか」ということが往々にしてあるのであり、物知らずな私はヴァン・ヘイレンの『You Really Got Me』が元々キンクスの曲だということも、このデビューアルバムを聴いて初めて知ったのだった。温故知新ってやつだわな。何が「知新」なのかよくわからんが。さらにキンクスのセカンドアルバム『Kinda Kinks』も聴いたら、『Dancing In The Streets』も入っていた。私はどうしてこの曲を知っているんだろう。キンクスの演奏では聴いたことがないが、曲はどこかで聴いた記憶がある。っていうか、どっかのバンドで演奏したんだっけ? ブラス入りのカバー・バージョンとか存在する? うーむ。記憶が混濁している。
それにしても左手の小指が痛い。あなたに噛まれたわけではなく、ギターの練習によるものである。薬指も痛い。おもに第二関節のあたりがズキズキする。このところ時間に余裕があったし、自主的に『モビー・ディック』(レッド・ツェッペリン)のコピーとか始めたら熱中してしまったこともあって、ちょっとハードにやりすぎたかも。もしかして練習後にアイシングとかしたほうがいいのだろうか。しかし、それでもギターを弾くときは痛みを感じないのが不思議だ。ようやくカラダがギターに適応し始めたのかもしれない。それで日常生活に支障が出たんじゃ、進化なのか退化なのかわかりませんが。逆リハビリ。
一昨日から昨日にかけて、レアル・マドリー×押すな押すなオサスナ(リーガ第32節)やらアストン・ヴィラ×チェルシー(プレミア)やらニューカッスル×アーセナル(プレミア)やらをダラダラと観戦した。面白いこともあれば面白くないこともあった。サッカーはいつだって、面白いことと面白くないことの繰り返しだ。いちばん面白かったのは、オサスナが先制したシーンである。ゴール前に投じられたロングスローにオタオタしたマドリーのDF2名が味方同士で衝突し、エリア内で折り重なって倒れたまま、ゴールが決まるまで起き上がれなかったのには笑った。俯瞰の映像だと、みんなが必死でサッカーをやってるときに、彼らだけ何か別のコトで汗を流しているようにも見えた。押し倒すな押し倒すな。0-3となった試合の終盤、観客が白いハンカチを振り、敵のパス回しに「オーレ」を連呼したときは、サンチャゴ・ベルナベウが(バルサがダメなときの)カンプノウになったかのように見えた。だからマケレレさんを手放しちゃいけなかったんだよ。
それが何より証拠には、マケレレさんが故障でお休みしたチェルシーもまた、3失点で負けやがったのだった。あー面白くない。CLの勢いでプレミアもひっくり返せるような気がほんの少しだけしていたのだが、世の中そんなに甘くはないのう。あっという間に目標が3分の1に減った後の2試合を1勝1分で乗り切ったベンゲルはさすがにしぶとい。まあいいや。クレスポも2ゴールで復調の兆しだし。ヴェーロンも戻ってきたし。しかし、それがCLに良い影響をもたらすのかどうかは、定かではない。どうなんだヴェーロン。やる気あんのか。
2004.04.12.Mon. 12 : 55 p.m.
BGM : THE STYLE COUNCIL "CAFE BLEU"
 スタイル・カウンシルのこともポール・ウェラーのことも何も知らないので、この『カフェ・ブリュ』というアルバムに収められた『ホワイトハウスへ爆撃』という、タイトルは痛快だが曲調はどこか野暮ったい感じのインストゥルメンタル・ナンバーに、どんな意図が込められているのかはわからない。単に言葉の響きが面白かったというだけで、べつに深い意味はないのかもしれない。どうして「ホワイトハウスを」ではなく「ホワイトハウスへ」なのかということもわからないが、それにもさして意味はないのだろう。そもそも、18歳のフリーライターをはじめとする3人の日本人の安否が気遣われているときに、あと5日で40歳になるフリーライターがこのアルバムを聴いていること自体、とりたてて意味はない。たまたまレンタルショップで気が向いたので借りてみたら、たまたま『ホワイトハウスへ爆撃』という曲が入っていたというだけのことである。世の中にはいろいろなフリーライターがいる、ということでもある。
スタイル・カウンシルのこともポール・ウェラーのことも何も知らないので、この『カフェ・ブリュ』というアルバムに収められた『ホワイトハウスへ爆撃』という、タイトルは痛快だが曲調はどこか野暮ったい感じのインストゥルメンタル・ナンバーに、どんな意図が込められているのかはわからない。単に言葉の響きが面白かったというだけで、べつに深い意味はないのかもしれない。どうして「ホワイトハウスを」ではなく「ホワイトハウスへ」なのかということもわからないが、それにもさして意味はないのだろう。そもそも、18歳のフリーライターをはじめとする3人の日本人の安否が気遣われているときに、あと5日で40歳になるフリーライターがこのアルバムを聴いていること自体、とりたてて意味はない。たまたまレンタルショップで気が向いたので借りてみたら、たまたま『ホワイトハウスへ爆撃』という曲が入っていたというだけのことである。世の中にはいろいろなフリーライターがいる、ということでもある。そういえば、このあいだ日光へ行ったときに足を運んだ東武ワールドスクウェアにも、25分の1のスケールで作られたホワイトハウスの模型があった。その近くには、やはり25分の1で作られた世界貿易センタービルもあった。旅客機は突き刺さっていなかった。その先には25分の1のピラミッドや25分の1のアンコールワットや25分の1の法隆寺などもあった。ピラミッドやアンコールワットや法隆寺は長い年月を超えて現存しているが、ツインタワーはすでに存在しない。ホワイトハウスはどうだろうか。いつまで存在するのだろうか。というか、なぜ法隆寺という宗教施設は現存しているんだ?
いったい何を書いているんだろうか私は。こういうとき、こういうサイトをやっていると、それについて何か書かなければという強迫観念に駆られていけない。「どう思いますか?」というメールをもらったわけでもないのに、そこはかとなく無言の圧力を感じたりもする。そんなことも含めて、ただ苛々ばかりが募る今日この頃。共感できる人物がひとりも登場しない映画を観ているような気分である、などと言うと怒られるのだろうか。
ゆうべビデオで観たユベントス×ラツィオ(セリエ第29節)は、終了間際にカモラネージとトレゼゲにやられて1-0。ぜんぜん負けた気がしない。解説の後藤さんは盛んにユーベの内容がいい内容がいいとおっしゃっていたし、たしかに決定的なピンチも多かったけれど、失点するまではまったく負ける気がしなかった。ポコンとラッキーパンチが決まって、ヘラヘラと勝ってしまうような気がしてたんだけどもなぁ。いちばん悔やまれるのは、これがコッパの決勝第2戦ではなかったということだ。延期されてるローマダービーとか、いろいろ忙しいんだからさ、agg.2-1でラツィオの優勝ってことにしてくんないかしら。
2004.04.09.Fri. 11 : 00 a.m.
BGM : GEORGE HARRISON "ALL THINGS MUST PASS"
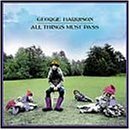 えーと、みなさん大丈夫ですか? 気持ちのほうは盛り上がっていますか? チャンピオンズリーグを楽しんでいますか? ベスト4の対戦表を見て、「どこがチャンピオンズやねん」とか「UEFAカップなのかそれは」とか吐き捨てていませんか? もう興味ないですか? ものすごく高揚してソワソワしているのは私だけですか? ゆうべビデオ観戦したデポルティボ×ミラン(CL準々決勝第2戦)はアッと驚く4-0の大逆転。agg.5-4でミラン敗退。これで、イングランド、スペイン、イタリアの国内リーグ首位チームが全滅してしまいましたね。ユナイテッドとユベントスもとっくに消えてますから、みなさんが「こんな大会、もう見ねぇよ」と言いたくなる気持ちもわからなくはありません。でもね、やっぱり現実は現実として受け止めないといけないし、過ぎ去ったことをクヨクヨしても始まらないじゃないですか。雲を吹き飛ばすのも、きみの気持ち次第。この灰色の日々もいつかは終わる。ジョージ・ハリスンも『All Things Must Pass』という曲でそんなふうに歌ってます。わかんないけど、訳詞にはそう書いてあります。だから済んだことは忘れて、比較的マシな明日を手にするために、せめて決勝がモナコ×ポルトにならないことを全力で祈りましょうよ。ほら、ワールドカップのときだって、決勝がトルコ×韓国にならないように祈ったでしょ? 祈りは通じるんですよ。っていうか、たまには私のためにチェルシーの勝利を祈ってくれたっていいじゃないか。歓喜に満ちた私の観戦記を読みたいだろ?「負けたときのほうが面白い」って言うなよ。ところで、今年のトヨタカップのチケットはまだ予約できないんでしょうか。
えーと、みなさん大丈夫ですか? 気持ちのほうは盛り上がっていますか? チャンピオンズリーグを楽しんでいますか? ベスト4の対戦表を見て、「どこがチャンピオンズやねん」とか「UEFAカップなのかそれは」とか吐き捨てていませんか? もう興味ないですか? ものすごく高揚してソワソワしているのは私だけですか? ゆうべビデオ観戦したデポルティボ×ミラン(CL準々決勝第2戦)はアッと驚く4-0の大逆転。agg.5-4でミラン敗退。これで、イングランド、スペイン、イタリアの国内リーグ首位チームが全滅してしまいましたね。ユナイテッドとユベントスもとっくに消えてますから、みなさんが「こんな大会、もう見ねぇよ」と言いたくなる気持ちもわからなくはありません。でもね、やっぱり現実は現実として受け止めないといけないし、過ぎ去ったことをクヨクヨしても始まらないじゃないですか。雲を吹き飛ばすのも、きみの気持ち次第。この灰色の日々もいつかは終わる。ジョージ・ハリスンも『All Things Must Pass』という曲でそんなふうに歌ってます。わかんないけど、訳詞にはそう書いてあります。だから済んだことは忘れて、比較的マシな明日を手にするために、せめて決勝がモナコ×ポルトにならないことを全力で祈りましょうよ。ほら、ワールドカップのときだって、決勝がトルコ×韓国にならないように祈ったでしょ? 祈りは通じるんですよ。っていうか、たまには私のためにチェルシーの勝利を祈ってくれたっていいじゃないか。歓喜に満ちた私の観戦記を読みたいだろ?「負けたときのほうが面白い」って言うなよ。ところで、今年のトヨタカップのチケットはまだ予約できないんでしょうか。
2004.04.08.Thu. 10 : 15 a.m.
BGM : FRANK ZAPPA "SHIP ARRIVING TOO LATE TO SAVE A DROWNING WITCH"
ゆうべは、モナコ×レアル・マドリー(CL準々決勝第2戦)をビデオ観戦。勝ったほうがチェルシーの相手である。とはいえ、昼間のうちにネットでうっかり結果を見てしまっていたので、観戦前からガッツポーズする準備はできていた。それにしても、試合を観るまでは「なんでそんなことになったかのう」と怪訝に思っていたのであるが、久しぶりに観るマドリーは何だかひどいことになっていたのである。みんな顔色が悪いし。見たことも聞いたこともない選手が何人もいるし。まあ、銀河系には名も無い星もいっぱいあるわけだが、こんなチームを追われたとあっては、そりゃあモリエンテスだって燃えるっちゅうもんですわな。
と、そんな物語性でも読み取らなけりゃ見ていられないぐらいダサい試合だった。白熱のロンドンダービーを観た後ということもあるが、これがチャンピオンズリーグの準々決勝だなんて思いたくない。たぶん、そもそも第1戦の2点差勝利&モリエンテスへのシンパシー&疲労等でモチベーションの低かったマドリーが、ぼやぼやしてる間にモナコのドタバタしたペースに巻き込まれちまったんだろうと思う。モナコって、どうしてここまで勝ち上がってきたんだか全然わからない。どいつもこいつもプレイがぎこちないし。スピードがあるわけでもなさそうだし。攻撃は行き当たりばったりな感じに見えるし。だが、それでもマドリーから3点取ってひっくり返したわけだから、何かあるんだろう。不気味だ。一つ思ったのは、モナコの連中はみんな動きは不細工だが妙に「人に強い」ということだ。ボールタッチは見苦しいのに結果的にはキープして味方につないでいる。フィンガリングは滅茶苦茶だが不思議とテンポはキープしてしまう修業中のギタリスト(私のことではない)、といったところか。侮るとやられる。しかし、この時期に「侮るとやられる」なんて言ってられること自体が嬉しかったりして。ぐふふ。
 きのう「近頃はわりと素朴なものを聴いている」などと書いた舌の根も乾かぬうちにフランク・ザッパというのもどうかと思うが、この『たどり着くのが遅すぎて溺れる魔女を救えなかった船』は、原稿が逼迫していた数週間前、仕事から逃避して立ち寄った中古店で何もわからずにタイトルだけで買ったものである。フランク・ザッパという名前は見たことも聞いたこともあったが、音は初めて聴いた。いまだかつて聴いたことのない音楽だった。というか、これは音楽なのか? 序盤はポップな雰囲気で、2曲目の『Valley Girl』はシングルとしてもヒットしたらしいが、3曲目の『I Come From Nowhere』あたりから徐々に世界が歪み始め、4曲目の『溺れる魔女』以降は音楽を超えた別の物のように響いてくるのである。たぶん根っこにはロックがあるんだろうけど、いわゆるプログレがジャズやらクラシックやら現代音楽やらといった他の音楽との融合を図ったものであるのに対して、フランク・ザッパはそこにとどまらず、音楽と他の分野の芸術(絵画とか彫刻とか演劇とか)を融合させたがっているようにさえ感じられるのだった。「正体はよくわからないが何だか凄いもの」がスピーカーからモリモリと溢れ出て来る。これまで私は今風の意味で「ヤバイ」という言葉を使ったことがなかったが、それを初めて使いたくなったのがこのアルバムだ。ヤバイよ、これ。
きのう「近頃はわりと素朴なものを聴いている」などと書いた舌の根も乾かぬうちにフランク・ザッパというのもどうかと思うが、この『たどり着くのが遅すぎて溺れる魔女を救えなかった船』は、原稿が逼迫していた数週間前、仕事から逃避して立ち寄った中古店で何もわからずにタイトルだけで買ったものである。フランク・ザッパという名前は見たことも聞いたこともあったが、音は初めて聴いた。いまだかつて聴いたことのない音楽だった。というか、これは音楽なのか? 序盤はポップな雰囲気で、2曲目の『Valley Girl』はシングルとしてもヒットしたらしいが、3曲目の『I Come From Nowhere』あたりから徐々に世界が歪み始め、4曲目の『溺れる魔女』以降は音楽を超えた別の物のように響いてくるのである。たぶん根っこにはロックがあるんだろうけど、いわゆるプログレがジャズやらクラシックやら現代音楽やらといった他の音楽との融合を図ったものであるのに対して、フランク・ザッパはそこにとどまらず、音楽と他の分野の芸術(絵画とか彫刻とか演劇とか)を融合させたがっているようにさえ感じられるのだった。「正体はよくわからないが何だか凄いもの」がスピーカーからモリモリと溢れ出て来る。これまで私は今風の意味で「ヤバイ」という言葉を使ったことがなかったが、それを初めて使いたくなったのがこのアルバムだ。ヤバイよ、これ。
2004.04.07.Wed. 14 : 20 p.m.
BGM : CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL "GREEN RIVER"
と、あと10日で30代も終わろうとしているにも関わらず子供のように叫んでいるのは、もちろん、アーセナル×チェルシー(CL準々決勝第2戦)を朝8時からビデオ観戦してきたからであーる。今日からセガレが小学校に通い始めたので、我が家は異様に朝が早いのだ。試合を見終わっても10時前だったので、びっくりした。ということは、つまり90分で決着がついたということであーる。どういう決着かというと、トップページを真っ青にしたくなるような決着だ。うほうほ。
チェルシーはとてもとてもとーっても素晴らしかった。今日の出来で勝てなきゃ、永遠にアーセナルには勝てないと思えるようなパフォーマンスだった。ラニエリを男にしようという結束感が漲り、それがギンギンギラギラな集中力を生み出していた。その表れが守備における「読み」だ。ほとんどの選手が、いつもより一歩早くアーセナルのパスに反応し、ピンチを未然に防いでいた。とりわけパーカーの俊敏さと言ったら。彼の危機察知能力がなければ、ピレスとアンリに加えてアシュリー・コールも復帰した世界屈指の左サイドを抑えることはできなかったに違いない。パーカー獲得はこの日のための補強だったとさえ言える。もちろん、メルヒオットのガッツも物凄かった。
もっとも、そのぶん反対側のサイドがケアしきれなかったのか、前半終了間際、ローレンのクロスからこぼれ球をスペイン人のガキに決められて1-0。ちょっとローレンをナメすぎましたね。あれだけ時間と空間を与えたら、そりゃあローレンだってあれぐらいのクロスは蹴るというものだ。
しかし、早い時間帯に先制するよりは先制させたほうがいいのである。それがFA杯、プレミア、前回の第1戦と続いた3試合で得た教訓だ。アーセナルとやるときは、先制するとロクなことがない。気取り屋のあいつらは欲深さというものに欠けるところがあるので、リードするとガツガツせずに手を緩めるところがある。この過密日程ならなおさらだろう。したがって、勝負はここからじゃ。それゆけチェルシー。いつもやられていることを、ここぞとばかりにやり返すのじゃ。ここで復讐せずに、いつ復讐するというのじゃ。
後半開始早々の同点ゴールは、GKレーマンを責めてはいけない。マケレレさんのロングシュートが凄すぎた。マケレレさんが唯一苦手にしているプレイがシュートであり、ふだんは滅多に枠に行かないのだが、今日は完璧にジャストミート。低い弾道でゴールマウスを強襲したあのシュートは、オリバー・カーンでも前に弾くのが精一杯だったであろう。「カーンを超えた」と自ら豪語するだけあって、レーマンもよく反応してパンチしたものの、いったん下がってオフサイドを解消してから再び飛び出したランパードの動きがそれを上回っていた。agg.2-2。こうなると、アウェイのチェルシーが有利である。1点取られても1点取り返しゃ勝ち上がりだ。ゆけゆけチェルシーどんとゆけ。リスクを負って攻めるのじゃ。
ほんとうに攻めまくりだった。いくらかピンチもあったが、青い怒濤は引くのも早く、アーセナルにほとんどカウンターを許さなかった。ゴール前で体を張り続けたテリーの存在感も忘れてはいけない。いや、今日のチェルシーはとにかく全員が目立っていた。全員のアタマとカラダとハートが最高のコンディションで噛み合っていた。必ず勝てる。いつか必ずゴールが決まる。観ていてそんなふうに思えたアーセナル戦は初めてだ。
試合の行方を決めた要素の一つが、両監督の選手起用だったのは間違いないだろう。ベンゲルは、アンリに代えてベルカンプ投入。たしかにアンリはアカンかったが、あの時間帯に途中出場したベルカンプは試合のテンションにうまく馴染めず困惑しているように見えた。スタメンだったら、もっと仕事ができただろう。2試合とも空を飛ばないオランダ人を使えるというCLでは本来あり得ない幸運を、ベンゲルは生かし損ねたように思う。ともあれ、アンリ抜きのベルカンプはそんなに怖くない。テリーやギャラスはちょっと怖かったかもしれないが、私は怖くなかった。私が怖くなければそれでいいのである。
かたやラニエリはダフとハッセルバインクを下げてジョー・コールとクレスポを同時投入。決して悪くない感じで攻撃しているときにアタッカーを2枚交替させるというのは、相当に勇気のいる決断であろう。だが、これが効いた。フレッシュな2人が前線を攪乱したことで、ジョー・コールのお陰でブリッジに、クレスポのお陰でグジョンセンに、それぞれ余裕が生まれたと見るのは結果論に過ぎるだろうか。左サイドをドリブルで進んだブリッジが中央のグジョンセンにパスを出し、そのままの勢いでゴール前に突進。絶妙の角度でグジョンセンがワンタッチの股抜きリターンパス。フィールド上に巨大な三角定規が出現したかのような鮮やかなワンツーだった。今日のグジョンセンは、すばらしく頭が冴えていたように思う。周囲の状況が、見なくても感知できる状態だったに違いない。
ブリッジが落ち着いてレーマンの左を抜いたとき、すでに残り時間は10分を切っていた。あー、もう、嬉しかったよう、嬉しかったよう。ラニエリも嬉しそうだった。アブラ様も嬉しそうだった。アブラ夫人が笑っているのも初めて見た。笑うんだな、あの女。ともあれ、もはやアーセナルに抵抗力はなく、agg.2-3でチェルシーがベスト4進出。次はどこだ。どこでもいいや。矢でも鉄砲でも持ってこい。最高の気分だぜベイベ。こんな日に日誌をリスタートせずに、いつリスタートするというのだ。
さて、久しぶりの更新なので何をどこから書けばいいのかよくわからないが、この2週間ばかり、ゴースト仕事の追い込み、二泊三日の温泉旅行、友人の結婚式、サッカーズの〆切と、ほんとうにバタバタしていた。しかし、それも昨日の入学式で一段落。桜もまだ咲き残り、空もよく晴れて、入学式らしい日和になってよかった。忙しくて当日まで感慨に耽る余裕もなかったけれど、なんだよもう小学生かよ参ったなオイ。給食費って月に4000円も払うのかよ。義務教育ってタダじゃないのかよ。知らなかったよ。まあいいや。安いっちゃ安いし。
ともあれ、セガレは女性教師が担任する1年1組である。新入生は1組40人、2組39人の総勢79名。あと2人いれば少人数の3クラスになったらしい。しかし人数が少なければいいのかというと、それも甚だ疑問だから、どっちでもいいと思う。少人数で教師の目が届きやすいっていうのは、子供から見ると逃げ場がないってことでもあるしね。陰でコソコソしてこその教室だ。死角のない集団生活は息苦しい。それに、40人ぐらい居たほうが気の合う人間も見つけやすいのではないか。集団に溶け込めなくても、1人か2人の友達がいれば生きていけるもんじゃないだろうかね。二十数人の一枚岩集団って、(うちのセガレがそうだとは言わないが)マイペースな人間には辛いと思う。イギリスみたいなお国柄ならともかく、個人主義的な感覚が希薄な日本で少人数クラスにすると、同調圧力をガス抜きできなくておかしなことになってしまうような気がしなくもない。
いずれにしろ、パーフェクトな教育システムなんか存在しないわけで、物は考えようである。公立の小学校に過大な期待はしないし、絶望もしない。わが子の将来を台無しにするようなヘンタイ教師に出会いさえしなければ、それで十分だと思うことにしよう。どんな環境だろうと、何らかの知恵はつく。
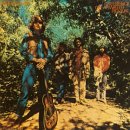 短期間にプログレ方面を探索し過ぎた反動なのか、近頃はわりと素朴なものを聴いている。クリーデンス・クリアウォーター・リバイバルは、インターネットラジオで出会って興味が湧いた。「クリクリ」ではなく「CCR」と略すらしい。ドラムの人がヘッドセットつけて歌うわけではないので勘違いしてはいけない。それはCCB。そういえばCCBって何の略だったんだろうか。「ロマンティックが止まらない」の頭文字? 違うか。違うよな。違いすぎるもんな。それはともかくCCRである。私は知らなかったが、愚妻は知っていたぐらいだから有名なバンドのようだ。実際、最初にベスト盤を聴いてみたら、ものすごく有名な曲が入っていた。『雨を見たかい』という曲で、CMなんかでしばしば耳にするやつだ。「雨を見たかい?」って、質問としてどうかと思う。何が訊きたいのかよくわかりません。
短期間にプログレ方面を探索し過ぎた反動なのか、近頃はわりと素朴なものを聴いている。クリーデンス・クリアウォーター・リバイバルは、インターネットラジオで出会って興味が湧いた。「クリクリ」ではなく「CCR」と略すらしい。ドラムの人がヘッドセットつけて歌うわけではないので勘違いしてはいけない。それはCCB。そういえばCCBって何の略だったんだろうか。「ロマンティックが止まらない」の頭文字? 違うか。違うよな。違いすぎるもんな。それはともかくCCRである。私は知らなかったが、愚妻は知っていたぐらいだから有名なバンドのようだ。実際、最初にベスト盤を聴いてみたら、ものすごく有名な曲が入っていた。『雨を見たかい』という曲で、CMなんかでしばしば耳にするやつだ。「雨を見たかい?」って、質問としてどうかと思う。何が訊きたいのかよくわかりません。
いま聴いている『グリーン・リバー』はCCRのサードアルバムで、とくに何がどうということもないが悪くない。というか、かなり気に入った。聴きながらギターでブルース・スケールの練習をするのにちょうどいい感じ。ちなみにジャケットでいちばん手前の人が持っているのは、例の「Dobro」(リゾネイター・ギター)だよね、たぶん。あ、そうそう、「リバー」といえば『週刊にっぽん川紀行』(学研)だ。友人が編集長を務めているので、そういうものが出るのは知っていたが、きのうの朝日新聞朝刊でドカンと全面広告が載っていてのけぞった。うおお。すげえビッグ・プロジェクトじゃないか。まだ買っていなくて申し訳ないのだが、江戸川だの深川だのと名乗っている私としては見逃せない企画である。次の筆名をナニ川にしようか迷っていたので、このシリーズを読んで決めることにしよう。その前に、別の筆名でナニを書くのか考えるのが先ですが。それはそれとして、川は大事だと思うので、興味のある人は書店へゴー。