2004.05.25.Tue. 10: 50 a.m.
BGM : BOB DYLAN "BLOOD ON THE TRACKS"
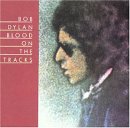 先週の土曜日は、セガレの満七歳の誕生日だった。ゾイドの「エナジーライガー」をプレゼントとして買い与え、一家総出で組み立てる。部品が多く設計図もやけに複雑なので数日かかると思っていたが、こういうモノを作るときだけは大変な集中力を発揮するセガレの粘りもあって、みごと完成。ちゃんと動いたので感動した。私は子供の頃から手先が不器用で、こういうモノは兄に任せてしまうタイプだったので、設計図を理解して自分で組み立てているセガレの姿を見ると尊敬してしまう。明らかに母親の血である。
先週の土曜日は、セガレの満七歳の誕生日だった。ゾイドの「エナジーライガー」をプレゼントとして買い与え、一家総出で組み立てる。部品が多く設計図もやけに複雑なので数日かかると思っていたが、こういうモノを作るときだけは大変な集中力を発揮するセガレの粘りもあって、みごと完成。ちゃんと動いたので感動した。私は子供の頃から手先が不器用で、こういうモノは兄に任せてしまうタイプだったので、設計図を理解して自分で組み立てているセガレの姿を見ると尊敬してしまう。明らかに母親の血である。ところで、このあいだ知ったのだが、この日(5/22)は奇しくもワーグナーの誕生日(1813)であるらしい。さらに私たち夫婦の結婚記念日(10/15)は奇しくもニーチェの誕生日(1844)なんだそうだ。なかなかの因縁話である。運命のひとひねり。意味よくわかんないけど。生きていれば、ワーグナーは191歳、ニーチェは160歳。あんがい最近の人だ。
日曜日はセガレの祖父母計4名を招いてお誕生日会。毎年この席では、私が料理を作るのが恒例になっている。このところレパートリーが増えていないので、申し訳ないと思いつつ、何年か前にも出したカルド・ガジェゴとトレヴィスのフジッリでお茶ニゴ。この二品はいつだって旨いが、とくに今回のフジッリはトマトと生クリームの配分が絶妙だった。しかし、初めて挑戦してみた茄子とモッツァレラのグラタンはいまひとつの出来。何事も経験だが、次もうまく作る自信がない。双方のおじいちゃん&おばあちゃんが、大相撲の千秋楽を熱心に語り合いながら見ていたのが意外だった。ふだんから見てるんですね、大相撲。もちろん(と言っていいのかどうか微妙だが)北勝力応援モードだったので全員ガッカリでしたけども。「それ行け!」と力を入れた3秒後に「やっぱり勝てないよな、そりゃあ」と脱力させるのだから、相撲ってある意味ジェットコースター・スポーツだ。
大仕事は一段落したものの、小仕事がいろいろあって気忙しい。7月に書く単行本の口述作業が始まり、その展開を考えつつ、一方で『わしズム』の対談原稿を進めながら、シギーにダメ出しされたコラムの手直しも考えなければいけない。自分としては前回も今回も手応えに大差ないのだが、読んでもらうと面白かったり面白くなかったりするのが悩ましい。自分の書いたものを客観的に分析できていない証拠である。自分のゴーストをしているつもりで書けばふだんどおり客観視できるのかもしれないが、なかなかそうもいかない。あー。短い文章って難しいなぁ。同じ1ページでも、5枚(サッカーズ)と3枚半(わしズム)では距離感がまるで違う感じ。もしかしたら300枚の本と500枚の本より違うかも。ちょっと、ブルーにこんがらがっている。能力の天井に頭をこすりつけながら書いているような気分。未熟な自分と向き合うのは、楽ではない。が、それも伸びシロがある証拠、ダメ出しされているうちが華だと自分に言い聞かせて、顔を上げることにする。でも天井は高くなっていない。
2004.05.21.Fri. 11: 50 a.m.
BGM : AEROSMITH "HONKIN' ON BOBO"
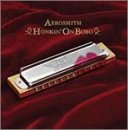 ふと気づけば、この半年足らずのあいだに、エアロスミスのアルバムをもう10タイトル以上は聴いている。いったい何をしてるんだ私はと思わないでもないが、好きなんだからしょうがない。で、私にとって、エアロスミスの最大の魅力は「やかましさ」である。ロックというのは総じてやかましい音楽だと思われているフシがあり、じっさい大音量でガンガン演奏するロックバンドはエアロスミスだけではないのは勿論なのであるが、エアロスミスの「やかましさ」はそういう意味のやかましさとはちょっと違う。「えーい、やかましいわい!」という関西風のやかましさだ。ボケとしてのやかましさ、とでも言えばいいだろうか。
ふと気づけば、この半年足らずのあいだに、エアロスミスのアルバムをもう10タイトル以上は聴いている。いったい何をしてるんだ私はと思わないでもないが、好きなんだからしょうがない。で、私にとって、エアロスミスの最大の魅力は「やかましさ」である。ロックというのは総じてやかましい音楽だと思われているフシがあり、じっさい大音量でガンガン演奏するロックバンドはエアロスミスだけではないのは勿論なのであるが、エアロスミスの「やかましさ」はそういう意味のやかましさとはちょっと違う。「えーい、やかましいわい!」という関西風のやかましさだ。ボケとしてのやかましさ、とでも言えばいいだろうか。そのやかましさが、歳を取るにつれて甚だしくなっているように思われるのが、エアロスミスの凄いところだ。スティーヴン・タイラーの「ゲゲゲゲゲゲゲゲガオーッ」という人間性を打ち捨てた奇怪な雄叫びで始まる『Permanent Vacation』(87年)を聴いたときは「やかましさもここに極まれり」と思ったものだが、『Get A Grip』(93年)では1曲目が終わるやいなや「ぐうぇ〜っぷ」という盛大なゲップを聞かせて「何しとんじゃワレ」という聴き手のツッコミを引き出し、さらに『Nine Lives』(97年)でものっけから「ミャー!ミャー!ミャミャー!!」という発狂した猫の鳴き声とも名古屋人の産声ともつかぬヘンチクリンな低音シャウトで笑わせてくれた。前作『Just Push Play』(01年)の1曲目にも、途中に「ヤッダッ! ヤッダッ!」と聞こえるタイラーの絶叫が入っている。ああ、もう、やかましいっつうの。
そんなわけで、アルバムの冒頭で何かしらブチかましてくれるエアロスミスが私は好きなので、この新作『Honkin' On Bobo』もどんなツカミから入るのかと楽しみにしていたら、藪から棒に「レイディ〜ス・アーンド・ジェントルメ〜ン!」と来るのだから嬉しいじゃないか猿渡君。エンターテインメントのオープニング挨拶としてはごく常識的な台詞ではあるものの、そんなにガッツ入れて叫ばんでもええやんか。っていうか、怒るトコちゃうやろ。みたいな。
といった具合に、エアロスミスは健在なのだった。今回はオリジナルが1曲だけで、大半が古いブルースナンバーのカバーということもあって渋い面が強調されてはいるものの、それでも、やっぱり、やかましい。こんなにやかましいブルースは滅多にないと思う。聴いていて、要するにエアロスミスの特徴は「誇張」なのかなと思った。ある意味、漫画的。ロックをカリカチュアライズしているとまでは言わないけれど、その娯楽づくりに傾けるエネルギーは大したものである。
ゆうべは、バレンシア×マルセイユ(UEFAカップ決勝)をビデオ観戦。UEFAカップの決勝は大概そうなのだが、そこまでの経緯をよく知らない大会のファイナルというのは、どうも観ていてピンと来ない。絶頂感に欠けるとでも言いましょうか。放送はしてるんだから観ときゃいいわけだが、時間にも限りってもんがあるんである。それでも、くどいようだが、これが「カップ・ウィナーズ・カップ」のファイナルであれば、それなりにクライマックスな感じがすると思うんですけどね。「UEFAカップ」じゃ、何の頂点を目指して試合してんのかわからん。まあ別にどうでもいいんだけど、せめてこの大会の優勝者を「チャンピオン」と呼ぶのはやめてほしいなぁ。カップ戦の勝者は「ウィナー」っていうんじゃないの?
試合のほうは、久しぶりに見たマルセイユのGKバルテズが、一対一になったミスタを倒して前半のうちに一発レッドを食らい、ハイそれまでよ。あの状況のあのプレイは即退場という取り決めになっているのかどうか知らないし、バルテズが自制すべきだったのは言うまでもないが、それにしてもいかがなものかと思うような判定ではあった。コッリーナさんのジャッジは必ず正しいって、みんな思い込んでないか? たしかに立派なレフェリーだと私も思うけれど、審判という立場の人間があまりに尊敬を集めすぎるのも、それはそれで考えものだ。判定が正しいか否かは、それを下した人間の言動に「説得力」があるかどうかという問題ではないと思う。社長や総理大臣の意思決定ならそういうこともあるかもしれないが、審判は「リーダー」ではない。
ともあれ、決勝の舞台にいきなり送り出されて、のっけからPKを受けるハメになったマルセイユのセカンドGKの人は、そのためにプロとしてベンチ入りしているんだから当然の仕事とはいえ、ひじょうに気の毒だった。なんて名前か忘れたが、これがまた気弱そうな顔をしてるもんで、ひどく同情してしまいました。2-0で敗れたあと、彼は地べたに座り込んだままなかなか立ち上がらなかったらしいが、それは悔しさのせいではなく、単に腰が抜けていたんじゃないかと思う。立ち上がったときは、なんだかキモチ悪そうだったし。あんな可哀想な人をつかまえて、「彼はハンドリングが下手だから、バレンシアは遠くからシュートを撃てばいいのに」と喜々としたイジワル口調で盛んにけしかけていた、何という名前なのかよく知らない解説の人の品性を、私は疑う。勝つために選手が作戦としてそれをやるのは当然だろうが、どちらに肩入れしているわけでもないニュートラルな観戦者として、私はそんなゴールシーンを観たくない。
2004.05.20.Thu. 10: 25 a.m.
BGM : 森圭一郎 "ONE"
終演後、六本木4丁目あたりで編集者と一杯飲んでいたら、店の前の狭い路地を馬鹿デカいリムジンがのろのろと移動していったので何かと思ったら、そこにはオジー・オズボーンが乗っているのだと、ガーナ人の店員が日本語で教えてくれた。おお。黒い安息日の人じゃないか。それしか聴いたことがないが、姿が見えないのが残念だった。聞くところによると、近所の時代屋とか何とかいう店で撮影だか収録だかをしていたらしい。ふーん。さらに、まったく関係ない話だが、店員のガーナ人は『ここがヘンだよ日本人』とかいう番組にも出演していたタレントだということがわかった。本人がそう言っていたので間違いないだろう。「バツイチ・コブつき・波瀾万丈」というワケのわからないキャッチコピーの入った、やけに派手な名刺もくれた。ガーナ人も十分にヘンだよ。妙な夜だった。六本木っておかしい。
先週の金曜日にようやく脱稿した単行本の担当者H氏よりメール。すでに原稿は著者の手に渡っており、さては内容にクレームでもついたかと慌てたがさにあらず、必要なら初版分のギャラを半分だけ早めに支払えるがどうするかという要件だった。うう。あんなに遅れて迷惑をかけたにもかかわらず、しかもまだ著者校の段階だというのに、なんていい人なんだろう。こういうことを言われると、次はちゃんと〆切を守ろうと思いますね。北風と太陽の寓話はかなり正しい。一方で原稿アップから9ヶ月経っても本にならず、したがって一銭も払ってもらっていない仕事もあったりなんかして資金繰りも楽ではないので、著者校が済んでこの仕事が私の手を離れたことが確定した段階でお言葉に甘えます、と返事を出した。ライターの生活を考えてくれるPHPは、とてもいい会社だと思う。
さらに、シギーから留守電にメッセージ。きのうの昼間にも電話をもらってコラムの原稿を催促されたのにまた催促かよと思ったがさにあらず、月末に福岡で『わしズム』の対談取材があるがどうするかという要件だった。福岡には(というより阪神地区より西には)行ったことがないので、ぜひ行きたい。でも、あの人たち、福岡でも平気で日帰りするからなぁ。今回はどうなんだろう。福岡の街を見ないで帰ってくる予感たっぷり。そんなことよりコラムを書かねば。ねばねば。
2004.05.19.Wed. 10: 50 a.m.
BGM : LES DUDEK "LES DUDEK"
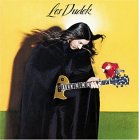 やはりレス・デューデックは愉しい。きのうから何十回もくり返し聴いているのは、76年に発表された初のリーダー作である。私が最初にUSENで気に入った『City Magic』という曲は、このアルバムの1曲目。当初はうっかり国内盤だけチェックして「在庫なし」だと諦めていたのだが、あらためてよく見てみたら輸入盤はあった。こういうことがあるから、やはり選択肢はいろいろあったほうがよろしい。
やはりレス・デューデックは愉しい。きのうから何十回もくり返し聴いているのは、76年に発表された初のリーダー作である。私が最初にUSENで気に入った『City Magic』という曲は、このアルバムの1曲目。当初はうっかり国内盤だけチェックして「在庫なし」だと諦めていたのだが、あらためてよく見てみたら輸入盤はあった。こういうことがあるから、やはり選択肢はいろいろあったほうがよろしい。ところでUSENで聴いたときは「フュージョン風味」などと感じた『City Magic』だが、あらためて聴くと、これはそういうもんではないですね。たぶん、ふつうにアメリカのロックなんだろうと思う。それが私の耳にあまりロックっぽく聞こえなかったのは、おそらくデューデックのギターがやけに明るいからではなかろうか。ロックのギターが一般的に暗いというわけではないけれど、この明るさはデューデック独特のもののような気がする。暗めのブルースを弾いても明るい。やたらカツゼツのいいギター、とでも言えばいいだろうか。なんともハキハキしているのである。ひょっとしたらダサいかもしれないフレーズも彼が弾くとカッコよく聞こえるのは、その天真爛漫さゆえか。「痛そうな顔」をせずに笑いながら弾いているように感じられたロック・ギタリストは、ジェフ・ベックに次いで二人目だ。
ともあれ、レス・デューデックはポップである。作戦としてのポップ、あるいは迎合としてのポップではなく、根がポップ。なんじゃないかな。プロデューサーがボズ・スキャッグス、バックをジェフ・ポーカロ、デヴィッド・ペイチ、デヴィッド・ハンゲイトといった二年後にTOTOを結成する人々が務めているとなればポップになるのも当然ということかもしれないが、しかしレス・デューデックはこのアルバムでも次作の『Say No More』でも、自分のやりたいことをやった結果としてポップになっているんだろうと思う。付け焼き刃の通俗的歴史観に基づいて言うと、70年代後半にロックがポップ化していく過程で、いわゆる「産業ロック」の誕生前夜にポロリと転がり出てきたのがこのアルバムなのかもしれないが、ロックが本当にポップ化したのかどうかも私にはわからないし、たまたま60年代終盤から70年代前半までのロックだけがあんまりポップじゃなかっただけなのではないかとも思わなくもない。まあ、そのへんはこれから勉強することとして、何が言いたいかというと、私はレス・デューデックが好きだということだ。五曲目の『It Can Do』はいつか必ずコピーしてやるから待ってろ。誰に向かって言っている。
ゆうべは、バルセロナ×ラシン・サンタンデール(リーガ第37節)をビデオ観戦。ルイス・エンリケのカンプノウ千秋楽であったらしい。現役続行の可能性もあるようだからアレだが、じつにテレビ映えする愉快なフットボーラーでありましたね。消えるときは退場したかと思うほど見事に消え、映るときはずっと主役を張り続けるというメリハリが素晴らしかった。スタンドに向かって胸をひとつポンと叩く控え目だが誇らしげなゴールパフォーマンスは、いつまでも私の脳裏に焼き付いていることだろう。試合のほうは、そのルイス・エンリケに譲ることなくロナウジーニョが蹴ったPK一発で1-0。スコア的には物足りないゲームだったものの、そのペナルティをゲットしたときのロナウジーニョの抜き方がすごかったので許す。あれは何と言うのか、右脚一本による「ひとりワンツー」とでも言えばいいのだろうか、とにかく、ちょっとあり得ないようなプレイだった。そのあと、同じ位置で同じことをダビッツが左脚でやろうとして失敗していたのが面白かったです。ダビッツ、浮き球のラストパスも何回か試みていたが、見た目だけでなくプレイでもロナウジーニョの影武者になろうとしているのだろうか。
引き続き、ムルシア×レアル・マドリー(リーガ第37節)をビデオ観戦。結果およびマドリーのダメさ加減は師匠からも愚妻からも聞いていたので、読書しながら横目でちらちら見ていたのだが、本から顔を上げるたびにフィーゴがへろへろになりながらドリブルし、ラウールが半泣きで泥にまみれていた。マドリーが負けるのは気持ちがいいが、あんなに七転八倒するラウールの姿はあんまり見たくない。退場ドミノが今回はベッカムに波及したこともあって、2-1でマドリー四連敗。クラブ史上初の屈辱なんだそうで、ザマアミロである。優勝には届かなかったバルサだが、二位浮上は十分にミラクル。マドリーとユナイテッドが予備予選送りって、弱小国の強豪クラブには迷惑な話でしょうけども。
2004.05.18.Tue. 14: 45 p.m.
BGM : GENTLE GIANT "THREE FRIENDS"

俺ってどうなのよ。
はい。ジャケットだけで買いました。ジェントル・ジャイアントの『Three Friends』というアルバムだ。どうなのよって……すげぇよ、あんた、すげぇよ。としか答えようがない。この半年ほどのあいだに私もいろんなロック・アルバムを見てきたが、発見した瞬間に息が止まったジャケットはこれが初めてである。スキッツォイド君やジェスロ・タルなんか目じゃないっつうの。無敵だよこの人。知っている人も多いかもしれないが、実はこの絵、首から下はジャケットの裏側に描かれていて、そこではバンドのメンバー六人がこのおじさんのてのひらの上に乗っている。つまり、このおじさんはキングコング並みにデカいということだ。彼こそがジェントル・ジャイアントなのである。そう言われてみれば、この上なくジェントルな微笑ですね。モナ・リザを超えている。私はこのアルバムのアナログ盤が欲しい。どうしても欲しい。30センチ×30センチのサイズで見たい。同じおじさんが描かれたファースト・アルバム(←今夜悪夢を見たい人はアクセスして「イメージを拡大」をクリックしてみたまえ)でもいい。中古店で見つけた人はご一報を。
いいかげん、予定どおり仕事を進められない自分に嫌気が差してきたので、あまり心地よい解放感は味わえなかったものの、とりあえず繁忙期が一段落したので週末はプチGW気分で過ごした。とはいえ、小学校入学と同時に高井戸西SCから久我山イレブンに移籍したセガレは土日ともサッカーの練習があったので、お出かけはナシ。いちいち金をかけて遠出せずに済むのは助かりますね。久我山イレブンは小学生を対象にした地域のクラブで、学校とは関係がないが、練習は校庭を借りて行っている。汗びっしょりになって走り回っているセガレを見て、やはりサッカーはこれぐらい広いグラウンドでやらなきゃいけないと思った。ただ、学校スポーツから地域のクラブへという方向性は良いと思うものの、サッカー限定というのがどうもなぁと思う。野球は野球で「久我山イーグルス」というクラブチームがあって、毎年、両者が新入生の獲得をめぐって張り合っているという噂も聞いた。べつに反目し合っているわけではないと思うが、同じグラウンドですれ違っている様子を見ていると(同じ校庭を時間帯をずらして使用しているのだ)、とくに挨拶することもなく、積極的に交流しようとはしていないような雰囲気。こういう競技間の垣根って、学校スポーツの延長上にあるものだと思うのだがどうなんだろうか。野球とサッカーが両方ともできる準総合型クラブにできないもんかなぁと思う。
日曜の晩にライブ観戦したラツィオ×モデナ(セリエ最終節)は2-1。インテルもパルマも勝ちやがったようなのでCL出場権は逃したが、まあよい。スタムもミラン入りが決まったようだし、ほかにも退団していく主力が何人もいるんだろうから、無理してCLなんか出てると今季のセルタみたいなことになりかねない。そうは言ってもUEFAカップはあるわけだから大変は大変だが、カップ・ウィナーとして堂々と戦ってもらいたいものだ。前から思っていたのだが、どうしてカップ・ウィナーズ・カップがUEFAカップに吸収されてしまったんだろう。UEFAカップを吸収してカップ・ウィナーズ・カップの名前を残したほうが、大会の意味がわかりやすくていいじゃないか。
しかし、そんなことはともかくラツィオ来日だ。なんで来るのかよくわからないが、7月19日に仙台、27日に神戸戦だ。行くぞ。必ず行く。私が行かないで誰が行くというのだ。いや、みんな行くのか。ニッポンのラツィアーレ大集合だ。仙台と神戸のスタンドがスカイブルー一色に染まる風景を想像すると、胸が熱くなる。……あ、おれ、CIRIO時代のシャツしか持ってないんだった。色は問題ないとしても、ちょっと古すぎるよな。チャイナカラーじゃないしな。でも、いま、ラツィオのシャツなんかそこらで売ってんのかなぁ。
きのうは久しぶりに師匠のところでギターのレッスン。もろもろの修正点を指摘され、緻密な練習を疎かにしていたことを反省した。初心者は「ギターを弾く」ばかり考えて「音楽を演奏する」を忘れがちなので気をつけなければいけない。リズムとテンポを正確に表現すること。それができなければ、どんなに「それっぽいフレーズ」が弾けても音楽にはならないのである。とは言いながら、今回は初めて「和音」の鳴らし方を教わり、これがまあ、ちょっとやってみただけで「ロックっぽいフレーズ」になるから困ったものだ。楽しいなぁギターって。『スモーク・オン・ザ・ウォーター』と『天国』という、「楽器屋で弾いてはいけない二大名曲」の一部も習い、喜々として弾く。近所の人に「もう文化祭の季節?」と怪訝に思われるかもしれない。