2004.06.09.Wed. 12: 20 p.m.
BGM : GILBERTO GIL "1971 GILBERTO GIL"
もしかすると、出版関係者は「本番」のある職場の緊張感に馴染めないのかもしれない。あの会社では、オフィスのそこここでオンエア中の番組がBGMとして流れているのであるが、考えてみるとこれは、番組の出演者やスタッフにとって大変なプレッシャーなのではないか。何かミスでもあれば、リアルタイムで社内から一斉に「無言のダメ出し」がなされることになるんである。社長室から総務部や経理部にいたるまで、全社員が同時に「あちゃあ」と顔をしかめる風景が想像できてしまうのだから、これは作っている人間にとってはたまらん。たとえば講談社の全社員が自分の書いたものを同じ時間に読んでいるようなもので、そんなの私はイヤだ。
もちろん、ラジオにしろ本にしろ、最終的には作ったものが不特定多数の聴取者や読者の耳目に触れるわけで、社内レベルの批評に耐えられない者が「マス」のプレッシャーに耐えられるわけがないと人は思うだろうし、本来そうあるべきなんだろうとは思う。けれども不思議なもので、現実には、何千人何万人もの読者の目にさらされることよりも、ひとりの編集者に書いたものを差し出す瞬間のほうがはるかに怖い。緊張する。少なくとも私はそうだ。それはたぶん、その原稿を良しとするかどうかに、相手の生活がかかっているからだと思う。ダメなものをダメなまま世に出せば会社が損をするのだし、それは編集者本人の出世や給料にも跳ね返ってくるであろう。ある制作物の価値を認めるかどうか、その評価自体が自らの社会的評価に直結するわけで、これはやはり、いわゆる一つの真剣勝負というやつである。ある意味、マネーの虎だ。むろん読者だってなにがしかの対価を支払って面白いとかつまらないとか言うわけだが、評論家でもないかぎり、その評価に生活まではかかっていない。だからって編集者の評価が必ず正しいということではないし、読者の評価に価値がないはずがないのは言うまでもないことだが、ともかく、ひとりの編集者を乗り越えるのは書き手にとってきわめて大きな跳躍なのである。役者にとってのオーディション、ミュージシャンにとってのプロデューサーやディレクターなども、たぶん似たようなものだろう。
ところでインターネットは、そういったハードルなしに、作り手が受け手に向かってダイレクトに情報を発信することを可能にした。いまや小学生でさえ、自作の小説を全世界に向けて公開している世の中だ。1日に何万ものヒット数を誇るカリスマ的テキストサイトもあると聞く。いや、仮に1日のヒット数がヒトケタであったとしても、作り手は表現者としての喜びを多少なりとも感じられるものだ。それはそれで、きっと良いことであるに違いない。個人が表現の場を手軽に持つことができるのはすばらしい。私自身、こうしてその恩恵に預かっている。だが、自らの生活をかけて立ちはだかるハードルを持たない表現物は、その厳しさにさらされていないぶん甘くなりやすいし、独善にも陥りやすいだろう。商売でやっているわけではないのだから、個々のサイトに文句をつけるつもりはない。そんな天に唾するようなことはしない。ただ、そういう表現の場としてのインターネットが、世の中全体の「表現力」のようなものを脆弱化させてしまう恐れはあるような気がする。「命がけのダメ出し」が人の表現力を鍛えるのだとしたら、こうして多くの個人が自分だけの裁量でどうにでもできるメディアを持てる状況が本当に豊かな有り様なのかどうか、はなはだ疑問である。
 W杯予選でブラジル国歌を歌っていたジルベルト・ジルのことを原稿に書いたくせに実はまだ彼の音楽を聴いたことがなかったので、慌てて後付けで『1971 GILBERTO GIL』を聴いている。『イン・ロンドン』という邦題(邦題なのかそれは)のとおり、何やら母国で政府に弾圧されたジルベルト・ジルが、60年代末から亡命していたロンドンで録音したアルバムであるらしい。すごい時期にロンドンに居たものである。それ以前のジルベルト・ジルを聴いていないので比較のしようがないのであるが、このブルースな感じは英国で受けた影響がモロに出たものであるに違いない。めちゃめちゃカッコイイのである。何度も何度も聴いている。全編英語でブルースを歌っているのに、ちゃんとブラジルの音楽のように聞こえるような気がするのは、当然と言えば当然だが面白いと言えば面白い。アコギ一本で歌っている『Sgt.Pepper's Lonely Hearts Club Band』(ボーナストラック)が新鮮。これはこういう曲でもあったのか、という発見が得られるカバーというのは実のところ滅多にないものだが、この演奏は、あの曲が潜在的に持っていた未知の鉱脈を掘り起こすことに成功しているように思われる。具体的に何がどうと言えないので、小難しい言い方で誤魔化してみました。こういう物言いをハードルなしに通過させてしまうのが、ネットの良くないところだ。それにしても驚いたのは、ジャケットで見られるジルベルト・ジルの髪の毛の量だった。嗚呼、三十年の歳月よ。ブラジル国歌を歌っていたあの人は、ほんとうにジルベルト・ジルだったのだろうか。
W杯予選でブラジル国歌を歌っていたジルベルト・ジルのことを原稿に書いたくせに実はまだ彼の音楽を聴いたことがなかったので、慌てて後付けで『1971 GILBERTO GIL』を聴いている。『イン・ロンドン』という邦題(邦題なのかそれは)のとおり、何やら母国で政府に弾圧されたジルベルト・ジルが、60年代末から亡命していたロンドンで録音したアルバムであるらしい。すごい時期にロンドンに居たものである。それ以前のジルベルト・ジルを聴いていないので比較のしようがないのであるが、このブルースな感じは英国で受けた影響がモロに出たものであるに違いない。めちゃめちゃカッコイイのである。何度も何度も聴いている。全編英語でブルースを歌っているのに、ちゃんとブラジルの音楽のように聞こえるような気がするのは、当然と言えば当然だが面白いと言えば面白い。アコギ一本で歌っている『Sgt.Pepper's Lonely Hearts Club Band』(ボーナストラック)が新鮮。これはこういう曲でもあったのか、という発見が得られるカバーというのは実のところ滅多にないものだが、この演奏は、あの曲が潜在的に持っていた未知の鉱脈を掘り起こすことに成功しているように思われる。具体的に何がどうと言えないので、小難しい言い方で誤魔化してみました。こういう物言いをハードルなしに通過させてしまうのが、ネットの良くないところだ。それにしても驚いたのは、ジャケットで見られるジルベルト・ジルの髪の毛の量だった。嗚呼、三十年の歳月よ。ブラジル国歌を歌っていたあの人は、ほんとうにジルベルト・ジルだったのだろうか。
2004.06.07.Mon. 10: 45 a.m.
BGM : SANTANA "ABRAXAS"
 4日間も更新が途絶えてしまったが、生きている。博多で取材した対談原稿を3日未明に仕上げ、その日の午後は半蔵門で単行本の口述作業、帰宅後にサッカーズのコラムを書こうとしたらネタを何も考えていなかったことに気づいて焦った。こういうときは散歩をするとアイデアが浮かぶという話をよく耳にするので、試しに夜10時頃から近所をぶらつき、公園のベンチで独り煙草をふかしてみるとアラ不思議、なーんも思いつかないのである。誰がそんなことを言い始めたのか知らないが、「散歩でひらめき」はウソなので真似しないほうがいい。散歩の最中、人はただ意味もなく散歩のことを考えてしまうということがわかった。公園のベンチで煙草を吸っているときは、公園のベンチのことを考えている。散歩は不毛だ。ちなみに私は、風呂やトイレで何かを思いついたこともない。
4日間も更新が途絶えてしまったが、生きている。博多で取材した対談原稿を3日未明に仕上げ、その日の午後は半蔵門で単行本の口述作業、帰宅後にサッカーズのコラムを書こうとしたらネタを何も考えていなかったことに気づいて焦った。こういうときは散歩をするとアイデアが浮かぶという話をよく耳にするので、試しに夜10時頃から近所をぶらつき、公園のベンチで独り煙草をふかしてみるとアラ不思議、なーんも思いつかないのである。誰がそんなことを言い始めたのか知らないが、「散歩でひらめき」はウソなので真似しないほうがいい。散歩の最中、人はただ意味もなく散歩のことを考えてしまうということがわかった。公園のベンチで煙草を吸っているときは、公園のベンチのことを考えている。散歩は不毛だ。ちなみに私は、風呂やトイレで何かを思いついたこともない。絶望的な気分で家に帰り、担当すずき君に「4日の午前中までには」などと約束したことを猛烈に後悔しながら、茶の間でゴロリと横になった。しばし天井を睨みつけながら茫然としてみたが、茫然としていると茫然のことを考えてしまう。茫然と向かい合う私。そこには、合わせ鏡のような無限の虚無が広がっていた。しかし与えられた時間は有限なので、一生懸命にサッカーのことを考える。散歩に出かける直前に見ていたブラジル×アルゼンチン戦で、キックオフ前にブラジル国歌を歌っていたジルベルト・ジルとミルトン・ナシメントの姿が脳裏に蘇ってきた。「これだ!」と膝を打つような勢いはまるでなく、「だから何?」と自問自答するような具合だったものの、そこを起点にダラダラといろいろなことが頭の中でつながる。ブラジルは偉大だ。そう思って今日はサンタナを聴いているのだが、私は大いなる勘違いをしていたようで、カルロス・サンタナってメキシコの人なんですね。『キャプテン翼』に出てくるカルロス・サンターナと混同していたのかもしれん。そんなことはともかく、眠くて原稿は書けそうにないので、アイデアのメモだけ書いて深夜2時に就寝。翌朝8時に起床し、自宅で一気に書き上げた。11時半に送稿。綱渡りもいいところである。金曜日はそのまま自宅で過ごし、週末も休んでいたので今日まで日誌が更新できませんでしたという、要するにそういう話だ。
で、ふと気づけば、書くべき仕事が手元に一つもない。次の大仕事(単行本)は来月だ。〆切直前にもしばしば茫然とする私だが、これはこれで茫然とせざるを得ないのだった。ヒマになったらアレもしようコレもしようと思っていたのに、漠然とした生活の不安を前に茫然としている。しかし先のことを考えてもしょうがないので、とりあえず今月は読書とギターの練習と欧州選手権にウツツを抜かすことにしよう。仕事場の片づけもしなければいけない。自宅へのブロードバンド導入もまだやってないし、使用不能になっている携帯電話の機種変更も急務だ。それに、区の健康診断も受けなければいけないんだった。やることはいろいろある。酒も飲みたい。歌も歌いたい。でも小仕事もほしい。
欧州各国のリーグ戦が終わると、地上波民放を見る時間が増える。ゆうべはテレビ朝日で放送していた『クリムゾン・リバー』という映画を鑑賞した。竜頭蛇尾。ああいう込み入ったミステリは、最後に金田一耕助や京極堂みたいな人が出てきてきちんと謎解きをしてくれないと、私のような頭の悪い受け手には意味がよくわからないのである。ちなみに、この映画にロバート・フリップは出てこないので勘違いしてはいけない。さらに、何年かぶりで『ガキの使いやあらへんで』を見た。ザ・ベストテン形式で芸人たちの「ハイテンション芸」とやらを次々と見せるという企画だ。3割から4割の芸人が裸で登場するあたり、明らかに煮詰まっている。ただ千原兄弟のお兄さんは、何やら前衛演劇のごとき異様な迫力を感じさせて秀逸。彼のパフォーマンスだけが唯一「芸」に見えた。しかし2時間半のテレビ視聴の中でいちばん面白かったのは、社内の派閥争いに疲れたOLが「どっちでもいいの」と電話をするスタッフサービスのコマーシャルだった。
2004.06.02.Wed. 20: 35 p.m.
BGM : THE ALLMAN BROTHERS BAND "BROTHERS AND SISTERS"
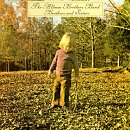 オールマン・ブラザーズ・バンドが二人のメンバーを亡くした後に作ったのが、この『ブラザーズ・アンド・シスターズ』であるらしい。10代のレス・デューデックがゲスト参加しているのも、このアルバムだ。裏ジャケットを見ると、おそらくはメンバーのブラザーとシスターたちだと思われる人々が一堂に会して撮った写真があり、「サザン・ロックの人は集合写真が好き」という私の説を裏付けてくれているわけだが、そんなことはともかくとして、このところ「家族」について考えさせるニュースばかり続くのはどうしてなんだろう。拉致された家族が解放された人、拉致された家族の安否がわからない人、家族を初めて自分の祖国に迎え入れた人、家族にどこで会えるかなかなか決まらない人、家族のキャリアや人格を否定する動きにご立腹めされているお方、家族が戦場で殺された人、家族が教室で命を奪われた人。家族が教室で人の命を奪ってしまった人のことも忘れてはいけない。今までだって、あらゆる事件や事故の背後には家族がいたはずなのに、こんなに家族に目が向くことはなかったような気がする。家族は人を孤独や絶望から救う存在であり、しかしながら時として人を孤独や絶望に追いやる存在でもある。そんなことを考える。
オールマン・ブラザーズ・バンドが二人のメンバーを亡くした後に作ったのが、この『ブラザーズ・アンド・シスターズ』であるらしい。10代のレス・デューデックがゲスト参加しているのも、このアルバムだ。裏ジャケットを見ると、おそらくはメンバーのブラザーとシスターたちだと思われる人々が一堂に会して撮った写真があり、「サザン・ロックの人は集合写真が好き」という私の説を裏付けてくれているわけだが、そんなことはともかくとして、このところ「家族」について考えさせるニュースばかり続くのはどうしてなんだろう。拉致された家族が解放された人、拉致された家族の安否がわからない人、家族を初めて自分の祖国に迎え入れた人、家族にどこで会えるかなかなか決まらない人、家族のキャリアや人格を否定する動きにご立腹めされているお方、家族が戦場で殺された人、家族が教室で命を奪われた人。家族が教室で人の命を奪ってしまった人のことも忘れてはいけない。今までだって、あらゆる事件や事故の背後には家族がいたはずなのに、こんなに家族に目が向くことはなかったような気がする。家族は人を孤独や絶望から救う存在であり、しかしながら時として人を孤独や絶望に追いやる存在でもある。そんなことを考える。
ところで私の家族はといえば、きょうの午後、セガレが入学後はじめてクラスメイトを家に招いたそうだ。一般的には安心すべき事態なのであるが、しかしこれはまったく親が想定していなかった展開なのであり、それというのも、ひとりで遊びに来たのが女性だったからである。うーむ。あり得ないでしょう、それは。どうやら教室で隣の席に座っているお嬢さんらしいが、二人きりでセガレの部屋で過ごす時間帯もあったりなんかして、愚妻をドキドキさせたんだとか。やってることが、過不足なしにキッカリ十年早いような気がする。しかもセガレが招いたというよりは、彼女のほうが来たがったようだ。放課後、本人がうちに電話をかけてきて、愚妻に「遊びに行ってもいいですか」と確認したらしい。セガレから何も聞かされていなかった愚妻がうろたえたであろうことは想像に難くない。押しまくられてないかR太郎。私の「可愛いのかその女は」という質問を、愚妻が聞こえないフリをしていたのも気になる。大丈夫なんだろうか。あした教室の黒板に相合い傘とか書かれたりしないのか。近頃の1年生はそんなもんなのか。それよりも気がかりなのは、このことを相手のお嬢さんの父親が関知しているかどうかである。私が怯える必要はないのだが怖い。ドラえもんのビデオを見ながら、セガレがお嬢さんを押し倒してと取っ組み合いをして遊んでいたなんて、お父さんには絶対に言えない。
2004.06.01.Tue. 20: 10 p.m.
日本×マリ(U-23)放送中
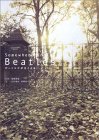 さて『わしズム』ワークはまだ続くのであって、きのうの月曜日は次号二本目の対談記事の取材で博多に出張。福岡空港に到着するなり、前夜OKをもらったばかりのコラムのゲラをクニトーさんから渡されてありゃまこりゃまである。いかに進行が切羽詰まっているかがわかるというものだ。対談の開始前に取材現場で赤を入れて返した。愉快なムードで対談の収録を終えた後、西中州の店で馬肉料理をたらふくいただく。馬肉を口にしたのは生まれて初めて。刺身も焼き肉も、とても美味しかった。あえて「ウマかった」とは書かない。書いてるけど。ヒヒーン。食後、カメラマンの福岡耕造さんとその助手の女性と三人で中州を徘徊。福岡さんは最近、ビートルズゆかりの地を訪ね回って撮った『Somewhere In The Beatles ビートルズがきこえる…』という写真集を出したばかりだとのことで、当然、ビートルズをはじめロックに造詣が深いのであり、ご自身もギタリストとして仲間とバンドをやってらっしゃるとのことで、そんなこともあって、初対面でありながらすっかり話が弾んでしまったのだった。ビートルズ好きのあなたやあなたも、ぜひ買いなさい。一竜という有名な屋台で芋焼酎を呑みつつ、深夜三時までロック談義および業界の情報交換。泥酔してホテルに戻ってベッドに倒れ込み、しかし一刻も早く帰京してテープ起こし作業に着手せねばならぬので、八時に起床して羽田行きのJALに搭乗。ライターの仕事は取材が終わってから始まる。仕事の手離れがいいカメラマンが、ちょっと羨ましい。
さて『わしズム』ワークはまだ続くのであって、きのうの月曜日は次号二本目の対談記事の取材で博多に出張。福岡空港に到着するなり、前夜OKをもらったばかりのコラムのゲラをクニトーさんから渡されてありゃまこりゃまである。いかに進行が切羽詰まっているかがわかるというものだ。対談の開始前に取材現場で赤を入れて返した。愉快なムードで対談の収録を終えた後、西中州の店で馬肉料理をたらふくいただく。馬肉を口にしたのは生まれて初めて。刺身も焼き肉も、とても美味しかった。あえて「ウマかった」とは書かない。書いてるけど。ヒヒーン。食後、カメラマンの福岡耕造さんとその助手の女性と三人で中州を徘徊。福岡さんは最近、ビートルズゆかりの地を訪ね回って撮った『Somewhere In The Beatles ビートルズがきこえる…』という写真集を出したばかりだとのことで、当然、ビートルズをはじめロックに造詣が深いのであり、ご自身もギタリストとして仲間とバンドをやってらっしゃるとのことで、そんなこともあって、初対面でありながらすっかり話が弾んでしまったのだった。ビートルズ好きのあなたやあなたも、ぜひ買いなさい。一竜という有名な屋台で芋焼酎を呑みつつ、深夜三時までロック談義および業界の情報交換。泥酔してホテルに戻ってベッドに倒れ込み、しかし一刻も早く帰京してテープ起こし作業に着手せねばならぬので、八時に起床して羽田行きのJALに搭乗。ライターの仕事は取材が終わってから始まる。仕事の手離れがいいカメラマンが、ちょっと羨ましい。
2004.05.28.Fri. 10: 50 a.m.
BGM : FREE "HEARTBREAKER"
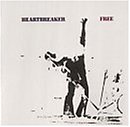 ふと気づけば、フリーのアルバムをもう5枚も聴いている。ライブを含めても7枚しか発表していないようだから、これはもう「フリーのファン」と呼ばれても文句は言えない。いや別に文句はないし事実ファンなのだが、なんでそんなに聴きたくなるのか我ながらよくわからないのもたしかだ。わりかしフツーな感じだし。……お。例によって話は逸れるが、「フリー」と「フツー」って似てるよな。誤解されやすい「フリーライター」を名乗るのはやめて、これからは「フツーライター」にしようかな。でも「不通ライター」だと思われると困るしな。なに書いても意味が通らないみたいだもんな。それより、フリーのコピーバンドを作るなら名前は「フツー」に決まりだよ。うんうん。決まり決まり。何の話だっけ。そうそう、フリーはフツーだという話だ。
ふと気づけば、フリーのアルバムをもう5枚も聴いている。ライブを含めても7枚しか発表していないようだから、これはもう「フリーのファン」と呼ばれても文句は言えない。いや別に文句はないし事実ファンなのだが、なんでそんなに聴きたくなるのか我ながらよくわからないのもたしかだ。わりかしフツーな感じだし。……お。例によって話は逸れるが、「フリー」と「フツー」って似てるよな。誤解されやすい「フリーライター」を名乗るのはやめて、これからは「フツーライター」にしようかな。でも「不通ライター」だと思われると困るしな。なに書いても意味が通らないみたいだもんな。それより、フリーのコピーバンドを作るなら名前は「フツー」に決まりだよ。うんうん。決まり決まり。何の話だっけ。そうそう、フリーはフツーだという話だ。まあ、要はそのケレン味のなさが私は好きなんだろうと思うわけで、いま聴いている『HEARTBREAKER』というラストアルバムもフツーにいいのだが、あんまりフリーらしくはない。それもそのはずで、このときにはベースのアンディ・フレイザーが脱退しちゃっているのだ。フリーのフツーさに微妙な匙加減で独特の味つけをしていたのが彼のベースだと私は感じているので、どうも物足りないのである。あと、このアルバムではラビットというふざけた名前のキーボーディストが正式メンバーとして加わっているのだが、フリーにキーボードは似合わないような気がする。音数の少ないシンプルなサウンドの中で、ポール・コゾフの汗臭いギターとアンディ・フレイザーのデオドラントなベースが絡み合うフリーが私は好きなのだということが、これを聴いてわかった。ベターっと鳴っているオルガンは邪魔。フレイザーがいないので、そうでもしないと間が持たないんだろうとは思うが。
いずれにしろ、もし私がリアルタイムでフリーを聴いていたら、フレイザーが脱退した時点で「このバンドは終わった」と感じたことだろう。ところで、ではフレイザーの代わりに誰がベースを弾いているのかというと、山内テツという人だった。おお。フリーに日本人が参加しとったのかー。戦前、アメリカの黒人野球チームに「ジャップ・ミカド」と呼ばれる日本人プロ選手がいた!という話を聞いたときのような感動がある。でも、やっぱり、アンディ・フレイザーのほうがいい。
3月にゴーストした原稿が本になって届いた。脱稿して以来、編集部から何の音沙汰もないので、また著者が気に入らなくてゴチャゴチャになっとるんじゃないのかと疑心暗鬼にとらわれていたのだが、ざっと眺めてみた限り大幅な書き直しはされていないようだし、予定どおりスムースに刊行にこぎつけたようで、ホッとした。あらためて自分の文章を読んでみても、まあまあ、うまいこと書いている。なんだよ、まだまだ大丈夫じゃないか俺。というような自画自賛は虚しいので、著者校が問題なく進んでいるなら進んでいると連絡して安心させてほしいよなぁと思うのだが、編集者も忙しいのだし、「便りがないのは良い知らせ」と思うことにしよう。それにしても苦笑させられたのは、著者の書いた「はじめに」にあった、こんな一文である。
本書は、質問に答える形で語り下ろしたテープ速記をまとめ、それを私がチェックするという手法で作られたもので、内容については私が責任を負うべきものである。本が特定されると困るので表現は少し変えてあるが、あんまり責任を負いたくなさそうですね。「まあ、しょうがねえか」とか何とかブツブツ言いながら、稟議書にハンコを押してるみたいな感じである。まあ、それはそういうもんだと思うし、他人の書いた原稿に心から納得できるほうがどうかしていると思ったりもするのだが(私がそんなことを言ってはいけないんだろうが)、しかし、ここまであからさまに本の「作り方」を明かさなくてもいいのではないか。「言い訳」だもんな、これ。著作物の責任を著者が負わずに誰が負うというのか。当たり前じゃないか、そんなこと。読者に対してちょっと失礼なんじゃないかと思いました。
2004.05.27.Thu. 14: 05 p.m.
BGM : BACAMARTE "DEPOIS DO FIM"
話を戻すと、このところ、どうも書いた原稿に匿名・署名を問わず自信が持てなくていけない。無論これまでも自信満々だったわけではないし、いつだって「大丈夫かなぁ」と心配しながら送稿しているわけだが、なんちゅうか、ここ一年ぐらい、原稿の帳尻が合っていないように感じてしまうというか、うまく着地が決められていないような気がするというか、そんなような不安定さを以前よりも強く感じるのだった。編集からNGが出ているわけではないものの、なーんかシックリこない。帳尻を合わせる作業に倦んでいるような気がしなくもないが、それが仕事なんだからそんなこと言ってちゃダメだ。ダメよダメダメ、ダメなのよ。
関係あるような無いような話だが、発売中の『わしズム』に「匿名原稿は私の人格とは関係ない」というようなことを書いたところ、編集部に読者の方から「どんな原稿であれ書き手の人格と無関係ということはあり得ないのではないか」という疑問の声が寄せられたらしい。あの本の読者がいかに真面目かということがわかって勉強になったのだが、それはともかく、たぶん「匿名原稿」という言葉を使ったことが誤解の原因だろう。私はゴーストライターとして書く原稿や雑誌のタイアップ記事や対談原稿などのことを言ったつもりなのだが、おそらくその読者は、新聞記者が署名なしで書くコラムのようなものを思い浮かべたんだと思う。たしかに新聞の匿名記事はそもそも大半が署名で書くべきものだと私も思うし、名前を「伏せて」書いた自分の意見やら感想やらを「人格と無関係」と言うのは卑劣なことだ。でも、ゴースト原稿や対談記事をまとめるライターは名前を「伏せて」いるわけではなく、文責が自分にはないから名前が出ないだけで、その内容に自分の人格を投影させたら、そのほうが問題である。というか、対談原稿を自分の人格と関係づけろと言われたって、私にはできません。あえて言うなら、テープ起こし原稿が速記者の人格と関係ないのと同じことだ。
そのへんを区別するには「匿名原稿」ではなく「リライト原稿」とでも書けばよかったのかもしれないが、「リライト」という作業がどこまで世間に認知されているかよくわからないので、それもいかがなものか。うーむ。結局のところ、「フリーライター」という職業の幅広さが世の中に理解されていないということのような気がする。たとえば『フリーランス・ライターになる方法』(吉岡忍・古木杜恵グループ/生活人新書) という本があって、私は未読だが、アマゾンではこんなふうに紹介されていた。
フリーの雑誌記者になる方法と技術、知識と心構えを、先輩たちがよってたかって、伝授。経済的には、確かにきびしい。しかし、走り回って取材し、記事を書く。それが雑誌上で活字になる。多くの読者が読んでくれる。そのうえ原稿料がもらえる。この仕事の、喜びの大きさと自由を伝えたい。リライターとしての私が共感できるのは「経済的には、確かにきびしい」という部分だけだが、世間のフリーライターに対する認識は、まあ、こんなものだろう。フリーライターといえば「記者」であり、記者といえば「走り回る」のが仕事だ。走り回りもせずに何のフリーライターぞ、というぐらいのモンである。汗をかきかき東奔西走した結果、ときにはヤクザとトラブって殺され、ときには外国で武装組織に拉致されてこそのフリーライターだ。雑誌によっては、複数の記者が「走り回って取材し」て書いたデータ原稿をとりまとめて最終原稿にするリライター(アンカーマン)がいることも少なくないのだが、ふつうの人はそんな分業体制があることなんか知らないだろうし、知っていたとしても、それは編集者の作業だと思っているに違いない。私自身、出版社に入って雑誌の編集者になるまで知らなかったよそんなこと。
そんなわけだから、「ライター」というからには自分の「好きな分野」や「得意なジャンル」を持って積極的に情報を発信するのが仕事だと思われるのは当然だ。興味があろうがなかろうが与えられた材料を記事や本という形にまとめ上げる「技術者としてのライター」が存在するなんて、思いも寄らないのである。世間に認知されていない仕事は山ほどあるだろうから、それは全然かまわないのだが、誤解されるのは困るよなぁ。
というようなことを三枚半のスペースで説明するのは無理なので、そのあたりがコラムの難しいところだよね、というのが結論でした。さて言い訳はこれぐらいにして、書き直し作業に取りかからねばねば。ねばーギブアップ。
などと言いながら、ポルト×モナコ(CL決勝)を朝からビデオで観てきたので、もう少し続ける。平幕同士の優勝決定戦、などと言っては怒られるかもしれないけれど、判官贔屓をしにくい組み合わせなので当初は「どっちも頑張れ」と思っていたものの、キックオフからわずか三分後にアゴを出して疲労感を滲ませていたジョルジュ・コスタの姿を目にしたあたりから、ポルト寄りの姿勢になりましたね私は。なので、3-0は嬉しかった。もっとも、ニュートラルに観ていても、紙一重のプレイが多くて大変面白い試合だったと思うが。試合中、かなりイケてると思われる「似てる人」を発見したのだが、これは次回のお茶ズボまで非公開にしておこう。それより、リプレイのときにグルリンチョとアングルが変わる画期的な映像を初めて見たのだが、どういった仕組みになってるんだあれは。複数のカメラで撮った映像を瞬時に合成してたりするわけなのかしら。すごいねぇ。あれがリアルタイムでやれるようになったらと思うと、想像しただけで目が回りますが。
そういえば、タイムアップしたところでビデオを止めてしまい、表彰式を観るのを忘れていた。帰宅したら、ジョルジュ・コスタがビッグイヤーを掲げているシーンを堪能しなければ。そんなシーンがあり得たなんて驚きだ。こうなると、欧州選手権でフェルナンド・コウトが雄叫びを上げるシーンだって、あり得ないとも言い切れない。なにしろパンカロが二度目のスクデットを獲るような世の中なのだ。コウトにだって、神様が微笑んでくれることがあっていい。