
 |
| #06 | TOP | BACKNUMBER | FUKAGAWA | B.I.P. | GUEST BOOK | #08 |
|
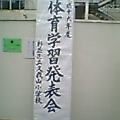
10月10日の校門。
10月10日のスコア。
BAGDAD CAFE
DARWIN !
汚染された世界
10月9日の書庫。
はるかー遙歌
СТАЛКЕР
たからもの
幸せな夜 儚い時間
|
2004.10.12.Tue.
21: 50 p.m. BGM : ベネズエラ×ブラジル(W杯南米予選)
セガレの出場種目は4つ。最初の「ぜったいに元気!」という(日本語として熟しているのか熟していないのか微妙な)タイトルのダンスでは、序盤からノリノリで、誰よりも激しいアクションを見せていた。ハジケていた、と言ってもよい。踊りが好きなようだ。父親の私は小学校から高校まで運動会や体育祭を前向きに楽しんだことが一度もないので、わが子のハイテンションが信じられない。50メートル走は、4人中3位。距離があと10メートル長かったら隣の女の子に抜かれていたかもしれないが、最後まで横をちらちら見ながら抜かれまいと歯を食いしばって走る姿は親を喜ばせる。1位の子との差も、親が思っていたほど大きくはなかった。団体競技の玉入れでは、みんながホイホイと拾っては投げ拾っては投げているのに対して、セガレは慎重なプレイスタイル。時間をかけてじっくりカゴを狙ってから投げている。3つか4つぐらいは決めていた。シュートの本数が少ないぶん、ゴール決定率は誰よりも高かったかもしれない。全校競技の大玉ころがしでは、大玉を顔面で受けて転倒。私はよく見ていなかったのだが、倒れたセガレの脚の上を大玉が転がっていったらしい。アメリカのアニメだったら、押し潰されてペラペラになった状態で大玉に張りついて一緒に転がっていくところだ。ともかく、なんというか、とてもアグレッシブに大会に参加していたことは間違いない。結果的には、所属する赤組が360対225の大差で白組を粉砕したのだった。 それにしても見ていて気になったのは、玉入れのカゴである。正式名称がわからないので、ここでは仮に「玉入れられ」と呼ぶことにするが、あの「玉入れられ」はあまりにも旧態依然としていないだろうか。少なくとも私が小学生だった30年前から、何ら技術革新が起きていない。そう思ったのは、入った玉をカウントするときだ。いまだに「玉入れられ」全体を横倒しにして、中から手で玉を取り出している。倒したポールを持って支えている人は重くて大変だ。玉入れ競技には必ずあの作業が伴うわけだから、もっと簡便にできないものだろうか。たとえばポールが真ん中あたりで折れてカゴが低い位置まで下がるようにするのは、そう難しいことではあるまい。いや、現在の科学技術をもってすれば、「玉入れられ」を立てたまま、スイッチを押すたびにカゴから玉が一つずつ飛び出るようにするぐらいのことは朝飯前だろう。いやいや、玉の重さを計って電光掲示板に個数を一発表示することだって可能なはずだ。玉入れられメーカーに、そういう発想がないことが理解できない。スポーツ用品全体の進歩から、学校体育は取り残されていないか。ハイテク運動会を目指さないかぎり、その業界に未来はない。かもしれない。
買っただけで観ていないLDは『七人の侍』と『ストーカー』だけではないのであって、土曜の晩に鑑賞した『バグダッド・カフェ(完全版)』も押入の中で何年か「つんどく」になっていたものだ。これも私ではなく愚妻が買った。イラク映画ではなく、アメリカを舞台にしたドイツ映画なので勘違いしてはいけない。映像も音楽も登場人物も、すべてが美しい。こういう映画にありがちな「どうだ美しいだろう」という押しつけがましさがないところが、また美しい。この淡々とした禁欲的な作品には、「ジャスミンの帰還」以降のハッピーなエンディングが蛇足だったような気がしなくもないが、それは私の個人的な趣味(悲劇好き)に基づく印象か。ともあれ、持っていて損はない映画である。愚妻は私と違って、ちゃんと何度も見たくなるLDを買っているのだなぁ。えらいえらい。
バンコ・デル・ムトゥオ・ソッコルソ(バンコ)はイタリアのプログレバンドである。意味は知らない。この『ダーウィン!』は1972年のアルバム。鬼形智という人が書いたライナーによれば、「キリスト教的価値観に疑問を投げかけた過激なコンセプト・アルバムだった」んだそうだ。ちなみに1曲目の『革命』の歌詞には、こんな一節がある。「アダムは、もはや死んだんだ。僕の起源は人間ではなく、猿だ」。30年前のイタリアでは、これが「過激」なメッセージと受け止められるぐらい、ダーウィニズムが危険視されていたんだろうか。ともあれ、バンコがどこまで本気で「キリスト教的価値観に疑問を投げかけた」のかはわからないが、進化論なんぞというテーマでコンセプト・アルバムを作ってしまうという、その大風呂敷ぶりが70年代だったのかなぁとも思う。全体に哀調を帯びたダークなサウンドで、きのうのRDMよりもこちらのほうが『汚染された世界』というタイトルが似合う感じ。アルバムのラスト曲『疑問』の歌詞には、こんな一節がある。「永遠の歯車、重い歯車/ゆっくりときしる音がする/君は踏んでいるんだよ/僕の骨と意欲を」「顔は変わっても、何も変わらない/先祖の古い精液/僕は怒りを叫んだ/だが、僕も死にそうだ」。なんだか哀しそうですね。もしかしたら、むしろダーウィンにアダムとイヴの物語を汚されたバチカンの心情を代弁しているのかもしれない。
時事キーワードノックが佳境を迎えるなか、シギーに頼まれたゴースト仕事にも本腰を入れなければならなくなり、ますます仕事が逼迫してきた。ふたつ以上のことを同時にこなせない不器用な私にとっては苦しい状況で、きのうもどちらを先にやろうか迷っているうちに、ふと気づくと仕事場の掃除&片づけなど始めていたじゃありませんか。自分で自分が信じられない。大量にプリントアウトしなければならない文書があり、しかし現在使っているMacには手持ちのレーザープリンタが接続できないため、古いMacを物置から引っ張り出して設置しようと思ったらスペースがなく、そのための場所を書庫の片隅に確保しようとしているうちに大変なことになってしまったのである。書庫に山積みされていたダンボール箱などを処分し、本棚をひとつ移動。分解されていたテーブルを組み立てて、そこにMacを設置した。腰が痛くなったが、仕事部屋がもうひとつできたようで、気分は悪くない。屋根裏部屋みたいな雰囲気で、妙に落ち着く。Macもスタンドアローン状態なので、そっちで原稿を書いたほうが逃避を抑えられそうな気もする。
ゆうべは、WOWOWで録画しておいた映画『マイノリティ・レポート』を鑑賞。公開から2年も経っている映画を何の予備知識もなく楽しめるんだから、世間知らずってすばらしい。へえ、こういう映画だったのか。タイトルだけ耳にして、少数民族か何かの哀しい歴史かなんかを地味に描いた眠たい映画(べつに少数民族の歴史が眠たいとは言ってない)だとばかり思ってました。アホである。歴史どころか未来の話だ。おもしろかった。でも、トム・クルーズの上司があの陰謀をどういう段取りで仕組んだのかがよくわからない。それも私がアホだからなのだろうか。あのホテルにトム・クルーズをおびき寄せるためには、本人にプリコグ(予知能力者)の透視イメージを見せなければならず、しかしプリコグが未来を透視するには上司のみならずトム・クルーズにも「犯意」が芽生えている必要があるようにも思われ、だが彼の「犯意」はプリコグの予知あってのものだからして……ああ、わからないわからない。メグ・ライアンの『ニューヨークの恋人』なんかもそうなんだけど、タイムスリップ系の映画を観ると、いつも頭が混乱する。
ロヴェッショ・デッラ・メダーリャ(RDM)はイタリアのプログレバンドである。「メダルの裏側」という意味だそうだ。どういう意味だ。この『汚染された世界』は1973年のアルバム。左の写真ではわかりづらいが、ジャケットにはバッハの顔があしらわれており、アルバム全体がバッハをモチーフにしている(「ヨハン・セバスチャン・バッハ」というタイトルの曲もある)。邦題がおどろおどろしいわりに、希望を感じさせる音。バロック風のクラシカルな響きとロックのサウンドが、時には滑らかに、時にはスパークするかのように混じり合っていておもしろい。こういうのを聴いてしまうと、たとえばEL&Pの『展覧会の絵』とかそういうやつは、ちょっと聴くのが辛くなる感じ。イタリアのプログレは、妙ちきりんなものが多くて愉快だ。
買っただけで観ていないLDは『七人の侍』だけではないのであって、ゆうべ鑑賞したタルコフスキー監督の『ストーカー』も押入の中で何年か「つんどく」になっていたものだ。私ではなく愚妻が買った。私はたぶん一本も観たことがないが、彼女はタルコフスキー作品が好きらしい。 さて『ストーカー』は、1979年の作品。無論ロシアがまだソ連だった時代だ。ブレジネフさんもまだ生きていた。久しぶりにソ連と書いてみると、昔は感じなかった漢字カナ交じりへの違和感が噴出する。ソ連。ソ連。今なら2ちゃんねるで「ン連」と表記されるに違いない。ンビエト社会主義共和国連邦。ちょっと楽しそうだ。ソ連を知らない子供たちは、正しいイントネーションで発音できるだろうか。「のれん」と同じイントネーションになってしまったりしないだろうか。と、およそどうでもいい心配をしてみた。ちなみに「СТАЛКЕР」は「クタンケップ」ではなく「スタルケールルルッ」(英語のSTALKERに相当)と発音するんだと思うが、映画冒頭の役者名やら何やらのロシア文字にも読めないものが多くて愕然としたので、自信はない。まあ、間違っていたら旧ロシア語クラスの同級生が教えてくれるだろう。あらすじ等を知りたい人はここらあたりをどうぞ。 ワケのわからない映画だったが、ひと晩たつと、不思議とまた観たい気分になる。ビデオで観たことがあるのに、あえてLDを買った愚妻の気持ちもわからなくはない。作品の舞台である謎の立入禁止区域「ゾーン」もまた、ワケがわからないがまた侵入したくなる場所なのかも。それにしても、旧ソ連の風景や旧ソ連人の風貌には「絶望」という言葉がよく似合う。『トレイン・スポッティング』のスコットランド人たちといい勝負。『トレイン・スポッティング』の若者たちが「ゾーン」に侵入する映画を観てみたい。僕たちは、絶望について一体どれだけのことを知っているだろうか。
きのう、セガレが学校からPTA広報誌をもらってきた。私の疑問を見透かしたようなタイミングで、下記のような記事が掲載されている。たぶん、私以外の保護者からも「なぜ?」が相次いだのだろう。運動会を「体育学習発表会」などと言い換えられれば、ふつうは「なぜ?」と思う。
うーむ。ビミョーというかアイマイというか、ひたすら要領を得ない文章であるなぁ。「隔靴掻痒」という言葉は、こういうときに使うために存在するのかもしれん。引き写しながら、うっかりリライトしてしまいそうになるじゃないか。私が思うに、これが読み手の欲求不満を募らせるのは、この文章がタイトルに反して「なぜ『体育学習発表会』か」についてだけ説明しており、「なぜ『運動会』から」の部分に触れていないからであろう。要するに、質問の答えになっていないのである。
それに、これはいったい「誰の」文章なんだろうか。冒頭の一文からして、平成14年度からそういう「ねらい」で運動会を行ってきたのが、「校長と教頭」なのか「本校」なのか「この国(あるいは東京都あるいは杉並区)の小学校」なのかわからない。ちなみにセガレの学校に現在の校長が着任したのは平成15年4月、教頭は平成16年(今年)4月である。去年のことは知らないが、今回こういう記事が出たということは、去年まではふつうに「運動会」だったのであろう。それが今年から「体育学習発表会」になったのだから、そこには校長か教頭の意向が反映されていると見るのが妥当だ。なのに事の始まりは2人が着任する前の「平成14年度」にあるという。よくわからない。よくわからないが、憶測や想像(やほんの少しの悪意)をまじえて私なりに上の文章を書き直してみると、こういうことだろうか。
|
|
| #06 | TOP | BACKNUMBER | FUKAGAWA | B.I.P. | GUEST BOOK | #08 |
|
 |