
 |
| #12 | TOP | BACKNUMBER | FUKAGAWA | B.I.P. | GUEST BOOK | #14 |
|
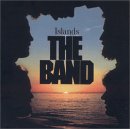
Islands |
2004.11.23.Tue. 12: 20 p.m. BGM : THE BAND "ISLANDS"
そんなジャケットも含めて、どこか「宴会の余興」的な雰囲気の漂うラスト・アルバムである。ファースト・アルバムの『Music From Big PInk』以降、ザ・バンドの音楽はキャリアを積むにしたがって軽く明るくなっていったような印象もあり、その意味では必然的な結末だったのかもしれないのだが、それにしてもこの『Islands』はかなりのヘラヘラ感だ。『Georgia On My Mind』なんか、「元プロ歌手が酔客に懇願されて歌ったカラオケ」みたいだもんなぁ。回転するミラーボールが目に浮かぶ。でも、まあ、楽しいよ。ザ・バンドは素敵だよ。 というわけで、Capitolからリリースされたアルバムはこれでコンプリート。あとは『Last Waltz』(こちらはワーナー・ブラザーズ)を残すのみだが、もったいなくて、すぐ聴く気にならない。どうも私は「取っときたがる性格」のようで、『七人の侍』もまだ観ていないし、レッド・ツェッペリンDVDもまだ最後まで観ていないのだった。そういえば98年フランスW杯のスコットランド×モロッコ戦もまだ観ていない。それはまあどうでもいいんだけどね。どっちが勝ったのかも忘れた。ともあれ『Last Waltz』は、サンタさんへのウィッシュリストに入れておくことにしよう。
ゆうべビデオで観たチェルシー×ボルトン・ワンダラーズ(プレミア第13週)は、あろうことか2-2のドロー。チェルシーが2失点もするなんて、とってもワンダラーズだ。キックオフから34秒で決まったダフの電光石火ゴールも、CKからロッベンの低いクロスに飛び込んだティアゴのゴールもビューティフルなものだったが、2-0から追いつかれたらあかんよ。あかんあかん。結果が悪かったのみならず、内容的にも先行きへの不安を抱かせるものだった。ボルトンの1点目、CKに飛び出したのにボールに触れなかったGKツェフ(どうしてチェフじゃないんだろう)は、やはり前後の動きに問題がある。そういうタイプなのか調子が悪いのかはわからないが、アーセナル戦でレーマンに嗤われるような失態だけは絶対に避けなければいけない。あと、ロッベンに早くも慢心の気配が見られる。ボール持ちすぎじゃ。たしかに最近の貢献度は抜群に高いが、おまえ一人でゴールしてると思うなよ。もっと謙虚に活躍しなさい謙虚に。さらにモウリーニョも、グジョンセンをジョンソンに替えるという守備的采配で大失敗。ジョンソン投入で守備が固まるとはフツー思えないので、守るつもりではなかったのかもしれないが、とにかく失敗。失敗したから2-2。まあ、どうやらアーセナルもまた失敗したみたいだからいいけどさ。しかし、こういうことをしていたのではバルサに勝つことはできません。バルサも応援してるからいいけどさ。 |

Moondog Matinee |
2004.11.22.Mon. 13: 55 p.m. BGM : THE BAND "MOONDOG MATINEE"
それにしてもカラフルなバルサのサッカーではあった。巨大な絵筆でフィールド上に極彩色をちりばめているかのような90分。その一大絵巻に絶妙のアクセントを加えていたのが、守備から攻撃へのシャープな切り替えである。その鮮やかなコントラストは、それだけで観る者を興奮させる効果を持っていた。さぁ前を向け! そして追い越せ! それはサッカーで勝つために必要な極意であるばかりではなく、生を楽しみたいと願う全ての人間に向けられた普遍的なメッセージだったかもしれない。スポーツが芸術であることを証明したゲームだった。
オールディーズのカバー集であるザ・バンドの『Moondog Matinee』を聴きながら、はてムーンドッグとは何だろうと調べていたら、ムーンドッグのディスコグラフィーに行き当たった。ルイス・ハーディンという作曲家の筆名(というか芸名というか源氏名というかリングネームというか)が「ムーンドッグ」であるらしい。ふーん。知らなかった。どんな音楽なんだろうか。たぶんザ・バンドとは関係ないと思われるムーンドッグだが、少なくともヒゲもじゃの容貌はザ・バンドのメンバーたちと似た感じ。ステージでこっそり混ざってても違和感はなさそうである。そして、会場の警備員に見つかった彼がステージから逃げ出すときに追っ手からかけられる言葉は決まっている。ムーンドッグ、待ちねぇ。
|

Rock Of Ages |
2004.11.21.Sun. 20: 30 p.m. BGM : THE BAND "ROCK OF AGES"
|

南十字星 
まとまるくん。 |
2004.11.20.Sat. 12: 20 p.m. BGM : THE BAND "NORTHERN LIGHTS - SOUTHERN CROSS"
どうか正夢じゃありませんようにと祈りながら朝食を済ませたのち、小学校の学習発表会へ。学習発表会といっても、別にテストの答案が張り出されたりするわけではなく、合唱やら合奏やら劇やらの舞台発表および図工の制作物の展示から成るイベントで、要は学芸会である。運動会は「体育学習発表会」で、学芸会は「学習発表会」だ。精神分裂病は「統合失調症」で、狂牛病は「BSE」、そして痴呆は「認知症」である。いずれそのうち、「ぼく」や「おれ」は性差別的だから日本語の一人称は「わたし」に統一しましょって話になるに違いない。「日本」だってどうなるかわからんよ。アジアの国々に忌まわしい過去を想起させちゃうし、科学的にも正しくない(ここは「日出ずる国」じゃない)から変えたほうがいいと思うのアタシ、うんうん賛成賛成、じゃあどんな名前がいいかなぁ、そうねぇ「平和国」なんてどうかしら、ああそれは素敵素敵、アタシたちったら今日から「平和語」を話す「平和人」なんだわウットリしちゃーう……なんてことにならない保証はどこにもないのだった。一生懸命に言語クレンジングに励んでる人たちって、ヒマそうで羨ましい。
それにしても学校というのは、行くたびに何かしら不愉快な思いをするという意味でも役所に似ている。とはいえ、きょうアタマに来たのは学校や教師ではなく、親どもだ。私は、セガレが「はじめの言葉」(10人ぐらいで一言ずつ順番に言う)を大きな声でしっかりと口にしたときの表情を見ることができなかった。舞台に向けてデジカメを構えたオヤジが、通路に立って視界を遮っていたからである。私が「座れよこの野郎!」と声を荒げたいのをグッと堪えて「座ってくんねーかなぁ!」と実に丁重な口調でお願いしてクソ馬鹿オヤジを追い払ったとき、すでにセガレは自分のパートをほとんど言い終えていた。クソ馬鹿オヤジを張り倒してそのデジカメを床に叩きつけてやろうかと思った。こっちはな、カメラもビデオも持たず、肉眼でセガレの晴れ姿をしっかり見届けようとしてんだ。デジタルデータなんかじゃなくて、脳味噌にその記憶を焼き付けようとしてんだ。おまえが遮ったそのシーンは二度と再現できないんだよ、このスットコドッコイ。 まあ、たかだかその程度のことでそんなに怒る私も十分に親バカなわけだが、とにかくあのカメラは何とかしなきゃダメだ。傍迷惑なバカ親は、そいつだけではなかった。司会の教師が「撮影は周囲の迷惑にならないようお願いします」と事前に注意しているにもかかわらず、どいつもこいつも座高より高く三脚立てたり中腰で携帯のカメラ構えたり(しかも「ピロピロピロ〜ン」とかいうわけのわからんシャッター音を鳴り響かせたり)して迷惑かけまくりだ。撮影で手一杯で、拍手もしやがらない。劇が終わると、てめえの撮った映像をチェックしてニタニタしてやがる。何しに来とんじゃこのボケカス。舞台芸術ってのはな、観客の拍手があって初めて完成すんだよ。観てるおれたちも作品の一部なんだよ。写真だけ撮りに来てんじゃねえよバーカ。アイドルとか鉄道とかの撮影会かこれは。おまえらは子供マニアなのか。だいたい、そういうワサワサした客席の風景を子供たちが舞台の上から見てるってことも考えたほうがいいと思うよ。そんな姿を見せといて、「授業中は先生の話を静かに聞きなさい」とか言えんのかって話だよ。親のお行儀が崩壊しとるんだから、そら学級だって崩壊するわさ。
観劇後、出番を終えた1年生が授業を受けている教室を廊下からチラリと覗いたら、みんな、客席の親どもよりよっぽど落ち着いた雰囲気で座っていた。セガレもやけに真面目な顔で先生の板書をノートに書き写していて、感心感心。数日前に新しい消しゴムを買ってもらったので、モチベーションが高いのかもしれない。その消しゴムというのが、いま小学生のあいだで大流行の「まとまるくん」だ。消しカスがまとまるので散らからないらしい。しかも、従来の消しゴムよりよく消えるんだとか。自分のために消しゴムを買わなくなって久しいが、知らないあいだに文房具も進化しているのだった。
|
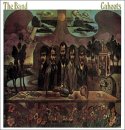
Cahoots |
2004.11.19.Fri. 10: 55 a.m. BGM : THE BAND "CAHOOTS"
火曜日以降、ザ・バンドのアルバムを発表順に聴いている。こういう聴き方をするのはツェッペリンのボックスセットを買ったとき以来だ。デビュー作の『Music From Big Pink』が68年、いま聴いている4作目の『Cahoots』が71年だから、ツェッペリンとほぼ同じ時期に同じようなペースでアルバムを発表していたわけですね。 そしてザ・バンドも、ハズレがない。この4作目は低く評価されることが多いようだが、私は最初の2作を聴いた時点ですっかりファンになってしまったせいか、これのどこが良くないのか全然わからない。過去3作と同様、何度も何度もくり返し聴いていられる。冒険や逸脱のない音楽だし、ツェッペリンのようなアルバムごとの「新鮮な驚き」もないけれど、どうにもこうにも居ても立ってもいられずに何度もくり返して聴きたくなるのがザ・バンドだ。キャッチーと言えばキャッチーだが、それは人の首根っこをつかまえて「おら聴けよ」というようなキャッチーではない。通りすがりの人が自らふと立ち止まって耳を傾けるのを待っているような音楽。聴かせる音楽ではなく、聴かれたがっている音楽。そんな感じ。
類似の事件は過去に多々あったし、当然どれも腹が立ったり悲しかったり許せなかったりしたのだが、きのう奈良で起きた誘拐殺人事件は、最初にヤフーでヘッドラインを見た瞬間から、これまでのニュースでは経験したことのないような種類のとてつもなくリアルな憤怒が体の底から湧き上がってきた。どういうことか自分でもわけがわからないが、とにかく「この野郎」と頭に血がのぼったのだ。理性とか感情とかいう以前に、肉体が怒っていた。この野郎。この野郎。この野郎。できることなら、これから奈良県警に就職して捜査に加わりたいぐらいだ。何だろう。なんでこんな気持ちになるんだろう。新事実を告げる続報を見るたびに、体がワナワナと震える。がんばれ奈良県警。絶対に逮捕しろ。
犯人が送ったと言われる携帯メールを再現して「イメージ映像」とやらをこしらえているワイドショーにも腹が立った。その、被害者の母親をどれだけ苦しめたかわからない邪悪な文面を、番組スタッフの誰かが携帯電話にタイプしている様子を想像すると、盛大に虫酸が走る。いくら仕事とはいえ、そんなことが平気でやれる鈍感さとはいったい何なのだ。自分が何をしているのかわかってるのか。いや、そのスタッフだって本当はイヤだったのかもしれない。陳腐な「絵づくり」しか思いつかない想像力貧困なディレクターか誰かに命じられて、渋々やったのかもしれない。だけど、仮にそうだとしても、そんな仕事は断れよ。クビになってもいいから断れ。泣きながら「できません」と言え。くだらないイメージ映像なんかなくたって、とっくにみんな想像してるんだよ。想像して、いたたまれない気持ちになってるんだよ。おれは泣きたいよ。この野郎。この野郎。
|

Stage Fright  似てないが武双山。 |
2004.11.18.Thu. 13: 10 p.m. BGM : THE BAND "STAGE FRIGHT"
そういえば尾曽時代の彼は、たしか「相撲サイボーグ」という、カッコイイんだか笑っていいんだか、そのへんの塩梅が微妙だとしか言いようのない異名でも呼ばれていたのではなかったか。「尾曽 相撲サイボーグ」で検索しても該当するページがないので私の記憶違いかもしれないが、とにかく相撲サイボーグだ。仮に誰かがそれを長年の研究の末に開発したのだとしたら、その目的は何だったのかが真摯に問われなければいけないと思う。それより先に開発すべきサイボーグがいくらでもあるはずだからである。
うっかりしていて途中から録画したため最後の20分ぐらいしか観られなかったが、日本×シンガポール(W杯アジア1次予選)は玉田くんのゴールで1-0の辛勝。なぜか玉田くんは「くん付け」で呼びたくなる。玉田くーん、玉田くーん、んもう玉田くんったらぁ。何度も呼ぶなよ気持ち悪いから。ロスタイムに決定的なシュートを浴びて危うく引き分けるところだったが、その前の大久保は完璧にオンサイドだったのに誤審で取り消されたから、まあ、よかろう。いったい何がいいと言うのか。
それより私はカズを見せてほしかった。いいじゃん、見せてくれたって。各方面の反対意見はごくごく真っ当なものだけどさ、そんな真っ当なことばっかりやってても面白くないよ。みんな、代表を強くすることばっかり考えすぎだ。代表が強くなりゃいいと思っていやがる。でもね、サッカーってW杯のためだけにあるものじゃないと思うんだよ私は。たまには「娯楽としての日本代表」のサッカーを楽しむ機会があってもいいのではないか。だって辛いじゃん、代表戦って。喜と怒と哀はあるけど楽がないじゃん。きのうの試合だって、観ててストレス溜まるばっかりじゃん。みんな仕事でくたびれてるんだから、勘弁してほしいわけよ、そういうのは。こんなことでファンをウンザリさせるより、たとえ負けてもカズとかゴンとかゾノとかで一発笑いでも取っておいたほうが、明日の活力になるってもんである。国民にとっても代表チームにとっても。ゾノはあんまり関係なかったですね。でも「ゾノ」と「オゾ」って、ちょっとだけ似ている。
|

The Band |
2004.11.17.Wed. 18: 30 p.m. BGM : THE BAND "THE BAND"
それでもまあ、当面は日夜ヒーヒー呻いたり頭を掻きむしったりしながら働いているのだし、実際に受注する本数はそんなに変わっていないのだが、発注は明らかに減った。つまり、日程的な都合で申し訳ないが丁重にお断り申し上げるケースが減っている。激減といってもいい。数年前までは2ヶ月に一度くらいのペースで「ごめんなさい無理です〜」と言っていたような気がするが、今年に入ってから単行本の依頼を断ったのは、たぶん一回だけだ。それも6月下旬に電話してきて「8月に出したいんだけど、これから取材して7月中に書けない?」という非常識な依頼だった。そんなもん、ふつう無理に決まってるのである。 ところがその編集者ときたら、自分が無茶な相談を持ちかけたことを棚に上げて、周囲に「いやあもう、江戸川センセーは半年ぐらい先まで詰まってるから私ごときの仕事は引き受けてもらえませんよ〜」などと吹聴したらしいから困るじゃないか。その後、共通の知り合い数人から「聞いたよ〜、なんか順番待ちの行列ができてるらしいじゃん。売れっ子だねぇ」と言われた。全然そんなことはないのである。そんなことはないのに、この噂話を真に受けて私への依頼をためらう人がいるかもしれないのである。いわゆる一つの風評被害というヤツである。なんでそんなウソをつきたいのかまったく理解できないが、事情通ヅラしてヘラヘラヘラヘラあること無いこと言いふらしてんじゃねえぞコラ。まじで死活問題なんだよこっちにとっては。おれたちフリーは口コミの評判が命綱なんだよ。自分が日頃どういう人間をコキ使って給料もらってるのか、わかってんのかよ。こんど同じことしたら実名で告発するからね、S社のGちゃんことY先輩。なんだよ先輩かよ。そうだよ先輩だよ。先輩にもいろいろあんだよ。
実際問題、たしかに今はやたら立て込んでいるものの、このトンネルの先には闇しか待っていなかったのであり、「順番待ちの行列」どころか年明け早々のスケジュールもロクに埋まっていなかったのであるが、きのう、1月の仕事を発注されてホッとしたのだった。久々に、これまで縁のなかった版元から依頼を受けたというのもうれしい。これがないと、この仕事はジリ貧だ。私を推薦してくれたフリー編集者Kさんには、ひたすら感謝あるのみである。依頼のメールによれば、「ご活躍のほどをKさんから伺い、ぜひ信頼のできる方にお願いできないかと切望しております」とのことであった。どうよこれ。切望だよ切望。文脈から考えて、これはまさか「絶望」のタイプミスではあるまい。そこで絶望してどうするんだよ。望みが切れたわけでもありません。切に望むと書いて切望だ。迷惑な風評を垂れ流す編集者もいれば、こうして誇大広告を打って売り込んでくれる編集者もいるのだから、この世も捨てたもんじゃない。本当にありがたいことです。
|
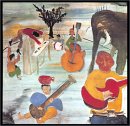
Music From Big Pink |
2004.11.16.Tue. 11: 40 a.m. BGM : THE BAND "MUSIC FROM BIG PINK"
そんな季節感と関係あるのかもしれないし無いのかもしれないが、数日前から突如としてザ・バンドの音楽が私の胸を打ち始めたのだった。ザ・バンドについては前に「ふつうにイイ」とか何とか寝惚けたことを書いた記憶があるが、反省している。ものすごくイイ。まったくもって「何を今さら」な話で、抜け毛にワビサビを感じる年齢になるまでそんなことも知らなかったのかと言われると返す言葉がないわけだが、まあ、知らなかったものは知らなかったんだから仕方がない。ザ・バンドの音楽は、わかりやすいがわかりにくいのだ。決して自分がその良さになかなか気づかなかったから言うわけだが、ほんとうの味わいは行間の深〜いところに隠されているのだ。人はあるとき、何かの拍子にその味を知り、そしてオトナになるのだ。ザ・バンドはそういうバンドなのだ。きっとそうに違いない。 それにしてもザ・バンドの検索しにくさといったらどうだ。世界いち検索困難な固有名詞かもしれない。何とかならないのだろうか。ちなみにアマゾンの「ポピュラー音楽」で「THE BAND」を検索してみると、「売れている順番」でザ・バンドのアルバムは6番目である。1位は「YOSUI TRIBUTE」というオムニバス盤で、なんで「THE BAND」でこれがヒットするのか全然わからない。「アーティスト名」でも1位は「YOSUI TRIBUTE」。ザ・バンドは「Bank Band」「band apart」「Band Aid」に次いで5番目だ。結成当初は「ホークス」という名前だったというのに、なんでまた「ザ・バンド」にしたかなぁ。まあ、本拠地にしていたスタジオ(BIG PINK)のご近所で「例のあのバンドさんたち」みたいな呼ばれ方をしていたのが由来だという説は知っているし、それも含めて彼らのワビサビの一部だからいいんですけど。そりゃあ、ホークスはないよ。ホークスじゃ台無しだ。魅力半減。無論、だからって福岡の例のあの球団も「ソフトバンク・ザ・チーム」にしろと言っているわけではない。 しかしアレだ。こうして今さらのように70年代前後のロックと出会うのは私自身にとってたいへん実り多いことであるのだが、世間的に見ると、単に物を知らないオジサンがフツーのオジサンになっているだけだったりするような気がしてきた。40歳の男が「ツェッペリンは凄い!」だの「ザ・バンドはイイ!」だのと力説してるのって、ものすごく当たり前な風景だもんな。そら髪の毛も抜けるっちゅう話だ。
そんな折、一つ年下の都職員が高貴な女性と共に新たな人生を歩み始めるというのは、実に心あたたまるイイ話であるなぁ。不安を抱えた人間集団は「幸福なカップル」の登場を願う傾向があるというのは、心理学の世界でも言われていることだ。ところで愚妻が教えてくれたところによると、黒田さんは私と誕生日が同じであるらしい。ということはフィオーレや若松監督や板垣退助とも同じなわけだが、きっとイイ人であるに違いない。さらに私はその黒田さんのご学友と顔が似ていることもあって、奇妙な因縁を感じるのだった。感じなくてよろしい。おまえは関係ない。
ゆうべ、先週の水曜日に開催されたセリエA第11節のハイライトを観た。ラツィオはウノゼロでリヴォルノに負けたわけだが、ローマがウディネーゼに0-3でボコボコにされていたので気分は悪くなかった。もう、そういうところに活路を見出すしかない。活路なのかそれは。しかしラツィオも良い材料を探せば見つかるもので、もしかしてGKセレーニが格段に成長していないか。この頃そういうシーンが多いのだが、リヴォルノ戦でも好セーブを連発していて目を疑った。あれでキックがもう少しうまけりゃ、世間並みのGKになれるんだけどなぁ。ところでスカパー!のセリエAハイライトを観るといつも思うのだが、アナウンサーがシュートのことをイタリア語で「ティロ〜!」と言うのが恥ずかしくて聞いていられない。それじゃ気合い入りませんよ日本人視聴者は。しかも全部イタリア語で言うならともかく、ミドルシュートは「ミドルシュート!」だ。言ってておかしいと思わないのだろうか。私はおかしいと思う。ドリブルは「ドリブリング」で、二重におかしい。誰か「おかしい」って言ってやれ。
|
|
| #12 | TOP | BACKNUMBER | FUKAGAWA | B.I.P. | GUEST BOOK | #14 | |
 |