
 |
| #17 | TOP | BACKNUMBER | FUKAGAWA | B.I.P. | GUEST BOOK | #19 |
|
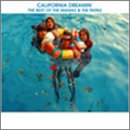
California Dreamin' |
2005.01.24.Mon. 9: 00 a.m. BGM : "CALIFORNIA DREAMIN'" THE BEST OF THE MAMAS & THE PAPAS
|

Wheels Of Fire |
2005.01.21.Fri. 9: 05 a.m. BGM : CREAM "WHEELS OF FIRE"
しかし拾った一万円札を落ちていた場所に戻すわけにもいかないので、井の頭線の駅員に託すことにした。「ここはケーサツじゃねえ」と追い返されるんじゃないかと危惧していたのだが、私が「こちらにお届けしてもよろしいでしょうか」と訊ねると快く受け取り、「権利は主張なさいますか?」と問うてきた。なるほど、ちゃんと応対マニュアルがあるようだ。昼間、憲法本の口述作業で人権の大切さについてさんざん勉強していたので権利はちゃんと主張したほうがいいようにも思われたが、「おまえは(たった一万円のことで強硬に)権利を主張する(ような人間な)のか」と訊かれて「主張する」とはなかなか答えにくいし、とにかく私は早く帰りたい。なので、「主張しません。落とし主が現れなかったら、どっかに寄付か何かしてください」と言って電車に乗った。また一つ徳を積んでしまった。一夜明けた今朝、愚妻に生活費を要求され、財布を開けたら六千円しか入っていなかったので、とても後悔した。落とし物を見つけた時点で、どう行動しようが後悔以外の結末があり得ない話。今日からは、上を向いて歩くことにしよう。
|

American Beauty |
2005.01.20.Thu. 8: 45 a.m. BGM : THE GRATEFUL DEAD "AMERICAN BEAUTY"
「セックス、ドラッグ、ロックンロールがロックの売り物だったなんて恥ずかしい。音楽だけで十分やっていけるよ」自分がザ・バンドの音楽に惹かれた理由が、なんとなくわかったような気がした。さて、今夜は『月刊 PLAY BOY』ロック関連特集のお仕事。ミュージシャンのインタビューではなく、ライナーノーツ界の大御所お二人(ちなみに渋谷さんと湯川さんではありません)の対談記事を担当することになった。サッカーでいえば、セルジオ×後藤の対談みたいなものだろうか。ちょっと違うような気もするが、なんだか嬉しい。倉敷さんや八塚さんにお目にかかったときの気持ちを思い出す。それにしても、4時に憲法本の口述を終えてから対談の始まる9時まで、どう過ごせばいいのだろうか。都心にオフィスがないと、こういうとき厄介だ。 |
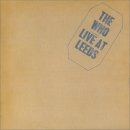
Live At Leeds
これを私が書いた? |
2005.01.19.Wed. 11: 20 a.m. BGM : THE WHO "LIVE AT LEEDS"
口述のほうは、レジュメどおりに理路整然と立て板に水で喋ってくれる著者なので、執筆もスムースに進みそうだとひと安心。しかし、テープ起こしを愚妻にやってもらう(つまり私の発言を愚妻に聞かれる)ことになっているのに、うっかりそれを忘れていて、口述の合間にくだらない冗談を飛ばしてしまった。授業参観されているのと同じことなので、気をつけなければいけない。場合によっては、著者の思想信条に合わせて、ふだん家で言ってるのと逆のことを口走ることもあるし。いい加減な奴だと思われると困る。いい加減な奴なんだけどさ。その場その場でサヨクにもウヨクにもなる定見なき文筆業者。それがゴーストライター。だから優柔不断な私には向いているのだと思っている。
2年ほど前にゴーストした本が韓国語に翻訳され、講談社から見本が届いた。去年は同じ本が中国語にも翻訳されている。親本は初版7000部止まりという惨憺たる結果に終わったことを考えると、なんでそんなに翻訳したいのかよくわからない。年間数十冊もの著書を出している著者なので、どれもがベストセラーだと勘違いされているのだろうか。私にもお年玉レベルの印税が入るので、ありがたい勘違いではあるけれど。日本の文庫編集者にも、どんどん勘違いしてもらいたい。
それにしても(前にも同じことをここに書いたような気がするが)ハングルはわからん。アラビア文字もわからんが、すぐ隣にある国の文字がこれぐらいわからないというのは人を茫然とさせるものがある。しかもこれは私の書いた文章なのだ。自分の書いたものがサッパリわからないという、このもどかしさ。学校でカタカナを習ったばかりのセガレは興味津々の様子でページを繰りながら「あ、ユがあった! フがあった! スもあった!」などとはしゃいでいたが、それはユでもフでもスでもないのです。「じゃあ何なの?」って、おれに訊くなよ。「だって父さんが書いたんでしょ?」って、説明の難しいことも訊かないでほしい。たしかに私が書いた文章だが、しかしそれは二重の意味で私が書いた本ではないのである。二重に「翻訳」されているとも言えるわけだが、しかし、こんなモン3冊も送られても困るよなぁ。韓国人の友達のいる人は言ってください。2冊あげます。 |

Pet Sounds |
2005.01.18.Tue. 10: 10 a.m. BGM : THE BEACH BOYS "PET SOUNDS"
ゆうべはラツィオ×パレルモ(セリエ第19節)を録画放送で観戦。なんでこんなマイナーなカードを放送してくれたのか知らないが、放送してくれなくてもよかった。サンプから新加入のバッツァーニがヘッドで先制ゴールを決めたときには「ようこそラツィオへ!」と欣喜雀躍したものの、タラモンティ&シヴィーリアのCBコンビが若さ爆発、終わってみれば1-3の完敗である。しかしまあ、ザウリの逆転ゴールは相手を褒めなきゃしょうがないスーパープレイだったし、じゃあコウトが出てたら負けなかったかといったらそんなことはないような気がするし、年明けからダービー含みの3試合で勝ち点6は立派なもんだよ。うんうん、立派立派。だいたい、ほんの一ヶ月前には「今季はダービーで一つ勝ってくれりゃ御の字」と思ってたんだから、贅沢を言ってはいけない。もっとも降格だけはカンベンしてほしいが。
いま、スカパー!やケーブルテレビなどで見られるヒストリーチャンネルで「ヒストリー・オブ・ロックンロール」というシリーズ物が連続で放送されている。先週は60年代のお話で、キリスト冒涜発言を批判されて弁解しているジョン・レノンとか、初めてエレキを弾いて聴衆のブーイングを浴びているボブ・ディランとか、ステージで破壊のかぎりを尽くしているザ・フーとか、ギターを燃やしているジミヘンとか、ボタンダウンのシャツなんか着てて全然イケてない若きミック・ジャガーとか、たぶんかなり貴重なんだろうと思われる映像がいっぱいあって面白い。当時を振り返ってインタビューに答えているピート・タウンゼントの背後には、破壊されてバラバラになったギターの破片が、恐竜の化石のように並べて飾られていて笑った。誰がぜんぶ拾い集めたんだそれは。本人だったら、ものすごくカッコ悪い。
で、その中でけっこうな時間を割いて取り上げられていたのがビーチ・ボーイズである。ビートルズ来襲に刺激を受けて、というか嫉妬心を燃やして(?)作り上げたのが『ペット・サウンズ』というアルバムであるらしい。一昨年の秋にタボン君がツェッペリンのボックスセットと一緒に貸してくれたCD群のなかにもそれが入っており、「なぜビーチ・ボーイズ?」と思っておったのだが、なるほどこれは歴史的名盤なのであるか。これまでは何度聴いてもピンと来なかったのだが、歴史的背景を踏まえながら改めてコピーしておいたCD−Rを聴いてみると、やっぱりピンと来ないのだった。あらら。ザ・バンドをまとめて買って以降、アマゾンでも盛んにビーチ・ボーイズを「おすすめ」されるようになったのだが、どうしてなのかよくわからない。むろん、誰にだって「ピンと来ない音楽」はあって当然だけど、なんだか気になる。ビーチ・ボーイズにおける重要な何かが私の耳には「聴けていない」ような感じ。同じCD群に入っていた小島麻由美のことはあまりわかりたいと思わないが、ビーチ・ボーイズのことはわかりたいと思う。
|

The Melody At Night, With You |
2005.01.17.Mon. 16: 15 p.m. BGM : KEITH JARRETT "THE MELODY AT NIGHT, WITH YOU"
その後、廊下やエレベーターで「やあ、どうかね」「はっ、いや、もう、あの、えーっと、ゴニョゴニョゴニョ……」「まあ、頑張りなさい」というお決まりの挨拶を交わす以外、さほどお話をさせていただく機会はなかったけれど、一度だけ黒崎さんに褒めてもらったことがある。今はどうか知らないが、当時あの会社には半年の試用期間を終えた新入社員に「会社に入って得たもの失ったもの」というタイトルの作文を書かせる慣習があり、それを「とても良い作文だった。面白かったよ」と言ってくださったのだ。たぶん誰にでもおっしゃっていたのだと思うが、私がこの世界で何となくやっていけそうな自信を持てたのは、あのときが最初だった。
もっとも、その自信は専ら「書く」ほうに関するもので、編集業務にはからっきし自信が持てず、給料だけ貰って会社には何の貢献もしないまま、さっさと辞めてライターになってしまったのは申し訳ないことだ。でも私のほうは勝手に、この業界に引き入れてくださった大恩人だと思っている。やさしい微笑を投げかけておられる遺影を前にして18年前の初心が蘇り、今の自分はずいぶん生意気になっているのではないかと身の縮む思いだった。ほんとうに、お世話になりました。ご冥福をお祈り申し上げます。 |

1962〜1966 |
2005.01.16.Sun. 22: 35 p.m. BGM : THE BEATLES "1962〜1966"
4番目に登場したバッヂは、4曲中3曲が新ネタという意欲的なステージ。いや、ぜんぶ新ネタだっけ? 『ラ・フィエスタ』もバッヂで演るのは初めてだったような気がしなくもない。昔からあちこちで演ったり聴いたりしてるから、よくわかんないや。ともあれ、そのほかには同じチック・コリアの『セニョール・マウス』、アキコだか何だかという人バージョンの『ギフト』(『RECADO』ともいう)、ステップスの『Kyoto』というラインナップである。忌憚のないご意見は終演後にキーボードのSUNEO君や女性フルート奏者先輩に伝えたのでいちいちここには書かないが、以前よりも聴いていて安心感の持てる演奏だったように思いました。あえて「安定感」とは言わないけどね。えへへ。なかでも『Kyoto』は落ち着きのある知性的で美しい演奏。「愛のあるユニークで豊かな書体」みたいな物言いになってしまったが、3月のライブも期待してるのでがんばってくらはい。おれもがんばる。 5番目はユーミン、中島みゆき、八神純子などニューミュージック(!)中心の実演カラオケ隊、6番目は3ピースのハードロック・バンド(だったと思うがホールの外で飲み食いしていてちゃんと聴いていなかった)、そして大トリが6人組のビートルズ・トリビュート・バンドとして私たちの仲間うちでは有名なApple Jamであった。正確には、リーダーのクリフさんが欠場でApple Jam 5。クリフさんって、ふつうの日本人ですが。四十過ぎたオッサンたちが「マリック」(K先輩)だの「ジニー」だのと名乗っているのが、このバンドの特徴である。でも(でもってことはないが)、リーダー不在にもかかわらず演奏はとても良かった。2年ほど前に聴いたときより、確実に上達している。上達する中年はえらい。一番カッコよかったのは、ベースのタボン君がギンギンノリノリだった『ロックンロール・ミュージック』かな。K先輩が代打ちでリードギターを務めた『サムシング』と『レット・イット・ビー』には手に汗を握ったものの、ほぼノーミスでこなしてらして感動した。私も早く、あれぐらい弾けるようになりたいもんだなぁ。 最後は客席も交えた『ヘイ・ジュード』の斉唱でおひらき。大塚駅前の「甘太郎」で打ち上げをやったのち、同じ杉並区在住のK先輩と一緒に帰ろうとしたら、新宿で山手線を降りてからまた隣のホームで山手線に乗って高田馬場まで戻ってしまってアホである。二人いてどっちも気づかないのって珍しい。慌てて逆方向の山手線で新宿に戻り、やっと正しく中央線に乗って吉祥寺までたどりついたら、井の頭線の富士見ヶ丘行き終電が発車する寸前だった。乗れてよかった。ツイてるのかツイてないのか、よくわからない。
単行本の口述作業のために、今月下旬に北海道の小樽へ二泊三日で出張することになっているので、きょうの午後、吉祥寺で厚手のズボンを一本買う。しかし敵は零下10度の世界。こんなもので太刀打ちできるとは思えない。東京もじゅうぶん寒いもんな。ちょっぴり憂鬱。しかし今回は初版2万部は確実、うまくいきゃ3万部という、いまどき希有な仕事である。初版3万部のためなら、おら南極にだって行ぐだ。
トッテナム×チェルシー(プレミア第20週)をビデオ観戦。ランパードのPKを含む2ゴールで0-2。とくに何がどうということもなく、ふつうに勝ち点3。ごく日常的な完封勝利。いまのチェルシーは、世界でもっとも安心感と安定感のある人間集団かもしれない。
|

サンクチュアリ(禁漁区) |
2005.01.14.Fri. 12: 50 p.m. BGM : THE J.GEILS BAND "SANCTUARY"
ゆうべはシギーに誘われて、ブルーノート東京でマイク・スターン・グループのステージを堪能。シギーが番号の若い整理券をゲットしておいてくれたおかげで、最前列のテーブルでかぶりつきだ。ギターのボリュームを下げたときには、ピックで弦を弾く生音がカリカリと聞こえてくるほどの至近距離。目が合えばニッコリと微笑んでもらえるポジションである。もっとも私はほとんど左手ばかり見ていたし、マイク・スターンも男の客とはあまり目を合わせようとしないので、私は微笑んでもらえなかったが。 ビギナーの私はまだ、超一流ギタリストの運指を観察して何かを具体的に理解し参考にできるほどギターの奏法に習熟していないが、正しい弾き方のイメージを感覚的に把握する上で、これほど良いトレーニングの機会はない。なので、眼光がネックの裏側に達するほどの念力を込めながら凝視していたら、ぐったりと疲れた。こんなに「目」を積極的に使ってライブを鑑賞したのは初めてだ。しかしその甲斐あって、マイク・スターンの左手はひと晩たった今も私の頭のなかで動いている。彼の左手は、私の左手と解剖学的に似た特徴があるようにも見えたので、なおさらこのイメージは大事だ。 それにしても、じつに愉快&痛快なすばらしい演奏だった。圧巻だったのは、カメルーン出身のベーシスト、リチャード・ボナ。「陽気で健康なジャコ」とでも呼びたくなる感じの、ユーモラスな天才である。表情の豊かさはハッセルバインク並み、深刻な話が苦手そうな点ではロナウジーニョ的とでも言えば、サッカーファンにはわかってもらえるだろうか。わかんねえよな。要するに、プレイしている姿を見てるだけで楽しくなる人だということだ。エムボマもそうだったが、カメルーンってやっぱり関西ノリなのかも。 とはいえ、もちろんボナはただ賑やかなだけの人ではない。まるで、身体の細胞がすべて音楽でできているかのような演奏。全身ミュージシャン。銀の匙ではなく、楽器を持って生まれてきたのかもしれない。正確で超絶的なテクニックと、カヌの魔法使い的ステップを連想させる不思議だが心地よいリズム感と、意表を突くアイデアに溢れたフレーズの数々に、口あんぐりである。ベースでソロを弾きながら、同じフレーズをユニゾンで(時にハモりながら)スキャットで歌うという例のアレも、高橋ゲタ夫の100倍ぐらいうまい。壮絶に速くて複雑なフレーズでも、ベースと声が完璧にシンクロしている。しかも声がとても美しい。いやぁ、スゲかったスゲかった。 どの曲もよかったが、とりわけスターンとボナのかけあい漫才的デュエットは最高。笑いと驚きと興奮の詰め合わせセットである。途中、スターンがおどけて『スモーク・オン・ザ・ウォーター』の罰金リフを弾き始めたのだが、それを受けたボナの「変奏」がすばらしかった。最初は初心者が「探り弾き」をしているような案配で、同じリフをわざと半音ずらしたりしながら調子っぱずれに弾いて笑いを取っていたのだが、やがてその奇妙なコード進行が深みを持った「聴ける音楽」に変容してゆき、それまで笑っていた聴衆を唸らせるのだった。それがあまりに印象的だったせいで、帰り道、頭の中で『スモーク〜』のリフばっかり鳴ってしまったのには参ったが。なんでマイク・スターンのライブを聴いた後にディープ・パープル歌いながら帰ってるんだ私は。ほんとうに困った曲である。まあ、それはそれでディープ・パープルの偉大さでもあるのでしょうが。ともあれ、やっぱミュージシャンよりカッコイイ職業は無いぜ!ということを再認識した90分間であった。それを踏まえた上で、あしたはFor Badgeholders OnlyとApple Jam(どちらも友人たちのやってるバンド)のライブだ。楽しみ楽しみ。
……と、人にプレッシャーをかけている場合ではないのだった。GUEST BOOKをご覧の方はすでにご承知だろうが、師匠が私に「おさらい会」(発表会)をやらせようと、サポート・メンバーの募集をしているのだ。うげげげ。ななな、なんだそれは。そんな話、聞いてないっつーの。書き込み見るまで知らなかったっつーの。冷や汗かいたわ。だいたい、曲をちゃんと練習するどころか、まだギターを弾くためのフィジカル・トレーニング(おもに左手の薬指と小指)をしている段階だというのに、そんなことが可能なのだろうか。うー。いきなり緊張してきた。予定は約1年後とはいえ、この1年の進歩が想像をはるかに下回るスローペースだったことを考えると憂鬱だ。しかしまあ、「目標が必要」なのはそのとおりで、「〆切」がないと物事がはかどらないのは原稿も楽器も同じである。ここは一つ、師匠の術中にハマることにしよう。そんなわけなので、誰か助けてくれ。
|

The J.Geils Band |
2005.01.13.Thu. 11: 20 a.m. BGM : "THE J.GEILS BAND"
そんなことより、J.ガイルズ・バンドだ。ジャケットはザ・バンドに似ているが、音楽は何だかストーンズっぽいよなぁと思っていたら、とっくの昔に「アメリカのローリングストーンズ」と呼ばれていたとかで、ほほう、私の耳もずいぶんロックを解するようになってきたものだと自画自賛することしきりである。渋くてかっこいいよなぁ、J.ガイルズ・バンド。シブかっこ隊だな。以前、Kay'n師匠のところで、うまいハーモニカ吹き(
諸事情あって、今月中にやっつける予定だったゴースト仕事が一本なくなった。簡単に言うと、「1月末〆切」ということで発注しておきながら、編集者がいまだに原稿に着手できる状態にしてくれないので、私のほうがケツをまくったのである。当初は「12月アタマ」にやるはずだった打ち合わせが「年内には」になり、「年内」が「年明け」になり、「年明け」が「連休明け」になり、「連休明け」が「13日か14日」になったのが一昨日のことだ。だんだん間隔が短くなってはいるものの、この調子では「明後日」が「明日」になり、「半日後」になり、「六時間後」になり……と半減していくばかりで、永遠に打ち合わせができないのではないか。アキレスはカメに追いつけないのである。「11分15秒後に打ち合わせを」ってメールで言われても、どうしたらいいかわかりませんが。 おまけに、もう〆切の3週間前になっているというのに、この期に及んで「口述を読み直したらネタが足りないようなので追加取材が必要かも」なんて言われちゃったらねぇ。口述のテープ起こしが上がってから40日ぐらい経ってるのに、いままで何をしてたんですかっちゅう話ですわ。こんな編集者と仕事をしていたら、無事に原稿を上げたとしても、半年ぐらいたってからダメ出しされかねない。本になるのは2年後、カネになるのは2年半後ぐらいだろう。 その編集者に私を推薦してくれた恩人の顔に泥を塗ってしまう結果になったのは、本当に申し訳ないと思う。でも、このまま続けていたら日程が押せ押せになって次に控えている編集者諸氏に多大な迷惑をかけることになるし、私は口述作業に立ち会っていない(それが終わってから発注された)ので、私の代わりに別のライターが起用されても条件は同じだ。どっちにしろ、会ったことのない著者の口述原稿を読むところから始めるわけだから、私が次の人に迷惑をかけることにはならないだろう。むしろ、次に発注されるライターのことが私は羨ましい。待ち時間は私より少ないはずだし、それより何より、私が途中で手を引いたからには、この本きっとバカ売れするに違いないからだ。そして本は宝くじではないので、当たっても「前後賞」はないのだった。嗚呼。 それにしても、このところ、やけに「待ち」の仕事が多い。11月に書いた本は、不足分を補うために追加取材をすることになっているのだが、共著者の一人がなかなか原稿を読んでくれないので先に進めない。12月に書いた本は、最終章のデータをまだ著者が用意してくれないので、脱稿したくてもできない。ついでに暮れに書いた愚痴をくり返せば、去年の2月に書いた本はいまだにいつ刊行されるのかわからない。本が出なければ金にもならないわけで、こうして私は働いても働いても貧乏になってゆく。まるで貧乏スパイラルだ。いや、べつに循環はしてないか。ちなみに運転資金も循環してません。うー。たぶん、いつも人を待たせてばかりいるのでバチが当たっているんだろう。因果応報、目には目を、である。 もちろん、私のような人間に、他人様に向かって「早くしろ」と言う資格がないのは承知しているから、たまに待たされてもなるべく文句を言わないようにはしている。だけど今回は堪忍袋の緒が切れてしまったんだよなぁ。緒が切れたというより、袋自体が破裂しちゃった感じかしら。ひらすら待たされることで奪われた時間は、およそ半月分。年収の24分の1を盗まれたのと同じことだ。ちくしょう、150万円ぐらい返しやがれ。といった途方もないスケールの大ウソはともかくとして、社員編集者は待ち時間も給料のうちだが(だから待たせてもいいとは言ってないし思ってもいませんが)、フリーの場合、ただ待っているだけでは一銭にもならないのである。……という認識が相手にあるように思えなかったから堪忍袋が爆発しちゃったんですね、きっと。
そんなこんなで、金もないのに仕事断っちゃって参ったよなぁとヘコんでいたら、きのうハポエル君の同僚でありニューカッスル・ファンでもある『月刊PLAY BOY』編集部S氏から電話をもらい、仕事にありつけそうな雲行きなのでヨカッタ。仕事したら掲載誌も貰えるしね。いや〜ん。しかも70年代ロック関係の特集企画でミュージシャンにインタビューするというのだから嬉しいじゃないか。これもウェブ営業の効果であろう。サッカーの話をしていればサッカーの仕事、ロックの話をしていればロックの仕事が舞い込むのである。これからはベストセラー本の話ばかりするといいかもしれない。
ところでサッカーとロックといえば、このサイトに「フットボール ロック」というキーワードで検索して来られた方があり、そのグーグルの検索画面に行ってみたら、私のページが1件目に表示されていて感動した。なんか、すごくメジャーなサイトになったように錯覚できて気分がよろしい。「フットボール界を代表するサイト」でも「ロック界を代表するサイト」でもないが、「日本のフットボール&ロック界を代表するサイト」ではあるわけだ。そういう「界」はたぶん存在しないし、「サッカー ロック」だと話にならないんだけどね。その場合、1件目に表示されるのはHONDA LOCK SOCCER CLUBなのだった。LOCKかよ。JFL昇格おめでとうございます。それにしても、「フットボール ロック」というキーワードで、いったい何をお調べになろうとしていたのかが謎だ。なんにしろ、このページが役に立ったとは思えないのが辛いが。 |

G. Lasts… (1) SUM 41 (2) Felix Da Housecat (3) ZEBRAHEAD (4) STEREOLAB (5) LOW IQ 01 (6) 10-FEET (7) BANK$ feat. HALCALI (8) mold bond akiko (9) 須永辰緒 (10) Hoobastank (11) The Chemical Brothers (12) Keith Emerson |
2005.01.12.Wed. 21: 30 p.m. BGM : "G. Lasts…Tribute to GODZILLA 50th"
……そう言って、セガレが映画『GODZILLA FINAL WARS』のパンフレットに載っていたジャケ写を見せてくれたのが、このゴジラ生誕50周年記念トリビュート・アルバムなのだった。笑ったよなぁ。グッドジョブとしか言いようがない。デザイン&アート・ディレクションを手がけた7 STARS DESIGNが何者かは知らないが、間違いなく代表作の一つになる仕事であろう。べつに私はゴジラマニアでも何でもない(たぶん一生、何マニアにもなれない)が、こんなモノの存在を知ってしまったら、買わないわけにはいかないよ。そりゃあそうだよ。うんうん、ほっとけない、ほっとけない。 というわけで、これはジャケットだけで2800円の価値がある!と無理やり自分に言い聞かせてカネもないのにゲットしたのだが、これは中身もじつにスバラシイのである。「洋楽、邦楽のメジャー・アーティストがレーベルを超えて大集結!!」と言われても、いまだロック体験が70年代で止まっている私が知っているのは当然ながらトリを務めている「E」大先生だけで、それ以外は洋邦の区別もつかないわ読み方も怪しいわ個人名なのかユニット名なのかも判然としないわという惨状なわけだが、にも関わらず12曲中(トラック2、8、9以外の)9曲は「おもろい!」「かっこええやん!」などと思えたのだから大変な高打率だ。これが私にとって21世紀ロックへの玄関口になりそうな雲行きで、そういうことでいいのかどうかわからんが、まあ音楽との出会いなんてそういうものだろう。とくに気に入ったのは、(3) ZEBRAHEAD、(5) LOW IQ 01、(10) Hoobastankあたりでしょうか。
それにしても、各曲の随所に挿入された「ぐぅわお〜〜〜〜〜〜〜んぁあ」という例の咆吼を聴くと、やはりゴジラは本邦最大最強のロックスターだと思わされる。最後に「ぁあ」と半音ぐらい上がるところなんて、ある意味ブルースかも。単なるSEではなく、ちゃんと「音楽のサウンド」に聞こえるから凄い。このアルバムのなかでもっとも浮いている面白味のないハードバップ・ナンバー(トラック9)さえ、最後にゴジラさんに一発シメてもらうとピタリと着地が決まったりするのだった。ともあれ我が家は、3人そろって「かっこいい!」と大満足。家族で楽しめるロックアルバムです。ウチだけかもしれんけど。
|
|
| #17 | TOP | BACKNUMBER | FUKAGAWA | B.I.P. | GUEST BOOK | #19 | |
 |