
 |
| #22 | TOP | BACKNUMBER | FUKAGAWA | B.I.P. | GUEST BOOK | #24 |
|
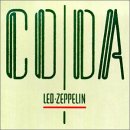
1.We're Gonna Groove |
2005.03.11.Fri. 12: 35 p.m. BGM : LED ZEPPELIN THE COMPLETE STUDIO RECORDINGS
|
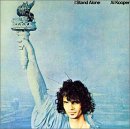
1.序曲
|
2005.03.10.Thu. 9: 50 a.m. BGM : AL KOOPER " I STAND ALONE "
数ヶ月前から、愚妻とセガレがおりがみにハマっているのだった。たまの休みに私が茶の間で居眠りしていると、押し黙って作業に集中している二人が、「カサ…カサカサ、カサ」と紙を折る音だけを室内に響かせていたりして不気味だ。とくに愚妻の没入ぶりと進歩は凄まじく、今朝は『Origami Zoo: An Amazing Collection of Folded Paper Animals』という本を見て折ったカマキリを見せてくれた。これが一枚の紙を折るだけ(つまり切ったり貼ったりしない)で出来上がるというのは驚く。聞くところによると、折った紙を広げて「折り図」(たとえばこんなようなモノ)を研究するようになってから、おりがみの世界は急速に進歩しているらしい。しかもそれはごく最近のことで、江戸時代(かどうかよく知らないが、とにかく大昔)から日本ではおりがみ文化が盛んだったにもかかわらず、折ったものを広げて研究しようとしなかったというのが不思議だ。結果オーライの精神だったということか? また、おりがみ雑誌には、「この折り図でコレが出来上がるはずだが、折る手順はわからないので考えてください」と展開図だけ載っていたりすることもあるというから、意味がよくわからない。実践より理論が先行しているということだろうか。帰納から演繹への転換? 私は設計図を見てモノを作るのが苦手だし、手先も不器用なので、おりがみ自体はやろうと思わないけれど、おりがみ研究者(数学者や建築家が趣味でやっているケースが多いとか)にはかなり興味がある。『ORIGAMIと日本人』みたいな新書でも作ったら、あんがいイケるのではないか。
仕事は佳境。ゆうべ第四章を送稿し、ようやく最終章を残すのみとなった。この本の担当者と次の仕事の担当者をそろって待たせているという状況は、いつ味わっても辛い。つい、ひょっとしたら「べつのライターに書かせればよかった」と悔やまれているのではないか……などと思ってしまうのが、自前の本を書いている物書きと違うところだ。著者が自分で書いている原稿は待つ以外にないが、ライターを使う場合は「もっと早く上げる方法」が理論上はあるんである。などとブツブツ言ってないで、待たせているのが辛いなら、はよ原稿を書きなさいっちゅう話でした。
|

ディスク: 1 |
2005.03.09.Wed. 12: 40 p.m. BGM : TODD RUNDGREN " Something/Anything ? "
だからというわけではないのだが、朝からチェルシー×バルセロナ(CL1/8ファイナル第2戦)をビデオ観戦。仕事前に目を無駄遣いしている場合ではないものの、なぜか今回は夜まで情報遮断できない(させてもらえない)のではないかというイヤな予感があったので、すぐに見ることにしたのだった。 お互い、ガッツとか執念とかハートの強さとか根性とかそういうことではなく、「技術で決着つけようぜ」と言い合っているように見える、とても綺麗なゲームだったと思う。もちろん、彼らにガッツや執念やハートの強さや根性がないと言いたいわけでは全然ない。べつに、心配してわざわざコッリーナさんを呼んでくるような試合ではなかったのではないか、というようなことだ。 あまり長々と書いている余裕がないが、ともかく、すげえおもしろかった。でも、心境は複雑。チェルシーが凄いことをやってのけたとわかってはいるし、相手がバルサじゃなければ今ごろ仕事なんか放り出してビール飲んで歌ったり踊ったりしているかもしれないが、正直、ちょっとガッカリしている。最後にもう一押し、バルサがトンデモないことをしでかすのを見たかった。決定機じゃないのにゴールを決定してしまったロナウジーニョの2点目だけでも十分にトンデモないことなわけだが、なんかこう、いかにもモウリーニョの筋書きどおりに事が運んでしまったような気がしてねぇ。まるで最初から、「トータル160分過ぎてからテリーの頭が炸裂するかどうか」が勝敗のポイントだったみたいに見えるじゃないか。要するに、私はもっともっと阿鼻叫喚したかったというだけの話かもしれないが。というわけで、試合は4-2、agg.5-4でチェルシーが準々決勝に勝ち上がり。めでたさも中ぐらいなりおらが春。
……おっと、また「素粒子」ノリになってしまった。
激しく労働にいそしみながらも、いまの仕事と次の仕事が終わったら4月以降はヒマになっちゃうなぁマズいなぁと思っていたところ、きのう祥伝社S氏から久々に電話があり、新規のゴースト仕事を発注されてありがたい。著者は28歳で、今回が初めての著著とのこと。この商売をしていると、いろいろな経歴の人に会えておもしろい。たとえば次は東大法学部在学中に司法試験に合格した人の本を書くのだが、きのう頼まれた企画の著者は、なんと東大法学部在学中に司法試験に合格した人であるらしい。あらまあ。またですか。昔から私の原稿は東大出の著者にウケがいい傾向があるので、いいんですけどね。 それで思い出したのが、私の出身大学の話だ。早稲田「一文」「二文」に幕 新学部に07年度再編。<文学そのものを主に扱う文学部(仮称)と、作家や演劇人ら文化の担い手養成を目指す文化構想学部(仮称)の二つに再編>されるんだってさ。どうなのよコレ。再編後の「文学部」は文化の担い手養成を目指さないわけか? 文学は文化じゃないってこと? ともかく、ひどい名称だよなぁ。露文とかのOB諸君は「文学部」のままだからいいだろうけどさ、文芸科の私とか演劇科のヤマちゃんとかは、出身学部が「文化構想学部」になっちゃうんだぜ。まだ仮称だけど、なんだ「文化構想学」って。そんな学問あんのか。しかも略称はどう考えたって「ブンコー」だ。文学部の人たちに「あっちはブンコーで、こっちが本校だから」とバカにされるのが目に見えている。いや、でも、文芸は文学部のほうかなぁ。文学部のほうに入れてほしいなぁ。どっちにしても、卒業生のひとりとして、この軽薄かつ安っぽい名称には断固反対しておきます。そんなネーミングで良しとするような人たちが構想する文化なんて、ろくなもんじゃないと思う。
トッド・ラングレンは、キャラがアル・クーパーと似ている。
|
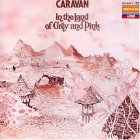
1.Golf Girl |
2005.03.08.Tue. 10: 10 a.m. BGM : CARAVAN "IN THE LAND OF GREY AND PINK"
その一。変異型ヤコブ病 80−96年英仏 滞在1日で献血禁止 数十万人が対象。……行っとる。わし、行っとりますがな。82年にパリ、96年にロンドン。いずれも四泊か五泊だったと記憶している。牛肉食ったかな。食ってないわけないよな。ヤだな。専門委は「感染経路の厳密な特定は困難」って言ってるのに、なんで「日本の牛じゃない」と言いたいがために数十万人だけが不安にならにゃいかんの? 英仏渡航者差別とちがう? 向こうでハンバーガーやらグレービーソースやらを食った証拠ばっかり躍起になって探してないか? その二。人さし指、短い男性は暴力的? カナダの研究チーム発表。「指の長さで推測できるのは性格のごく一部にすぎない。指の長さで人を選別しないように」って、自分で勝手に恣意的としか思えないような聞き取り調査か何かしておいて、いったい何を言ってるんだろうか、このハード博士という人は。マッチポンプじゃないか。じゃあ、どうしろと言うのだ。ちなみに日本では、後天的に小指が短い人に暴力的なお仕事の人が多い印象がありますが。
その三。<痛風>「ビールを飲んでも治る!」鹿児島大教授が自ら実験。これだよ。納(おさめ)教授、男だよ。これが科学者の実証的な態度というものだ。見込み捜査みたいに状況証拠だけ必死に集めて差別や不安を助長している学者や役人には、納教授の爪の垢でも煎じて飲んでもらいたい。こちらは飲んで治るかどうか知らないけど。ともあれ「売れたら第二弾」はこの業界の鉄則なので、教授にはぜひ次の病気にかかって自ら実験し、できれば私にゴーストさせてほしい。『痛風はビールを飲みながらでも治る!』(小学館文庫)に続く「それでも治るシリーズ」第二弾のタイトルは、もちろん『虫歯はチョコを食べながらでも治る!』ではなく、『肺気腫はタバコを吸いながらでも治る!』だ。
|

1.I Believe In Love |
2005.03.07.Mon. 21: 30 p.m. BGM : PAULA COLE BAND "Amen."
|
|
| #22 | TOP | BACKNUMBER | FUKAGAWA | B.I.P. | GUEST BOOK | #24 | |
 |