
 |
| #23 | TOP | BACKNUMBER | FUKAGAWA | B.I.P. | GUEST BOOK | #25 |
|

1.Twice as Hard |
2005.03.22.Tue. 16: 15 p.m. BGM : THE BLACK CROWES "Shake Your Money Maker"
仕方がないので、中央三井信託銀行の支店がある荻窪駅前まで歩くことにした。西荻から荻窪は電車だとものすごく近いが、歩くとものすごく遠い。現金を88円しか持っていないときは、なおさら遠く感じる。汗かきかき歩いて、ようやく中央三井信託銀行の支店があるはずの場所にたどりついた。そこに、中央三井信託銀行はなかった。むかし中央三井信託銀行だったビルが明治生命のビルになっていた。そうなのだ。中央と三井が一緒になったあと、南口支店は北口の支店に吸収されたのだ。北口に走った。あちこち探し回って、ようやくビルの中にひっそりと佇む中央三井信託銀行荻窪支店を発見した。あれはたぶん地上でもっとも目立たないところにある銀行だ。できることなら誰にも発見されたくないと思っているようにしか見えない。ホッとしつつ、ATMコーナーに飛び込もうとした。しかし残念ながら、自動ドアは開こうとしない。営業時間は17時までだった。時計はすでに18時20分をさしていた。そして僕は途方に暮れた。途方もない大きさの途方だった。人生最大の途方だったかもしれない。「トホーとトホホって似てるよな」と、およそどうでもいいことが脳裏を過ぎったりもした。ポケットから88円を取り出して強く握りしめ、おそるおそるてのひらを開いてみる。奇跡は起こらなかった。50円玉は、いくら強く握っても500円玉には変身しない。穴さえ埋まらない。 目に涙を溜めて「まいったよなー」と呟きながら、私は考えた。いつまでも荻窪駅前にいても何もいいことはないが、もう仕事場を出てから一時間近く歩いているので、これ以上は歩きたくないし歩けない。そして、88円しか現金を持っていない人間が徒歩以外の手段で移動する方法は、思いつくかぎり三つしかなかった。(1)ドラえもんにタケコプターを借りる、(2)ドラえもんにどこでもドアを借りる、(3)カード支払いOKのタクシーに乗る、の三つだ。荻窪駅前にドラえもんの姿は見当たらなかったので、私はタクシー乗り場に並んだ。想定される行き先は(1)家族が待っている久我山、(2)仕事が待っている松庵、(3)FOR BADGE HOLDERS ONLYが待っている大塚、の三つだ。仕事は山ほどあるので仕事場に戻るのが職業人としてもっとも正しい選択だが、FOR BADGE HOLDERS ONLYのサポーターとしては正しくない。それに、私は仕事は沢山あるけれど友達は少ないのだから、人生においてどちらを大切にすべきかは自明だ。ほんとうは友達よりお金のほうが少ないのだが、私は友達よりお金を大切にするような人間になりたくない。タクシー代が何だというのだ。だいたい、これで大塚行きを諦めたのでは、この一時間の苦闘が水の泡になってしまうではないか。 タクシーの順番が来た。運転手に「カードで払えますよね?」と確認してから、「大塚駅前までお願いします。大塚って、山手線の大塚ね」と告げた。車が発進するやいなや、スネオくんに電話をかけた。大塚までは行けても、ライブハウスの受付でカードが使えるとは考えにくいからだ。FOR BADGE HOLDERS ONLYのライブはタダではないのである。しかもライブが開催されることを教えられたのはその日のことなので、チケットも受け取っていない。なので、受付に私の分のチケットを置いておくよう頼みたかったのだが、スネオくんの携帯は留守電になっていた。次にヤマちゃんに電話をかけた。留守電だった。誰も出やがらない。もっとも、その時点で本番の20分前だったのだから当然かもしれない。しょうがないので、客としてライブ会場に行くはずのモルちゃんに電話をした。すぐに出てくれた。いい人だ。彼が手配しておいてくれたおかげで、会場にキャッシュレスで入ることができた。ビールも飲めた。ちなみに、荻窪から大塚までタクシーに乗ると4900円かかるということがわかった。amazonでCDが4枚ぐらい買える金額である。 すでに演奏は三曲目の終盤にさしかかっていた。FOR BADGE HOLDERS ONLYの出番は約40分、全6曲のステージだったので、私は半分の3曲しかまともに聴けなかった。1曲あたり1633円ぐらいの計算だ。しかし、それでもまったく不満を感じないすばらしい演奏だった。あの気品と熱情にあふれた『Kyoto』と『ラ・フィエスタ』を聴けただけで、それまでの苦労と苦悩と疲労が報われたように感じた。もしかしたら苦労と苦悩と疲労のモトを取ろうと思って聴いていたせいかもしれないが、これまで(というのは学生時代から数えているわけだが)私が聴いた彼らの演奏のなかで最高の部類に入る名演だったと思う。もっとも、1曲目の『セニョール・マウス』はモニターのトラブルのせいで最大3拍ものズレが生じるという惨状だったらしいから、それを聴いていたらどんな印象を持ったかわからないが。
終演後は打ち上げに参加し、「カードで払って割り勘」という奥の手を使うことによって、ようやく現金を手に入れた。現金のありがたみが身に沁みた。その後のことは、私の原稿を待っている人が読んでいるかもしれない日誌に書くことはできない。翌日の日曜日は、風邪もひいていないのに喉がとてもヒリヒリしていた。
|

1.Narcolepsy |
2005.03.19.Sat. 14: 10 p.m. BGM : BEN FOLDS FIVE "The Unauthorized Biography Of Reinhold Messner"
きのう、『ワールドサッカーダイジェスト』の付録DVD『スーパーゴール70』を観た。かなりカネがかかっているらしい。カネさえあれば作れる種類のおもしろさだとは思うし、つまりエライのはDVD制作者ではなくプレイヤーたちだと思うが、相当おもしろかった。きわめて主観的に言って、白眉は98年のパルマ戦でマンチーニがミハイロビッチのCKをヒールで流し込んだファッショナブルな一発。コウトに呼ばれてあのチームを追いかけ始めた私が、本格的にラツィオ・ファンになることを決定づけたゴールだった。ともあれ、82年以降の見ておくべきゴールがすべて封じ込められているのではないかと思えるような、とても見応えのあるDVDである。欲を言えば、(この手のハイライト物を見るといつも思うのだが)BGMに使われているロック・ナンバーが何なのか気になるので、曲名とアーティスト名を出してもらいたい。 さらにきのうは、サッカーズを離れた岩本編集長が手がけた新雑誌『ワールドサッカーキング』が編集部から届いた。ある意味、この雑誌のために私の連載が終わったということにもなるわけだが、まあそれは冗談として、このたびは創刊おめでとうございます。心よりご健闘をお祈り申し上げます。そして、送本ありがとうございました。きわめて主観的に言って、白眉はモウリーニョの連載コラム。ライターの聞き書きのようだが、人柄が滲み出ていて、かなり読ませる。のっけから「なんでこんなに忙しいんだ!」という調子の愚痴がほとばしっていておかしい。忙しい忙しいと言いながらコラムの連載なんか引き受けているあたりにも好感が持てる。忙しいときって、なんだか知らないけど言いたいことが沢山あるもんだよな。
で、そのチェルシーはCL準々決勝でバイエルンと対戦するらしい。おーし、がぜん気合いが入ってきたぜベイビー。ここから先は、まっしぐらに応援できる。いずれも優勝経験のあるバルサ、バイエルン、ユーベ、ミランを連破してのビッグイヤーほど値打ちのあるものがあるだろうか。あるかもしれないけど、とにかく勝て。勝って勝って勝ちまくれ。ユーベとミランも、チェルシーと当たるまで負けんなよ。
|

1.Yellow Butterfly |
2005.03.18.Fri. 9: 50 a.m. BGM : TAHITI 80 "PUZZLE"
聴いているものにまったく脈絡がありませんが、きょうはタヒチ80です。べつにタヒチで1980年にW杯やコンフェデ杯のようなサッカー・イベントが開催されたわけではないので、勘違いしてはいけません。そういう名前のグループがあるのです。あ、有名なんですか。ふーん。私は何のこっちゃかまったく知りませんでしたが、TSUTAYAの店頭で愚妻が「夏も近いしコレなんかどう?」というので借りてみました。まだ春も本格化していないわけですから夏はぜんぜん近くないと思いますが、愚妻はとにかく夏が待ち遠しい人なので、この中途半端なイラストをあしらったジャケットと「タヒチ」の語感に反応したのでしょう。ともあれ、悪くありませんねタヒチ80。天気の良い爽やかな午前中のBGMにはバッチグーって感じでしょうかしら。バッチグー。バッチグー。古い言葉も、こうして無理やり三回くり返してみると、意外に「アリ」なんじゃないかと思えてくるものです。ナウなヤングにモテモテ。ナウなヤングにモテモテ。ナウなヤングにモテモテ。……ね? そう思えませんか? 思えませんよね? でもタヒチ80はバッチグーな感じ。
|

Disc 1 |
2005.03.17.Thu. 12: 20 p.m. BGM : CARAVAN "Travelling Ways"
それにしても原稿を書いていて驚いたのは、ボーズのトータル・プレミアムオーディオシステム「Lifestyle48」だ。ユーザーの好みを学習して、CD約350枚分の楽曲の中から、そのときに最適な音楽を提供してくれるっていうんだから、どうかしているじゃないか。キモチ悪い機械だよなぁ。いったい、何をどう学習するんだろう。「そのときに最適」とは何を基準に判定するのか。まさか室温や湿度ではあるまい。ひょっとして、脱稿まで残り35枚になるとレッド・ツェッペリンのアルバムが年代順にかかったりするんだろうか。怖いわそんなオーディオシステム。なんにしろ、そんなことまで機械にお任せしていいものなんでしょうか。いま何が聴きたいか自分で決められない人に、50万円もするオーディオシステムが必要だとも思えない。豚に真珠。 ちょっと言い過ぎた。 ともあれ、自分のせいで仕事の段取りが狂ったので、きのうはペースを取り戻すのに苦労した。突発的な事態に遭遇すると平常心に戻るまでやたら時間がかかってしまうのは、私の無数にある弱点のひとつである。深夜1時半頃にようやく憲法本の序章を仕上げ、担当Kさんに送稿。2時半就寝。なので、今朝はセガレの登校時間までに起きられなかった。11時前に出勤してメールをチェックすると、Kさんから「とてもよい感じだと思います」との返信。発信時刻は8時過ぎだ。は、はやい。レスポンスの早い編集者ほど書き手を安心させるものはない。
いま聴いている『Travelling Ways』は、90年代に入ってからキャラヴァンが録音した新曲・旧曲を取り混ぜた2枚組のベスト盤である。じつに楽しい。これを聴いていると、おそらくは若かりし頃の衝動が枯れてきたせいだと思うが、30年前には隠れがちだったキャラヴァン本来のポップ性のようなものがよくわかるのだった。そのぶん、オモシロおかしいアイデアには欠けるところがあるけれど、「枯れたがゆえにポップになる」というのがちょっと逆説的でおもしろい。そういえばPFMが90年代に入ってから録音したアルバムにも、そんなような雰囲気を感じた。「オヤジになれた喜び」が、そこにはある。それはつまり、生きるのが楽になるということだと思う。人はよく「子供は伸び伸びと育てたい」と言うし、私もそう思うが、それは子供というものが本来的に伸び伸びと生きにくい存在だからであろう。放っておいても伸び伸びと生きられるなら、わざわざ「伸び伸び育てたい」と企む必要はない。放っておいても伸び伸び暮らせるのは、むしろおじさんとおばさんなのだ。だから子供には逆に、「伸び伸び生きたかったら早く大人になってみろ」と教育したほうがいいのかもしれない。青春は、鬱屈しているのが当たり前なのである。
|

1.Waterloo Lily |
2005.03.16.Wed. 10: 25 a.m. BGM : CARAVAN "Waterloo Lily"
しまった!(その2) 毎朝ほぼ決まって7時55分にセガレと一緒に家を出て、途中で「じゃあね、いってらっしゃい」「いってきまーす! いってらっしゃーい!」「はい、いってきます」という挨拶を交わして手を振りながら別れたあと、駅へ向かう人の波に逆行するかっこうで仕事場まで歩くので、毎朝ほぼ決まった通勤・通学者たちとすれ違う。走っている人は毎朝ほぼ決まって走っているのがおかしい。わりと美人のOLらしき女性が、いつも同じタイミングで真っ赤な目をして路地の角から現れ、白い息を吐きながらダッシュして来ると、つい「明日こそ三分だけ早く起きようよね」と声をかけたくなる。しかし、いつも大慌ての様子で、化粧もしていないのに、ヘッドホンだけは欠かさず装着しているのが不思議といえば不思議だ。そんなに手間のかかるものではないとはいえ、一刻を争っているようなときは煩わしいだろうし、だいいち走るのに邪魔ではないのか。まったくもって、大きなお世話である。 あと謎なのは、30歳近く年齢差のありそうなカップル(40代と見られるやけに色っぽい女性と70代と見られる男性)が、いつも仲むつまじく腕を組んで歩いてくることだ。夫婦なのだろうか。そして、それは「出勤」なのだろうか。同じところへ行くんだろうか。何なんだろうか。とても気になる。つい、「まさか財産目当てで後妻の座を射止めたんじゃないだろうなぁ」などとイケナイ想像が頭をもたげ、たまに女性がひとりで「出勤」していたりすると、「死んだのか!?」とか思ってしまうのである。いけません、いけません。翌日にまた二人で歩いているとホッとしますが。 近所の公立中学校に通う生徒たちとも大量にすれ違う。今朝は、ほかの女子生徒がみんな「仲良し三人組」で登校するなか、いつも誰ともつるまずに一人で歩いているので好感を持ち、内心で「がんばれよ」と応援していた女の子が、たまたま道で会ったと思しきクラスメイトと談笑しながら登校していて、なんだか安心した。笑顔を初めて見たからだ。われながら何を心配しているのかとバカバカしくなる。しかし考えてみると、私のことを「やけに規則正しい生活をしていやがるのに何の仕事をしているか見当もつかないヒゲを生やした謎の中年男性」として気持ち悪がっている人もいるに違いない。中学生の仲良し三人組に「あのオヤジ、キモいよね〜」「うんうん、キモいキモい」とか言われてたらヤだな。連れ去ったりしないから警戒しないでくれ。ともあれ、毎朝すれ違う人々というのは、人生においてすれ違っているわけではなく、むしろかなり濃密に「出会って」いるのかもしれない。
アバに『恋のウォータールー』という曲があって、中学生の頃から「ウォータールーって何だ?」と思いながら調べもしなかったのだが、さっき、それがナポレオンがらみで有名な「ワーテルロー」のことだと知ってびっくりした。常識だった? 水ともカレー粉とも関係ないなんて意外だ。それが転じて、「決定的敗北」とか「大敗北」という意味でも使われるらしい。アバのアレは大敗北の歌だったのかー。そうは思えないほど元気な歌だが、それはつまり「ヤケクソ」ってことなんだろうな、きっと。 というわけで、『ウォータールー・リリー』はキャラヴァンが『夜ごと太る女のために』の前に発表した1972年のアルバムである。これもいい。『夜ごと〜』にかぎらず、キャラヴァンは曲がいいのである。メロディが美しい。ライナーを読むと、これは「キャラヴァンのなかでもとくにジャズロック色の強い作品」という話になっているのだが、こういう物言いは何だかなぁと思う。キャラヴァンというと常に「ジャズロック」という言葉がついて回るわけで、それも私が今までこのバンドになかなか手を伸ばさなかった一つの理由なのだった。「ジャズロック」と言われると、なんとなく「理屈っぽくて面倒臭そう」と思うのは私だけだろうか。
たしかにキャラヴァンはジャズっぽいことをやるが、そんなものは彼らが迸らせているさまざまな衝動の一つにすぎないと私は思う。彼ら自身、べつに「ジャズロックやりま〜す」と旗を掲げてやっているわけではなかろう。いや、それはどうだかわからないが、結果として、そこに「ジャズロック」と呼べるジャンルが成立しているようには少しも聞こえない。むしろキャラヴァンの才能はポップで美しいソングライティングにあるのであって、それを「ただのポップで終わらせたくないじゃん」という衝動が、彼らにいろんなことをやらせているのではないか。そういう音楽を「ジャズロック」と呼ぶのは乱暴だし、たいへん誤解を招く表現だと思う。たぶんロック界では「こういうのをジャズロックと呼びましょう」という暗黙の取り決めがあるのだろうが、そういう業界内部の恣意的な言葉づかいは「外」の世界に通じないのである。だいたい「ジャズロック」って、なんだか「そばめし」みたいでダサい感じ。造語センスが野暮ったすぎる。
|
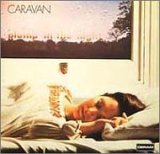
1.Memory lain Hugh |
2005.03.15.Tue. 11: 35 a.m. BGM : CARAVAN "For Girls Who Grow Plump In THe Night"
ここではまず、それが「意思」であることが大事だ。「動物的な本能」のようなものではない。動物に衝動はない。たとえば「あー、ここで愚にもつかない駄洒落を言い放ってしまいたい!」というのも、それが「やむにやまれず噴出してしまう意思」であれば、人間的な衝動である。動物は駄洒落を言いたくならない。言いたくなっても言えない。 もう一つ大事なのは、その衝動がコントロールされていることだ。駄洒落衝動でさえ、それをコントロールして表現に昇華させる技術があればロックを生む可能性がある。逆に言えば、いかにも「ロックっぽい」感じの破壊衝動や攻撃性だって、そのまま叩きつければロックになるというものではない。したがって私は「ロックはハートだよ」といった物言いにも反発を感じる。ハートだけでロックができるなら誰も苦労はしない。もちろん、仮に演奏のテクニックは下手でも、それをコントロールされた衝動の発露として「聴かせるスキル」があればロックになるだろうが。
さて、キャラヴァンである。キャメル好きな私としては、同じカンタベリー出身の彼らに以前から興味津々だったのだが、なんとなく、これまで手が伸びなかった。理由は簡単で、TSUTAYAに置いてなかったからである。amazonでもあまり安く売っていなかったし、中古屋にもなかった。つまり私は貧乏なのだ。しかし最近になって浜田山のTSUTAYAが5タイトルを仕入れてくれたので、2回に分けてぜんぶ借りた。ものすごく気に入った。 キャラヴァンの音楽には、やや駄洒落衝動に近い衝動があるように思う。とくに『キャラヴァン登場』や『グレイとピンクの地』あたりはそうだ。そこかしこに顔を出す独特の「なんちゃって感」に裏打ちされたユーモアに、私は彼らの衝動を聴く。「このポップなメロディを7拍子にしてみちゃったり何かして」「うんうん、べつに必然性ないけどな」とか、「ここでやおらジャズワルツ風にやってみちゃったり何かして」「うんうん、おまえ、あんまり上手く叩けてないけどな」とか何とか言いながら作っていそうな彼らの「だってやってみたいんだもん」を半笑いで聴くのが、キャラヴァンとのつき合い方であろうと思っちゃったり何かしてな。 で、もっとも気に入ったのが、いま聴いている『夜ごと太る女のために』である。夜ごと太る女のためにアルバムを一枚こしらえてしまうあたりが、キャラヴァンの偉大なところだ。どんな女ですかそれは。これを衝動と呼ばずに何を衝動と呼ぶのだ。もっとも、ジャケットの裏側を見るとこの女性が妊娠していることが判明し、べつにキャラヴァンのメンバーが「デブ好き」だということではないらしいとわかるわけだが、まあ、そんなことはどうでもよろしい。このアルバムは、とにかく曲がいいのである。私は好きだ。 でも、なぜか話は急に変わるが、べつに人には勧めない。私の書いたものを読んで「聴いてみたい」と思う人がいればそれはとても嬉しいが、私からは「聴け」とも「聴くな」とも言わない。私は人一倍の「共感されたがり」だと自分で思っているが、同時に、物を書く仕事を通じて、共感されることの難しさも知っている。きのうも同じようなことを書いたつもりだが、共感をナメてはいけない。嗜好の合う人間、何らかの価値観を共有できる人間には、そう滅多に出会えるものではない。だから友達は貴重なのだ。この日誌は学生さんの読者も多いようなので言っておくけれど、「学生時代になるべく多くの友達を作っておいたほうがいい」というアドバイスはウソだと私は思う。友達は作るものではなく授かるものだし、三人いれば十分だ。よほど運の悪い人間でも、三人ぐらいなら授かるだろう。その三人を大事にすることを考えたほうがいい。少なくとも私は自分のセガレにそう教えるつもりだし、その点で愚妻と見解が一致しているというだけで良い結婚をしたと思えるぐらいだ。良い結婚をしたと思える理由はそれだけではないが。 ともあれ、たとえば「ロックが好き」「サッカーが好き」「イギリス文学が好き」「アニメが好き」「テニスが好き」という人間を集めてサークルを作ればみんな友達になれるというほど、共感は簡単なものではない。「自分には友達が百人いる」などと言う人間は信用できない。共感がそんなに簡単なものなら戦争は起きないし、孤独に苦しむ者もいなくなるだろう。それに、共感はするのもされるのもそれなりの技術と能力が要る。それは主にリテラシーである。その点で、自分自身の未熟さを感じている今日この頃である。
ゆうべは、バルセロナ×ビルバオ(リーガ第28節)をビデオ観戦。前半20分、遠くからデコがテキトーにデコっと(←衝動)蹴ったシュートがDFに当たってコースが変わり、バルサ先制。デコって、こんなゴールばっかりだ。それはいいのだが、髪を切ってから松崎しげる感が薄まったのが少し寂しい。さらに前半39分にはジュリのゴールも決まってバルサの2-0。後半、追い上げたいビルバオが後ろにスペースを作ってくれたお陰で、ロナウジーニョがセンターサークル付近から前を向いてぐいぐいドリブルする姿がいっぱい見られて面白かった。たぶん、友達と「今日は90分間で合計30人抜く」とか何とか宣言して賭けでもしていたんじゃないかと思う。数えていなかったが、それぐらいは抜いたであろう。ローラーゲームだったらバカ勝ちだ。昔よく12チャンネルで観てたよな、ローラーゲーム。東京ボンバーズだよ。リッキー遠藤とかミッキー角田とかビンゴ河野とか、いま何してるんだろうか。
|
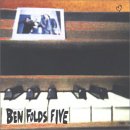
1.Jackson Cannery |
2005.03.14.Mon. 12: 55 p.m. BGM : BEN FOLDS FIVE " BEN FOLDS FIVE "
しかし、その翌日からはまた別の著者になるための営みが始まるというのが辛いところだ。せっかく成りきれたのに、速攻でリセットしなきゃいかんのである。そのまま憑依させておけば同じ著者の本を別のテーマでもう一冊ぐらい書けそうだが、頼まれていない原稿を書いても無駄なのでしょうがない。なので、さっさと頭を切り換えるべく、土曜日から次の仕事の資料を読み始めた。憲法関係の本。前回の仕事では私が構成案を考えるまで著者からも編集者からもレジュメやコンテの類が一枚たりとも提示されなかったが、今回は取材前からほぼ目次どおりのコンテがあり、著者が口述用に作成したレジュメがあり、さらに編集のKさんが口述原稿に詳細な指示を書き込んでくれたので、「順番」を考える作業から完璧に解放されている。ありがたい。ここまで丁寧にナビゲートしてもらうとものすごく楽。口述自体も理路整然としているので、ほとんどリライトに近い作業になるだろう。ただし約2週間で400枚も書かないといけないのだが。うー。 きのうの午後は、そのKさんと吉祥寺のJOHN HENRY'S STUDYで打ち合わせ。担当者が近所に住んでいると楽だ。JOHN HENRY'S STUDYは私が高校生の頃から愛用している店。薄暗い店内で煙草なんか吸っていると、とてもオトナになったような錯覚を味わえたものだ。いけないことです。ともあれ、ここが無くなったら吉祥寺もおしまいだという気がしているが、けっこう繁盛している様子だったので何よりである。もっとも、おそろしく急勾配の階段を三階まで昇らなければいけないので、あと15年か20年経ったら、こっちの足が遠のくかもしれないけれど。
ところで、まだ煙草の味を覚える前、中学生の頃によく聞いていたのがかぜ耕士さんの『セイ!ヤング』だった。急にそんなことを思い出したのは、愚妻とニッポン放送の話をしているうちに「昔の深夜放送」の話題になったからだ。そうだ! かぜ耕士だ! 私の原点はあの番組の名物コーナー「再起不能講座」にあったんじゃないか! ……と思いながら検索してみたら、本人が日記らしきものを書いていたので嬉しくなった。「再起不能講座」の中身はまったく覚えていないが、リスナーからの投稿を読み上げるかぜさんの口調(というか文体)が面白くて、いつも布団の中で笑い声を押し殺していた記憶がある。つまらない投稿でもオモシロおかしく聞かせてしまう彼の芸が好きだった。たぶん、当時の深夜放送には、いまのインターネットにおける「カキコ」と「レス」の原型みたいなものがあったんだろうなぁ。で、そのかぜさんが、ライブドア問題について、こんなことをお書きになっていた。
それにしても社員の決意表明書を「言わされてるだけ」とはホリエモンもラジオを知らないな。ま、知る必要もないんだろうけど、テレビと違ってラジオマンは会社に対して(と言うより、ラジオという媒体に対して)言いようのない厚い,熱い、愛情を抱いてる。それをテレビと同じように扱ってしまうとはラジオ世代に属さない人間の思わぬ盲点かも。 時間外取引だのTOBだの何だのといった話は私には何のことやらわからないし、フジテレビがどうなろうと知ったことではないのだが、ニッポン放送の社員には何となくうっすらと同情心を抱いていた。そして、あの堀江という人には以前から(近鉄騒動の頃から)何となくうっすらと反感を抱いていた。というか、M&Aとやらに血道を上げている人間におしなべて品性下劣なものを感じていた。まあ、私が見ているのはそういう世界のごく一部にすぎないので一概には言えないだろうが、知り合いが勤めている某社の経営者が行っている企業買収の顛末など聞くと、どうしてそこまで他人の人生を振り回すことに無頓着でいられるのか理解できない。買っては捨て、買っては捨ての繰り返しで、相手の企業で働いている社員やその家族の人生に対する想像力が完全に欠落しているのである。おそらく彼らは、世の中が「人」ではなく「法人」で成り立っていると思っているのだろう。だから「法人格」のことしか目に入らず、それぞれの個人の「人格」なんか眼中にないのではないか。 もう一つ、今朝のワイドショーで村上とかいう人が「経営者に株主のことを決められてたまるか!」とか何とか吠えているのを見ながら、愚妻が「こういう男の人たちって……カッコ悪いよね」と呟くのを聞いて思ったのは、あの人たちには「やりたいこと」がない(あってもあるように見えない)からカッコ悪く見えるのではないか、ということだった。やりたいことがあるように見えない人がムキになって戦っている姿は、ちっともカッコ良く見えない。また、やりたいことのない人間が、やりたいことをやるために企業活動を行っている人々の人生を振り回していいはずがない。何かとても青臭いことを言っているような気がするし、ひどく見当違いなことを言っているかもしれないので間違っていたら教えてほしいが、とにかく私は堀江という人が嫌いだ。虫が好かない。生理的にイヤ。あんな人を「ホリエモン」などと呼ぶのは、ドラえもんに対してとても失礼なことだと思う。ドラえもんは、あんな薄気味の悪い笑い方はしない。もっと楽しそうに笑う。 なので、自分のゲストブックにアクセスするたびにライブドアのURLが目に入るのもじつに不愉快である。私はライブドアから掲示板を借りた覚えはない。知らないうちに買収だか統合だか知らないがそんなようなことが進んでいて、勝手にライブドアの「客」にされただけだ。気に入らない。なので、いずれ別の掲示板に移行したいと思っている。近々そうなるかもしれないが、それは数週間前から考えていたことで、べつに私のゲストブックを乗っ取る動き(笑)があるからではないので勘違いしないでほしい。もちろん、過去ログは残しておきたいので、いまの掲示板を消滅させたりもしません。できれば過去ログごと引っ越したいんだけど、そんなことできないよねぇ?
ベン・フォールズ・ファイヴの存在をどこで知ったのか記憶が曖昧だ。たぶん、サッカーファンには『ぼくのプレミア・ライフ(原題『Fever Pitch』)』(新潮文庫)の著者として有名な英国人作家ニック・ホーンビィの『ソングブック』(同)という音楽エッセイで紹介されていたのを読んだんだと思う。いま、その本が手元にないので違うかもしれないけど。自分の好きな曲について書かれたそのエッセイ集は、目次を見たらZEPの『ハートブレイカー』が入っていたので買ったのだが、その中で絶賛されていたブルース・スプリングスティーンの『サンダーロード』を聴いてみたら「なんじゃこりゃ」だったので、人間の好みというのは一筋縄ではいかないものだなぁという話だ。きっと、同じ音楽を愛好している人間が同じところに感動しているとは限らないということだろう。もちろんサッカーも同じ。アーセナル・サポーターであるホーンビィのサッカー語りに、すべてのアーセナル・ファンが共感できるとは限らない。たまに、その共感をお互いに押しつけ合っているようなタイプのファンサイトを見ると、背中で虫酸が全力疾走を始めることがある。 それはともかく、このベン・フォールズ・ファイヴはすばらしくカッコいいぞ! 完全に私好みのノリ。生ピアノ、ベース、ドラムというギターレス・トリオでロックが演れるというのは、けっこうな驚きである。なんで3人なのに「ファイヴ」なのかわからないところも含めてロックだ。これを聴きながら思ったのは、ロックとは「衝動的な音楽」のことではないかということだった。いっそ「ロックだけが衝動的な音楽だ!」と言ってのけてしまいたいという衝動に駆られるぐらいだ。ジャズは理念的で、ロックは衝動的−−かどうかはまだちゃんと検証していない(というか単なる思いつきの)仮説にすぎないけれど、芸術的な音楽には理念か衝動かのいずれかが不可欠なのではないかという気がするし、少なくともこれまで私が聴いてカッコいいと思ったロック・ミュージックは、いずれも「やむにやまれぬ衝動」を感じさせるものだった。やむにやまれぬ衝動に突き動かされた人間の作る音楽は楽器の編成がどうであれロックになり、衝動のない奴らの演奏はいかに編成がロックバンドっぽくてもロックに聞こえないのではないか。そして、やりたいこともないのにデカい金を動かして遊んでいる人たちは、ぜんぜんロックじゃない。理念もないから、ジャズでもない。べつに人の生き方が音楽的である必要はないけれど、しかし、音楽的である以上にカッコいい生き方があるだろうか、とも思う。よくわからないが、そんな気分。
ゆうべビデオで観たラツィオ×インテル(セリエ第28節)は1-1のドロー。あまり音楽を感じさせない試合だったが、唯一、いいフィリッピーニのラストパスをええフィリッピーニがダイビングヘッドで叩き込んだラツィオの先制点は、理念と衝動が高い次元で融合された、すばらしくカッコいい双子ゴールだった。それを守りきろうとすることしかできないあたりが今のラツィオのカッコ悪いところだが、まあ、ジャンニケッダがイエロー2枚で退場させられたのでは仕方がない。腕力で強引にむしり取ったようなフリオ・クルスの1点で済んでよかった。それにしてもモウリーニョはいったい何をしにオリンピコまで来ていたんだろう。インテルはまだCLの勝ち上がりが決まったわけじゃないし、どちらのチームにもチェルシーに必要な選手はいないように思うのだが。あ、翌日にユーベやミランの試合があるから、ついでにインテルも冷やかしておこうと思っただけか。
|
|
| #23 | TOP | BACKNUMBER | FUKAGAWA | B.I.P. | GUEST BOOK | #25 | |
 |