
 |
| #28 | TOP | BACKNUMBER | FUKAGAWA | B.I.P. | GUEST BOOK | #30 |
|
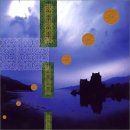
1.コーラス・リール / アシュモリーン・ハウス |
2005.05.19.Thu. 14: 50 p.m. BGM : オムニバス "深い森のケルト(pure teaditional ambient 2)"
それにしても、「20年前の自分が手書きの文字で埋め尽くした原稿用紙の束」ほど甘酸っぱいものが他にあるか。400字詰めの原稿用紙って、ひょっとしたら卒論で使ったのが最後のような気がするが、真ん中にあしらわれた蝶ネクタイみたいなオレンジ色の模様を眺めていると、なんだかグッと込み上げてくるものがあるのだった。うー。前にも似たようなことをここに書いた記憶があるが、ワープロやパソコンと違って、原稿用紙の場合は「埋められるべき空白」が予め用意されており、それが書き手を駆り立てるようなところがある。意外だったのは、学生時代の自分が万年筆で書いていたこと。たぶん鉛筆で下書きをしてから提出用に清書していたのだと思うが、きっと「万年筆で書く」に憧れてたんだろうなぁ。いじらしいぞ、20年前の私。
それから20年後の私に、小説は書けるだろうか。
|

1. Hard Luck and Troubles |
2005.05.18.Wed. 13: 50 p.m. BGM : DELANEY & BONNIE & FRIENDS "TO BONNIE FROM DELANEY"
また、立って弾くと弦が見にくくなるので、正確に「ブラインドタッチ」ができるようにならないといけません。下手なアマチュアを見ていると、たまにツムジがこちらに見えるような格好で弦を覗き込みながら弾いていて「カッコわりぃなぁ」と思うことがあるが、あれはたぶん、ふだん立って弾く練習を怠っているに違いない。でも、家族の前で立ってギターを練習するのって、とても恥ずかしい。そんなお父さんに威厳はあるのか。
ところで、ギターをやり始めると似たタイプの楽器を見る目も変わってくるもので、あれは土曜日だったか、BS-2で深夜に放送していた『BBCフィルハーモニック演奏会』で神尾真由子というバイオリニストがメンデルスゾーンの協奏曲を弾くのを見て、あらためてバイオリンという楽器の表現力やバイオリニストの技術というものに感服した。もちろん私はバイオリンの弾き方なんか何も知らないが、たとえば「小指でビブラートをかける」ということ一つ取っても、それを完璧にこなすためにどれだけの訓練が必要かということが、なんとなく想像できるのである。神尾真由子はまだ二十歳にもなっていない娘さんで、顔はあどけない感じなのだが、ビブラートをかけているときの小指はいくつもの試練を乗り越えてきた「大人」に見えた。ともあれ、芸術を理解するには自分でもやってみるのが一番、という結論。たぶん、絵や彫刻なんかも同じだろう。「楽器の弾ける音楽評論家」や「油絵の描ける美術評論家」が、世間にどれだけいるかは知らないけれど。
ちなみに、その『BBCフィルハーモニック演奏会』のメイン・プログラムはホルストの『惑星』だった。『惑星』を演奏しているオケを見るのは初めて。吹奏楽以外では使われないと思っていたユーフォニウム(私が高校時代に演奏していた金管楽器)が使われているのを知って、ちょっと嬉しかった。吹奏楽のオリジナル曲でもユーフォニウムをかなり活躍させるところを見ると、ホルストはあの楽器が好きなのかもしれない。ただ、『惑星』はテーマ的にも音的にも映像喚起力が強いというか、音だけ聴いていると演奏している人間の姿が思い浮かばないようなところがあるので、見ていると何だか違和感がある。それはまあいいのだが、聴衆の気持ちを考えると、派手にエンディングを迎える『木星』で拍手ができず、お通夜みたいな『海王星』がフェイドアウトした後でようやく拍手を許されるというのは、カタルシスの点で物足りないのではないか。テレビで見ていても、『木星』の後で聴衆がコソコソと咳払いなんかしていると欲求不満になる。いずれにしろ、あまりコンサート向きの曲ではないような感じ。『木星』で拍手させろ。そこで終わっても別に文句は出ない、という説もあるし。
|
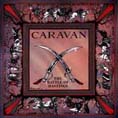
1.It's a Sad, Sad Affair |
2005.05.17.Tue. 10: 35 a.m. BGM : CARAVAN "THE BATTLE OF HASTINGS"
もっと激しく舌打ちしたくなったのが、ゆうべビデオで観たローマ×ラツィオ(セリエ第36節)である。ローマダービーが単なるサッカーの試合ではなく「事件現場」であることを証明するような一戦であった。どんな事件かというと、ボールを使った「談合事件」です。ひどく粗悪な出来レース。シュートらしいシュートもほとんどなく、というか決定機らしい決定機もほとんどないまま、淡々とスコアレスドローである。きのうバルサの「20分パス回し」について触れたばかりだが、その最長時間稼ぎ記録はあっさり更新された。前後半90分をフルに使った時間稼ぎ。いや、まあ、たぶんW杯のグループリーグ等でも過去に似たようなことはあったのだろうと思うが、とにかく呆れた。昼休みのバレーボールを見てるような気分だった。いまどき屋上で輪になってバレーボールやってる会社はないと思うが、ともかく、結果的には生中継しなかったスカパー!の判断が妥当だったことになってしまったじゃないか。ブリテン島で下位4チームが殺気に満ちた至高のサバイバル合戦を繰り広げていたのとほぼ同じ時間帯に、ローマでは眠気に満ちた最低の無気力相撲が行われていたわけだ。テキトーなファウル連発してイエローいっぱいもらえば戦ってるように見えると思ったら大間違いだぞコラ。でも、トッティが出場していたら、こうはならなかったような気がしなくもない。トッティのいないローマダービーなんて、炭酸の抜けたサイダーみたいなものだ。したがってラツィオは悪くない。トッティが悪い。トッティが悪い。トッティが悪い。すべてトッティのせいにして、この試合のことは忘れることにしよう。
|

1.Thick as a Brick |
2005.05.16.Mon. 18: 05 p.m. BGM : JETHRO TULL "THICK AS A BRICK(ジェラルドの汚れなき世界)"
さらにゆうべは、サウサンプトン×マンチェスターU(プレミア最終週)を中心に、残留争いをザッピング観戦。「首位」のノリッチがフルアムに先制を許したのを見た直後にチェンネルを戻したら、すぐに「2位」のサウサンプトンが先制したのでコーフンした。こんなふうにザッピングが成功するのは、とてもめずらしい。それ以降はユナイテッドの2ゴールしか目撃していないが、4試合の得点経過を聞いているだけでめちゃくちゃオモロかったですね。バルサ優勝直後のフィールドは、選手がはしゃぐためのスペースを奪った観客や報道陣がうざったくて仕方がなかったが、ミラクルな残留を決めたウエストブロムのほうは、どんどん増殖するサポーターがカラフルできれいだった。前者の観客と報道陣には「主役」を追いかけ回す軽薄さがあったが、後者は自分たちが「主役」として歓喜に浸っていた、という感じ。それにしても稲本はどこでシャンパンを振り回していたのか。
|

1.遠い世界に |
2005.05.15.Sun. 12: 05 p.m. BGM : 矢野真紀 "遠い世界に"
発売中の『SAPIO』5月25日号の『新・ゴーマニズム宣言』で、「みなちゃん」こと秘書の岸端さんが、欄外に『嫌いな日本語』のことを書いて宣伝してくれた。『わしズム』の豊富きわまりないコンテンツの中から、あえてあのささやかなページに注目して取り上げてくれたことが、とてもありがたく、うれしい。しかも、私が書き手として狙っているスタイルのようなものをきちんと汲み取ってくれている。つまり、本人が褒めてほしいところをまっすぐに(とても簡潔な表現で)褒めてくれている。これは、人の自己愛をくすぐるときの基本だ。取材現場で会うときもいつもそう思うが、ほんとうに、若いのにしっかりしたお嬢さんだと思う。
人は、自分が褒められると人を褒めるものである。
水疱瘡などのために買いそびれていた矢野真紀のシングル『遠い世界に』をようやく入手。テレビCMに使われたのが好評だったので急遽リリースしたようだ。その「好評」が、団塊前後の世代が懐かしがった結果なのか、原曲を知らない若い世代(私だってリアルタイムで聴いた世代ではないけれど)が好意的に反応した結果なのか、どっちなのかは知らない。仮に後者だとすると、いまの10代や20代がこの歌をどのように聴いたのかが興味深い。CMに歌詞のどの部分が使われたのかを知りたいところだ。テレビで聴いたことのある人は教えてください。 おそらく矢野真紀本人にとっても、この35年前の歌にどうやって今日的なリアリティを与えるかは、困難かつ意欲をかき立てられるチャレンジだっただろうと思う。無伴奏で始まる冒頭部分から最後まで、懸命に独自性を出しつつ、しかし原曲の味わいは損なわないよう慎重に工夫している様子が感じられる。キモは、やはり<雲に隠れた小さな星は これが日本だ 私の国だ>という、この曲でもっとも印象的な一節だ。いまは「愛国心」というと保守派の専売特許のように思われているが、小熊英二が『民主と愛国』で書いていたように、戦後しばらくの間は左派も「愛国」を掲げていたわけで、五つの赤い風船の『遠い世界に』も(この場合は「愛国心」というより「愛郷心」といったほうがいいかもしれないが)その延長線上にあるものなのだろう。私がこの歌を知ったのはたぶん中学生時代で、その頃はすでに「愛国心=右」という図式になっていたからなのか、「左」であるはずのフォークソングに「日本」「私の国」という言葉が使われていることに漠然とした違和感を抱いた記憶がある。「あ、日本が好きでいいんだ」と、ちょっとドキドキしながら思った記憶もある。その意味では、以前ほど「愛国」に抵抗感を抱かなくなっていると言われている今の若い世代のほうが、この歌を素直に聴けるのかもしれない。
それはともかく、矢野真紀は<これが日本だ 私の国だ>という一節を、ぐっと声量を落とし、ささやくような声をかすかに震わせながら、もしかしたら泣いているのではないかと思わせるような歌い方で歌った。そこに込められた彼女の思いは、まだ私にはわからない。わからないが、そこには聴く者の心をとらえて離さない何かがある。ここで歌われている「日本」は、間違いなく「今の日本」だ。いや、「今の日本」が思い出すべき「私の国」の姿だろうか。うまく言えない。うまく言えない。うまく言えない。うまく言えないので、多くの人に聴いてほしいと思う。ピアノとギタレレによるシンプルで美しい伴奏も含めて、じつに素晴らしいカバー曲である。……ギタレレ?
|

1.My Sunday feeling |
2005.05.13.Fri. 12: 40 p.m. BGM : JETHRO TULL "THIS WAS(日曜日の印象)"
一昨日、某編プロのマッキー社長より緊急指令が下り、きょうの夕刻に日本語の上手なアメリカ人と元人気女子アナの対談を取材して速攻でテープを起こし、月曜日の夕刻までに原稿を仕上げることになった。「土日に働け」ということである。ンもう、あいかわらず無茶いうんだからぁ。急な話だったので、対談のテーマさえ聞いていない。何の話になるんだ? まあ、何の話でもいいんだけどね。意味のわかることさえ喋ってくれれば。まだ顔が完全には復旧していないので取材現場に足を運ぶのは気が重いが、しょうがない。テープだけバイク便で送ってもらう手もあるが、現場で話を聞いていないと起こすのに手間がかかるのだ。元人気女子アナにも会ってみたいしね。へへへ。それにしても、近頃は雑誌の仕事というと対談や座談会ばかりだ。増えてるんだろうか、対談記事。わりと好きな仕事なので、そうだとしたら私にとっては良い傾向である。対談や座談会は、書籍のゴースト以上に「腕を振るっている」という手応えが得られるのがいい。散漫な対話に無理やり流れをつけてまとめていると、ちょっとした神様気分が味わえるものなのだ。収録後に出席者が「とっちらかった話になっちゃってスミマセン。こんなんで、まとまります?」などと申し訳なさそうに言うときほど、ワクワクする。
チェルシー優勝の余韻に浸って浮かれているあいだに、どうやらラツィオのほうはレッチェとウディネーゼに連敗していたらしい。あらまあ。今季のラツィオはたまにしか調子が良くない。つまり弱い。で、今週末はローマダービーが行われるわけだが、スカパー!の放送予定を見て愕然とした。月曜日19時30分からの録画放送。とうとうローマダービーがライブで観られない時代になってしまったのである。どうせ誰も見やしない埋め草カード(ウディネ×サンプ)が生中継なのに、だ。嗚呼。何やってんだローマ! おまえらが14位なんかに低迷してやがるから、ローマダービーの重みも考えずに見た目の順位でしか放送の優先順位を決められない不見識なスカパー!がこんなバカげた編成をしでかしやがるんじゃないか! ……と、人のせいにしておく11位チームのファンであった。しかし真面目な話、どんな「事件」が勃発するかわからないローマダービーを生中継(できるのに)しない放送局というのは、ジャーナリスティックなセンスが欠落しているとしか思えませんね。ローマダービーは単なるサッカーの試合ではなく、「事件現場」なんだよ。そんなもんを翌日に録画でお茶の間にお届けしてどうすんだよ。デリバリーのピザだって冷める前にお届けしなきゃ意味ないんだよ。少しはアタマ使えよ。でも、まあ、しょうがない。このダービーとバルサ優勝決定試合で私の04-05シーズンは終わるので、どうかラツィオには有終の美を飾ってもらいたい。
|
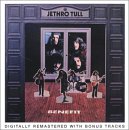
1.With You There To Help Me
Nothing Is Easy |
2005.05.12.Thu. 16: 35 p.m. BGM : JETHRO TULL "BENEFIT"
しかし、「たまたま書いたことにしてくれ」と頼んだ部長は言語道断のバカで論外だが、つい「わかりました」と一度は罪を引き受けてしまった30代のフリーライター氏も、気の毒だとは思うものの情けないよなぁ。ああ情けない情けない。「部下が」「秘書が」と責任が下へ下へと押しつけられていくような、そういう「組織の論理」ってモンがヤだからフリーで仕事してんじゃないの?と思うのである。フリーランスの人間はしばしば「自由でいいなぁ」などと言われるが、実際は雇い主(その大半は組織)に生殺与奪を握られている不自由な立場なんであって、自由といえばせいぜい「ケツをまくる自由」(収入を犠牲にしてアホバカマヌケと一緒に仕事をしない自由)があるぐらいのものだ。それを放棄しちゃったら、非組織人でいることの意味なんか無いじゃぁありませんか。この場合、その部長に向かって「おれはアンタの手下じゃねえぞ、このスットコドッコイ!」と啖呵を切って突っぱねることでカタルシスを得るのがフリーに与えられたささやかな特権というものではないのか。そのチャンスを、30代のフリーライター氏がみすみすフイにしてしまったことが残念でならない。ああ勿体ない勿体ない。などと言っている私は、ルサンチマンが強すぎるのでしょうか。 それにしても判らないのは、どうせ誰も読んでないHPの埋め草コラムなんかを、なんでわざわざ盗用までして書いてたんだこの部長は、ということだ。どうせ誰も読んでないからバレないと思ったんだろうけど、書けないなら書かなきゃいいじゃんねぇ。『天声人語』や『斜断機』ならともかく、HPのコラムなんて3年ぐらい休載したって誰も文句なんか言わないだろうに。でも、まあ、書きたかったんだろうな。書きたいんじゃしょうがないよな。 しかし、アレだ。あえて暴論を吐かせてもらえば、現場で取材しないと話題に乏しくてモノが書けないようなご立派なジャーナリストは、埋め草コラムなんか書いちゃいけないのである。昔、尊敬する業界の先輩が「取材なんて、しないと書けない奴のすることだ」と言っていたことがあったが、そこには一面の真理があると私は思う。ジャーナリストは往々にして「現場で取材」していることをとても偉いことであるかのように言い募るし、もちろんジャーナリズムはそうあるべきだろうが、世の中にはそうではない原稿もあるんである。自慢じゃない(こともない)が、私は2年間の「お茶ズボ」連載中、サッカーの「現場」に足を運んで材を取ったことが、たぶん一回しかない。その一回も、取材したのは生身の選手やフィールドではなく、たまたま遊びで見に行った試合の「客席」だ。積極的な「現場取材」と呼べるものでは到底なかった。だって、いかに現場取材なんて面倒なことをせずに言葉を膨らませて、現場取材した記事と同等かそれ以上の満足を読者に与えられるかってのが、埋め草稼業の醍醐味じゃないか。現場で取材して書くなんて、そんなの簡単すぎるじゃないか。誰でもできるじゃないか。ちょっと言い過ぎたような気もするが、せっかく「どうせ誰も読んでない埋め草コラム」を好き勝手に書く場を手にしながら、この部長が盗用などという退屈な手段で「埋め草の愉悦」を味わうチャンスをみすみすフイにしたことが残念でならない。ああ勿体ない勿体ない。私に任せてくれれば、同じ新聞記事を使いながら盗用がバレな(以下略)。
それはともかく、今回の「フリーライターへの責任転嫁」が決して特殊な事例ではなく、ある意味で象徴的なケースなんじゃねえかなぁと思うのは、ここ1〜2年、フリーランスの扱い方が以前よりも粗雑になっているような実感があるからである。私自身、近頃はギャラや日程などをめぐって「フリーの立場わかってんの?」と言いたくなることがやたらと多いし、今朝は今朝で最近フリーになったばかりの編集者から「版元と支払いの件でトラブっている」というメールをもらった。ある仕事が完了した後で、着手前に提示されていたギャラを値切られているらしい。詳しい事情は知らないが、たぶん、その提示条件というのは口約束にすぎないのだと思われ、法的な支えがないのが例によって厄介なところだ。まあ、カネのことは、いちいち契約書なり何なりで文書化していくというごく当たり前の解決策が(現実にやれるかどうかは別にして)あるわけだが、それだけでフリーランスの人間が安心を得られるとも思えない。もっと根本的なところで、自分たちの組織とフリーランサーの関係性や、フリーランサーの(組織人とは異なる)日常といったものに対する理解や想像力が欠落している輩が増えているように感じるのである。どうしてなのかは、わからない。要するに「不景気で余裕がない」ということかもしれない。利益や効率をせちがらく追求するようになったせいなのか、なんというか、ざっくり言って、業界全体が「荒れている」という印象もある。出版の場合、たまたま「安全の確保」のような社会的使命を担っていないから、JR西日本のような目立った「事故」が起こらないだけかもしれない。その代わり、フリーの人間の周囲で小規模な「脱線」が頻繁に起きているということだろうか。
さて、世間は胸クソ悪いことばかりではないのであって、マンチェスターU×チェルシー(プレミア第32週)には実にスカッとさせられたのである。なにしろ選手入場からして気分がいい。オールド・トラフォードであのユナイテッドの面々を整列させ、チャンピオンチームのお出迎えをさせるほどスカッとすることがあるだろうか。あんまりスカッとしたので、「わはは、ざまあみやがれ」と下品な言葉を口走りながらヨダレ垂らしちゃいましたよ私は。やっぱルサンチマンが強すぎるんだと思う。しかも試合は1-3の逆転勝ちだ。ユナイテッドはホーム最終戦でホーム初黒星だ。わはは。さらにチェルシーは勝ち点94で、プレミアの最高記録更新である。いやぁ、惜しいよなぁ。唯一負けたシティ戦で勝ってりゃ、最後のニューカッスル戦で「100点」に届いたのになぁ。惜しい惜しい。わはは。わはは。
昨日と今日の二日間、日本のどこかでジェスロ・タルがコンサートをしているはずなのだが、そういうものがあると私が知ったときにはすでにチケットが完売していたので残念なことである。そこで悔し紛れに……というわけでもないのだが、やはり動いているジェスロ・タル(というか動いているイアン・アンダーソン)を見てみたいので買ったのが、70年のワイト島フェスティバルの模様などを収録した『Nothing Is Easy』というDVDだ。噂に聞いていたアンダーソンの一本足奏法は、まさに「ロック界の王貞治」と呼ぶにふさわしい切れ味。その切れ味にどんな音楽的意味があるのかは不明だが、フレーズの合間に左足をひょいひょい上げ、ときおり空中にキックをかましながらも体の軸がブレない(フルートの音も乱れない)そのバランス感覚はすごい。誰か王さんにこの映像を見せて、技術面の解説をしてもらってくれないものだろうか。演奏シーンの合間には、変わり果てた姿になった現在のイアン・アンダーソンのインタビューも収録されており、それによれば、デビュー当初にマーキークラブでギグを行ったとき、実際はハーモニカを一本足で吹き、フルートはふつうに吹いていたのに、新聞のレビューに「片足のフルーティスト」と書かれてしまったので、仕方なくフルートも一本足で吹けるように練習したそうだ。とてもウソ臭い話で、じゃあそもそもハーモニカを一本足で吹いていたのは何故なんだという話にもなるわけだが、まあ、何であれ、練習によって培われた技術は尊い。それも含めてロックである。
|

1. The Future Won´t Be Long |
2005.05.11.Wed. 14: 25 p.m. BGM : SPIROGYRA "St.Radigunds"
ここ数日、「元気だが外出は不可」という状態だったので、家で本ばかり読んでいた。私はめったに翻訳小説を読まない(むろん原書で読むわけでもない)のだが、今回は愚妻が前に読んでいたマイクル・コーディ『イエスの遺伝子』(徳間書店)とダン・ブラウン『ダヴィンチ・コード』(角川書店)の2タイトルを一気に読了。「いまごろ何を」という話で、例によって流行に乗り遅れがちな自分というものを再認識するわけだが、二つとも活劇としてよくできていて面白かったです。いずれもキリスト教がらみの陰謀話で、立て続けに読んだら秘密結社を作りたくなってきた。秘密結社。じつに誘惑的な語感である。ヒリヒリするような緊張感というか、油断も隙もない毎日というか、風呂やトイレに入っていてもつい眼光が鋭くなってしまう日常というか、そういうのってカッコイイよな。ヤクザと何が違うのかよくわからないと言えばよくわからないが、秘密結社は素敵だ。これ以上にエキサイティングな趣味はないと思う。秘密結社が趣味でやるものかどうかは議論の余地があるが、どうやったら作れるんだろう。二つの小説を読むかぎり、秘密結社に必要なのは、「守るべき秘密」「味方」「敵」「隠れ家」「不幸な生い立ちを持つ暗殺のスペシャリスト」「お金」などのようだ。うーむ。どう考えても、秘密結社よりロックバンドのほうが作りやすそうである。
このスパイロジャイラは、あのスパイロジャイラとは別のスパイロジャイラである。あのスパイロジャイラ(Spyro Gyra)はフュージョンで、このスパイロジャイラ(Spirogyra)は70年代前半あたりに存在した英国のフォーク・グループだ。勘違いして買うと、どちらのファンも相当なショックを受けると思うので気をつけたほうがいい。このスパイロジャイラは男声と女声のツイン・ボーカルで、男(Martin Cockerhamという人)は歌い方がボブ・ディランに似ていて微笑ましい。イギリスでも流行ってたんだろうなぁ。バイオリンも入っているので、ディランが女性コーラス(エミルー・ハリス)とからんでいた『欲望』を思い出したりもする。とはいえオリジナリティがないというわけでは決してなく、妙に気持ちに引っかかる独特な響き。アメリカのフォークとは何かが違う。なんちゅうか、こう、素直じゃない感じ。ジェスロ・タルにハマっていることもあって、イギリスのトラディショナルなフォークというようなものへの興味が高まっている。もちろん、それはレッド・ツェッペリンとも無縁ではない。
|
|
| #28 | TOP | BACKNUMBER | FUKAGAWA | B.I.P. | GUEST BOOK | #30 | |
 |