
 |
| #29 | TOP | BACKNUMBER | FUKAGAWA | B.I.P. | GUEST BOOK | #31 |
|
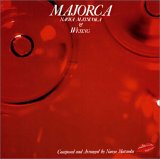
1.DESAFIO |
2005.06.01.Wed. 13: 55 p.m. BGM : �������� & WESING "MAJORCA"
�@���̗͂���ď����������j�ƁA���y�̗͂���Č��e���������C�^�[�́A�ǂ��炪���l�Ƃ��ă_�����낤���B
�@���̂��͌ߌォ��A�킵�Y���̎�ނP�{�ځB���悢��n�܂����킯�����A����ɒǂ��ł���������悤�ɁA�˓`�Ђr�����獡�����Ɏ��M����{�̃R���e���͂����B���ȂɋN�����Ă�������ŏI��̃e�[�v���L�𑗂����̂͂��̂��̒��Ȃ̂ɁA����10���Ԍ�ɂ̓R���e���o���Ă���̂�����A�d���������B�_���Ă����X�y�[�X�ɁA�����^�b�`�ŃX���[�p�X���o���Ă�������悤�ȉ���������B�{�[�������������Ȃ��ҏW�҂́A���C�^�[�ɂƂ��Ď��ɂ��肪�����B���̂ق����A�Ȃ�ׂ�������𑁂�����悤�w�͂��Ȃ�������Ȃ����A���������v���X���L�c���Ă˂��B�ƁA�u�����v���I����āu�n���v�ɓ˓������r�[�Ɏ㉹��f���Ă݂��킯�ł��邪�A�܂��A�̒����������Ȃ���Ή��Ƃ��Ȃ邾�낤�B�c�c���A���������A�����ӂ����ׂ̗\�h�ڎ킪�܂�����Ȃ����B
�@�������l���Ă݂�ƁA���{�]���̗\�h�ڎ�݂����ȕ���p���Ȃ��Ƃ�����Ȃ��̂������B���܂̎��́A�������Ă����ڂɏo�����ȋC�����ĂȂ�Ȃ��̂ł���B�Ȃ̂ŁA����ȃy�[�W�������ēǂ�ł݂��B����ƁA���s�������B���i�����ӂ����ׁj�́u���N�`���ڎ��10�����̜늳�҂�����v�Ƃ̂��ƁB�V���[�g10�{������P�_�ȏ�������A������ƃZ�[�u�����Ⴂ��ȁ[�B�L���������̓}�V��������A���̏ꍇ�A���[�}�����݂Ɏ~�߂Ă���Ȃ��ƃ_������B�������A�ڎ�҂��瑼�l�Ɋ������邱�Ƃ��H�ɂ���炵���B�Ă߂��̌��N�̂��߂ɑ��l��a�C�ɂ��Ăǂ�����Ƃ����̂��B���q�̂��߂Ȃ瑼����N�����Ă��\��Ȃ��Ƃ����̂����܂��́B�����艽���A�u���݂̓��{�̃��N�`���͕���p���������߂��Ȃ��v���ď����Ă��邶��Ȃ����I�@�l�b�g�ɏ����Ă��邱�Ƃ��z�ʂǂ���Ɏ���Ă̓C�J�����ǂ��A���ƐM�p�ł������ȕ��͋C�̃T�C�g�����Ȃ��B������ɂ���A���Ղɐڎ킵�Ȃ��ق��������悤�ȗl�q�ł���B���ƂŁA�m�荇���̈�҂Ƀ��[���ő��k���Ă݂悤�B�m�荇���̈�҂��āA�Z�ł����ǂ��ˁB�ǂ����̑������Z����͒��������̂ŁA�e�ɃA�h�o�C�X���Ă����ɈႢ�Ȃ��B
|

1.���X�̂����� |
2005.05.31.Tue. 11: 40 a.m. BGM : ���^�I "������"
�@�������B�����ɂ͎O�U���Ȃ����z�[���������Ȃ��̂������B�u�V���O���q�b�g�ɂȂ肻���ȃz�[�������v�Ƃ����������͔�g�Ƃ��đ����ɂЂ˂���Ă��邪�A���������Ȃ��Ȃ��B����A�ׂɃV���O���q�b�g�������ȋȂȂȂ��Ă������̂����A���Ɉ����������ĉ��x�����݂��߂����Ȃ�悤�ȋȂ���������Ȃ��̂��₵���B�{�l�v���f���[�X�Ȃ̂ɁA���^�I�炵��������Ȃ��B�ޏ��ɂ������o���Ȃ����ȑ��݊��ƃ��A���e�B���������l�Ԃ␢�E���o�ꂵ�Ȃ��B�v����ɁA�u�t�c�[�ɃC�C�J���W�̋ȁv����Ȃ̂ł���B �@�����Ȃ��������̂ЂƂ́A���Ԃ�A�����̃\���O���C�^�[���Q�����Ă��邱�Ƃ��낤�B���͖��^�I�Ɏ��쎩���́u�V���K�[�^�\���O���C�^�[�v�ł����Ăق����Ǝv���Ă��邪�A����A�u�쎌�E��ȁ^���^�I�v�͂R�Ȃ����B����ȊO�̂V�Ȃ́A�L��^�_�V�A����א��A�R�������q�A�J�����A�c�������A���������Y�A�����C�i�Ƃ������l�X���쎌���ȂɊւ���Ă���B�M�^���X�g�Ƃ��Ĕޏ��̃c�A�[���ɎQ�����Ă��钆���C�i�ȊO�A���ꂪ���҂����Ȃ̂����͒m��Ȃ��B�ǂ����i�|�o�n�o�E�́u������q�v���܂܂�Ă���炵���B������ɂ���A�ނ�̌��𑩂˂ĂЂƂ̍�i�Ɏd�グ�悤�Ƃ������ʁA�ő���I�Ȗ���ȃZ���ɂ܂Ƃ܂��Ă��܂����A�Ƃ����悤�Ȉ�ہB���̈Ӗ��ł́A��͂蕡���̃\���O���C�^�[���N�p���āu�����ȋȁv����ׁA�u���̍�������v�Ƃ��u���̈Ǘ��v�Ƃ���_���Ă����Ƃ����v���Ȃ��f�r���[�A���o���Ǝ��Ă���B���̘H������ޏ��Ɣޏ��̍˔\���~���o���A�S�Ȗ{�l�̍쎌��Ȃɂ�閼�Ձw���̂����x����点���̂��T�c�����v���f���[�T�[�������킯�����c�c�B�ǂ����A�������������u���сv�Ƃ������[�x���𗧂��グ�Ĉȍ~�̖��^�I�͕s���R�����Ɋ������Ďd�����Ȃ��B
�@���̂��͉J�̒��A�\�Q���`�_�ے��`�_�y��Ƃ������[�g�ŕҏW���c�A�[�B�m�l�̏Љ�ŏ��߂ĖK�ꂽ�\�Q���̂b�o�łł́A�S105���́u���������̈ꗗ�\�v����������A�����̎�����Ɂu�o�����◚�����͂������ł����H�v�Ɛu����A����Ȃ��Ƃ�15�N�Ԃŏ��߂Ă̌o���������̂ŁA�������S�����B�ǂ����A�ق�Ƃ��Ɂu�ʐځv�������悤���B�܂��A��������ȕ��͋C�������������i���X�g��p�ӂ��čs�����킯�ŁA����ȏ�ɂ킩��₷�����C�^�[�Ƃ��Ắu�o�����v�͂Ȃ��Ǝv����ł����ǂˁB�u������ł́A�����������m���K�v�Ȃ�ł����H�v�Ɛu������A�u���������킯�ł͂���܂��v�Ƃ������Ƃ��������A�����ȏo�ŎЂ�������̂��ƕ��ɂȂ�܂����B �@���̌�A��ɂ���ė�̂��Ƃ��u�Ƃ��ɂ��D���ȕ���͂���܂����H�v�u����܂���B�������ӂ��Ɛu�����A���e���������Ƃł��A�Ƃ��������܂��v�Ƃ��������B�_�y��҃̕v���ł��A�����悤�ȉ�b�������B�����̂��Ƃ����A�ǂ����d���ɑ��鎩���̃X�^���X�����܂������ł��Ȃ��č���B�����ŋA���A���߂āu��̂���͉����D���ȂH�v�Ǝ��⎩�����Ă݂��̂����A���Ԃ�A���͌��t��a������M�肷�邱�Ǝ��̂��D���Ȃ̂ł����āA���������Ĉ����f�ށi�W�������j�͉������Ă����̂��B�����āu�D���ȃ^�C�v�̎d���v��������Ȃ�A�u���t�̃A���v�݂����Ȃ��̂��H�v����]�n�̑����d���A�Ƃ������ƂɂȂ邾�낤���B�ŁA���������X�y�[�X�������Ƃ������̂��A������O���������R�������̎��O�̌��e�ł���B������A���ꂪ������y�����B�u�S�[�X�g�d���ƈ���Ď����̌����������Ƃ�������v����y�����Ƃ������A�u�S�[�X�g�d���ƈ���Đ���Ȃ��ɏ��������������ŏ�����v����y�����̂ł���B���܂�傫�Ȑ��ł͌����Ȃ����A����A����ȂɁu�����������Ɓv������킯����Ȃ����ȁB��i���ړI�����Ă���Ƃ����Ӗ��ŁA���́u���̓t�F�`�v�Ȃ̂�������Ȃ��B�Ȃ�ϑԂ���B
�@�T�b�J�[�̂ق��́A���������A�C�^���A�ƃX�y�C���̎c���������ϐ킵�Ă����B�E�G�X�g�u�����E�B�b�`�ɑ����ăt�B�I�����e�B�[�i�ƃ}�W�����J���c�������߁A���B�̎㏬�N���u���u�����v����ɓ��{�l����l���ق������Ȃ肻���ȍ������̍��ł���B�Ȃ�قǁA�L�����J�b�v�̘A�s�łƂ��Ƃ��W�[�R�W���p���̃o�J�d�L���r�ꂽ���Ǝv���Ă������A�v���C���[�������N���u�Ńc�L���ێ����Ă����킯�ł��ˁB�Ȃ�A�܂��C�P��B��v�ۂ��Ăב�v�ۂ��B�����O����A�O���[�v�Q�ʂ��炢�ɂ͎c���ł���͂����B
|
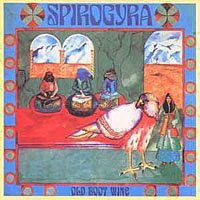
1. Dangerous Dave |
2005.05.27.Fri. 12: 40 p.m. BGM : SPIROGYRA "OLD BOOT WINE"
�@�������킳�킳�����n�߂�Ƃ��Ƃ����̂͘A���������N������̂Ȃ̂��A���̂��́A����܂ʼn��̖��������b�o�ł̕ҏW�҂���d�b�B���������Ŏ��̉c�Ɗ��������Ă��������Ă���t���[�ҏW�҂j���A���C�^�[��T���Ă����b�o�ł̂��m�荇���ɐ��E���Ă��ꂽ�̂ł���B�����Ȃ�d�������ꂽ�킯�ł͂Ȃ��A�Ƃ肠�����獇�킹�Ƃ������ƂŁA���T�A�ʒk�����邱�ƂɂȂ����B�u����܂łɏ��������̂������������Ă��Ă��������v�Ƃ̂��ƂŁA�ʒk�Ƃ������u�ʐځv�݂����Ȋ����B20��̍��́A���߂Ă̕ҏW�҂Ɖ�Ƃ��Ɏ����̎肪�����{�������Ă������Ƃ������������A���̍������������Ƃ����Ă��Ȃ������̂ŐV�N�ȋC�����B �@�����A�S�[�X�g�ŏ������{��l�Ɍ�����Ƃ��́A�����u����Ŏ��̉����킩��낤���v�Ƃ����s��������̂������ȂƂ���B�S�[�X�g���C�^�[�ɂ́A���҂̌����������Ƃ���ēۂݍ��ޗ���͂ƁA��������ʓI�ɓ`�B����\���͂����߂���Ǝ��͎v���Ă��邪�A�����̎����͊��������{�����������ł͂킩��Ȃ��B���ޗ��i��Ɍ��q�̑��L�^�j�Ɗ����i������ׂď��߂āA���̉ߒ��Ń��C�^�[���ǂꂾ���̗���͂ƍ\���͂����������킩��̂ł���B�d�オ��͓��������̍��i�W�{�ł��A���i���ߕs���Ȃ��p�ӂ���Ă���v�����f����v�}�ǂ���ɑg�ݗ��Ă�̂ƁA���@�����o���o���ȍ����i��̕�������Ă��邩�ǂ������킩��Ȃ���ԂŁj�g�ݗ��Ă�̂Ƃł́A�܂�œ�x���Ⴄ�̂Ɠ������ƁB�v����ɁA���̖{�Ń��C�^�[���ǂ�Ȗ������ʂ����������킩��̂́A�ꏏ�ɂ��̖{��������ҏW�҂ƒ��҂����Ƃ������Ƃ��B�����i���������l�ɂ킩��̂́A���������u�ӂ��ɕ��͂�������v�Ƃ������Ƃ��炢�ł��ˁB����Ōق����ǂ������߂�̂́A�u�ӂ��ɃX�g���C�N����������v�Ƃ��������Ńs�b�`���[�ƃv���_������Ԃ̂ƕς��Ȃ��悤�ȋC������B
�@�����Ƃ��A�n������i��ǂ�ł���ӌ��Ȃ芴�z�Ȃ�������Ă��ꂽ�ҏW�҂͂قƂ�ǂ��Ȃ��i��l�����Ȃ�������������Ȃ��j�̂ŁA���g���ᖡ���ė͗ʂ����ɂ߂����Ƃ������A�v�͂ӂ���̎d���Ԃ���G�c�ɔc�����Ĉ��S�������Ƃ������ƂȂ̂��낤����A���ۂ͂���Ȃɐ[���l����K�v�͂Ȃ��̂ł���B���̂ق����A���Ζʂ̕ҏW�҂Ɂu�ӂ���ǂ�Ȃ��d�����H�v�Ɛu�����ƁA���܂������ł��Ȃ��č��邱�Ƃ������i�ւ�������҂̖��O�����X���X���o�Ă��Ȃ��j�̂ŁA�����������Ă������ق����b�������B�����Ƙb�������̂́A�ߋ��Ɏ肪�����{�̃��X�g�𗚗�������Ɏ����Ă������Ƃ��B�Ȃ̂ŁA��邻������ăv�����g�A�E�g���Ă݂��B���łɊ��s���ꂽ���̂����ŁA105���B15�N������Ă�����ꂮ�炢�ɂ͂Ȃ�̂ŁA���ԓI�ɂ͑��������Ȃ����Ȃ������Ǝv�����A��������U��Ԃ��ăQ���i������ɂ͏\���ȗʂł���B�Ƃ��낪���ȂɌ�������A�u�ق�Ƃɏ����̂��D���Ȃ̂ˁv�ƌ���ꂽ�B���ƈӊO�ȃ��A�N�V�����ŁA�{�l�́u����ȊO�ɂł��邱�Ƃ��Ȃ��v�Ə����@�őI�d�����Ƃ����ӎ��ł����̂����A�����Ă݂�A�����������ƂȂ낤�Ǝv���B���̂Ƃ���Q���̈����邪�����̂́A�����ƁA������D���Ȃ��Ƃ��\���ɂ���Ă��Ȃ�����Ȃ̂��B�킵�Y���ƒP�s�{���d�Ȃ闈�����A�y���݂Ŏd�����Ȃ��B�y���݂Ŏd�����Ȃ��B�y���݂Ŏd�����Ȃ��B
|

1. Alba Mediterranea |
2005.05.26.Thu. 15: 50 p.m. BGM : ARTI & MESTIERI "ESTRAZIONI"
�@�Ƃ��낪�A�̂������炱�����̊��҂𗠐�W�J�B�L�b�N�I�t����Q�����o���Ȃ������Ƀ~�������搧���A�u�[���[���ło�j��v�Ƃ������i�Ƃ������S���E�j���v���`���Ă����Q�[���v�����͖��[���o�ɐ�����̂������B���x�����K�����Ƃ����v���Ȃ��K�E�Z�b�g�v���C���A���肪�܂��u���[�ƁA���ꂪ�X�^���ŁA���ꂪ�N���X�|�ˁB�c�c�Ӂ[��A����Ȃ�`�F���V�[�ɂ��������H�v�Ȃǂƃ}�[�L���O�̊w�K�ɗ��ł��闧���オ�葁�X�Ɏd�|�����s�����ƃ}���f�B�[�j�̍�폟�����B�b�k�ő��S�[���L�^�������ŁA����܂ł̋L�^�ێ��҂̓o�����V�A����̃����f�B�G�[�^���Ƃ����B�r���𗁂тėǂ������ˁA�K�C�X�J�N�B�L�~�͉��B�Q�ʂ̈̑�ȃt�b�g�{�[���[�Ȃ̂��ˁB �@�Ƃ����킯�ŁA�u�ق猩��A�ދ��Ȏ����ɂȂ�������Ȃ����v�Ƃ͌����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ł��邪�A���̌�A�`�F���V�[���~�����ɑ݂��Ă���Ă���N���X�|�i�����c�B�I�j�̘A���S�[����3-0�B�ف[�猩��A�����@�v�[���Ȃ����c��₪�邩��A����I�Ȏ����ɂȂ������������Ȃ����I�@���[�O�T�ʂ̃`�[�������ۂ��킫�܂����ɖ������邩��A�����������ƂɂȂ��Ȃ����I�@�v���~�A�̃c����������Ȃ����I �@�c�c�Ȃǂƌ������l��Ȃ���ϐ킵�Ă��������A���������N���ӂ߂��悤�B����A�ӂ߂��邩�B�ӂ߂����ȁB���߂�Ȃ����B�����ǁA�����ӂ邩��A�~�������ӂ�B���܂��牽���炵�Ƃ�˂�B���������A���̖��f�O�Z������ǂ����B���Ă��������c�B�I��ł����܂ɂ͖��f���Ă��������Ƃ����b�ɂ��Ȃ�킯�����A�㔼�A�W�F���[�h�A�X�~�`�F���A�V���r�E�A�����\�iPK�j�ł����Ƃ����Ԃ�3-3�ł���B�u�^�̃T�|�[�^�[�̓X�^���h�ł͂Ȃ��t�B�[���h�ɂ���v�����˂Ă���̎��̎��_�����A�w�b�h�łP�_�ڂ����߂��W�F���[�h�������Ȃ���藧�āA�V�����Ƃ��Ă����t�@����E�C�Â����V�[���́A�܂��ɂ���𗠕t������̂������B�������傤�A�������芴���������������Ȃ����B�����ʔ��������ɂȂ����܂�������Ȃ����B �@�ł��A���_�ɂȂ����r�[�ɁA�o���Ƃ��{���̃Q�[���v�������v���o�����炵���B60���ԂłU�_�Ƃ����S�[�����b�V�����E�\�̂悤�ɁA����ȍ~��60���Ԃ́u����ό����͂����łȂ�����v�ƌ�������̃[���[���ło�j��˓��B�����֔��A�Ƃ�����ł���B�ǂ��������ƁA�����@�v�[���ɂ͈�C�ɋt�]�܂ōU�߂����Ăق��������B�o�j��́A�f�j�f���f�N�̉��i�ȁu���˂��˃_���X�v�Ɍ��f���ꂽ�~�������~�X���d�˂āA�����@�v�[���̗D���B�f���f�N�C���������B���w�����l�������ȍ��ŁA���B�`�����v�����߂��ɂӂ��킵���s�ׂɂ͌����Ȃ������B�������܂��A����Ńo�[�N���[�E�C���O���b�V���E�v���~�A���[�O���������B�ō��̃��[�O�ł��邱�Ƃ��ؖ����ꂽ�킯���B���B�ō��̃��[�O�𐧂����`�[���������I�ȉ��B�i���o�[�����ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�`�F���V�[�����[�O��Ń����@�v�[���ɂQ�����Ă��邱�Ƃ܂ł́A���Ɍ��킹�Ȃ��łق����B
�@�b�͑O�シ�邪�A�䂤�ׂ����c�B�I�~�t�B�I�����e�B�[�i�i�Z���G��37�߁j���悤�₭�r�f�I�ϐ�B1-1�̃h���[�B���̌��ʂ͎��O�ɒm���Ă������A����ł��A�U�E���̐_�̎�f�B�t�F���X���܂߂ăn���n���i�����ăC���C���j�������鎎���������B����͐_�̎���Ă������A�܂��A�v����ɁA�肾���ǂˁB�ƂĂ�����ȃV���[�g�������̂ŁA�U�E����������܂��Ă��Ȃ����S�z���B�������Ɏ��Â���킯�ɂ����Ȃ��i�����ăn���h���o����j����A���̏ꍇ�͎蓖���x��ďǏ�������\��������B����Ȃ��Ƃ�S�z���Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��B���c�B�I������A�܂��c�������܂��Ă��Ȃ��炵���B���[�B�ŏI�߂Ŏc�������߂���A���������t�@�����t�B�[���h�ɂȂ��ꍞ��őI��𗇂ɂЂ�ނ����肷��낤���B�������~�i�̂ق����߂����Ɍ��܂��Ă��邪�A����͂���łƂĂ��߂������i�B
�@�A���e�B�E�G�E���X�e�B�G���́A�o�e�l�ƕ��я̂�����i���Ƃ�����j�C�^���A�̃v���O���o���h�ł���B���͂܂��A��\��Ƃ��ėL���ȁw�e�B���g�x�ƍ��������[�X���ꂽ���̐V���������������Ƃ��Ȃ����A���܂����X�������O�ȃt���[�W�����F�̋������t���J��L���Ȃ���A�ǂ������}���e�B�b�N�ȍ���Ƃ������A�Ȃ��Ƃ������A���D�Ƃ������A�l�ԂƐl���̊Ԃɂ���U���U�������ڐG�ʂ̎肴���Ƃ������A����Ȃ悤�ȏ��Y�킹��f�G�ȉ��y���B����Ȃ悤�ȏ��������͎̂�������������Ȃ��Ƃ��v�����A�Ƃɂ����A�܂��A�J�b�R�C�C��A���e�B�ƃ��X�e�B�G���B�u�A���e�B�v�Ɓu���X�e�B�G���v�����Ȃ̂��͒m��܂���B���Ԃ�l���ł͂Ȃ��Ǝv���B�����o�[�̒��ł́A�u����h���~���O�v�̃t���I�E�L���R��������L���炵���B�������ɁA�f�l���ɂ��u�葫�����{����낤�v�I�ȕ��������Ƃ�����Ă���悤�ɕ�������B�ŁA���̃X�S���l�������U���ɓ��{�Ń��C�u�����킯�����A����́u����30�N�ɂ��Ċ�Ղ̏������I�v���������B�����ǂ��u��Ձv�Ȃ̂��́A�悭�킩��Ȃ��B�u����̉Ȋw�Z�p�ł̓A���e�B�E�G�E���X�e�B�G���̗����͕s�\�v�Ƃł��v���Ă����̂��낤���B���邢�́A����ȃo���h�̌��������{�Ńr�W�l�X�ɂȂ邱�Ǝ��̂��u��Ձv�����ĈӖ��H�@�Ƃ�����A���̃r�W�l�X�𐬗������镨�D���̂ЂƂ�Ƃ��āA�N���u�`�b�^���łǂ�ȃ~���N�����N����̂����y���݂ɑ҂��Ƃɂ��悤�B
|
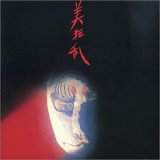
1.��d�l�i |
2005.05.25.Wed. 14: 55 p.m. BGM : ������ "������"
�@�ĂуV�M�[�Ƀ��[���𑗂�A��x�����������Ƃ�`������A�u�Ȃ�ΐV�h�������f�B�X�N���j�I���E�v���O�����֍s���ׂ��v�Ƃ̕ԐM�������̂ŁA������܂܂ɐV�h�ցB�����������̂�����̂����̒��ɂ́B���Ȃ݂Ɂu�v���O���فv�́u�v���O���₩���v�Ɠǂ݂����Ȃ�C�������킩��Ȃ��ł͂Ȃ����A�c�O�Ȃ���u�v���O������v�Ɠǂ݂܂��B���O�ɒn�}���`�F�b�N���Ă��Ȃ������̂ŁA�O�ɃV�M�[���狳������ꏊ���v���o���Ȃ���u�������̂ւ낤�v�ƃe�L�g�[�Ɍ��������Č����������̂́A�������s�̎�������ł��ǂ蒅����͂����Ȃ��A�ӂƋC�Â����Ƃ��ɂ̓f�B�X�N���j�I���E�N���V�b�N�ق̑O�ɗ����Ă����B�������s�Ȃ̂ł͂Ȃ��A���y���s�Ȃ̂�������Ȃ��B���傤���Ȃ��̂ł܂��V�M�[�Ƀ��[���ŏꏊ��₢���킹���̂����A���܍l����ƁA���Z�ȕҏW�҂̎��ς킹��O�ɁA�N���V�b�N�قɓ����ēX���Ɂu�v���O���ق͂ǂ��ł����v�Ɛu���ׂ��������悤�ȋC������B �@�M�����Ȃ����ƂɁA����Ƃ̂��ƂŔ��������v���O���ق͉c�Ƃ��Ă����B��s�̃P�[�X������̂ŁA�u���������܂��Ă�̂���`�v�Ίo�債�Ă����̂����A�������ɋx�݂����قǃv���O���ƊE���o�J����Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�t�ɂ����ƁA�������ɓX��߂₪���s�ƊE�́c�c����A��߂Ă������B���͋�s�����e�ɕ��������ő傫�����Ă�����������B �@�f�B�X�N���j�I���E�v���O���b�V�����b�N�ق́A���߂đ��ݓ��ꂽ�l�Ԃ��ْ��������Ԃ������B�����āA�Ȃɂ���v���O���قɂ́u�v���O������������v�Ȃ̂��B����ԃv���O���b�V���Ȃ̂��B����قǗ��������Ȃ���Ԃ��ق��ɂ��邾�낤���B�v���O���̂b�c�A�v���O���̃A�i���O�ՁA�v���O���̂a�f�l�A�����ƃv���O���D���ł���ɈႢ�Ȃ��X���A��Ƀv���O���D���ł���͂��̃v���O���ȕ��̂̋q�B���̂̒m��Ȃ��ЁX�����������āA������Ɠ����o�������C���ɂȂ������́A�v���O���ɑ��ĉ����Ό��ł������Ă���̂�������Ȃ��B �@�O���̃��X�g�����ňӖ��̂킩��Ȃ����j���[�߂Ă���Ƃ��̂悤�ȃw���Ȋ���e�̉��ɂ����Ȃ���A��������܂Ńv���O���b�V���ȒI�F�B�ړ��Ăɂ��Ă����u���W���̃o���h�̖��O���v���o�����Ƃ��ł����A�u��ăR�[�i�[�v�̑O�ł���ɗ�⊾���������B���������u�s�v���Ƃ������Ƃ����v���o���Ȃ��B�u�s�Ŏn�܂�u���W���̃o���h����܂����v�Ȃ�āA�v���O���b�V���ȓX���ɐu���Ȃ��B���Ȃ炻�ꂪ�u�e���v�X�E�t���[�W�b�g�v���Ɗy���Ŏv���o����̂����A���̂��͍Ō�܂Ŏv���o���Ȃ������B���ɍs�����Ƃ����A�v���o���鎩�M���Ȃ��B �@��ނɍs�����Ԃ������Ă����̂ŁA�Ƃ肠�����ڂɂ������̂��S���w���B�����̒��{�ɏ������������T���Ă���A���e�B�E�G�E���X�e�B�G���A�挎�w�X�g�����W�E�f�C�Y�x���œ��W���ꂽ������i�t���[�W��������Ȃ��ق��́j�X�p�C���W���C���A���{�̔������A�|�b�v�ȃL�������@���Ƃ����A���S�Ҋۏo���̊ό��q�I���C���i�b�v�ɂȂ��Ă��܂����B�t�B�����c�F�̃��X�g�����ŁA�J���p�b�`���ƃJ���{�i�[���ƃ~���m���J�c���c���I�[�_�[����悤�ȃI�m�{�����o�ł���B�ł��A�u�ꖜ�~�D�����肵�߂ăv���O�����X�֍s���v�͌��\�G�L�T�C�e�B���O�ȃc�A�[�����B �@���̌�A18������_�J���ŁA�����S�[�X�g����P�s�{�̌��q��ލŏI��B���̔��M�����vጂ̂��߂ɉ��щ��тɂȂ��Ă������̂ŁA����������f�������Ă��܂������A28�̒��҂��܂����vጂ�����Ă��Ȃ��Ƃ̂��ƂŁA����ȃ^�C�~���O�ʼn���Ă����Ȃ������̂��s�K���̍K���ł���B��̌��q�͒��鑤�������������Ă���̂Ńe���V�����������肪���Ȃ��̂����A���̂��͈ӊO�ƃm���̗ǂ���ނɂȂ�A�g����l�^��������������o�����̂ŗǂ������B���Ƃ́A����������ǂꂾ���c��܂����邩�������B
�@�s�[�^�[�E�o���J���~���������~���R�N���̊e���ɂ����k��L�����\�������Ă�������w����PLAYBOY�x�V�������ҏW������͂����B���{�őn��30���N�L�O���ł���B�n�����ꂽ1975�N�Ƃ����Ύ��͏��w�Z�T�N���ŁA����ȑO�Ɂw���v���x�����݂��Ȃ������Ƃ����̂́A������ƈӊO�ȋC������B�����ƌÂ��G���̂悤�ȋC�����Ă������A����͂܂�A���������Ŏv���Ă���ȏ�ɌÂ��l�Ԃ��Ƃ������Ƃ��B����ɂ��Ă��A���ʕt�^�u�n�����~�j�`���A�����Łv�͂��܂���悾�Ȃ��B�������W���P�b�c�݂����Ȋ��o�ł��ˁB�L�O���ׂ���P��PLAYBOY�C���^�r���[���A�f��X�^�[�ł��~���[�W�V�����ł���Ƃł��A�X���[�g�ł��Ȃ��A���˔����q�����i�R���~�����ŗL���Ȍx�����̌Y���j�������Ƃ����̂��V�u���B���̓`���Ɗi������C���^�r���[�y�[�W���A�������x�̓��C�^�[�Ƃ��ĒS�����Ă݂������̂ł��B
�@�������́A���̖��O����n�`�����`�����h�^�o�^��z�����Ă����̂����S�R�����������̂ł͂Ȃ��A�ƂĂ��@�ׂ��{���ʂȉ��t�ōD�������Ă�B�{�[�J���̐���̂������l�l���q�Ɏ��Ă���悤�ɕ�������̂͋C�̂������낤���B
|

1.Radio Song |
2005.05.24.Tue. 13: 15 p.m. BGM : R.E.M. "OUT OF TIME"
�@�ȉ��A���������̐g�ӎG�L���������Łi���s���j�B ���A�[�Z�i���~�}���`�F�X�^�[�t�i�e�`�t�����j�͂o�j��ŃA�[�Z�i���D���B�Ō�̂o�j�����߂����B�G���̑ԓx�Ɋ��������B���ꂾ���̏d�����Č��߂��ɂ�������炸�A�u�I�����I�����I�������߂��v�ƃn�V���M��邱�ƂȂ��A�����ɒ��Ԃ��ĂъāA��M�҃��[�}���̂Ƃ���삯������̂ł���B����Ȃӂ��ɐU�镑����L���v�e�������E�ɉ��l���邾�낤���B �����j���̓Z�K���̒a�����B�W�ɂȂ����B���̑O���̓y�j���́A�S�l�̑c����������ĉ���B���苍���̃`�[�Y���ɂ�ɂ����i�̃g�}�g�ρj�A������̃������[�h�A�̃N���[���E�X�p�Q�e�B�����B��������D�]�B�Ƃ�킯�z�E�������y�[�X�g�̃X�p�Q�e�B�́i�t�[�h�v���Z�b�T������j�ȒP�Ō����ڂ��������A���܂��B���V�s�����J���Ă���TOMATO & BASIL����Ɋ��ӁB �������i�a���������j�̓Z�K���̑�D���̎芪�����i�B����A���ŐH���߂��āA���̒��q�������B���M�Ɛ��vጂŘA���L�����Z�������M�^�[�̃��b�X�����߁X����̂ŁA�C�����Ȃ���B��x���邱�Ƃ͎O�x����Ƃ������B���������ƕK���u�ł��A�O�x�ڂ̐����Ƃ�������ˁv�ƌ����l�����邪�A����͂ƂĂ��T���������ƁB�Ƃ�����A���ȊǗ����܂߂ă~���[�W�V�����̔\�͂ł���B�X�e�[�W�͌��e�̒��ߐ�ƈ���đ҂��Ă���Ȃ��B �����̋G�߂ɒ���W���P�b�g���ꒅ�����Ȃ��A��ޓ��Ől�ɉ�Ƃ��ɂ������Ȃ��Ƃ͂������̂́A�������Ɉꒅ�ł͍���̂ŁA�������B���܂łȂ��ɑI�Ȃ��J�^�`�̗m�������A���K�l�������Ă���Ǝ������C�����邩��s�v�c���B���K�l�����������ƂŁA�ق�̂�����Ɛl�����V�����Ȃ����悤�ȋC���B�������A����𒅂Ă���Ƃ��̓��K�l���O���Ȃ������B ���o���Z���i�~�r�W�����A���i���[�K��37�߁j��3-3�̃h���[�B���_���𑈂��Ă���t�H�������͏c�����s�ɓ�������ă`�����X���[�N�����Ȃ��玩���łR���A�u�{�N�Ɍ��߂����Ă�`��v�ƃS�[���O�ɒ�����Ă����G�g�[�͕s���B���̎����̃r�f�I�́A�q���Ɂu�t�H���[�h�͂f�j�̑O�ɗ����Ă��邾������_���v�Ƌ�����Ƃ��̋��ނɂ���Ƃ����Ǝv���B ���q���̃T�b�J�[�Ƃ����A�Z�K���͓��j���̃~�j�Q�[���Ńo�[�X�f�B�E�S�[�����Q�������߂��炵���B�悤�₭�{�[����S�[���ւ̈ӗ~���萶���Ă����̂��낤���B���̖�͂߂��炵���u�ȂT�b�J�[�^�悵�ĂȂ��́H�v�ƃe���r�Ŏ��������������Ă����B����������ƃT�b�J�[���̂��̂ɑ���u�X�C�b�`�v���������̂�������Ȃ��B���܂��ܘ^�悵�Ă������̂��_���_���ȃ}�h���b�h�E�_�[�r�[�������̂ŁA�r���łR�l�Ƃ��Q�Ă��܂������B ���Q�Ă��܂����̂ŁA�������������p���Ă����̂Ƀ��c�B�I��͖����B���ʂ͒m���Ă��邪�A�܂��A���Ă��珑�����Ƃɂ��悤�B ���q�}�Ȑl�Ԃ͉������邩�킩��Ȃ����̂ŁA�䂤�ׂ͉��������������l�b�g�������y�Ƃ����Q�[�����_�E�����[�h���Ă���Ă݂��B�����͋�̕��ו��Ɠ���������m���Ă��邾���ŁA�Z�I���[�������F�ڂ킩��Ȃ��������A�₯�ɑ��肪�キ�i�f�l�ڂɌ��Ă��w�{�Ƃ����v���Ȃ��̂����ǂ��Ȃ낤���j�A�Q��ɂP��͏��Ă�B���Ă�Ɩʔ����̂ŁA���x����肽���Ȃ�B���发�Ƃ������Ă��܂������Ȑ����B�u�X�C�b�`�v�������̂��H
���Ƃ������A���������͏����Q�[���ł͂Ȃ��A�����Q�[����T���Ă��������B������肽���B�����͂Ȃ����ǁB����A�������Ȃ��Ă�����Ă������ƂɂȂ��Ă���킯�����B�\�����́B
|
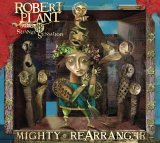
1.Another Tribe |
2005.05.20.Fri. 13: 40 p.m. BGM : ROBERT PLANT AND THE STRANGE SENSATION "MIGHTY REARRANGER"
�@�q�}�Ȃ̂ŁA������M�^�[�̗��K���肵�Ă���B���g���m�[���́u�{�[�i������v�����F�B�B���̂���l�ɉ�Ɓu�ǂꂮ�炢�e����悤�ɂȂ����̂��v�Ɛu����邱�Ƃ������̂����A��{�I�ɂ́u�e���Ȃ��v�̂����A�u�ǂ̂��炢�v�ƌ����Ă�����������̂Łu����A�܂��A�܂��S�R�A��������v�Ȃǂƌ��t������Ă���B���\����ɂ�Łw�ږ��̉́x�ƁwLiving Loving Maid�x�̗��K�͂��Ă���A�i�����Ēe���j������ۂ��y���炷���Ƃ͂ł��邩��A�c�ɂ̂����������₨�������������u�M�^�[�̒e����l�v�Ǝv����������Ȃ����A���ۂ͂܂��u�^�����v�̈���o�Ă��Ȃ��B�R�[�h�͐��m�ɉ��������Ă��Ȃ����A���Y���������������B����ȑO�ɁA�܂��܂��M�^�[��e�����߂̃t�B�W�J�����ł��Ă��Ȃ��B���̕I�Ǝ��������Ə_��ɂ��A���w�Ɩ�w�̃p���[�Ɖ��������߂Ȃ��ƁA������ƌ������������Ȃ��̂��B�Ƃ��Ƀn���}�����O�I���ƃv�����O�I�t�i�s�b�N���g�킸�A����̎w�Ō���@����������~�����肵�ĉ����o�����@�j�̏K���ɂ͋�J���Ă���B�Ȃ̂ō������A���ꎞ�Ԃ����ċg���̂��Ƃ��X�g�C�b�N�Ȋ�b���B�������犾�������܂ł��ƁA�悤�₭�I���M�^�[�ɓ����ł���B�����Ƃ��A���̍��ɂ͎w�悪�ɂ��Ȃ��Ă���A�x�e������Ȃ��̂���V�ȂƂ��낾�B�������A���K������������́u���Ԃ�v��������̂��y��̂����Ƃ���B�����Ȃ������w�������悤�ɂȂ�A�e���Ȃ������t���[�Y���܂���Ȃ�ɂ��e����悤�ɂȂ�ƁA���ꂾ���ōK���ȋC���ɂȂ��̂������B �@������肱�����Ă݂�ƁA�d�Ԃ̉^�]���s�@�̑��c���͂��߁A���̂Ƃ��됢�̒��ł́u�v���̃e�N�j�b�N�v���S�ʓI�Ƀ��x���_�E�����Ă���悤�Ȉ�ۂ�����A�����������Ƃ���ƁA����͒n���Ȕ������K���a���ɂ���Ă��邩��ł͂Ȃ����Ǝv��Ȃ��ł��Ȃ��B�e�N�m���W�[�̂������ŁA�������K���s�v�ɂȂ����ʂ����邾�낤�B�悭�m��Ȃ����A���ꂱ�����y���A�������K�Ȃ��ō��グ������̂������Ă���ɈႢ�Ȃ��B�e�N�m���W�[���l�Ԃ̃e�N�j�b�N������Ă����̂��Ƃ�����A�Ȃ����X�����B
�@���X�����Ƃ����A���܂���Ȃ���ؗ��h���}�ł���B�䂤�׃e���r���U�b�s���O���Ă���Ƃ��ɁA���߂Ėڂɂ����B�ق�̂R���Ԃقǂ��������A�A�^�}�ɂ��Ă���ȏ�͌��Ă��Ȃ������B�ǂ���A����Ȋ����Ȃ̂��B��u�Ŋw�|��x���Ƃ킩��؍��l�o�D�̎ŋ��͂������A���{�l�̐��D�������Ђǂ��d���Ԃ�B�܂��������A�o�D�̌��̓����Ɛ��D�̃Z���t���Y���܂����Ă���B�����������킹�悤�Ƃ����C���Ȃ����A�u���K�v�Ȃ��̂Ԃ����{�Ԃł���Ă���Ƃ����v���Ȃ��B�e�������ŁA���ߍׂ����d�������Ă���]�T���Ȃ��Ƃ������ƁH�@�O���A�j���݂����ȃZ���t���A�����Ă��Ēp���������B�o�D�̎ŋ����ŋ�������A����Ȃӂ��ɂ������悤���Ȃ��̂�������Ȃ��Ƃ��v�������A�܂��A�Ƃɂ������܂������E�ł���Ȃ��B����Ȃ��̂������ɂȂ��Ă���i�吨�̐l���ʔ����Ɗ����Ă���j�Ƃ������Ƃ́A�܂�A���x���_�E�����Ă���͓̂��{�l�S�ʂ��Ƃ������Ƃł��ˁB����ȃh���}�ɖ����ɂȂ��Ă����l�ɁA�K�L�̊w�͒ቺ��J���鎑�i������̂��H�@�Ȃ�Ƃ������A�u�����Ȃ���e�Ȃǂ��ł���낵���v�Ƃ������f�B�A�i�o�ŊE���܂߂Ăł����j�̌㉟���������āA���̒����g���f���Ȃ��u�n���X�p�C�����v�ɛƂ荞��ł���悤�Ɋ������Ďd�����Ȃ��B
�@����Ȃ��Ƃ��A���܂̓s�A�m�}������B�X�E�F�[�f���l�Ƃ��������������炵���̂ŁA�䂪�Ƃł͓��ʁu�A���f�V��������v�ƌĂ�ł��܂��B�����Ă�ł݂�ƁA�ӊO�ɃA���f�V�����Ȋ�Ɍ����邩��s�v�c���B �@����͐^�ۗT��́w��Ղ̐l�x���������A�L���r���̂ƂĂ��P�ǂȒj���A�����̓w�͂Ǝ��͂̎x���ɂ���ċL�������߂����r�[�A�������ƍߎ҂��������Ƃ�����Đ�]�̕��ɒ@�����܂��Ƃ����߂����������������̂��v���o����������邪�A������C�ɂȂ�̂́A�u���ԔG��̃X�[�c�p�ŊC�݂�f�r�v����n�܂�ނ̍s�����Ȃ�Ƃ��P�����ɖ����Ă��邱�Ƃł���B�ѕz�ɂ���܂����ʐ^�͂₯�Ƀ|�[�Y�����܂��Ă��邵�A�����Ă���ʐ^�͑厖�����ɕ����Ă���ܐ��������ɂ����Ƃ��B�e���Ă݂����̂��w�����̌x�ƃr�[�g���Y�́w�A�N���X�E�U�E���j�o�[�X�x���Ƃ����̂��A�E�P�_���̒ʑ�����������B����Ȃ��Ă������炢�͏����邾�낤�ɁA���Ɖ��M��n����ĊG�����`���Ȃ��Ƃ����̂��A�l���Ă݂�ƃt�U�P���b���B��������ăR�~���j�P�[�V���������₵�Ă����Ȃ���A�s�A�m�͊�X�Ƃ��āi���ǂ����m��Ȃ����j�����Ԃɂ킽���ĉ��t���Ă݂����Ƃ����̂�����A����́A�ӂ��A�u�l��n���ɂ��Ă���v�Ǝv���Ă��d�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�ق�Ƃ��ɋC�̓łȐl��������A���ł����ǂ��A�ŋ����������A�C�e�������������Ă��ċC����������Ȃ��B �@���������A�ނ��{���Ɂu�s�A�m�}���v�Ȃ̂��ǂ��������Ȃ��B�������Ƀs�A�m�̊G�͈ٗl�ɂ��܂����A��ʓI�ɂ̓s�A�m�̊G�Ȃ`���Ȃ��s�A�m�}���̂ق������|�I�ɑ����킯������A���t�������Ȃ��Ń��f�B�A���u�s�A�m�}���v�Ă�肵�A�s�A�j�X�g�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B���苭������̂͂ǂ����Ǝv���B����ɁA�ق�Ƃ��ɏ�肢�̂��Ƃ��Ă��A���ӂȂ̂��s�A�m�������Ƃ͌���Ȃ����낤�B�����Ƀ��X�|�[���Ƃ��n���Ă݂���A�����M�^�[�q�[���[��������Ȃ�����Ȃ����B�M���M���Ɂw�ږ��̉́x�Ƃ��e���n�߂邩������Ȃ�����Ȃ����B�����A�L�����������Ƃ��ɃM�^���X�g���Ǝv���Ă��炦�邮�炢�e�����炢���Ȃ��B
�@�����Ă���̂́A���o�[�g�E�v�����g�̐V��A���o���B���قNJ��҂��Ă��Ȃ��������������邩������Ȃ����A�v�����g�̓��m��ƃw���B�ȃ��b�N�E�T�E���h���S�n�悭�n�����킳�����A�Ȃ��Ȃ��̉��삾�Ǝv���B�v�����g�̐��́i����͂Ƃ������Ƃ��āj�F�C�������Ă��Ȃ����A�Ƃ�����W�����E�{�[�i���̂悤�ȃX�P�[���̑傫��������������Clive Deamer�Ƃ����h���}�[�������B�c�c�Ƃ�����ɁA�ǂ����Ă��c�F�b�y�����O��Œ�����Ă��܂��̂��h���Ƃ��낾�Ǝv���܂����B�܂��A���傤���Ȃ��B
|
|
| #29 | TOP | BACKNUMBER | FUKAGAWA | B.I.P. | GUEST BOOK | #31 | |
 |