
 |
| #30 | TOP | BACKNUMBER | FUKAGAWA | B.I.P. | GUEST BOOK | #32 |
|

1.Sea Song |
2005.06.14.Tue. 14: 15 p.m. BGM : Robert Wyatt "Rock Bottom"
|
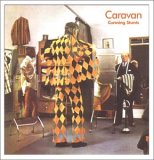
1. Show of Our Lives |
2005.06.13.Mon. 21: 15 p.m. BGM : CARAVAN "CUNNING STUNTS"
帰宅後は昼飯作りを担当。初めてミートソース・スパゲティをこしらえてみた。子供の頃、母親がよく作ってくれたミートソースに似た食感。なので決して不味くはないが、自分で期待していたようなものではなかったので、やや不完全燃焼である。『基本のイタリアン』とか何とかいう本のレシピどおりに作ったのだが、何かが足りない。まさに「基本」しかない感じ。基本は大事だが、基本だけではエンターテインメントにならない。料理も授業も。 その後、夕刻から白金台の都ホテル東京で、わしズム取材3本目。2本目もそうだったのだが、今回も3時間に及ぶ長い対談になった。テープを起こす愚妻も大変だが、おそらくは原稿用紙150枚分ぐらいになる内容を50枚にまとめる私も大変である。わしズムは「知的娯楽本」だから、基本に忠実にまとめるだけではいけない。エンターテインメントに仕上げるには、基本以外の何かが必要だ。もっとも、それ以前にライターの「基本」が何なのかよくわからないから困るのだが。
きのうの日曜日は、午後6時よりクラブチッタ川崎にて、アルティ・エ・メスティエリの来日公演を鑑賞。辞書で調べたところによると、「アルティ」は「芸術、技術(つまり英語のアート)」、「メスティエリ」は「熟練、職人(英語のマスターかな?)」といったような意味合いのイタリア語であるらしい。そこに込められた正確なニュアンスはわからないが、「技術と熟練」とでも訳せばいいだろうか。ただし演奏のほうは、最初から最後までフロントのサックスとバイオリンのピッチが合わないなど、バンド名を裏切ってくれた部分もあった。基本は大事だ。サックスとバイオリンは音色が似ているだけに、ユニゾンのフレーズで音程がズレていると猛烈にイライラしますね。ライブ・レコーディングだったようだが、大丈夫なんだろうか。あとは、途中から黒のスカート姿になって身をくねくね捩らせながら歌っていたヒゲ面のボーカリスト(むろん男・しかも中年太り)が気色悪かったです。とはいえ、フリオ・キリコのやたら手数の多いドラミングは凄まじかったし、私の好きな曲も演奏してくれたので、それなりに楽しかった。フリオ・キリコだけが男前(マルディーニとデル・ピエロを足して2で割ったぐらいかも)であるところを見ても、このバンドはひたすらドラムに注目するのが正しい聴き方かも。なにしろ「フリオ」だけに、マダムにモテモテって感じもなくはない。ともあれ、どういうわけか、80年代前半に新宿や六本木のピットインあたりで日本人のフュージョンを聴きながら感じた「ゴリ押しの熱気」を思い出すような2時間半だった。
ところで、クラブチッタ川崎では、10月にハットフィールド&ザ・ノースの初来日公演も行われるらしい。一体どうなってるんだろうか、この国は。ずっとバンドが存在していたのかどうかよく知らないが、それ、無理やり再結成させてないか? 「THE ROTTERS' CLUB CITTA' 川崎」というタイトルにも、どこか悪ノリ感がある。などと言いながら、ちょっと行ってみたくなっている自分がいるのだが。いま聴いているキャラヴァンのアルバムに、リチャード・シンクレアは参加していないのだが。キャラヴァンは、リチャード・シンクレアがいないときの作品のほうが好きだったりするのだが。だが。
|
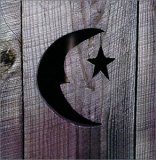
1.Farmhouse |
2005.06.10.Fri. 14: 10 p.m. BGM : Phish "Farmhouse"
眠い目をこすりながら出勤する途中、仕事場近くの自販機に千円札を入れて130円の飲み物を買ったら、釣り銭が370円しか出てこなかった。頭の中で何度も何度も計算してみたが、どう考えても500円足りない。まだちょっと寝惚けていたので、入れたのが500円札である可能性も捨てきれないが、岩倉具視を野口英世と見間違えるほど視力は落ちていないし、いまどき500円札を押し込まれて吐き出さない自販機もあるまい。なので、自販機に書かれている連絡先に電話をした。女声の留守番電話が「本日の営業時間は終了しております」と言った。わかるけど、朝8時半にこのメッセージはまずいのではないか。「ただいま営業時間外です」とでもしておけばいいだろうに。 あらためて10時すぎに電話をして事情を話したら、2時間後にはペプシのお兄さんが返金に来てくれた。意外に迅速な対応。よくわらないが、不具合の原因は井の頭通りの排気ガスであるらしい。自販機は排気ガスに弱いのであるか。たいがい屋外にあるのだから、かなり深刻な弱点である。500円玉を受け取りながら、「こういうのって証拠がないからアレですよね」と言ったら、「中の本数と金額を計算したら、500円余計に入ってましたから」とのこと。意外に厳格な仕事ぶり。架空請求は通用しないので、この日誌にヒントを得ておかしな真似をしないように。
しまった! 2回分の電話代を請求するのを忘れた!
こうしてウェブサイトをやっていると、見知らぬ読者からメールを頂戴することもあるので、「こんにちは!」とか「はじめまして!」とかいったタイトルのメールは、アドレスに見覚えがなくても念のため開いてみることが多い。もしかしたらスパムだと決めつけて読まずに捨ててしまったこともあるかもしれないが、どうか勘弁してください。ちなみに、外国語(近頃は中国語も増えましたね)のタイトルが書かれたメールは100パーセント読まずに捨てるので気をつけてくれ。ところで、きのうは「でっかいわ」というタイトルのメールが来た。アドレスに見覚えはないし、藪から棒にそんなことを言われても困るが、もしかしたら、見知らぬ読者が私の才能その他を評してそのような表現をしているのかもしれない。そんなこたぁねえよなと思いながらも開けてみたら、そこには短く「ひときわでっかい清原」とだけ書かれており、その下にケータイで撮影したと思しき清原の後ろ姿の写真が貼付されていた。これはスパムなのだろうか。それとも、この写真をどうしても私に見せたいと考えた読者からのお便りなのだろうか。判断に迷う。後者であっても少しも不思議はないという現状こそが問題だ。ちょっと面白かったからいいけど。次は、「ひときわでっかいイブラヒモビッチ」を頼む。
|
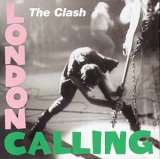
1.London Calling |
2005.06.08.Wed. 23: 30 p.m. BGM : THE CLASH "LONDON CALLING"
|

Disc 1 |
2005.06.07.Tue. 11: 00 a.m. BGM : PRINCE "SIGN OF THE TIMES"
しかしまあ、それでも昨今の情勢を見ればかなり多い(その半分以下の本もたくさんある)ので、仕方がない。それに、売れ筋のジャンルやシリーズや著者であっても、私のところに仕事が回ってきた頃にはブームが終わっているというのは、いつものことだ。私が終わらせているのではないかと疑いたくなるぐらいである。「売れ筋デストロイヤー」とでも呼ぶがいい。ツイていないといえばツイていないが、他力本願で「売れる企画を回せ」というのも虫がよすぎる話なので、そのへんはもう諦めている。文句があるなら、自分で企画してみろっちゅうことだ。 なので、名刺に「出版プロデューサー」とでも刷って各社に企画を持ち込んでみようかと思わなくもないのだが、私はプレゼンテーションというものがものすごく下手クソであるし、なにしろ売れ筋デストロイヤーなので、からっきし自信がない。徒労感ばかりが想像されて、始める前からウンザリしちゃうのだった。もっとも、相手が「売れる企画」ではなく「売りたくなる企画」を求めているのなら、話は少し違ってくるような気もする。「売れる企画があったら持ってきてね〜」と言う編集者は大勢いるが、「面白い企画があったら聞かせてください」と言う編集者には会ったことがない。
ゆうべは、アイルランド×イスラエル(W杯欧州予選)をビデオ観戦。ダフと平林君(テルアビブ在住の友人)の両方に義理があるので、どちらに肩入れするか迷っていたが、大胆予想のお好きな解説者が「この組はふつうにアイルランドが1位で抜けると思ってますけどね、ええ」と言い放つのを聞いて、心の底からイスラエルを応援することにした。敵の敵は味方である。べつに「敵」ってほどのことはないが、あの人の予想が外れれば外れるほど私はうれしい。だからウエストブロムウィッチのプレミア残留も最高にうれしかった。チェルシーのCL敗退も、そのおかげで少しだけ救われた気持ちになった。 ところが立ち上がり早々、イアン・ハートのFKでアイルランドが先制。大胆予想のお好きな解説者が試合前から「ハートの左足」と(言われなくたってサッカーファンなら誰もが注目することを)盛んに言っていたので、とても不愉快だった。ハートの左足だけは炸裂してほしくなかった。さらにロビー・キーンの器用なボレーシュートも決まって早い時間帯で2-0。大胆予想のお好きな解説者が「だけど3-0から勝てなかったチームもありますからね、イヒヒ」と言うのを聞いて、何をどう応援していいのかわからなくなってしまった。イスラエルが追いついても、あの人の「予想」が当たったことになってしまうからである。要するに、どう転んでも「ほらね」と言えるだけの布石を打っているのだ、あの人は。こうなると、いちいち気にするのもバカバカしい。 アウェイが苦手なのか、なんだか序盤はオロオロあたふたしていた感じのイスラエルだったが、20分を過ぎた頃から落ち着きを取り戻したようで、15番のアタッカー(ベナユン、だったかな)を中心にチャンスを作り始めた。あの15番は、ちょっと売人系のヤバイ風貌も印象的だし、ドリブルやフェイントのアクションが派手なのもいい。なかなかポップなフットボーラーである。で、その15番が蹴った鋭いFKを何者かが頭で巧みに叩き込んで2-1。さらにオシェイが与えたPKを何者かが(蹴り直しになったにもかかわらず)見事に決めて、イスラエルが前半のうちに追いついたのだった。けっこうビックリした。 後半は、イスラエルのゴール前を何度も何度も危険なクロスが横切り、そのたびに「やっぱダメか」と頭を抱えたものの、なぜかボールはゴールラインを越えることがなく、そのままドロー。決して「ファイン」ではないが、ヤケクソに手足を出してセーブしまくっていたGKの好守も光った。接触プレイのたびにのたうち回って時間を稼ぎ、大胆予想と紳士的なプレイがお好きな解説者の顰蹙を買っていたが、なに、気にすることはない。デュデクのくねくねダンスよりはよほどサッカーらしい振る舞いだし、イスラエルの試合を解説するのに「イスラエルの選手のことは知りません」と平然と言ってのける勉強のお嫌いな解説者よりはプロフェッショナルな仕事ぶりである。いずれにしろこのゲームは、ボコボコにされる可能性もあった試合で勝ち点1をむしり取った、イスラエルのミラクルな勝負強さを称賛すべきであろう。そして、試合前にはロイ・キーンとスティーヴン・カーの不在について「選手層が厚いから問題ない」と断言していたにもかかわらず、試合後は「キーンやカーのような精神的支柱がいなかったのが痛い」などと言う解説者がいたとしたら、その仕事を称賛することはできない。
先日、月刊PLAYBOYの座談会記事(この30年間の名盤30選)で撮影に使ったCDを編集部からお借りした。まあ、それぐらいの役得はあってよかろう。いま聴いているプリンスも、そのなかの一枚。いまごろプリンスを初めてまともに聴くというのは、一昨年ツェッペリンを初めて聴いたとき以上の恥じらいを感じるわけだが、これはもう完全に食わず嫌いというやつで、どうせ自分の耳には馴染まない音楽だろうと思い込んでいたのである。でも、いいじゃんコレ。最高じゃん。同じ座談会記事で取り上げられていたスティーヴィー・ワンダーの『キー・オブ・ライフ』に勝るとも劣らない充実度を誇る二枚組と言えよう。そういえばタイトルもちょっと似ている。
|

1.Songs From The Wood |
2005.06.06.Mon. 10: 25 a.m. BGM : JETHRO TULL "SONGS FROM THE WOOD"
土曜の朝にビデオで観たバーレーン×日本(W杯アジア予選)は、小笠原のゴールで0-1。先制点が入るまで文句ばっか言っていたので、どうして勝てたのかよくわからない。久しぶりに見たウナギ沢が、蒲焼きのような色合いになっているのがヤだった。足下にボールをもらってからしばし考え込まないと次のプレイに移れない左ウィングバックは、もっとヤ。将棋やってんじゃないんだから、とっとと走りやがれ。立ち止まるな振り向くな。
土曜の夜は、晩飯を担当。愚妻のリクエストに応じて、ホウレン草ペーストのスパゲティをまたこしらえる。加えて、ゆで豚のツナソースにチャレンジ。ツナソースにアンチョビを入れすぎて、やや塩辛くなってしまった。塩加減は難しいが、アンチョビ加減はもっと難しい。
クライファートがバレンシアへ。3年契約の1年目を終えたところなのに、移籍金が発生しないというのが物悲しい。世界最強の不発弾といったところだが、なにしろチェルシーをFAカップ敗退に追い込んだほどの男だ。まだ爆発力はある。フランスW杯以降、7年ほど眠っていた潜在能力が、そろそろ開花する頃ではないか。セミみたいだけど。1年後、ファン・ニステルローイを蹴落としてドイツのピッチに立ち、ロッベンとの華麗なコンビネーションを披露する姿が目に浮かぶようだ。永遠の希望的観測。でも、リバウドよりは可能性あるだろ。
ジェスロ・タルに「プログレっぽさ」より「フォーク風味」を期待している私にとって、この『神秘の森』はたまらない逸品である。最初から最後まで、タイトル&ジャケットが醸し出しているテイストを裏切らない音が聴けるのがうれしい。英国のトラディショナル・フォークを引用しながら作り上げたものだそうだが、隅から隅までジェスロ・タルの音楽になっている。音楽も料理も、「素材の味」を生かせばいいというものではない。イアン・アンダーソンの気高いイモ臭さを心ゆくまで堪能できる一枚。
|
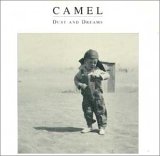
1. Dust Bowl |
2005.06.03.Fri. 11: 55 a.m. BGM : CAMEL "DUST AND DREAMS"
私たちの座席は、舞台に向かって左側の三階席。あれはテラス席というのかバルコニー席というのか何というのか知らないが、とにかく目の前に手すりのある席で、椅子に深く腰かけるとステージが半分しか見えない(身を乗り出しても下手側の司会者やピアニストが見えない)のがちょっと残念だったが、そのぶん、「見る」を諦めて「聴く」に集中できた面もある。出演者たちのトークは(話者の口元が見えないせいか)やや聞き取りづらいところもあったが、音楽はとても豊かに響いており、すべての歌い手が歌の言葉を一つ一つ丁寧に慈しんでいるように感じられたのが印象的だった。 なかでも白眉は、やはり『さとうきび畑』(補編曲はKay'n師匠)。新垣&森山のデュエットによる全曲演奏(約10分)は、弦楽カルテットによる美しい伴奏も含めてまさに鳥肌モノで、途中、三回ほど全身にゾクゾクッと電気が走るような戦慄を覚えた。もっと正直に告白すると、私、泣いちゃいました。ヤラレたよなぁ。もともと「父子モノ」に弱い私ではあるが、コンサートで落涙したのは初めてだよ。嗚咽を堪えるのが精一杯だったよ。代表戦の『君が代』をテレビで聴いたときもスゴイと思ったが、ナマで聴く森山良子の歌には、ほんとうに参った。降参。新垣勉という声楽家も、私はきのう初めてその存在を知ったが、その誠実な歌唱によって聴衆のハートを鷲掴みにしていたように思う。思い出トークがやや冗長になりがちな出演者もいる中で、寡黙な彼は、音楽を通して「自分が今この場所で歌っている理由」を雄弁に語っていた。 また、この音楽会は寺島尚彦という作曲家の「個展」でありながら、一方で谷川俊太郎という「作詞家」の作品集的な側面を持つ結果になったことも、似た名前を名乗っているフリーライターにとっては嬉しいところ。彼の詩に初めて曲をつけたのが故人だったそうだ。ゆうべのプログラムでは三分の一ぐらいを谷川作品が占めており、作詞家自身の歌も聴くことができた。決して上手くはないけれど味はあったし、「歌手じゃないのでアレですが」とか何とかいう言い訳や謙遜をせず、表現者としての責任を持って堂々と歌う姿がカッコよかった。 友人の演出するステージを鑑賞するのは初めての経験で、開演前は客席で無意味に緊張して手に汗をかいたりもしたが、トラブルに見舞われることもなく、おそらくは大部分の聴衆を満足させる形で終演して何よりである。コンサートで演出家がどのような役割を果たしているのか(あるいは、どのような役割を果たせないのか)素人の私にはよくわからないけれど、ひとつ、これは確実に演出家の手腕による成功だろうと感服したのは、オープニングの場面だった。開演が告げられ、場内の照明が落ち、暗闇の中で客席のざわめきが静まる。やがてステージに一本のスポットライトが当てられると、そこには客席に背を向けて立つ男性がひとり。何事かと思いきや、次にステージ後方の二階席に照明が浴びせられると、そこにはいつの間にか混声合唱団が陣取っており、背を向けた男はその指揮者だとわかるのだった。間髪を入れずに始まる美しい合唱曲。そういえば暗闇の時間がわりと長く、その間に合唱団が隠密行動で入場・整列していたわけだが、ちょっとしたマジックを見せられたような気分である。すべての聴衆が日常からスッパリと切り離され、ステージ上の別世界に支配された瞬間だった。シビれました。
ところで、初台の東京オペラシティに足を運んだのは初めてだったが、とても広々としているし、レストランなども数多くあって、なかなか快適かつ贅沢な気分にさせてくれる空間である。数あるショップの中でもとくにすばらしいのは、2階に入っているくまざわ書店だ。どうしてそんなことになっているのか皆目わからないが、入ってすぐの新刊コーナーの目立つ場所に集英社インターナショナルの「勝利学シリーズ」が4タイトルほど(新刊じゃないのに)並べられており、あろうことか拙著『キャプテン翼勝利学』が平積みになっていたのである。三年前の本が平積みというのは通常あり得ない(棚差しだって滅多に見ない)ことなので、ものすご〜くビックリした。W杯アジア予選が佳境を迎えているので勘違い需要を喚起しようという作戦かもしれないが、ありがとう、くまざわ書店。
|
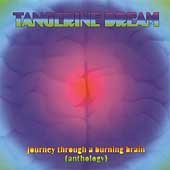
CD 1 |
2005.06.02.Thu. 11: 15 a.m. BGM : TANGERINE DREAM "JOURNEY THROUGH A BURNING BRAIN(ANTHOLOGY)"
欧州のシーズンも終わり、いよいよ花いちもんめの季節である。チェルシーとミランのあいだでは、クレスポとカラーゼの交換話が浮上しているようだ。クレスポの保有権を手放すのは惜しいが、いまさらプレミア復帰でもあるまいし、チェルシーは左SBが絶対に必要なので、まあ、悪くない話である。ただ、この話には不安もないわけではない。もしカラーゼ本人がチェルシー行きを渋ったりした場合、ミランが次に差し出す左SBは誰か。マルディーニであるわけがないじゃないか。うへえ。青いシャツを着たニクイあんちくしょうの姿を想像しただけで、頭がクラクラする。
3枚組1600円で売っているのを中古店で見つけ、何だかよく知らずに(それがドイツのバンドだということさえ知らずに)「安いじゃないか」と不純な動機で入手したのが、いま聴いているタンジェリン・ドリームである。あはは。なんで笑うのかよくわからない。70年から98年までの音源を収録したアンソロジー。初めて聴くタンジェリン・ドリームがコレというのは順番を間違えているような気がしなくもないが、何から聴いても印象は大して変わらんだろうという気もする。なんちゅうか、こう、ずーっと「鳴っている」音楽。怪しげな臨床心理士なんかが音楽療法とか称して聴かせたがりがちな音楽(もしくは「癒し」という言葉が大好きなわりに癒される必要があるほど疲れているとは決して思えないタイプの人たちが好みそうな音楽)とでも言えば、知らない人でも何となく想像がつくだろうか。はてなダイアリーの「タンジェリン・ドリームとは」によれば「初期は前衛音楽、中期はシンセサイザー音楽、現在はアンビエントテクノ」とのことで、「シンセサイザー音楽」って何のことだかよくわからないが、要は「70年代は難解で退屈だったけど80年代中盤以降はわりと聴きやすい」ぐらいに解釈すればいいのかもしれない。実際そんな感じ。と、なんとなくネガティブな感じの言葉を並べているように思われるかもしれないが、これが意外に聴かせるのだった。BGM向きのようでありながら、聴き手の背中を指先でつついて振り向かせようとする「引っかかり」のようなものがある。W杯もあることだし、今後はドイツ方面にも手を伸ばしてみようかしら。先日シギーに「美狂乱にまで手を出し始めると泥沼だよな」と言われたばかりなのでアレだが、まあ、毒を食らわば皿まで、である。
……そうだ。W杯の出場国が決まったら、火曜日じゃない日に目白のワールドディスクに行って、各国のプログレを一枚ずつ買うことにしよう。エクアドルやセルビア・モンテネグロにだって、きっとプログレはあるはずだ。イランやコートジボワールにあるかどうかはわからんが。
|
|
| #30 | TOP | BACKNUMBER | FUKAGAWA | B.I.P. | GUEST BOOK | #32 | |
 |