
ディスク: 1
1.Mellon Collie and the Infinite Sadness
2.Tonight, Tonight
3.Jellybelly
4.Zero
5.Here Is No Why
6.Bullet With Butterfly Wings
7.To Forgive
8.An Ode to No One
9.Love
10.Cupid de Locke
11.Galapogos
12.Muzzle
13.Porcelina of the Vast Oceans
14.Take Me Down
ディスク: 2
1.Where Boys Fear to Tread
2.Bodies
3.Thirty-Three
4.In the Arms of Sleep
5.1979
6.Tales of a Scorched Earth
7.Thru the Eyes of Ruby
8.Stumbleine
9.X.Y.U.
10.We Only Come Out at Night
11.Beautiful
12.Lily (My One and Only)
13.By Starlight
14.Farewell and Goodnight
|
2005.07.07.Thu.
11 : 30 a.m.
BGM : The Smashing Pumpkins "Mellon Collie and the Infinitie Sadness"
ゆうべ友人がゲストブックに書き込んでくれたところによれば、試験前夜にディープ・パープルの『ハイウェイスター』を聴くと、「マシン・ヘッド状態」になって勉強の能率が上がるような気がするらしい。だとすれば、これから夕方までに原稿を20枚ばかり書かなければならない私にとって、仕事しながら何を聴くかは切実なモンダイだ。うっかりイエスなんか聴いて、頭が「危機状態」や「こわれもの状態」になってしまったらえらいことである。イエスはダメだ。ダメよダメダメ、ダメなのよ。むろん、ピンク・フロイドの『ダーク・サイド・オブ・ザ・ムーン』も邦題的にまずい。そんなことになったらどうしてくれるんだよ。一体だれが責任取ってくれるんだよ。ついでに言えば、エマーソン・レイク・アンド・パーマーの『恐怖の頭脳改革』なんか論外なんだよ。どっか行っててくれよ。それに対して、Tレックスで「電気の武者状態」になるという作戦はわりとアリかもしれないという気もしたが、どうも意味がよくわからないといえばわからない。そんな状態になって原稿が書けるなら苦労しねえんだよバカ野郎。ふざけてんのかよおまえ。そして、もっとわからないのはグレイトフル・デッドだ。「アオクソモクソア状態」ってなんだ。ちょっとその状態になってみたい衝動も感じるが、それは今ではないほうがいいような気がする。間違って「アホクサヤケクソ状態」になっても困るしね。そこで、さっき試しに矢野顕子を聴いて「オーエス オーエス状態」にしてみたのだが、これなら励まされて頑張れるかと思いきや、かえって力が抜けるのだった。聴く者を脱力させたら矢野顕子の右に出る者はいないかも。しかも、このアルバムの場合、あろうことかラーメンまで食いたくなるじゃないか。ラーメン食ってる場合じゃないじゃないか。そんなわけで、七夕も意識しながら最終的に選んだのが、このスマッシング・パンプキンズの二枚組である。「メロンコリーそして終りのない悲しみ状態」だ。どうだ参ったか。参りました。これ聴く前から、とっくにその状態だったじゃないか。ところでメロンコリーってなんだ。
|
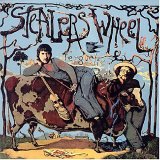
1.Good Businessman
2.Star
3.Wheelin'
4.Waltz (You Know It Makes Sense)
5.What More Could You Want
6.Over My Head
7.Blind Faith
8.Nothing's Gonna Change My Mind
9.Steamboat Row
10.Back on My Feet Again
11.Who Cares
12.Everything Will Turn Out Fine
|
2005.07.06.Wed.
14 : 50 p.m.
BGM : Stealers Wheel "Ferguslie Park"
いま聴いているスティーラーズ・ホイールとはまったく関係ない話だが、きのうゴダイゴのことを書いてから気になってAmazonで調べてみたところ、中学時代の私が下校途中に見知らぬ家の窓越しに聴いたのは、『DEAD END』というアルバムではないかという気がしてきた。たぶん、そうだ。発表されたのは1977年で、ちょうど私が中学生になった年だし、「70年代初めに流行していたハードロックのサウンド」「ゴダイゴのアルバムの中で最もロック色が強く、歌詞もその後のそれとは一線を画し、観念的で重いテーマが多い」といったカスタマーレビューの言葉も、あの日、私が受けた印象と合致している。世にAmazonのカスタマーレビューほどアテにならないものも少ないが、ときどき素晴らしいことを書いている人もいるのだし、これにはピンと来るものがある。いまも私の耳の奥に残っている音像には、なんというか、「苦悩」とか「失望」といったようなものが漂っているのである。ああ、やっぱり聴いてみたい。28年前のあの日の気分にはなれないだろうが、そうでなくとも、あれは私にとって価値のある音楽であるはずだ。少なくともそのアルバムタイトルは、原稿が最後の追い込み段階に突入しているにもかかわらず完全に煮詰まっている今の私の気分にぴったりだよ。本当ははっぴいえんどじゃなくてデッド・エンドなんだよ。参ってるんだよ。ひどい衰弱ぶりだよ。一方、スティーラーズ・ホイールはとってもポップでスムースなロックなのだった。悪くない。でも私はデッド・エンド。
|
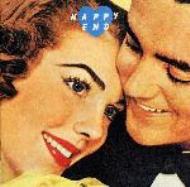
1.風来坊
2.氷雨月のスケッチ
3.明日あたりはきっと春
4.無風状態
5.さよなら通り3番地
6.相合傘
7.田舎道
8.外はいい天気
9.さよならアメリカ さよならニッポン
|
2005.07.05.Tue.
14 : 40 p.m.
BGM : はっぴいえんど "HAPPY END"
ゆうべ、仕事場から家に帰る途中、傘をさして薄暗い路地を歩いていたときに、通りがかりの古いアパートの2階から聞こえてきたのが、はっぴいえんどの『風来坊』であった。前にも同じことを書いた覚えがあるが、どうして、見知らぬ他人の部屋の窓から流れてくる音楽は、ああも魅力的に聞こえるのだろうか。私がそれに初めて気づいたのは、中学生時代、学校からの帰り道に、やや離れた家の開け放たれた窓から流れてくる、ゴダイゴの曲を耳にしたときだった。知らない曲だったし、まだゴダイゴが『ガンダーラ』やら『銀河鉄道999』やらでブレイクする前だったと思うが、なぜかそれがゴダイゴだということはすぐにわかった。とても印象的な曲だった。しかし、私がその曲を聴いたのはそれが最後だ。ベスト盤は持っているがそれに入るようなヒット曲ではないし、なにしろ曲名がわからないので探しようがない。聴けば絶対に「これだ」とわかる自信があるので、片っ端からゴダイゴのアルバムを聴けば見つかるのだろうが、それも面倒だ。それに、たとえ見つけて聴いたとしても、あの日の午後、学校近くの畑に反射する西日に目を細めながら、あの曲を耳にしたときのような気持ちには、きっとなれない。いま聴いている『風来坊』も、ゆうべの『風来坊』とはまったく違うものだ。なぜだかわからないが、他人の窓から聞こえる音楽には何か特別な力がある。しかも、その発信源は、人の生活している部屋でなければいけない。店舗から漏れ聞こえるBGMではダメだ。その窓の向こうに、その音楽を自分の意思で選んだ人がいるということが重要なのかもしれない。ブラウザのウィンドウからは音が流れていかないのが残念だ。
|
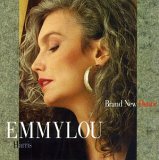
1.Wheels of Love
2.Tougher Than the Rest
3.In His World
4.Sweet Dreams of You
5.Easy for You to Say
6.Rollin' and Ramblin' (The Death of Hank Williams)
7.Better Off Without You
8.Never Be Anyone Else But You
9.Brand New Dance
10.Red Red Rose
|
2005.07.04.Mon.
19 : 40 p.m.
BGM : Emmylou Harris "Brand New Dance"
デパートの1階を歩いているような気分になる写真だが、これは高級化粧品の無駄に紙質の良いカタログやパンフレットの類ではなく、エミルー・ハリスというカントリー・シンガーのCDである。あの名盤『欲望』でボブ・ディランと共演したことで有名な人ですね。世間的にはどうだか知らないが、私にとってはそれで有名。
それにしても、これほど中身の音楽とミスマッチなジャケットもめずらしい。カントリー・ミュージックのサウンドと合わないという以前に、なかに音楽が入っているように見えない。「音」よりも「匂い」を感じさせるパッケージである。石鹸の詰め合わせだったとしても驚かないと思う。「EMMYLOU」の文字が「エメロン」に見えてきたりなんかして。
キャラクター的には、ちょっとヒラリーさんを想起させるものもある。どこか攻撃的な横顔だ。いや〜ん、お願いだからレストランで回し蹴りはしないで〜ん。と、それはまた別の人の話だったが、ともあれ、かつて映画『ラスト・ワルツ』でザ・バンドと一緒に『Evangeline』という曲を歌っていた可憐な娘さんが、ほんの15年程度でこんなにゴージャスなセレブに変身してしまうのだから女はオソロシイ。「ゴージャスなセレブ」というノータリンな表現はどうにかならんのかとも思うが、それは今後の課題にするとして、女の子の行く末というのはわからないものだ。もしセガレが女だったらと思うと、ドキドキしてしまう。「セガレが女」ってことはないか。その場合はセガレではなくムスメだ。セガレでヨカッタ。
でもね、外見は変わってもムスメさんの魂は変わってないから心配しなくていいよ、お父さん。ツンとおすましした歌は歌ってないから大丈夫。何がどうということもない当たり前な感じの音楽なのに、どうしてこんなに何度も聴きたくなるんだろう。
|
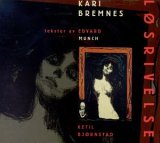
1. 月の力
2. 君の眼
3. 夢遊病者
4. 病気の子供
5. 叫び
6. マドンナ
7. 魅惑
8. なきがら
9. 世界という空間での出会い
10. 森の中の1シーン
11. ふたり
12. ジェラシー
13. 別離
14. メランコリー
15. 怒り
|
2005.07.03.Sun.
20 : 15 p.m.
BGM : Kari Bremnes "Losrivelse(別離〜エドヴァルド・ムンク画集メモより〜)"
カリ・ブレムネスはノルウェイ人のシンガーソングライターである。なにしろソルスキアとスールシャールの国なので、表記が「カリ・ブレムネス」でいいのかどうか怪しいところだ。たとえ「ケーリャ・ビリャーミニスデヤンス」だったとしても私は驚かないでやんす。これは彼女がムンクの絵を下敷きにしてこしらえたコンセプト・アルバムだ。最初にシギーから借りたときはそうとは知らず、ナニ人なのかもわからないまま、隅から隅まで意味不明な輸入盤のジャケットを茫然と眺めながら聴いていた。なんとなく、そのときのほうが謎めいていて面白かったような気がする。「ノルウェイ人でムンク」「5曲目は『叫び』がテーマ」などと知った瞬間に、神秘の霧がスカッと晴れてしまった。とはいえ、好きな音楽であることに変わりはない。二ヶ月に一度ぐらい、ふと思い出して聴きたくなるアルバム。ちなみにタイトルの「Losrivelse」の「o」は、ほんとうは斜線が一本入った団子みたいな文字です。

ギターを練習していて困るのは、ときどき途中で咽(む)せて咳き込んでしまうことだ。咳をしては弾けぬ。なんで咽せてしまうんだろうと考えてみたところ、どうやら私はギターを弾くときにちゃんと呼吸をしていないようだ。ずっと管楽器しかやったことがなかったから、演奏中に自由に息を吸ったり吐いたりしてかまわないという状況にうまく馴染めず、呼吸の仕方がわからなくなるのかもしれない。それってアタマ悪いかも。そう思って、ためしに管楽器を吹いているつもりでフレーズの合間に意識的にブレスをしてみたら、さらに激しく咽せてえらいことになった。それってバカなのかも。ふつう、ギタリストはどういうふうに呼吸をしているのだろうか。そんなことは考えたこともないのか。
|

1.You Can All Join In [Stereo Single Mix]
2.Pearly Queen
3.Don't Be Sad
4.Who Knows What Tomorrow May Bring
5.Feelin' Alright
6.Vagabond Virgin
7.Forty Thousand Headmen
8.Cryin' to Be Heard
9.No Time to Live
10.Means to an End
11.You Can All Join In [Mono Single Mix] [*]
12.Feelin' Alright [Mono Single Mix] [*]
13.Withering Tree [Stereo Single Mix][*]
|
2005.07.02.Sat.
11 : 15 a.m.
BGM : Traffic "Traffic"
きのう訃報が流れた元ヤマト運輸社長の小倉昌男さんには、2年ほど前に、仕事でたしか4回、お目にかかってお話をうかがったことがある。官と正面から闘ったこともあって、メディアでは頑固で攻撃的な人物として描かれることが多く、ちょっとおっかない方だろうと内心ビクビクしながら銀座のオフィスに行った。しかし、すでにビジネスの第一線から退かれていたせいもあるのか、とても柔和で朗らかな方だったので安心した記憶がある。盛んに「僕は気が弱くていつも困っている」とおっしゃっていた。そして、物事をとても論理的に考えておられるのが印象的だった。もしかしたら、経営者ではなく科学者になっても大成なさったのではないかと思うぐらい、ロジックを大切にされる方だった。たかだか7〜8時間程度のつき合いしかない人間がこんなことを言うのも何だが、だからこそ官の理屈に合わないやり方が許せなかったのではないだろうか。だとしたら、それは「頑固」とか「反骨精神」とかいったものとは、ちょっと違うものだ。もちろん「ハート」の強さもご本人が謙遜なさるようなものではなかっただろうけれど、それよりも「頭で考える力」の強さが際立つ人物だった。と、そんなことを考えていた昨日の夕刻、仕事の資料がクロネコヤマトの宅急便で届いた。伝票に印鑑を押し、「どうもありがとう」と言いながら、いつもより深く頭を下げた。

先日、セガレが楽しみにしていたプールの授業が中止になった。2年生を担任している男性教師が5〜6年生の移動教室に同行するためだという。その教師がいないと移動教室ができないというのは不思議な話だし、その教師がいないとプールの授業ができないというのも不思議な話だ。理屈に合わない。「その先生がいないとキャンプファイヤーができない」といった話なら理解できるが、プールの授業や移動教室はそういう特別な(やってもやらなくてもいい)イベントではなく、どの教師にとっても「できて当たり前」のルーティンワークであろう。2年生、5年生、6年生の担任集団すべてが、プロとしての力量を疑われても仕方あるまい。その教師が異動で転任したらどうするつもりなんだろうか。べつにプールの授業が一回なくなるぐらいどうでもいいが、表向きはもっと無難な理由を掲げておけばいいのになぁと思う。こんな恥ずかしい理由を臆面もなく公表する神経が理解できない。
|

1.Francine
2.Just Got Paid
3.Mushmouth Shoutin'
4.Ko Ko Blue
5.Chevrolet
6.Apologies to Pearly
7.Bar-B-Q
8.Sure Got Cold After the Rain Fell
9.Whiskey'n Mama
10.Down Brownie
|
2005.07.01.Fri.
10 : 00 a.m.
BGM : ZZ TOP "RIO GRANDE MUD"
7月だ。7月かよ。7月だよ。7月かー。体内カレンダーはまだ6月なのになぁ。などと思いながら出勤して留守電を再生したら、7月アタマから着手する予定だった仕事の担当者から「資料を送りました」というメッセージが入っていた。送ったかー。届くのかー。届いてもなぁ。なんか、こう、どんどん食欲がなくなっていく今日この頃だ。私は体温が39度あっても食欲だけはなくならない男なのに、今朝はめずらしく朝めしを食う気にならなかった。こういうときは、ZZトップだよ。ZZトップほど食欲を刺激するロックはないよ。と思って聴いているのだが、たしかに粗挽き胡椒のたっぷりかかったステーキの焼ける匂いなど思い浮かぶものの、食いたくはない。しかし、ガッツはちょっぴり注入された。がしがし書くべし。

ジャンフランコ・ゾラが引退を表明したらしい。残念だが、もう十分だろうという気もする。もう十分だろうという気がするほどのベテランが自分より2つも年下だというのは恐るべきことだが、ともかく、私はゾラが好きだった。だいたい、名前がカッコイイよな。なにしろ「ジャンフランコ」で「ゾラ」だもんな。すごく謎めいていて魅力的。セガレに買い与えたチェルシーのユニフォームも、背中には「ZOLA 25」の文字が入っているぐらいだ。ゾラがいなかったら、たぶんチェルシーファンにはなっていなかったと思う。99-00シーズンの開幕戦(対サンダーランド)でポジェのゴールをアシストした美しいループパスの軌道を、私は一生忘れたくない。そして、敵のFK時に彼がル・ソーやデニス・ワイズと並んで作った小さな「壁」のケナゲさも。フィールドに立っているだけで見る者を幸福な気分にさせる稀有なプレイヤーだった。どうもありがとうございました。ところでポジェは今どこで何をしてるんだ?
|
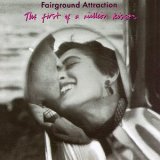
1.Smile in a Whisper
2.Perfect
3.Moon on the Rain
4.Find My Love
5.Fairground Attraction
6.Wind Knows My Name
7.Clare
8.Comedy Waltz
9.Moon Is Mine
10.Station Street
11.Whispers
12.Allelujah
13.Falling Backwards
14.Mythology
|
2005.06.30.Thu.
9 : 35 a.m.
BGM : Fairground Attraction "The First of a Million Kisses"
久しぶりに、愚妻から寝言を指摘された。
睡眠中の私が吐いたのは、こんなセリフだ。
「連番ってのがキツイよなー」
なんでしょうか。私はなんの夢を見ていたのであるか。「連番」といえば宝くじ用語である。宝くじを買う趣味はないが、だからといって宝くじの夢を見ないというものでもあるまい。先日も私は、ふだん野球を見ないし横浜ファンでもないのに、ベイスターズがリーグ優勝を果たした夢を見たぐらいだ。ものすごく驚いた。夢は日常と無関係に立ち現れる。だから宝くじの夢を見た可能性はあるのだが、しかし連番が「キツイ」とはどういうことだ。わからない。宝くじとは関係ないのかもしれない。ひょっとして「れんばん」ではなく「レイバン」の聞き違いか? ゆうべ、レイバンのPR記事を書くのに必要な資料がファックスで届き、その文字が読みにくいので拡大したものを再送してもらったりしたので、レイバンの夢なら見そうだ。〆切もけっこう「キツイ」しね。夢は日常との関係性の中で立ち現れることもある。じっさい、私はしばしば夢の中で原稿を書いている。悪夢としか言いようがない。だが、「連番」と「レイバン」を人は聞き違えるものだろうか。字面は似ているが、アクセントの位置が違いすぎる。やはり「連番」だったのか。ことによると、神様のお告げだったのかもしれない。連番はキツイから「バラで買え」ということだ。うむ。きっとそうだそうに違いない。こんどバラで買ってみよう。そして、もういちど夢を見よう。

ここ数日、8時出勤→仕事→18時帰宅→シャワー→晩飯→19時半出勤→仕事→24時帰宅→シャワー→就寝→7時半起床という、とても規則正しい生活を送っている。なんて健康的な毎日なんだろう。不規則な生活というのは体に悪いからね。こうして規則正しく1日2度の出勤を続けていると、ほんとうに気持ちがいい。目がしょぼしょぼして肩が凝って腰が痛いなんて、まるでウソのようだ。まるでウソのようだ。まるでウソのようだ。
|

1. Franny
2. Put a Little Love in My Soul
3. Stone Cottage
4. Speak Your Mind
5. Back Down Home
6. Good Times
7. Baby I Love You
8. Baby Like You
9. Before I Go
10. Don't Let the Sun Go Down
|
2005.06.29.Wed.
10 : 40 a.m.
BGM : Marc Benno "Minnows(雑魚)"
夏だ!と思ったらいきなり梅雨に逆戻りしたようだが、小学校ではプールの授業が始まっている。セガレはきのうが最初だったらしい。まだ泳げないので、ちょっと前まで憂鬱そうにしていたのだが、先日の日曜日に母親と高井戸の区民プールに行って練習し、バタ足で5メートルほど進めるようになったら、とたんに「学校のプールが楽しみだぁ」と言い出すのだからわかりやすい男である。そんな気持ちになるぐらい、早いうちから「泳げる子」が多いということなんだろう。じっさい、3歳とか4歳のうちから子供を「スイミング」に通わせる親はものすごく多い。なんで「水泳」ではなく「スイミング」なのかがよくわからないし、なんでこんなにマイナーな競技が幼児の世界だけで超メジャーなのかもわからない。まるで、「泳ぐ」という能力が、読み書きソロバン並みに重要であるかのようだ。「小学校に入る前に泳げるようにさせないと」と考えている親も多いと聞く。どういうことなのか、うまく理解できない。セガレは2年生でようやくバタ足だが、まあ、あと1年か2年すればクロールでがしがし泳いでいるだろう。それで「遅い」という理由は何ひとつないと思うのである。それに、就学前に泳げる子供が多い反面、運動会などを見ていると、まともなフォームで走れない子供が多い。つまり、「泳げるのに走れない子供」がたくさんいるということだと思う。優先順位がおかしくはないか。泳ぎも走りも苦手な子の親に、そんなことを言われたくはないだろうけど。

ついでに言うと、セガレは親に似て鉄棒も苦手。だけど、逆上がりなんて、泳ぎ以上にどうでもいいスキルだと思いませんか。いったい誰が考え出したんだ。逆上がり。学校で教える必要あんのか。しかも、こんな大袈裟な練習用具まで開発しやがって。近頃はこんなモノにまで税金が使われているのだ! 諸君! 身のまわりの逆上がりに注意されたし! ゆとり教育で授業時間が足りないというなら、まず逆上がりをやめろ。あんなもの、やりたい奴だけ公園で練習してりゃいい。

名前を聞いたこともなかったアーティストのCDをAmazonに勧められるまま購入し、それが思ったよりも心地よい音楽だったりすると、とても得をした気分になれる。エエなぁ、マーク・ベノ。『雑魚』というやさぐれた雰囲気の邦題から、なぜか長渕剛みたいなテイストを想像しておったのだが、これはそういうものではありません。いわゆるひとつのスワンプ・ロックである。もともとはレオン・ラッセルとコンビを組んでデビューした人であるらしい。レオン・ラッセルのような球威はないけれど、上品で、素朴で、滋味にあふれた音楽。料理評論家なら、「素材の味をギリギリまで生かしつつも職人の技を感じさせる和のミニマリズム」などと表現するかもしれない。「和」じゃないけどね。でも、マーク・ベノの音楽はどこか「和」な感じがする。奥ゆかしさ、だろうか。
|

1.Brass in Pocket
2.Message of Love
3.Don't Get Me Wrong
4.Kid
5.Human
6.I Go to Sleep
7.Forever Young
8.I Got You Babe
9.Night in My Veins
10.Spiritual High (State of Independance)
11.Talk of the Town
12.Stop Your Sobbing
13.Hymn to Her
14.2000 Miles
15.Breakfast in Bed
16.Popstar
17.Middle of the Road
18.Thin Line Between Love and Hate
19.Back on the Chain Gang
20.I'll Stand by You
|
2005.06.28.Tue.
11 : 25 a.m.
BGM : The Pretenders "Greatest Hits"
新シーズンということで、ちょっとだけ衣替え。

久我山駅前の小さなレコード屋さんが店を畳んだ。私がそこで『サンボマスターは君に語りかける』を買ったのはほんの2ヶ月ほど前だったと思うが、焼け石に水だったようだ。気の毒なことをした。こんなことなら、もっとあそこでCDを買ってあげればよかった。たぶん、久我山で暮らし始めてからの8年間で、合計1万5千円ぐらいしか売り上げに貢献していない。これだけ音楽に金を使っている人間でさえそんなモンなんだから、店やってけるわけないよなぁ。井の頭線の急行に乗れば、一駅でタワーレコードやらHMVやら複数の新星堂やらが割拠している街に行けるんだもんなぁ。いつも暇そうに店番をしていたおじさん、これからどうするんだろうか。完全無欠の他人事ながら、なんだか心配だ。店名どおり、おじさんが何らかの形で元気よく復活することを祈っておこう。さらば、フェニックス・レコード。

ゆうべ仕事場で探し物をしていたら、机の引き出しの奥から驚くべきものが出てきた。大学1年生のときのクラス名簿である。各自が手書きした原稿をコピーしてホチキスで留めただけの、簡素なものだ。なんでこんなモノを後生大事に引き出しにしまってたんだ私は。忙しいのに、思わず読みふけってしまったじゃないか。名簿とはいえ、各自が自己PRなんかを書いているので、けっこう読むところがあるのだ。で、19歳になったばかりの私がどんな自己PRをしていたかというと、能力的な特徴として挙げているのは次の2点である。
☆方向音痴。
☆一般常識の欠落。
あんた、ぜんぜん変わっとりゃせんじゃないの! 本気であきれました。それ以外には、「こんにゃく嫌い」とか「かずのこ喰えない」とか、どうでもいいことばっかり書いてある。三つ子の魂百までと言うが、10代の頃からこんな路線だったのか私は。しかしまあ、文字を書き始めると饒舌になりがちな私にしては言葉数の少ない内容になっているぶん、思わず赤面してしまうようなことは書いていないので助かる。なにしろ文学部だから(しかも第二外国語でロシア語を選択するような者どもの集団だ)、長々と書いてる人が多いのだ。なかには、こんなことまで論じている人もいて驚く。
我々の身のまわりはウソで固められていると言っても過言ではない。多くは我々の無知と固定観念による生産物であるが、例えば、「日本は単一民族国家である」という言い回しがあるが、これなど明らかに真赤なウソなのである。また、ノーベル賞は世界最高の栄誉ある賞であるとする考え方。ノーベル賞が「アメリカ帝国主義の走狗的役割」を果たしていることは、もはや常識である。そうでなければ、ベギンや佐藤栄作などが「ノーベル平和賞」を受賞するものか! 諸君! 身のまわりのウソに注意されたし!!
一体この人は名簿で何を言い出すのかとうろたえてしまうが、ひょっとすると、80年代前半の大学では、名簿がブログの役割を担っていたのかもしれない。あと、これが当時の特徴だったのかなぁと思うのは、人間性を評するに当たって「明るい/暗い」がひとつの基準になっているように見える点だ。表紙には「超ネクラとウワサされているロシア語T組の実態はいかに?」などと書かれているし、自己PRでも「外見ほど暗くありません」「ブラームスとショパンを愛する根暗な女の子です」「早稲田に来たからにはもう少し明るく楽しい子になりたい」といった言葉が散見される。うー。読んでて切なくなりますな。一方で、なぜか中島みゆきの似顔絵をデカデカと描いている男もいたりして、何のことだかよくわからない。「巨人の河埜を応援してネ(私ファンなんです)」という女の子がいるのには笑ったが。まあ、そんな時代だったのだ。「ばいなら」という言葉も存在した。
いちおう顔写真の添付が義務づけられていて、どうしても変化球を投げたかったらしい私は2歳か3歳ぐらいの頃の写真(なぜか頭に洗面器をかぶって嬉しそうに笑っている写真)を使ったりしているのだが、二名だけ、クラスメイトに似顔絵を描かせている人がいる。ニシムラ君の顔を描いたのはKay'n師匠で、アイダ君の顔を描いているのは私だ。そんな似顔絵班の二人が20年後に師弟関係になっているというのは、なかなか興味深い。しかも、師匠が誠実なタッチで写実的にニシムラ君を描いているのに対して、私のほうは殴り書きの「へのへのもへじ」だ。似顔絵でも何でもねえじゃん。すげえ不真面目じゃん。師匠になる人間と弟子になる人間の差が、こんなところにも滲み出ているのだった。
ところでこの名簿では、クラス全員の履修科目も一覧表になっている。語学以外の一般教養で私が受講していたのは、哲学C、社会思想、政治学、歴史学A、経済学A、生物学Cといった科目だったらしい。社会思想と政治学はKay'n師匠と一緒だったようだ。しかし、そこで何を教わったのか、ぜんぜん覚えていない。内容はもちろん、先生の顔すら思い浮かばない。覚えているのは、生物学Cがきのうの朝日新聞夕刊で話題になっていた「楽勝科目」だったということだけだ。できることなら、もういちど最初からやり直して、一般常識の欠落を克服させてほしい。方向音痴はもう諦めるから。ちなみに、こんにゃくとかずのこは克服しました。
|
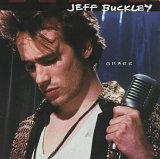
1.Mojo Pin
2.Grace
3.Last Goodbye
4.Lilac Wine
5.So Real
6.Hallelujah
7.Lover, You Should`ve Come Over
8.Corpus Christi Carol
9.Eternal Life
10.Dream Brother
|
2005.06.27.Mon.
10 : 05 a.m.
BGM : Jeff Buckley "Grace"
あれはたしか4月の末、水疱瘡を発症する三日ほど前に友人のタボン君と大久保の鯉登りでたらふくホルモン焼きを食ったのち、二軒目の店を求めて高田馬場まで歩き、ふらふらと迷い込んだムトウ楽器で、タボン君に「これを買わんでどうする」と脅迫されて買ったのが、この『Grace』なのだった。脅迫はされてないか。ほんとうは「これは気に入ると思うよ」と言われただけだ。ともあれ、そんな成り行きもあって聴くたびにホルモン焼きと水疱瘡のことを思い出してしまうのはジェフ・バックリーに対してひじょうに申し訳ないことなのだが、しかしこれは買って正解。どうも以前からタボン君のすすめる音楽は私にとって当たり外れがデカい傾向があり(三振よりホームランのほうが多いけど)、実をいうとこれもちょっと不安を抱いてはいたものの、結果的には「カキ〜ン!」という金属音が聞こえてきそうな大当たりである。これほどの圧倒的な美と哀感と激情と狂気と品格と破壊力を兼ね備えた音楽は、そう滅多にあるものではない。いまさらながら、惜しい人を亡くしたものだ。ほんとうに、惜しまれる。でも、しょうがない。神様に生贄を差し出さなければ成り立たない音楽だったのかもしれない。たった一枚でも、彼が生前にこれだけのアルバムを完成させておいてくれたことを幸運だと思うことにしよう。
|


