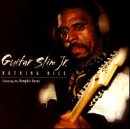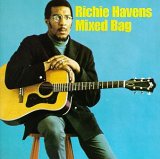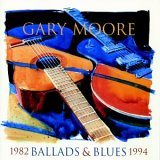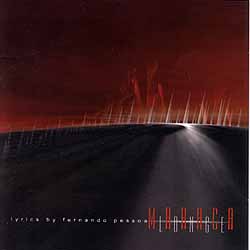Side1
1.東京日暮れ色
2.Musician
3.都方人(みやこかたびと)
4.想い出がつきない夜
5.月影に揺れて
Side 2
1.海を渡る手紙
2.サンルームの鍵
3.春の日の終りに
4.五月雨
5.Blue Blue Hawaii
(青き海によせて)
2005.10.20.Thu. 15 : 45 p.m.
BGM : 北斗七星 / 伊勢正三
押入から大量に出土したカセットテープを聴きたいと思い、しかし仕事場にはカセットデッキがないので、ラオックスでソニーのラジカセを買ってきた。ソニーのラジカセを買うのはとても久しぶり。幅30センチぐらいの小ぶりな機械で、正真正銘「ラジ」と「カセ」しか聴けないラジカセである。仕事場にはラジオもなかったので、一石二鳥だ。いまどきラジカセに「一石二鳥」のありがたみを実感する人間は少ないと思うが、本来はそれがラジカセ最大のセールスポイントであろう。偉大な発明である。それにしても、まだ作ってるんだな、こういうの。「語学レッスンに最適!」とか書いてあったから、音楽を聴くことを前提にはしていないのかもしれないが、中学生のときに技術の授業で作ったトランジスタラジオみたいな安〜い音がして、やけにいとおしい。聴いているのは、かぐや姫(75年解散)と風(79年解散)での活動を経てソロとなった伊勢正三が、80年に発表したファースト・アルバム。微妙な時代の微妙なシティ派感覚が、またいとおしい。もっとも私自身はその時期、すでにYMOに走っていたのだった。もしかして、そんな私の転向を見かねた誰かが「これを忘れるな!」とばかりに、これらのテープを貸してくれたのだろうか。そんな奴ぁ、いねえよな。いまだ記憶は蘇らない。
1.If You Think That Jive Will Do
2.I Feel So Bad
3.Oo Wee Baby, I Love You
4.Steal Away
5.Things I Used To Do
6.Try A Little Tenderness
7.I Want You
8.The Rivers Invitation,
9.Our Only Child
10.Leave My Girl Alone
11.I Got Sumpin' For You
2005.10.19.Wed. 12 : 30 p.m.
BGM : Nothing Nice / Guitar Slim Jr.
iTunesミュージックストアで購入したアルバムを、iPodを持っていないのでCD-Rに焼いてCDプレーヤーで聴いている。「ニューオーリンズのブルース」というジャンルと、「ギター・スリム・ジュニア」という個人名なのかユニット名なのか判然としない謎めいた名前に惹かれて手を出したのはたしかだが、しかし本当にこのアルバムが欲しかったのか、「iTunesミュージックストアでアルバムごと音楽を買う」という新しい行為をしてみたかっただけなのか、自分でも正直よくわからない。
まあ、どっちでもいいのだけれど、ともあれ体験してみた上での直観的な感想は、月並みかもしれないが「これはひどく危険だ」であった。怖いよなぁ。いくら何でもお手軽すぎるじゃないか。ちょっと蛇口をひねるだけで、まさに湯水のごとく、どばどばとMacに曲が溜まっていく。しかし(同じアルバムをamazonで買うよりは安いものの)湯水ほど安くはない。湯水ほど安くないものが湯水のように流れてくるんだから、危ないに決まっている。もし、こんな仕組みが私が10代の頃に存在していたら、えらいことになっていたに違いない。先日の押入発掘作業では当時FM放送をエアチェックしたカセットテープが大量に出土したが、それは湯水ほどではなかった。エアチェックには「FM雑誌の番組表を隅から隅まで見て赤線を引く」「少ない小遣いをはたいてカセットテープを買う」「タイマーをセットする」「途中でテープをひっくり返す」などそれなりに煩雑な手間があったし、NHKとFM東京の2局だけでは聴きたいコンテンツも限られていたが、音楽ダウンロードのほうは、チューナーの電源を入れて周波数を合わせる程度の手軽さで、無限に用意されたコンテンツを自分のモノにできるのだった。目の玉が飛び出るほどの請求額を見てお父さん大激怒、となるのは火を見るより明らかだ。
だが、えらいことになりかねないのは40代の私も同じである。昨夜も、この『Nothing Nice』をダウンロードした直後に「あと一つぐらい……」と別のアルバムの購入ボタンを押そうとする自分を必死で押しとどめたのだが、その葛藤が何に似ていたかというと、かつて競馬にハマっていたときにしばしば場外馬券売り場で幻聴した「あと1000円分ぐらい……」という悪魔の囁きとの戦いにとてもよく似ていた。誰か俺を止めてくれ!という感じ。自制心のユルい私のような人間の場合、家族の目の届かない仕事場では絶対にアクセスしてはいけない。あんな場所に逃避なんかし始めたら、身の破滅だ。さいわい仕事場のMacに入っているiTuneはミュージックストアに対応していないが、今後もバージョンアップは厳禁。
1.High Flyin' Bird
2.I Can't Make It Anymore
3.Morning, Morning
4.Adam
5.Follow
6.Three Day Eternity
7.Sandy
8.Handsome Johnny
9.San Francisco Bay Blues
10.Just Like a Woman
11.Eleanor Rigby
2005.10.18.Tue. 11 : 55 a.m.
BGM : Mixed Bag / Richie Havens
押入発掘作業が片づき、本棚の移動をはじめとする部屋のレイアウト変更がほぼ終わって腰の痛みに顔を歪めていた昨日の夕刻、某編プロのマッキー社長から久々に仕事のご発注。例によって「今週はどんな感じ?」という場当たり的な依頼だが、ブラブラしているときに速攻で着手できる仕事をいただくのは、話が早くてありがたい。それを含めて、今週はチマチマとした仕事が何本かあるのでライターらしい生活。ずっと肉体労働ばかりしていたため、頭脳労働にスイッチが切り替わるまで時間がかかるかも……と思ったら、とくに何の問題もなかった。そりゃそうだよな。短い原稿のリライトに使う頭脳なんて、部屋の模様替えに使う頭脳と大差ないもんな。大事なのは手を動かすこと。重い肉体労働が軽い肉体労働に切り替わっただけの話なのだった。
ラツィオはまたホームで勝った模様。フィオーレ&パンカロ含みのフィオレンティーナを1-0で下したゲームを観られなかったのは、歯軋りで奥歯が砕けそうなほど残念無念である。そんでもってセリエA上位は、1位ユベントス、2位ミラン、3位インテル、4位フィオレンティーナ、5位(得失点差で)ラツィオだ。わーお。ビッグ7時代みたいじゃないか。いまやロッテ×阪神の日本シリーズが開催されるほどの新時代だというのに、イタリアのほうはなんだか復古調な感じになっているのだった。まあ、復古ったって、ほんのちょっと前のことですけども。で、次節はダービーだ。ローマ主催なので放送は可能なはずなんだが、スカパー!の判断能力ほど信用ならないものはないので不安である。「オリンピコのラツィオ」を拝める唯一のチャンスなんですけどね。頼むよ。
あのウッドストック・フェスティバルにトップバッターとして登場し、まるで弦を切るために弾いているかのような狂おしいほどの迫力でギターをかき鳴らしていた(じっさい弦を切っていた)のが、いま聴いているリッチー・ヘヴンスである。そのマサカリ投法のごとき無骨なフォーム&スピード感しか知らなかったので、このアルバムでしっとりとした曲を渋い声で歌い上げているのは、ちょっと意外だった。秋雨の冷たさによく似合う『Just Like a Woman』は、なかなかの逸品。
1.About To Make Me Leave Home
2.Runaway
3.Two Lives
4.Louise
5.Gamblin' Man
6.Sweet Forgiveness
7.My Opening Farewell
8.Three Time Loser
9.Takin' My Time
10.Home
2005.10.17.Mon. 14 : 30 p.m.
BGM : Sweet Forgiveness / Bonnie Raitt
土曜日(15日)は私たちの11回目の結婚記念日だった。以前は自分が両親の結婚式に出席していなかったことに理不尽な不満を漏らしていたセガレが、今年は初めて「結婚記念日おめでとう」と言ってくれた。それは嬉しかったのだが、11年前の挙式写真など見ながら「父さん、結婚するときライバルいなかったの?」と妙なことを訊きやがるのは困る。汗かいたわ。「いや、いないと思う」と答えたら、愚妻に「思うってどういうことよ」と叱られてまた汗をかいた。
きのうの日曜日は、夕刻にヤマちゃん夫妻が来訪。愚妻の誕生日だったが、べつにお誕生会をしようというわけではなく、入手困難でTSUTAYAにも置いていないラーメンズのビデオを借してもらうために、無理やり「メシでも食いに来い」と誘ったのである。そんなことをしてしまうぐらいラーメンズは面白いということ。
料理は、先日も作ったチキンのフライ、トマトとほうれん草のスクランブルエッグ風サラダ、「なんちゃってメキシコ風」のスパイシーミートボールシチュー。シチューのレシピはハインツのサイトで見つけたもので、それはもうどうしたってハインツのデミグラスソースを使うことになっており、素直にそれに従って作ったので、それはもうどうしたってハインツの味。ミートボールを鍋に投入する直前に、そこにツナギの卵を入れるのを忘れていたことに気づいて慌てた。あやうく、「デミグラス味のミートソース」を大量にこしらえてしまうところだった。せっかく丸めた30個のボールを再びボウルに戻して卵と混ぜ混ぜし、あらためて丸め直す。以前、停電のせいでワープロの中から消え去ってしまった原稿を泣きながら書き直したときのことを思い出した。
さんざん飲み食いしたあとの深夜、このところiTunesミュージックストアに頻繁に出入りしているらしいヤマ(嫁)ちゃんの手引きで、初めてネットからの音楽ダウンロードにトライ。今まで手を出さなかったのは「これ、ハマるとヤバイんじゃねぇの?」と第六感が告げていたからだが、当然興味はあったわけで、酔っ払った勢いでヘラヘラとアカウントを作成したのだった。とくに目当ての曲があったわけではなく、何を購入しようか迷っていたら、愚妻が唐突に「遠藤賢司なんかどう?」と言う。なんでそんなことを思いつくのか、全然わからない。人の心の闇に何が隠れているのかというのは、11年いっしょに暮らしていても読めないものだ。しかし誕生日の人の言うことは聞いたほうがいいので「遠藤賢司」を検索したら、たくさんあった。遠藤賢司といえば『カレーライス』だが、それは私が持っている『不滅のにっぽんフォーク史』という二枚組LPに入っているので、とりあえず『夜汽車のブルース』という曲を試聴した上でゲット。その後も、あれこれ検索しながら懐メロ系を試聴しまくった。いったい何をしているのかよくわからないが、夜中に4人でキャーキャー言いながら遠藤賢司をダウンロードしたり『あずさ2号』のリミックスバージョンを試聴したりするのは、わりと愉しい。小銭を払って音楽と戯れるという意味で、あれは要するに底無しのジュークボックスみたいなものなんですね。
土曜日の23時から日曜日の1時まで、つまり私たちの結婚記念日と愚妻の誕生日をまたぐ形で生中継されたチェルシー×ボルトン(プレミア第8週)は、まるで我が家を祝福してくれているかのような5-1。前半は0-1と先行されてしまい、みんな代表戦でお疲れなのかなぁと不安に駆られたが、ハーフタイム後にグジョンセンが投入されて以降はお神輿わっしょい的ゴールラッシュで笑いが止まらなかった。勝ち越し点は、マケレレさんが突き刺したクサビをグジョンセンがワンタッチで前に送り、DFを3人ほど引き寄せたドログバがヒールで後方に流したボールを、ランパードが決めたもの。あれほどスリリングで流麗な中央突破攻撃は、これまで見たことがない。あったかもしれないが、なかったことにしておきたい。信頼し合った4人のプレイヤーが次々とタスキを渡していく姿は感動的ですらあった。駅伝を数秒間に凝縮したようなゴール。
1.Always Gonna Love You
2.Still Got the Blues
3.Empty Rooms
4.Parisienne Walkways
5.One Day
6.Separate Ways
7.Story of the Blues
8.Crying in the Shadows
9.With Love (Remember)
10.Midnight Blues
11.Falling in Love With You
12.Jumpin' at Shadows
13.Blues for Narada
14.Johnny Boy
2005.10.14.Fri. 11 : 20 a.m.
BGM : Ballads & Blues 1982 - 1994 / Gary Moore
先週の水曜日に着手した押入発掘作業は延々と続いているのだった。その後も、恐るべき遺物との出会いの連続だ。押入はサプライズに満ちている。
たとえば、かぐや姫と伊勢正三と風と吉田拓郎のミュージック・テープ。「ミュージック・テープ」でいいんだっけ、あの、LPの代替物みたいな感じで市販されてたアレは。なんでこんな物があるんだろう。たしかにかぐや姫関係は好きだったが、ミュージック・テープを買ったことはないはずだ。買うならLPを買う。なのに、持っている。じゃあ、誰のだ。誰が、いつ、私にこれを貸したんだ。それに混じってLPからダビングしたと思しき『明日に向かって走れ』(吉田拓郎)もあって、そこには絶対に私の筆跡ではない男の文字で曲のタイトルなどが書かれている。誰の字だか、全然わからない。たぶん、この男が他のミュージック・テープの持ち主でもあるのだろう。こんな物を貸し借りするぐらいなのだから、かなり親密な間柄だったはずだ。なのにそれが誰だかわからないのは情けないし、ちょっと不気味でもある。記憶から欠落してしまった、かなり親密な友。ものすごく謎だ。これがファンタジー小説か何かだったら、主人公の「私」が怪訝に思いながらテープをデッキに投入して再生してみると、そこからは吉田拓郎の声ではなく、「江戸川くん、お元気ですか」で始まる聞き覚えのない男の声が聞こえてきた……みたいな展開になるところだろう。うああ。なので、手書きタイトルのテープは怖くてまだ聴いていない。ミュージック・テープのほうは、ちゃんとかぐや姫や伊勢正三や風や吉田拓郎の歌が入っていたが。もし、彼がこれを読んでいたら、心から謝りたい。テープ、借りっぱなしでごめんなさい。そして、僕はキミが誰だかわかりません。ほんとうに、ごめん。キミは僕と僕に貸したテープのことを覚えていますか。覚えていたら、連絡ください。テープは返すし、一杯ごちそうします。
たとえば、ちょうど今聴いているアルバムの曲たちが録音されたぐらいの時期(18歳以降の独身時代)に買った洋服たち。今や着る物の大半を吉祥寺の西友とエディ・バウアーで間に合わせている私だが、当時は新宿の丸井メンズ館とかラフォーレ原宿とかパルコとか青山のブルックス・ブラザーズとかそんなところに足繁く通っていた。いったい何をやってたんだ。ものすごい無駄遣いだし、だいたいかぐや姫や伊勢正三や風や吉田拓郎の世界とのギャップがひどすぎるじゃないか。あの頃のおまえはどこへ行ってしまったんだ。などと思うが、まあ、カラッポの中身を覆い隠すヨロイが必要だったんだろうなぁ、この時期は。だからといって今は中身が詰まったというわけではなく、カラッポの中身を剥き出しにしても平気でいられるぐらい無神経になっただけのことだと思いますけども。歳を取るって、そういうことだろ? 違うの?
たとえば、私が高校生のころ北海道に単身赴任していた父から届いた手紙の束。大学に入ってからは母も父のところへ行き、私は東京で独居していたので、両親から頻繁に手紙が来ていた。というのはその束を見て思い出したことで、「こんなにたくさんの手紙を書いていたのか私の親は」と持つ手を震わせたというのが本当のところ。近況報告のような内容が多く、そんなに特別な言葉が記されているわけではないが、読んでいると思わずグッときてしまう。とくに父は、大学入試や就職活動といった「男の勝負時」に息子の近くにいられないことが、きっと大変に歯痒かったのだろう。男親として必要なことを伝えておきたいんだよ俺は……という気持ちが、いま読むと行間からひしひしと感じられるのだった。しかし当時は「うるせえなぁオヤジは。俺だってわかってるよそれぐらい」などと思いながら、ろくに返事も書かなかったような気がする。お父さん、ごめんなさい。
そのほかにも、TOKYO-FMがまだFM東京だった時代にエアチェックした吉田拓郎の武道館コンサートや小室等の『音楽夜話』などのテープ(サントリーマイルドウォッカ樹氷のCM含み)、差出人が女の子なのであまり大きな声では言えないが中学生時代に受け取った手紙(「こんな手紙をもらっても迷惑だよね、わたしのこと敬別してる?」という決して軽蔑してはならない誤字含み)、貸しレコードからダビングしたソニー・ロリンズやジョン・コルトレーンやチャーリー・ミンガスや荒井由実やグレープ、田原総一朗と麻原彰晃の対談を収録したテープ、何のために買ったのか皆目わからないパーティ用の三角帽子、ハンドボール、10フラン紙幣、百円札、小学生時代に市内のサッカー大会で優勝したときチームの最優秀ディフェンダー賞として先生がくれたメダル(なぜか「FOOTBALL FRIENDLY MATCH/HERTHA BSC V. ALL JAPAN」という刻印が入っている)、一度もつけたことがない早大文学部のバッヂ(これって全員に配ったのか?)、ニューヨークのヴィレッジ・ヴァンガードやスウィート・ベイジルでこっそり録音したトニー・ウィリアムズやティト・プエンテのライブ、89年の大晦日にホノルルのコンサート会場で撮影した女性誌編集者時代の唯一のスクープ写真(後藤久美子の芸能生活における最初のスキャンダルを出会い頭に偶然スクープしたのは私だ)、自分が写っていないのにどういうわけか持っているヤマちゃんやタボン君やスネオ君の若かりし日の写真などが次々と発掘されており、♪思い出に〜浸るには〜十分す〜ぎて〜、結果的に仕事場は散らかる一方なのだった。
ゆうべビデオ観戦したアイルランド×スイス(W杯欧州予選)はスコアレスドロー。ダブリンの思い出を反芻しながら応援していたアイルランドだったが、「ガッツはあるのに勇気がない」とでもいうような、おかしな戦いぶりだった。ダフ不在が痛すぎ。終盤、フレイ(だったかなスイスのFWは)との一対一を止めたGKシェイ・ギブンのセーブには感動したが、結果的にはあれがフランスを救うことになったのだから皮肉な話である。ドログバもロッベンもジョー・コールもショーンライトフィリップスも出場するのに自分だけ出場できないダフと、ロナウジーニョもラーションもジュリもデコも出場するのに自分だけ出場できないエトーのどちらかに、CLファイナルで決勝ゴールを決めさせてやりたいと思ったりする。
引き続き、サンマリノ×スペイン(W杯欧州予選)を観戦。サンマリノを観るのはものすごく久しぶりだったが、相変わらずユニフォームは世界屈指の美しさだった。同じブルー系のラツィオやチェルシーも美しいが、サンマリノにはかなわない。あれは何というブルーなんだろう。色の名前を知りたい。ボーリングのピンみたいに自陣ゴール前に林立していながら6点を奪われたものの、これから就職活動を控えているかもしれない学生選手たちにとっては、圧迫面接に負けない不屈の精神力を養う場になったに違いない。ところで「6点取ったのにうなだれるスペイン」って、たしかフランスW杯のグループリーグ最終戦でも見たような気がする。そんな人たち。
1. Adular's Wondering
2. The Unicorn
a) Magic Woods
b) Madrigal
c) The Battle-hunt
d) The Coming-home Pastoral
e) Dance with the Unicorn
3. Eljzao
4. Where Do The Angels Go?..
2005.10.13.Thu. 10 : 45 a.m.
BGM : The Unicorn / Er. J. Orchestra
編集者諸氏から所用で連絡をもらうたびに、「ヒマだ。仕事くれ」という意味のことをもっと丁寧な言葉で伝えている今日この頃だが、どういうわけか、このところ、私にゴーストさせるつもりの企画があったものの著者が「自分で書く」と言うので残念ながら頼めない、というケースが続いている。ううむ。著者が著書を自分で書くというのは一般的に言ってきわめて健全(というかごく常識的)なことなので、そう言われてしまうとグウの音も出ない。なかには「あの人にこんな本を書かせたら面白いんじゃない?」と私が言い出したことから始まった企画もあり、それは当然「私がゴーストする」を前提にしているわけで、本人が執筆したのでは私は単なる「善意の第三者」になってしまって困るのだが、それでも「おれが考えた企画なんだからおまえは書くな」と主張するのは何かが決定的に間違っているような気がする。しかし、自ら企画を口にすること自体が珍しい私が、編集者に「それ売れるかも」と言わせるなんて実に稀有なケースだったのになぁ。そういえば今朝のワイドショーを見て、これも編集者に「いいね」と言われていた別の企画がもはや成立しなくなったことを知った。上司と不倫関係にあった消防庁職員の女性がネットで相手の妻の殺害を依頼し金も払ったのだが「騙されたのでは」と思って警察に駆け込んだりその計画を知った上司から暴行を受けたりした、という気の毒なんだかそうでもないんだかよくわからない事件のせいでどんな企画がポシャッたのかは内緒だが、いずれにしろ、他人のフンドシで相撲を取るのも簡単ではないということか。やれやれ。
聴いているのはウクライナのEr. J. Orchestraの三作目。一作目のほうがシャープで面白かった。こっちは巧いんだけど全体にボンヤリしていて、シェフチェンコがいないって感じ? というわけで、話のマクラになっているようなそうでもないような雰囲気だが、ウクライナ×日本(国際親善試合)は、1-0でラトビア人主審の勝ち。中田(仏)の一発退場といい、PKの判定といい、こんな練習試合でレフェリーがなにムキになってんだよぉ、と失笑を禁じ得ない過剰かつデタラメなジャッジだった。それを見ていて思い出したのが、このあいだ仕事で書いた「各国の科学分野における女性研究者の比率」のことだ。大半の欧米先進国が20〜30%であるのに対して日本は12%弱と際立って低いという話だが、それより私が「へえ」と思ったのは、1位がラトビア(約53%)ということだった。男性研究者より女性研究者のほうが多いのは、調査対象となった国のなかで唯一ラトビアだけである。意外な国ラトビア。科学分野における研究者といえば、求められる資質は論理性、客観性、観察力、想像力、公正な判断力などであろう。だとすると、ラトビアの男はそれらの点で女性より劣っているという、安直かつ乱暴(かつ日本女性に叱られそう)な仮説が成り立つわけだ。なるほど、ならばサッカーの審判には向いていないかもしれない。叱られる前に慌てて言っておくと、たぶん本当は、ラトビアは日本と違って働く女性をサポートするための環境が整備されているとかそういう事情によるものだと思います。ともあれ、まあ、ウクライナに負けたわけじゃないからいいや。10人になってから何度か見られた中田(英)経由のカウンターには、W杯本番を期待させるだけの鋭さがあった。あのタイミングに対応できるウイングとストライカー(誰だかわからんが)を優先起用すれば、勝ち点4ぐらいはイケそうな気がしたんだけど甘いですか。
1.Dobre
2.Sonhos
3.Ao longe
4.I know
5.I am the escaped one
6.Nuvens
7.Berima
8.Intervalo
9.E hoje e ja outro dia
10.Pessoa
11.Meu triste coracao
2005.10.12.Wed. 13 : 50 p.m.
BGM : Longe - lyrics by fernando pessoa / Maraca
土曜日は小学校の体育学習発表会(という名の運動会)、火曜日はその代休でセガレが家にいたため、私も4日間、家で過ごしていた。学校、休み多すぎ。子供のうちからこんなにゆるゆると軽ストレスな生活をさせていたら、将来の日本は、逆境への耐性を持たぬ逃避型人間ばかりうじゃうじゃ増えるんじゃないかと心配になる。逃避型人間って、私に言われたくはないだろうけど。
ゆるゆるといえば、運動会の最初と最後もゆるかった。準備体操および整理体操のときに教師が「体操の隊形に開け!」「元の位置に戻れ!」と号令をかけるのは昔と変わらないのだが、子供たちは走って移動せず、ダラダラ歩いてジワジワと広がったり集まったりしている。「かったり〜」という声が聞こえてきそうな態度。シマリのないこと甚だしい。それがおまえらの体育学習の成果かよ。そんなことじゃ立派な自衛官が育たないじゃないか! 昨今の不祥事もここに遠因があるのではないか! などと乱暴なことを考えたりもしたが、まあ、どうせ「軍隊式」を嫌う学校特有の空気がその背景にあるんだろう。でも、そのわりに「号令」という行為や「隊形」という言葉にはアレルギー反応を示していないようなのが不思議だし、それ以前の問題として、あれはスポーツをやる人間の態度ではない。スポーツは、もっとキビキビと楽しむものだ。
で、私はキビキビと楽しんだ。PTA競技の障害物リレーに出場し、全力疾走でトラックを1周したのである。おかげで、4日後の今も太腿に筋肉痛が残っている。たった1周でこんなことになるなんて、人体って不思議だ。しかも痛いのは脚だけではない。左肘もまだヒリヒリする。これについては、運動会終了後、帰宅したセガレにも心配された。
子「父さ〜ん、大丈夫ぅ〜?」青チーム第3走者の私がものすごい勢いで1回転したのは、第4走者にタスキを渡す直前のことだ。第2走者から1位でタスキを受け取った私は、第1障害(スプーンにボールを乗せて運ぶ)を難なくクリアし、バックスタンド側の直線を「すごい顔して走ってたよね」とセガレに言わせるほどのガッツで走り抜け、第2障害(フラフープに体を3回くぐらせる)にさしかかった。地面に置いてあるフラフープの中に立ち、まず輪を下から上に持ち上げて1回。上から下に通して2回。再び下から上に持ち上げて3回。それが、前夜から考え抜いて「いちばん効率がよい」と結論づけた作戦だった。体の小さい人は縄跳び方式でぴょんぴょん跳ぶのがいちばん早いが、図体のデカい私はそれだと引っかかって難儀なことになる恐れがあるのだ。
父「大丈夫じゃない。猛烈に痛い」
子「ものすごい勢いで転がってたもんねぇ」
父「1回転してた?」
子「うん、1回転してた」
しかし、私のやり方でもフラフープは体に引っかかった。最後に下から上へ持ち上げ、フラフープを後方に投げ捨てようとした瞬間に、首に引っかかったのである。抜ききらないうちに走り出したのがいけなかったのだろう。サイドからのクロスも、抜ききらないうちに上げようとすると往々にして相手に引っかかるものだ。「うわ」と小さく叫びながら、なんとかフラフープを首から外して投げ捨てたものの、その時点で、走りのリズムは大きく乱れていたに違いない。
そして最後の直線。肩にかけたタスキを外して手に持ったときにも、リズムが崩れたのだと思う。筋肉も悲鳴を上げており、もう末脚は残っていなかった。明らかに、脚の運びが気持ちについてきていない。なので、3歩ほど前から「あ、おれ、転ぶ」とわかってはいた。「このままだと、おれは紋切り型の秋の風物詩を演じてしまうことになる」という思いも脳裏を過ぎった。しかし、そう気づいたときにはすでに手遅れなのが転倒というものだ。「嗚呼やっぱり」と絶望する私の視界の中で、前日からの雨で湿った地面と、灰色の空と、指を差して笑っている観客たちの姿がぐるぐると回転した。みんな、手を叩いて大喜びだ。お父さん、大ウケ。だが、照れ臭そうに頭をかいたり痛がったりしているヒマはない。すぐに立ち上がって、「早く早く」と手招きしている第4走者のもとへ。転倒したにもかかわらず、1位をキープして次につないだのだから大したスピードだ。
左肘からは真っ赤な血がじくじくと滲んでいた。痛みを堪えるのに精一杯で、その後のレース展開を見物する余裕がなかったのだが、結果、わが青チームはブッちぎりで優勝。報われた、と思った。終了後、顔見知りの父兄たちが、口を揃えて「名誉の負傷ですね」と言ってくれた。ふだん滅多に使わない「名誉」などという言葉が複数の人たちの口から出てきたのは、それがいかに不名誉な風景だったかという証拠であろう。あるいは、運動会が軍隊的な何かであることの証拠かもしれない。
さて、話はこれで終わらないのである。レース終了後、私はPTAの役員に連れられて、本部テント内の救護班のところへ行った。救急箱を開いて待っていた保健の先生らしき女性に、血の滲んだ左肘を見せながら「いやはや面目ない。よろしくお願いします」と頭を下げると、相手はニコニコしながら「江戸川さんですよね?」と言う。……は? どうして私の名を? 学校の保健室なんか行ったことないのになぜ?
訝しそうにしている私に向かって、彼女は言った。「わたし、小金井の第一中学校で同級生だったKです」。うっそー。やっだー。まじでー。同じクラスになったことがないので名前は記憶にないが、言われてみれば彼女の顔にはうっすらと見覚えがあった。どうやら彼女のほうは、生徒の名簿か何かを見て、父兄に私(と同姓同名の人間)がいることを前から知っていたらしい。怪我をした私の顔を見て、それが間違いなく「一中の江戸川くん」だと確信したわけだ。
不意打ちのような再会と怪我の痛みがごちゃごちゃになって激しく動揺し、そのあと自分が何を言ったのかよく覚えていない。たぶん、四半世紀ぶりに会った同級生に消毒液を塗ってもらいながら、「ええっ、あの、じゃあ、いつもここの保健室に? うわぁ、そりゃまた何とも、へえ〜」とか何とか収拾のつかない言葉をまき散らしていたのだと思う。状況が状況なので、ひどく恥ずかしかった。中学の同級生と四半世紀ぶりに会ったときに血を流している人間はそういない。しかし、運動会で怪我でもしないかぎり生徒の父親が保健の先生と顔を合わせる機会はないわけで、これも何かのお導きだったのかなぁとも思う。なんにしろ、これまでの人生でもっとも印象に残る運動会になってしまった。
そんなこんなで、その晩、わが家の団欒が私の転倒騒動で持ちきりになったことは言うまでもない。「50メートル走で4人中4位」という無念な結果に関する話題がすっかりどこかへ吹き飛んでしまったのは、セガレにとってじつに幸いであった。
運動もよくしたが、料理もよくした連休だった。日曜日にアイリッシュ・シチューを作ろうと思い立ったのは、そぼ降る雨と暗い空が、数年前に半日だけ訪れたことのあるダブリンの天気を想起させたからかもしれない。ロンドン在住の著者にインタビューするために英国へ出張した際、仕事のない日を利用して、TOKYO-FM出版のOさんと二人でアイルランドまで足を伸ばしたのだ。午前中からダブリンの市街を歩き回り、ギネスの工場でめちゃくちゃ旨いギネスを飲み、帰りの飛行機の時間を気にしながらアイリッシュ・シチューを食わせる店をさんざん探し回って、黄昏時にようやく見つけたパブで味わったそれはものすごく旨かった。歩き疲れていたせいもあって、シチューの旨味が体中に染み渡っていくように感じたのをよく覚えている。
例によってアイリッシュ・シチューの定義はよくわからないが、まあ、羊肉とジャガイモとその他の野菜(玉ねぎ、にんじん、セロリ、長ねぎ等)が煮込んでありゃいいんだろうということで、ネットで見つけたレシピを参考にしながら適当に調理。ラムの塊は売っていなかったので、ラム・チョップを使った。この料理のキモは、「ドロドロに溶けたジャガイモ」と「ホクホクした形のあるジャガイモ」がシチューの中で共存していることだ。なので、用意したジャガイモのうち半分は薄切りにして1時間以上、残りは半分に切って30分だけ煮込む。肉と野菜と水以外に投入したのは、塩、胡椒、タイム。煮込み料理の醍醐味は、徐々に「それっぽくなっていく鍋」の様子を見ながらニタニタとほくそ笑むことだが、アイリッシュ・シチューはそのニタニタ度が際立って高い。鍋から漂ってくる野菜たちの甘い香りをかいでいると、いつまでも料理していたくなる。完成したシチューは、やや胡椒を効かせすぎたような気もしたが、ダブリンで味わったそれに肉迫する出来映えだった。ギネスのサイトで見つけたChicken Gougonsというツマミも、これはまあ単なるチキンのフライだが、カラッと揚げるのに成功して絶品。前日の転倒の汚名を返上し、心の傷を癒すには十分なパフォーマンスであった。
きのうの月曜日は、キーマカレーに挑戦。あまり過激な香辛料はセガレにはまだキツイだろうし、面倒なので、市販のカレー粉を使った手抜き系。にしても、想像以上に簡単。「料理したぜ」という手応えが希薄だったので、次はスパイスいろいろ買い込んでやってみたい。出来映えは、まあまあ。セガレの舌に配慮しすぎてカレー粉が足りなかった感じ。そういえばKay'n師匠のかなり辛いガンボも平気で食っていたぐらいから、もうそんなに子供扱いしなくていいんだよな。
聴いているのは、チェコのバンドが2003年に発表したアルバム。弦楽器とかフルートとかトランペットとか入っていて、ロックなのか何なのかよくわからないが、とても巧くて面白くて昏〜い音楽。面妖な雰囲気の女性ボーカルは、ノルウェイのカリ・ブレムネスを思い出させるような魅力を持っている。と言ったって、カリ・ブレムネスを知らない大半の人に対しては何の比喩にもなってませんが。書き手の自己満足にすぎないこの手の比較が音楽レビューにはしばしばあって、読むと「知らねえよそんなもん」と腹が立つのだが、まあ、そんなことを書きたくなる気持ちはわからんでもない。とりあえず自分の知っている音楽と比較しておけば、何かを書いたような気分にはなれる。それ以外の手法で、音楽について何かを書いた気分になるのは容易ではない。何かを書いたような気分になっているだけの文章が多いのはあまり良いことではないが、それはまた別の話。
関係あるような無いような話だが、ゆうべビデオで観たチェコ×オランダ(W杯欧州予選)は0-2でオランダの出場が決定。いちばん前にファン・ニステルローイ、いちばん後ろにファン・デル・サールのいるオランダを応援する気にはなかなかならないし、GKチェフがファン・ニステルローイにゴールを奪われるシーンなんぞ絶対に見たくないのでチェコに肩入れしていたのだが、そのシーンはなかったものの残念な試合だった。ネドベドがいればなぁ。で、チェコのサッカーとチェコのバンドに何か共通点があるかというと、たぶんあると思われるのだが、それが何なのかはわかりません。とりあえず、このアルバムのサウンドは、陰鬱な表情で疾走するロシツキのBGMに使うとよく馴染むような気がする。もちろんPK失敗シーンにも。