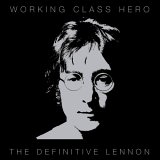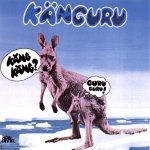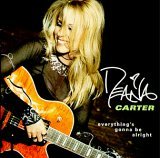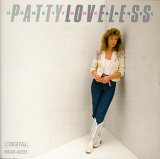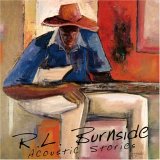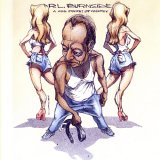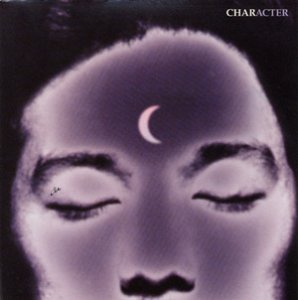Disc 2
1.Woman
2.Mind Games
3.Out Of The Blue
4.Whatever Gets You Thru The Night
5.Love
6.Mother
7.Beautiful Boy (Darling Boy)
8.Woman Is The Nigger Of The World
9.God
10.Scared
11.#9 Dream
12.I'm Losing You (Anthology Version)
13.Isolation
14.Cold Turkey
15.Intuition
16.Gimme Some Truth
17.Give Peace A Chance
18.Real Love
19.Grow Old With Me
2005.11.18.Fri. 10 : 15 a.m.
BGM : Working Class Hero / John Lennon
ゆうべは、まずチェコ×ノルウェイ(W杯予選プレーオフ第2戦)をビデオ観戦。幸運なこぼれ球に陰鬱な表情で走り込んだロシツキが爽快に決めたゴールを守りきって、チェコの1-0。見かけ上の性格とプレイのあいだに大きなギャップがあるという点で、ロシツキはデンマークのグロンキア(元チェルシー。現在は行方不明)に勝るとも劣らないと思うのだが、そんなことないですか。「憂鬱なスピード感」って、そう滅多に見られるものではない。GKがチェフ(もしくはチェフと同等の体長の持ち主)じゃなかったら入りそうな場面が三つぐらいあったと思うので、チェコの予選突破はチェフのおかげ。もしくは、あの体格を製造したチェフのご両親のおかげ。
引き続き、トルコ×スイス(W杯予選プレーオフ第2戦)をビデオ観戦。近年稀に見る面白おかしい試合だった。恫喝としか思えないトルコ人サポーターの声援、ブーイングにかき消されるスイス国歌、おそらくは世界でもっとも戦闘的な勇猛きわまりないトルコ国歌などによって極限まで高まったスタジアムのテンションを見れば、誰だって「こりゃスイスきついかも」と思う。どう考えても、「2点差じゃ足りない」感じだった。なのに、いきなりハンドだ。キックオフの約90秒後、試合前には誰よりも猛々しい表情で国歌を吠えていたアルパイが、顔のあたりのボールをエリア内で「ぱしん」とハタキ落としたのである。なんであんなことしちゃったかなぁ。それをハンドと呼ばずに何をハンドと呼ぶのかというような、申し開き不可能なハンドだった。とはいえ、主審は角度的に見えなかったようだから、試合の興味を削がない(つまり見逃す)道がなかったわけではない。だが、空気の読めない副審がハンドの判定。それまでの熱気がウソだったかのようにピキ〜ンと凍りつくスタンド。あそこまで温度の低い「冷水」がサッカーの観客に浴びせられるのを、私はこれまで見たことがない。それはもう、どうしたって「コールド・ターキー」という言葉を思い出してジョン・レノンを聴きたくなるというものである。
冷え切ったターキーは前半のうちに2点を返してオーブンに戻され、後半早々のPKで再びアツアツな食べごろ状態になったものの、その後はなぜかロングボールを放り込むばかりで、ダウン寸前だったスイスに深呼吸をする余裕を与えてしまう。そして終盤、再び冷水。スイスの11番は、角度のないところからよく決めた。しぶといチームである。もっともスイスの場合、その後またすぐトルコにゴールを許し、「取られてもいい点は簡単に取られる」あたり妙にあっさりしているところもあるのだが、まあ、〆切ギリギリにならないと本気になれないライターにはその気持ちがわからなくもない。ともあれ、まだ5分ほど時間を残した時点で再び「あと1点」になったものの、トルコはもうオーブンを温め直す気力が残っていなかった。agg.4-4、アウェイゴールの差でスイスがドイツへ。おめでとう、ベーラミ。W杯本番までにラツィオで結果を出して、レギュラーの座を奪取してください。エムレにさえケンカを売るその不良性は、人の良さそうな選手の多いスイスチームの貴重なアクセントになるであろう。
1 oxymoron
2 immer lustig
3 baby cake walk
4 ooga booga
2005.11.17.Thu. 10 : 35 a.m.
BGM : Kanguru / Guru Guru
ゆうべ生中継で観戦した日本×アンゴラ(国際親善試合)は、ジーコジャパンの必殺技(閉店間際の駆け込みゴール)が炸裂して1-0。この試合で一番えらかったのは松井で、一番ダメだったのはTBSの実況担当者である。
「不用意に試合の結果を言わない(書かない)」は、サッカーがらみのコミュニケーションにおける基本中の基本だ。だから私も読者が知りたくない試合結果を目にすることがないよう、トップページのインデックスで「この試合のこと書いてますよ」と予告し、その上ご丁寧なことに、うっかり日誌にアクセスしてしまった読者が結果からギリギリで目を逸らすことができるよう本文では対戦カードを(スコア抜きで)太文字にして目立たせている。誰もそれに感謝しようとしないどころか私がそんな配慮をしていることに気づいてもいないが、以前サッカーズのコラムにも書いたとおり、野球と違ってサッカーは「録画して見る」が日常である以上、それぐらいは当然のマナーであろう。
そんな最低限のマナーもわきまえず、だしぬけにオーストラリア×ウルグアイ戦の試合結果を口にしやがったアナウンサーはサッカーファンの敵なのであって、今後サッカー関係の仕事に携わる資格はない。こっちはな、おまえのそのやかましい実況を我慢してナマで聞いてやりながら、「裏番組」のプレーオフを録画してたんだよ。紅白歌合戦の司会者が曙×オロゴン戦の結果なんか言うか? 言わないだろ? 曙×オロゴン戦の実況担当者が紅白歌合戦の勝敗なんか言うか? 言わないだろ?
まあそれはジャンルが違いすぎるから比較にならんかもしれんし、紅白歌合戦の勝敗については発売中の『週刊アサヒ芸能』でKay'n師匠が提案しているような改革(おもろいので「アサ芸大法廷」という記事を読んでみましょう)がなされないかぎり視聴者の重大な関心事にはなり得ないだろうが、それはともかくとして、昨夜はサッカーファンの多くが、南半球の二ヶ国のどちらかがW杯出場を決める瞬間を後追いのライブ感覚で楽しもうと思っていたのだ。それをまるで「速報に価値がある」とでも言わんばかりに得々とアナウンスしやがって。そんなのは突発事故でも何でもなく、その時間に何らかの結果が出ることは予めわかってるんだから、いちいち速報するほどのニュースバリューはねえんだよ。知りたい奴は自分でネットでも何でも見て知ることができるんだから、おまえらが世話焼かなくていいんだよ。百歩譲って「オーストラリア出場決定」まではいいとしても、「PK戦を制して」まで言わなくたっていいじゃんか。こういうのって損害賠償請求の対象にならないんだろうか。人権蹂躙(幸福追求権の侵害)だよな。こんな不作法を放置していたのでは、時差があってライブ観戦が困難なドイツ大会が思いやられる。しかしメディア関係者の良心になんか期待はできぬ。来年のW杯本番までに、テレビ局とラジオ局を規制対象とする「ネタバレ防止法」を制定すべし。
それでも一応オーストラリア×ウルグアイ(W杯予選プレーオフ第2戦)をビデオで観戦したわけだが、PK戦になることがわかっている試合を最後まで真面目に見ろというのは無理な相談である。オーストラリアが1点取った時点で眠気に襲われ、それでも90分間はなんとか頑張っていたのだが、延長戦に入ったところで睡魔に負けた。満員の観衆が緊迫感と高揚感にあふれた良い雰囲気を作っていたし、そうでなくともW杯を賭けた「最後の戦い」というのはサッカー自体のレベルはともかく人間の営みとして面白いので、結果を知らなければ絶対に眠くならなかったはずだ。映画2本分ぐらいの娯楽を奪われたような気分である。TBS許すまじ。ところで、いま聴いているグルグルというバンドは、ジャケットにはカンガルーが描かれているがオーストラリアのバンドではなく、ドイツのバンドである。オーストラリアがドイツ行きを決めたので、祝意を込めて聴いている。どちらかというとマニア好みの面倒臭い系ジャーマンロックなので、そういうときでもないと聴く気にならない、とも言えるが。
1. このまま・・・
2. 好きな人
2005.11.16.Wed. 11 : 20 a.m.
BGM : このまま・・・ / 矢野真紀
『世界ふしぎ発見!』(TBS系)というテレビ番組には以前から妙に縁があって、番組の本の制作には何冊か関わったことがあるし、ゴーストで書いた考古学関係の本が番組内で取り上げられたこともある。で、こんどは矢野真紀だ。それが私との「縁」と言えるのかどうかわからない(たぶん言えない)けれど、現在あの長寿番組のエンディングテーマに使われているのが、1ヶ月ほど前にリリースされた『このまま・・・』という新曲である。「…」をナカグロで表記するのはキモチ悪いが、本人の公式サイトでも「・・・」になっているのでしょうがない。それが正式なタイトルなのであろう。発売から間もなく買って聴いていたのだが、ここで取り上げるのをうっかり忘れていた。忘れてしまう程度の第一印象だったということだ。引っかかりがないというかパンチがないというか人を立ち止まらせる驚きがないというか何というか、まあ、要はすごく「フツー」な感じだったのである。番組の終わりに流れているのも一度だけ耳にしたが、気にしていなければそこに音楽が流れていること自体に気づかないのではないかと思うような存在感の希薄さだった。経験上、『世界ふしぎ発見!』のような強力ブランドの「お世話になる」のがそう簡単なことではないというのは想像がつかないわけではないので、タイアップと引き替えに何か犠牲にせざるを得なかったのかなぁ、などと思ったりもした。
しかし、どうやらその第一印象は、曲を聴く前から「ふしぎ発見で流れる」という情報が頭に入っていたがゆえの歪んだ先入観に基づくものだったようだ。TBCのCMでヴィクトリア・ベッカムとの「共演」を果たした前回のタイアップ曲『キラキラ映して』がいかにも「会議室で作りました〜」という感じだったので、どうせ今回も狙いが見え見えのセットプレイみたいなあざとい「キャッチー」が用意されているに違いない、TBCとTBSって字面も似てるし・・・と、ハナからネガティブな態度で聴いていたような気がする。ところが実際に聴いてみると事前に恐れていたような「キャッチー」のないフツーな感じで、だったらポジティブな印象になるはずなのだが、いつの間にか私の中でその「恐れ」が「期待」と裏腹なものになっていたのか、どこかで価値観が転倒してしまった結果、物足りなさが先に立ったのだった。要するに私自身が、聴く前から「矢野真紀らしさ」より「ふしぎ発見らしさ」に対して身構えていたということであろうか。それが感じられなかったから、ガッカリする必要がないところで無駄にガッカリしてしまったのである。なに言ってんのかわかりますか。
まあ、そんなことはわからなくても構わないのであって、あらためて何度も何度も聴いてみると、これはじつに良い歌だ。たぶん同じタイアップでもCMとテレビ番組では事情が異なるのだろうが、「使ってもらう」ために何か(少なくとも表現面では)代償を払ったようには聞こえない。むしろ、矢野真紀らしさ満載。シンプルなアレンジは歌い手の持つ多彩な表現力を最大限に際立たせようとしているようで好感が持てるし、その簡潔なサウンドの中でときおり鳴る中村修司のスライドギターも効果的だ。「B面」(あいかわらずシングルCDの2曲目を何と呼ぶのかわからない)の『好きな人』もすばらしい。「好きな人」などという極端に凡庸な言葉に、ここまで鮮烈な生命力を吹き込める歌い手が、ほかにいるだろうか。いるかもしれないが、いないことにしておきたい。
矢野真紀といえば、来週の水曜日には「矢野真紀ビギナー様にお届けする初のお試し企画」という触れ込みで、『やのまき』という8曲入りのミニアルバムがリリースされるらしい。「矢野真紀推進委員会(仮)」という、実在するのかどうかよくわからない組織が推薦する曲を集めたものだそうで、それを聴けば彼女の「様々な表情」がわかるというのだが、私に言わせれば収録曲のチョイスに問題がありすぎる。『タイムカプセルの丘』も『君の為に出来ること』も『明日』も『アンスー』も入ってないのに『夜曲』が入ってるアルバムなんか、ぜったい矢野真紀ビギナーに聴かせたくない。そんなもの、『天国への階段』も『ロックンロール』も『アキレス最後の戦い』も『カシミール』も入ってないのに『ホット・ドッグ』が入ってるツェッペリンの編集盤と同じだ。そんなものが存在したら、誰だっておかしいと思うだろう。『やのまき』はそれぐらいおかしい。ぜんぜん、矢野真紀を推進することにならないと思う。そういう委員会を設立すること自体はたいへん大きな社会的意義があると思うが、だったら私を委員長にしろ。
1. You Still Shake Me
2. Ruby Brown
3. Absence Of The Heart
4. Brand New Key
5. Michelangelo Sky
6. People Miss Planes
7. Never Comin' Down
8. Make Up Your Mind
9. Colour Everywhere
10. Angels Working Overtime
11. Dickson County
12. The Train Song
13. Everything's Gonna Be Alright
1.Somewhere Between
2.Someday Soon
3.Outbound Plane
4.Cross My Broken Heart
5.Letting Go
6.Heartache
7.Drive South
8.Aces
9.Hopelessly Yours
10.I Want to Be a Cowboy's Sweetheart
1.Blue Side of Town
2.I Won't Gamble With Your Love
3.Go On
4.If You Think
5.Chains
6.Don't Toss Us Away
7.Lonely Side of Love
8.I'll Never Grow Tired of You
9.Timber, I'm Falling in Love
10.I'm on Your Side
2005.11.15.Tue. 10 : 55 a.m.
BGM
Everything's Gonna Be Alright / Deana Carter
Greatest HIts / Suzy Bogguss
Honky Tonk Angel / Patty Loveless
Amazonで「これを購入した人はこれも」と言われるまま、芋蔓式に注文した3枚である。「ポテトはいかがですかぁ?」に抗えない心理とあまり変わらない。……あっ、だから「芋蔓」っていうのか! そんなわけはないが、どれも1000円以下(3枚で2500円ぐらい)だったりすると、どうも歯止めがかからなくていかん。
べつにカントリーだからって芋だのポテトだのを持ち出したわけではないが、しかしエミルー・ハリスあたりも含めて、女性カントリーシンガーには「微妙な美人」が多い印象がある。何がどう微妙なのかはうまく言えないが、中途半端に美人であるがゆえに、これらの歌手たちを「好きだ」というと趣味をヘンなニュアンスで誤解されそうな微妙さというか、そんな感じ。もしかすると、それは「美人演歌歌手」の微妙さと通じるところがあるのかもしれないとも思うものの、だからって「カントリーってアメリカの演歌みたいなもんだろ?」などと知ったふうなことを言いたいわけではないのだし、アメリカの田舎で男たちが女性カントリーシンガーをどのように消費しているのか知る由もないが、とりわけSuzy Bogguss(上から二番目)の迸らせている微妙さといったらどうだ。その妖艶な目線はアリなのか。そこには何か勘違い的なものがないか。こんなに歌が上手いのに、なんでそんな厚化粧をする必要があるんだ? 歌が上手い人には、もっと歌が上手い人らしい撮られ方というものがあるのではないか。三番目のPatty Lovelessもそうだよ。なんだよ、その、ちょっぴり乙女チック(死語)な媚び媚びポーズは。近くでよく見たら、おまえ、そんなに若くないじゃんかよ。戦略が間違ってると思うよ。月刊PLAYBOYの表紙とか見て、おのれを知れよ。
何をムキになっているのか自分でもよくわからなくなっているが、どの音楽もかなり気に入ったがゆえに、その見せ方をもうちょっとどうにかしてもらいたいと思うのだった。とはいえ、私がこれらを純粋に音楽的な意味でのみ気に入ったのかといえば、それは「男女のあいだで友情は成立するか否か」という永遠のモンダイにも似ているような気がするのであって、どこまで行っても微妙としか言いようがないのだが。
ゆうべは、スイス×トルコ(W杯欧州予選プレーオフ第1戦)をビデオ観戦。2-0でスイスの先勝。欧州のプレーオフ3試合の中では、これがもっともスリリングな好勝負だった。いままでスイスの試合を面白いと思ったことはなかったような気がするが、実はかなり素敵なチームなのだなぁ。サイドアタッカーがよく走るキビキビとした折り目正しいサッカーに好感を持ちました。右サイドの「ギガックス」って名前がいいよな。機動戦士ギガックス。とても強そう。空だって飛べそうだ。それに、なんつったって、あまり広く知られていないから大きな声で言うが、終盤に途中出場して(たしか)ファーストタッチでスイスの2点目を決めたベーラミという若者はラツィオの所属選手なのである。おお。よくやった。今回のW杯予選でラツィオの選手が活躍するのを初めて見たよ。ペルッツィやオッドが本番で代表に招集されるような気が全然しないので、彼には唯一のラツィオ人として是非ドイツに行ってもらいたい。
さらにゆうべは、ウルグアイ×オーストラリア(W杯予選南半球プレーオフ第1戦)もビデオで観た。1-0でウルグアイ先勝。いままでウルグアイやオーストラリアの試合を面白いと思ったことはなかったような気がするが、これは、かなりつまらなかった。レコバの左足だけが印象に残った試合。この勝者とバーレーン×トリニダード・トバゴの勝者のあいだで、さらにプレーオフをやるぐらいで丁度いいのではあるまいか。っていうか、本大会の前にグループリーグを済ませておくぐらいで本当は丁度いいんだけどね。
1.When My First Wife Left Me
2.Death Bell Blues
3.Skinny Woman
4.Monkey in the Pool Room
5.Hobo Blues
6.Walking Blues
7.Long Haired Doney
8.Poor Black Mattie
9.Meet Me in the Bottom
10.Miss Glory B.
11.Kindhearted Woman Blues
2005.11.14.Mon. 16 : 25 p.m.
BGM : Acoustic Stories / R. L. Burnside
おたふく風邪の予防接種を打ってきた。いや、打ったのは看護婦さんだから、「打たれてきた」というべきか。いや、看護婦さんは私を打ったわけではなく注射を打ったのだから、「打たれた」のは私じゃなくて注射だよな。野球だって、バッターにバットで打たれたのはピッチャーじゃなくてボールだ。だから「打ち込まれた投手」などと怖いことを言ってはいけない。マウンドに首まで埋まってそうじゃないか。といった判りにくい冗談はともかく、これでひと安心。水疱瘡が治ったあと、医者をやっている兄にも「おたふく風邪の怖さは水疱瘡の比じゃないから早めに予防接種しとけ」と警告されていたにも関わらずボヤボヤと先送りしていたのだ。打つ前に感染しなくてヨカッタ。
ゆうべビデオ観戦したノルウェイ×チェコ(W杯欧州予選プレーオフ第1戦)はスミチェルのゴールで0-1、スペイン×スロバキア(同)はルイス・ガルシアの3発やモリエンテスなどのゴールで5-1と、リバプール勢の得点ばかり見せられたのはあまり愉快ではなかったものの、大会を賑やかにしてくれそうなほうの国が出場に向けて大きく前進したのは何より。チェフやデル・オルノやシャビやプジョールも出られるとなると、ますますダフとエトーの寂寥感は募るばかりですが。
1.Going Down South
2.Boogie Chillen
3.Poor Boy
4.2 Brothers
5.Snake Drive
6.Shake ‘em On Down
7.The Criminal Inside Me
8.Walkin’ Blues
9.Tojo Told Hitler
10.Have You Ever Been Lonely
2005.11.11.Fri. 17 : 05 p.m.
BGM : A Ass Pocket Of Whiskey / R. L. Burnside
およそどうでもいい知識だが、きょう十一月十一日は「鮭の日」なんだそうだ。けさJ-WAVEを聴いていたらクリス智子さんがそう言っていたのだが、それを聴いて、普段そんなにJ-WAVEを聴くわけではない私が、平成11年の11月11日にもその日付を話題にしているJ-WAVEを聴いていたことを思い出した。だから何だというわけではないが、まあ、そういうことだ。で、なぜきょうが鮭の日かといえば、鮭という字は魚ヘンに「十一十一」と書くからである。なるほどー。ということは、きょうは鮭の日であると同時に「蛙の日」や「畦の日」や「街の日」でもあるかもしれない。それだけで地球にやさしい感じの三題噺が作れそうだ。ところで、十一月十一日に生まれたという理由で「圭子」と名づけられた圭子さんは存在するだろうか。
あと、「乾電池の日」や「ドライバー(ネジ回し)の日」でもいいよな。いや、でも、それは十月一日でいいのか。一月十日でもいいかもしれないが、やはりプラスが先に来たほうが語呂がいいというものだし、重ねておよそどうでもいい知識を披露しておくと、一月十日はヤマちゃんの誕生日だ。でもヤマちゃんの名前は「干男」ではない。
1.スモーキー
2.シャイニン・ユー,シャイニン・デイ
3.闘牛士
4.気絶するほど悩ましい
5.ガール
6.逆光線
7.ネイヴィー・ブルー
8.かげろう
9.空模様のかげんが悪くなる前に
10.ふるえて眠れ
11.ワンダリング・アゲイン
12.ブルー・クリスマス
13.ザ・リーディング・オブ・ザ・リーヴィング(ロンリネス)
2005.11.10.Thu. 12 : 40 p.m.
BGM : Character / Char
マッキー社長から『マンスリーエム』の商品紹介記事5本を特急で頼まれたので、きのうは久しぶりに終日原稿書き。ここで公言した以上、お待たせするわけにはいかないので、「木曜の昼まで」の〆切を100分ほど前倒しして、さっき送稿した。とてもすがすがしい気分。それにしても、きのう届いた『日本の論点2006』(文藝春秋)の200本ノックも含めて、このところ短距離の原稿しか書いていない。4ヶ月も書籍のゴースト仕事をしていないのは、この15年間で初めてじゃないだろうか。腕がナマるには十分なブランクなので、次に依頼されたときにちゃんと書けるかどうか心配になってきたが、それより何より、まずは次の依頼があるかどうかを心配したほうがいいのだった。しかしまあ、心配して仕事が来るなら心配するが心配していても仕事は来ないので心配したってしょうがない。きっと、これも厄年の厄年たるところなのであろう。という具合に、「厄年さえ終われば何とかなるはず」と無根拠に楽観的になれるのが厄年のいいところ。
ファックスを買った。もう何年も前に使用不能になって以降、ずっと自宅のファックスだけで間に合わせていたのだが、たまにしか使わないとはいえ、やはり何かと不便であるし、「ファックスがない」はライターの仕事場にあるまじき非常識な状態なので、しぶしぶながら買った。人生4台目のファックスである。子機がついているので、これまで使っていた電話機は不要になった。もったいない。
思えば15年前に会社を辞めて独立した際、最初の(というかほぼ唯一の)設備投資がファックスだった。当時はまだ家庭用ファックスが普及していなかったこともあって、真新しいキカイを部屋の隅に設置しながら「ああフリーになったんだなぁ俺」とシミジミ実感したものだ。カッターがついておらず、複数枚受信すると感熱紙がつながったままビロビロビロ〜ンと垂れ流されてくる困ったちゃんだった。最初に受信したメッセージは、今でも覚えている。試運転のために「何か送ってみてちょ」と会社で仕事中のヤマちゃんに頼んだら、彼はたった一行「家にファックスあって羨ましいぞ」と書いて寄越したのだった。いまの若い人には信じられないリアクションだろうが、これはニッポンが敗戦から立ち直る前の話である。というのはウソですけども、まあ、そんな時代もあったよね。
それ以来、どれだけの原稿をファックスで送信しただろうか。短い雑誌原稿はともかく、書籍の原稿を送るのはものすごく大変だった。時間に余裕があれば郵送するのだが、ほとんどの場合、時間には余裕がない。徹夜して書き上げた原稿を何十枚もプリントアウトするだけでもウンザリするのに(昔のワープロの印字速度をキミは覚えているか!)、それをまた「ジッジッジッジッジッジッジッ」とモタモタ送りやがるファックスに食わせる作業は、気絶するほど悩ましかった。途中で警告音と共にエラーメッセージなんか出ると、「何枚目から送り直せばいいんだコノヤロー!」と頭を掻きむしりながら毒づいたものだ。それ以前に、プリントアウトの途中でインクリボンを使い果たして茫然自失することもあったよなぁ。文字がかすれるのを承知の上でインクリボンを二度使うのは日常茶飯事、三度使って「さすがに読めねぇかなぁ」と思いつつエイヤっと送ったこともある。それでも本は出版されたんだから、きっと読めたんだろう。キカイを使って原稿を作成するのが、ときどき手書きより不便に感じられる時代だった。
などと、新品を買ったのに昔のことばかり振り返ってしまうあたりに、ファックスというキカイの置かれた現状が滲み出ているような気もする。同じキカイに将来への希望と不安を感じた15年前とは大違いだ。ファックスに未来はあるのか。もしかしたら、このあいだ購入したラジカセと同じぐらい後ろ向きなキカイかも。そして私のデスク周辺では、その両者がどちらも銀色のアンテナを立てた姿で肩を寄せ合っているのだった。どことなく、ケナゲでいじらしい感じ。
1.Salvador
2.Sweet Leilani
3.Did You See Harold Vick?
4.Nightingale Sang in Berkeley Square
5.Charles M.
6.Moon of Manakoora
2005.11.08.Tue. 12 : 10 p.m.
BGM : This Is What I Do / Sonny Rollins
この日誌に似つかわしいタイトルのアルバムだにゃ。
私はきのうの午後、おたふく風邪経験の有無を検査する採血のためだけに3時間も病院にいた。経験が無いから予防接種を受けようとしているわけだが、しかし「経験が無い」は私と私の母親の記憶に基づく認識でしかなく、医者に「ホントにやってないですか?」と訊かれると、確たる証拠がないので断言はできない。ひょっとしたら本当はやったのに、ものすごく軽く済んだので気づかなかった可能性もないわけじゃないだろう。
無論、おたふく風邪経験者がおたふく風邪の予防接種を受けても健康上の問題がないなら、「無駄になってもいいから打ってくれ」と頼むところだ。ところが、それについては医者(たぶん70歳前後の耄碌系)も「どうなるのかなぁ」などと頼りないことを言いやがる。全然アテにならない。そんなことも知らない医者はイヤなので、診察の途中で「そんなことも知らない医者はイヤだ!」と捨て台詞を吐いて帰ろうかとも思ったが、そこで短気を起こしたのでは、診察室に入るまでに2時間以上も待った苦労が水の泡だ。それに、もし検査で「おたふく経験アリ」という結果が出たら、それはそれでミステリアスで面白い。なので採血をして、検査結果が陰性なら1週間後に予防接種を受けることにしたのだった。採血の注射は痛かったが、泣かずに最後まで我慢できた。また少しだけ大人になったような気がする。
採血を終えてから料金の支払いまで、また40分ほど待たされた。挙げ句に4960円も請求され、こっちのほうが痛くて泣きそうになった。しかし、「人をさんざん待たせた挙げ句にお金を取る奴」に文句を言う資格が私にあるかというと、きっと、ない。
ちなみに、今なら決してお待たせいたしませんので、なんか書かせろ。
5種類のリコーダーが揃ったのがうれしいので、並べて写真を撮ってみた。このところ無駄に写真が多いのは、先日デジカメを買ったばかりで撮りたい盛りだからだ。左から、テナー、アルト、ソプラノ、ソプラニーノ、クライネ・ソプラニーノ。誰もが学校で使ったはずのソプラノと比較すれば、テナーの巨大さとクライネ・ソプラニーノの可憐さがおわかりいただけるだろう。それぞれ、ものすごく近くやものすごく遠くに置いてあるわけではありません。クライネ・ソプラニーノは、サッカーの主審に持たせることもできそうなサイズだ。これをグレアム・ポールさんが首からぶら下げているところを想像すると、けっこう和む。短いメロディを何種類か用意して、キックオフ、タイムアップ、オフサイド、ハンド、ゴールキック、コーナーキック、直接フリーキック、間接フリーキックなど場面によって吹き分けたら(着メロみたいだけど)きっと楽しいし、人の気持ちを逆撫でするようなあのホイッスル音がなくなれば、選手とのイザコザも減るんじゃなかろうか。「このレフェリーはいい笛を吹きますね」の意味も根底から変わるはずである。
そんな戯れ言はともかくとして、テナーリコーダーは右手の運指が辛いのもさることながら、息をたくさん使うのがきつい。肺に溜めた息を「小出し」にするような感覚で唇を振動させる金管楽器と違い、リコーダーは吐いた息がドドーッと丸ごと抜けていくので、トロンボーンよりテナーリコーダーのほうが苦しいかも。ギターのほうは両腕や背筋などの鍛錬が必要だが、こちらは腹筋の増強や肺活量のアップが求められる。中高年がフィジカルを鍛えようと思ったら、怪我をしやすい過激なスポーツに手(や足)を出すより、何か楽器を始めるのが良いのかもしれない。
1.Tenor Madness
2.When Your Lover Has Gone
3.Paul's Pal
4.My Reverie
5.The Most Beautiful Girl In The World
2005.11.07.Mon. 17 : 40 p.m.
BGM : Tenor Madness / Sonny Rollins
うれしい話から始めよう。
きのう、サッカーの練習を終えて帰宅したセガレが、玄関に入ってくるなり、どうだと言わんばかりの勢いで「5回バッヂ!」と誇らしげに掲げて見せたのは、ボール・リフティングが5回できるようになった者にコーチから授与される「勲章」であった。コーチの見守る「試験」を一発でクリアしたというから、やはり本番に強い奴だ。数週間前に公園で練習につきあってやったときは3回が限度で、それも最後に脚を伸ばしてようやく3回になる(つまり4回目の可能性を微塵も感じさせない)ような状態だったので、5回できるのは3年生になってからだろうと思っていたのだが、どうやら毎日のように一人で練習に励んでいたらしく、親の予想を裏切るペースで上達しやがったのがうれしい。本人も、努力した自分にとても満足している様子だった。私がギターを習い始めた背景には、できることしかやろうとしないセガレに「できないことも練習すればできるようになる(こともある)」を身をもって教えたい、というたいへん立派な動機もあったのだが、先に結果を出されてしまってちょっと悔しい。おさらい会では、「リフティング5回」を上回るレベルのパフォーマンスを見せなければ。
その後、夕刻に東京国際フォーラムのホールAへ。某誌編集部のS氏が、ソニー・ロリンズのコンサートに誘ってくれたのである。おそらくは今回が最後の来日公演で、私にとっては最初で最後の生ロリンズだ。ありがたやありがたや。しかも前から10列目の中央やや下手寄りという、願ってもない絶好のポジションである。本来はそこに座るはずだったのに来られなくなったS氏の奥さんには申し訳ないけれど、最高に嬉しかった。あいにくの雨天だったものの、そういえば私がNHK−FMの生中継を聴いてソニー・ロリンズを大好きになるきっかけになった1981年のライブ・アンダー・ザ・スカイも土砂降りの田園コロシアムでの演奏だったので、なんとも感慨深い。ソニー・ロリンズは雨男なのかもしれない。
真っ白なヒゲに真っ赤なズボンという出で立ちで登場したソニー・ロリンズは、ちょっとフライング気味に出勤したあわてん坊のサンタクロースみたいだった。サンタのおじさんと違うのは、大きな白い袋を背負う代わりに首から金色のテナー・サックスをぶら下げていることだが、そこから次々に出てくるものは、サンタと本質的には違わない。年老いた巨人は、客席を埋め尽くした人々に真心のこもったプレゼントを配って回るような慈愛に満ちた表情で、その一つ一つにぎっしりと中身の詰まったすばらしい音を聴かせてくれた。81年の生中継で最も強烈な印象を受けた『Don't Stop the Carnival』も聴けた。24年前に私を打ちのめしたほどの豪快さやスピード感はさすがに失われているものの、図太くてハリのある音は「嗚呼これがロリンズだよなぁ」と私を感激させるのに十分なものだったし、「まだ吹くかコイツは」と思わせながらも1秒たりとも聴き手を飽きさせることのない長いソロには心底からシビれました。1曲終わるたびに、盛大な拍手に応えて小さくガッツポーズをしてみせたのは、決して単なるファンサービスではなく、自分の演奏に大いなる手応えを感じたが故の振る舞いだったに違いない。何十年も同じ姿勢で楽器を吹いてきたせいで骨格が歪み、左肩が右肩よりも高くなってしまった異様なシルエットに、極限まで努力と練習を積み重ねてきた人間の凄味を見た。
コンサートが始まる前にヤマハ銀座店に立ち寄り、シギーたちと結成したリコーダー・アンサンブルで使う楽器を物色。夥しい種類の楽器が並んだショーケースを眺めていると、どうしたって木製の本格派(右手小指用のキーも金属でピカピカだ)が欲しくなるのだったが、値段がプラスチック製の10倍ぐらいする(私のギターと大差ない)ので手が出ない。まあ、ギターだって国産の中級品から始めたわけだから、リコーダーも最初から高級品なんか使わないほうがいいというものだ。と、自分に言い聞かせながらヤマハのテナーリコーダー(YRT-304 B II)を購入。きょう、シギーが自らアレンジした譜面を送ってくれたので、リコーダー界のテナー・マッドネスを目指して練習することにする。ちなみにヤマハ銀座店では、クライネ・ソプラニーノ・リコーダー(ソプラノの1オクターブ上。ソプラニーノよりさらに小さい)もべつに必要ないのに勢いで買ってしまったのだが、こちらは両手の指をカンナで削らないと演奏できそうにない。
その前日の土曜日には、ボルシチ作りにトライ。言うまでもないが、このロシア料理にはビーツが不可欠なのである。あまり売っていない野菜だが、三浦屋の棚の隙間で名札もつけられずにひっそりと隠れていた長野産を発見。ビーツを手にしたのは初めてだ。また人生の経験値が増えたわけだが、しかし、これほどまでに猟奇的な食材がほかにあるだろうか。いや、ない。「皮」というより「皮膚」もしくは「肌」っぽい表面を剥ぎ取る……いや剥くために包丁を入れると、そこからは赤黒い液体がポタリポタリと滲み出し、手やら俎板やらを毒々しく染め上げるのだった。いかにも罪と罰を感じさせる野菜である。嗚呼、ラスコリニコフ。そのビーツを、玉ねぎ、にんにく、豪州産の牛肉、にんじん、トマト、セロリ、キャベツ、かぶ、じゃがいも、水、赤ワイン、トマトピューレ、ベイリーフなどと共に鍋の中でグツグツ煮込むと、それはまさに血の池地獄へようこそヘッヘッヘェ〜ッといったような風情になるのだったが、そんなことを台所でブツブツ呟いて家族に「やめなさい」と叱られながら最後にサワークリームを加えて完成させたボルシチは、たいそう旨かった。寒い季節は料理がたのしい。
さて、そろそろ悲しい話をしなければならないのだが、けさビデオで観戦したマンチェスターU×チェルシー(プレミア第11週)のことなんか今さら思い出して充実した週末の余韻を台無しにはしたくないのだし、きょうの午後おたふく風邪の予防接種に必要な診察を受けに病院に行ったらさんざん待たされて3時間も浪費してしまい、もう晩飯の時間が近づいていて家に帰らなければいけないので、書かない。ボールを80%も支配されて自陣に釘付けにされていた後半のユナイテッドは、スペイン戦におけるサンマリノのようだった……とだけ、悔し紛れに小声で呟いておくことにしよう。ちぇっ。