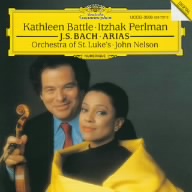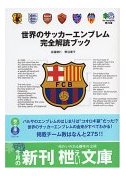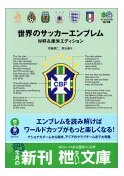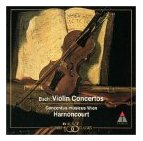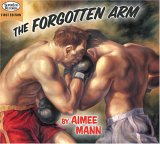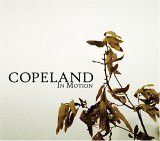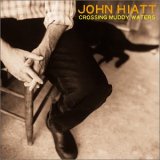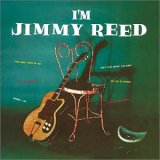Kathleen Battle
Itzhak Perlman
1.カンタータ第197番~第8曲
2.カンタータ第58番~第3曲
3.カンタータ第204番~第4曲
4.カンタータ第97番~第4曲
5.カンタータ第115番~第4曲
6.カンタータ第171番~第4曲
7.「ロ短調ミサ曲」~第23曲 /第5(6)曲
8.カンタータ第202番~第5曲
9.カンタータ第36番~第7曲
10.カンタータ第187番~第5曲
11.カンタータ第84番~第3曲
12.カンタータ第105番~第5曲
平成十八年四月二十一日(金) 午後一時二十分
BGM : J. S. バッハ ソプラノとヴァイオリンのためのアリア集
相変わらずセガレはサッカーのエンブレムにハマりっぱなしで、実在するものを模写するだけでは飽きたらず、架空のフットボールクラブ(「レッド・デビル・スパイダーズFC」とかそういう名称)を創り出し、そのエンブレムをデザインしたりもしている(背番号付きのメンバー表まである!)のだった。フットボールクラブは地名を冠するのが基本だということを教えなければいけない。
で、この「エンブレム好き」はセガレだけの特殊な趣味だとばかり思っていたのだが、どうやらそうではないようだ。去年発売された『世界のサッカーエンブレム完全解読ブック』(斉藤 健仁、野辺 優子 /木世文庫)という本があり、最近になって第2弾『世界のサッカーエンブレム W杯&南米エディション』(同)も刊行されたので、おそらく売れ行き好調なのだろう。第2弾のほうは売り切れだったので注文したほどだ。ちなみに「木世(えい)」は二つで一文字。パソコンで出ない漢字を社名に使うと検索しにくいので商売的に不利なんじゃないかと思うが、それはともかく、書店で見つけるやいなやセガレに買い与えたことは言うまでもない。たぶん小学生を中心に売れているのだろうと思われ、これを企画した編集者はなかなかの炯眼の持ち主といえよう。そういえば私も小学生の頃、プロ野球チームのエンブレムを盛んに書いて切り取っては筆箱の中にコレクションしたりしていた。男の子は、こういうシンボリックなものが好きなのかもしれない。
いずれにしろ、エンブレムには歴史や地理の情報がぎっしり詰まっており、その解説を読むのは世界を知るためのひとつの入口になるので、教育的にもなかなか良い企画である。サッカー好きな出版業界人としては「やられた」って感じもありますが。『完全解読ブック』のほうは欧州中心だが、『W杯&南米エディション』のほうはドイツ大会出場国はもちろん、北中米、アジア、アフリカのクラブまで載っている。さらに日本の地域リーグまでフォローしており、あのカマタマーレ讃岐まで掲載しているのには笑った。カマタマーレのうどんエンブレム、こうして各国のものと一緒に並べてみると、その良し悪しは別にして、世界に類を見ないほどユニークなデザインであることだけは間違いない。
ゆうべは、アーセナル×ビジャレアル(CL準決勝第1戦)をビデオ観戦。この試合でいちばん美しかったのは、フィールド上を全力で駆け抜けるリスたちの走行フォームだったような気がしないでもない。なんだか噛み合わせの悪い、ぎくしゃくしたゲームだった。「あんまりいいディフェンダーじゃない」という解説者の誹謗中傷に奮起した(わけではないが)コロ・トゥレの電光石火ゴールで1-0。あの反射神経はリスを凌駕していた。先制されても消極的な攻めに終始していたビジャレアルは「1-0で良し」と考えているようにしか見えなかったが、1-0で良しと考えていたのだろうかどうだろうか。そのへんの考え方がよくわからない。
1.イタリア協奏曲ヘ長調BWV971
2.パルティータ第1番変ロ長調BWV825
3.パルティータ第2番ハ短調BWV826
4.フランス組曲第2番ハ短調BWV813
5.フランス組曲第6番ホ長調BWV817
6.イギリス組曲第2番イ短調BWV807
平成十八年四月二十日(木) 午後三時四十分
BGM : J. S. バッハ イタリア協奏曲ほか / Glenn Gould
ゆうべは、ミラン×バルセロナ(CL準決勝第1戦)をビデオ観戦。せっかくインテル戦を休ませてもらったのに風邪をひいて欠場してしまうあたりが、ピッポさんの間抜けなところである。「温存」っていうぐらいなんだから、ちゃんとお布団かけて、あったかくしてなきゃダメじゃないか。一方のバルサもデコが不在で、そのせいか両軍とも若干やんちゃ不足の感があったが、ともあれ試合はジュリの一発で0-1。厳しいマークを嫌ってやや引き気味にポジショニングすることでボールタッチの回数を増やし、最後はガットゥーゾを振り切って難しい体勢からタテのラストパスを決めたロナウジーニョのプレイぶりは、奇しくもその翌日、第24回朝日オープン将棋選手権(五番勝負第2局)で羽生選手権者が見せた「引き角戦法」にちょっと似ていた。角道を開けず後手3一角としてから前進させるのが引き角戦法であるらしく、それが何を目的とした戦い方なのか私にはさっぱりわからないし、羽生選手権者のほうは藤井九段の穴熊をまったく崩せないまま負けちゃったわけですけども。サッカーは知っているが将棋を(私以上に)知らない人のために説明しておくと、穴熊というのは要するにカテナチオのことだ。と、思う。ミランも第2戦はクマさん(スタム)をセンターに置いて、がっちり玉を囲ったほうがいいんじゃなかろうか。それにしても「羽生選手権者」ってすごい日本語。
そんなわけで、最近はよくわからないまま将棋のニュースなど眺め、その世界の雰囲気だけでも理解しようとしているのだが、ペコペコと駒が動くアサヒ・コムの「指し手再生」はライブ観戦感覚で楽しめてなかなかよい。一方、名人戦を主催している毎日新聞のほうは、どうやら月額500円も払って会員にならないとネット上の棋譜速報も見られないようだ。名人戦のような公共性の高いビッグイベントの報道が、こんなふうに新聞社に独占されているとは知らなかった。で、今はその名人戦の契約をめぐって朝日と毎日が戦っているらしい。そういうのってサッカー中継だけじゃないんだなぁ、と妙なところに感心。事情を全然知らないのでアレだが、名人戦もタダで指し手再生を見せてくれるなら、これに限っては朝日を応援してやってもいい。
カルロ・マリア・ジュリーニ指揮
バイエルン放送交響楽団&合唱団
平成十八年四月十九日(水) 午後一時二十分
BGM : J. S. バッハ ミサ曲ロ短調 / Carlo Maria Giulini
きのうの夕刻、仕事場の電話が鳴った。最近はかかってくる電話の9割がセールスであるにもかかわらず、その瞬間、どういうわけか「あ、単行本の発注だ」と揺るぎない確信を抱いたのは、仕事減に対する強い危機感が第六感を鋭敏にさせていたからだろうか。受話器を取ると、すっかりご無沙汰していた集英社インターナショナルのS氏が「儲かる話があるんだけど(笑)」と言うのだから私の予知能力も捨てたもんじゃない。ほんとうに「儲かる」かどうかは定かではないが、仕事をすればふつうに「稼ぐ」ことはできるのだし(「稼ぐ」より「儲ける」が奨励されるのがバブルというものだろう)、ニタニタと薄笑いを浮かべながら書けそうな愉快な企画なのでありがたい。著者の名はむろん明かせないが相当に強烈な個性の持ち主で、ことによると「わたし」でも「ぼく」でも「おれ」でも「わし」でもない珍しい一人称で初めて原稿を書くことになりそうな気もする。どういう一人称かというと、それを明らかにするだけで正体がバレてしまうほどユニークな人なのだった。でも、それほど個性的な人なのに、素顔で現れたときにそれがその人だとわかる自信がない。……おっと、ついヒントめいたことを書いてしまった。
素顔といえば、1月に井上陽水さんにインタビューする機会があった(その記事はいま行われているコンサートツアーの会場で販売されているパンフレットに掲載されているので聴きに行かれた方には買って読んでいただきたい)のだが、撮影のない取材だったのでトレードマークのサングラスをかけておられず、そのためこっちは「陽水」に会っているような実感がなかなか得られなくていささか戸惑った。たぶん、あの井上さんと街頭ですれ違っても、話し声でも耳にしないかぎり100人のうち99人はそうだと気づかないだろう(声を聞けば一発でわかってしまうのが井上さんの凄いところですが)。メディアに顔をさらす著名人は日常生活で変装しているケースが多いけど、仕事で変装して日常で素顔を出している人のほうがはるかに楽そうである。そういえば先日、電車で向かい側の席に座っていた人が、ぜんぜん著名じゃないフリーライターの似顔絵が載っている雑誌の該当ページを開いて読んでいたので、思わずメガネを外したりなんかしちゃったものだが、これは完全無欠の自意識過剰。
それはともかく、家に帰って「単行本の仕事が入った」と愚妻に報告したら、思いがけず「やったぁ!」とまるで子供が入試に合格したかのごとき大きな反応を見せたので、そんなに夫のニート状態を心配していたのかと申し訳ない気持ちになった。もっとも愚妻的には、夏休みの旅行が規模縮小されるのを心配していただけかもしれんけど。いずれにしろ、まだまだスケジュールには空きがありますので、家族をより深く安心させるためにも、引き続き各社からのご連絡をお待ち申し上げております。だけど、6月に忙しくなるのはちと困るなぁ(←わがまま)。
この日誌を始めたのは1998年だが、BIG INNING PROJECTを名乗るサイト本体を開設したのは1996年の春だったような気がして、アップしたファイルの日付を確認してみたら、最古の記録は96年3月24日だった。うっかり創立記念日を通り過ぎてしまったわけだが、ともあれ創業10周年である。愚妻のMac(往年の名機IIci)を譲り受けてから約4ヶ月後、その扱いにも慣れてきてサイト構築を思い立ったのは、まだニィパッパのモデムが「ピ〜ガガガガ〜」と唸りをあげていた時代のことである。友人知人のサイトを参考にしようにも、そこへたどり着くこと自体が難儀だったが、見よう見まねでいろいろ試行錯誤をしていたことを懐かしく思い出す。いまから思えば尋常ならざる時間と労力を費やしていたし、仕事よりもそっちのせいで視力低下が始まったような気もするけれど、あれは楽しい作業だった。意味もなくカニの絵を動かすことにどれだけの情熱を傾け、その代償としてどれだけの視力を失ったかと思うと、とてもバカバカしい。でもおもしろかった。
そういえば当時は、HTMLのマニュアル本やインターネット雑誌等で、「クリッカブル」なんて言葉を盛んに目にしたものだ。たぶん「クリックするところが多いウェブページほど良い」という評価基準があったわけで、なんでそんなにクリックしたかったのか今となってはよくわからない。私もよそのサイトへ行くと、ページの中身を読みもしないでひたすら手当たり次第にクリックしていたことがあった。「クリック・フェチ」かよ。なんだかヤらしいですね。ンもう〜、タカシ君ったらクリックばっかりなんだから〜ン。しかし要は、みんな、リンクという機能で「つながっている」ことが妙に嬉しかったんだと思う。ズラズラと個条書きしたリンク先しかコンテンツのない本末転倒なサイトも少なくなかった。WWWという底無しの巨大な空間の中で、ちっぽけな自分が「ここにいる」ことを正当化するには、「リンクを張ってつながる」がいちばん手っ取り早い方法だったのかもしれない。無意識のうちに、「なにしろリンクしてるんだからオレはここにいていいんだ」と自分自身を納得させているような面が私自身にもあったような気がする。つまり、何が目的だかよくわからんがとにかくネット上に「存在すること」自体が大事だったんだろう。表向きは「自前の文章を書くトレーニングの場だ」とか何とかもっともらしい目的意識を掲げてはいたし、結果的にはそのおかげで自前の文章を商業メディアに書くチャンスを得ることができたとはいうものの、実のところ、「なぜウェブサイトを作るのか」と問われたら、「そこにインターネットがあるからだ」としか答えようがなかったというのが本音である。
では、それから10年が経った今、私がこうして(ときおりモチベーションの低下がありながらも)ウェブ上に何事かを書き続けるのはなぜなんだろう。正直に言うと、自分のウェブサイトを公開し、そこにロクでもない文章を書き連ねるのは「恥ずかしい」という意識が、私の中には常にある。拭いようもなく、ある。おまけに時間や体力の浪費も甚だしい。恥ずかしい上に無駄が多いならやめればいいのだし、事実「できることならやめたい」という思いがないわけでもないのだが、それでもやむにやまれずやってしまうのが、私にとっての「ウェブ上で書く」だ。いわば依存症、早い話がビョーキである。人のウェブ日記やブログを眺めていると、続けることに義務感や責任感や使命感みたいなものを感じているのか、更新が滞ることを「悪いこと」だと考えて悩んだり自分を責めたり読者に謝ったりしている人が多いけれど、こんなもん、更新せずに済むならそれに越したこたぁないんじゃないスか? と、私なんかは思うのである。だって、ビョーキなんだから。もっと大切なことが、日常生活の中にはたくさんあるんだから。ほかの手段で自分が「ここにいる」ことを明らかにしつつ自己愛やら自尊心やらを満たしたり孤独感を癒したりしたほうが、よっぽど健康なんだから。じっさい、家族とべったり過ごして日誌を更新していなかった春休み中の私は、とても健やかな日々を送っていた。富士五湖めぐりをしたり高尾山に登ったり花見をしながらセガレと将棋を指したりと、書ける「ネタ」は掃いて捨てるほどあったけれど、春休みが終わるまでは「日誌を書きたい」なんて1ミリも思わなかった。自分がそうだから、更新が滞っている友人知人のサイトを見ると、ああ健全な毎日をお過ごしなんだろうなぁと逆に安心したりする。
以前、テレビのニュース番組か何かで、深夜までブログ制作にハマってしまい、帰宅して風呂上がりのビールを飲んでいる夫の相手もしようとしない主婦の日常を取り上げていたが、あれは目を背けたくなるほど痛々しい風景だった。自分のやっていることに対する恥ずかしさが一気に倍増した。マジでもうやめようかと思った。10年前はそこに「参加する」こと自体に何らかの意味があった(かもしれない)WWWだが、今はそれを「やめる」ことに何らかの意味がある時代になっているような気もする。でも、それはたぶん、煙草をやめるよりも難しいこと。
1.BWV1043
2.BWV1042
3.BWV1041
4.BWV1056R
5.BWV1060R
Concentus musicus Wien
NIKOLAUS HARNONCOURT
平成十八年四月十八日(火) 午後十二時二十五分
BGM : J. S. バッハ ヴァイオリン協奏曲集 / Alice Harnoncourt(violin)
ドイツ語の「ヨハン=Johann」(英語の「ジョン=John」)はスペイン語の「ファン=Juan」だということを何かの拍子に知り、おおそうか、ならばヴェロン(Juan Sebastian Veron)の名付け親は大バッハにあやかったのかもしれん!と一人で藪から棒に感動しているわけだが、きのうビデオで観たミラン×インテル(セリエ第34節)にJ.S.ヴェロンは出場していなかった。その代わりに(というわけでは全然ないが)先発していたミハイロ翁も、わずか10分走っただけで脚が痛くなっちゃってアウト。スタムもいないし、ミラノダービーをラツィオのOB戦のつもりで見ている身としては残念である。しかもミハイロ翁と替わって入ったのがマテラッツィとあっては、まあ人格の邪悪さの点では甲乙つけがたい御両人だとはいえ、インテルに肩入れする義理はない。濡れ乱れたマテラッツィの顔を見て、「なんか井戸の底から這い上がってきたみたいだよな」と言ったら、妻子から「怖いからやめてよ」と抗議された。たしかに井戸から顔を出したマテラッツィを想像するとかなり怖い。そんなもん誰だって怖いですけども。そういえば、まったく関係ないが思い出したので書いておくと、愚妻がバルサTVから仕入れた情報によれば、ジュリはチームメイトから「ヒゲ生やしたらフレディ・マーキュリーそっくり」と、からかわれているらしい。いい話だ。CLで優勝した暁には、是非つけヒゲとステッキ状のマイクスタンドを用意して、場内に流れる『We Are The Champion』にアテ振りしてもらいたい。ブライアン・メイのエアギターのほうは髪型的にプジョルがお似合いだと思う。すっかり何の話だかわからなくなっているが、試合はカラーゼのゴールで1-0。
引き続き、トッテナム×マンチェスターU(プレミア第31週)をライブ観戦。ユナイテッドが勝ち点を落としたらチェルシー戦もライブで観ようかと思っていたのだが、序盤はトッテナムが猛烈に押し込みながらも鮮やかなカウンターを一発で決めたユナイテッドが先制、さらに、ナントカという韓国人がナントカという韓国人にゴール前でボールをかっさらわれて0-2、後半にトッテナムが1点返したもののチェルシーの優勝は持ち越しとなったので、エバートン戦は観ないで寝た。コンディションが悪かったのか最近はいつもあんなもんなのかわからないが、ちょっと太ったようにも見えるダビッツが鈍いプレイに終始していたのが寂しい。
1.第1番ロ短調BWV1002
2.第2番ニ短調BWV1004
3.第3番ホ長調BWV1006
平成十八年四月十七日(月) 午後一時二十分
BGM : J. S. バッハ 無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ / Gidon Kremer(violin)
板垣退助とかラーメンズの小林賢太郎とか私とかの誕生日である。ラーメンズの年齢は知らないが、私は42歳になった。37歳頃からときどき自分の年齢を忘れるような状態なので、今更とくに感慨も感想もないけれど、仕事もしていないのに疲れ目がひどい(左目に異物感のようなものもある)し、小林よしのり先生の『目の玉日記』(小学館)など読んでいろいろ心配になってきたこともあって、さっき久しぶりに眼科に行って診てもらったら、いよいよ老眼が始まったという。まだ初期段階なので老眼鏡は作らず、ややドライアイ気味であることも疲れ目の一因なので、当面は点眼液でしのぐことに。老眼について医者は盛んに「ショックでしょうけど」などと言って気を遣ってくれたが、べつにショックはなく、それはまあそういうもんでしょうと思うだけである。むしろ、緑内障とか白内障とかの心配はないと聞いて安心した。安心する42歳。
土曜日に、渋谷のスタジオで行われた東京カナデルバッハの練習に参加した。いきなりそんなことを言われても困るだろうが、昨年から始めたリコーダー同好会にそういう名称がついたのである。基本形は「東京カナデル(Cana Del Tokyo)」で、今年はバッハを中心に演奏するので「東京カナデルバッハ」なのだった(ちなみにこのユニットとはまったく関係ないので念のため)。モーツァルト・イヤーにバッハというのが天の邪鬼なところである。最近、装幀家S氏がメンバーに加わって総勢5人となり、編集者、校正者、デザイナー、ライターを擁する編プロもやれそうな集団になったのだが、しかし休日に集まって本を作ってもバカなわけで、年内に発表会のようなことをやりそうな雲行きになっている。うへえ。まじですか。そんなこととは思わずレクリエーション気分でぶらぶら参加していた私としてはかなりうろたえているし、ギターもあるのにそんなことしてる場合なのかおまえはという話だが、しかし、それはまあそういうもんでしょう。それはまあそういうもんでしょう、と呟き続けて42年。どういうわけか音楽にどっぷり浸っている友人にぐるりを取り囲まれた人生だ。ともあれ、ロックとバロックは字面もわりと似てるし、「音楽の上達」という意味で相乗効果もあるに違いない。実際、こうして『無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ』を聴いていても、考えるのは主にギターのことである。いま、「無伴奏エレクトリックギターのためのアメイジング・グレイス」とでも呼べるような課題にも取り組んでいるので、何かと参考になる。歌う技術。カナデル技術。
きのうはボルトン×チェルシー(プレミア第31週)をビデオ観戦。相変わらずどんな歌を歌いたいのかはっきりしないチェルシーだが、ボルトンがそれに輪をかけて音痴だったことにも助けられ、ドログバとテリーの世にも珍しい同時一発ヘッドとランパードのゴールで0-2。で、残り4試合で2位マンUと9ポイント差ってことは、えーと、今夜チェルシーがエバートンに勝ってマンUがトッテナムと引き分け以下だと優勝が決まるっていうことだな。向こうが負ければこっちは引き分けでも決まりか。そうかそうか。いやはや、良い誕生日になってほしいものであるなぁ。4位を争っているアーセナルのファンには悪いが、がんばれトッテナム!
1.Dear John
2.King of the Jailhouse
3.Goodbye Caroline
4.Going Through the Motions
5.I Can't Get My Head Around It
6.She Really Wants You
7.Video
8.Little Bombs
9.That's How I Knew
This Story Would Break My Heart
10.I Can't Help You Anymore
11.I Was Thinking
I Could Clean Up for Christmas
12.Beautiful
平成十八年四月十四日(木) 午後十二時四十分
BGM : The Forgotten Arm / Aimee Mann
味のあるイラストをあしらったデジパックの表紙を開くと、古ぼけたペーパーバックを思わせる赤茶けたザラ紙に歌詞と挿絵を掌編小説集のような体裁でプリントしたブックレットになっており、あえて「一枚」ではなく「一冊」と呼びたくなるような代物になっているのが、いま聴いているアルバムのジャケットである。「音」と「モノ」のコンビネーションによってある独特な世界を創り出そうとする渋いけれど実に意欲的な試みが成功していて、とても良い。パッケージ大賞を差し上げたくなるような一品。
きのうはKay'n師匠のところでギターのお稽古。しばらくギターのことを書いていなかったような気がするが決して放り出したわけではなく、仕事がヒマなので練習はかなりしているのであり、三歩進んで二〜三歩下がる日々である。戻っちゃいけないが、練習をサボれば下手になるのはもちろんのこと、たくさん練習したらしたで腕や指の筋肉が疲労のせいで硬くなって動かなくなってしまったりするのが、中年ビギナーの辛いところなのです。
とはいえフィジカルのことばかり気にしているわけにもいかないのであって、いま主に取り組んでいるテーマは、ざっくり言えば「歌う技術」みたいなこと。単音のメロディにしろバッキングにしろ、頭の中で鳴っている歌をイメージどおり楽器に歌わせるのは、とても難しい。弾き手に「歌心」みたいなものがあれば楽器が歌うかというと、全然そんなことはないのである。むろん、私の場合はそもそもの歌心自体が知れたものなのでそちらを涵養することも同時に進めなければいけないのだが、たとえばカラオケで「ちょっと自分なりに崩して歌う」程度の誰もが直観的にできることでも、当たり前だが楽器は弾き手の直観なんか察してくれないから、いくつもの技術が必要になるのだった。まあ、何だってそうだけどな。高度な戦術眼があってもボール蹴るのが下手じゃスルーパスは出せないし、企画力があっても原稿を書いたり書かせたりする技術がなきゃ本は作れない。ボールも原稿も念力では進まないのである。
もっとも世の中には人間に念力を与えてくれるパソコンという道具もあって、たとえば色指定や写植指定のできない素人でも自分のイメージしたグラフィックデザインをお手軽に作りあげちゃったり、墨さえすったことがない人間でも立派な毛筆書体で年賀状の宛名を書けちゃったり、マス・コミュニケーションの技術がなくても物書き気分で情報発信しちゃったり、楽器が弾けなくても音楽を作っちゃったりできるわけで、そうやってテクノロジーがテクニックを駆逐していくことを私たちは「便利」と称して歓迎しているのであるが、しかし退化もまた環境に適応した結果としての進化のうちだとはいえ、いいんだろうかそういうことばっかりで。というのが、私がギターを習い始めた動機の一つでもあるんである。私はうまくなりたい。歌うように弾きたい。それは別の言い方をすると、たぶん、「書くように弾きたい」ということなんだろうと思う。
それはともかく業務連絡をしておくと、課題曲としては、きのうからZEPの『コミュニケーション・ブレイクダウン』をやり始めたので、おさらいブラザーズ(仮)の諸君は頭の片隅に置いておくように。さらにもう一つ、報告しておくことがある。レッスン終了後、師匠のこしらえてくれた麻婆豆腐に舌鼓を打ちビールをがぶがぶ飲みながら、諸般の事情を踏まえつつ慎重に検討を重ねて参りました結果、穴馬はアッと驚く大三元、ジーコ退任後の次期日本代表監督はドイツのルディ・フェラー氏に就任を打診すべし、という思いがけない結論に到ったところで審議を終えました。どういう流れでそんな議題になったのかはすっかり忘れたし、ローマの元ヒーローを迎え入れるのは私としても内心忸怩たるものがあるのだが、主な理由は(1)日本人監督は論外、(2)トルシエも選手にラマダンとか強要しかねないので論外、(3)メンタリティの面で日本人とは相性が良さそうだしメキシコ五輪時代のクラマーさんの前例もあるのでドイツ人なんかいいんじゃねぇのか、(4)EURO2004で結果は出せなかったもののフェラーが採用した3−4−3はあんがい日本に適した面白いシステムだと思われる、(5)愛嬌があるので人気も出そう、といったところ。うちの師匠が「ハンブルガー・フォーメーション」と名づけたフェラーの3−4−3について知りたい人は、こちらのページを参照するように。
1.No One Really Wins
2.Choose the One Who Loves You More
3.Pin Your Wings
4.Sleep
5.Kite
6.Don't Slow Down
7.Love is a Fast Song
8.You Have My Attention
9.You Love to Sing
10.Hold Nothing Back
平成十八年四月十三日(木) 午前十一時三十五分
BGM : In Motion / Copeland
アマゾンなどの通販と違い、CD店に足を運んだときには、いわゆる「ジャケ買い」をしてしまうことが多い。近頃は(そうでもしないとダウンロード文化に対抗して「モノ」として売るのが難しくなっているのかもしれないが)紙ジャケ、デジパック、紙ケース入りなど写真やイラストをきれいに見せるパッケージが増えてきたようで、ネット上の写真ではわからないその質感やデザインの美しさを目の当たりにすると、ついグッと来て欲しくなってしまうのである。いま聴いているコープランドというバンドのアルバムも、そんな一枚。もちろんコープランドのことは何も知らず、「フロリダ出身のエモ・バンド」と言われても、エモ・バンドが何のことだかわからない。エモはエモーショナルの略だろうか。エモーショナルではない音楽のほうが探すのに苦労するような気がするので、わざわざ「エモ」と呼ぶ理由がどこにあるのか不明だが、まあ、「エモやん」だって別にエモーショナルの略ではないわけだから、これも違うのかもしれない。「プロデューサーがアホやからレコーディングでけへん!」とかゆうてスタジオを飛び出してしまうような気の短いバンドの総称か。そんなわけはありませんね。ともあれ、なかなか美しいロック・ミュージックで、わりと気に入ったのであるが、それもこの美しいジャケットの印象が手伝ってのことであるのは間違いないのであり、やっぱりレコード芸術(!)というのはパッケージも含めたトータルなものであってもらいたいなぁと思うのだった。iPodも悪くはないし、私もちょっと欲しいと思わないでもないけれど、なんかこう、音楽を詰め替え用の台所洗剤やインスタントコーヒーみたいに消費するのはひどく味気ないと思うのである。音楽のパッケージほどデザイナーが制約を受けずに腕をふるえる「何でもアリ」の舞台は少ないと思うので、大事にしたいものだ。それにしてもこのバンド、これでスーペルなギタリストがエモなソロでも歌い上げてくれたら最高だと私なんかは思うのだが、そういうロックは今時あまり求められていないのだろうか。
ヒマなので誰か仕事ください。
1.Lincoln Town
2.Crossing Muddy Waters
3.What Do We Do Now?
4.Only The Song Survives
5.Lift Up Every Stone
6.Take It Down
7.Gone
8.Take It Back
9.Mr. Stanley
10.God's Golden Eyes
11.Before I Go
平成十八年四月十日(月) 午前十時四十分
BGM : Crossing Muddy Waters / John Hiatt
新規採用だが「おばさんっぽい」セガレの担任は、29歳だということがわかった。新卒でもおばさんでもない。年齢的にはどちらもアリなので、一般選考なのか特別選考なのかもわからない。以前は学童保育の先生をしていたそうだから、それほど大胆な転身でもない。いろいろ想像したのがアホらしい。ふつうに頑張ってくれそうなので、話のネタになるような気もしない。いまどき、話のネタにならない教師ほどありがたいものはないのだけれど。
で、ふと、自分が29歳のときに何をしていたのだろうかと振り返ってみたら、そのころ私は、あろうことか、専務取締役をやっていたのだった。といってもそれは紙の上だけの肩書きで、先輩と一緒に立ち上げ(て一年後には解散してい)た編プロで今と何ら変わることのない過酷な労働にいそしんでいたわけだが、まあ、なんか、そんな転身をしてみたくなる、ややこしい年代なのかもしれない。その後、その編プロの仕事を通じて知り合った人と結婚して、子供が生まれて、四十を過ぎて、今はあまり人生がややこしくなくなったような気がする。たぶん、それは、いいこと。
金曜日の放課後、一家三人で府中のTOHOシネマズに行き、『レアル・ザ・ムービー』を観た。私はまるで興味がないのだが、セガレがクラブのエンブレム(こういうやつ)を「見ないで描ける」ほどの熱心なマドリディスタなので、まあ、しょうがない。スペイン、日本、アメリカ、セネガル、ベネズエラを舞台にしたショートストーリーと04-05シーズンのクラシコを絡めて織り上げられた、ろくでもない映画。オーウェンとかフィーゴとか、もういないし。もっとも、セネガルとベネズエラのエピソードはちょっと(だけ)いい話だったから、ベッカム狂いの女子高生とそのカレシを主人公にした寒々しい日本編と、大学生の女子サッカー選手が脚の怪我と戦う安っぽいアメリカ編がなければ、まだマシだったかもしれない。つまり「経済的に豊かな国の若者」は「ちょっといい話」にしづらい、ということだろうか。見ていて唯一「なるほど」と思ったのは、ルシェンブルゴがRAULを「ハウール」と呼んでいたことぐらい。じゃあ、REALは「ヘアル」なのかな。「ヘアル・マドリー」って、ものすごく弱そうだな。なにしろへだもんな。観賞後、セガレの右目には涙が滲んでいたが、それは、初めて日本語字幕の映画を観て目が疲れたからだったようだ。
それにしてもセガレのエンブレムへの執着は凄まじい。母親からデザイナーのDNAを貰ったせいかどうかわからないが、マドリーだけでなく、世界各国のクラブのエンブレムを『ワールド・サッカー・キング』とにらめっこ(時には虫眼鏡で細部を観察)しながら山ほど描いている。どうやら自分でピンバッヂを手作りするつもりらしい。イタリアやスペインやイングランドの主要クラブはもちろん、きのうはコリンチャンス(ブラジル)やインデペンディエンテ(アルゼンチン)やオリンピア(パラグアイ)やコロコロ(チリ)やウニベル何とか(ペルー?)のエンブレムまで描いていた。小学校三年生の情熱って、よくわからない。
1.Honest I Do
2.Go on to School
3.My First Plea
4.Boogie in the Dark
5.You Got Me Crying
6.Ain't That Lovin' You Baby
7.You Got Me Dizzy
8.Little Rain
9.Can't Stand to See You Go
10.Roll and Rhumba
11.You're Something Else
12.You Don't Have to Go
平成十八年四月七日(金) 午後十二時四十分
BGM : I'm Jimmy Reed / Jimmy Reed
セガレはきのうが始業式。三年生になった。ウソのようなほんとうの話だ。そんなに慌てないで、もう少し二年生をやってたっていいんじゃないかと思う。人間の成長段階を一年単位で刻むことにどんな意味があるのか、考えてみるとよくわからない。
セガレの学年は、昨年度に引き続いて3クラス。転出者があって一時は2クラスに戻ると思われていたのだが、転入者があったおかげで総勢81人となり、ギリギリで3クラスになったわけである。いまさら役所の杓子定規に文句を言っても始まらないが、1人いるかいないかで、27人学級になったり40人学級になったりする制度って、教育について真剣に考えている人が作ったものだとはどうしても思えない。
担任は今年度から新たに着任した女性教師で、年齢はまだ不詳。セガレによれば「おばさんっぽかった」と言うのだが、職員名簿には「新規採用」と書いてある。東京都教育委員会のサイトを見ると、教員の採用には「社会人特別選考」なる制度があるようだから、それかもしれない。教員免許を取得していて、なおかつ「民間企業・官公庁等の常勤の職としての勤務経験が通算5年以上あるか、又は引き続き3年以上ある者」に受験資格があるという。免許があるのになんで特別枠が必要なのかというと、こちらは一般選考よりも受験できる年齢の上限が5歳上なのだった。なるほど。今年度の新規採用者の場合は「昭和36年4月2日以降に出生した者」だから、最高齢なら45歳だ。それぐらいの年代で、いきなり教員みたいな難儀な仕事に転身するのって、相当な覚悟というか決意というか情熱というか、何であれ「並々ならぬモノ」がないとできないんじゃないかと思われる。「並々ならぬモノ」を持った人って、ちょっと怖い。まあ、まだどんな人なのかわからないし、単に「やたら老けた新卒者」である可能性も捨てきれないわけだが、どうせならその特別選考とやらで採用された教員であったほうが、何かと話のネタにできておもしろそうだ。おもしろがってどうするんですかそんなもの。
初戦0-0で迎えたバルセロナ×ベンフィカ(CL準々決勝第2戦)は、2-0でバルサがベスト4進出。名前を忘れてしまったが、このゲームを担当したアナウンサーは「微妙」という言葉を安易に使いすぎるのがとても耳障りだった。「微妙な判定」「微妙なパス」ぐらいはまあまあしゃあないとしても、ロナウジーニョの「微妙な表情」まで行くと、プロの実況者が使う言葉ではないように思う。あんたは茶の間で感想言ってるわけじゃないんだからさ。その微妙さをうまいこと言って活写してみせちゃうのが、話芸ってもんでしょ。そういうことがしたくて、その仕事してるんじゃないの?
ユベントス×アーセナル(CL準々決勝第2戦)は0-0、agg.0-2でアーセナルの勝ち上がり。何人か主力が欠けていたとはいえ、ユベントスはこれがセリエAの首位チームだとは聞いて呆れるほどダメな戦いぶりだった。遅いし下手だしバカだし並々ならぬ覚悟や決意や情熱も見えない。だからぜんぜん怖くない。まるで倒産寸前の会社が無能な部課長を集めてダラダラとろくでもない意見を言い合っている会議を傍聴しているような気分にさせるサッカーチームって、最低だと思う。こんなことなら、あのブレーメンがこのアーセナルとビシバシ渡り合う試合を見てみたかったです。
1.Surfing With the Alien
2.Ice 9
3.Crushing Day
4.Always With Me, Always With You
5.Satch Boogie
6.Hill of the Skull
7.Circles
8.Lords of Karma
9.Midnight
10.Echo
平成十八年四月六日(木) 午前十一時十分
BGM : Surfing With The Alien / Joe Satriani
あまりに久しぶりなので何からどう書き始めてよいやらよくわからないが、とにかく、この二週間、一家三人でべったりと春休んでいたのだった。三月下旬には、二泊三日で山梨の石和温泉へ。滞在中、富士五湖すべてに(加えて忍野八海にも)足を運んだ。トップページの写真は河口湖畔で撮ったものである。ドライブしながら眺めた富士山は圧巻。カーブを曲がった先に富士が姿を現すたびに、へらへら笑いながら「あー、いたいた」「富士山デカいねー」「デカいねー」とアホのように同じセリフをくり返していた。やっぱり富士山はすごいよ。富士山の姿なんて写真や絵で見慣れてるし、ある意味陳腐なカタチだから、わざわざ見に行こうとはあまり思わないものだが、近くで見るとほんとうにびっくりする。三十六景を描きたくなる気持ちがよくわかった。さらに、コウモリ穴と鳴沢氷穴と富岳風穴も探索。私は「窒息」に対する恐怖感が人一倍強いようで、東京ディズニーシーの「海底二万マイル」でさえ一刻も早く脱出したくてパニック寸前になったほど閉所や水中や地底が苦手なのだが、セガレと愚妻は穴があったら入りたいタイプの人間で、洞窟を見れば喜々として潜りたがるので、冷や汗をかきながらつきあった。とても怖かった。
富士山を見て刺激されたというわけでもないのだが、一昨日は高尾山へ。小学校時代は遠足といえば高尾山だったが、それ以降は「山登り」という言葉自体が我が輩の辞書から消えていたような状態だったので、ちょうど30年ぶりの登頂である。できるかどうかちょっと不安だったが、セガレも愚妻もケーブルカーやリフトを使わずに頂上まで登り切った。みんなそれなりに元気で何よりだ。セガレは親が思っている以上に体力をつけ、逞しくなっている。
セガレとは将棋もさんざんやった。土曜日に砧公園で花見をした際、ヤマちゃんから「棒銀戦法」なる序盤の定跡を教わり、その後も本で勉強したりして、めきめき強くなっている。「好きなようにやればいいじゃん」などと言わず、素直に「型」を学ぼうとする姿勢を持っているあたり、もしかしたら才能あるんじゃねぇか? というのはもちろん親バカで、そもそも子供って、「型」を面白がって身につけようとするものなのかもなぁ。「自由にのびのびやらせたほうがいい」というのは、大人の幻想にすぎないような気もする。
それと関係あるような無いような話だが、「こどもの現実」を特集した『わしズム』18号はきのうあたりから絶賛発売中。特集にからませてもらった『嫌いな日本語』は、一挙3ページの拡大版だ! 折に触れてここで書いてきた「学校への不平不満」の集大成みたいな内容になってますので、是非ご一読を。
きのうは、ビジャレアル×インテル(CL準々決勝第2戦)をビデオ観戦。どちらもそれなりに肩入れしたいチームだったが、途中からは完全にビジャレアル応援モードになった。きっかけは言うまでもなく、ソリンの顔面を強打したマテラッツィの肘打ちである。あれはもはや「反則」ではない。「犯罪」である。したがって彼に突きつけるべきは黄色や赤の紙ではない。逮捕状である。科すべきは出場停止ではなく懲役である。初犯ではないから執行猶予は要らない。私は三年前に「ラフプレーの好感度」と題した月刊サッカーズのコラムで、彼のファウルは「ラフなだけでプレーになっていない」と書いた。つまりフットボールという競技の枠から外れた行為だということだが、その感想は今も変わっていない。あの触法ディフェンダーを、ただちにサッカー界から追放せよ。まさかとは思うが、もしイタリアが彼をW杯のメンバーに選んだ場合には、ドイツには犯罪者の入国を拒否してもらいたい。試合は1-0、agg.2-2、アウェイゴール差でビジャレアルの勝ち上がり。サッカーの神様は正しい審判を下した。
ミラン×リヨン(CL準々決勝第2戦)は3-1。どうして私はフィリッポ・インザーギがゴールを決めるとこんなに嬉しいんだろう。その瞬間に味わう感覚は、突如として姿を現した富士山を見たときの感覚に似ているような気がしなくもない。あー、入った入った。ピッポすごいねー。すごいねー。「陳腐なのにスーペル」な存在に遭遇したとき、なぜか人は笑うのだった。