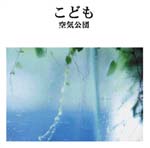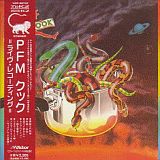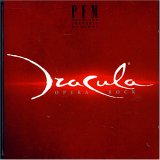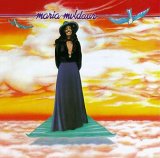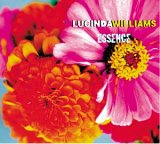1.白のフワフワ
2.音階小夜曲
3.季節の風達
4.あかり
5.電信
6.今日のままでいることなんて
7.壁に映った昨日
8.例え
9.旅をしませんか
10.こども
平成十八年五月十四日(日) 午後二時三十分
BGM : こども / 空気公団
明朝までにSAPIO誌のインタビュー原稿を上げねばならず、明後日が校了だとなればその〆切は掛け値なしだと判断せざるを得ないので、母の日をどうしようと案じるセガレに「母さんのお手伝いをしていなさい」と言い含めつつ、日曜だが出勤。ゆうべ、いったい我が身に何が起きたのかとうろたえるほどの強烈な睡魔に襲われて早く休んでしまい、まったく原稿が進んでいないので、こんなところでこんなことを書いている場合ではない。
そんなわけだから、昨夜の日本×スコットランド(キリンカップ)もハーフタイム以降は茶の間で熟睡してしまい、どういうゲームだったのか皆目わかっていないのだが、どうやらスコアレスドローに終わった模様。やはりキリンカップ男のエース柳沢を故障で欠いていたのが痛かったのだろうか。3点差勝利で、この伝統ある最重要タイトルを獲得してくれると信じていたので、とても残念だ。タイトルへの執念という精神力の面でスコットランドを下回っていたのだとすれば、開催国として恥ずかしい。日本サッカーの実力を満天下に知らしめるためにも、来年こそは全勝で優勝を果たすことで雪辱してほしいと思う。
ところで来月ヨーロッパのほうで、日本以外はキリンカップ出場を逃した弱小国しか参加しない国際大会が開催される。もちろん、凄まじい重圧のかかる仕事を終えたばかりでひどく疲弊しているであろう代表選手たちに、4年に一度しか開催されないようなマイナーな大会で良い結果を出せとは言わない。我々の最終目標はあくまでもキリンカップだ。来月の大会は国内での関心もあまり高まっていないから、気合いも入らないだろう。しかし、すでに1年後に向けた準備は始まっている。したがって昨夜の敗北で受けたショックから1日でも早く立ち直り、気持ちを切り替えて(そのためには監督交代も一つの手かもしれない)、明日につながる成果を一つでも二つでもいいから持ち帰ってもらいたいものだ。ぜんぜん関係ないけども、上記BGM欄、基本的に左にアルバムタイトル、右にアーティスト名を書くようにしているのだが、本日のはこれで合っているのだろうか。自信がない。逆のほうが面白いような気もする。
1 原始への回帰
2 何処…何時…
3 通りすぎる人々
4 セレブレイション〜甦る世界
5 ミスター9〜5時
6 アルタ・ロマ5〜9時
〜ウィリアムテル序曲
平成十八年五月十三日(土) 午後二時三十五分
BGM : Cook / P.F.M.
既報どおり、ゆうべはクラブチッタ川崎で、PFMの来日公演を堪能。どんなライブ会場にもそういう輩は必ずいるので今さら文句を言っても始まらないとはいえ、いちいち裏声でホゥホゥと発情したマントヒヒのような奇声を発して意図的(あるいは偽善的?)に感極まってみせるという形式的な手続きによってしか自分が演奏会に参加したという実感を得られないタイプの人たちは(クラシック業界のブラボー族も含めて)何とかならないのかと思うのだし、ある友人が前に「それがイヤだからライブに行かない」と言っていたキモチも(サッカーファンの立ち居振る舞いが気に入らないからサッカー場で試合を観戦するのがあまり好きではない私には)よくわかるのだが、しかしそんなことはともかくとして、途中15分間の休憩をはさみつつ3時間にわたって繰り広げられた精緻なアンサンブルと技巧と白熱は、じつにじつにすばらしいものだった。日頃そんなに数多くのライブに足を運んでいるわけではないが、ロックを集中的に聴き始めてから鑑賞した中では、文句なしに最高のステージ。
初期の『Photos Of Ghosts』(邦題は『心霊写真』ではなく『幻の映像』)や中期の傑作『Chocolate Kings』から最新作のロックオペラ『Dracula』にいたるまで、30年を超えるバンドの歴史の中で生み出された名曲の数々は、ときに叙情的で、ときに情熱的で、ときに知性的で、ときに諧謔的で、ときに衒学的で、ときに牧歌的で、ときに耽美的で、そして、その全てが、あれは何と言えばいいのか、そう、祝祭的な幸福感を内包していた。同じイタリアのエンターテイナー集団として、ユベントスには、PFMの持つ成熟した清廉さみたいなものを学んでほしいものである。
譜面台を見るときにやおら老眼鏡をかけるメンバーがいたのにはいささか物の哀れを感じないではなかったものの、しかし「懐メロにいそしむ同窓会」的なおもむきは一切なく、30年前の曲であってもそれは彼らの老いた風貌によく似合っており、仮にそれが現在の彼らが作り上げたものだったとしても何の違和感もないどころか深く納得すると思われるのだが、逆にいえば、そういう音楽を彼らは20代の時点ですでに完成させていたということなわけで、むしろその事実に驚嘆すべきなのだよなぁ。「まだやっている」ではなく、「もうやっていた」なのだ。あー楽しかった。
1 OUVERTURE
2 IL CONFINE DELL'AMORE
3 NON E' UN INCUBO E' REALTA'
4 IL MIO NOME E' DRACULA
5 IL CASTELLO DEI PERCHE'
6 NON GUARDARMI
7 HO MANGIATO GLI UCCELLI
8 TERRA MADRE
9 MALE D'AMORE
10 LA MORTE NON MUORE
11 UN DESTINO DI RONDINE
平成十八年五月十二日(金) 午後四時三十五分
BGM : Dracula / P.F.M.
しばらく怠惰な日々を送っていたので、急に忙しくなって溜め息ばかりついている。きのうは夕刻から小学館で某保守系大物論客のインタビュー。保守系論客って、いつも会う前は「怖そうだなぁ」と怯えるのだが、会ってみるとみんな物分かりのよいやさしい人で安心する。取材後、地下鉄から井の頭線に乗り換える前に、渋谷駅構内のそば処二葉でひとり晩飯。取材後のひとりメシは、二葉率90パーセントを超えていると思う。
そのまま仕事場に戻るつもりだったのだが、ひどい湿気で汗をかいたので、夜9時にいったん帰宅、入浴してから再び出勤。2時まで原稿書き。リライトする予定だった原稿を、ソウル在住の執筆者が体調不良を理由に急遽「書けない」と言い出したので、電話インタビューして書き下ろすことになったもの。韓国に電話したのは初めてだったが、受話器から聞こえる呼び出し音が「プルルル、プルルル」ではなく保留音や着メロみたいな音楽だったので、一瞬うろたえた。出る前に保留にされたみたいで、ちょっとキモチ悪い。
けさは7時20分起床。ゆうべ2割程度しか書けていなかった原稿をなかば強引にフィニッシュに持ち込み、編集部に送信。きょうの夕方までと言われていた原稿を3時半に仕上げたのはとても立派だが、この迅速サービスは実のところ、これから川崎まで出かけなければいけないという自己都合によるもの。クラブチッタでPFMのライブ。昼飯を抜いたので、かなり空腹。また乗り換える前に二葉に寄ってしまいそう。うどんでかき揚げ玉入り〜。
1.The Pearl
2.Michaelangelo
3.I Don't Wanna Talk About It Now
4.Tragedy
(Featuring Bruce Springsteen)
5.Red Dirt Girl
6.My Baby Needs a Shepherd
7.Bang the Drum Slowly
8.J'ai fait tout
9.One Big Love
10.Hour of Gold
11.My Antonia
12.Boy from Tupelo
平成十八年五月十一日(木) 午前十時三十五分
BGM : Red Dirt Girl / Emmylou Harris
けさ、仕事場に着いて玄関のドアを開けようとしたら、カギが無いので、ものすごく焦った。ポケットのキーホルダーに自宅のカギはついているのだが、留め具が外れている。うへえ、来た道を全部トレースして探し歩くのかよ〜と絶望的な気持ちになったものの、しかし冷静に考えてみると、キーホルダーはあるのだから、落としたのはポケットからキーホルダーを取り出した場所だけに限定できるはずだ。そこで家にいる愚妻に電話して外を見てもらったら、あんのじょう家の玄関前に落ちていた(家のカギを締めたときに外れたらしい)ので事なきを得たのだが、カギや財布の管理には細心の注意を払っているつもりの私も、キーホルダーからカギが落下する可能性までは考えたことがなかった。それは去年の秋に浅草で買ったゴールデン招き猫キーホルダーで、これを使うようになってから重版通知がオカルティックともいえるハイペースで届くようになり、まあ、ほんとうはそれ以前がオカルティックなほどローペースだったと言うべきなのだが、とにかく霊験あらたかなものを感じて「ありがたやありがたや」と大事にしていたので、どうも留め具の造りがユルいようなのは困ったものである。怖いので別のものに買い替えたいが、その場合、この猫が招いたものは、一体どうなるのであろうか。金運ホルダーの「留め具」も、やはりユルいのだろうか。わりかし真剣に悩んでいる。
ゆうべ、午前中に録画しておいた『スーパーモーニング』(テレビ朝日)を見ていた(ワイドショーは録画して早送りしながら見るのがもっとも合理的だということを最近になって悟った)のだが、例のあの女性容疑者が警察に連行されるシーンのVTRが流れたときに愚妻が呟いた言葉は衝撃的だった。
「この人……北の湖に似てる」
嗚呼。ひょっとして、私はいま、良識ある人間ならば決して書いてはならないことを書いてしまったのだろうか。しかし、書かずにいられない。そうなのだ。はじめて見たときから、誰かに似ているような気がしていたのだ。だから何だというわけでは全然ないが、なんだか、まいりました。まいりましたとしか言いようがない。
きのう、リコーダーについて「学校教育ではバロック式ではなくジャーマン式を使う」と書いたが、Guestbookにもたらされた情報によると、少なくとも横浜市の学校ではバロック式を使うそうなので、全国一律にそう決まっているわけではないのだった。「ジャーマン式は学校教育ぐらいでしか使われない」ならそう間違っていないだろうと思われるが、ともあれ訂正しておきます。ちなみにセガレは、きのう、音楽の授業で初めてリコーダーを使ったそうだ。右手で楽器の根っこを握り、背筋をしゃんと伸ばしてシの音を出す練習をしたとのこと。なるほど、最初はそういう教え方をするのか。全国一律でそうなのかどうかは知らないけど。
1. Last Train
2. Worldwide
3. Back in Baby's Arms
4. Country John
5. Basic Lady
6. Southern Nights
7. You Will Not Lose
9. When the Party's Over
10. Cruel Way to Go Down
平成十八年五月十日(水) 午前十時四十五分
BGM : Southern Nights / Allen Toussaint
きのう初めて合唱部の朝練に参加したセガレに、どんな歌を練習したのかと訊いたら、『翼をください』だというので笑った。そっかー。いまだにそうなのかー。今の学校はいろいろなことが昔とは変わってしまい、親としては子の世代との断絶を感じることが多いので、こうして共有できる文化が残っていると安心する。中学1年生のとき、あれは文化祭か何かだったのか、どうしたわけか合唱の指揮者としてこの名曲を体育館で演奏したことを懐かしく(&恥ずかしく)思い出した。生意気に指揮棒なんか振り回してたんだから、小学生将棋名人戦で扇子を手に指してた子供(※5/8の日誌参照)に難癖つけてる場合じゃねえよな。それにしても、本来はポピュラーソングだった音楽が30年もの長きに渡って教育現場で生き残っているというのは、いいか悪いかは別にして、なかなかすごい話だ。「それなら父さんも知ってるぞ」と風呂場でデュエットしたら、最後の「ゆきたい〜」をセガレが3度上でハモろうとした(ぜんぜんハモれていなかったが、音をハズしたのではなくハモろうという意図があることはわかった)ので驚愕。初めての、しかも始業前のわずか15分の練習で、いきなりそこまで教えているとは思わなかった。歌詞もほとんど覚えていたし、一体どんな教え方をしてるんだろう。だけどおまえ、「いま富とか名誉ならば要らないけど翼がほしい」って意味わかって歌ってんのか?
一方、授業で使うソプラノ・リコーダーのほうも、学校で注文したものがきのう届いたようで、家に持ち帰っていた。我が家的には、これが6本目のリコーダー。ヤマハの製品だろうとばかり思っていたら、意外にもトヤマ楽器の「アウロス」である。リコーダー業界のことは知らないが、対学校の営業に関してはアウロスのほうが強いのだろうか。あるいは「ほかの楽器はたいがいヤマハだからリコーダーはアウロスね」という棲み分けでもあるのかもしれない。そう思って振り返ると、自分が小学生のとき使っていたのもアウロスだったような気がしなくもないが、どうだっただろうか。学校教育ではバロック式ではなくジャーマン式(ファの右手が人差し指1本なので押さえるのが楽)を使うのは昔も今も同じだが(※5/11に訂正)私の時代と違うのは、色が白ではなく黒っぽいやつなのでカッコイイことと、持ち主のネーム入り(!)であることだ。裏側の穴の下あたりに刻まれているのだが、漢字で縦書きされているので、リコーダーというより、ちょっと尺八みたいな印象を受けなくもない。もしかして、この名入れサービスがアウロスの強み? とりあえず、ドレミファソラシドの押さえ方を教えて吹かせてみつつ、「そんなに大きく指を楽器から離す必要はない」などと偉そうに指導したが、それはギターを弾く私がいつも師匠に言われていること。
日本×ブルガリア(キリンカップ)は、日本がブルガリアを90分間ゼロに抑えたものの、その前後に失点したので1-2の負け。なにボーっとしてんだヨシカツ。GKの仕事はボーっとしないことがいちばんの基本なのに。キックオフ前の君が代斉唱、セガレが合唱デビューを果たした日に少年少女合唱団みたいな子供たちが出てきたのには妙な因縁を感じたものの、ちゃんと歌の訓練をしている人間の演奏には聞こえなかったので脱力。入学式じゃねえんだから、まともに歌える少年少女を連れてきやがれ。
1.Break It Down Baby
2.Solace for the Lonely
3.Press On
4.Down the Mountain
5.Whippin Wind
6.Come Back My Way
7.Little Boy
8.Oh So Sexy
9.Teardrops
10.All I've Given
11.Waiting
12.Brand New Key
13.I Fall in Love as Much as I Can
平成十八年五月九日(火) 午後三時二十分
BGM : Solace for the Lonely / Robinella
きょうは無駄に長いからね。
どういう風の吹き回しだか知らないが、セガレが小学校の合唱部に入った。音楽の教師が始業前に週2回(だったか3回だったか)、土曜日の午前中に月1回(だったか2回だったか)指導するそうだ。当然、と言うべきではないかもしれないが部員の大半が女子で、全部で何人いるのかは知らないけれど男子は4人ぐらいしかいないという。昨今は吹奏楽部でさえ女だらけなのだから、まあそんなもんだろう。ならば助っ人で私も参加しようかと思わなくもないが、バスがひとりだけいても使いようがないだろうし、いずれにしろ迷惑なだけだからやめておく。小学生の合唱というと、たまにNHKあたりで見かける、あの、お坊ちゃんお嬢ちゃん風の薄気味悪い衣裳に身を包み、顔面にビックリマークを貼りつけたような歓喜の表情をこしらえて体を左右に揺らしながら歌うあざとい有り様をどうしたって思い出してイヤ〜な気分になるのだし、自分のセガレがそれをやっている姿を想像すると笑いが込み上げてくるわけだが、しかし親にけしかけられたわけでもなく、自らすすんで音楽に取り組む姿勢を見せてくれたのは喜ばしい。ほんとうは何か楽器を習わせたいのだが、それはそれで金もかかるしな。3年生は授業でリコーダーを習うようだから、楽器のほうは家で一緒に練習することにしよう。にぎやかな家庭。
どういう風の吹き回しかと自分でも思うが、『プレジデント』というビジネスマン向け雑誌を初めて買った。いや、今は「ビジネスマン」ではなく「ビジネスパーソン」って言わなきゃいけないようで、だけど「カメラパーソン」とか「営業パーソン」とかって聞いたことないよなぁと思うわけだが、それはともかく、中吊り広告で今号の特集が<「書き方」のコツ>だということを知り、そんなコツがあるなら私もぜひ教わりたいと思ったのだった。
だが、のっけから読者を不安に陥れるのは、特集の冒頭に置かれた記事のタイトルである。<読まれる文章に「文才」は必要ない>というのだ。じゃあ、一体どんな文章に文才が必要なんですか。と、誰だって即座に疑問を感じるような隙だらけの文言を真正面から突きつけてくるような者が、人に文章の書き方を教えられるものだろうか。と思うが、なにしろ読まれる文章に文才は必要ないのだから、読まれる文章の書き方について読まれる文章を書く者にも文才なんか必要ないのであろう。「文才のない奴ぁオレんとこへ来い! オレもないけど心配するな」というわけである。なるほど。不安になった私がバカだった。それを見てホッと安心するのが、このタイトルの正しい読み方というものだ。書き方を学ぶ前に、読み方をちゃんと身につけなければいけない。
その記事を執筆したのは後藤禎典という人で、河合塾で国語を担当する講師であるようだ。雑誌を家に置いてきてしまったので内容を正確に引用することができないが、一読してとても印象に残ったのは、「主語と述語のねじれ」をいかに避けるかという部分だった。日本語は主語と述語のあいだに多くの修飾語が挟み込まれるので、たとえば「私が目標としているのは、愛のあるユニークで豊かなフレーズを魔術師のごとき流麗な手さばきで次から次へと紡ぎ出してみせるギタリストになるのは決して容易なことではありません」(※例文は江戸川)といったようなバカ丸出しの文章を書いてしまいがちだというのは、よく言われることである。それを避けるには、「長々と続けないで文章を短く区切るべし」などと言われることが多いのだが、後藤氏の指導は違う。あとからいくらでも書き足せるパソコンの特性を生かして、まず主語と述語だけの短文を書き、それを徐々に増やしていけというのだ。それは、たとえばこんな具合(※例文は江戸川)である。
なるほど、たしかにこの手法だと(なんと途中で述語が変わっても!)主語と述語がねじれないが、やってみると意外に楽しいので、うっかり調子こいて文章が無限に膨張しかねないのがモンダイだ。そうでなくとも、私の場合は放っておくと文章が膨張しやすい体質なのだが、それはともかくとして、私はしたくない。私は仕事をしたくない。私は一緒に仕事をしたくない。私はビジネスパーソンと一緒に仕事をしたくない。私はこんなビジネスパーソンと一緒に仕事をしたくない。私はこんなねじれてしまうビジネスパーソンと一緒に仕事をしたくない。私はこんな手間をかけないとねじれてしまうビジネスパーソンと一緒に仕事をしたくない。私はこんな手間をかけないと主語と述語がねじれてしまうビジネスパーソンと一緒に仕事をしたくない。
私は した。→ 私は インタビューを した。
→ 私は 1月に インタビューを した。
→ 私は 今年の 1月に インタビューを した。
→ 私は 今年の 1月に 都内某所で インタビューを した。
→ 私は 今年の 1月に 都内某所で およそ3時間に渡って インタビューを した。
→ 私は 今年の 1月に 都内某所で およそ3時間に渡って コーヒーを飲みながら インタビューを した。
→ 私は 今年の 1月に 都内某所で およそ3時間に渡って コーヒーを飲みながら 井上さんに インタビューを した。
→ 私は 今年の 1月に 都内某所で およそ3時間に渡って たしか5杯ぐらい コーヒーを飲みながら 井上さんに インタビューを した。
→ 私は 今年の 1月に 都内某所で およそ3時間に渡って たしか5杯ぐらい コーヒーを飲みながら シンガーソングライターの 井上さんに インタビューを した。
→ 私は 今年の 1月に 都内某所で およそ3時間に渡って たしか5杯ぐらい コーヒーを飲みながら シンガーソングライターの 井上さんに パンフレットのための インタビューを した。
→ 私は 今年の 1月に 都内某所で およそ3時間に渡って たしか5杯ぐらい コーヒーを飲みながら シンガーソングライターの 井上さんに ツアーの パンフレットのための インタビューを した。
→ 私は 今年の 1月に 都内某所で およそ3時間に渡って たしか5杯ぐらい コーヒーを飲みながら シンガーソングライターの 井上さんに 3月にスタートする ツアーの パンフレットのための インタビューを した。
→ 私は 今年の 1月に 都内某所で およそ3時間に渡って たしか5杯ぐらい コーヒーを飲みながら シンガーソングライターの サングラスをかけていない 井上さんに 3月にスタートする ツアーの パンフレットのための インタビューを した。
→ 私は 今年の 1月に 都内某所で およそ3時間に渡って たしか5杯ぐらい コーヒーを飲みながら シンガーソングライターの サングラスをかけていない したがってちっとも陽水らしく見えない 井上さんに 3月にスタートする ツアーの パンフレットのための インタビューを した。
→ 私は 今年の 1月に 都内某所で およそ3時間に渡って たしか5杯ぐらい コーヒーを飲みながら シンガーソングライターの サングラスをかけていない したがってちっとも陽水らしく見えない 井上さんに 3月にスタートする ツアーの パンフレットのための インタビューを したら 眠れなかった。
→ 私は 今年の 1月に 都内某所で およそ3時間に渡って たしか5杯ぐらい コーヒーを飲みながら シンガーソングライターの サングラスをかけていない したがってちっとも陽水らしく見えない 井上さんに 3月にスタートする ツアーの パンフレットのための インタビューを したら その夜は 眠れなかった。
→ 私は 今年の 1月に 都内某所で およそ3時間に渡って たしか5杯ぐらい コーヒーを飲みながら シンガーソングライターの サングラスをかけていない したがってちっとも陽水らしく見えない 井上さんに 3月にスタートする ツアーの パンフレットのための インタビューを したら その夜は いろいろな意味で 眠れなかった。
私の手で明日までにリライトされるべき原稿がまだ編集部から届かず、だからといって急ぎでない別の仕事に着手する気にもならないので、こんなものは読み手にとって苦痛でしかないと承知しながらダラダラ続けるが、なにより疑問なのは、文章の書き方を伝授する文章というものが、文章を書く上でほんとうに役に立つのかどうかということだ。
たとえば(なんでこんな本が私の手元にあるのかよくわからないが)樋口裕一『樋口式「頭のいい人」の文章練習帳』(宝島社新書)という深い溜め息の出るようなタイトルを冠した本の前書きには、「今では、文章を書かずに済ますことはむずかしい。ところが、文章を書くのが苦手という人が多い。(中略)だが、ビジネス文書を書くのはそれほどむずかしいことではない。ほんの少しのコツを身につけ、書き方を知り、少しだけ練習すれば、すぐに書けるようになる」と書いてある。また「コツ」だ。「コツ」というからには、あらゆる文章に広く応用できる基本技術なのだろうと思うが、私自身は(わざわざお金を払ってリライト=人の原稿の書き直しを頼んでくれる人があるぐらいだから決して文章を書くのが下手ではないと思われるにもかかわらず)そういう「コツ」が存在するように思えたことが一度もない。同書の目次には、<イエス・ノーで考えて文章を書く>、<第一段落では、必ず「問題提起」をする>、<第二段落は、「YES−BUT」で書く>、<第三段落は、「なぜなら」で根拠を書く>などといった「鉄則」がズラズラと個条書きされているが、どれ一つとして意識したことがないし、無意識のうちにそうしているとも思えない。……ああ、でも、この文章の第一段落は「問題提起」になってるな。第二段落は……えーと……これ、「YES−BUT」なんだろうか。そんなような気もするが、ちょっと違うような気もする。よくわからない。そんなこともよくわからないぐらいだから、これらの「鉄則」を遵守して書けと言われたら、手がすくんで一行も書けないんじゃないかと思う。じっさい、次の段落を「なぜなら」で始めることはできません。
ともあれ、私の場合は一般的に通用する「コツ」を知らないから、「書き方」はその場その場で個別に考えるしかない。もしかすると、何度も私の原稿を読んでいる編集者(やこの日誌の継続的な読者諸氏)には「またこのパターンかよ」と思われるような毎度お馴染みの運び方があるのかもしれないが、それは「コツ」ではなく「クセ」という。そして、クセというやつは個条書きにしてマニュアル化することができないのだった。
マニュアル化できないから、人に書き方を指導しようとすると、どうしていいかわからず困惑する。私は教師じゃないのでそんなケースは滅多にないが、先日、PTA関係の文書を作成していた愚妻に「こんなんでどうかなぁ」と文案について相談されたときも、それを手直しするのは簡単だったし、結果的には「このほうがスッキリする」と愚妻も納得する文章になったのだが、しかし、なぜその文案に手直しが必要なのか、どうして手直しした文章が原案よりもスッキリ読めるのかといったことを、一般論として説明することはできなかった。というより、それは単に私の「クセ」を反映した形になっただけのことであって、ほんとうに手直ししなければいけなかったのかどうかも自信がない。そのままでも、その文書で伝えるべき事柄は十分に伝わる文章だったからだ。同じようなことは仕事でもあって、極端な話、著者が喋ったまんまのテープ起こし原稿を読みながら、「このまま印刷して本にしたって、言いたいことは伝わるよな。だって、読んでるオレが理解できてるんだから」と、オノレの生業を全否定するような思いに駆られることがしばしばだ。これから届くであろう原稿だって、きっとリライトなんかしなくたって意味は通じるに違いない。
プレジデントの特集にも「樋口式」にも、企画書や小論文などの添削例がいくつも紹介されているが、たしかに添削前のものは「下手だなぁ」と思うものの、どれも言いたいことは概ねわかる。「下手だなぁ」と思われることさえ厭わなければ、手直ししなくても十分に用が足りるのである。無論、たとえ意味が通じてもその企画書がボツになることはあるわけだが、それは書き方が悪いのではなく、企画が悪いからだ。書き方が良くても、著者の考えていることがつまらなければその本はつまらないのと同じことである。
だんだんこの文章で何が言いたいのかわからなくなってきているが、要するに(というツナギ方が適切かどうかも怪しいけど)「書き方のコツ」を知りたいと願っている「文章を書くのが苦手という人」たちは、文章で何かをうまく伝えられなくて困っているのではなく、「文章が下手」と思われるのがイヤなだけなのではないか。もちろん、誰だって「下手」と思われるより「うまい」と思われたほうがいいに決まっているが、それは「芝居が下手」より「うまい」と思われたほうがいい、というのと同じ程度の問題であって、どっちだっていいっちゃどっちだっていい話だ。物書きや役者などそれを仕事としている者でもないかぎり、そんなもん下手で当たり前だと思う。役者ではない人は芝居が下手でも日常生活に何の支障もないのと同様、文章が下手でも、意味さえ通じりゃ人に迷惑をかけることはない。なので、前言を撤回します。私はあんな手間をかけないと主語と述語がねじれてしまうビジネスパーソンとも一緒に仕事をします。選り好みしてる余裕もないし。
それにしても、「芝居が下手な奴」と言われても傷つかない人が、「文章が下手な奴」と言われると傷つくというのは不思議である。人が「いやあ、私は芝居が苦手でして」と言う場合、そこにはむしろ「裏表のない正直者の自分」を誇らしく思う気持ちがあるが、「私は文章が苦手でして」と口にする人たちは、ほんとうに辛そうだ。おそらく、彼らが「おまえは文章が下手だ」と言われて傷つくのは、例の「文は人なり」という(多くの古風な文章指南書に書かれている)幻想が常識のようにはびこっているからだろうと私は睨んでいる。書いた文章がダメだと言われると、「人としてダメ」だと言われたような心持ちになってしまう人が多いのではないか。
だが、いつも他人になりすまして文章を書いているゴーストライターの辞書に、「文は人なり」という格言は載っていない。だって、それ、オレじゃねえもん。それこそ役者と同じで、お芝居として別の人間を演じているだけだ。自前の文章だって、似たようなものである。実在の他人になりすましているわけではないけれど、どこかに芝居っ気を持っていないと書けないのが文章というものだろう。そういえば「樋口式」の目次に並べられた「鉄則」の1番目は、<ありのまま書いてはダメだ!嘘でいい!>だった。どういう意味かは中身を読んでいないのでわからないし、嘘を書いちゃまずいのではないかとも思うが、いずれにしろ、うまいこと文章をこしらえるなんていうのは、人でなしの所業なのかもしれない。
ふむ。『文は人でなし』って、あんがい新書でイケそうなタイトルだな。企画書を書いてるつもりじゃなかったんだけど。
1.Any Old Time
2.Midnight at the Oasis
3.My Tennessee Mountain Home
4.I Never Did Sing You a Love Song
5.Work Song
6.Don't You Feel My Leg
(Don't You Get Me High)
7.Walkin' One and Only
8.Long Hard Climb
9.Three Dollar Bill
10.Vaudeville Man
11.Mad Mad Me
平成十八年五月八日(月) 午後二時三十五分
BGM : Maria Muldaur / Maria Muldaur
5月4日に国立科学博物館のナスカ展に足を運んだ以外、とくに連休らしいことはせず、本を読んだり、料理をしたり、右手の親指が内出血を起こしてジッポを擦るのにも苦労するほど『コミュニケーション・ブレイクダウン』のリフを練習したり、平塚5遺体事件を報ずるワイドショーを(録画までして)貪り見たり、ようやく謎のハッチが開いたところで終わってしまった『LOST』(シーズン1)の最終回を見て「なあんもスッキリせんじゃないか!」とブツクサ文句を垂れたりしていた連休だった。5月5日の端午の節句には、将棋でセガレに2連勝のあと4連敗。強い男の子に育っていて何よりである。私も早く強い男になりたい。
将棋といえば、たしかそれと同じ日、NHKで放送された「第31回小学生将棋名人戦」(準決勝&決勝)を見た。羽生をはじめ、多数のプロ棋士を輩出している大会だそうだ。地区大会から勝ち上がって準決勝に進出した4人の6年生の中からも、いずれプロになる者が出てくるに違いない。で、そういう将棋界の将来を担った重要なイベントだからこそ苦言を呈したいのだが、この世界も世間一般の例に漏れず、礼儀作法やら立ち居振る舞いやらといった面の教育がうまくいっていないのではなかろうか。むろん全国にテレビ中継されるのはどの子も初めての経験だろうから緊張していたのだろうとは思うが、それを割り引いても、司会者の質問への受け答えなどがフニャフニャしすぎだし、口元が常に半開きのまま閉まらない者、目がうつろな者、その両方を兼ね備えた者ばかりで、早い話、テレビゲームばっかやってるようなタイプの子供と印象が変わらない。「将棋みたいな格調の高い世界で抜きん出ている子供はそれに見合った人柄を身につけているに違いない」というのは凡人俗人の勝手な期待(思い込み)にすぎないのかもしれないけれど、いかにも「盤上のことしか学んでないんだろうなぁ」と感じられるのが残念だ。少なくとも私は、あれを見て我が子を将棋の世界に進ませたいとは思えない。
なかには一手指すたびに他の駒に触って盤上をぐちゃぐちゃにしてしまう子もいて、そのぎこちない手つきを見ていると、ふだんは将棋盤さえ使わずに、パソコンか何かで研究してんじゃないのか?などと深読みしたくもなる。それを悪いとは言わないが、一流のプレイヤーは道具の扱い方も一流であってほしい。いっちょまえに扇子を手に対局していた子もいたが、そんなことを覚える以前に身につけるべきことがいくらでもあるはずだ。私の場合、盤上の将棋に関してセガレに教えられることは一つもなく、始めと終わりの挨拶や駒の置き方などマナー面しか指導できることがないので余計に気になるのだろうが、強い男の子は振る舞いも立派じゃないと格好良くない、と思いました。そういえば優勝した子は、胸に「BAD BOYS」というバカげた文言がプリントされたTシャツを着ており、そこには格調も風紀もへったくれもないのだった。小学生将棋名人戦のテレビ出演者にそれを着せるのをおかしいと思わない親が育てた子供、ということ。
SAPIOや月刊PLAYBOYなど今日から追いまくられる仕事上の必要に迫られて(と強調しすぎるのも著者に失礼だが)、この連休中、崔基鎬氏の『日韓併合の真実―韓国史家の証言』(ビジネス社)と『日韓併合―韓民族を救った「日帝36年」の真実』(祥伝社)、渡辺淳一先生の『失楽園』(講談社文庫)と『愛の流刑地』(幻冬舎より近日刊行予定)など、いろいろな意味で感想の書きにくい本ばかり読んでいた。それ以外にも、これから『祇園うちあけ話』(三宅小まめ・森田繁子/PHP文庫)や『京都 舞妓と芸妓の奥座敷』(相原恭子/文春新書)など、とくに感想を抱きそうにない本を読まなければならない。来る仕事拒まずでやっているとこういうことになるわけだが、こうしてタイトルを並べてみると、自分がいったいナニ屋さんなのか謎な感じ。
それはいいのだが、妻子のいる自宅の茶の間で、性愛という「死ななきゃ治らない病」の深刻さ(と、愚かしさと、ある種の滑稽さ)をこれでもかこれでもかと執拗な筆致で描いた二つの不倫ポルノ巨編を(たまに鉛筆で書き込みなんかしながら)読み耽っている四十路の男−−という光景には、かなりモンダイがあるような気がする。いずれも日経新聞朝刊に連載されていたこの作品を、満員の通勤電車や午前中のオフィスで読み耽っていたであろうビジネスマン諸氏と、どちらがより健全かわからない。
ところで「治らない病」といえば、崔基鎬氏の二冊も、支配者が国を私物化して少しも恥じるところがないという、李氏朝鮮の時代から変わらずに受け継がれている朝鮮半島の宿痾について論じたものだった。「宿痾」の意味がわからない人は辞書を引きましょう。さて、愛欲に溺れて自滅する男女と、私利私欲に溺れて自滅する権力者は、どちらがより健全だろうか−−などと考えてもまるで意味がないのだけれど、まあ人にはいろんな病気があるわけで、ならば自分はどんな宿痾を抱えているのかということについて、たまには考えてみたほうがいいかもしれない。だって、欲望で自滅するのはいやだよ。なぜなら死んだときに人から感謝も尊敬もされないから。……いや、だけど、『愛の流刑地』の主人公・菊治さん(元ベストセラー作家で今はゴーストや雑誌のアンカーをやっている50代半ばの物書き。げげげ)は、死んではいないものの、自滅したのに息子の尊敬を得ていたよなぁ。そういうこともあるのかなぁ。あの息子は、そんな親父のどこかに男の強さを見出したのでしょうか。文学ってむずかしい。
1.Paralelo
2.Bossa de Kris
3.Endless Is Love
4.Peace of Mind
5.Bells
6.Shape of My Heart
7.Walk
8.Too Fast
9.Te Perdi
10.Here Comes the Sun
11.Tears of Joy
平成十八年五月二日(火) 午前十一時五十五分
BGM : Peace Of Mind / Carmen Cuesta
きのう、セガレを相手にうっかり「打ち歩詰め」をやってしまった。将棋の話である。持ち駒の歩を打って相手の玉を詰ますのが「打ち歩詰め」で、これは詰ました側が反則負け。将棋のルールなんてたいがい知っているつもりだったが、この禁じ手は数ヶ月前にセガレが買った『はじめての将棋』(中原誠永世十段監修)という本を見るまで知らなかった。
盤上の歩を動かして詰ます「突き歩詰め」はオーケーだし、持ち駒を打った場合でも歩以外なら許されるのに、打ち歩詰めだけイカンというのは、ふつうに考えればきわめて不合理である。PK戦で、「決めれば勝ち」という最後のキックを、「GKが蹴ってはいけない」と言っているようなものだ。ウィキペディアによれば、「打ち歩詰めが禁じ手となった理由として、最下級の兵士(=歩兵)が大将の首を取るなどまかりならないとされた、という説が残されているが、真偽のほどは定かではない」とのことだが、仮にその説が正しいとしたら「突き歩詰め」だってダメだろう。
でも私は、そういうルールがあることを知ったとき、直観的に「なるほど。これはなかなか立派な取り決めじゃ」と思った。理屈もへったくれもない単なる感情の発露として、打ち歩詰めに対しては「そりゃあねぇだろう」「あんまりだよな」と思うからである。京言葉なら「かんにんしとくれやすぅ」といったところだろうか。「武士の情け」という言葉を思い出したりもする。いずれにしろ、これは日本人なら説明抜きで容認し合える美しい約束事だと思うわけだ。
ところが、そう思っていた私でさえ、実戦では(相手は小学生という弱者であるにもかかわらず)躊躇なしに歩を打って詰ましてしまったというあたりが、この国における倫理観の崩れっぷりを象徴している……などと言ったら、てめえの個人的ミスを社会問題化して誤魔化してんじゃねぇぞコラ、と怒られるだろうか。怒られますね。そのとき心に何の痛みも感じず、「うへへ、勝った勝った」とデレデレしていた自分がとても恥ずかしい。子供相手になりふり構わず必死にならないと戦えない棋力の低さも情けない。あとで気づいて、「さっきのは打ち歩詰めという反則だから、父さんの負けだ」と言った私に対して、「そっか。でも、どうせボクが負けただろうから、引き分けっていうことにしておこうよ」と言って勝敗表に△を書き込んだセガレのほうが、圧倒的に人として立派である。
ともあれ、打ち歩詰めを禁じる規則の背後には、美学なきアコギな勝利至上主義を「そこまでして勝ちたいか」と戒める精神があるのだろうと思いたい。もしかしたら、当初はそれを規則で禁じるまでもなく、誰もが打ち歩詰めを「みっともない」と考えて自粛していたのかもしれない。その美意識がどこかの段階で崩れ、棋士たちのあいだで合理主義がはびこった結果、ルールとして明文化せざるを得なくなったのかもしれない。実際はどうだかわからないけれど、世の中の移ろい次第では、今後、打ち歩詰めに対する規制緩和が要求される可能性もあろう(たとえば先日8キロ痩せた状態で保釈された彼はこの禁じ手を容認できるだろうか?)。私自身は、百年後の日本でも、打ち歩詰めが禁じ手であってほしいと願っているけれど。
1.Lonely Girls
2.Steal Your Love
3.I Envy The Wind
4.Blue
5.Out Of Touch
6.Are You Down?
7.Essence
8.Reason To Cry
9.Get Right With God
10.Bus To Baton Rouge
11.Broken Butterflies
平成十八年五月一日(月) 午後二時五分
BGM : Essence / Lucinda Williams
日誌を書いていなかったおよそ10日間、FAカップ準決勝でチェルシーはリバプールに負け、ラツィオは先制しながらも不当な判定で10人にさせられたためにユーベと惜しくも引き分け、私は雑誌の取材で祇園に出張してお座敷遊びを経験し、アーセナルとバルセロナはCL決勝進出を果たし、うちのクルマは隣で行われている建売住宅の新築工事で壁に吹き付けられていたペンキが飛散して汚され(現場周辺のクルマにカバーをかけるという初歩的な作業さえ怠るようなシロートが建てた家を買う人が気の毒だ)、対応が悪かった建設会社の担当者は私にさんざんどやしつけられ、それとはぜんぜん関係ないが私は木曜日に38度まで発熱したものの金曜日には回復し特段の理由もなくタボン君&ヤマちゃんと朝まで歌ってヘロヘロになるなど、まあいろいろあったわけだが、とにもかくにも、チェルシー×マンチェスターU(プレミア第33週)は3-0だったのであり、ホームで宿敵を完膚無きまでに叩きのめすという最高の形で優勝が決まってほんとうに良かったのだった。
いまだにチェルシーがどうして強いのか私にはよくわからず、彼らの何がうまいかといえば「勝つのがうまい」としか言えないような気もするわけなのだが、しかし優勝を決めたこの試合で見せたパフォーマンスはとてもすばらしく、モウリーニョ3年目となる来季こそは息を呑むほど美しいめくるめくような官能的サッカーでタイトルを総ナメにしてくれるのではないかという予感だけは十分に抱かせるものだったと思う。過酷なプレミアリーグを2年連続で制覇しながら3年計画でチームを育てるという、きわめて困難なプロジェクトにモウリーニョが成功しつつあるのだと思いたい。いずれにしろ、そんなチェルシー躍進の影響もあって、イングランドのフットボール界はますますレベルアップしているように感じる。来季は、チェルシー、ユナイテッド、アーセナル、リバプールが途方もなく高い次元でしのぎを削る物凄いリーグ戦が展開されるに違いない。
ところで話は変わるが、この試合で自陣から駆け上がって見事なゴールを決めてみせたリカルド・カルバーリョの髪型を見たセガレは「実験に失敗して薬がボン!って爆発しちゃった博士みたい」とのたまい、以来わが家では、あんがい白衣も似合いそうな彼のことを「ハカセ」と呼ぶことになったのだが、そういう昔からの紋切り型イメージがいつのまにか子供の頭に刷り込まれているのって、けっこう不思議だ。ちなみに話はまた変わるが、エッシェンの渾名は「アサッテ君」である。どうしてかというと、シュートがいつもアサッテのほうに飛ぶから。
一方、アサッテではなく「おととい来やがれ!」と声を大にして罵倒したかったのは、FAカップ準決勝のテレビ中継にゲストとして出演していたトニー・クロスビーとかいう男だ。ニュートラルな立場で試合の模様を伝えるべき場所に熱心なリバプールファンだけを呼ぶフジテレビの見識を心の底から疑うが、まあ、それはいいとしよう。「おれも呼べ」とまでは言わない。許し難いのは、観客席のリバプールサポーターがチェルシー陣内右サイドのエリアに中身の入ったビール瓶を投げ込んだときの彼の発言である。なにしろペットボトルではなく瓶なのだし、それが頭部を直撃したときのことを考えればパウロ・フェレイラに対する殺人未遂にも相当する犯罪行為だと私は思うのだが、それを見たトニー・クロスビーは、あろうことか「中身が入っててモッタイナイですね(笑)」と軽口を叩きくさったのである。冗談というのは言っていいときと悪いときがあるし、たとえ言っていいときの冗談だとしても、それはちっとも面白くない。だいたい、リバプールファンの代表として公共の電波にコメントを垂れ流している人間があれほどの蛮行を目の当たりにした場合、まっとうな職業意識と常識的な倫理観さえ持ち合わせていたら、何かほかに言うべきことがあることぐらいわかるだろう。まさかそこまでの含意があったとは思えないが、もし彼が「自分はリバプールファンだから、チェルシーの選手の生命よりビールのほうに大きな価値を見出すのだ」と言いたかったのだとしたら、そんな奴はサッカー報道の場から永久に追放しなければいけない。すでに『オレとオマエとリバプール』と題した月刊サッカーズの連載は終わっているようだが、こんなに愚劣で下品(おまけに退屈)な人間が、自分の連載終了後に同じ雑誌の同じスペースを与えられて何事かを書いていたのかと思うと、じつに腹立たしい。モッタイナイのは1本のビールではなく、おまえごときの吐き散らした言葉で埋められていた1ページの誌面のほうじゃ。
生まれて初めて(そして人生最後かもしれないが)祇園のお座敷で芸妓さんと同席して感じたのは、あの非日常的な空間で「よろしおすなぁ」なんていうやわらかい京言葉に取り巻かれていると、漢語を含めた外来語を使って喋るのがアホらしく思えてくるということだった。もちろん京言葉といっても今どき純然たる大和言葉だけで喋ることができるわけはなく、外来語もそれなりに混じるのではあるけれど、その外来語を取り入れたがゆえに日本語でも可能になったロジカルな物言いというか、相手との阿吽の呼吸なしに成立する具体的で正確な描写というか、平たくいえば堅苦しい説明口調みたいなものが邪魔くさくなって、まあ、なんというか、いろんなことがどうでもよくなってくるんどすえ。なので、ふだん論理の言葉と取っ組み合いをしている作家や学者といった職業の人たちが祇園で遊びたがる気持ちがちょっとわかったような気がした。それはきっと、言語的な気分転換なのだと思う。そういう気分転換ができる場所は、たぶん、そう多くない。