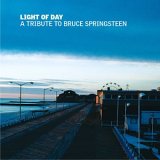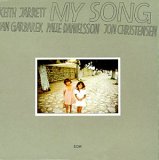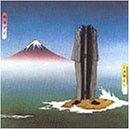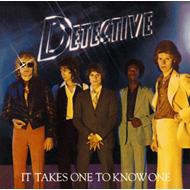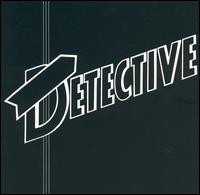1.Twenty Nine
2.Strawberry Wine
3.Night Birds
4.Blue Sky Blues
5.Carolina Rain
6.Starlite Diner
7.Sadness
8.Elizabeth, You Were
Born to Play That Part
9.Voices
平成十八年六月六日(火) 午後十二時四十五分
BGM : 29 / Ryan Adams
次に更新するときはデザインをワールドカップ仕様に作り替えようと思っていたのだが、そんな暇がないまま1週間が過ぎてしまった。取材、〆切、取材、〆切の日々。吸ったら吐く。吐いたら吸う。止めると死ぬ。しばらく雑誌原稿ばかり書いていたが、このところバタバタと書籍仕事が発注され、すべてが順調に進行すれば来月から4ヶ月で3冊書くことになる予定。しかしそのうち1冊はゴーストではなく「おまえが書け」と言われているので、どういう成り行きになるのかわからない。もんのすげえ分量の勉強をこなさないと書けそうにないが、苦し紛れの共同制作剽窃だけはしないよう気をつけよう。
ところで今朝ワイドショーを見ていて気になったのは、和田画伯がマスコミ各社にファックスで送りつけた文書が、四百字詰め原稿用紙に書かれていたことである。原稿用紙というのは読んで字のごとく「原稿」(発表する文章の下書き/印刷のもととなる文章や絵画・写真など=大辞林 第二版)を書く用紙であるからして、相手が編集者や印刷所や作文指導者ならともかく、完成品として他人様に見せるものではない(もちろん商品として流通させるべきものでもない)。マスコミ各社が文書の字数を正確に把握できるよう配慮してどうする。この場合、べつに印刷する必要はないけれど、手書きなら手書きで、それにふさわしい書式ってもんがあるだろう。常識的な感覚の持ち主は、手紙を原稿用紙に書いたりしない。そのあたりの線引きや作法に無頓着なところから推して、何かにつけて物事を「まあいいや」と処理してしまう雑駁かつ横着なお人柄なのかもしれんと思ったのだが、どうだろうか。リミックスならリミックスだと明記すればよかったのに。
1.Don't Panic
2.Shiver
3.Spies
4.Sparks
5.Yellow
6.Trouble
7.Parachutes
8.High Speed
9.We Never Change
10.Everything's Not Lost
平成十八年五月三十一日(水) 午前九時十五分
BGM : Parachutes / Coldplay
えーと、完全な内輪話なので事情のわからない方は読み飛ばしてほしいのですが、ワールドカップ開幕が近づくにつれて、98年と02年の2回に渡って主催してきた例のイベントを「今回はやらないのか」というお問い合わせが各方面から続々と寄せられており、楽しみにしていただいているのはたいへん嬉しいことではあるものの、いろいろ思うところあって、今回は開催いたしません。ごめんなさい。なので、いきなり「ブラジル32点、イタリア31点……アンゴラ2点、トリニダード・トバゴ1点」みたいなメールは送らないよう、お願いします。たぶん前回終了時に「ではまた4年後に」とか何とか申し上げたと思うので、約束を破ることになるのは心苦しいのですが、主な理由は以下のとおり。
1)たまには雑念なしにありのままのW杯を堪能したい。
2)セガレが一緒に観戦する都合上、生放送を見ることができず、開催順に観戦できるかどうかも怪しいため、作業が滞る可能性が大。
3)セガレに「なんでそんなに一生懸命パラグアイ応援してんの?」などと質問されたとき、正直に答えると教育上あまりよろしくない。
4)家計の状況を考えると、その作業時間を確保するために仕事の受注に関して消極的な姿勢を見せている場合ではない。
5)大会期間中はただでさえテレビ観戦で目を酷使するので、ドライアイ対策上、パソコンの画面を見る時間はなるべく減らしたい。
6)時間および労力の負担に耐えられるほどの情熱を1ヶ月間にわたって維持できるだけの自信がない。
7)つまり気力・体力の限界。
そんなわけで、事情のわからない方にもどんなイベントなのかすっかり丸わかりになっているような気がしなくもないですが、あしからず御了承くださいませ。ぺこり。
1.勇気あるキャプテン
2.センチメンタル
3.マーロン・ブランド
4.音楽の時
5.虎
6.“46”
7.エゴ電気通信
8.ビー・ビー・バップ
平成十八年五月三十日(火) 午後四時三十五分
BGM : PFM ? PFM ! / P.F.M.
7時半起床、8時20分出勤。きのう深夜まで取り組んでも片づかなかった月プレの原稿を13時前に仕上げて編集部に送り、さっきOKをもらったところ。たかだか1ページ1600字のインタビュー記事を書くのに、1日半もかかってしまった。連日連夜ベターッと切迫感がくっついて離れない単行本仕事を抱えておらず、飛び石で雑誌の〆切が訪れる状態だと、仕事に取りかかってもすぐにはテンションが上がらなくて困る。この場合、「テンションが上がる」は「オレ様化」とほぼ同じ意味なのではないかと、何かの拍子にふと思った。毎日グツグツ煮詰まりながら原稿を書いていると、「オレ様の原稿に文句はつけさせないぜベイビー」とか、「安心してオレ様に任せときなよ子猫ちゃん」とか、半ばヤケクソで(相手もおらんのに)威圧的な精神状態になれるので、何を書き始めてもすぐにトップギアで走れるのだが、前日までダラダラしていると、「どう書いたら喜ばれますかねぇ、はてさて」などと妙に遠慮深い姿勢になってしまっていけない。人として正しい生き方かもしれないが、いけない。
原稿を送ってOKの返事を待つあいだ、昼飯を食いがてら吉祥寺まで散歩しつつ、〆切の近づいたコラムの構想などボンヤリと考える。途中、スルスルと天から神が降臨したかのようにとてもナイスな展開を思いついたのだが、タワーレコーズに立ち寄ってバッハのカンタータ&ミサ曲集4枚組1995円をゲットして「むふふふ」とほくそ笑んでいるうちに、何をどう書こうと思っていたのかすっかり忘れて茫然自失である。着想の神様って意地悪だ。前髪しかないのは、チャンスだけではないのだった。こんどから、何か思いついたらケータイで原稿書いて自分にメールするようにしよう。親指でのろのろ打ってるあいだに忘れそうだけど。
散歩の帰りに寄ったコンビニで、「スパークリング・カフェ」なる缶入りの飲み物を買った。それが単なるコーヒーではなく「コーヒー入り炭酸飲料」であることに気づいたのは、キャップを開けて中身を口にした後だった。日本人って、どうして時々こういうものを作ってしまうんだろう。着想の神様の悪戯としか思えない。思わず椅子から飛び上がらんばかりの不味さ。なぜ社内で誰もこの企画にストップをかけなかったのか、ぜんぜん理解できない。それだけ景気が上向いているということなんだろうか。だとしたら、好景気なんてロクなもんじゃない。余裕があるなら、「売れないけど世に出す価値のあるモノ」を作りましょうよ。
1.Prima Che Venga la Sera
2.Amore Vero
3.Finta Lettera d'Addio
Di Una Rockstar Per Farsi Propaganda
4.Josephin Baker
5.Tempo Tempo
6.Chanson d'Un Aviateur
7.Colazione a Disneyland
平成十八年五月二十九日(月) 午前十時三十五分
BGM : Miss Baker / P.F.M.
金曜日は京都・祇園で屋形(置屋)のおかあさん、土曜日は両国国技館で某相撲通のインタビュー。どういうわけか和風の仕事が続いた。かたや女の園、こなた男の世界という違いはあれど、どちらもおよそ近代的ではないヘアスタイルの人たちが着物姿で当たり前に歩いている業界。そういえば舞妓・芸妓さんもお角力さんも本名とは別の風変わりな名前を持っているし、言葉遣い(「どすえ」と「どすこい」)も似ているといえば似ている。そして、どちらも「伝統を継続するための変革」という匙加減の難しいテーマを抱え、若い人材の確保および教育に頭を痛めているのだった。大相撲はとっくの昔に国際化しているが、いずれ祇園にも「青い目の舞妓はん」が登場する日が来るのだろうか、どうだろうか。
ところで京都では、取材後に錦市場に立ち寄り、三木鶏卵でだし巻玉子を購入。同行した編集者Mさんのお知り合いが経営しているとのことで勧めてもらったのだが、これはやたらウマかった。国技館では、琴ノ若の断髪式をちらりと見物。けっこうな数のお客さんが集まって、たいそう華やかな雰囲気だった。「人が髪を切られているところを拍手しながら見守る群衆」って、考えてみるとすごい光景だ。館内をうろうろしているあいだ、栃東、雅山、元大徹の湊川親方、元琴錦の竹縄親方、貴乃花親方などとすれ違うたびに「おお」と唸ったが、間近で見ていちばん強烈だったのは、なんといっても尾車親方。やさしげな包容力とおそるべき破壊力が渾然一体となった、異様な存在感である。
きのうの日曜日はヤマちゃん夫妻を招いて夏休みの過ごし方について打ち合わせ。ソーセージのトマト煮、ほうれん草とくるみのスパゲティ、魚介のスープ仕立てでもてなす。日本ダービーの3連複を取ったヤマちゃんは、シャンパンを買ってきてくれた。マークミスで、買ったつもりのない馬券が当たったというのだから、結果オーライのバカヅキもいい加減にしろという話である。バチが当たらないよう、どこかで徳を積んでおいたほうがいいと思う。
1.Suonare Suonare
2.Volo a Vela
3.Si Puo Fare
4.Topolino
5.Maestro Della Voce
6.Sogno Americano
7.Bianco E Nero
8.Tanti Auguri
平成十八年五月二十五日(木) 午前十時五十分
BGM : Suonare Suonare / P.F.M.
きのうの夕刻、セガレがジュニア・ドラム教室を見学し、その場で入会を決めた。私も終わり頃に顔を出し、レッスンの様子を少しだけ見学。個別指導ではなく、(きのうは2人だったが)数人の子供に同じことをやらせる「一斉授業」のスタイルで、厳しさというものもなく、こんなんでちゃんと叩けるようになるのかどうか些か疑問は感じたし、あまりドラマーらしくない穏やかな口調で喋る先生も上手いんだか下手なんだかよくわからない感じではあったが、まあ、本人は楽しみにしているようなので、「入口」としては悪くないだろう。ドラムの場合、レッスンの内容より何より、楽器の特性上、家で練習できないことがいちばんの問題だよな。月3回の教室だけでは、どんなに良いレッスンを受けたところで上達には限界があろう。せめて耳から良いドラミングを学ばせる必要があるので、どんどんCDを買わなければ。えへへ。うまい口実ができた。耳元では「サイレント・ドラム……」という悪魔のか天使のかわからない囁き声も聞こえるが、レッスン代だけでもバカにならないので、今は考えないことにする。3年生になってからZ会も始めたし、いよいよ「教育費の負担」ってやつがじわじわと押し寄せてきたのだった。ともあれ、セガレがドラムを始めるとなると、私もボヤボヤしていられない。中学や高校でバンドを組んだとき、その仲間に「おまえのオヤジ、全然ダメじゃん」とバカにされたのではセガレが気の毒だ。などと妄想をふくらませつつ入会手続きを済ませ、食事をして帰宅しようとしたら、外は激しい雨と雷鳴。もしかして、嵐を呼ぶ男?
70年代終盤から80年代にかけて、PFMがやや低迷していた時期のアルバムたちが紙ジャケで再発されたので、さっそく手に入れて聴いている。ご多分に漏れず、この時期のPFMも「時代の波には逆らえず」的な語られ方をされることが多く、たしかにポップ化というのかコマーシャル化というのか「器楽」から「歌モノ」への変化というのか、そんなようなプログレっぽくない音楽になっていることは否めないけれど、それ以前と同じように曲は良いのだし、PFMらしい上品な手触りみたいなものも決して失われてはいないので私は好きだ。少なくとも、何かを断念して不本意な思いを抱きながら作っているようには聞こえない。この種の変化を時代への「迎合」というニュアンスで一括りに語るのは乱暴だと思う。時代が彼らの音楽を作ったのではなく、彼らの音楽が時代を作るひとつの要素になったのだと考えたい。
しかし気になるのは、いま聴いているアルバムに『Bianco e Nero(邦題は『黒と白』)』という曲が入っていることで、こうなると、どうしたって「こいつらシマウマさん派か?」という疑念が湧いてくるのだった。うー。その曲の訳詞を見ると、<空のロール 白く、中は黒い>とか<この地球の子孫を止めることの出来なかった 2000年の戦争の手の中に戻る>とか、意味のよくわからない謎めいた言葉が並んでおり、少なくともカルチョのことを歌っているわけではないようだが、ユベントスが嫌いなイタリア人が『Bianco e Nero』というタイトルの曲を作るとも考えにくいよなぁ。いや、しかし、彼らはきっとカルチョには大して興味がないに違いない。セリエに似合うのはPFMのような慎み深い音楽ではなく、しばしば「シアトリカル」などと形容される胡散臭さ&ギミック満載の大言壮語系ユーロ・ロックのほうだからである。何のことだかよくわからないが、まあ、そんな感じ。長く溜め込んでいた胡散臭さが噴火して炎上中のカルチョ劇場のほうは、ラツィオも巻き込まれて「黒か白か」(黒なんだろうけど)という話になっているわけだが、あのう、B落ちした場合、UEFAカップの出場権はどうなるんでしょうかしら。そっちもダメですか。ダメですよね。すみません。
1.Viene il Santo
2.Svita la Vita
3.Se Fossi Cosa
4.Trame Blu
5.Passpartu
6.I Cavalieri del Tavolo Cubico
7.Su Una Mosca E Sui Dolci
8.Fantalita
平成十八年五月二十四日(水) 午前十一時三十分
BGM : Passpartu / P.F.M.
わしズム入稿シーズンが接近しているのにコラムの題材が決まらず、気分が落ち着かない。そんな折、文藝春秋6月号に「私たちの嫌いな日本語」と題した阿川弘之・阿川佐和子・村上龍の「爆笑憂国座談会」が掲載されていたので、ネタがかぶってはマズイと思い、買って読んでみた。取り上げられていたのは、「生きざま」「癒し」「こだわり」「とんでもございません」「キレる」「させていただきます」「頑張れ」「私って……じゃないですか」等、いずれも嫌いな日本語業界のスタンダードナンバーばかりである。そういう耳タコなヤツでいいんなら、ネタ探しも楽なんだけどなぁ。みんなが嫌ってるものを「嫌いだ」って言っても、あんまり面白くないんだよなぁ。
ところで、残念ながら一度も「爆笑」することのできなかったこの座談会記事のなかで、唯一ちょっとだけ苦笑させられたのは、かつては否定的な文脈で使う副詞だった「とても」をめぐるやりとりである。「肯定的に使うのは、芥川龍之介なんかも反撥を感じてたようだねえ」という阿川弘之の権威主義的な発言に対して、自分の本名と同じ名の文豪を引き合いに出された村上龍が、「僕も小説を書くときにたぶん肯定的に使ってしまうんですけれども、一ページの中に二つぐらい重複して使うと、気持悪くなってくるんです」と苦しげに答え、無理やり論点をすり替えていた(その後、「とても」は放置され、話題は「文章における単語の重複の是非」に転じた)のは、面白かった。取材現場の気まず〜い空気がビビビッとビビッドに伝わってきて、ふだん対談や座談会記事の構成を仕事にしている者にとっては「とても」スリリングだ。
このクダリを削除させなかった村上龍には一定の敬意を払ってもいいと思うが、ことほどさように、仕事で言葉を扱う者が他人の言葉遣いについて批判的に語ることには怖い面があるのだった。偉そうに言葉の誤用を指摘した者が、別の言葉を誤用しているケースは(むろん私も含めて)少なくない。たとえば、さんざん「いまどきの日本人ときたら!」という調子で日本語の誤用をあれこれと論っている著者が、「すべからく」を明らかに「すべて」の意味で使っているという無惨な本が、私の知る範囲でも二冊はある。そのうち一冊には「的を得る」もあったような気がする。村上龍の「肯定的とても」は単純な誤用ではなく、おそらく過去の使用法を知りながら「でもまあ、今はいいじゃん」と思ってるんだろうけれど、それでも「そもそも本来は」と言われるとあまり堂々と反論できない感じなので(じっさい村上龍も、肯定的に使って「しまう」という言い方をしている)、辛いところだ。自分の首を絞めることにならぬよう、ネタ選びはすべからく慎重にすべし、と思いました。
……そういえば、この「ネタ」って言葉の使われ方も、なんかヤな感じがあるよな。昨今は、批判や説教や攻撃を受けそうな言動を冗談や悪ふざけとして軽く受け流してほしいときに、「ネタですから」という言い方で防御線を張るケースが多いように見受けられるが、これを聞くと、「ネタっておまえ、それをどこかで発表するアテでもあんのか。そんなもんでお金もらえるとでも思ってんのか」と問い質したくなる。昔は同じようなときに「シャレだよ、シャレ」という言い方をした。この変化はなかなか興味深い。ネタ帳にメモしておこう。
Disc 1
1.Better Days
2.Book of Dreams
3.Valentine's Day
4.Thunder Road
5.Candy's Room
6.Johnny 99
7.Man at the Top
8.If I Should Fall
9.Something in the Night
10.Atlantic City
11.Highway Patrolman
12.Mansion on the Hill
13.Badlands
14.State Trooper
15.I Ain't Got You
16.Bobby Jean
17.River
18.Back in Your Arms
19.E Street Shuffle
Disc 2
1.Brilliant Disguise
2.New York City
3.Pink Cadillac
4.Streets of Philadelphia
5.My Hometown
6.Light of Day
7.Lucky Town
8.I'm on Fire
9.Downbound Train
10.Stolen Car
11.Souls of the Departed
12.Two Hearts
13.Promise
14.For You
15.Hungry Heart
16.Secret Garden
17.Born to Run
18.Working on the Highway
平成十八年五月二十三日(火) 午前十一時
BGM : Light Of Day - A Trbute To Bruce Springsteen / V. A.
ずいぶん前からテレビで見かけるたびにブツブツ文句をつけているのだが、日本生命のCMで谷川俊太郎の偽善的な作文が朗読される中で快打を放ち、仕事が終わるのが遅れてギリギリで観戦に駆けつけた美しい母親の前で、3塁ベースを蹴って一気にホームまで突入した少年は、アウトだと思う。セーフにしたいなら、もっと確実にセーフに見えるような映像をこしらえてくれ。あれでは、バックホームした野手やタッチした捕手の親御さんたちが激怒しているんじゃないかと思って、気が気じゃない。私だったら、きっと主審に詰め寄ることだろう。判定をお金で買うことは(私には)できないが、抗議に愛情を込めることはできる。
私はブルース・スプリングスティーンをかなり苦手にしているのだが、きのう月刊PLAYBOY編集部に顔を出したら、ニューカッスルファンでギターも弾くNさんがこのトリビュート盤をくれたので、ありがたく聴いている。Nさんは、私に仕事をくれることよりもCDをくれることのほうがちょっと多いかもしれない。貴重な仕事仲間。日頃これだけロックを聴いているのに、参加37組のアーティストのうち私が名前を知っているのはただ一人エルヴィス・コステロだけだというのは驚くべきことで、その世界の広さに茫然とするわけだが、そんなことはともかくとして、これはなかなかどうして悪くない。つまり私はスプリングスティーンの書く曲ではなく、声や顔や人柄(会ったことはないけどよ)や「青春18きっぷ」みたいな名前の語感などが苦手なのだということがわかった。でも、たとえ曲は良くても、声や顔や人柄や名前の語感などが気に入らない人の演奏を聴くのはやっぱり辛いこと。ところで、きのう取材に同行してくれた同編集部の若手編集者K君と話していたら、彼もまたギター(しかもレスポール)を弾く人だということが判明し、初対面なのに、それだけで旧知の間柄のごとく接せられるようになった。ギターを習い始めて以降、こういうことが時々ある。ギターってすばらしい。でも、これがもし「えっ、そうなんですか? 実は僕もリコーダー吹くんですよ」だったら、ちょっと引くかもしれないような気がするのが不思議なところ。
秋田で起きた事件の犯人が誰かということについて、ものすごくイヤな可能性を妄想してしまった。とてもここに書けるような話ではないが、愚妻もうっすら同じことを考えていたようなので、そう珍しい妄想ではないのだろう。実際はそんなことあるはずがないとは思うが、ふだん小学生やその保護者と接している人間でさえ、荒唐無稽な安っぽいミステリ小説のごとき恐ろしい筋書きが「あっても不思議じゃない」と思えてしまうこと自体が恐ろしい。ともかく、あれは連休前だったか、セガレの小学校の通学路でも(うちからは遠い地域だが)、カッターナイフを手にした男が登校中の女児を脅かす事件が発生し、さいわい怪我などはなかったものの、まだ捕まっていないようなので、いよいよ他人事ではない。このごろ、通勤途中にすれちがう小学生たちの私(を含めた大人たち)を見上げる視線が、かすかな怯えと不信感を孕んでいるようにも感ぜられる。微笑を投げかけて安心させてあげようかとも思うが、見知らぬ子に馴れ馴れしく振る舞うとかえって怪しまれるような気もして、つい目を逸らしてしまうのだった。毎日そんな重苦しく緊張した空気の中で通学する子供たちは、本当に気の毒だ。
1.Questar
2.My Song
3.Tabarka
4.Country
5.Mandala
6.Journey Home
平成十八年五月二十二日(月) 午後十二時四十五分
BGM : My Song / Keith Jarrett
セガレの誕生日。満9歳になった。おめでとう、R太郎。あっという間の9年間だったような気がするが、反面、昭和40年代のジャイアンツはずいぶん長く優勝し続けていたんだなぁとも思う。きのうは4人の祖父母を招いて恒例のお誕生日会。椎茸のグラタン、蟹のトマトクリームスパゲティ、鶏肉のトマト煮込みでもてなす。書いておかないと来年同じものを作りかねないので、メモしておいた。どうやら祖父母は最初から「イタリア料理を食べられる」と思って楽しみにしているようなので、私にとっては結構なプレッシャーだ。レパートリーを増やさなければ。ところで9歳になったセガレは、先日「ドラムを習いたい」と言い出した。クラスメイトがヤマハのジュニア教室で習っているのを知り、自分もやりたくなったらしい。いまから申し込めるのかどうかは不明だが、どうしたわけか、すでにスティックは持っているので、準備は万端である。
1. Sentiments
2. Andalusia, Andalusia
3. A Sevilla
4. Ball De Les Fulles
5. Magic
6. Joguines
7. Alegries Del Mediterrani
平成十八年五月十九日(金) 午後二時五分
BGM : Sentiments / Iceberg
なんとか試合結果に関する情報をシャットアウトしたまま半日をしのぎきった家族3人がテレビの前に集結したのは、きのうの午後4時ぐらいのことである。バルセロナ×アーセナル(欧州チャンピオンズリーグ決勝)の中継を収めたビデオを再生し、やたらと員数をかけたわりには貧相な印象ばかりが残った試合前のセレモニー(あの暦年を順番に記しただけの巨大な布のいったい何が面白かったのだろうか)を見ながらキックオフを待っている最中に、セガレがこんなセリフを呟いた。
「……レッドカードのない試合になるといいなぁ」
ほぅ。なかなか立派なご意見を述べる感心な男じゃ、これも日頃の家庭教育の成果であろう。と、親バカな私を自己満足に浸らせるには十分な発言である。セガレは(両親がバルサ贔屓であるにもかかわらず)かなり熱心なレアル・マドリーのファンで、ならばバルサの決勝進出は我慢ならないはずなのだが、国内のライバルの後塵を拝したことよりも、準々決勝でマドリーがアーセナルに惜敗したことのほうがよほど悔しかったらしく、ファイナルの組み合わせが決まったときから、「バルサにアーセナルをボコボコにしてほしい」と、怨念さえ感じさせる物騒な発言をくり返していた。したがって、「アーセナルが9人ぐらいになっちゃえばいいのに」などと言ったとしてもおかしくはないのだが、それでもなお勝負のプロセスを重んじ、最後まで数的な有利不利のない状態でゲームを楽しみたいという姿勢を見せたことは、実際はそんな家庭教育をした覚えのない親にとって、とても喜ばしいことだ。まあ、子供というのは元来、時に残酷で邪悪な面も見せるが、時に大人よりも倫理的だったりするのである。
しかし実のところセガレの言葉は、そんなこととはまるで関係なく、単に子供の第六感が言わせたものだったのかもしれない。考えてみれば、今までそんな発言を聞いたことはないのだから、ユベントスやインテルがらみの試合ならともかく、両チームともさほどラフプレイが多いとは思えず、荒れそうな気配も感じられないこの対戦を前に、唐突にそんなことを言い出すのは不思議といえば不思議だ。
いずれにしろ、そんなこともあったので、早い時間帯に、先制ゴールをほぼ手中に収めていたエトーを倒したGKレーマンが退場処分を受けたのは、ひどく残念だった。それは、双方が最高のパフォーマンスを発揮できる状態で決着をつけてほしいという良い子の願いが叶わなくなったせいでもあるし、一人多いバルサがアーセナルを「ボコボコ」にしても面白くねぇよな、という身勝手なファン心理のせいでもある。アンチ・アーセナルで一致団結していた我が家の茶の間には、あの瞬間、とてもシラケた空気が漂っていた。アーセナルに対する惻隠の情が芽生えてしまい、猛り狂ってバルサに声援を送りづらい雰囲気になってしまったのである。
なので、セットプレイからキャンベルのヘディングでアーセナルが先制したことは、「頭に血を上らせて歯軋りしながらみんなで試合を楽しめる状況」を作ってくれたという意味で、我が家にとって幸いであった。あそこでFKを得たエブゥエの転倒にバルサの選手が関与していないように見えたことも、惻隠の情を消し去る一因になったように思われる。だいたい、レーマン退場までの展開を見れば、ボコボコにされそうなのはむしろアーセナルの速度に翻弄されっぱなしだったバルサのほうだったのだ。もし立ち上がり早々にバルサゴールを強襲したアンリのシュートをGKバルデスが奇跡(=「偶然」の別名)とも思える反応で防いでいなかったらと思うと、恐ろしい。ファン・ハール時代から今日にいたるまで、バルセロナというチームは強いときも弱いときもどういうわけか妙に「浮き足立ったところ」のある集団だと私は日頃から感じているのだが、この試合でも彼らは見事に浮き足立っていた。
で、あるからして、相手が10人になったからといって、バルサがアーセナルを「ボコボコ」になんぞできるはずがないのである。私たちは、レーマン退場ぐらいのことで油断したおのれの不明を恥じ、自らに猛省を促しながら、頭に血を上らせ、歯軋りをし、「なんだよ、それ、レーマンだったら入ってたんじゃねぇのか!?」と愚痴をこぼし続けた。浮き足立った攻撃からボールを奪われ、前を向いたアンリが疾走する姿を見ながら、いったい何度「2点差」の恐怖に背筋を凍りつかせたことだろう。
しかし、あれは70分前後だったか、コーナーフラッグの下にしゃがみ込み、疲労感をあらわにして喘ぐアンリの姿を大きく映し出したテレビ映像は、パリの現場で起きていることを世界中の視聴者に生々しく伝達することに成功していた。アーセナルが1つの失点を無効にするために払った代償がいかに大きいものだったかということを、その映像は雄弁に物語っていたように思う。さらに、「この時間帯以降はバルサ得点の可能性が高まる」という過去のデータに基づいていると思しき八塚アナの発言も、私たちを励ました。あれは八塚さんにとっても「してやったり」の実況だったことだろう。ふだん試合展開に関する「小予想」を的中させることに血道を上げている某解説者がテレビの前で嫉妬に燃え狂っている姿が目に浮かぶ。ラーションの巧みなラストパスを受けたエトーの同点ゴールが決まったのは、八塚発言の数十秒後だった。
茶の間に(世間から12時間遅れで)渦巻く歓声。果たして、サッカーにおける味方の同点ゴールほど、ささくれだった人の心を和らげるものが他にあるだろうか。それはもしかすると、来月の家賃をいかにして支払うかということについて真剣に心配(=「絶望」の別名)しているときに思いがけず届いた重版通知よりも大きく心の平穏に寄与するかもしれない。セガレが「やったやった」と小躍りしながら、ヒーローを讃えるべく、愛読している『ワールドサッカーキング』の付録ポスターを広げて、クローゼットの扉に磁石で貼りつけた。右足を振り上げてシュート態勢に入ったエトーの雄姿をとらえた写真(ちなみに裏面はベルカンプ)である。私は重版通知を冷蔵庫の扉に磁石で貼ったりはしないから、やはり同点ゴールのほうがインパクトが強いということであろう。
その5分後に我が家の茶の間を支配した幸福感は、4年前の日本×ベルギー戦で一時は勝ち越しゴールとなる稲本のシュートが決まった瞬間を思い出させるほど豊穣なものだった。「稲本の左足」が信用に足るものではなかったのと同様、「角度のないエリアからシュートを撃つベレッチ」も、まったくアテにできないものだったのだ。何を言っているのかよくわからないことになっているが、とにかく、日頃からその不器用さに溜め息をつきつつも「がんばってほしいよなぁ」と言って(とくに愚妻が)愛玩していた選手が、おそらくは人生最大の手柄だろうと思われるグッジョブをやってのけたことが、私たちはうれしかった。折り重なる仲間たちの祝福と感謝の嵐を浴びているベレッチが、すでにその場で気を失っているのではないかと心配したが、その後もプレイを続けたので安心した。
良くも悪くも「らしい戦い」を見せたバルセロナが、2-1で逆転勝利。表彰式後、会場に『We Are The Champion』は流れず、したがって付け髭を与えられたジュリがフレディ・マーキュリー役を演じる姿も見られなかったが(曲が流れたとしても見られなかったとは思うが)、ロナウジーニョとベレッチが並んで踊っている後ろ姿は実に微笑ましかった。そして観戦終了後に私たちが3人で囲んだ食卓もまた、とても微笑ましく愉快なものになったことは言うまでもない。サッカー史に残る試合だったかどうかはわからないけれど、私たちの家族史にはしっかりと刻まれる一戦になった。続くワールドカップでも、親子で末永く共有し語り合うことのできる興奮と歓喜が量産されることを、私は願っている。あと、今年のトヨタカップのチケットが3枚手に入ることも。
1.City Life
2.Nude
3.Drafted
4.Docks
5.Beached
6.Landscapes
7.Changing Places
8.Pomp & Circumstance
9.Please Come Home
10.Reflections
11.Captured
12.Homecoming
13.Lies
14.Birthday Cake
15.Nude's Return
平成十八年五月十八日(木) 午前十一時二十分
BGM : Nude / Camel
CL決勝はセガレの下校後に観戦予定。情報遮断中。
ゆうべはギターのレッスン。いつまでたっても初心者で、始めてから2年半も経ったような気がしない。この2年半のあいだに、セガレが勉強やサッカーでどれだけの知識やスキルを身につけたか考えると、わが身の伸び率の低さに絶望的な思いを抱いたりする。
師匠宅から帰宅する途中、井の頭線の車内で、鉛筆と消しゴムを手にした大学の先生らしき初老の男性が、学生のレポートと思しき作文を添削していた。私は吊革につかまり、先生が座席で膝に置いた原稿用紙を前から見下ろしていた(つまり逆さまに見ていた)ので、細かいところまでは読めなかったが、どうも「新聞学科」の「文章作法III」という授業の課題として提出させたもののようだ。何やら「電車で人に席を譲ること」と「自由と平等」の関係について書かれており、「人間が平等ならば席を譲ろうが座っていようが本人の自由だと思う」というようなことが若々しい文体(物は言いようである)で力説されていたが、ほんの一部しか読めなかったので、そこにどういう脈絡と意義があるのかはよくわからない。たぶんこの学生さんは、どうしても電車で座りたいのだろう。先生は、「ゆずる」を「譲る」に直したり、読点を書き込んだり、一気に3行をバッサリと削除するなどして熱心に添削していたが、ひととおり修正を終えた後、欄外に「※ですます調に統一しましょう」と書いてから「ふうっ」と大きく溜め息をついていたのが印象的だった。新聞学科に進む学生でさえかようなことになっているのだから、巷間しばしば指摘される「大学生の国語力低下」はいかばかりかと案ずるのだし、大学に「文章作法」という授業が存在すること自体に「なるほどなぁ」と変に感心したりもするわけだが、しかし私のギターはその学生さんの作文以下のレベルなのだと思うと、もっと深い溜め息が出ました。
キャメルが1981年に発表した『ヌード』は、1974年にルバング島から帰還した元日本兵・小野田寛郎さんをテーマにしたコンセプト・アルバムだという。なんで英国人ミュージシャンがそんなことを思い立ったのか謎だし、タイトルは「onoda」と「nude」の語感が似ているところからつけられたという説があることを聞くとそれはちょっと無礼なのではないかと思わないでもないが、中身はキャメルならではの当たり障りのないホンワカした地球にやさしいサウンドで私は好きだ。褒めてるのか貶してるのかよくわからない。
それにしても、小野田さんの帰還からすでに32年である。そして終戦から小野田さん帰還までは、29年。今になってみれば、74年当時はまだあの戦争が「ちょっと前の出来事」だったことが実感を伴って推察されるけれど、そのとき10歳だった私は、小野田さんがまるで太古の昔から現代に蘇ったかのような印象を受けたものだ。たぶん、戦争が「ちょっと前の出来事」であることが実感できるような教育がなされていなかったに違いない。今から29年前って、ピンクレディーの時代だもんな。ピンクレディーの大流行を「ちょっと前の出来事」のように教えることは可能だと思われるのに、戦争が「大昔の出来事」のようにしか教えられなかったのは妙だ。映像が白黒しかなかったこともその一因かもしれんが。ところで、小野田さんの帰還に貢献した鈴木紀夫さんという冒険家が、その後、雪男発見に情熱を注ぎヒマラヤで遭難死していたということを、さっき初めて知った。うーむ。唸るしかない。ファンタジー風味たっぷりの音楽を聴きながら、キャメルと鈴木紀夫さんのモチベーションに何か共通点はあっただろうかなかっただろうか、などと考える。
1.Help Me Up
2.Competition
3.Are You Talkin' to Me?
4.Dynamite
5.Something Beautiful
6.Warm Love
7.Betcha Won't Dance
8.Fever
9.Tear Jerker
平成十八年五月十七日(水) 午前十一時五分
BGM : It Takes One To Know One / Detective
ペルッツィとオッドがイタリア代表に選ばれた。ということを、「サネッティがアルゼンチン代表から外された」という情報と共にセガレの口から風呂場で最初に聞かされたというのは、なかなか画期的な体験である。愚妻に教わったとはいえ、セガレのほうが私よりも先にサッカー情報を仕入れていたのは、オッドの代表入り以上に驚くべきこと。
ジミー・ペイジが(全面的にではないようだが)プロデュースに関わり、ZEPが設立したスワンソング・レーベルから1977年にデビューしたのが、きのうから聴いているディテクティヴである。最近その存在を知り、私が気に入らないわけはないだろうと思って手に入れたのだが、気に入った。事前に聞いていたとおりドラムの音はジョン・ボーナムのそれにとてもよく似ており、セルフタイトルのデビューアルバムには『クランジ』みたいなファンクナンバーも入っていたりして、ツェッペリン好きをニヤニヤさせる要素には事欠かないのだが、私の耳には、ちょっとストーンズも入っているように感ぜられる。ツェッペリンとストーンズを7:3の割合で足して6で割ったぐらいでしょうか。2で割れるほどの存在感がないのは、そりゃあ、しょうがない。6でも大したものである。それにしてもわからないのは、どうして「探偵」などという野暮ったい名前をつけてしまうのかだ。2枚ともジャケットのデザインからしてどうしようもないので、音楽を包むパッケージに対する関心や意欲が極端に低い人たちなのかもしれないが、「探偵」はないよ。もし知り合いが「探偵」というバンド名でデビューしようとしたら、私なら羽交い締めにしてでも止めると思う。
しかしまあ、それを言い始めたら、それこそローリング・ストーンズにしろビーチ・ボーイズにしろキング・クリムゾンにしろディープ・パープルにしろジェントル・ジャイアントにしろイエスにしろイーグルスにしろ、たいがいのロックバンド名は日本語にするとロクなことにならないわけで、ジェスロ・タルなんかは18世紀に実在した農学者の名前らしいので翻訳不能だが、あえて言うなら「新渡戸稲造」(こっちは19世紀生まれだが)だったりするのだから、それもいかがなものかと思うのである。ピンク・フロイドは「桃色音弥」ぐらいかな。いや「ピンク」も人名が由来だったっけ。ともかく、これはもう、ほとんどイカ天の世界である。こういうネーミングを英語圏の人々がどのような感覚で受け止めているのかというのが、かねてからの謎。
ゆうべは、エスパニョール×ソシエダ(リーガ最終節)をビデオ観戦。後半ロスタイムにようやく決まった可哀想な子犬コロちんのゴールで1-0、エスパニョールが感動の一部残留。「可哀想な子犬コロちん」はラーメンズ好きには説明不要だし、ラーメンズを知らない人には説明しても面白くないので、説明しない。ほんとうの名前は「コロ」である。きゃんきゃん走り回るコロちん、初めて見たのに、わが家では人気沸騰中。どうでもいい話ばかりしている。
1.Recognition
2.Got Enough Love
3.Grim Reaper
4.Nightingale
5.Detective Man
6.Ain't None of Your Business
7.Deep Down
8.Wild Hot Summer Nights
9.One More Heartache
平成十八年五月十六日(火) 午後三時四十五分
BGM : Detective / Detective
きのうの朝が〆切だったSAPIOの原稿を日曜の晩に自宅へ持ち帰り、夜明けまでには片づくだろうと思ってやっていたのだが、意に反して7時すぎに妻子が起きてきても終わっておらず、しょうがないのでセガレと一緒に朝飯とも夜食ともつかぬ食事をし、「ゴー宣」読者にはお馴染みの担当Tさんが編集部に出勤するまでに送らないとなぁ、でも出勤時間って何時だろうと思いながら再び書き続け、10時ちょうどに仕上げて送信前の最終チェックをしていたらTさんから「どうですか」と電話が来たので笑った。野球でも同時はセーフなのでこれも「セーフ」だったと思いたいが、出勤した時点で届いていないかったんだからアウトか。たかだか4ページの雑誌原稿なのに、近頃はこの程度の分量でもグズグズと徹夜仕事になってしまうことが度々あり、どうにも困ったことである。どんどん「文章を書くのが苦手な人」になっているような気がしなくもない。この先どう展開しようかとボーっと考え込む時間が、10年前の2〜3倍になっている。老いってわかりやすい。
しかし送稿から数十分後、心身ともにボロボロになって茶の間でブッ倒れていたところにTさんから電話があり、修正したいところがあるのだが「まだ余力ありますか?」と問われ、一瞬「もう無理だと言え」という悪魔の囁きと「おやりなさい」という天使の呟きが脳内で交錯したのだが、すぐに「やります」と答えたあたりは、老いと戦う男の意地というものだ。負けてたまるか! っていうか、職業人として当たり前の対応ですけども。必要な資料をファックスで受け取って朦朧とした頭で読み込み、原稿に手を入れて再び送信。OKの連絡をもらい、さて寝ようかと思ったが午後2時〆切の短い原稿があったことを思い出し、バシャバシャと半ばヤケクソでキーボードを叩きのめす。
送稿後、せっかくだからワイドショーで日本代表のメンバー発表を見てから寝ようと思ってテレビをつけたら、キャプテンと監督ちゃんが長々と挨拶をしやがるので気を失いそうだった。ジーコの話を聞いていて、一瞬、相馬と浅野と北沢が選出されたのかと勘違いして腰を抜かしそうになったのは私だけではあるまい。なんであの3人の名前が挙がってたんだろう。ジーコが選んだ23人のうち、22人が四捨五入すると30歳(20歳になるのは駒野ひとり)だということに気づく。みんな、いつの間にか大人になってたんですね。そりゃあ、おれだって老いるわいな。4年後の日本代表に不安を抱きつつ、2時半に就寝。さして眠れぬまま、晩飯前に起床。夜のニュースで、自分の息子が代表に選出された瞬間、「おわっ!」と叫んで飛び上がり、周囲の人たちに「いま言ったよね? マキって言ったよね?」と確認しながら恐慌状態に陥っていた巻のお父さんを見て、心が和んだ。