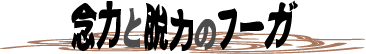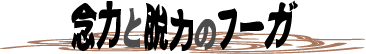1.Heroes Cry
2.In Your Eyes
3.Lovely Day
4.Living in the Moonlight
5.Blues
6.Wings in the Night
7.Moonshine
8.War Is Over
|
平成十八年六月十六日(金)
午前十時二十五分
BGM : Moonshine / Collage(ポーランド)
きのうは午後3時から神保町で某相撲通の口述取材4時間。大相撲の復興を目指す本を作ろうというわけだ。世界がフットボールに包囲されているときに、「おっつけ」「はず押し」「かんぬき」といった戦法に関する解説を聞くのもまたオツなもの。名古屋場所を見るのが楽しみになってきた。ちなみに初日は決勝戦と同じ日だ。そのへん、相撲協会もちょっと考えたほうがいいと思う。それにしてもワールドカップ期間中は取材に出かけたくないもので、神保町まで往復するあいだ、電車内で人々が手にしている夕刊紙の「ドイツ勝った」「ロスタイム」「ノイビル」といった見出しから逃げることができなかった。正確に言えば、一部が人々の体に隠れていたので「ドイツ勝」「スタイム」「ノイビ」しか目には入らなかったのだが、それだけも何が起きたのか丸わかりだ。だって「ロスタイムにノイビルのオウンゴールでドイツ勝ち点落とした」のわけがないじゃないか。見出しだけで丸わかりにするのが新聞の仕事だとはいえ、そんなにデカデカと報じるようなニュースなのかそれは。だったら大相撲もそれぐらい派手に扱ってやれよ。

◇チュニジア×サウジアラビア(グループH)
グループリーグ第1ラウンドの掉尾を飾るにふさわしい、大変な泡沫感にあふれたカードである。それを含めてグループリーグだ。実にワールドカップらしい。もっとも人のことは言えないのであって、日本×豪州と韓国×トーゴとこの試合のうち、欧州や南米や北中米の国々でどれがもっとも低い視聴率を獲得したのか知りたいところではある。ともあれ、もうさすがに全試合をフルサイズで観戦するのは困難なので、私が取材に出かけているあいだに「見てていいよ」と妻子に伝えたのだが、帰宅して話を聞くとこれがなかなかの試合だったようで、かなり損をした気分。家族と興奮を共有したいので後半35分以降のクライマックスだけ見たが、結末を知っていたのではやはりおもしろくない。『刑事コロンボ』は結果(犯人)がわかっているのにおもしろいが、サッカーはダメだ。いや、『刑事コロンボ』だって最後の10分だけ見たんじゃおもしろくないか。追いつ追われつで2-2の引き分け。

◇ドイツ×ポーランド(グループA)
というわけなので、この扇情的かつ劇的な一戦も心から堪能することはかなわず、何も知らずに判官贔屓で熱心にポーランドを応援している愚妻の横で黙〜って見ていたわけだが、しかし、私がこの試合を楽しめなかったのは、結果を知っていたことだけが理由ではないような気がしてならない。ロスタイムにノイビルの決勝ゴールでドイツが勝ったことは知っていたものの、スコアまでは知らない(つまり2-1とか3-2とかだったかもしれないと思っている)のだから、いつ得点が入るかと少しはドキドキしてもよさそうなものなのに、キックオフから15分ほど過ぎた頃には、なぜか「こんなサッカーの何がおもしろいんだよ」とやさぐれた精神状態になっていた。うまく説明できないのだが、それは、ふだんセリエAを見て「つまんねえ試合だな」とブツブツ言っているような日常レベルの問題とは異なる、もっと根源的なつまらなさのようなものだ。何だそれは。なんちゅうかこう、これまでのサッカー観がグニャリとひん曲がるような感触さえあったのだよ子猫ちゃん。だから何なんだっつうの。
わからないが、もしかすると、ドイツとポーランドの選手たちが身体的な快楽のようなものを味わいながらプレイしているように見えなかったことが私には退屈だったのかもしれない。「身体的な快楽」などと言い出すと村上龍みたいでイヤになってくるが、それは「ボールと自分」の接触から生じる単純なキモチ良さのことで、私には彼らのボール扱いが、キモチの良いモノに触れている人間の態度に見えなかったのである。これは多分に私の側の問題であり、たぶん今までも同じような試合は山ほど見てきたのにたまたまこの試合で何かに気づいたというだけのことで、したがって両国の選手を責めるつもりはないし、彼らがマシンのように見えたというわけでもないけれど、私はこの試合を見ながら、仮に「すばらしいスピードで走りながら華麗なパス回しを見せるロボットたちのサッカー」があったとして、私たちはそれを楽しめるのかといったようなことも考えたりしていた。うーむ。この言い方では陳腐だ。私が言いたいのはそんなことじゃないような気がする。ここで言いたいことを、大会が終わるまでにちゃんと言葉にできるといいのだが。1-0でドイツ2連勝。
|
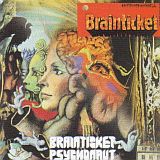
Brainticket
1. Black Sand
2. Places of Light
3. Brainticket, Pt. 1
4. Brainticket, Pt. 1: Conclusion
5. Brainticket, Pt. 2
Psychonaut
6. Radagacuca
7. One Morning
8. Watchinユ You
9. Like A Place In The Sun
10. Feel The Wind Blow
11. Cocユo Mary
|
平成十八年六月十五日(木)
午前十時五分
BGM : Brainticket & Psychonaut(2 in 1) / Brainticket(スイス)
忙しくて、ゆっくり日誌を書いている暇がない。ほんとうは、こんなに仕事を抱えているときにワールドカップなんか見てる暇ねえだろ、という話だが、ワールドカップやってるときに仕事なんかしてる暇ねえだろ、とも言える。言えるけど言っちゃいけないことというのも、世の中にはあるが。ところで、きのう興奮してちゃぶ台をひっくり返しているうちに書き忘れてしまったのだが、トーゴのダンス・アフター・ゴールは、ユニークでとてもおもしろかった。アフリカ勢のダンスはワールドカップの醍醐味のひとつだ。今回も新しいパターンを見ることができてよかった。ありがとう、トーゴ。

◇フランス×スイス(グループG)
スイスへの期待感が高かったので、もっとシャープな展開になるような気がしていたのだが、暑さのせいなのか何なのかモッサリした試合になって残念。フランスは、98年決勝ロスタイムのプティのゴール以来、ワールドカップでは360分間連続無得点である。あの大会、決勝トーナメントに入ってから得点したのはMFとDFだけ(たしかブラン1、テュラム2、ジダン2、プティ1)だから、FWに限っていえば720分間以上ゴールがないってことだ。冴えないプレイに終始したフランスの12番について、わが家では「偽アンリ説」がまことしやかに囁かれている。あんなに憎らしくないアンリなんて、アンリじゃないやい! 闘争心に欠けるゆる〜い表情からは、「ジダンと一緒にサッカーしたくないんじゃねえの説」も急浮上だ。ベラーミを使わなかったスイスには不満が残るが、国歌がすばらしく美しくて何度も聴きたいので今後も応援したい。古文の先生みたいなクーン監督の落ち着いた佇まいも好感度大。一方、化学の教師みたい(by 愚妻)なドメネク監督の神経質そうな佇まいは、なぜか見る者の心をざわつかせる。試合は、(たぶん)マケレレさんとギャラスががんばったお陰でスコアレスドロー。ちなみに本日のBGMは、スイス出身のサイケデリック・ロック・バンドである。かなりやかましい。国歌とは似ても似つかぬ音楽だ。当たり前だけど。一般的にはジャーマンロックとして語られることが多いようだし、リーダーはベルギー人らしいので、何がどう「スイス出身」なのかよくわからないのだが、まあ一応そういうことで。

◇スペイン×ウクライナ(グループH)
ふと気づけば、スペインはずいぶん世代交代が進んでいたのだった。モリエンテスとかエチェベリアとかメンディエータとかいないし。メンディエータかよ。寂しいよなぁ。ガイスカ君のいないスペインなんて、 ミック・エイブラハムズのいないジェスロ・タル、古澤良治郎のいない向井滋春バンドみたいなものだ。いいじゃんそれ。どっちも最高じゃん。どうにもこうにもよくわからない比喩になってしまった。「森君のいないSMAP」でもいいような気もするが、「スーちゃんのいないキャンディーズ」ではダメだ。スーちゃんのいないキャンディーズは、メンディエータのいないスペインというよりも、むしろガットゥーゾのいないイタリアみたいなものである。どんどん話がわからなくなっていくので、もうやめる。ともあれ、すっかり悪ガキ軍団に変身したスペインが、戦前の(わが家の)心配をよそに4-0の圧勝だ。あいつらをそのまま渋谷センター街に放っても圧勝しそう。誰に勝つのか知らないが、とにかくボコボコだ。いいからやっちまえ! いいからやっちまえ! 扇動してどうする。きょうは46年前に国会南通用門で樺美智子さんが亡くなった日なので、あんまり物騒なことは言わないほうがいい。ウクライナは酷かった。ペナルティ&退場の判定は気の毒すぎたとはいえ、こんなに弱っちいとは思わなんだ。あんなシェフチェンコなら、ロンドンには来なくていい。
|
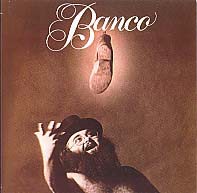
1.コーラル(軌跡のテーマ)
2.パンのなる木
3.変身
4.太陽の彼方から
5.一人ぼっち
6.ナッシングズ・ザ・セイム
7.軌跡2
|
平成十八年六月十四日(水)
午前十一時二十五分
BGM : イタリアの輝き バンコ登場 / Banco(イタリア)
セガレによれば、きのう(日豪戦の翌日)の3年2組は「みんな元気がなかった」そうだ。これは日本が負けたからというより、おもに寝不足が原因である。セガレ自身「ぼくも眠かった」と言っていた。みんなダラダラしていて、4時間目の終わりには図工の先生に長々と説教を食らい、給食開始が15分も遅れたらしい。ほほえましい話だ。この手の不良性というか逸脱行為のようなものは、小学校3年生ぐらいから一斉に始まるのかもしれない。要は親のほうが「大人だけライブ観戦で盛り上がるのもアレやし、そろそろちょっと無理させてもええやろ」と、少しばかり大人扱いし始めるということである。しかし4年後には、「おれが見ておくから父さんは早く寝なよ」とこっちが子供扱いされてるかもしれんと思うのは、まだグループリーグの第1ラウンドも終わっていないのに早くもくたびれてきたからだった。ときどき、テレビの前で目を開けたまま20分ぐらい気を失っていることがある。ほとんど苦行である。どうしてそうまでして私たちはワールドカップを見なければいけないのか。それが問題だ。

◇チェコ×アメリカ(グループE)
過去2大会だけの経験に基づく乱暴な仮説だが、ワールドカップが荒れた展開になるかどうか(つまり決トナで強豪国同士のガチンコを堪能できるかどうか)を判断する場合、「アメリカが活躍するか否か」が一つの重要な指標になるのではないか。少なくとも、多くの観戦者が「どうなんだ今回のアメリカは」と妙に気にして見ているのは間違いないと思う。もちろん、内心で「ふつうに弱いといいなぁ」と願いながらだ。違いますか。それは私だけですか。で、3-0で終わったこの試合を見るかぎり、このドイツ大会は波乱の少ない展開になりそうな予感。まあ、すでに多くの強豪国が無難に初戦を乗り切っているので、あまりおかしなことにはなりそうもなかったわけだが、チェコがあっさり先制したのを見て「ああ、この大会は大丈夫だ」とずいぶんホッとしたものだ。それにしても、なぜか笑ってしまうコレル(だかコラーだか)の先制点ではあった。ゴールが決まったとき、ふつう私たちは思わず「入った!」とか「来た!」とか「よっしゃ!」とか「うわ」とか「おお」とか口走るものだが、その瞬間、反射的に「でかっ!」と叫んだのは初めてである。そんなときに体格についての感想を漏らさせるコレルは偉大だ。そして巨大だ。でかいよコレル。知ってはいたけど、でかい。でかいから、彼を乗せた担架を持ち上げる人たちもフラフラして危なかった。あわや二次災害だ。何かほかの動物を運搬するのに使う道具を用意したほうがいい。しかし大丈夫かなコレル。どうやらロシツキはこの大会でキャリアのピークを迎えているような雰囲気なので、2トップさえ無事にプレイできれば、チェコは相当いいと思うのだが。

◇イタリア×ガーナ(グループE)
出てきた出てきた。イタリアだよイタリア。おもしろいなぁ。イタリアはいつだって出てくるだけでおもしろい。ペルッツィ御大に出番が回ってくるのを期待していたので、何かと身辺の騒がしいブッフォンが何事もなかったかのように平然とプレイしていたのは残念だし、髪の毛をさっぱり切ったトッティはあんまりイヤな奴に見えなくてつまらないが、なるべく長く大会に残っていてほしいチームである。イタリアのいない大会なんて、煙草の吸えない酒場みたいなものだ。試合は、ピルロとイアクィンタのゴールで2-0。ガーナのほうは、チェルシーのアサッテ君があっちゃこっちゃにシュートを散らしまくっていたのが哀しかった。あんなに枠に行かないものだろうかシュートって。あいつ、もしかして乱視なんじゃねえかなぁ。

◇スウェーデン×トリニダード・トバゴ(グループB)
前半は試合当日にライブで観ていたのだが、仕事の都合で睡眠を優先せざるを得ず、後半は未見だった。ここまでで唯一、波乱が起きた試合である。前半も十分におもしろかったが、後半開始早々にトリニダード・トバゴが10人になって以降は、じつにワールドカップらしい念力と念力の押し相撲。わずかに念波の強さで上回ったトリニダード・トバゴが、徳俵をちょっとだけ後ろに下げることに成功して凌ぎきったというところだろうか。結果を知っていても、手に汗を握るような戦いであった。こういうのが見たいから、私たちは多少の無理をしてでもワールドカップ中継にかじりつくのかもしれない。途中、何やら両チームのあいだで小競り合いが生じたとき、ヨークやイブラがヘラヘラ笑いながら相手選手と握手なんかしていたシーンがあったのだが、あれは何がそんなに可笑しかったのか。わからないが、あれほど緊迫および疲弊した状況で冗談を言い合える人たちのことが私は好きだ。

◇韓国×トーゴ(グループG)
なるほど。「トリニダード・トバゴ」をコピペして、その大半を削除するとアラ不思議、あっという間に「トーゴ」になるということに、いま気づいた。でも、ふつうに「トーゴ」とタイプしたほうが早い。トーゴは大会が始まってから監督が辞任してまた復帰したと聞いていたので、一体どんな人かと思っていたら、いかにも気の短そうなちょい悪オヤジだったので笑った。できることなら、トーゴのベンチには茶碗を並べたちゃぶ台を置いてほしいものだ。「だー!」とひっくり返すところを見たい。この試合でも、ちゃぶ台があったら最低3回(退場+2つの失点)はひっくり返したことだろう。2-1で韓国が逆転勝ち。……だー!

◇ブラジル×クロアチア(グループF)
クラスメイトに結果を言われてしまうのを恐れたセガレが、「学校に行く前に見たい」と言うので、朝5時半に起きて観戦。4時キックオフの試合を見てから登校する小3がどれだけいるか疑問だし、逆にセガレのほうが「カカーのゴールでイチゼロだぜ。ロナウドもアドリアーノも全然ダメでやんの」とか言いふらして友達をなくすのではないかと心配だ。いや、それよりも、いまごろ教室で居眠りしてやいないかと心配したほうがいいか。私も眠い。というわけで、そんなに無理をしてまで見るようなものではなかった試合は、カカーのゴールでイチゼロ。カカー、ちょっと見ないあいだに胸板が厚くなっちゃって、かわいげがなくなったよねぇ。結婚して「太った」のか、ふつうに「育った」のかわかんないけど。ともあれ、むしろ負けたクロアチアのしたたかさが際立った試合。勝てる気がしない。
|

1.あかずの踏切り
2.はじまり
3.帰れない二人
4.チエちゃん
5.氷の世界
6.白い一日
7.心もよう
8.待ちぼうけ
9.桜三月散歩道
10.ファン
11.小春おばさん
12.おやすみ
|
平成十八年六月十三日(火)
午後十二時五十五分
BGM : 氷の世界 / 井上陽水さん(日本)
一昨日(日曜日)の昼頃から24時間ぶっ続けで『わしズム』の座談会原稿に取り組んで(途中でこの日誌も書いたけど)ようやく仕上げ、一睡もせずに月曜の昼に帰宅するやいなや、土曜日が授業参観だったために代休で家にいたセガレもまじえて、12時間で4試合を観戦。目が潰れるっつうの。3試合目からはボールが2つに見えました。乱視が悪化している。

◇オランダ×セルビアモンテネグロ(グループC)
試合中、セガレと喋っている中で「セルビア」を「セビリア」と言い間違えたことをきっかけに、生まれて初めてオリジナルの早口言葉を考案した。「セルビア、セビリア、サルビア、シルビア、シベリア」って似た単語並べただけじゃん! しかも覚えるのが難しいだけで見ながらだと簡単に言えるじゃん! 思いついたときはとても面白かったのだが、こうして改めて見てみると、徹夜明けの人間にありがちな異様なハイテンション状態のなせるワザ以外の何物でもない。寝ていないとき、私たちはろくなことを考えないのである。だとすると、夜が明けてから書いた部分の原稿が心配だ。そういえば、まだOKの連絡が来ない。試合はロッベンのゴールで1-0。チェルシー好きな家庭だからさぞ盛り上がっただろうと思われるかもしれないが、私たちは一生懸命にスタンコビッチ君を応援していたのでガッカリ。我が家の外国人フットボーラー応援理由リストの中で、「ラツィオの優勝メンバー」というブランドは全てに優先する。ロッベンめ。そもそもファン・ニステルローイが居てクライファートの居ないオランダになんか興味はないのだし、今回のオランダはなんだか似たような顔の連中があちこちでうろうろしていて覚えにくい。なんで白い人ばっかりなの?

◇メキシコ×イラン(グループD)
たぶん、イラン人は、人にお土産をあげるのが好きなんだと思う。たしかフランス大会のときも、ドイツ戦のキックオフ前に、クリンスマン(当時主将)を苦笑いさせるほど大量のお土産を渡していたような記憶がある。今回、アリ・ダエイが贈っていたあの巨大な絵画みたいなものはいったい何だ。それはむしろ厭がらせではないのか。そして、ネクタイ柄のチョイスに個性の光るメキシコのラボルペ監督はブルース・スプリングスティーンにとてもよく似ているように見えたわけだが、そんなことはともかくとして、眉毛の濃いタイプの人たちがきびきびと走り回る試合のほうは、熱のこもった果敢な攻め合いで、とてもおもしろかった。前半に1-1となった頃、「メキシコ相手にイランがこれだけやれるなら、そのイランと一応は互角に渡り合ってきた日本も今夜は結構やれるんじゃねぇの?」と勇気が湧いてきたのだが、終わってみれば3-1でメキシコ。そうなのだ。終わってみれば3-1だったのだ。

◇アンゴラ×ポルトガル(グループD)
愚妻が「似てるよね」と指摘して以降、アンゴラのユニフォームが永谷園のお茶漬けのパッケージにしか見えなくなって困った。べつに困ることはないが。もう何年も食ってないよな、永谷園のお茶漬け。初出場のアンゴラがまだ自分たちがどこで何をしているのかちゃんと把握できずにボーっとしている隙に1点を掠め取っただけのポルトガルが、0-1で勝ち点3。見ていてかなり眠かったのは、私が徹夜明けだったせいばかりではあるまい。デコ不在のポルトガルはあっちこもっちもドリブラーばっかりで、一本調子な印象。しかしまあ、4年前や地元EUROでのことを思えば、初戦で勝利しただけでも立派なことだ。それにしても今回のドイツ大会、この試合まではほぼ順当に本命サイドで収まるオーソドックスな展開になっていて、それはそれでなかなか良い感じ。「そのまま!」と叫ぶにはまだ早いけれど。

◇日本×オーストラリア(グループF)
僕のテレビは壊れたけど買い替えたので画期的な色にはならず、いつも醜いあの子をグッと魅力的な子にもしてくれないのだった。ミリオンセラーを記録したアルバム『氷の世界』が発表されたのは昭和48年のことで、まだテレビが一家に一台あるかないかの時代に「うちのテレビ」ではなく「僕のテレビ」と歌ったのは当時としてはそれこそ画期的な表現だったのではないかと思ったりするわけだが、ともあれテレビという機械はとてもよくできていて、負けた試合を勝ったように映してはくれない。勝った試合を負けたように映すこともないだろうから、やはり、日本は負けたんだと思うよ。うんうん、負けた負けた。ワールドカップでは初の逆転負けだ。私たち日本人はワールドカップについて短期間で多くのことを経験したつもりでいたが、これはまだやっていなかった。なるほど、そういうこともあるよね。しかし逆転と言っても、日本の先制点は、きっと誰かがふざけて審判の真似をしていたお陰で認めてもらえたのだろうから、そんなに激しい「ひっくり返された感」はない。悔しさが沸騰することもなく、ただただ寒々しいだけ。どうせ小野を使うなら、故障の坪井がアウトした段階で投入して4バックに変更、という選択肢はなかったのでしょうか。勝ってる試合でそれはないか。ところでヨシカツ大明神は、明らかに調子こいていた。バシバシ止めまくって、とっても嬉しそうな顔をしていた。私も「きょうのヨシカツ様なら」とテレビの前で手を合わせてしまった。それがいけない。だもんだから、ロングスローのときもオレだオレだと張り切っちゃったんだよなぁ。でも、しょうがない。世界を相手に張り切っている人たちの姿を見るのは、それだけでも愉快なことだ。残り2試合(だよな、どう考えても)、いつかフェアプレイ賞ぐらいは貰えるつもりで最後までがんばって行こー。
|

1.No Toquen
2.Zocacola
3.Fanky
4.No Me Veras en el Subte
5.Ella Es Bailarina
6.Anhedonia
7.Suicida
8.Fantasy
9.Punto de Caer
10.Shisyastawuman
|
平成十八年六月十一日(日)
午後三時二十分
BGM : Como Conseguir Chicas / Charly Garcia(アルゼンチン)
昔の人が言ったことはちゃんと聞いておくもので、二兎を追う者は一兎をも得ずとわかってはいながらつい追ってしまい、仕事もワールドカップ観戦もすっかり中途半端になっている今日この頃なのだった。好意を無駄にしてごめんなさいね、昔の人。しかし仕事の〆切は待った無しなのだし、ワールドカップもボヤボヤしているとどんどん進行してしまい、情報を遮断するためにテレビも新聞もヤフーも友人知人のブログ等も目にすることができなくなり、これは生きていく上で大変よろしくないことなので、やはり二兎を追わざるを得ないのである。何が言いたいのかというと、ちゃんと試合を見ていないのでその内容をちゃんと書けないということだ。まあ、ちゃんと見てたってちゃんと書かないわけですが。

◇ポーランド×エクアドル(グループA)
予想イベントに手を染めていないときに困るのが、こういうカードである。知ってる奴が一人も出ていないのに、どっちに肩入れしろと言うのだ。どっちかに肩入れしてこその念力と脱力なのに。日本人には春夏の高校野球観戦で培った「相対応援の技術」があるとは言うものの、たとえば「南国より北国」という基本原則を適用するならポーランドを応援することになるのだが、一方では「でかい奴らより小さい奴ら」という基準もあるわけで、そうなると当然エクアドルである。「私立より県立」となると、もう何が何だかわからない。旧共産圏って県立か? 知るかそんなこと。そっかー、困ったよなぁ。などと自問自答しているあいだにエクアドルが先制し、あのスローインはファウル臭い(右手の力が勝ちすぎだ)よなぁとも思ったのだが、驚いたのはカビエデスの登場だ。おお、知ってる知ってる、おれ、おまえのこと知ってるよ、まだやってたのかー、いやはや元気そうで何よりだなぁ、でも太ったよね、おれは痩せたけど。というわけで、ようやく応援態度が決まったのだった。そのカビエデスが私の念力でアシストを記録したこともあって、0-2。おめでとう、エクアドル。ところで、あのカビエデスって元ペルージャのカビエデスだよな? 違ったらバカみたいだ。いや、バカだ。

◇イングランド×パラグアイ(グループB)
こちらはもう、知ってる人だらけである上にチェルシー勢てんこ盛り、しかもラツィオ時代に世話になったエリクソンが率いるイングランドを応援するのが人の道というものである。「生で見るんだ!」と気合いを入れて眠い目をこすりながら頑張っていたものの後半25分で力尽きて寝床に撤退したセガレも、パスを受けて実況アナに名前を呼ばれるイングランドの選手を「全員知ってる」と嬉しそうだった。私には、イングランドが決勝まで駒を進めるという予感がある。いや、大会前まではあった。でも、こうして実際に見てみると、個々の存在感は相当なものであるのに、なんというか、チームとしての線が細いように感じるのはなぜだろう。ちょっと押されるとポッキリ折れそうな脆さを感じるのである。単にクラウチの体格がもたらす外見的な印象にすぎないといいのだけれど。試合はガマラの今大会初自滅点で1-0。

◇アルゼンチン×コートジボワール(グループC)
これがまた、ポーランド×エクアドルとは別の意味で困るのである。クレスポとドログバのどちらか一方に肩入れするなんて、そんな酷いことは私にはできない。これがもしランちゃん対スーちゃんの試合なら、私は躊躇なしにランちゃんチームを応援するだろう。だが、チェルシーはキャンディーズではないのである。クレスポとドログバは「チェルシーの一部」だが、ランちゃんは「キャンディーズの一部」ではない。キャンディーズが「ランちゃんの一部」なのだ。いったい何を熱心に語っているのだ。早く仕事に戻らないといけないという焦りから、よく考えもしないで思いつくまま書き飛ばしている自分が怖い。なんでこの忙しいときにキャンディーズなのだ。まあよい。クレスポとドログバのゴールは、いずれも見ていて自然にガッツポーズが出るすばらしいものだった。途中、サビオラ君のゴールもあったものの、終わってみれば2-1でチェルシーの勝ち。
|
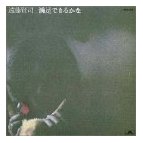
1.満足できるかな
2.カレーライス
3.おやすみ
4.待ちすぎた僕はとても疲れてしまった
5.外は暑いのに
6.今日はとってもいい日みたい
7.寝図美よこれが太平洋だ
8.ミルク・ティー
9.早く帰ろう
10.雪見酒
11.君はまだ帰ってこない
|
平成十八年六月十日(土)
午後十二時三十分
BGM : 満足できるかな / 遠藤賢司
いくら手直ししても気に入らず、デザインが定まらない。工事中のスタジアムで試合をしているようなことになっている。みっともないのである。せめてワールドカップが終わるまでには完成させたいと思う。

午前中、授業参観のため学校へ。愚妻から、セガレの担任は「片桐はいりに似ている」と聞いていたのだが、心配したほとではなかった。ナニを心配していたのかわかるようなわからないような話だが、それはともかく社会科の授業を見物。地図記号の学習である。先生が病院の記号(下図)を書いてみせたとき、

セガレと同じサッカークラブに所属している男の子が、「イングランドのユニフォームについてるやつみたい」と言ったので笑った。時事を踏まえたタイムリーな私語には好感が持てる。社会の授業だしね。一方セガレはぜんぜんタイムリーじゃない私語を交わして先生に名指しで注意されていた。なさけない。もっと面白いこと言わなきゃダメじゃないか。

◇ドイツ×コスタリカ(グループA)
さて、この大会に私が満足できるかどうかを考える上で問題になるのは、21世紀を迎えるやいなやワールドカップが変質したのかどうかということなのである。私がとても満足できた98年のフランス大会が「20世紀型ワールドカップ」の最後の花火であり、だから2002年の日韓大会があんなことになってしまい、したがって今回もそんなことになってしまうのか。それとも2002年はアジアで開催したがゆえの例外で、だからヨーロッパで開催される今回はまた私を満足させる大会になるのか。といったことを考えるわけだが、それをこの開幕戦で占っていいのかどうかよくわからない。仕事をしながらチラ見していたので細かいことは把握していないものの、その大雑把な展開と4-2という大味なスコアは先行きに不安を抱かせるのに十分なものだった。ドイツが先制してすぐに同点ゴールを許してしまったあたり、日韓大会と同じ粗雑感が漂っている。しかし開催国が緒戦で大量得点をあげて勢いづきそうという点では、98年のフランス(記憶が怪しいが、たしか5点ぐらい取ったはず)を思い出さないでもない。満足できるかなぁ。満足したいなぁ。
|
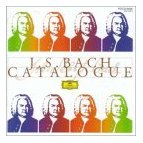
1.管弦楽組曲
2.ブランデンブルク協奏曲
3.ヴァイオリン協奏曲
4.チェンバロ協奏曲
5.ヴァイオリン・ソナタ
6.ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタ
7.フルート・ソナタ
8.無伴奏ヴァイオリン・ソナタとパルティータ
9.無伴奏チェロ組曲
10.オルガン曲
11.器楽作品
12.カンタータ
13.宗教作品・受難曲・オラトリオ
14.音楽の捧げもの
15.フーガの技法
|
平成十八年六月九日(金)
午後六時二十分
BGM : J. S. Bach Catalogue
午前中に『わしズム』の対談原稿を一つ仕上げ、さっきコラムのゲラを戻してひと息ついたとはいえ、これから月曜までに座談会原稿1万9000字をやっつけなければいけないので慌ただしいのだが、ぼやぼやしているとワールドカップが開幕してしまいやがるので、とりあえずデザインだけいじってみた。いかにも急ごしらえのやっつけ仕事らしく配色が安直だし、これではまるでドイツ代表チームの応援サイトみたいだ。そういう趣味はないのに。どうなんだドイツ。というか、どうなんだよワールドカップ。今回はあらゆる予想イベントから手を引いており(声をかけてくれたみなさん、どうもすみません)、したがって情報収集もほとんどしておらず、大会の展開や全体像について真剣に考えることもなかったので、何だかうろたえている。1週間ほど前に壊れたテレビを買い替えた以外は、とくに準備らしい準備をしていない。トーゴがナニ組なのかも答えられないぐらい、ワールドカップのことが把握できていないのである。……いや待て待て。トーゴって、出場するんだよな? おいおい、それさえちょっと自信がないじゃないか。こんな状態で開幕を迎えていいのか私。何かやり残したことはないのか私。だから仕事だよ。いっぱい残ってるよ。あー。うー。がんばれ私。みんなもがんばれ。がんばってこそのワールドカップだ。どうでもいいが、奇しくも今日は薬師丸ひろ子さんのお誕生日です。
|