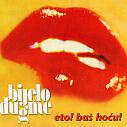1.Senorita
2.Heaven
3.Crazy Dream
4.Dime Mi Amor
5.Hollywood
6.More Than Love
7.Nobody Else
8.Onda
9.Real Emotions
10.Tell Me Why
11.Velvet Sky
12.La Contestacion
2005.09.30.Fri. 15 : 50 p.m.
BGM : Los Lonely Boys
こんな季節のこんな天気の日の「井の頭」といえば、「通り」より「公園」のほうが気持ちがいいに決まっている。だいたい、「通り」のほうは「井の頭」ではなく「井ノ頭」と表記するのが正解のようだ。どんな季節のどんな日だろうが、「井の頭」といえば「通り」ではなく「公園」なのである。吉祥寺の銀行で家賃を振り込み、ふらふらとレコファンに立ち寄ってロス・ロンリー・ボーイズやアル・クーパーを買ってから足を向けた井の頭公園には、完全無欠のノンビリムードが漂っていた。いつの間に建て替えたのか、やけに小綺麗になった池畔の食堂で山菜月見蕎麦をすすりながら、ゆらゆらと陽光を反射する木々の緑など眺めていると、ああ世界がすべて井の頭公園になってしまえばいいのに、などと頬の赤らむようなことを思ったりする。が、昼飯を終えて園内を散歩していると、そこかしこに「アンプを使用する楽器の演奏を禁止します」「金(木)管楽器の演奏を禁止します」という貼り紙。世界が井の頭公園になるのは困る。
すっかり汗ばんで、仕事のない仕事場に戻ると、マンションの玄関でガラスを拭いていた管理人さん(60代・女性)がその手を休めて私のほうを向き、「長く働かせていただいて、ありがとうございました」と頭を下げた。そうなのだ。10月1日から管理会社がかわるので、管理人さんも今日が最後なのだ。「こちらこそ、お世話になりました」と相手よりも深く頭を垂れながら、辛いよなぁこういうの、と思う。
管理会社変更の決定に関しては、私も管理組合の副理事長として深く関わってきた。値段が高くてサービスが悪くて信用できない管理会社との契約を打ち切り、値段が安くてサービスが良くて信用できそうな管理会社と契約を結ぶのは、きわめて合理的で正しい。3年ほど前にイヤイヤながら副理事長におさまり、管理会社のチョー無能な担当者と頻繁に接触するようになって以来、その仕事ぶりのほとんど全部が腹に据えかねていた私としては反対する理由などないし、役員の中でも積極的にその案件を進めてきたほうだ。
しかし、管理人さんに非はない。管理会社との契約を解く合理的な理由はあっても、管理人さんを解雇する合理的な理由はない。住人の中には「廊下の蛍光灯が切れているのになかなか交換しない」などの不満を抱いている人もいたようだが、少なくとも私はこのマンションに入居してから15年間、管理人さんの仕事に不満を感じたことが一度もなかった。毎日のように顔を合わせていれば、それなりに情も移る。先日ご主人を亡くされたばかりなので、暮らし向きが心配にならないわけでもない。でも管理人さんは管理会社の社員なので、しょうがないのだ。深く頭を垂れながら、内心で「恨むなら会社を恨んでね」と呟く。しょうがないのだ。しょうがないのだ。
きのうの朝日新聞夕刊を読んで、久我山駅前でちょっとした「書店紛争」が起きていることを知った。改修された京王井の頭線(こちらは「ノ」じゃなくて「の」だ)久我山駅構内に啓文堂書店が出店することになり、それによって経営の危機にさらされる駅前の2書店が、京王電鉄と子会社の「京王書籍販売」を相手に、書店の設置差し止めを求めて東京地裁に仮処分を申請したという。
いつも歩いている地元がニュースになっていると、なんだかドキドキするものだ。2書店のうちの1つは私もときどき利用するので、「あのおじちゃんやおばちゃんやお姉ちゃんが仮処分申請かー」と唸った。あんまり、仮処分申請をしそうなタイプには見えないからだ。「仮処分申請をしそうなタイプ」ってどういうことかわからないが、仮処分申請しそうなタイプではない人たちを仮処分申請に駆り立てる危機感の大きさはよくわかる。少し前に駅前のレコード屋さんが店を畳んだことを書いたが、その書店も、急行に乗れば一駅で吉祥寺に行ける街で今まで生き残ってきたのが不思議なぐらいのものだ。雑誌類のほかは漫画と実用書と文庫がちらほら置いてあるだけで、いわゆる新刊本は皆無に等しい。一時期『ハリーポッター』は何冊か置いてあったような気がするが、『キャプテン翼勝利学』は置いてない。それはもはや吉祥寺の大規模書店にも置いてないからしょうがないとはいえ、『わしズム』さえ置いていないというのはかなりモンダイだろう。たまにサッカー雑誌や音楽雑誌は買っていたけれど、はっきり言って、ぜんぜん使えない店。利用者としては、啓文堂ウエルカムである。
だけど、おじちゃんやおばちゃんやお姉ちゃんがなぁ。いつも交替で店番をしている彼らの横顔と、最後の日もいつもと同じように淡々と玄関のガラスを拭いていた管理人さんの後ろ姿が、脳裏で二重写しになってしまう秋の午後なのだった。他人の仕事の心配してる場合じゃないけどね。私の仕事が減っているのも、どこかに大規模書店みたいなライターが登場したからかもしれない。くっそー、大規模書店みたいなライターめ。と、人のせいにするのは良くないとわかってはいる。真面目にコツコツ働いてさえいれば仕事にありつけるというものではないことも、わかってはいる。わかってはいるが……というところで、これから新旧の管理会社が各種の書類やら管理人室のカギやら何やらの引き継ぎを行うのに立ち合わなければいけないので、本日はこれでおしまい。憂鬱だ。
1.Star Cycle
2.Too Much To Lose
3.You Never Know
4.The Pump
5.El Becko
6.The Golden Road
7.Space Boogie
8.The Final Peace
2005.09.29.Thu. 14 : 25 p.m.
BGM : There & Back / Jeff Beck
この際だから井の頭通りのことをもっと詳しく知ろうと思って「井の頭通り」で検索してみたところ、グーグルがトップ表示したのは、驚くべきことに井の頭通りこう門科胃腸科のサイトであった。この表示順位がどのように決まるのかよく理解していないが、なんにしろ、井の頭通り業界においてこの医院が相当にメジャーな存在であることを意味しているのは間違いないように思われるのであり、だとすると、なんかほかに持ってないのかよ井の頭通り。そんなことでいいのか。もっと頑張らないとダメじゃないか。とも思うわけだが、まあ、この医院の存在は開設当初からよく知っている。とはいえ受診したことがあるわけではなく、以前、減量のために夜な夜なウォーキングをしていた頃に、よくその前を通ったのだ。看板の「こう門科」という交ぜ書きを見るたびに、イヤ〜な心持ちになった。肛門はやっぱり肛門って書かなアカンよ。こう門なんて、ぜんぜん肛門っぽくない。だいたい肛門科を必要としている人というのは、たぶん日頃から肛門に思いを馳せることが多く、肛門に関する情報にも頻繁に接するだろうから肛門ぐらい読めるだろう(というか肛門を治したかったら肛門ぐらい読めるようにしておくのが基本だろう)し、それ以前に、こんな書き方をしたがために間違って水戸のご隠居が訪ねてきてしまったらどうするというのだ。井の頭通り、黄門快調か? わーっはっはっはっ。
あんまり面白くないので話を変えるが、さっき、通勤途中の井の頭通りで「道端にしゃがんで電卓を叩いている背広姿の男」を見たのである。さほど珍しい光景ではない。井の頭通りにかぎらず、道端にしゃがんで電卓を叩いている背広姿の男は時々いる。そして、道端にしゃがんで電卓を叩いている背広姿の男たちは、おしなべて「青い顔」をしているように見えるのだった。なにしろ道端にしゃがんでアタッシュケースか何かを膝の上に置き、さらには書類を脇の下にはさんだり(時には口にくわえたり)なんかして、ひどく窮屈な姿勢で計算をしているのだから、それはもう何だか知らないが「不測の事態」だ。しかも会社に戻ってから計算したのでは間に合わないのだから、それは「緊急事態」でもある。具体的に何をしているのかは見当がつかないが、とにかく、事前に準備していたことが通用しないことがわかって、何かを仕切り直しているのだろう。いわば、リスク・マネジメントに失敗してクライシス・マネジメントの段階に突入しているわけだ。丸めた背中が「やばいっす。おれ、やばいっす」と言っている。道端にしゃがんで電卓を叩いている背広姿の男は気の毒だ。がんばれ、道端にしゃがんで電卓を叩いている背広姿の男。
ところで、きのう江川達也の顔を眺めながら、もう一人こんな顔の人がいたよなぁと思い出したのが、久保田達也さんである。大昔にインタビューしたことがあるので「さん付け」にしてみたわけだが、ヒゲの量に差はあるものの、まあ、基本的なコンセプトは江川も久保田さんも一緒だろう。名前の表記まで同じとなれば、これはもう「達也系」と呼ぶしかあるまい。なかにはこんな達也やあんな達也やそんな達也もいるのでアレだが、まあ、何事にも例外というものはある。例外のほうが多いけどな。
けさは出勤前に、リバプール×チェルシー(CL第2節)をビデオ観戦。ああ、もう、リバプール鬱陶しい。何が鬱陶しいって、いちいち感涙にむせんでるようなアン・フィールドの陶酔感が鬱陶しい。いい加減やめてくんないかな、その、「ボクたちは世界の中心で愛を叫んでいるのです!」みたいな『ユー・ネバー・ウォーク・アローン』は。それさえ歌ってりゃ好感度アップすると思ってないか? 思ってないならいいけどさ、たかがグループリーグの2戦目で感極まってんじゃないっつうの。聞いてて胸ヤケするわ。あと、あのナナフシみたいな体型のセンターフォワードもかなり鬱陶しいです。チェフよりデカい人間がサッカーやっていいのか? いいのか。いいよな。というわけで、試合のほうは例によってスコアレスドロー。チェルシーの華麗なるディフェンス・ショウであった。とでも思ってなきゃ、苦しくて見てらんないっつうんだよ。久しぶりにキャーキャー言いながらチェルシーの試合を楽しめてよかったけどね。キャー。
ゆうべは、バルセロナ×ウディネーゼ(CL第2節)をビデオ観戦。ロナウジーニョのハットトリックもあって、4-1。いや、5-1ぐらいだっけ? どっちでもいいや。知りたい人は自分で調べてください。「一歩も動けぬシュート」を次々と決められたウディネのGKは、もうロナウジーニョの顔も見たくないと思う。まあ、私も顔はそんなに見たくはないが。そんなことより、これは以前から不思議に思っているのだが、セルジオ越後はなぜ「言うまでもない」を「言うもない」と言うのか。○○はなぜ××なのか。さすがにこれは新書のタイトルにはならないと思うが、聞いていていつもムズムズする。言うもない。言うもない。うーむ。言うもないってこたぁねぇよなぁ。あ、もしかして「言うまでもない」じゃなくて「ユーモアがない」の言い間違いかな。セルジオ越後の場合、ユーモアは、まあ、あるけどね。ただし一般論として「あなたユーモアがありますね」が本当に褒め言葉と言えるのかどうかは知らない。「キミってアイデアマンだよね」と同じくらい言われたくないかも。
巻末キーワード解説200字×200本ノックは、昨晩で終了。めずらしく、淡々と、コンスタントに、慌てず騒がず、雨にも風にも夏の暑さにもマケズ、つまりはマシンのように片づけた感じ。そして、仕事がなくなった。秋風が身に沁みる。
1.Led Boots
2.Come Dancing
3.Goodbye Pork Pie Hat
4.Head For Backstage Pass
5.Blue Wind
6.Sophie
7.Play With Me
8.Love Is Green
2005.09.28.Wed. 10 : 15 a.m.
BGM : Wired / Jeff Beck
けさ、通勤途中の井の頭通りで、「撮影隊」を見たのである。肩に担ぐ式のでかいビデオカメラを持った四十がらみの男と、デジカメっぽい物体と三脚っぽい物体を持った四十がらみの男と、何も持っていない四十がらみの男の三人組だ。ファミリーレストランの前で立ち話をしているだけで撮影はしていなかったが、これはもう、どこからどう見たってロックバンドではなく撮影隊である。
三人のうち二人はとくに誰にも似ていなかったが、一人だけ江川達也にちょっとだけ似た感じの男がいた。ビデオカメラの男だが、まあ、たいがいの撮影隊には、江川達也にちょっとだけ似た感じの男が一人いるものだろう。二人はいない。いても一人だ。そういえばバンドの場合も、江川達也にちょっとだけ似た感じの男が一人いることが多いような気がする。私がかつてトロンボーンを吹いていたバンドもそうで、江川達也にちょっとだけ似た感じだったのはKay'n師匠ではなく、キーボード担当のジョージさんだ。ジョージさんはとても冗談のきつい人で、私は彼の口から「コーディネートはこうでねぇと」という駄洒落を少なくとも20回は聞かされたと思う。少しはこっちの身にもなってほしい。今ごろ、どこで何をしてるのかなぁ、ジョージさん。
さて、ある種の男はなぜうっかりすると江川達也にちょっとだけ似た感じになってしまうのかという問題はまた別の機会に論じるとして、あの撮影隊はいったい何を撮影しに井の頭通りを訪れたのであろうか。わざわざ朝8時すぎにスタンバイしているのだから、その時間帯にしか撮れない何かが目当てだったに違いない。何だろう。本当はそんなこと全然興味がないが、成り行き上、きのうから「通勤途中の井の頭通りをネタにして無理やり日誌を書く」がテーマになっているので強引に推理してみると、まず思い浮かぶのは「朝帰り」だ。女のマンションから出てくる政治家とか芸能人とかを狙っているワイドショーのスタッフだったのではないか。うんうん、あり得るあり得る。
だが、それにしては正体をさらしすぎだ。あんなふうに撮影隊然としていたら、裏口から逃げられてしまう。私もかつて女性芸能雑誌の編集者時代に「張り込み」というやつを何度か経験したが、路上での張り込みなら車でも用意して隠れるのが常套手段というものだろう。当時の私は車の運転免許を持っていなかったため、ある芸能人を尾行するためにフジテレビの駐車場で6時間ぐらいタクシーを使って張り込んでいたことがあるのだが、完全な空振りに終わったため、しょんぼりと編集部に戻るなり「何やってんだおまえ」とデスクに叱られたものだ。いやなことを思い出した。
張り込みではないとしたら、彼らの目的は何だ。こんな何の変哲もない殺風景な住宅街にどんな被写体があるのだろう。「登校中の小学生の群れ」か。ワイドショーで教育問題とかを取り上げるときの資料映像でも作ろうってのか。そういえば私も編集者時代、何の記事に使ったのかは忘れてしまったが、カメラマンと一緒に早朝の東京駅に行って「サラリーマンの通勤風景」を撮ったことがあった。そんなもん貸しポジ屋に行けばいくらでもあったのかもしれないが、なんとなく、そんなことがしてみたかったのだ。記事の片隅に入れる「※写真と本文は関係ありません」という原稿を書いたとき、なぜか「ぐふふ」と笑ったことを覚えている。たぶん、「なんだよ関係ねぇのかよ」という笑いだったのだと思う。だって本文と関係ない写真を使うのはヘンだからね。もしも許されるなら、「※写真と本文はちょっとしか関係ありません」と書いてみたかった。
すっかり何の話だかわからなくなっているが、まあ、撮影隊を見ただけでこれぐらい書ければ上等だろう。要するに本日の結論は「私は撮影隊を見ると編集者時代を思い出す」ということだ。あと、私は松田聖子や近藤真彦や中森明菜や後藤久美子を見ても編集者時代を思い出すのだが、それはそれでとても長い話になるのでもうやめる。資料が届いたので、きょうは忙しい。
ところで『ある種の男はなぜうっかりすると江川達也にちょっとだけ似た感じになってしまうのか』というタイトルの新書はどうだろうか。『○○はなぜ××なのか』は新書の基本だ。『さおだけ屋』の3%ぐらい売れれば成功だと思うのだが。
1.What Mama Said
2.Psycho Sam
3.Brush With the Blues
4.Blast from the East
5.Space for the Papa
6.Angel (Footsteps)
7.THX138
8.Hip-Notica
9.Even Odds
10.Declan
11.Another Place
2005.09.27.Tue. 15 : 45 p.m.
BGM : Who Else ! / Jeff Beck
けさ、通勤途中の井の頭通りで、「手を挙げて横断歩道を渡っている人」を見たのである。ランドセルを背負った小学生ではない。メガネとヘアスタイルがちょっと宅八郎に似た感じの、四十歳前後とおぼしき女だ。確信はないが、たぶん女。連れはいなかった。彼女のほかに、横断歩道を渡る者もいない。交通量は少なく、横断歩道の手前で停止している車もなかった。そういう状況で、女は肘をまっすぐに伸ばした腕を垂直に挙げ、信念の強さを感じさせる生真面目な顔をいくらか強ばらせながら、私の通行している歩道のほうに向かって、スタスタと脇目もふらずに横断してきたのだ。それはまさに「脇目もふらず」なのであって、つまり女は左右を見て車道の状況を確認しようとしなかった。このあいだ轢き殺されそうになった私はそれがいかに危険かということをよく知っているが、女は「手を挙げていれば轢かれることはない」と頑なに信じているように見えた。
私が即座に「これについて何か書かなければ」と思ったことは言うまでもないが、しかしいざ書こうとするとどう処理していいのかよくわからない。日常の中に見出したささやかな綻びを可能なかぎり膨らませて文章化するのは物書きにとって重要なトレーニングのひとつだが、このケースは簡単そうに見えて意外にむずかしい。手を挙げて横断歩道を渡る宅八郎に似た四十がらみの女を見たからといって、それが何だというのだろう。
手を挙げて横断歩道を渡る宅八郎に似た四十がらみの女を見た私の脳裏を最初に過ぎったのは、当然ながら松崎真の顔である。おそらく、手を挙げて横断歩道を渡っている人を見た100人のうち70人以上が松崎真を思い出すだろうというあたりが松崎真の偉大なところだが、そんなことを書いてもつまらない。ここで松崎真を持ち出したのでは凡庸すぎる。このあいだ久しぶりに『笑点』の大喜利を見たら思いのほか面白かった、という方向に持っていきたいという衝動に駆られなくもないが、それとこれとは関係がない。ちなみに座布団はいまだに山田君が運んでいて、私はそれにかなり驚愕したのだが(だって彼が一生のうちに運ぶ座布団の枚数を考えたら気が遠くなるじゃないか! 誰かそれを昭和59年から正確にカウントしている人はいるのか!)、しかしそれも、手を挙げて横断歩道を渡る宅八郎に似た四十がらみの女を前にしたらどうでもよいことだ。
その次に私の頭の中で浮上してきたのは、和歌山の連続発砲事件だった。いま「発砲」と書いた瞬間に、世間には「発泡スチロール」を「発砲スチロール」と誤記してしまう人が「WOWOW」を「WOWWOW」と誤記してしまう人と同等かそれ以上に多いよなぁということを思い出したが、それはまた別の話。ここで、ならば「連続発泡事件」とは一体どんな事件なのか、そもそもそれは事件ですらないのではないか、と力説してみる手もあるが、それを始めるとどんどん読み手を置き去りにしていくことになるのでやめておこう。
手を挙げて横断歩道を渡る宅八郎に似た四十がらみの女を見た私が和歌山の連続発砲事件を想起したのは、つまりその女が車からの銃撃を避けるために「ホールドアップ」をしているのかもしれないと思ったからだが、それなら両手を挙げなければ意味がないのだし、発生したばかりの大きな事件と身近なエピソードを無理やり結びつけるのは退屈な予定調和型コラムにありがちな手法なので安易に手を出してはいけない。
だんだん書くのが面倒臭くなってきたし、ならば読むほうはもっと面倒臭いはずだが、きょうは編集部から送られる資料待ち状態でヒマなのでダラダラ続けると、手を挙げて横断歩道を渡る宅八郎に似た四十がらみの女を見た私が三番目に感じたのは、その女が全身から迸らせていた「怒り」のようなものだった。いや、本当のことを言えば、最初に感じたのがそれだ。たぶん彼女は、何かに対して憤っていたのだと思う。私はそれが怖かった。宅八郎に似た四十がらみの女に手を挙げて横断歩道を渡らせるような種類の憤怒に言いようのない恐怖を感じたからこそ、私はあえて松崎真の顔を思い出して自分をリラックスさせようとしたのだ。
私の感じた恐怖をうまく伝えられているような気がしないし、この文章自体が完全に収拾のつかないものになっていることに対してもうっすら恐怖感を抱き始めているが(だって私はけさ通勤途中の井の頭通りで手を挙げて横断歩道を渡る宅八郎に似た四十がらみの女を見ただけなのだ!)、いったいぜんたい、あの女は手を挙げて横断歩道を渡ることで何に対する怒りを表明していたのだろう。しばしば「明文化されたルールよりも<みんながやっていること>に従って行動しがち」と言われる日本人の規範意識だろうか。「手を挙げて横断歩道を渡りましょう」という標語が「明文化されたルール」かどうかはよくわからないが、まあ、タテマエとしては一応それが正しい行為とされているわけで、しかしそうであるにもかかわらず「みんな」はふつう手を挙げて横断歩道を渡らないのだし、そればかりか、手を挙げて横断歩道を渡っている人を見ると変人扱いしてクスクス笑ったり、反射的に「日誌に書かなければ」と思ったりする。そういう不真面目さが彼女には許せなかったのかもしれない。だとすれば、私は自分が怒られているように感じたから怖かったのかもしれない。それにしても、あの女は宅八郎に似ていた。言いたいのはそれだけかもしれない。
ところで、「洪水の夜」と題した9月5日の日誌の中で、私は浴室のドアの下についている穴のことをよく考えることなしに「排気口」と書いたが、親切な読者が調べて教えてくださったところによると、あれは「吸気口」なんだそうです。浴室内の換気扇が「排気口」で、ドアのほうは「吸気口」。下から吸って上から吐く、という構造になっているらしい。下水が逆流して浴室から水が溢れてくることまでは想定されていないのだった。まあ、あらゆる事態を想定して物を作ることなんかできないのは当たり前である。それに、ドアで完全にシャットアウトされた下水が浴室の天井まで溜まっていく光景というのも、考えてみればかなり怖い。水圧でドアが開きそうになる→お父さんがそれを懸命に抑える→しかしドアは水圧に耐えきれずに割れてしまい、お父さんずぶ濡れ……というシナリオもあり得そうだ。あとで考えたら、浴室内の排水口そのものを何らかの手段でふさげばよかったと思わないでもないのだが、しかしそれをやると逃げ道を失った下水がトイレのほうから噴出したかもしれず、それはちょっとカンベンしてほしいので、いずれにしても結果オーライだったのだと思う。
1.Esperanza
2.Contigo Sonar
3.Mi Rollo
4.Lere
5.Fuente De Colores
6.Punta Paloma
7.Jam @ De Studin
8.Siete Cuatro
9.This
10.The Heritage (Buleria)
2005.09.26.Mon. 12 : 25 p.m.
BGM : Thalisma / Miguel Sanchez
土曜日は、高田馬場のもめん屋で暮れに決行するおさらい会の初ミーティング。いや、おさらい会を高田馬場のもめん屋で暮れに決行するのではなく、ミーティングを高田馬場のもめん屋で行ったということである。高田馬場のもめん屋は居酒屋なのでおさらい会はできません。いや、修業中の板前のおさらい会ならできるかもしれないが、アンプやドラムセットはないので修業中のロック・ミュージシャンのおさらい会はできないということだ。ああ面倒臭い。いや、おさらい会が面倒臭いのではなく、誤解を招かないように文章を書くのは大変だということである。修業中のライターはどこでおさらい会をすればいいのだろう。あ、それがこの日誌か。さらい続けて早七年。無駄に長々とコースアウトした話を「ともあれ」で無理やり本筋に戻す癖はなかなか直らない。
ともあれ、ミーティングはおもしろかった。私にとっては全員が古くから見知った仲間だが、タボンくん(b)、ヤマちゃん(dr)、モルちゃん(vo)という3人のサポートメンバーとKay'n師匠は、これが初対面。こういうのって、ちょっとドキドキするものだ。結婚相手を自分の親兄弟に引き合わせるときの感覚に似ていなくもない。彼らの場合、この日誌の記述やゲストブックの書き込みを通じてそれぞれ一定の背景情報は持っていたわけだが、私は自分自身が「会ってみると文章のイメージと違う」としばしば言われる(愚妻にさえ「文章だとふだんと人格が違う」と言われたことがある)ので、誰でも大抵そうなのだろうと思っていたところ、どうもそういうものでもないようで、みんなほぼイメージどおりのキャラクターだったようだ。ふーん。厄介な議論になることを(というかおさらい会の話が忘れられることを)恐れた私が「きょうは政治とサッカーの話はナシね」と釘を刺しておいたにもかかわらず、どいつもこいつも政治とサッカーの話ばっかりしやがって大いに盛り上がった夜だった。
しかしまあ、政治とサッカーの話とカラオケは人柄を把握する上で役に立つのだし、当たり前だがちゃんとおさらい会の話もした。結果、12月下旬の開催が決定。世間に公開するようなシロモノではなく、単なる内輪の発表会なので、日時や場所はここに書かない。都内某所のスタジオに10〜15人ぐらい呼んで見物していただく予定である。おそらく忘年会を兼ねた形になると思われ、内輪の皆様にはいずれ詳細をご連絡しますので、ひとつよろしくお願いしたいのです。
ところでカラオケのほうは、当然のように朝までだった。なぜ私たちは当然のように朝まで歌ってしまうのだ。朝の5時に、あまり頭が良さそうに見えない学生たち(たぶん大半が我々の後輩たち)でごった返す1階レジ付近で「さっき(1次会)の余りが6000円あるから1人1500円ね」とか言ってて恥ずかしいと思わないのか。思いませんね。思いません思いません。おもしろかったならそれでよい。その晩のベストパフォーマンスは、師匠とモルちゃんのデュエットである。初対面とは思えぬ見事なハーモニーに、鳥肌が立った。さすが優秀なミュージシャンというのは、初参加のセッションでも一発で決めてみせるものだ。私もかくありたい。あの『夏の終わりのハーモニー』と『あずさ2号』を聴けただけでも、このおさらい会を企画してもらった意味があるというものだ、なんて言ってちゃいけません。うー。あと3ヶ月かー。練習しまくるぞー。えいえいおー。
ゆうべは、チェルシー×アストンヴィラ(プレミア第6週)をビデオ観戦。GKのロングキックからなし崩し的な先制点を奪われ、無失点優勝の夢が露と消えたのは残念だったが、すぐさまランパードのFKで同点に追いついてしまうあたり、まるで朝青龍のような強さである。あーあ。とうとう朝青龍って言っちゃったよ。いいのかよそれで。そんなチームが好きなのかよおまえ。ああ好きだよ好きで何か悪いか。といった自問自答はともかく、ここで初失点を喫したことで、これまで何となく安定した文体で流れていた無難な文章を推敲して破調をもたらす機会が到来したと見たのか、後半のモウリーニョはドラ切りリーチのような爆牌采配を連発。カルバーリョを引っ込め、ダフやエシアンを左サイドバックに回しつつアタッカーを逐次投入して、相手のみならず自分のチームをも引っかき回していた。得点はランパードのPKのみだったものの、あれを見たライバルチームたちもかなり頭の中を引っかき回されたのではあるまいか。朝青龍が猫騙しや八艘跳びをするかもしれないとなったら、これは怖い。目の前の試合だけでなく、シーズン全体の主導権を握り続けるための采配だったような気がする。そんなこんなの2-1で、開幕7連勝。
先週の木曜日にミラン×ラツィオ(セリエ第4節)をビデオで観たのに、金曜日の日誌で書くのを忘れていた。人間の脳には、本当に「忘れたい記憶」を封じ込める機能があるのかもしれない。いや、まあ、こうして書き始めてるんだから忘れてないわけだけども。今季はじめて見たラツィオに驚かされたのは、主に次の3点である。
1.キャプテンがリベラーニ。
2.ユニフォームに胸スポンサーが入っていない。
3.パスしたボールの速度がフランスW杯当時の日本代表より遅い。
1は人材難、2は経営難、3は絶望的な苦難の深刻さをそれぞれ象徴するものだとでも言えばいいだろうか。いくら相手がミランだとはいえ、それまで3試合で7つもの勝ち点をゲットしているのが信じられない状態であった。1と2はしょうがないとしても、3は何とかしてほしいよ。目を疑うほど弱いんだよパスが。どいつもこいつも、生卵でも蹴ってんのかと思うほど恐る恐るパス出してるじゃんか。そんなパス、通るわけないじゃんか。小笠原獲っとけばよかったのに〜、と、半ば本気で思いました。さらに守備陣も、コウトの退団が嘆かれるほどの惨状だ。まだ名前が覚えられないが、2番をつけたCBなんか、シェフチェンコとの1対1で「こんな切り返し見たことありましぇ〜ん」と泣きながらあっさり振り切られて先制ゴールを許していた。泣きたいのはこっちだよ。立て続けにカカにも決められて2-0。しくしく。しくしく。
と、語彙の貧困さがしのばれるステレオタイプな泣き方をしていたら、きのうの第5節は4-2でパレルモを粉砕したらしい。しかも0-2からの大逆転だった模様。うへへ。なんでそんなことができたのか見当がつかない。つまりホームではやけに強いということ? じっさい、オリンピコでは3連勝してるもんな。ところがゲストブックにもたらされた情報(烏龍茶さんありがとう)によれば、スカパー!はセリエA20チームのうちラツィオの主催試合だけ放送権を持っていないらしい。調べてみたら、(社)衛星放送協会公式サイトのニュースリリースにも、そう書いてあった。シーズン開幕後の9月8日に、それまでの14チームに加えて5チーム(メッシーナ、カリアリ、レッチェ、フィオレンティーナ、トレヴィーゾ)のホームゲーム放送権を獲得したとの発表があったようだ。なんだその中途半端さは。なんでラツィオだけ買えないんだよ。買えないんじゃなくて、買わないの? どして? 私が厄年だから? あとでスカパー!に訊いてみよう。まさか「え? あっ、忘れてました〜」じゃねぇだろうなぁ。
1. Culpa tuya
2. La luz no estaba en vos
3. Nectar
4. Union alta
5. Enamorada del muro
6. Calimba tornasol
7. Querida aduana
8. Ninfas
9. Laberintoso
10. Nostalgias (Cobian - Cadicamo)
11. Podria
12. Mil horas (A. Calamaro)
2005.09.23.Fri. 14 : 50 p.m.
BGM : Vuelo Uno / Nora Sarmoria
先日ウクライナのEr. J. Orchestraを発見して買ったザビエル・レコードのお勧めメールに素直に乗っかって購入したのが、この『Vuelo Uno』というアルバムである。スペイン語の「Vuelo」は英語の「Flight」のようだから、タイトルは「処女飛行」ぐらいの意味だろうか。アルゼンチンの女性ピアニスト兼シンガー兼作曲家(兼その他もろもろ)であるノラ・サルモリアが95年に発表したファースト・アルバムだ。いや、読み方はノーラ・サルモーリアかな。あるいはサルモリーア? よくわかんねえけど、これは素晴らしい音楽じゃ。ザビエル・レコードの宣伝文に書いてある「アルゼンチンの矢野顕子」という一部の評は、ディエゴ・シメオネを「アルゼンチンの柱谷哲二」と呼ぶのに近い冗談半分の物言いだと思うので無視してよろしい。私の知る範囲で比較するなら、同じ南米の女性ピアニスト兼シンガーであるタニア・マリアということになるだろうか。
とはいえ、ノラ・サルモリアの織り上げる音楽はタニア・マリアほど耳にスムースなものではなく、アコースティックで、器楽演奏の比重が高い感じ。うまく説明できないので、興味のある人はザビエル・レコードか、公式サイトのディスコグラフィで試聴してみるよろし。私のような素人はアルゼンチンの音楽というとタンゴしか思いつかないが、これはそういうものではない。タニア・マリアを連想したことからもわかるとおり、むしろ「ブラジルっぽい感じ」を強く受けるのであって、そのあたり南米の音楽文化がどのように混じり合っているのか興味深いところ。アルゼンチンとブラジルのサッカーはあまり混じり合っているように見えないけれど、音楽のほうはどうなっているんだろうか。
ともあれ、「ポップなものばっかりじゃなくて、アーティスティックな作品も聴いてもらいたいと思ってるのアタシ」とか何とか、ろくに仕事もできないくせに能書きだけは偉そうに垂れやがる勘違い女性編集者(27歳・独身)みたいなことを言ってるアメリカのお姉さんには、こういう音楽を聴いてから同じことを言ってみろ!と申し上げたくなるような作品である。
1.I Know Why
2.Perfect Lie
3.Good is Good
4.Wildflower
5.Chances Are
6.Lifetimes
7.Letter to God
8.I Don't Wanna Know
9.Always On Your Side
10.Where Has All the Love Gone
11.Live it Up
12.Wildflower (Acoustic Ver.)
13.Where Has All the Love Gone (Acoustic Ver.)
14.Letter to God Gone (Acoustic Ver.)
都立立川高校吹奏楽部第7回演奏会(昭和56年4月)
ムーアサイド組曲(ホルスト)/スー族の旋律による変奏曲/We Are All Alone(B.スキャッグス)/La Fiesta(C.コリア)/パンチネルロ(A.リード)/貴婦人、貴族そしてジプシー(A.O.デイヴィス)/交響詩『ローマの松』より(レスピーギ)etc.
同第8回演奏会(昭和57年4月)
バンドの為のソナタ(P.W.ホエアー)/エディフィス(フォースブラッド)/第2組曲(A.リード)/On The Move(深町 純)/Touchdown(B.ジェイムス)/海の歌(R.ミッチェル)/組曲『ハーリ・ヤーノシュ』(Z.コダーイ)etc.
2005.09.22.Thu. 11 : 10 a.m.
BGM : Wildflower / Sheryl Crow
暑さはお彼岸までと頭ではわかっているのに、毎年この時期は気温の変化にうまく対応できず、鼻がぐしゅぐしゅになる。今朝もくしゃみがひっきりなし。
毎日毎日、Yahoo! ニュースにアクセスするたびに「9月21日発売!」と言われていたら、その日に買いに走らざるを得ないのがシェリル・クロウの新譜である。ライナーに載っている本人の弁によれば、「ポップ・ソングばかり」のアルバムと同時発売すると注目されない恐れがあるので先にリリースした「アーティスティックな方」のアルバムがコレ、ということだ。端的に言って、あんまり面白くない。というか、かなりガッカリ。たしかに「ポップ」ではないけれど、だからといって「アーティスティック」だとも思えない。訳詞を斜め読みすると、本人が「アーティスティック」だと言っているのは歌詞のことなのかなぁと思わないでもないが、そもそも「ポップ」と「アーティスティック」をそんなふうにパッキリ分別する発想自体がつまらないと思う。「燃やすゴミ」と「燃やさないゴミ」の分別だって、けっこう微妙なんだからねぇ。
ともあれ、私にとってこのアルバムがつまらないのは、おそらく、サポートしているミュージシャンの演奏に、ユニークな音楽を作り出そうとする意欲や野心みたいなものが感じられないからだ。これまでシェリル・クロウのアルバムは、ソロ・アーティストの作品でありながら「ロックバンド」の音がしたけれど、これは「カラオケ」で歌っているような印象を受ける。これまでは「サイド」で彼女をサポートしていたミュージシャンが「バック」に回ってしまったというか、「お仕事」として演奏させられているというか、主役と同じ空気を共有していないというか、ガチンコのぶつかり合いがないというか、そんなふうに聞こえるのはどうしてだろう。シェリル・クロウという人は歌がむちゃくちゃ上手いわけではない(わりと口先だけで歌っているように聞こえる)ので、もっとバンドと絡み合いながら曲を織り上げないと、こっちまで届かないのではあるまいか。と、思いました。3曲のボートラに惹かれて国内盤を買ったけれど、オリジナル・バージョンに魅力がなければ「アコースティック・バージョン」も楽しいはずがないわけで、輸入盤が出るまで待てばよかったと後悔している。
ブラバン経験者なら知らぬ者のない吹奏楽の作曲家アルフレッド・リードが亡くなったそうだ。私は吹奏楽のオリジナル曲というものにどこか「教材臭さ」みたいなものを感じるので、昔から基本的にあまり好きではなかったのだが、高校時代に演奏したリード作品の中では『パンチネルロ』と『第2組曲』がかなり気に入っていた。いずれもポップかつアーティスティックな曲。そこで偉大な作曲家を偲びつつ、20年ぶりぐらいに当時の演奏会を収録したLPレコード(わざわざ作ったのだ。それも各2枚組だ)を引っ張り出して聴いているのだが、ヘッタクソだなぁ、こいつら! こんなにヘタだったのかー。ガッカリだよなー。盛大にズレるピッチとクラリネットのリードミスに耳を覆うね。楽器のチューニングもまともにできない奴らがレコードなんか作ってんじゃないっつうの。ガキの勘違いを厳しく諫めるオトナが周りにいなかったことが悔やまれる。『パンチネルロ』の美しい中間部なんか、われわれユーフォニウムは朗々と歌い上げているのに、ホルンの連中が台無しにしていやがるじゃないか。ホルンの連中が読んでいないことを信じて書くが、ロングトーンからやり直したほうがいいぞマジで。しかし、こうして第7回と第8回を聴き比べてみると、私たちが最上級生だった第8回のほうが圧倒的にうまいな。リードの『2組』もメリハリの効いた好演だ。さすが私たち。ほんとうは上の学年と入れ替わった下級生たちのお陰かもしれないが、いずれにしろ『ローマの松』のような大曲は第8回で演奏すべきだった。最後に取って付けたような感じになってしまいますが、アルフレッド・リードさんのご冥福をお祈りします。
1. Izgledala je malo cudno u kaputu zutom krojenom bez veze
2. Lose vino
3. Eto! Bas hocu!
4. Dede, bona, sjeti se, de tako ti svega
5. Slatko li je ljubit tajno
6. Nista mudro
7. Ne dese se takve stvari pravome muskarcu
8. Sanjao sam nocas da te nemam
9. Sanjao sam nocas da te nemam (live)
2005.09.21.Wed. 10 : 00 a.m.
BGM : Eto! Bas Hocu! / Bijelo Dugme
ビジェロ・ドゥグメ、と読むのだろうか。旧ユーゴを代表するバンド、であるらしい。あはは。思えば遠くへ来たもんだ。サラエボ出身だから、今でいえばセルモンテではなくボスビナですね。ちゃんとボスニア・ヘルツェゴビナと書きなさい。全曲のソングライティングを担当しているのはゴラン・ブレゴビッチという人。上背を生かしたポストプレイと強烈な左足のシュートが持ち味のストライカーだ。というのはウソで、本当のところブレゴビッチが何の楽器を担当しているのかは知らない。ジャケットの裏にはギブソンのダブルネックを手にしたギタリストが写っているのだが、これがブレゴビッチだろうか。77年発表のサードアルバム。つい艶めかしいジャケットに惹かれて手を出してしまったことは言うまでもないが、「苦悶のハードロック」という感じの渋いダークサウンドで、これがなかなかどうして悪くない。だからって仮に再結成して来日したとしても行かないとは思うが、ジミー・ペイジ風の重金属ギターがズシズシとキモチイイ。バラード系の曲も美しく、とくに『Sanjao sam nocas da te nemam』は意味も読み方もまるでわからんが全盛期の布施明に歌わせてみたかったような名曲。今が全盛期なら今でもいい。仮にコンサートで歌ってくれたとしても、聴きには行かないと思うが。
ゆうべは、バレンシア×ラ・コルーニャ(リーガ第3節)をギターの練習しながら横目でビデオ観戦。というか、愚妻がサッカーを見ている横でギターを弾いていた、と言ったほうが正しい。無駄に図体のデカい夫が茶の間の片隅で立ってギターを弾いているのはかなり邪魔くさいだろうと思うが、まあ、しょうがない。それも含めて結婚生活である。ベンディングの練習は指先にかかる負担が重く、しばらく弾いているとキーボードを叩きたくなくなるので、最近は仕事を終えてから家で練習しているのだ。っていうか、楽器は家で練習するのがふつうか。
ともあれ、必死でメトロノームと格闘しているので、試合の印象はほとんどナッシング。週末にはバルサ戦やマジョルカ戦も観たのだが、いずれもよく覚えていない。たしかバルサはアトレチコに負け、マジョルカはアランゴ(だったかな)というベネズエラ人のハットトリックで勝ったんだよな。ああ、そうそう、アランゴの3点目はすげえシュートだったよなぁ。スローインを胸で落として振り向きざまに左足のダイレクトボレー。あれがいつも入るんだったら、サッカーって簡単だ。
話がどんどん逸れているが、忘れちゃいけないのはバレンシアのクライファートである。最後のほうに出場していた。まずは出場することが大事。新入社員のようなサッパリした髪型になっていたので、心を入れ替えて一から出直す覚悟を決めたようにも見えたが、とりたてて目立った仕事はしていなかったような印象。いや、新入社員ならむしろそれが当然か。次節のバルサ戦、カンプノウでハジケるクライファートが見たい。試合は双方が退場者を出す乱戦で、2-2の引き分け。