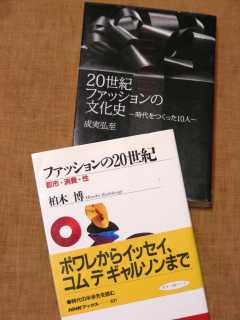 読書メモ。
読書メモ。
10人のデザイナーを取り上げての伝記という形をとってはいますが、 アパレル産業を含む産業構造の変化や他の文化 (デザイン、建築やアート) との関係から 19世紀半ばからのファッションの変遷を描いた本です。 全体の流れはだいたい予想通り、というか、特に前半は 柏木 博 『ファッションの20世紀 &mdash 都市・消費・性』 (NHKブックス 831, ISBN4-14-001831-1, 1998) をデザイナーを主役に組み換えたような感じ。 後半になるとスタンスの違いが明確に。 基本的にモダンの線で評価する 柏木 と違い、 成美は「抵抗のポストモダン」の意義も強調します。 あと、柏木 の本の方が歴史展開を捉え易いと思いますが、 エピソードや具体例は 成美 の本の方が豊冨でしょうか。
取り上げられているデザイナーは以下の10人: Charles Frederick Worth, Paul Poiret, Gabrielle Chanel, Elsa Schiaparelli, Claire McCardell, Christian Dior, Mary Quant, Vivienne Westwood, Comme des Garçons, Martin Margiela。 1920s Avant-Garde ファンとしては、 やはり Chanel と Schiaparelli の章が興味深く読めました。 Chanel には舞台衣装デザインの才能が無かったという指摘に、そういえばそうだなぁ、と。
あと、柏木との Comme des Garçons に対する評価のポイントの違いが興味深かったです。 柏木は Comme des Garçons をミニマリズムの観点から評価していましたが、 成美は抵抗のポストモダンとして評価しています。 ミニマリズムをアヴァンギャルドの一形態とすれば、 いわゆる「アヴァンギャルドなのか抵抗のポストモダンなのか」問題というか。 10年くらい前に The Residents をネタに そんな議論をしたことを思い出してしまいましたよ (遠い目)。 しかし、モダニスト的なミニマリズムであればむしろ Issey Miyake の方が典型的。 Comme des Garçons はミニマリズムの観点よりも 「抵抗のポストモダン」の観点から評価した方が良い服が多いと思いますが、 モダニスト色薄い Yohji Yamamoto の方が「抵抗のポストモダン」らしい、とも思ったり。
 で、今週の読書メモ。
で、今週の読書メモ。